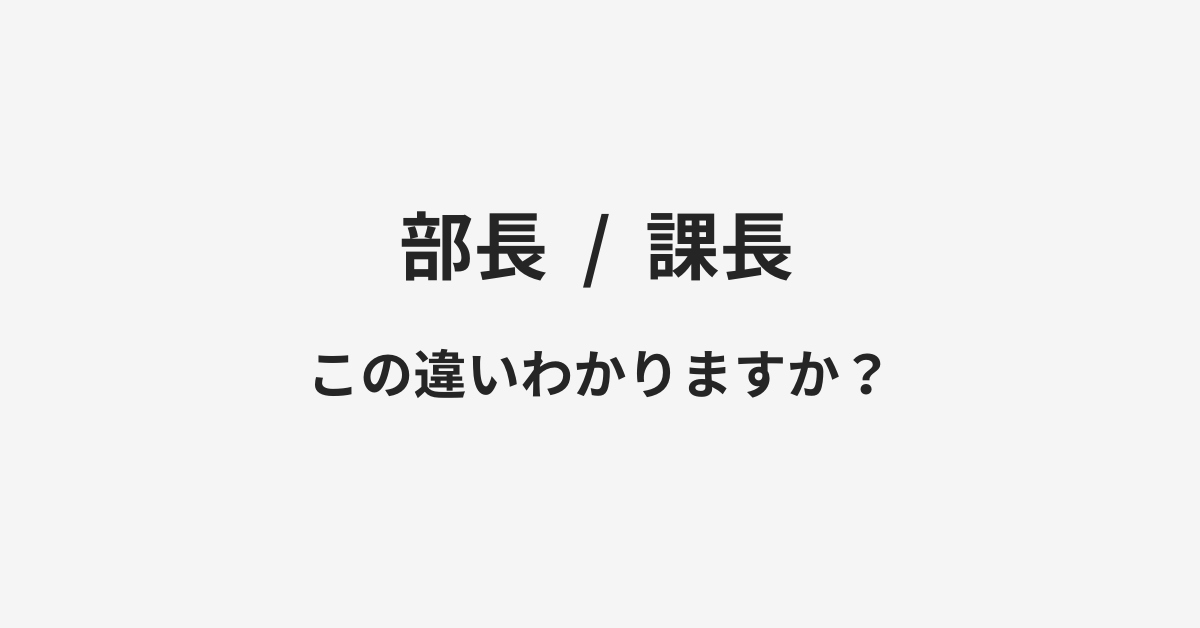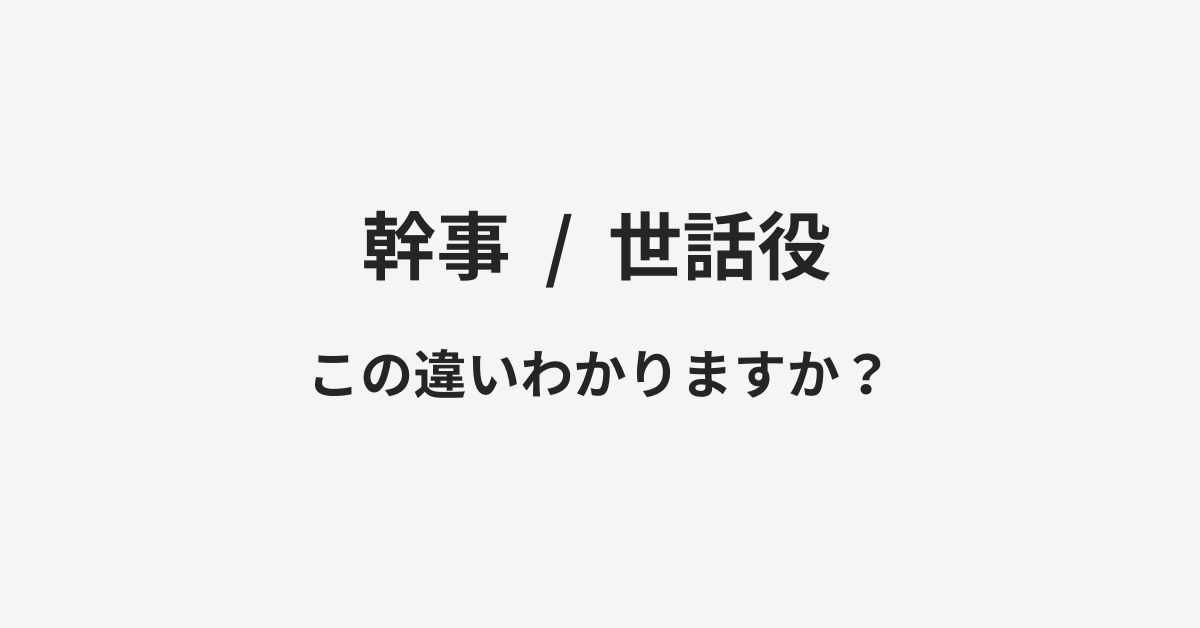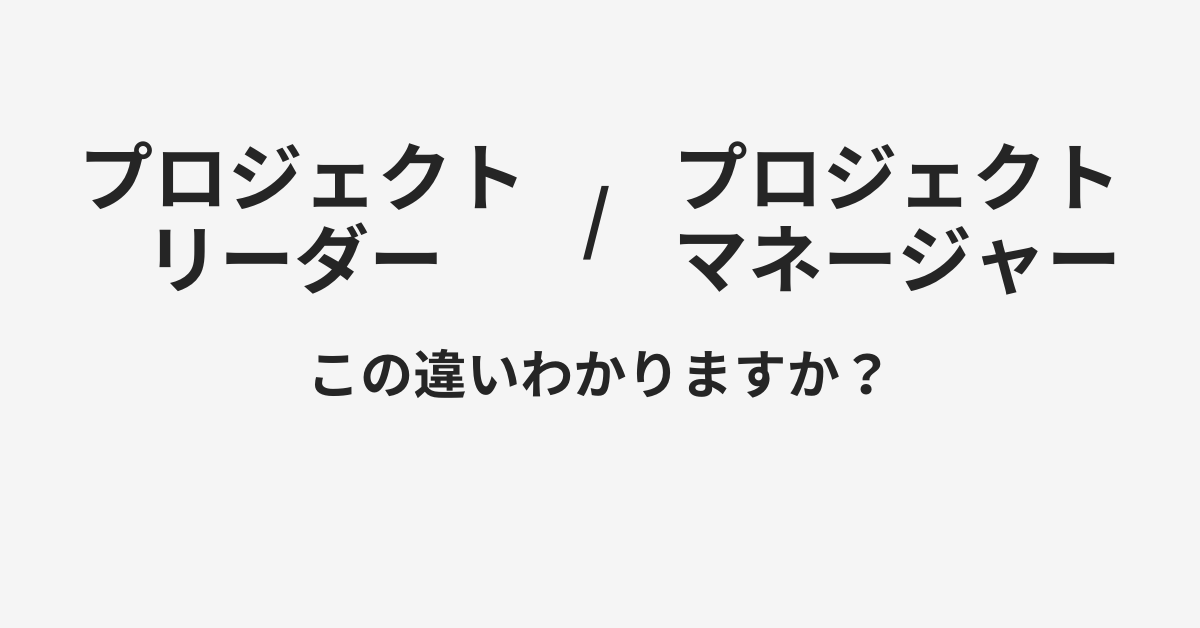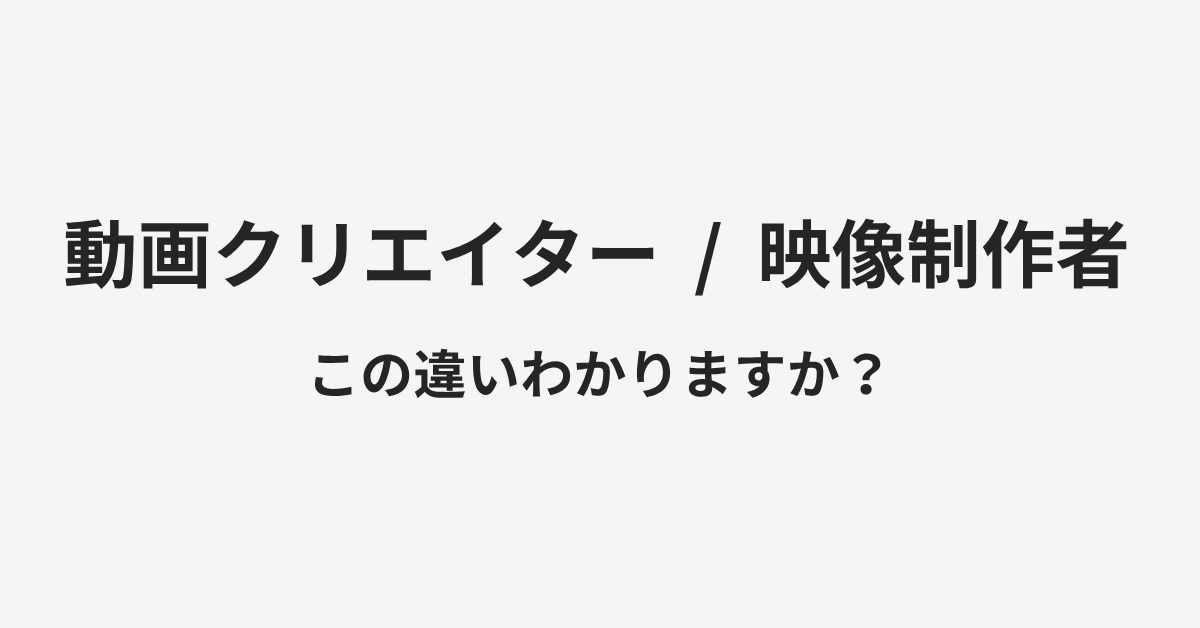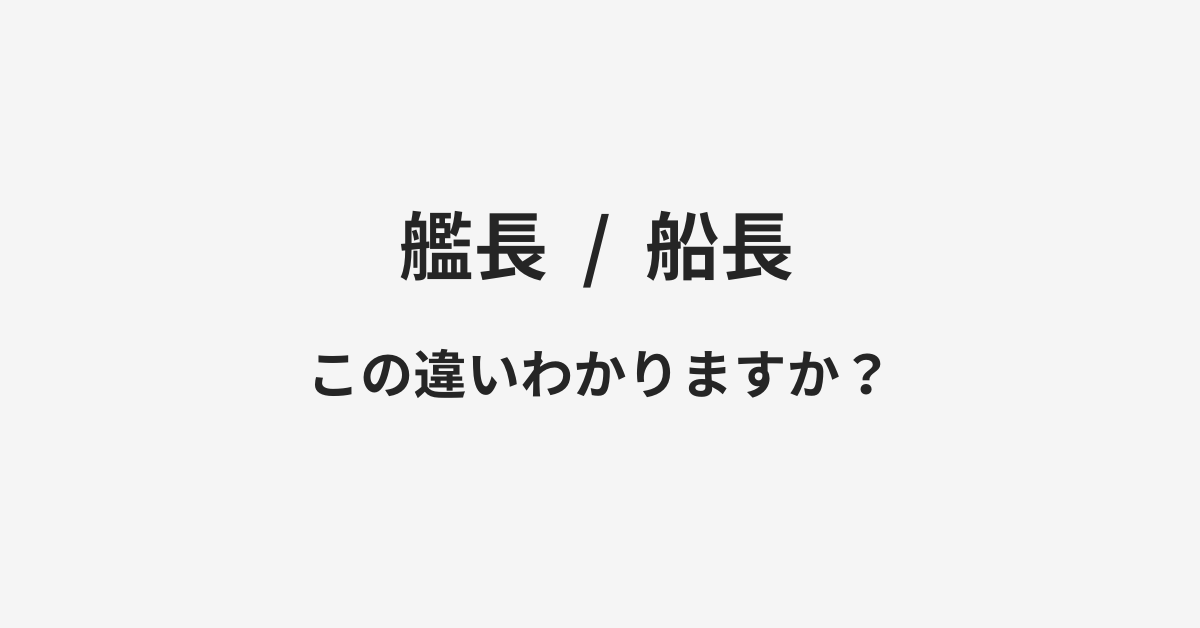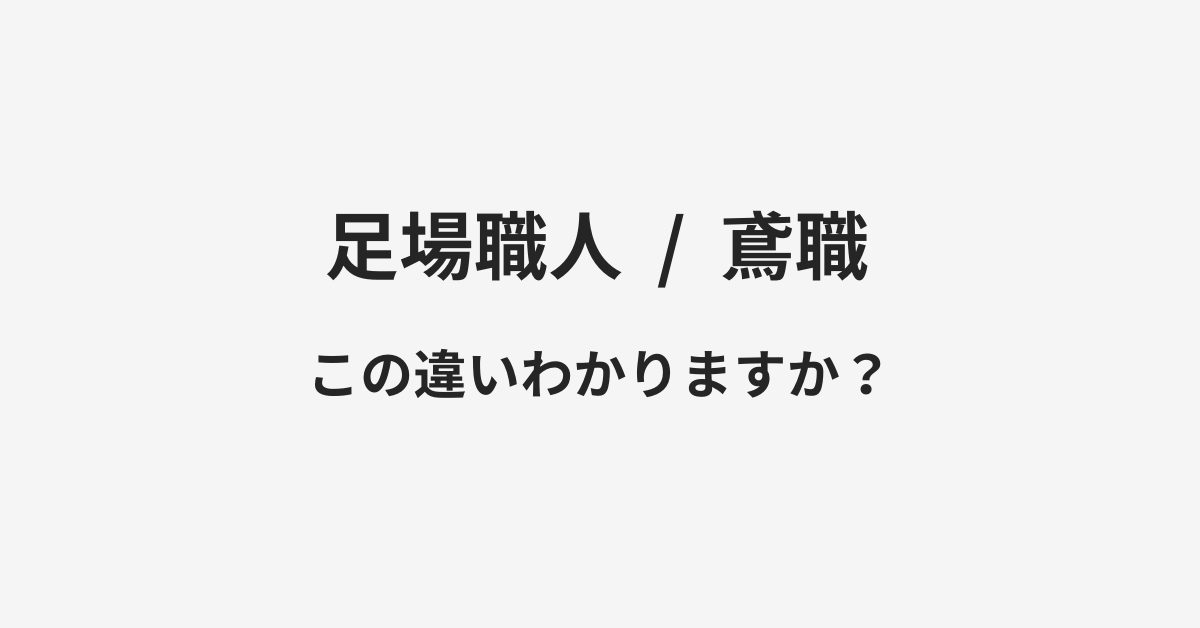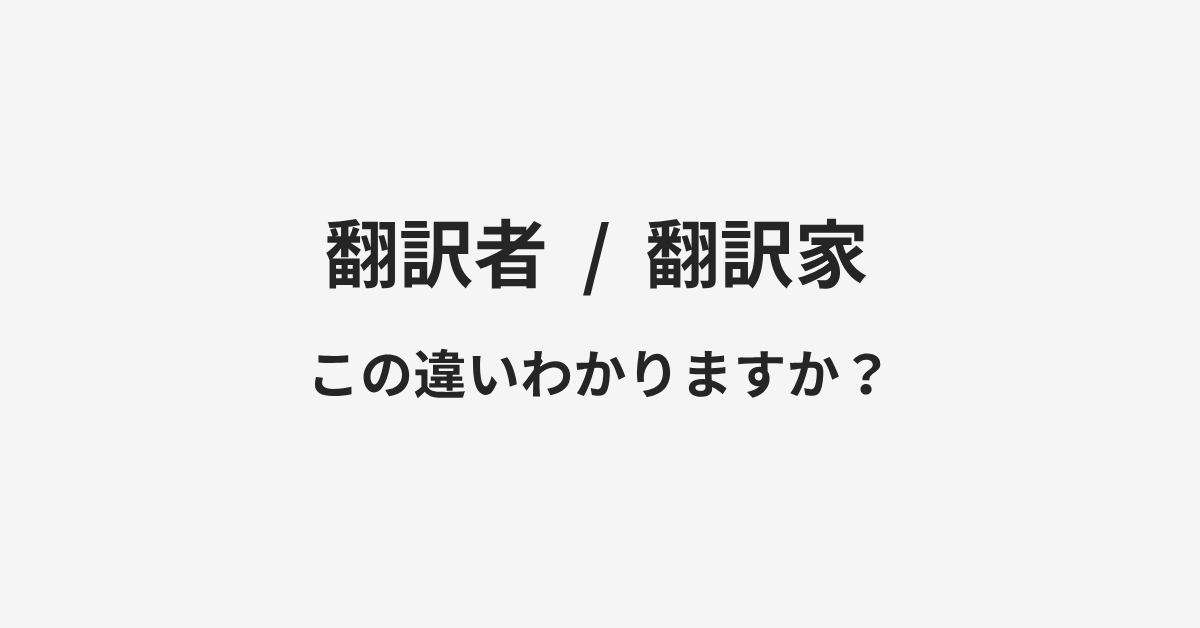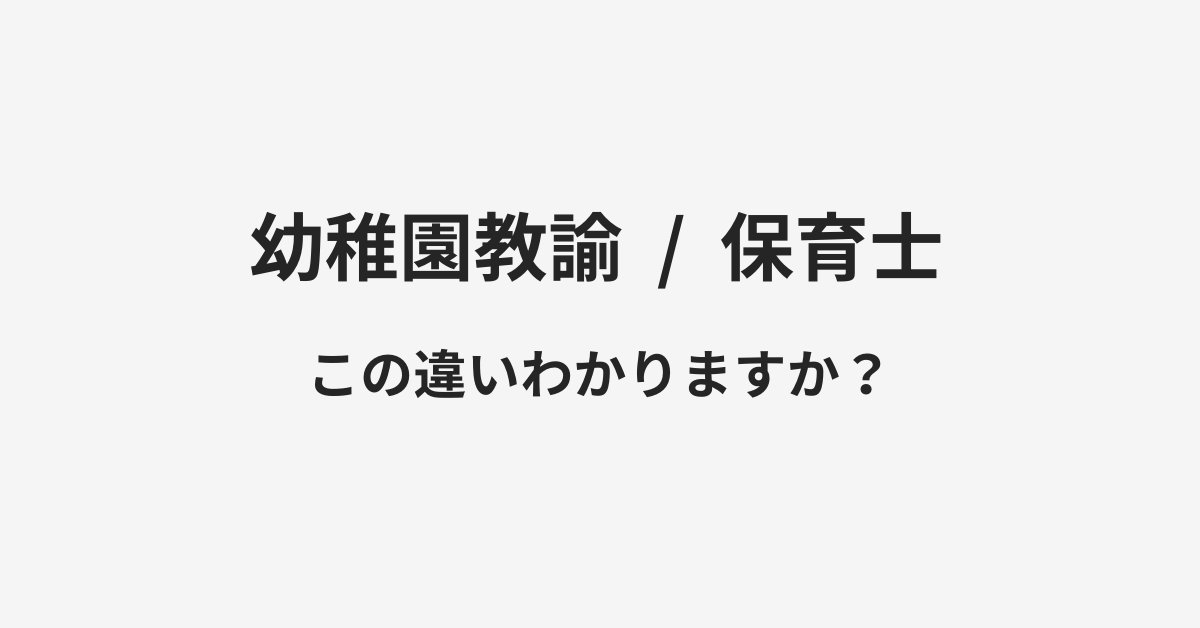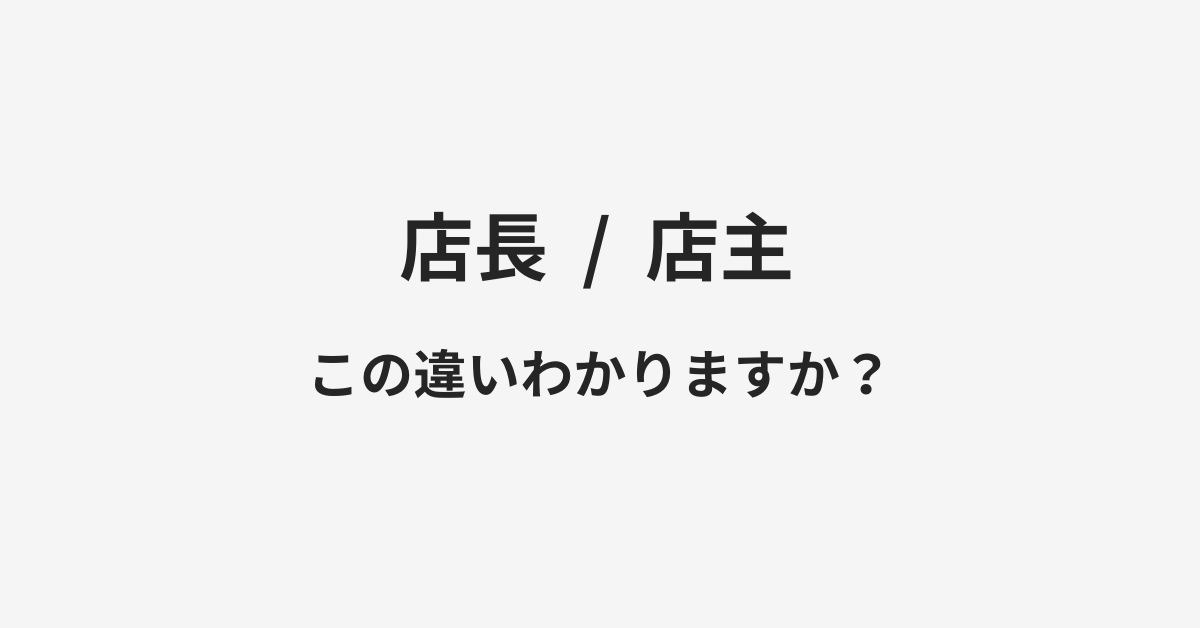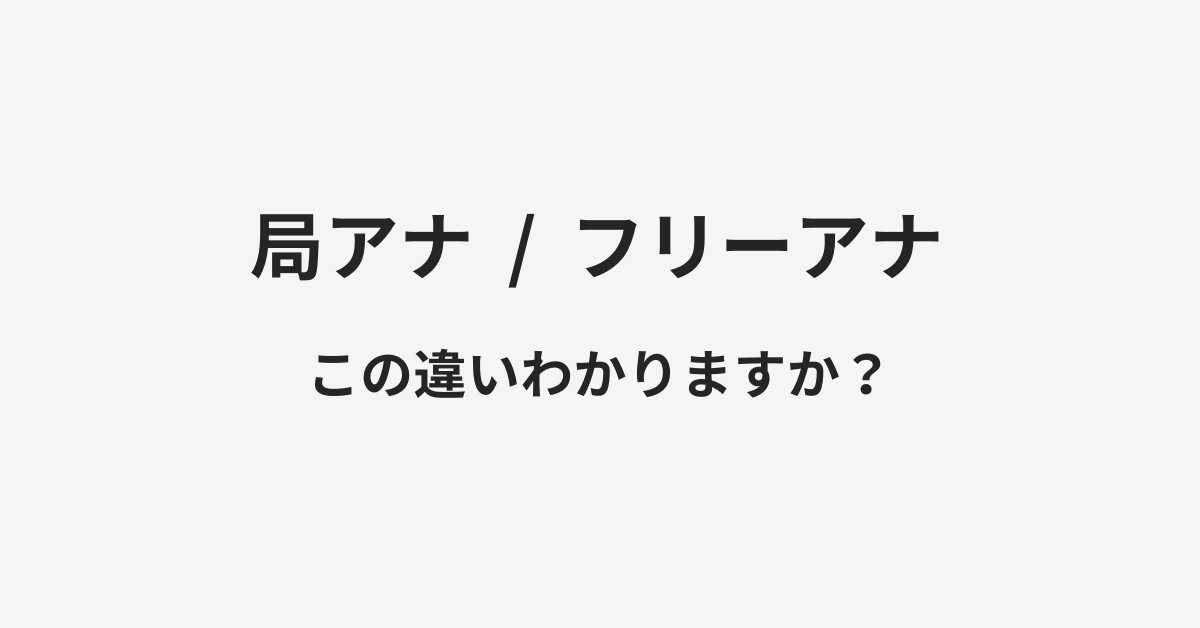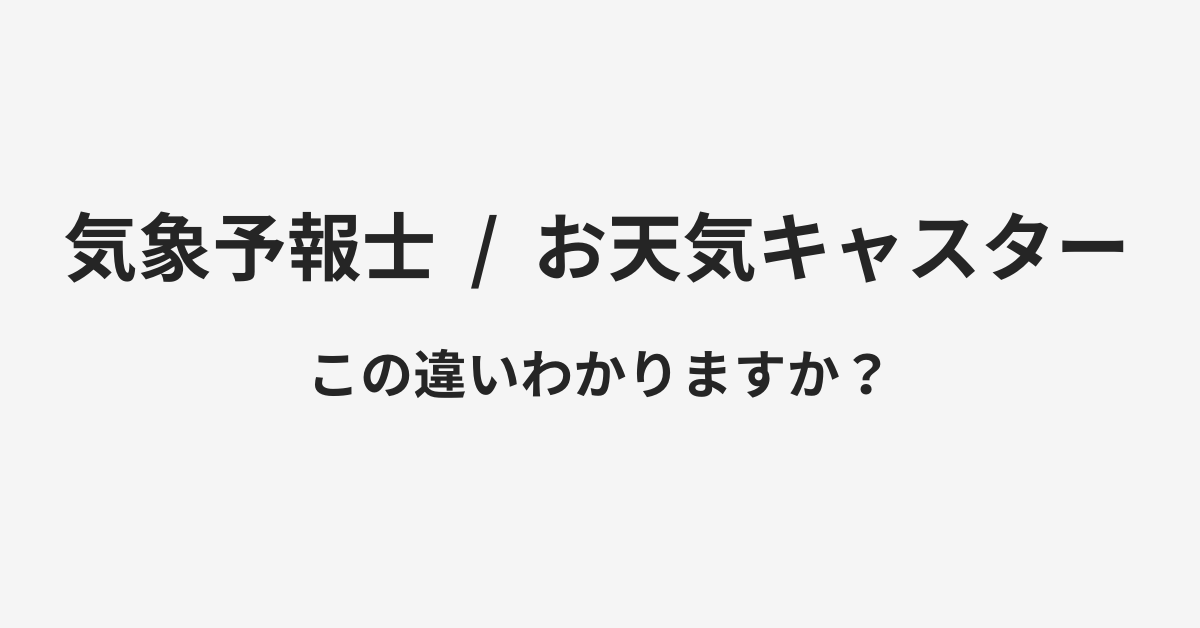【座長】と【司会】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
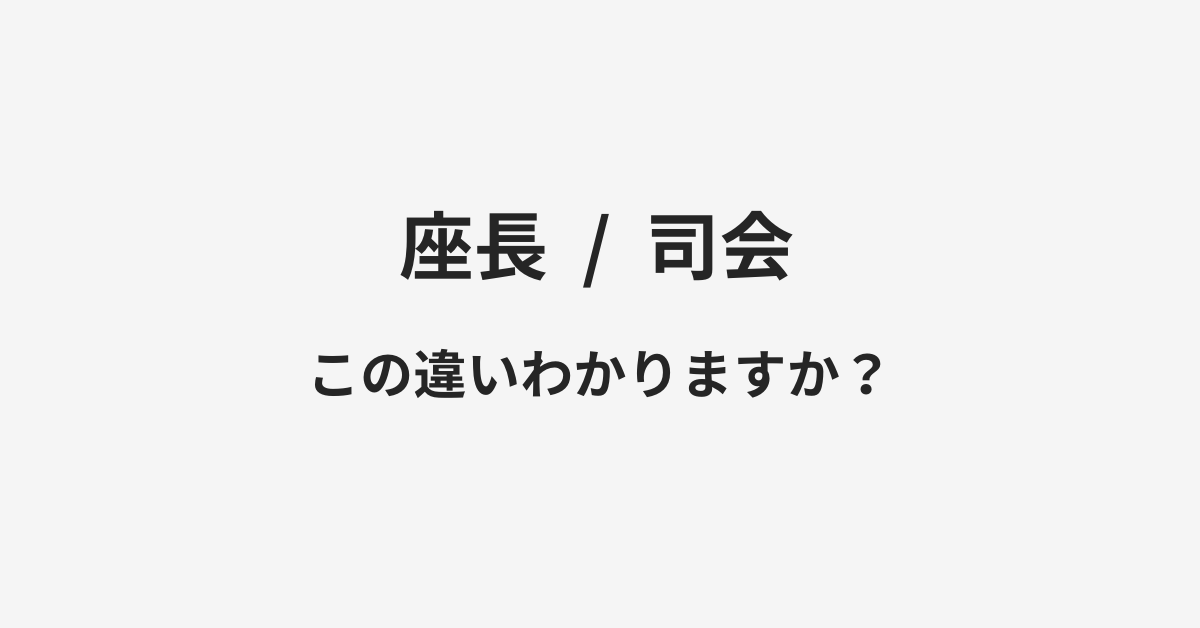
座長と司会の分かりやすい違い
座長と司会は、どちらも会議を運営する役割ですが、その権限と責任の範囲が大きく異なります。座長は会議の内容に責任を持ち、議論を導いて結論を出す立場です。
一方、司会は会議の進行を円滑に行い、時間管理や発言順の調整をする立場です。
ビジネスにおいて、重要な会議では座長が方向性を決め、司会が実務的な進行を担当するという役割分担が効果的です。
座長とは?
座長とは、会議、委員会、研究会などにおいて、その会の最高責任者として議事を統括する役職です。単なる進行役ではなく、議論の方向性を示し、参加者の意見を取りまとめ、最終的な結論や決定に導く重要な役割を担います。学術会議ではチェアマン、審議会では委員長と呼ばれることもあり、その分野の専門知識と経験が求められます。
座長の主な職務は、議題の設定、議論の整理、意見の調整、採決の実施、そして会議の成果に対する責任です。参加者の発言を促しつつ、時には自らの見解を示して議論を深めることも必要です。また、対立する意見がある場合は、中立的な立場から調整し、合意形成を図る高度なファシリテーション能力が求められます。
企業における座長は、経営会議、プロジェクト会議、各種委員会などで任命されます。通常は上級管理職や専門分野のリーダーが務め、会議の決定事項に対して説明責任を負います。座長の力量により会議の成果が大きく左右されるため、適任者の選定が重要です。
座長の例文
- ( 1 ) プロジェクト評価委員会の座長として、最終報告書の取りまとめを行います。
- ( 2 ) 座長として、本日の議論を整理し、次回までの検討事項を明確にしました。
- ( 3 ) 技術審査会の座長を拝命し、公正な評価基準の策定に取り組んでいます。
- ( 4 ) 座長の判断により、この議題については継続審議とすることに決定しました。
- ( 5 ) 経営戦略会議の座長として、5か年計画の方向性を示しました。
- ( 6 ) 座長経験を活かし、難しい利害調整を成功に導きました。
座長の会話例
司会とは?
司会とは、会議、セミナー、イベントなどにおいて、プログラムの進行を担当する役割です。時間管理、発言者の紹介、議事進行の円滑化など、会の運営面を支える重要な存在です。内容への関与は限定的で、中立的な立場から公平に進行することが求められます。モデレーター、ファシリテーターと呼ばれることもあります。
司会の主な業務は、開会・閉会の宣言、アジェンダの説明、発言者への振り分け、時間の管理、質疑応答の調整などです。参加者全員が発言機会を得られるよう配慮し、議論が脱線した際は軌道修正を行います。ただし、議論の内容そのものには深く立ち入らず、あくまで進行役に徹することが基本です。
ビジネスシーンでは、部署の定例会議から大規模なカンファレンスまで、様々な場面で司会が必要とされます。優れた司会者は、場の雰囲気を読み、柔軟に対応しながら予定通りに会を進行させます。話術だけでなく、事前準備の徹底と臨機応変な対応力が成功の鍵となります。
司会の例文
- ( 1 ) 本日の会議の司会を務めさせていただきます、総務部の田中です。
- ( 2 ) 司会として、各部署からの発表時間を厳守していただくようお願いします。
- ( 3 ) 司会進行表を作成し、スムーズな会議運営を心がけています。
- ( 4 ) 司会の経験を積むことで、プレゼンテーション能力も向上しました。
- ( 5 ) 明日のセミナーの司会打ち合わせを行い、進行の詳細を確認しました。
- ( 6 ) 司会として質疑応答の時間調整を行い、予定通り会議を終了しました。
司会の会話例
座長と司会の違いまとめ
座長と司会の最大の違いは、権限と責任の範囲です。座長は会議の内容と結論に責任を持つ意思決定者であり、司会は進行に責任を持つ運営者という明確な違いがあります。役割の違いも重要で、座長は議論に参加し方向付けを行いますが、司会は中立的立場を保ち進行に専念します。
また、座長は通常その分野の専門家や上級管理職が務めますが、司会は進行スキルがあれば誰でも務められます。
効果的な会議運営では、座長と司会を別々に置くことで、座長は内容に集中でき、司会は円滑な進行を確保できます。両者の適切な連携により、生産的な会議が実現します。
座長と司会の読み方
- 座長(ひらがな):ざちょう
- 座長(ローマ字):zachou
- 司会(ひらがな):しかい
- 司会(ローマ字):shikai