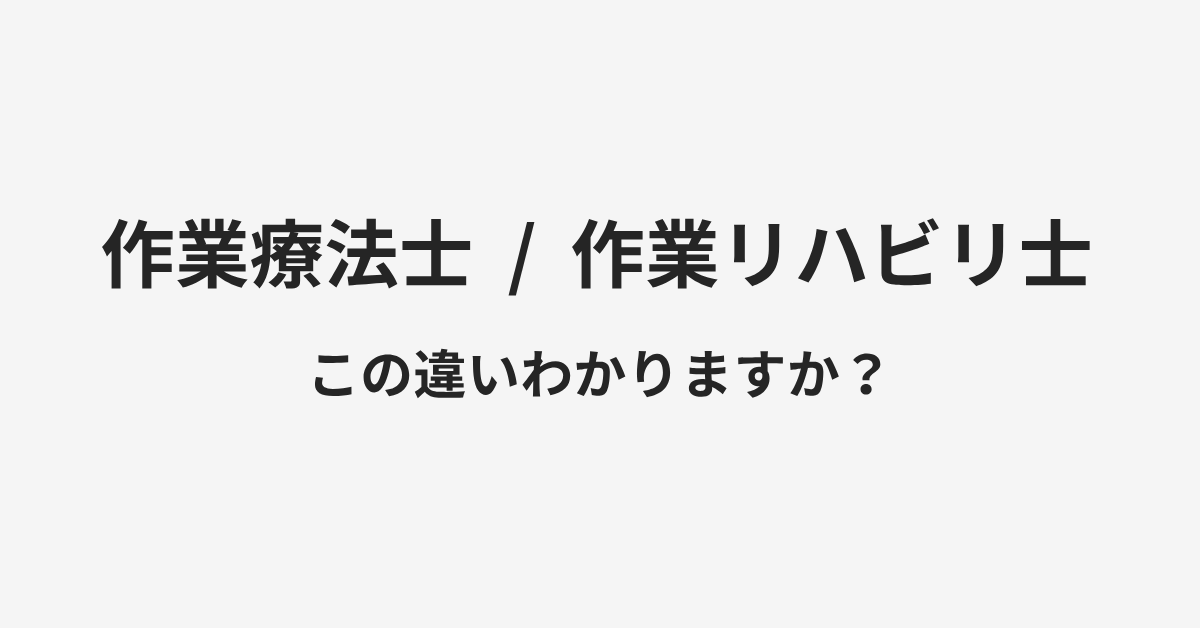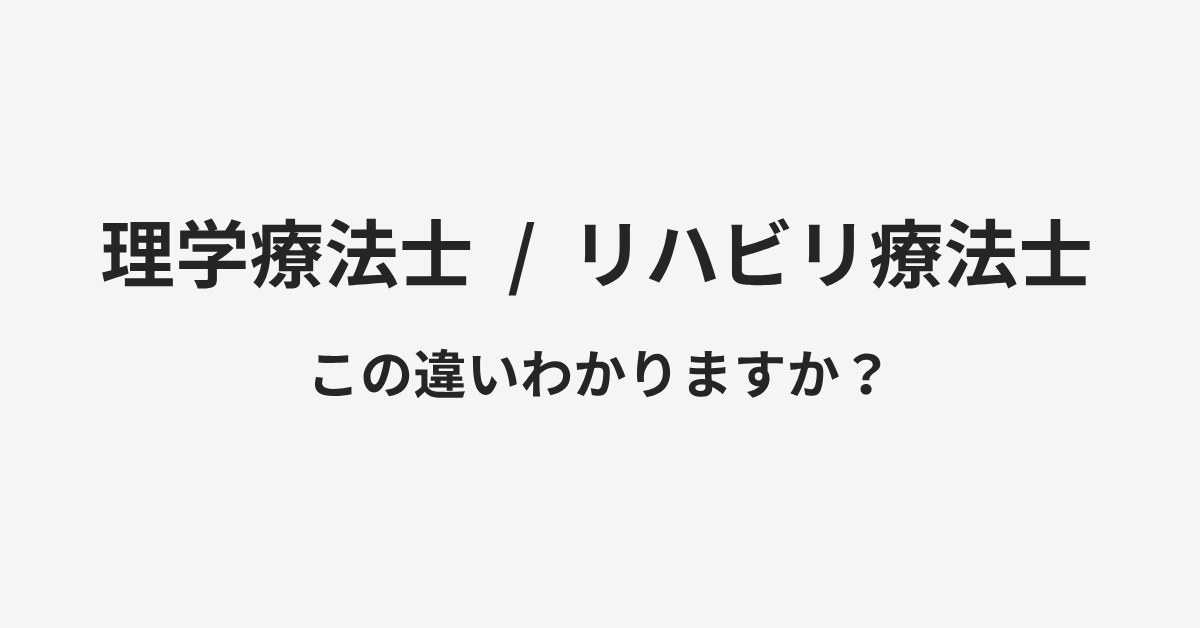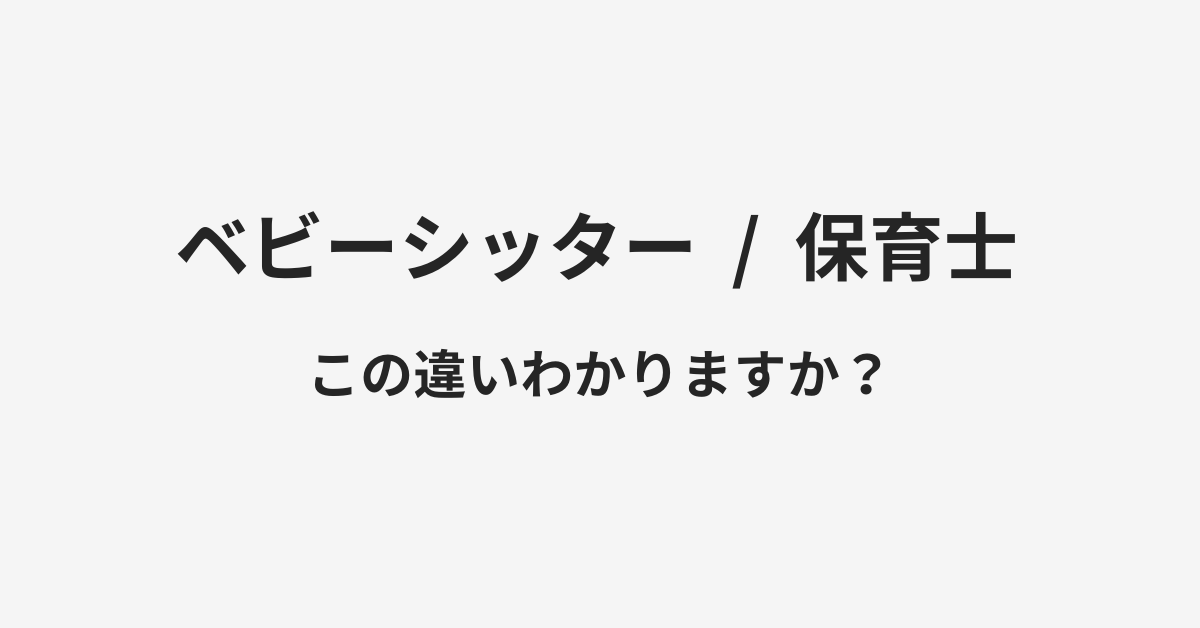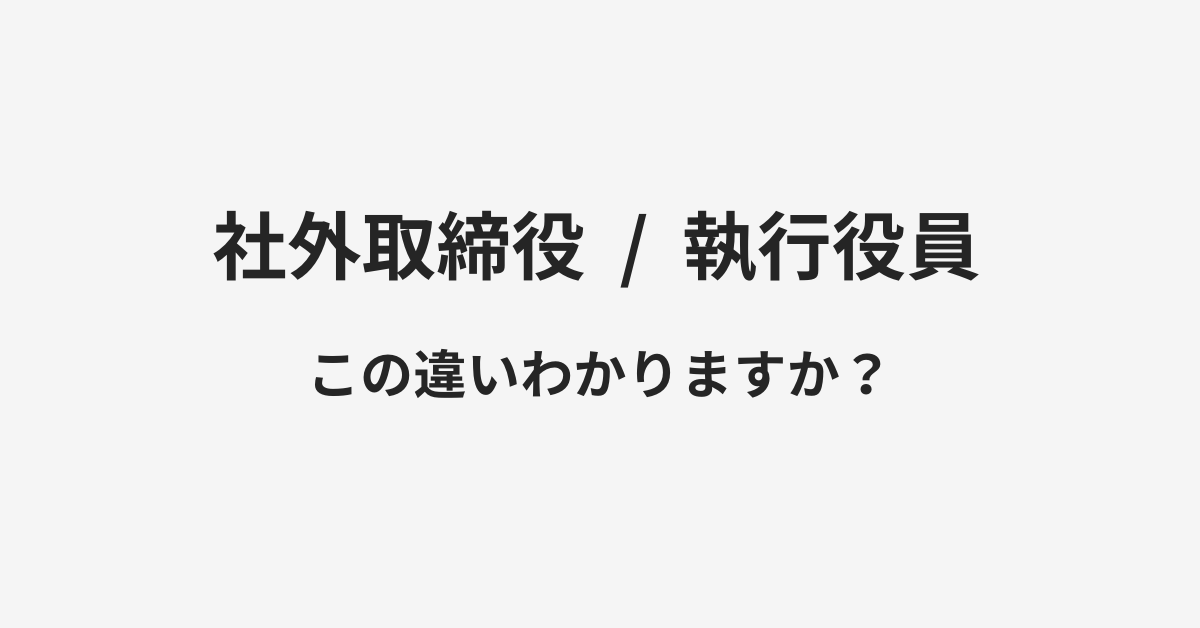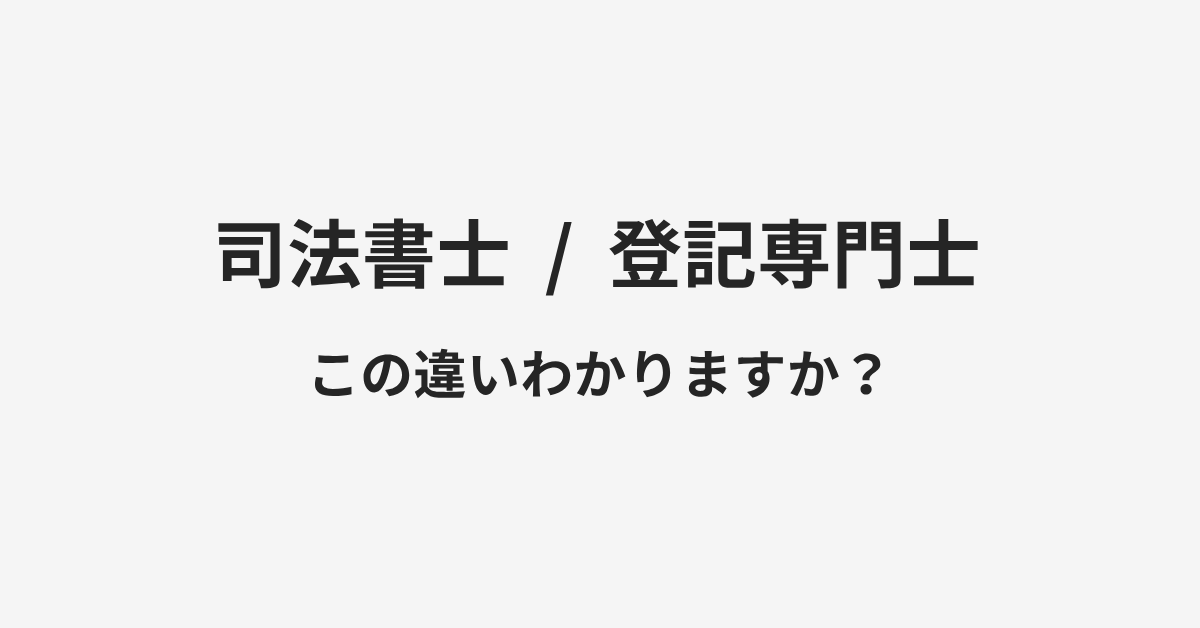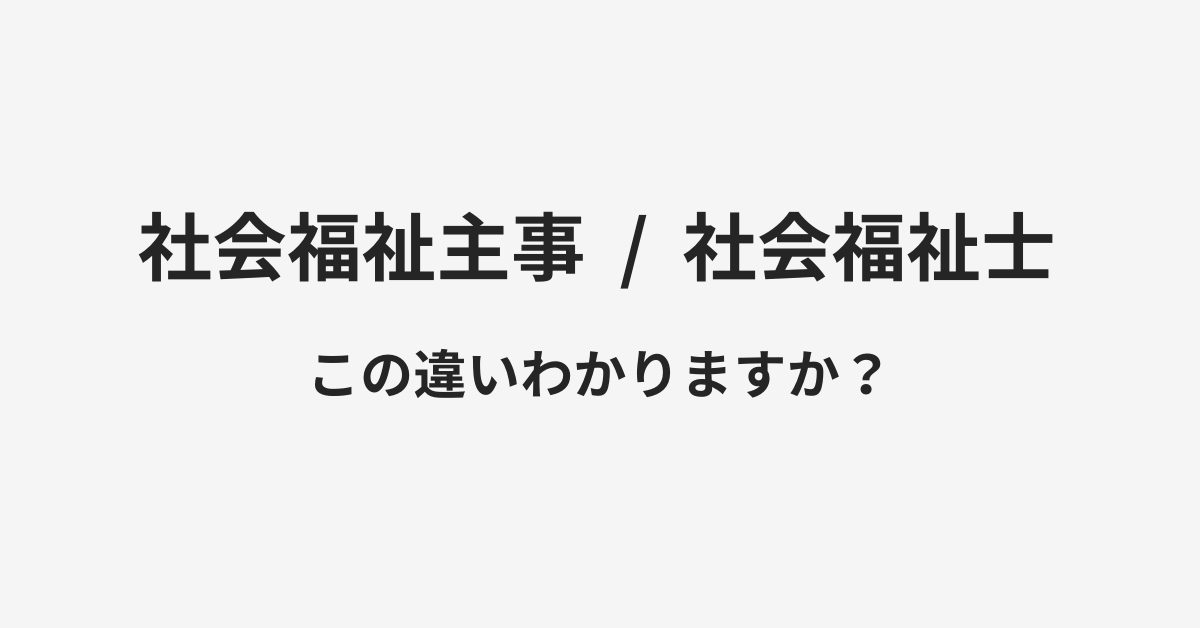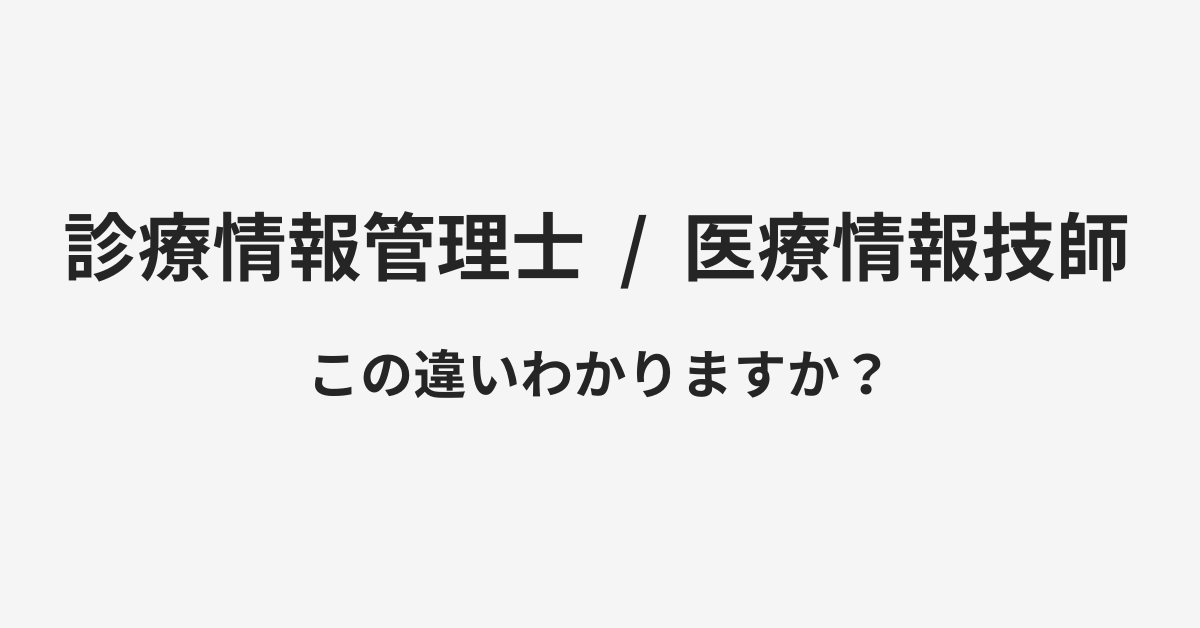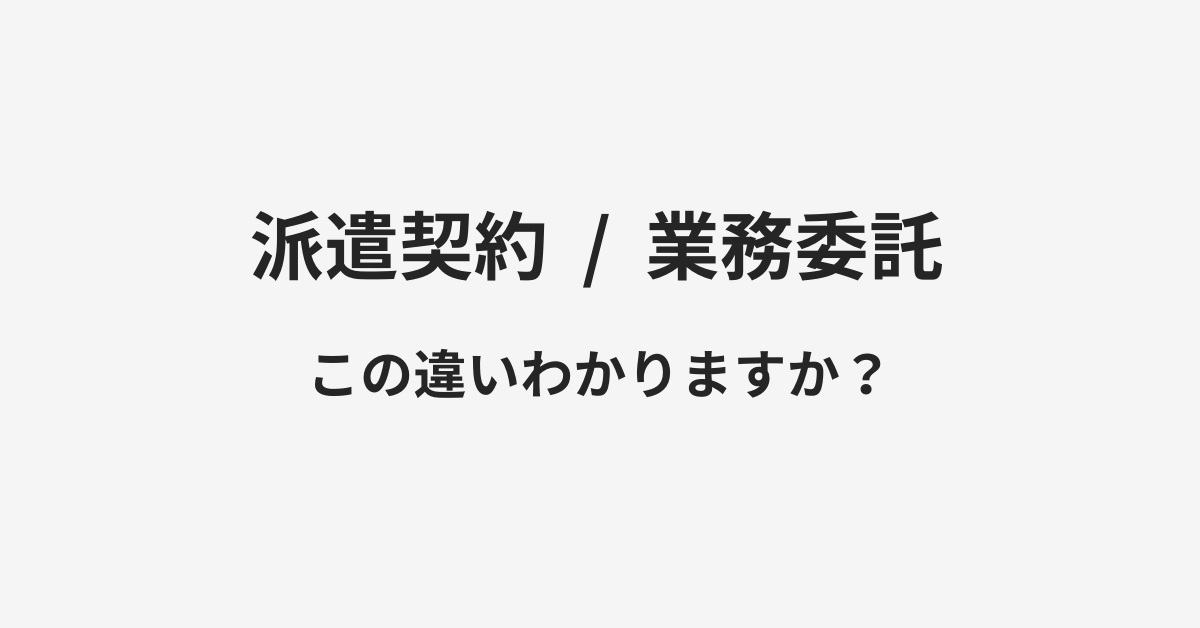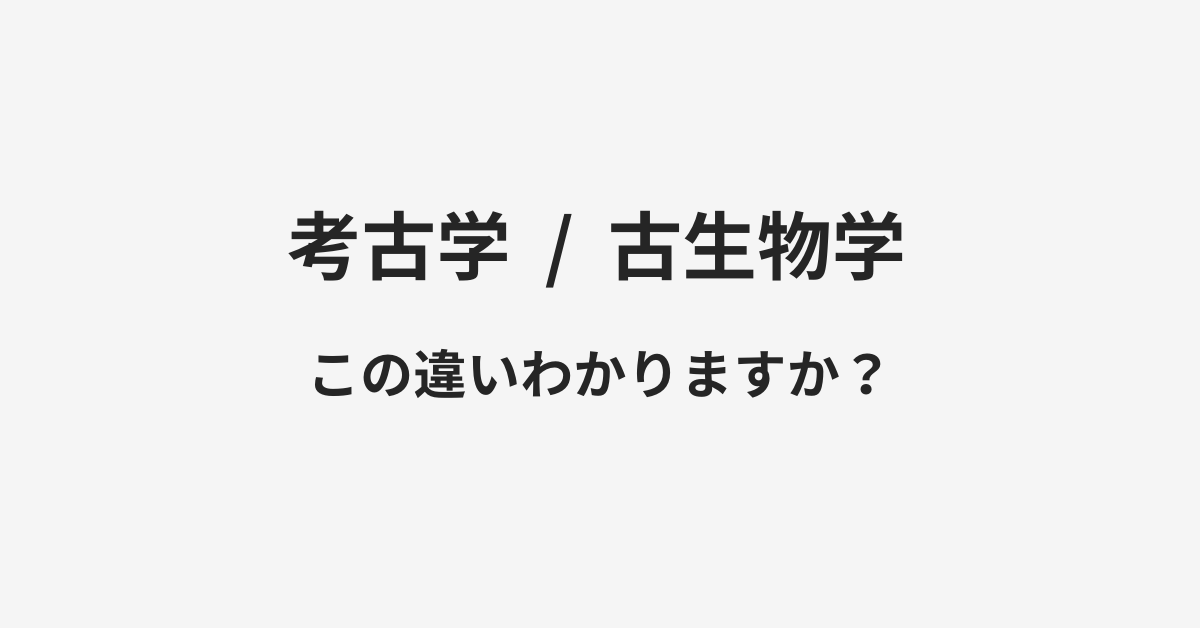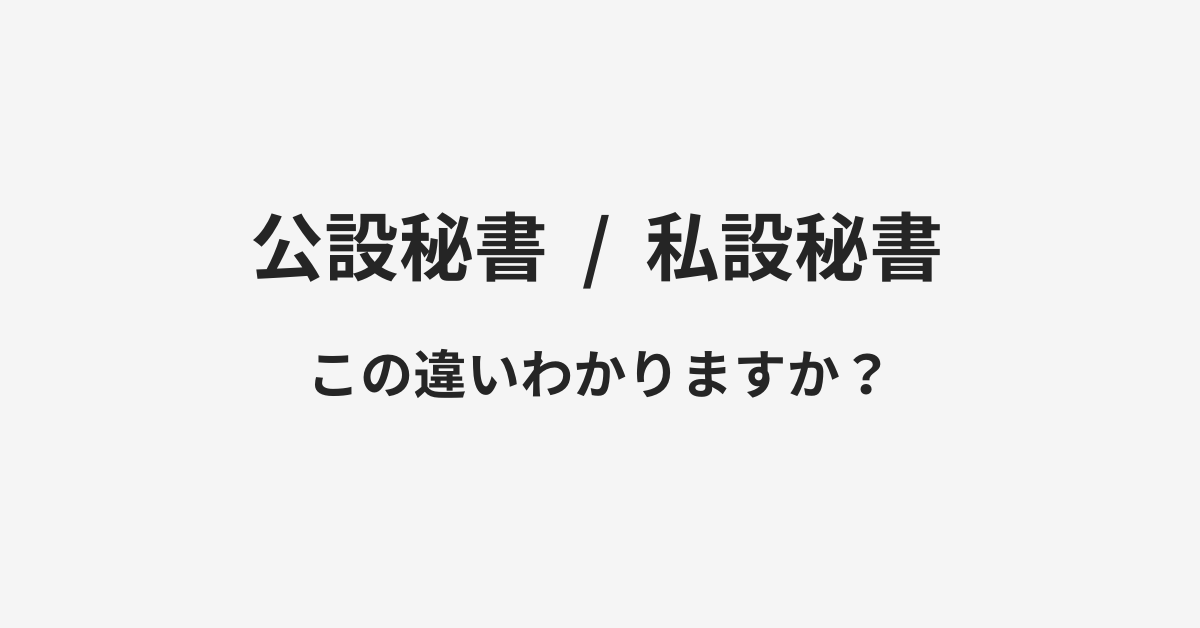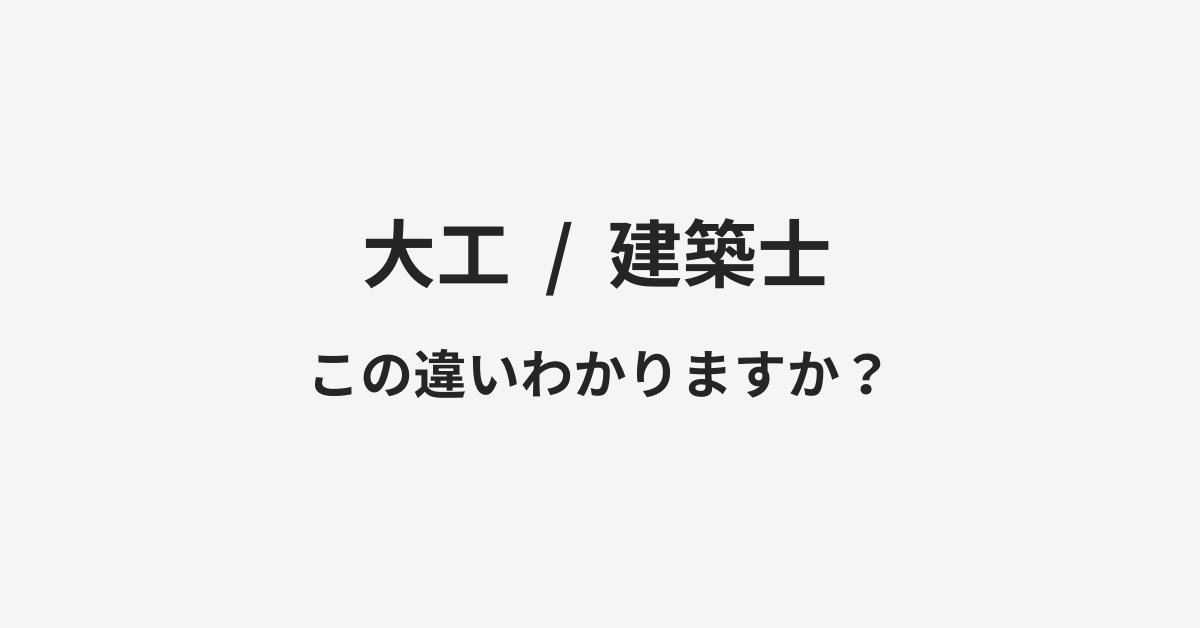【助産師】と【産婆】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
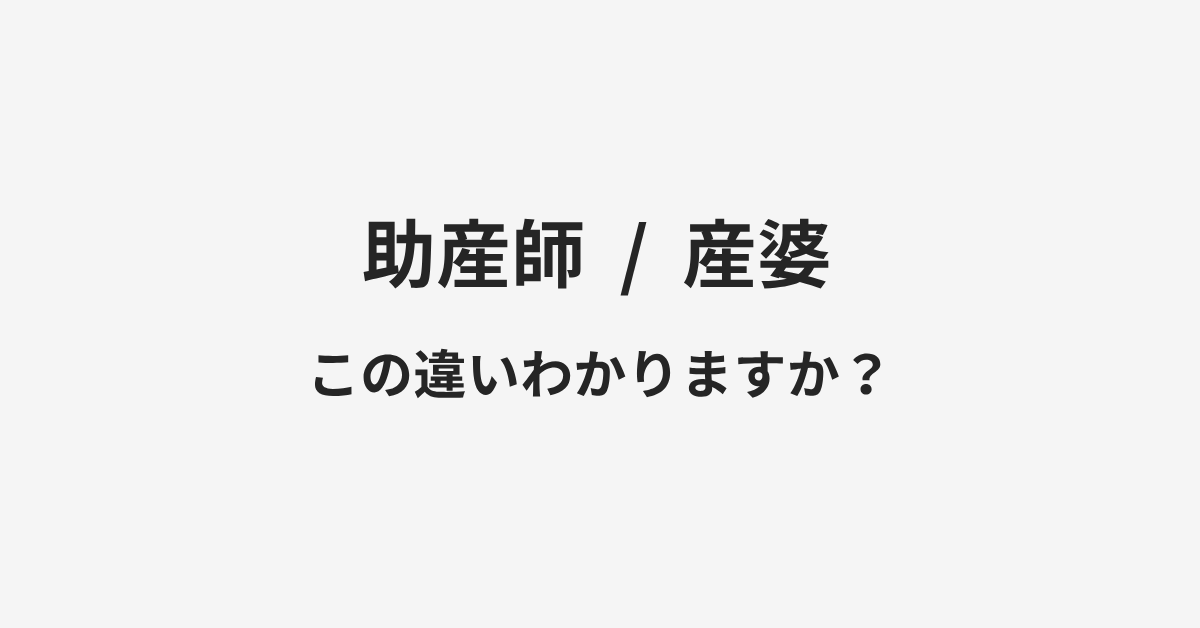
助産師と産婆の分かりやすい違い
助産師と産婆は、どちらも赤ちゃんを取り上げる仕事ですが、時代と資格が大きく異なります。助産師は現在の正式な名前で、看護師資格を持った上で、さらに専門の勉強をした国家資格を持つ専門家です。
産婆は昔使われていた呼び方で、今では使われません。
戦前は地域で出産を助ける重要な存在でしたが、現在は助産師という言葉に変わりました。
助産師とは?
助産師とは、保健師助産師看護師法に基づく国家資格を持ち、妊娠・出産・産褥期の女性と新生児のケアを専門に行う医療職です。正常分娩の介助、妊婦健診、母乳指導、育児相談など、女性の生涯にわたる健康支援を行います。助産師になるには、看護師資格取得後、助産師養成課程(1年以上)を修了し、国家試験に合格する必要があります。
病院、診療所、助産院での勤務の他、地域での母子保健活動も行います。開業権があり、助産院を開設することも可能です。
キャリアパスは、病院勤務から始まり、アドバンス助産師認定取得、母性看護専門看護師への道もあります。少子化でも需要は高く、不妊治療や更年期ケアなど、活躍の場は広がっています。平均年収は約550万円です。
助産師の例文
- ( 1 ) 助産師として独立開業を考えていますが、準備すべきことは?
- ( 2 ) 男性でも助産師になれますか。実際に働いている人はいますか
- ( 3 ) 助産師の夜勤は大変だと聞きますが、実際はどうですか
- ( 4 ) 病院勤務の助産師から地域での活動に転向したいです
- ( 5 ) 助産師として不妊治療分野で働くことは可能ですか
- ( 6 ) アドバンス助産師の認定を取るメリットを教えてください
助産師の会話例
産婆とは?
産婆とは、戦前から昭和中期まで使用された、出産介助を行う女性の呼称です。1947年の保健婦助産婦看護婦法制定により助産婦に改称され、2002年から男女共通の助産師となりました。現在、産婆という呼称は使用されていません。
歴史的には、地域に根ざした存在として、医療機関が少ない時代に自宅出産を支えました。経験と勘に頼る部分が大きく、徒弟制度で技術を伝承していました。取り上げ婆さんとも呼ばれ、地域の女性たちの相談役でもありました。
現代では産婆という言葉は時代錯誤とされ、専門教育を受けた助産師が科学的根拠に基づくケアを提供しています。ただし、高齢者の中には親しみを込めて産婆さんと呼ぶ人もいますが、職業名としては不適切です。
産婆の例文
- ( 1 ) 昔の産婆さんはどんな仕事をしていたのですか
- ( 2 ) 私の祖母が産婆でした。その経験は今でも活かせますか
- ( 3 ) 地域の高齢者が私を産婆さんと呼びますが、どう対応すべき?
- ( 4 ) 産婆の歴史について研究したいのですが、資料はありますか
- ( 5 ) 昔の産婆と現代の助産師で、変わらないものは何ですか
- ( 6 ) 産婆という言葉が使われなくなった理由を教えてください
産婆の会話例
助産師と産婆の違いまとめ
助産師と産婆の最大の違いは、時代背景と専門性です。助産師は現代の国家資格による専門職、産婆は過去の呼称で現在は使用されません。履歴書や公的な場面では必ず助産師を使用し、産婆は歴史的文脈でのみ使用します。
現代の医療現場で産婆という言葉を使うことは、専門性を軽視する印象を与えるため避けるべきです。助産師は医学的知識に基づく専門職として、女性と赤ちゃんの健康を守る重要な役割を担っており、その専門性と社会的地位は時代とともに大きく向上しています。
助産師と産婆の読み方
- 助産師(ひらがな):じょさんし
- 助産師(ローマ字):josannshi
- 産婆(ひらがな):さんば
- 産婆(ローマ字):sannba