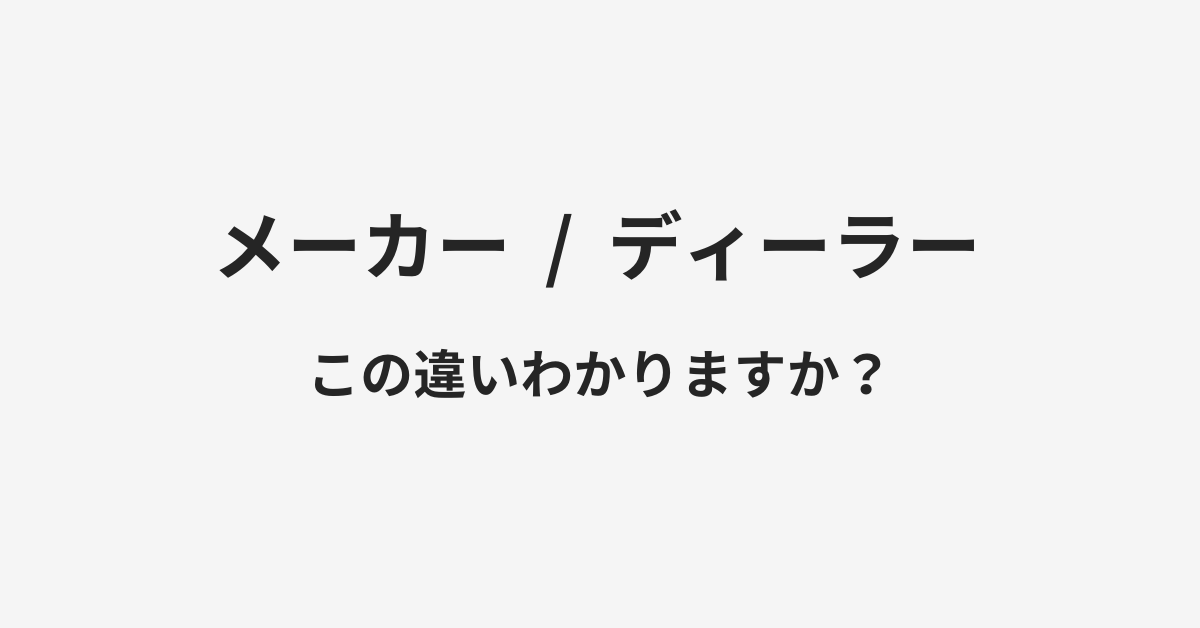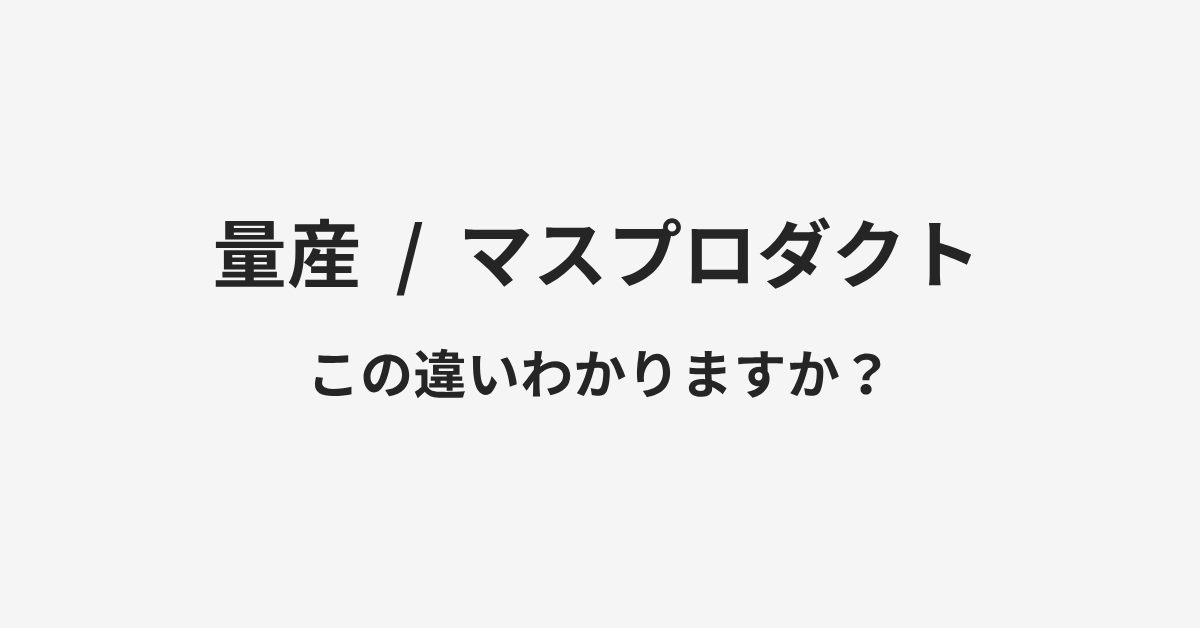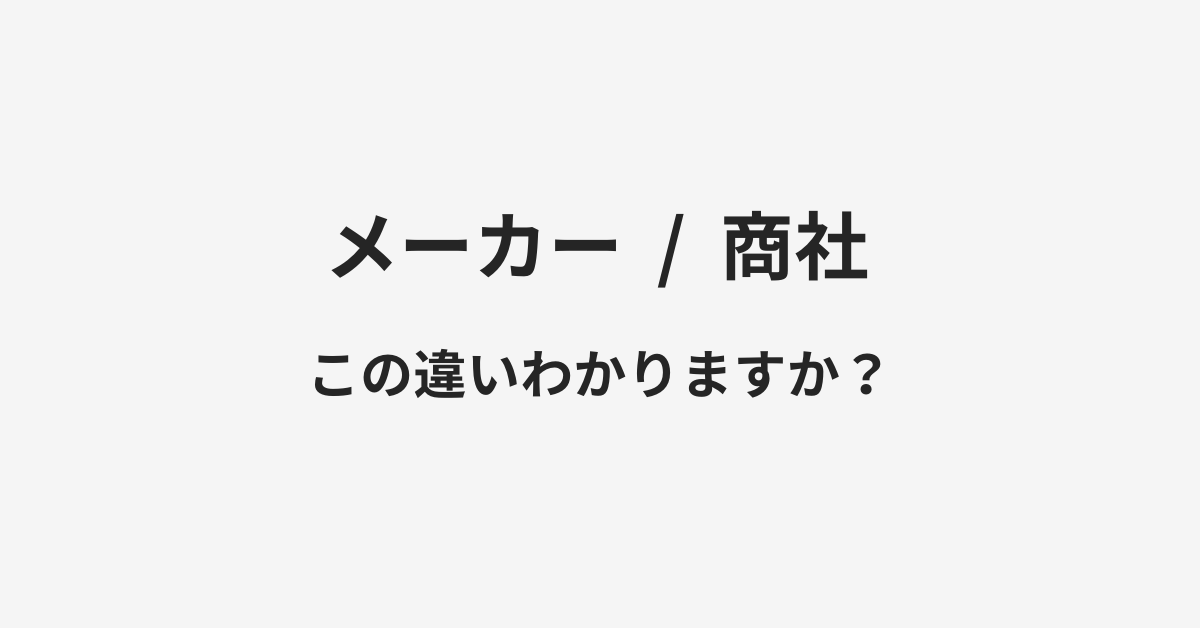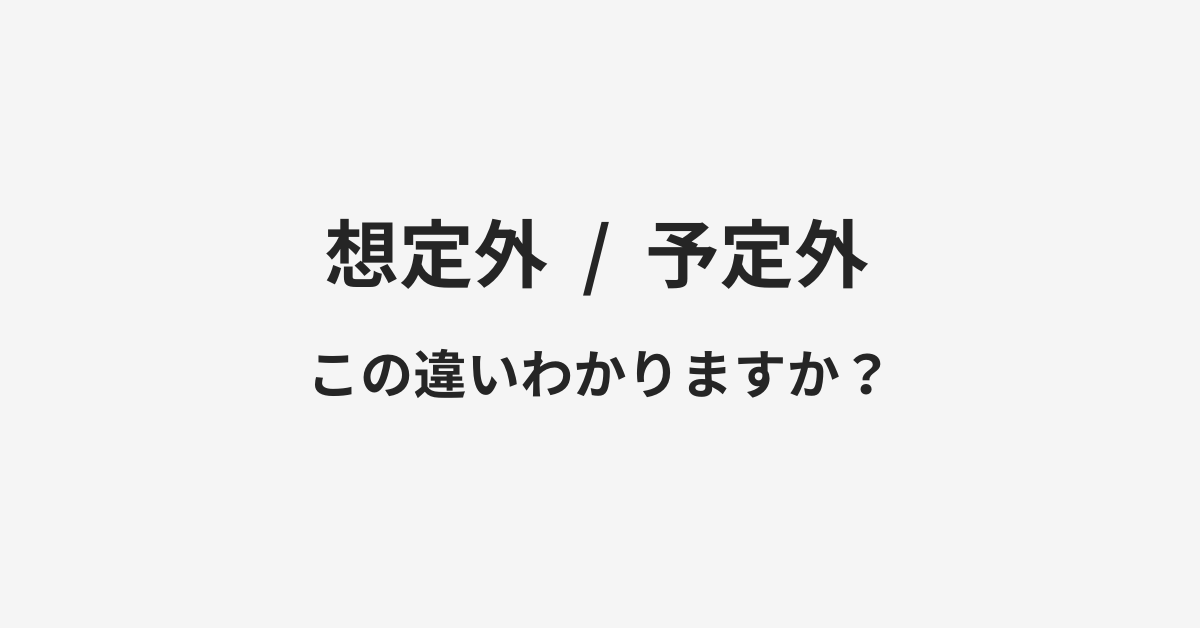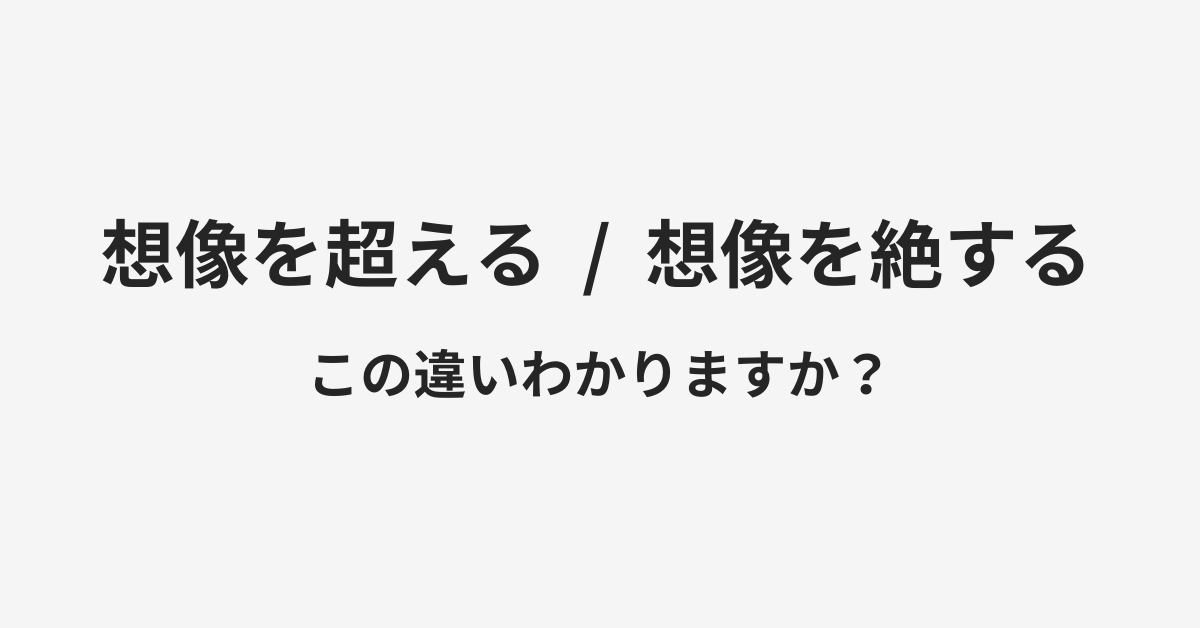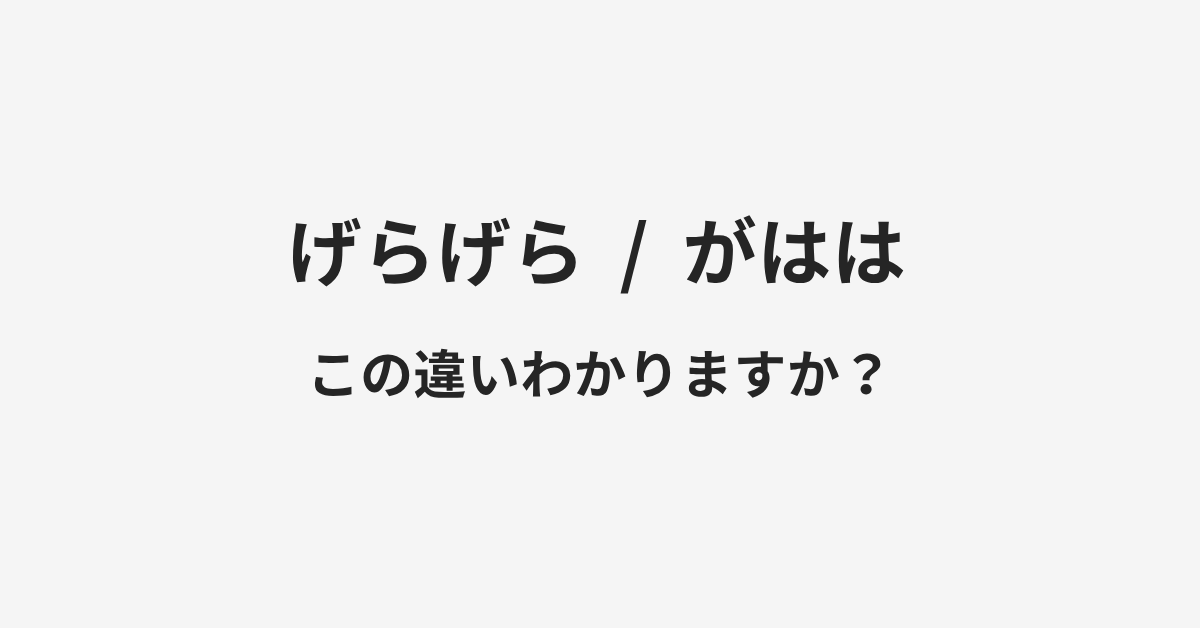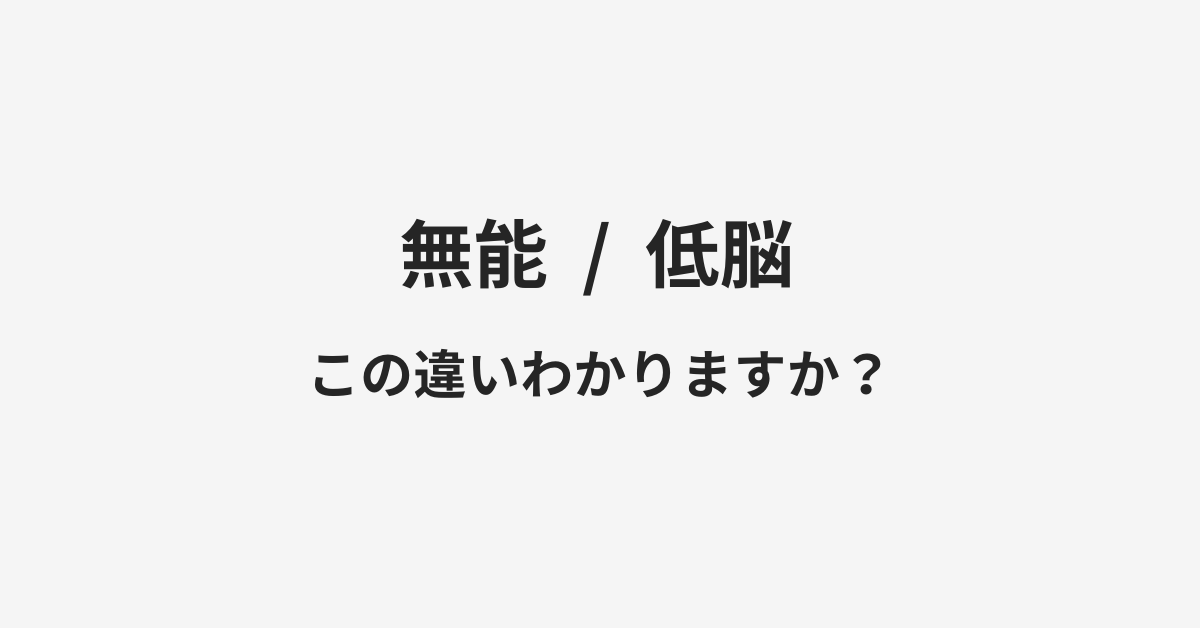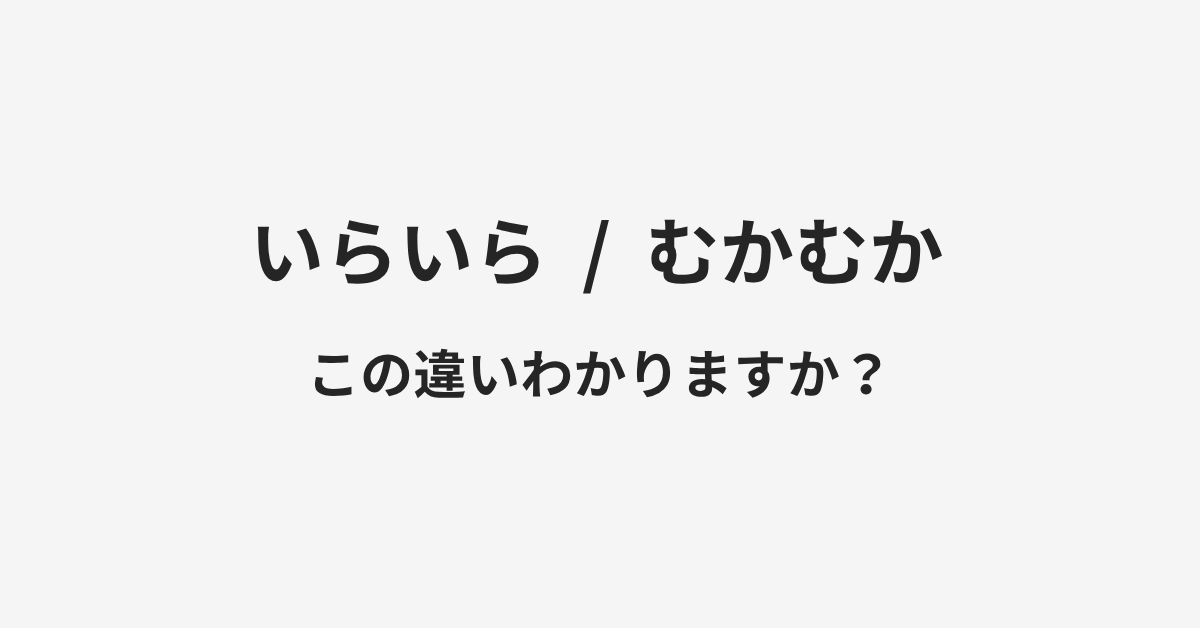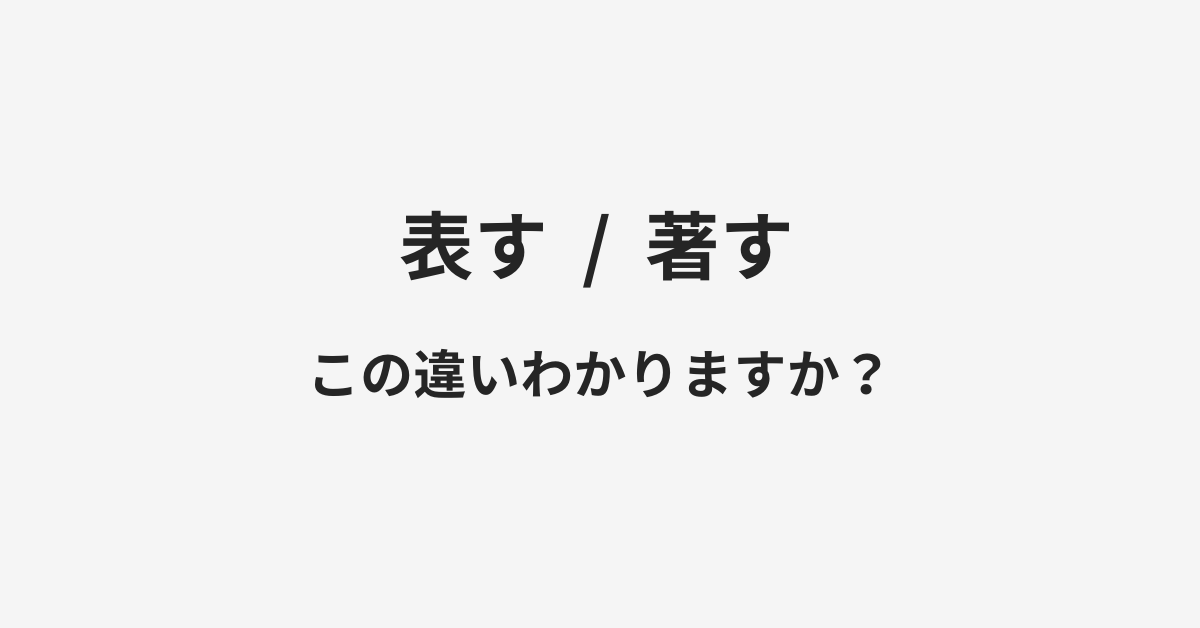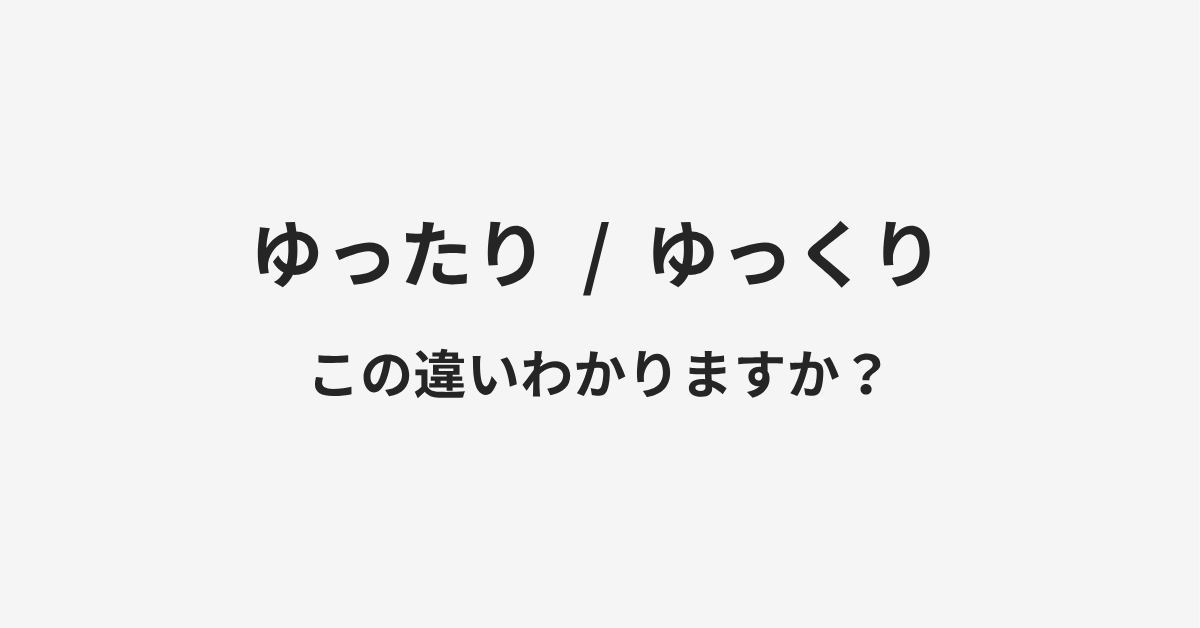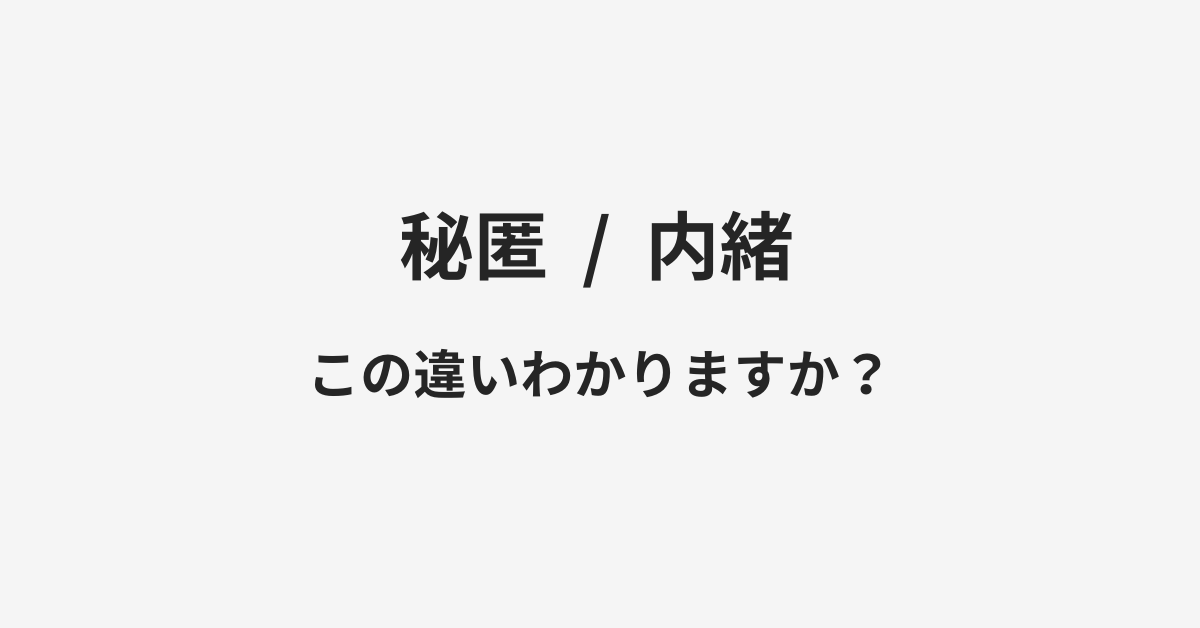【副産物】と【連産品】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
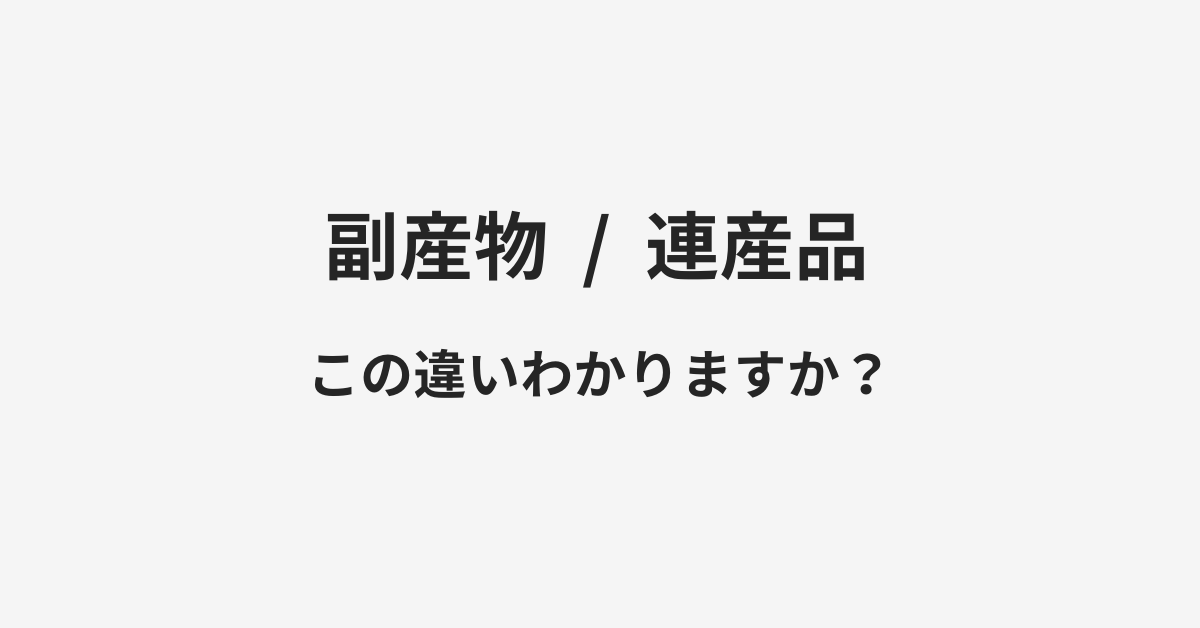
副産物と連産品の分かりやすい違い
副産物と連産品は、どちらも製造過程で生まれる物ですが、意図が異なります。副産物は主製品のおまけ的な物、連産品は同時に生産される複数の主要製品です。
砂糖製造の副産物である糖蜜と、石油精製の連産品であるガソリンと軽油の違いです。
副産物とは?
副産物とは、主な製品を作る過程で、付随的に生まれる物のことです。本来の目的ではないが、結果として得られる物で、価値がある場合もない場合もあります。廃棄物として扱われることもあれば、有効活用されることもあります。
製造過程の副産物、研究の副産物、副産物として生まれたなど、主目的ではない付随的な産物を表現します。
思わぬ発見や利益を指すこともあります。ビール製造のビール粕、精米時の米ぬか、研究中の偶然の発見など、主目的以外で得られる物や成果を表す時に使われます。
副産物の例文
- ( 1 ) ビール製造の副産物であるビール粕は家畜の飼料になる。
- ( 2 ) 精米の副産物である米ぬかは、美容にも使われる。
- ( 3 ) 研究の副産物として、新しい技術が生まれた。
- ( 4 ) チーズ製造の副産物のホエーを活用した商品開発。
- ( 5 ) この発見は実験の副産物だった。
- ( 6 ) 副産物を有効活用することで、廃棄物を減らせる。
副産物の会話例
ビール粕って何?
ビール製造の副産物だよ
これは捨てるの?
副産物だけど、活用できるかも
思わぬ収穫だね
実験の副産物として発見したんだ
連産品とは?
連産品とは、一つの原料や製造工程から、必然的に複数の製品が同時に生産されるものです。どれも主要な製品として扱われ、それぞれに経済的価値があります。石油精製や食肉加工などで典型的に見られます。
石油の連産品、食肉の連産品、連産品の需給バランスなど、同時に生産される複数の主要製品を表現します。すべてが計画的に生産される点が特徴です。
石油からのガソリン・軽油・重油、牛からの各部位の肉、大豆からの油と豆粕など、一つの原料から複数の主要製品が生まれる場合に使われます。
連産品の例文
- ( 1 ) 石油精製では、ガソリンや軽油などの連産品が生まれる。
- ( 2 ) 牛一頭から様々な部位の肉が連産品として得られる。
- ( 3 ) 連産品の需給バランスを考慮した生産計画が必要だ。
- ( 4 ) 大豆からは油と豆粕が連産品として製造される。
- ( 5 ) 連産品すべてに付加価値をつけることが重要だ。
- ( 6 ) 製材所では板材と木片が連産品として生産される。
連産品の会話例
ガソリンと軽油の関係は?
石油精製の連産品だよ
なぜ同時にできるの?
連産品は必然的に一緒に生産されるんだ
価格設定が難しそう
連産品は全体のバランスを考える必要があるね
副産物と連産品の違いまとめ
副産物は付随的な産物、連産品は同時生産される主要製品群です。副産物は偶然性や副次性、連産品は必然性や主要性という違いがあります。
製造業では副産物の有効活用と、連産品の需給調整が重要な課題となります。
副産物と連産品の読み方
- 副産物(ひらがな):ふくさんぶつ
- 副産物(ローマ字):fukusannbutsu
- 連産品(ひらがな):れんさんひん
- 連産品(ローマ字):rennsannhinn