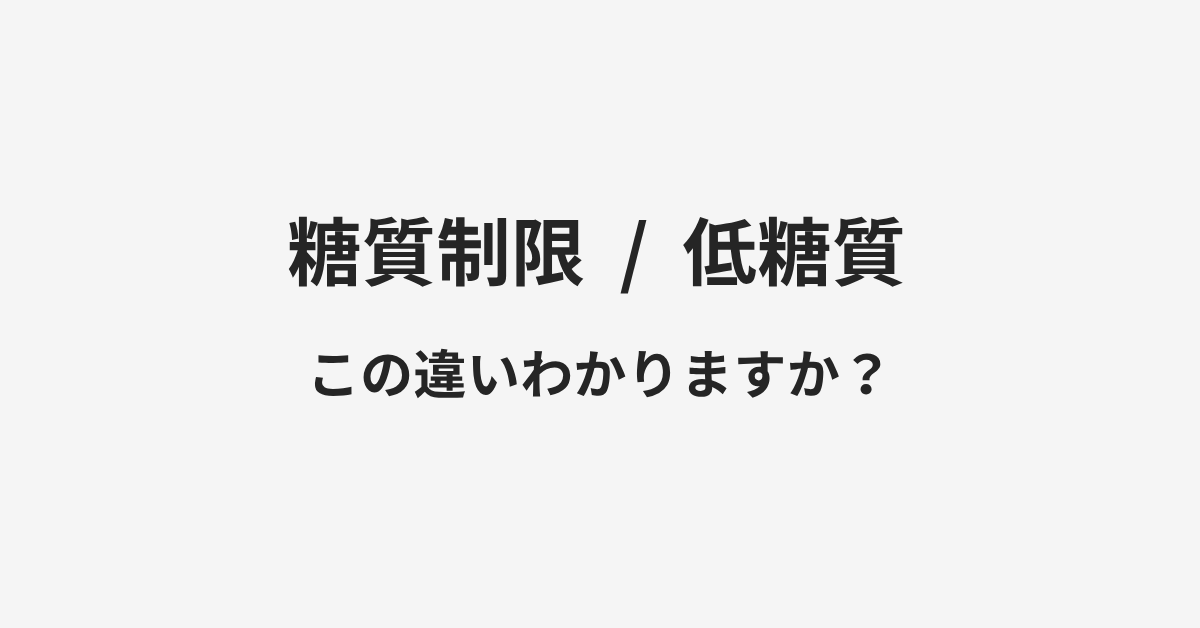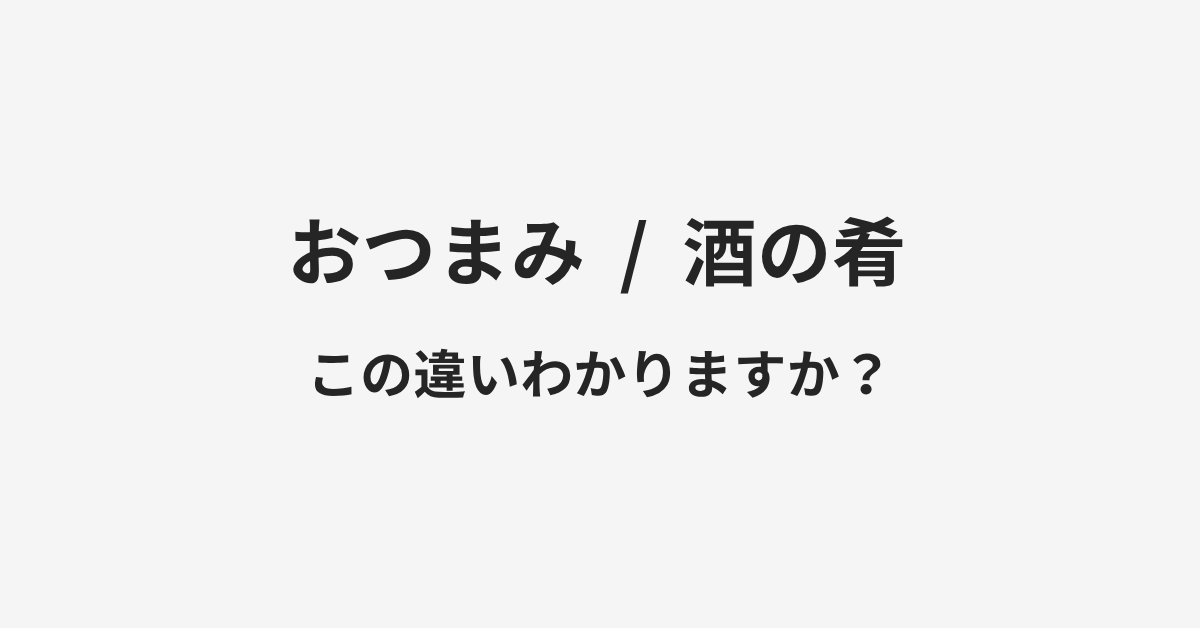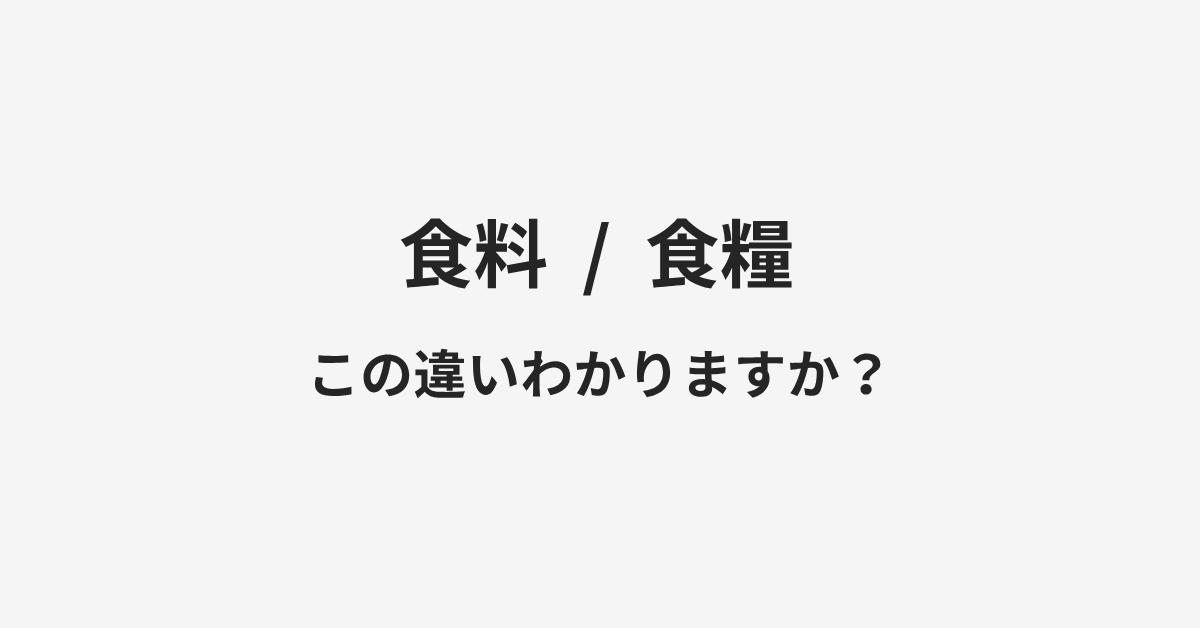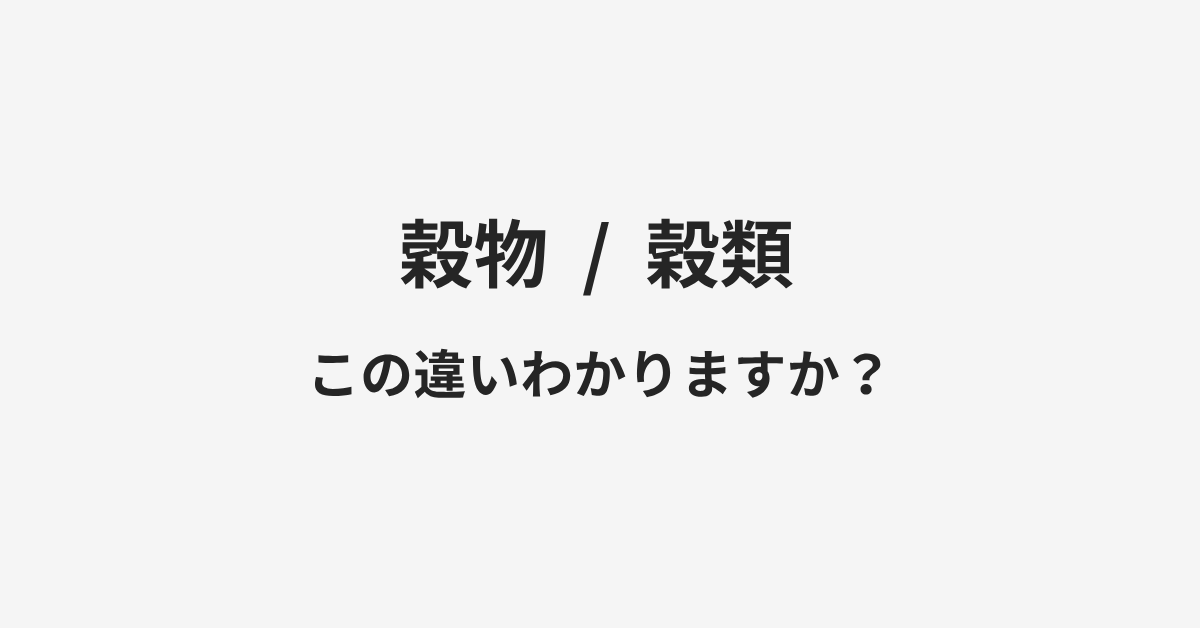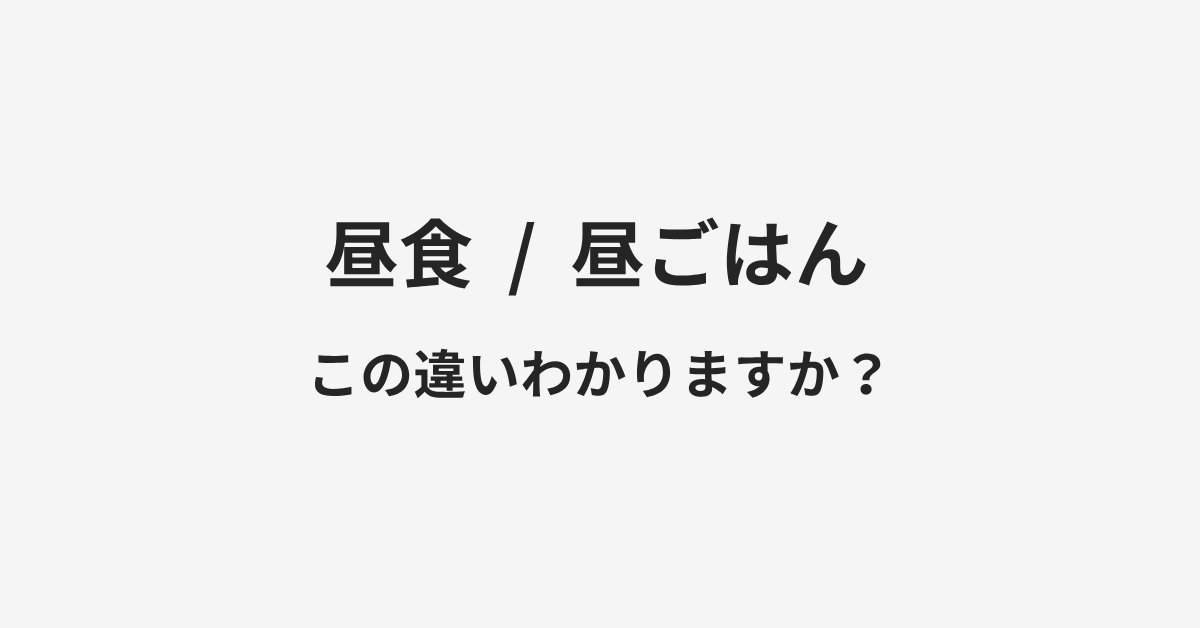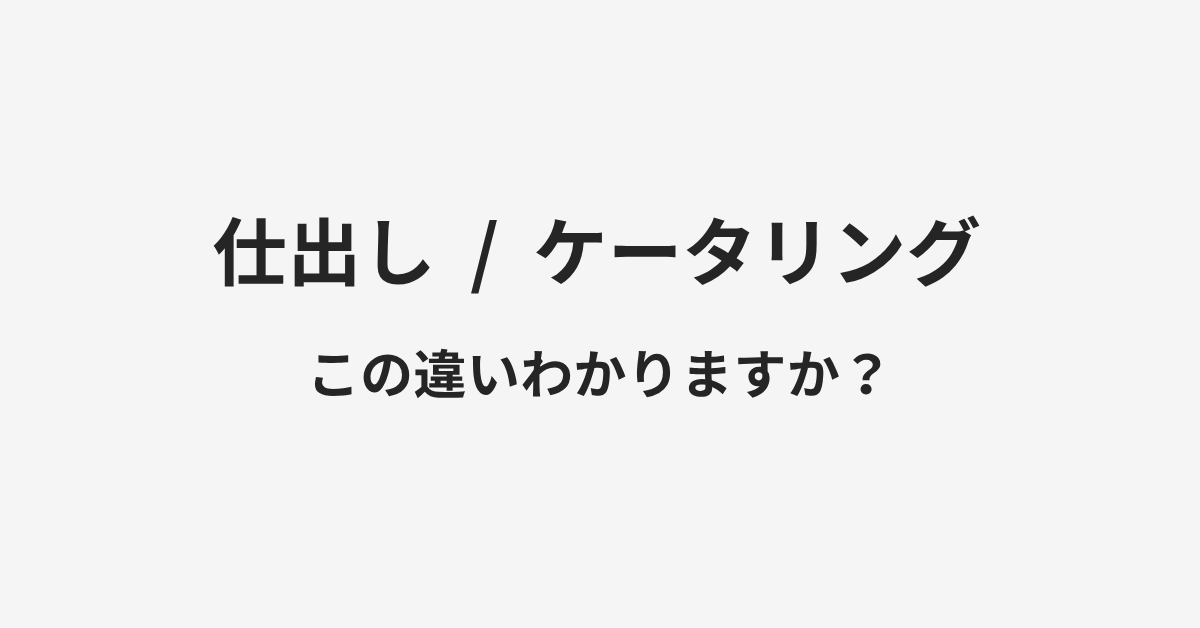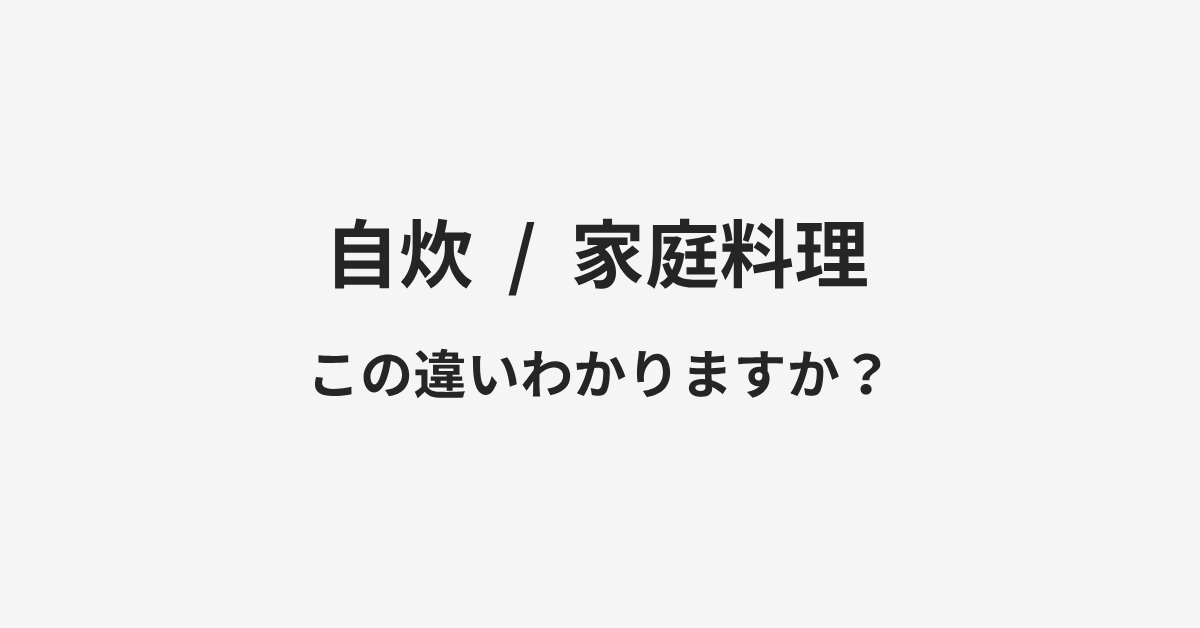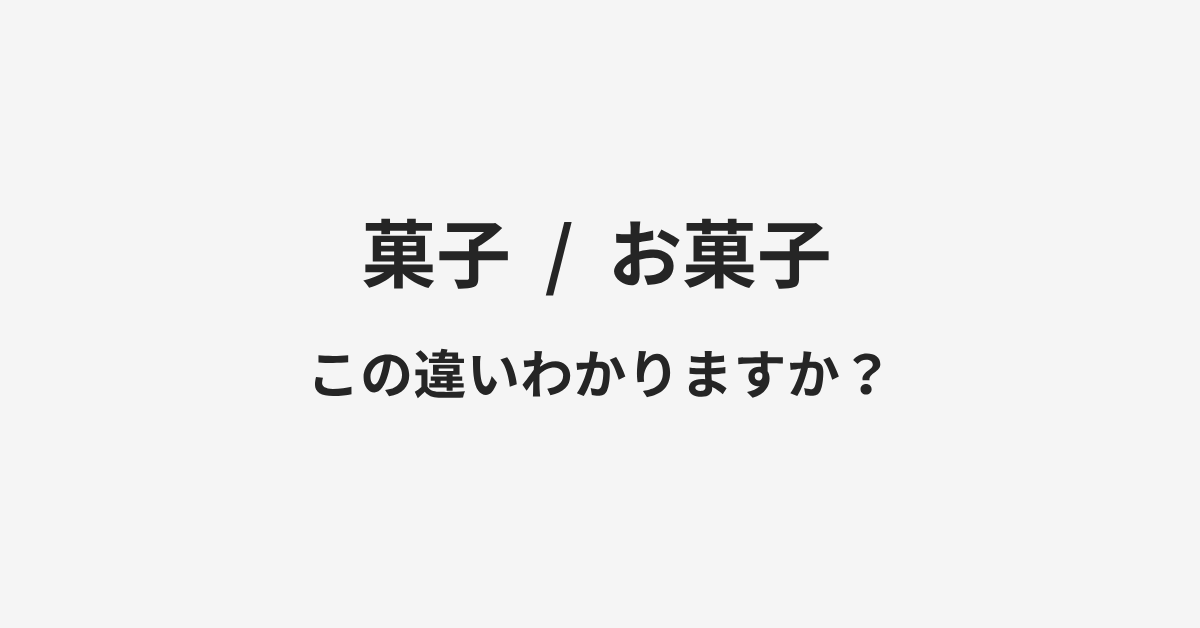【前菜】と【先付け】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

前菜と先付けの分かりやすい違い
前菜は、西洋料理のコースで最初に出される、食欲をそそる軽い料理のことです。先付けは、日本料理の会席料理で最初に出される、季節感のある小さな料理のことです。
前菜は西洋料理の開始料理、先付けは日本料理の開始料理という違いがあります。
前菜とは?
前菜とは、フランス語のオードブル(hors-d'œuvre)やイタリア語のアンティパスト(antipasto)に相当する、西洋料理のコースで最初に提供される料理です。メインディッシュの前に食欲を刺激し、これから始まる食事への期待を高める役割があります。
サラダ、カルパッチョ、テリーヌ、スープなど多彩です。前菜の特徴は、見た目の美しさと軽やかな味わいです。量は控えめで、後に続く料理の邪魔をしないよう配慮されています。冷製と温製があり、冷前菜、温前菜と区別されることもあります。
高級レストランでは複数の前菜が提供されることもあります。家庭料理でも、おもてなしの際に前菜を用意することで、食事に特別感を演出できます。前菜盛り合わせ、本日の前菜など、レストランでは定番のメニュー表記となっています。
前菜の例文
- ( 1 ) 前菜の盛り合わせを注文しました。
- ( 2 ) シェフ特製の前菜が、見た目も美しく感動的でした。
- ( 3 ) 前菜にカルパッチョを選びました。
- ( 4 ) パーティーの前菜は、手でつまめるものを中心に用意しました。
- ( 5 ) 前菜で満腹にならないよう、量を調整しています。
- ( 6 ) ワインに合う前菜を考えるのが楽しみです。
前菜の会話例
先付けとは?
先付けとは、日本料理の会席料理や懐石料理において、最初に提供される小さな料理です。お酒を飲む前の口慣らしとして、また季節の挨拶として位置づけられ、その時期の旬の食材を使った繊細な料理が供されます。量は少なく、一口から二口程度で食べられるものが一般的です。
先付けの特徴は、器との調和と季節感の表現です。春は筍や山菜、夏は鮎や枝豆、秋は銀杏や栗、冬は蟹や白子など、その時期ならではの食材が使われます。盛り付けも、季節の花や葉を添えるなど、目でも楽しめる工夫がされています。
料亭や旅館では、先付けでその店の実力が分かるとも言われ、料理人の技術とセンスが問われる重要な一品です。季節の先付け、本日の先付けとして、その日の仕入れに応じて内容が変わることも多いです。
先付けの例文
- ( 1 ) 本日の先付けは、蟹の土佐酢ジュレがけです。
- ( 2 ) 先付けに使われた器も、季節を感じさせて素敵でした。
- ( 3 ) 料亭の先付けは、まさに芸術作品のようでした。
- ( 4 ) 先付けの繊細な味わいに、日本料理の奥深さを感じました。
- ( 5 ) 季節の先付けで、もう秋を感じることができました。
- ( 6 ) 先付けから始まる会席料理の流れが好きです。
先付けの会話例
前菜と先付けの違いまとめ
前菜は西洋料理の開始料理、先付けは日本料理の開始料理という文化的な違いがあります。前菜は種類や調理法が多様で国際的、先付けは季節感と繊細さを重視し日本的です。
レストランでは前菜、料亭では先付けというように、店の形態により使い分けられています。
どちらも食事の始まりを飾る重要な料理ですが、その思想と表現方法に違いがあります。
前菜と先付けの読み方
- 前菜(ひらがな):ぜんさい
- 前菜(ローマ字):zensai
- 先付け(ひらがな):さきづけ
- 先付け(ローマ字):sakizuke