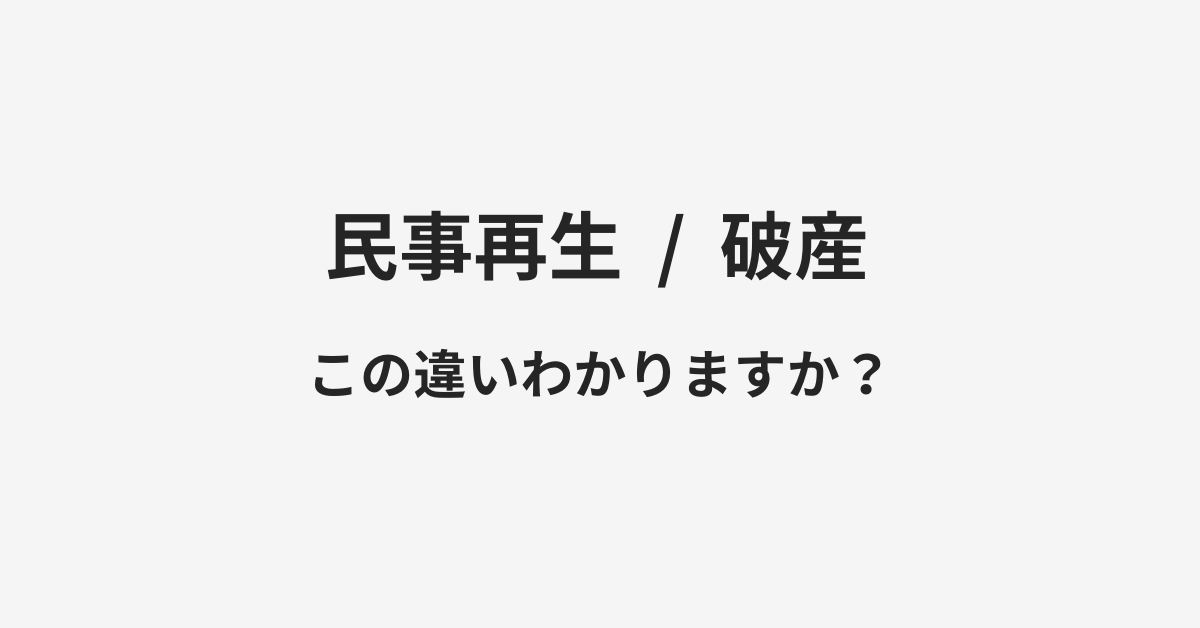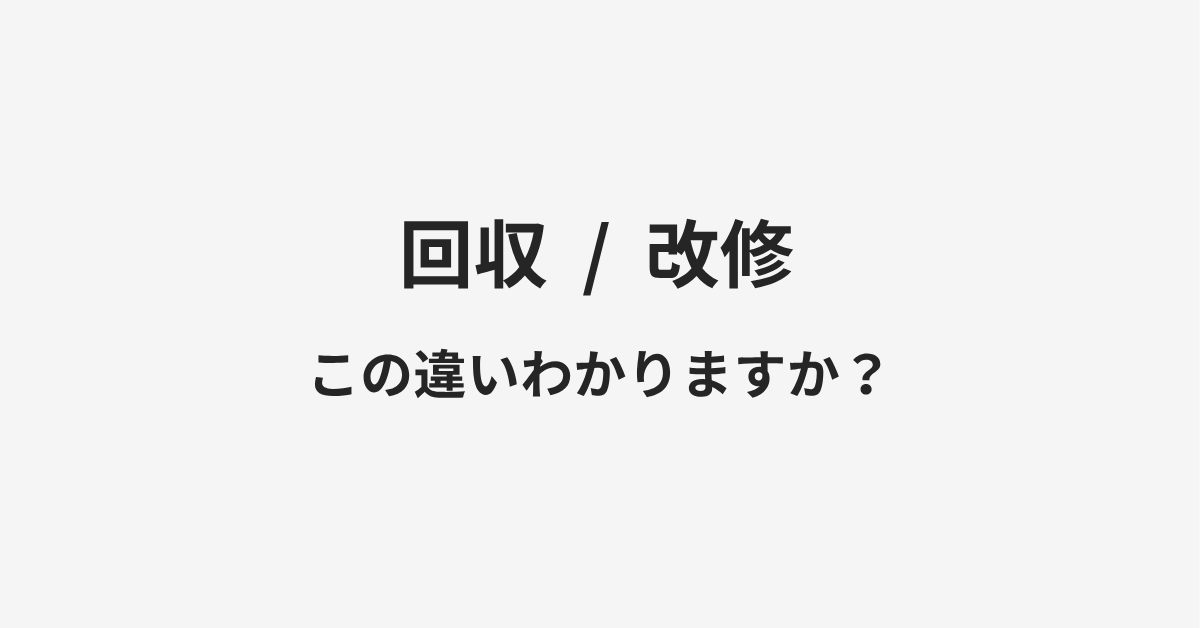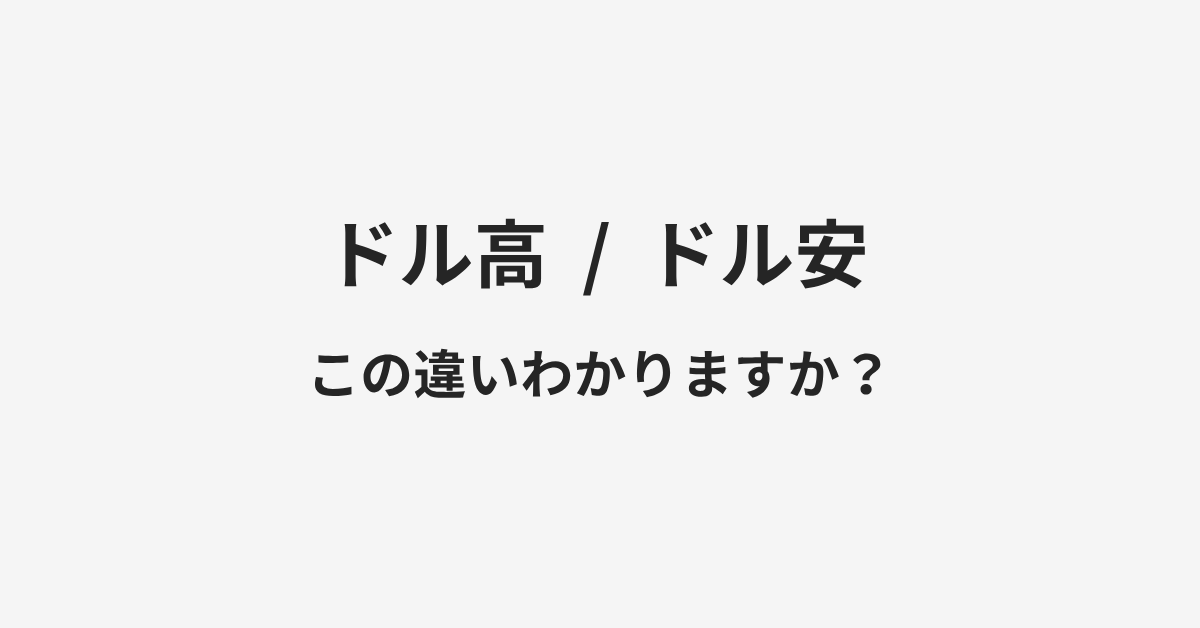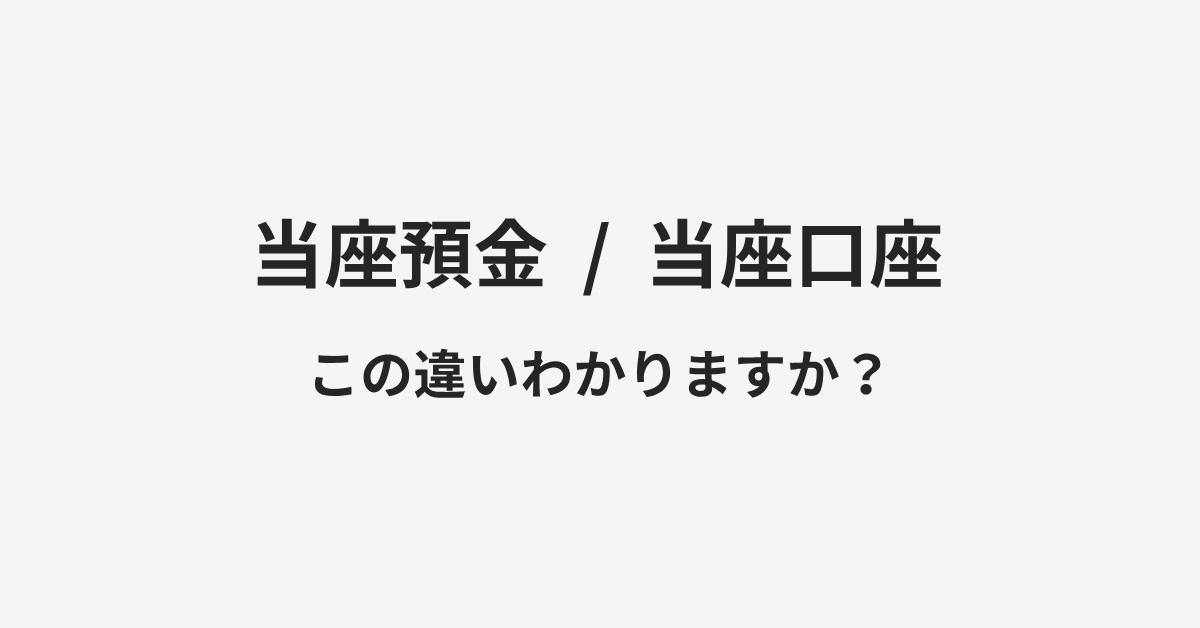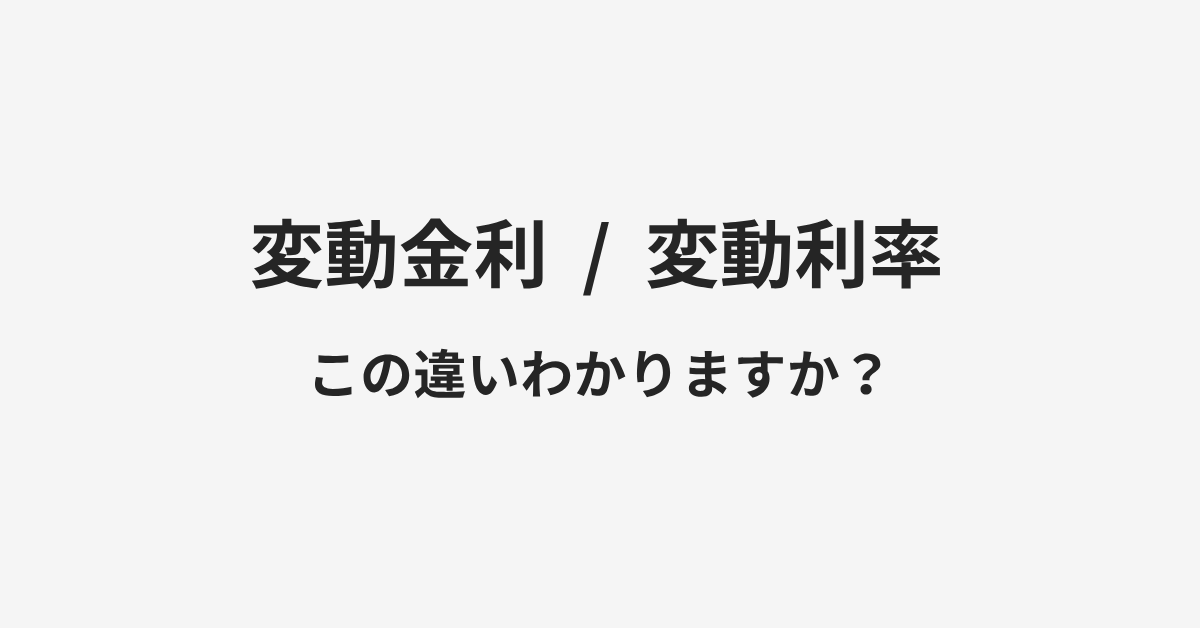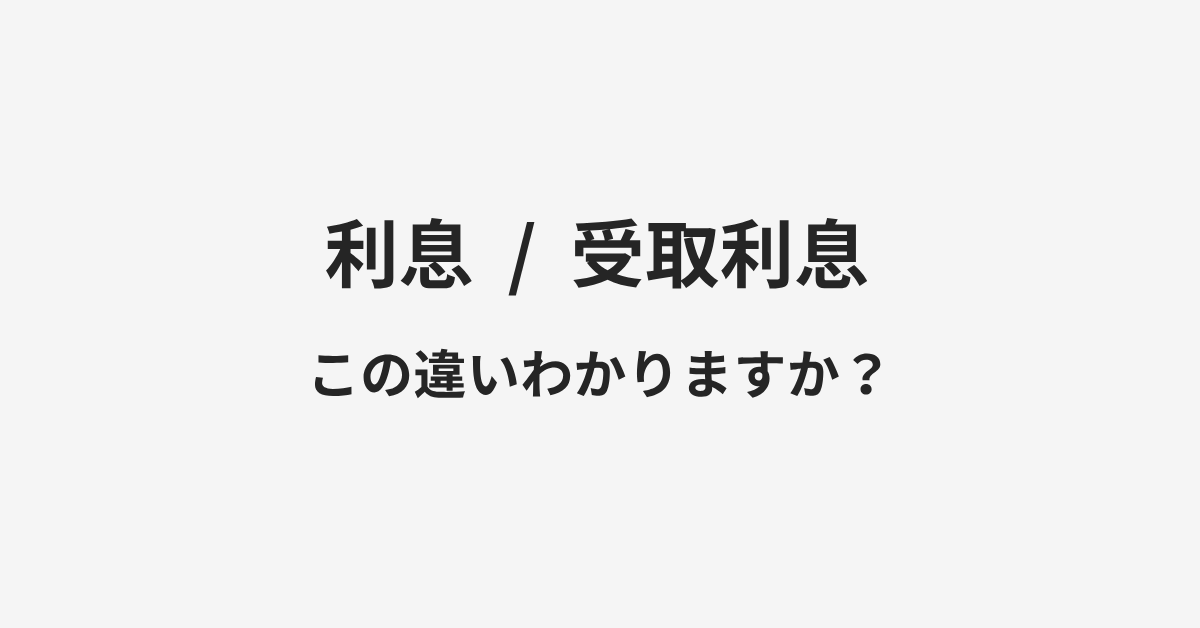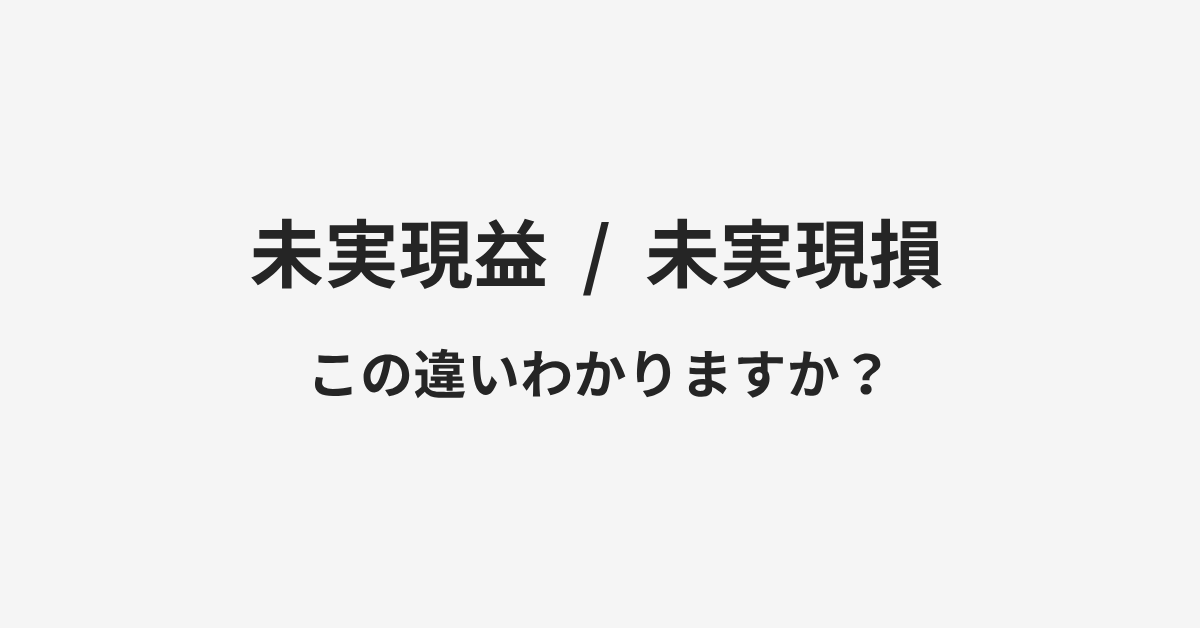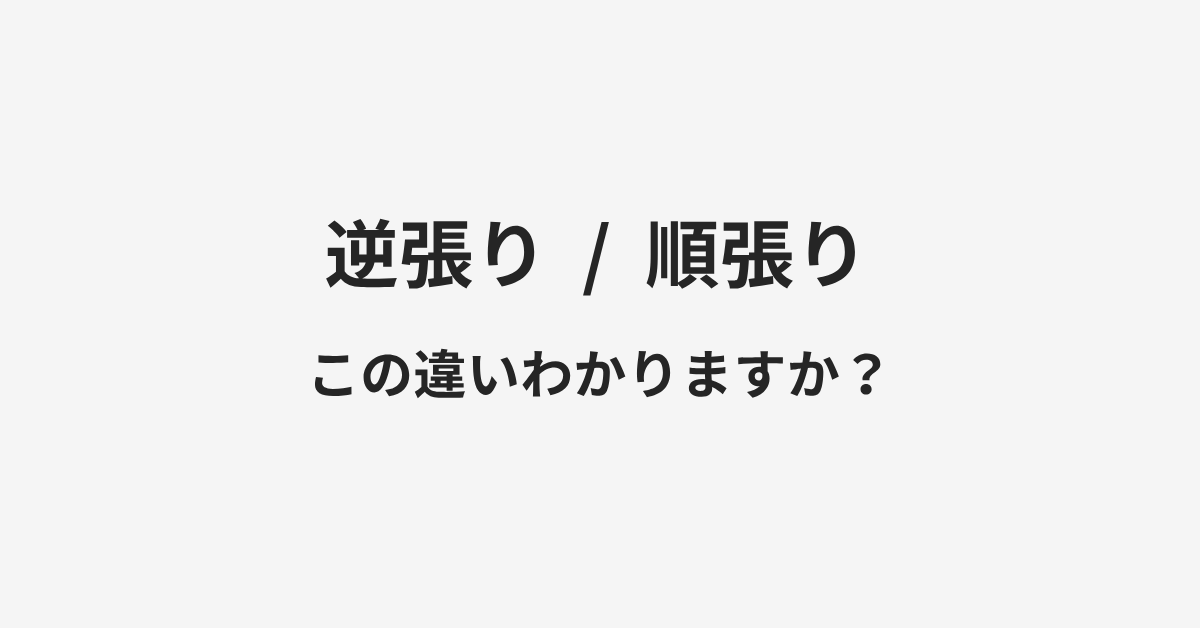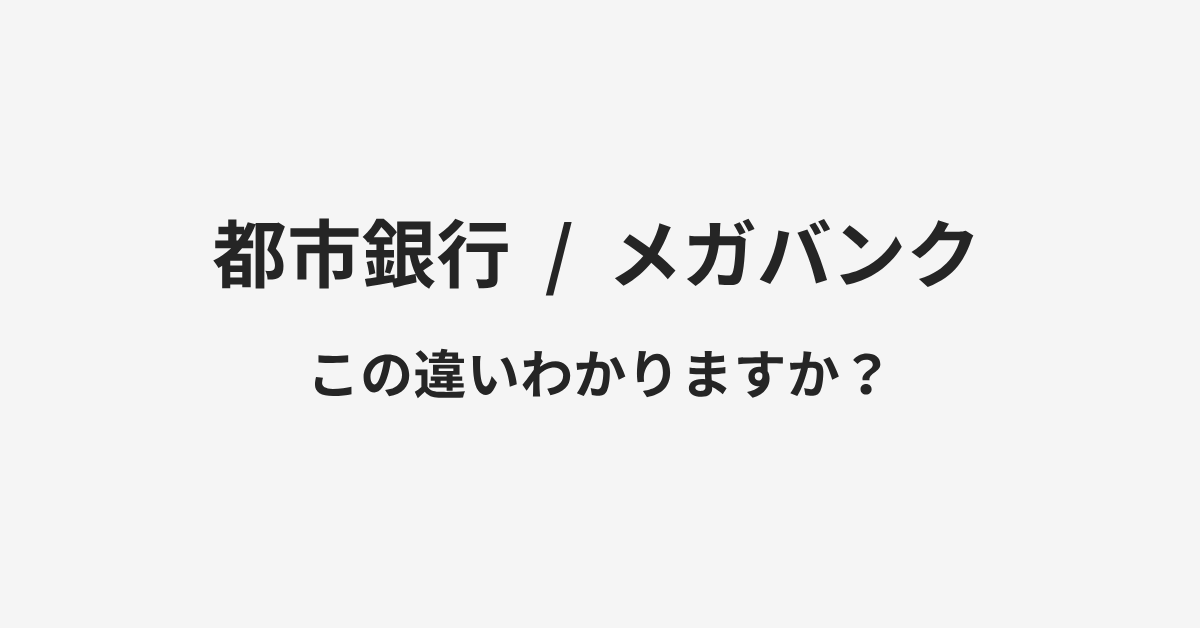【民事再生】と【会社更生】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
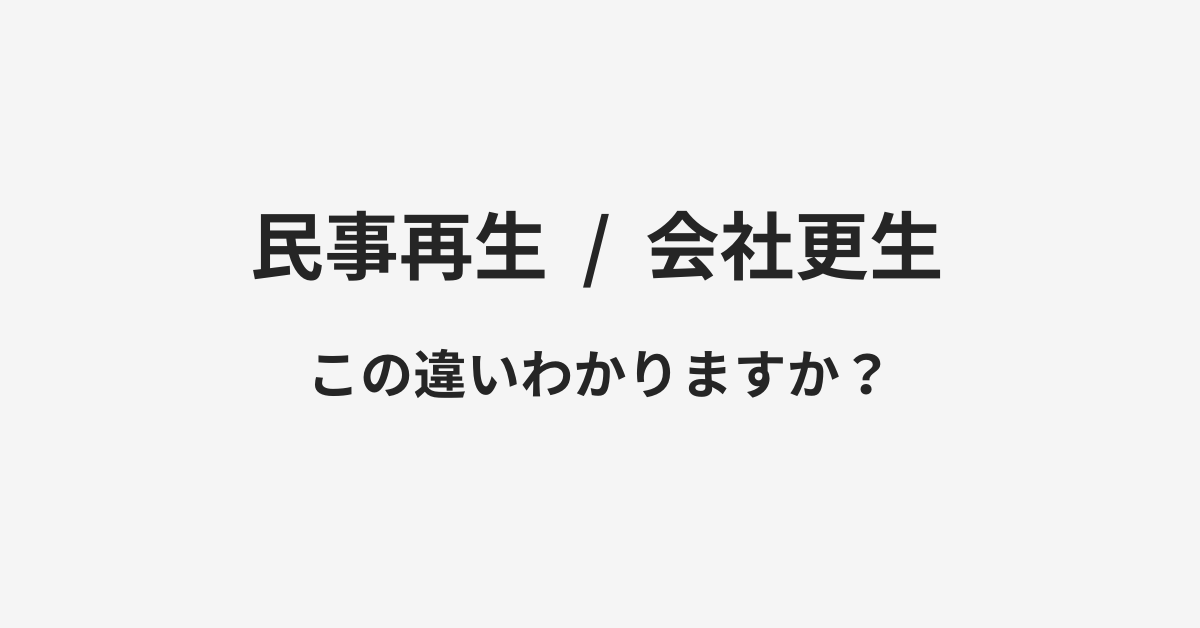
民事再生と会社更生の分かりやすい違い
民事再生と会社更生は、どちらも経営危機の企業を立て直す法的手続きですが、規模と方法が異なります。
民事再生は今の経営陣が中心となって再建し、会社更生は経営陣を入れ替えて再建します。
中小企業なら民事再生、大企業なら会社更生を選ぶことが一般的です。
民事再生とは?
民事再生とは、経営困難に陥った企業が、現経営陣の主導で事業を継続しながら再建を図る法的手続きです。民事再生法に基づき、裁判所の監督下で債務(借金)の一部カットや支払い猶予を受けながら、事業の立て直しを目指します。申請から再生計画認可まで約6ヶ月と比較的短期間で、経営権を維持したまま再建できるのが特徴です。
手続きでは、債権者(お金を貸している人)の過半数の同意で再生計画が成立します。例えば、債務の70%カット、残り30%を10年分割返済といった計画を立てます。中小企業を中心に利用され、スポンサー企業の支援を受けながら再建するケースも多くあります。
従業員の雇用も原則維持されます。民事再生のメリットは、事業価値の毀損を最小限に抑えられること、取引先との関係を維持しやすいことです。一方で、経営陣の責任が問われにくい、抜本的な改革が進みにくいといった課題もあります。申請企業の約7割が再建に成功しているとされています。
民事再生の例文
- ( 1 ) 当社は民事再生を申請し、現経営陣のもとで事業再建を進めることになりました。
- ( 2 ) 民事再生手続き中も、通常通り営業を継続し、取引先への影響を最小限に抑えています。
- ( 3 ) スポンサー企業の支援を受けて民事再生を行い、3年で黒字化を達成しました。
- ( 4 ) 民事再生により債務を80%カットし、残りを5年間で返済する計画が承認されました。
- ( 5 ) 民事再生法の早期申請により、従業員の雇用を守ることができました。
- ( 6 ) 金融機関として、民事再生企業への新規融資(DIPファイナンス)を検討しています。
民事再生の会話例
会社更生とは?
会社更生とは、大規模な株式会社が経営破綻した際に、裁判所の強い管理下で抜本的な再建を図る法的手続きです。会社更生法に基づき、原則として経営陣は退任し、裁判所が選任した管財人(更生管財人)が経営権を握ります。すべての債権者の権利が一時的に凍結され、公平な再建計画が策定されます。
手続きは厳格で、更生計画の成立には担保権者を含む各債権者グループの3分の2以上の同意が必要です。更生計画では、債務の大幅カット、債務の株式化(DES:デット・エクイティ・スワップ)、増減資などの抜本的な財務再構築が行われます。手続き期間は1年以上かかることが一般的です。
会社更生は、日本航空(JAL)のような社会的影響の大きい大企業の再建に適しています。管財人による強力な経営改革、既存株主の権利消滅、経営責任の明確化など、抜本的な再生が可能です。ただし、手続きが複雑で費用も高額なため、資本金5億円以上の大企業での利用が中心となっています。
会社更生の例文
- ( 1 ) 大手航空会社は会社更生法を申請し、更生管財人のもとで抜本的な再建を開始しました。
- ( 2 ) 会社更生手続きにより、既存株式は100%減資され、株主責任が明確化されました。
- ( 3 ) 会社更生計画では、不採算路線の廃止と人員削減により、3年での再上場を目指します。
- ( 4 ) 更生管財人に企業再生の専門家が就任し、強力なリーダーシップで改革を推進しています。
- ( 5 ) 会社更生により、債権者への弁済率は民事再生より高くなる見込みです。
- ( 6 ) 会社更生手続き中の企業との新規取引には、裁判所の許可が必要となります。
会社更生の会話例
民事再生と会社更生の違いまとめ
民事再生と会社更生は、企業再建の手法として重要な選択肢ですが、企業規模と再建の進め方に大きな違いがあります。
経営陣の続投可否、手続きの複雑さ、対象企業の規模などを総合的に判断して選択します。金融機関としては、どちらの手続きでも債権回収率を最大化しつつ、企業の再生を支援することが重要です。
民事再生と会社更生の読み方
- 民事再生(ひらがな):みんじさいせい
- 民事再生(ローマ字):minnjisaisei
- 会社更生(ひらがな):かいしゃこうせい
- 会社更生(ローマ字):kaishakousei