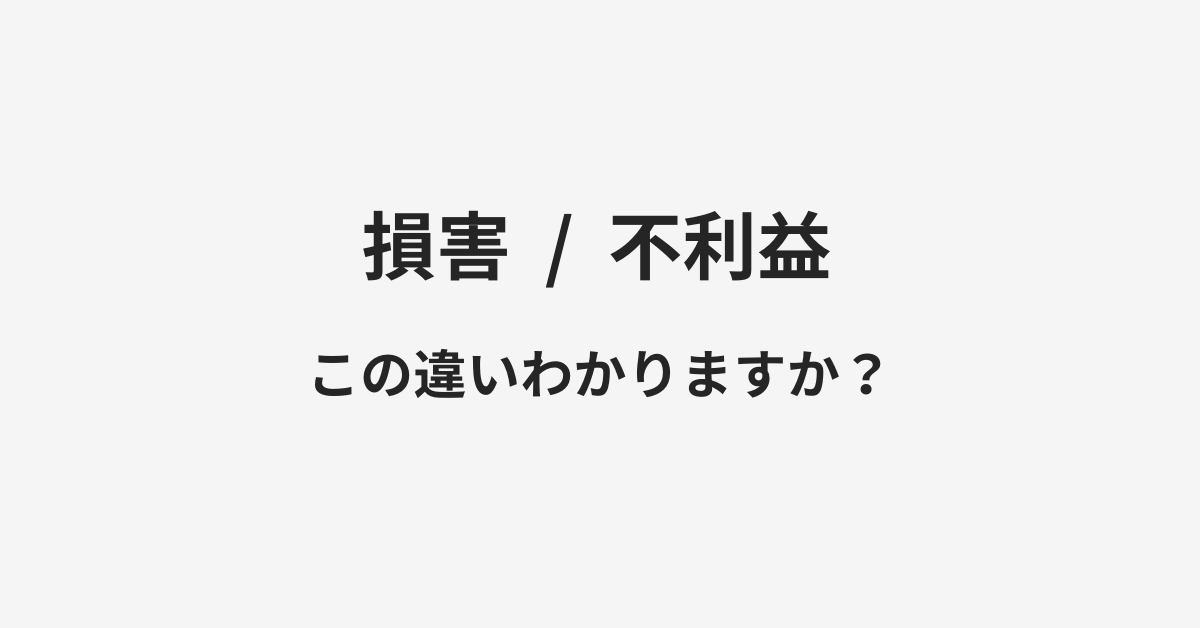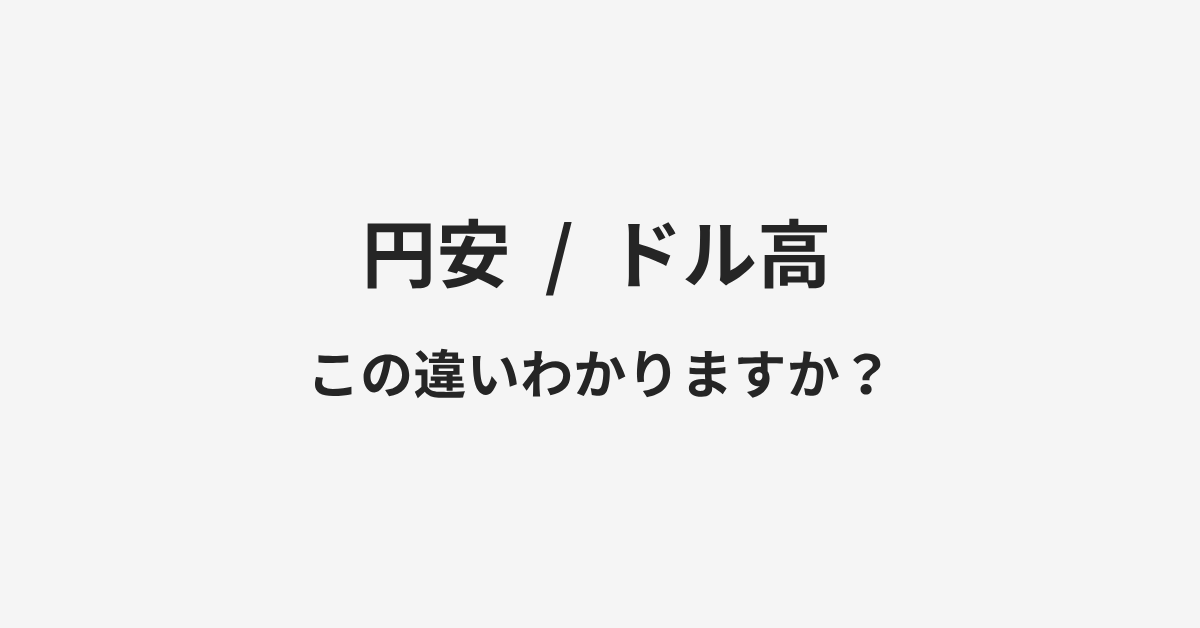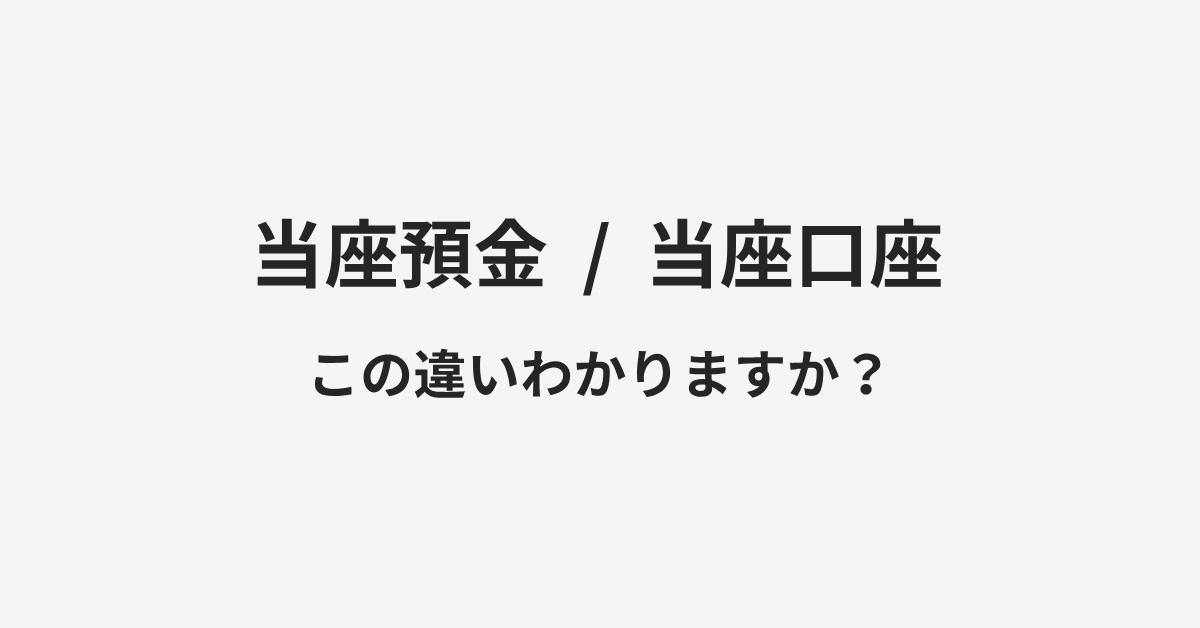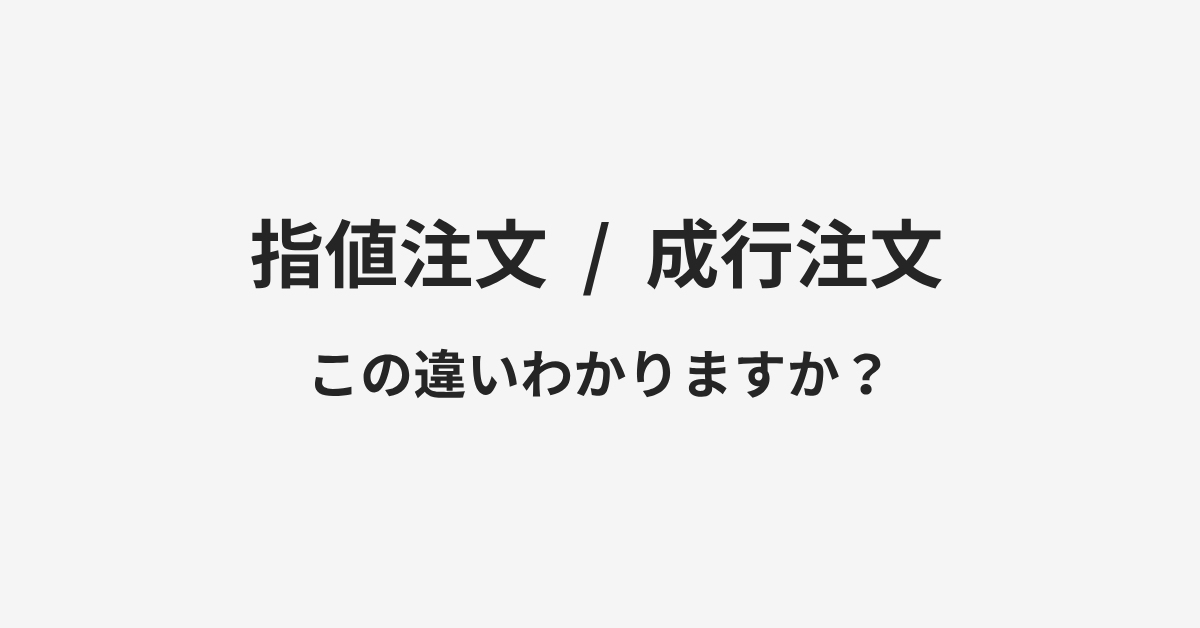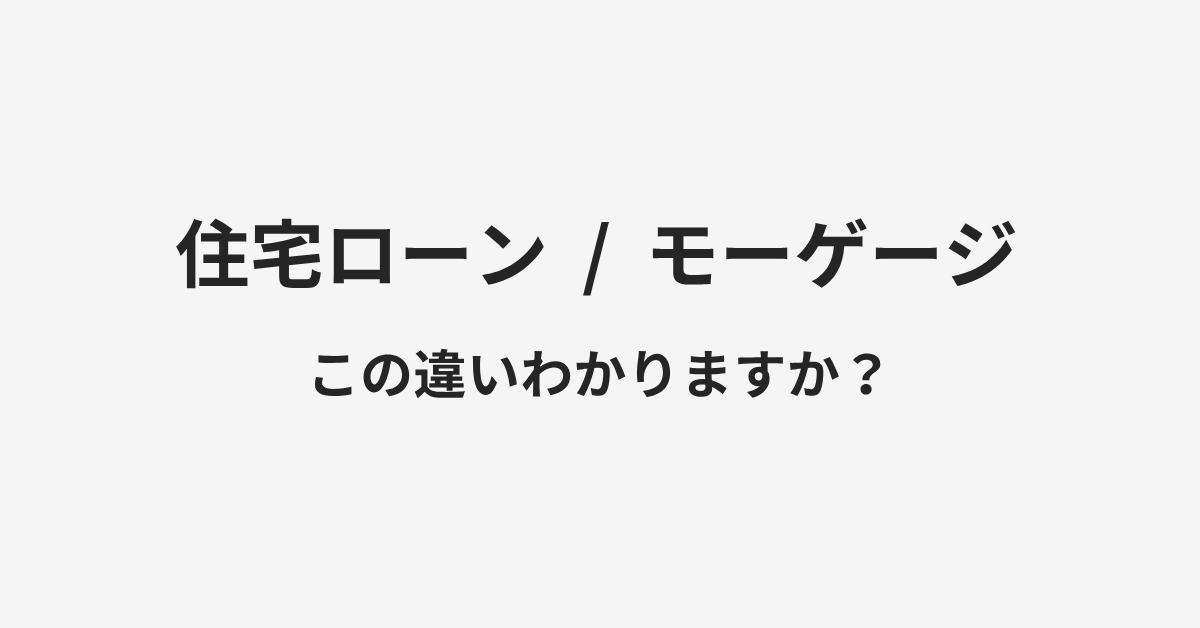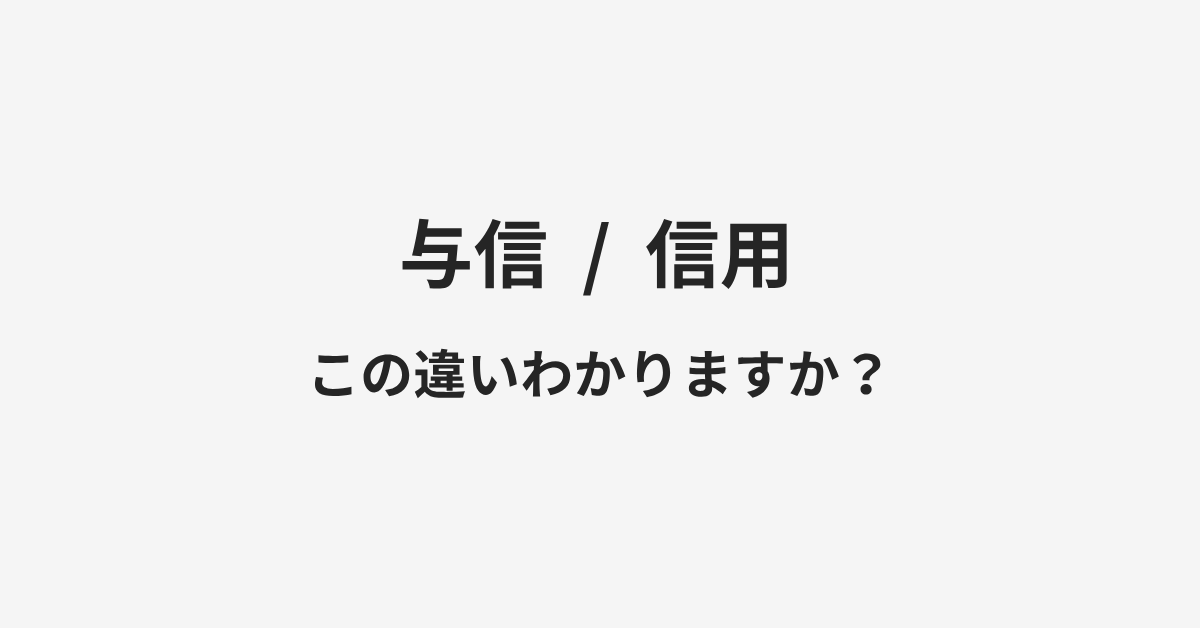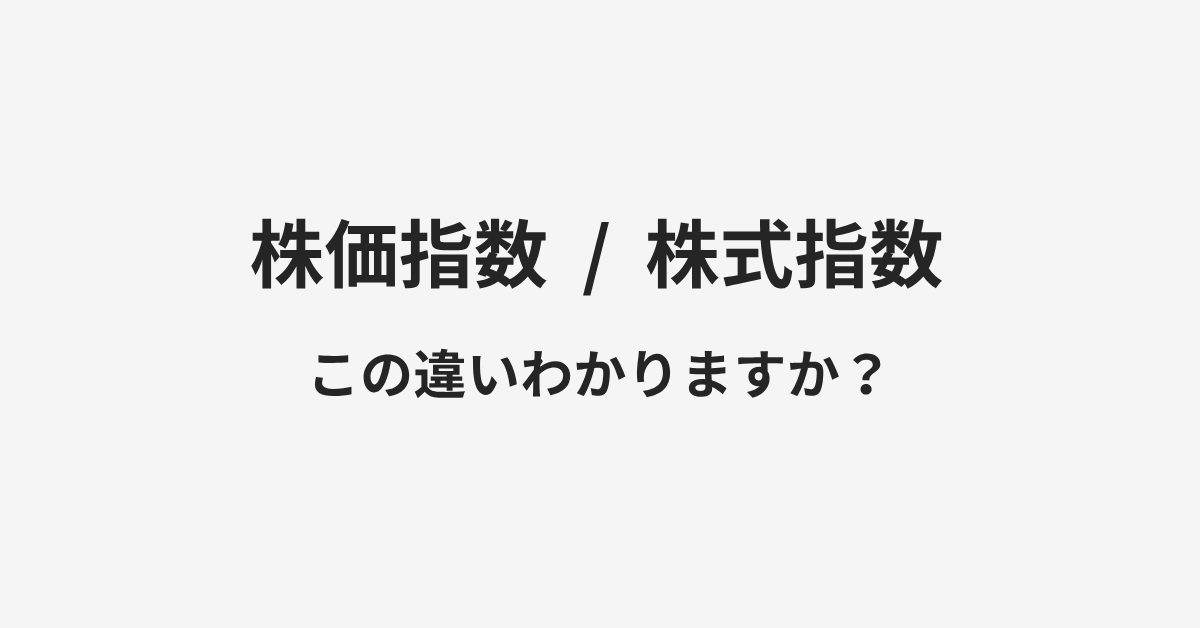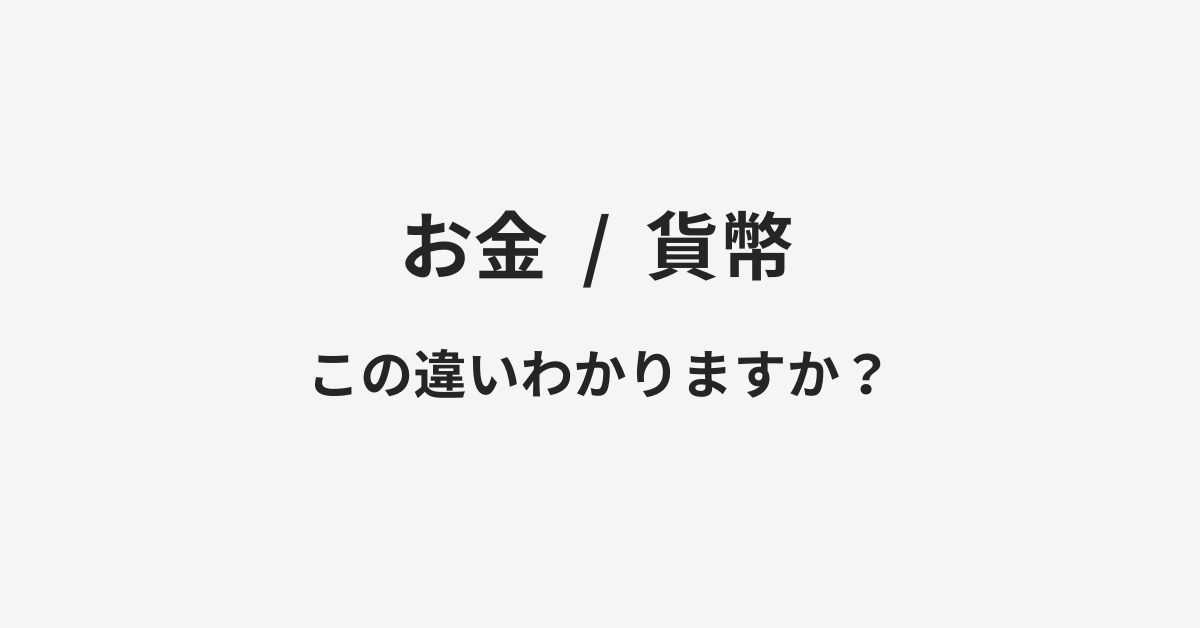【含み益】と【含み損】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

含み益と含み損の分かりやすい違い
含み益と含み損は、保有している金融資産の現在価値と取得価格の差を表す、正反対の概念です。含み益は時価が取得価格を上回る状態利益が出ている状態、含み損は時価が取得価格を下回る状態損失が出ている状態を指します。
どちらも売却するまでは確定しない未実現の損益です。
金融実務では、含み損益の管理が投資判断やリスク管理の基本となり、適切な対応が投資成果を大きく左右します。
含み益とは?
含み益とは、保有している株式や不動産などの資産の現在の市場価格が、取得時の価格を上回っている状態です。例えば、100万円で購入した株式が150万円に値上がりすれば、50万円の含み益があることになります。
含み益は評価益とも呼ばれ、売却して初めて実現益になります。含み益があるうちは税金もかからず、将来さらに上昇する可能性もありますが、相場の変動により消失するリスクもあります。
投資家は含み益に安心して利益確定を怠ったり、欲張って持ち続けた結果、相場反転で含み益が消失することもあるため、適切な利益確定戦略が重要です。
含み益の例文
- ( 1 ) この銘柄は50%の含み益が出ているので、一部利益確定します。
- ( 2 ) 含み益が出ている今のうちに、ポートフォリオを見直します。
- ( 3 ) 長期保有銘柄の含み益が、老後資金の支えになっています。
- ( 4 ) 含み益への課税強化が検討され、市場に動揺が広がりました。
- ( 5 ) 配当を再投資し、含み益の拡大を図っています。
- ( 6 ) 相場全体の上昇で、ほぼ全銘柄で含み益が発生しています。
含み益の会話例
含み損とは?
含み損とは、保有している資産の現在の市場価格が、取得時の価格を下回っている状態です。例えば、100万円で購入した株式が70万円に値下がりすれば、30万円の含み損を抱えていることになります。
含み損は評価損とも呼ばれ、売却しない限り実際の損失にはなりません。しかし、資金が拘束され機会損失が発生したり、信用取引では追証のリスクもあります。
多くの投資家は損失確定を避けて塩漬けにしがちですが、見通しが悪い銘柄は早期に損切りし、資金を有望な投資先に振り向ける方が合理的な場合も多いです。
含み損の例文
- ( 1 ) 30%の含み損を抱えていますが、業績回復を信じて保有継続します。
- ( 2 ) 含み損が膨らみ、精神的にきつい状況が続いています。
- ( 3 ) 含み損銘柄を損切りし、税金対策に活用しました。
- ( 4 ) ナンピン買いで平均取得価格を下げ、含み損を縮小させます。
- ( 5 ) 長期投資なので、一時的な含み損は気にしません。
- ( 6 ) 信用取引の含み損が拡大し、追証が発生しました。
含み損の会話例
含み益と含み損の違いまとめ
含み益と含み損は、投資における評価損益の両面で、どちらも未実現の状態です。含み益は心理的に余裕を生み、含み損はストレスとなりますが、重要なのは現在の投資価値と将来性です。
含み益があっても相場急変で損失に転じる可能性があり、含み損でも企業業績改善で回復することもあります。感情に左右されない冷静な判断が必要です。
実務では、定期的なポートフォリオ評価により含み損益を把握し、リバランスや損益通算など、税務も考慮した総合的な資産管理が求められます。
含み益と含み損の読み方
- 含み益(ひらがな):ふくみえき
- 含み益(ローマ字):fukumieki
- 含み損(ひらがな):ふくみそん
- 含み損(ローマ字):fukumisonn