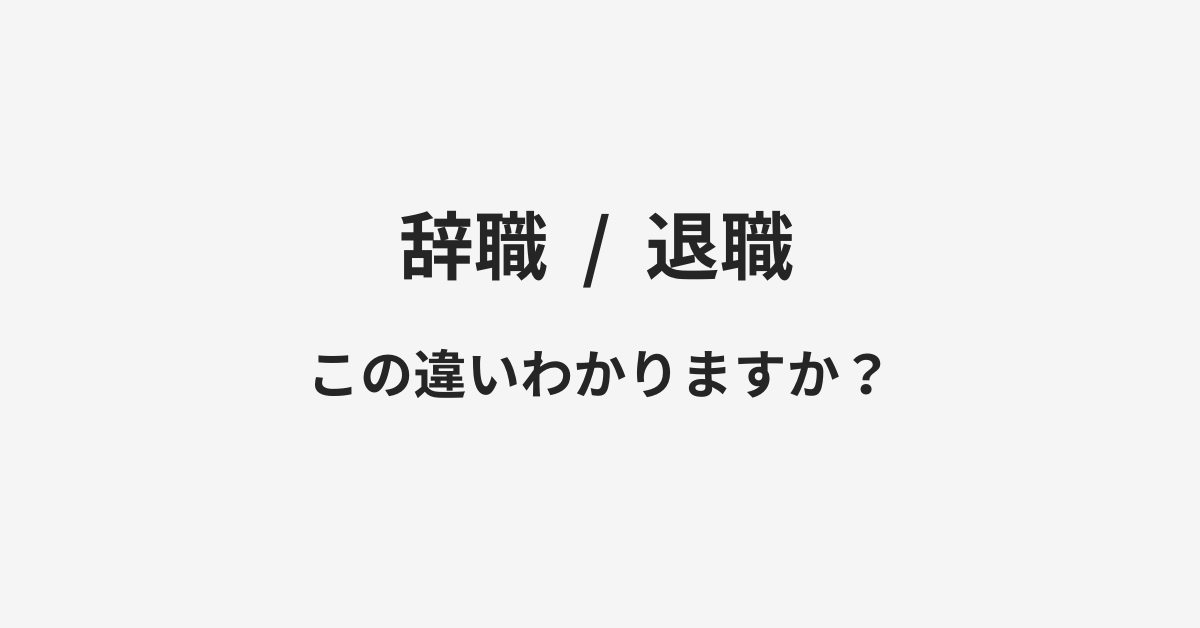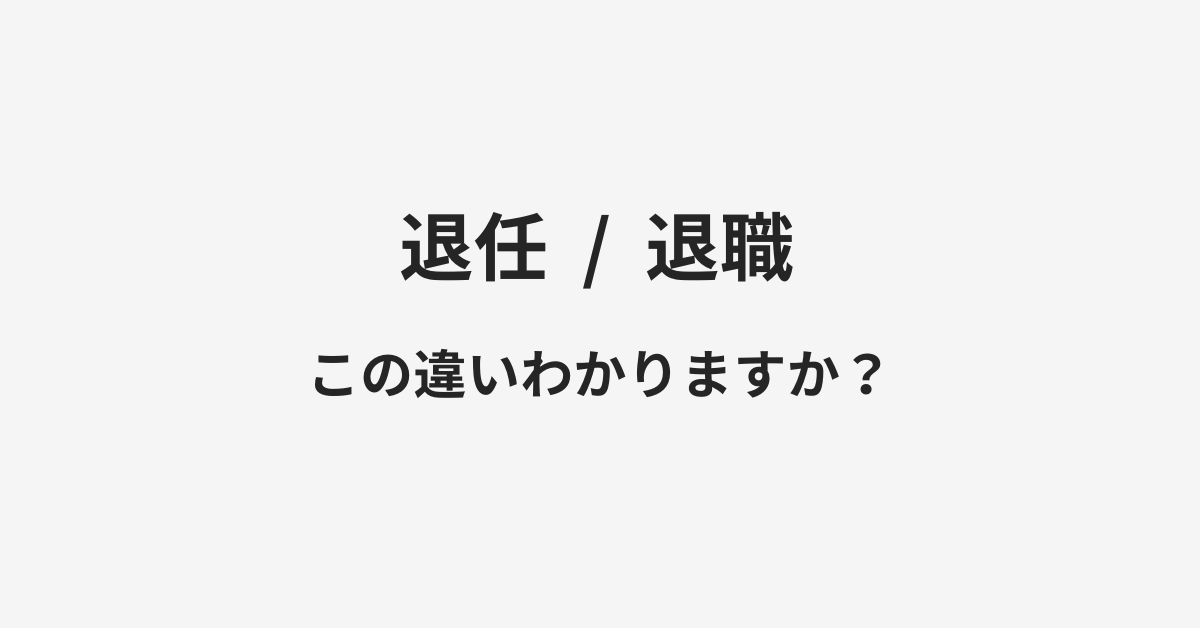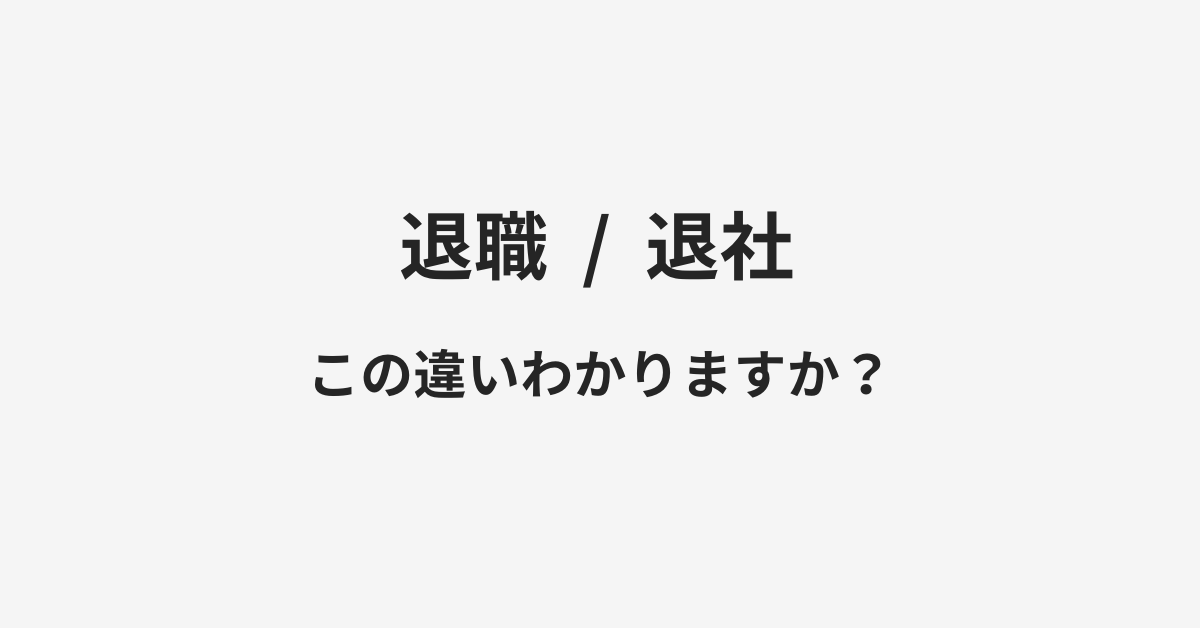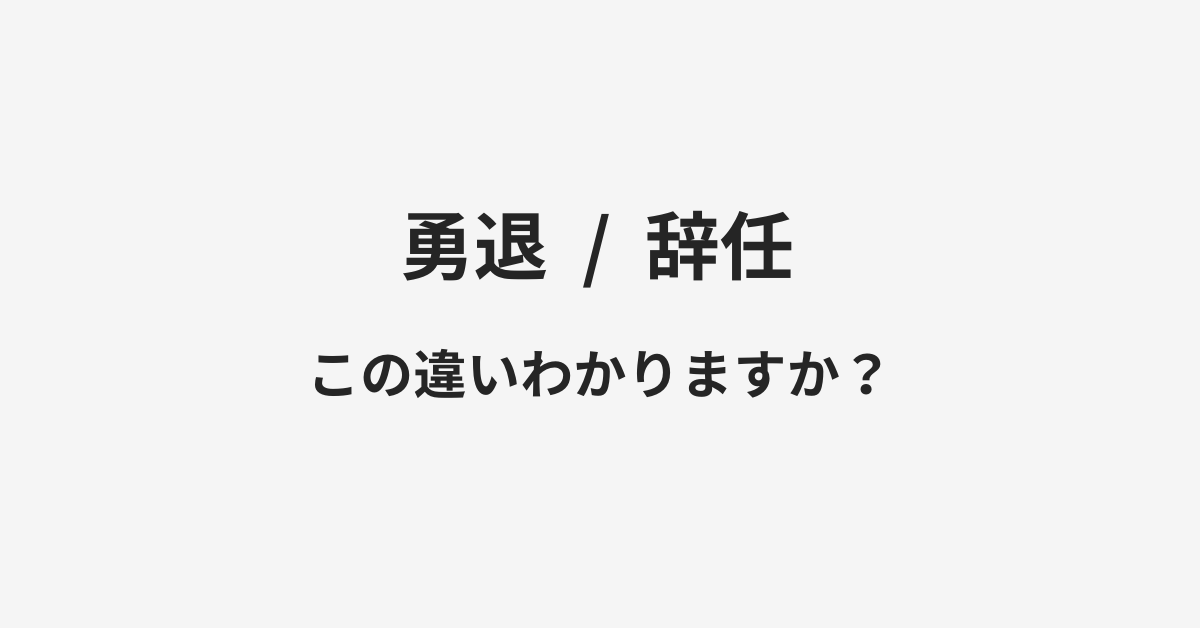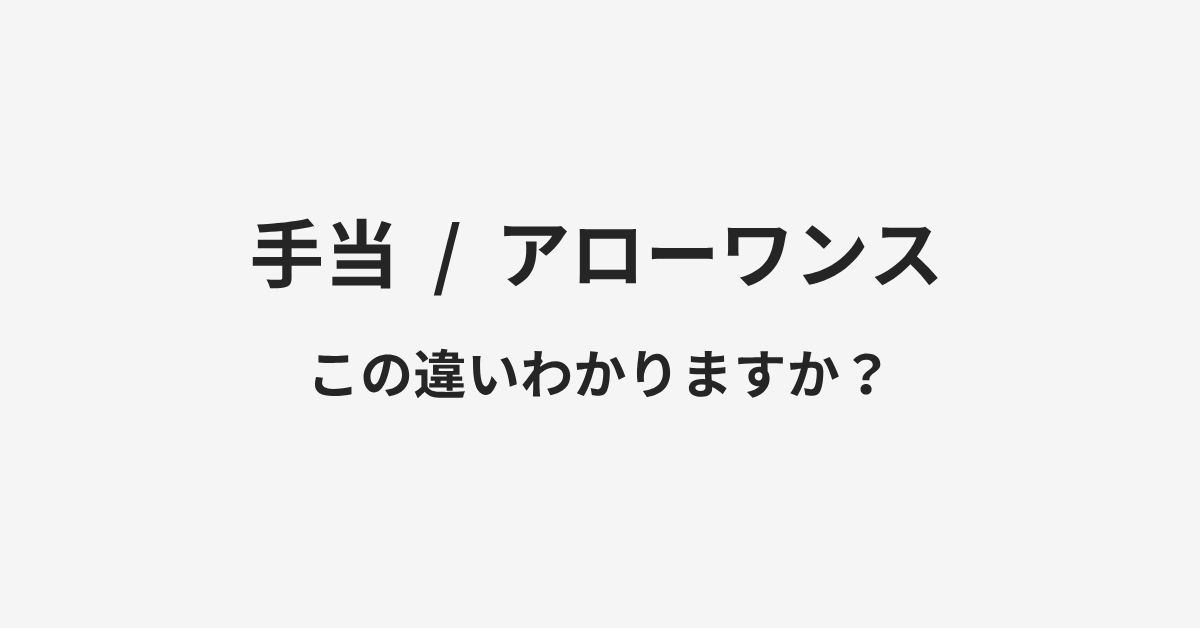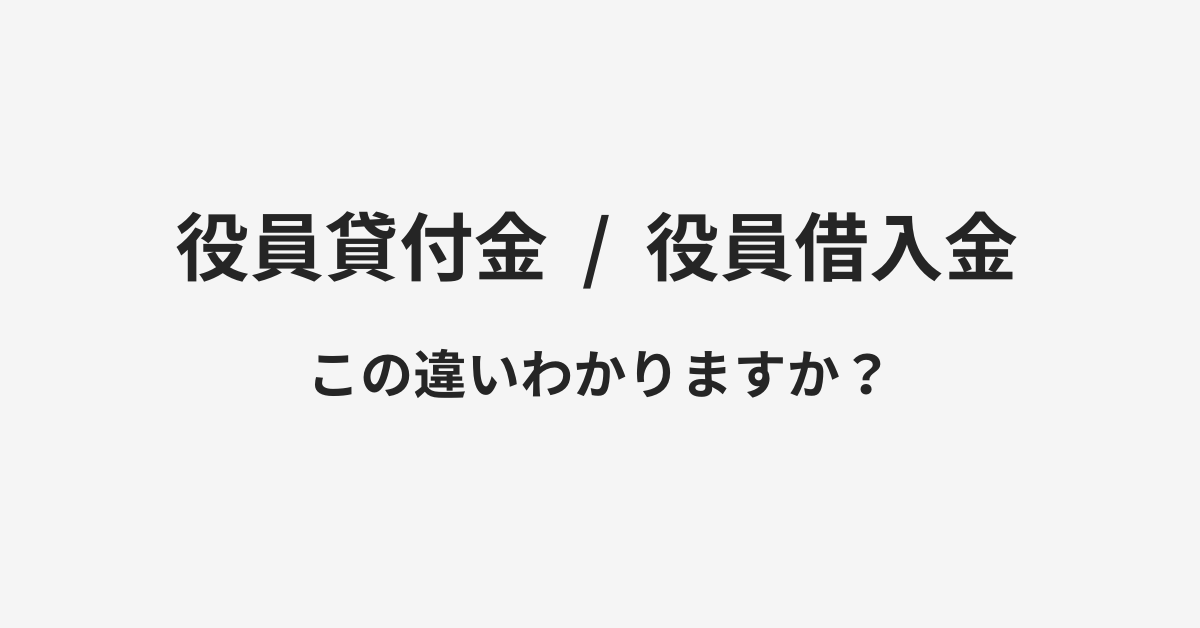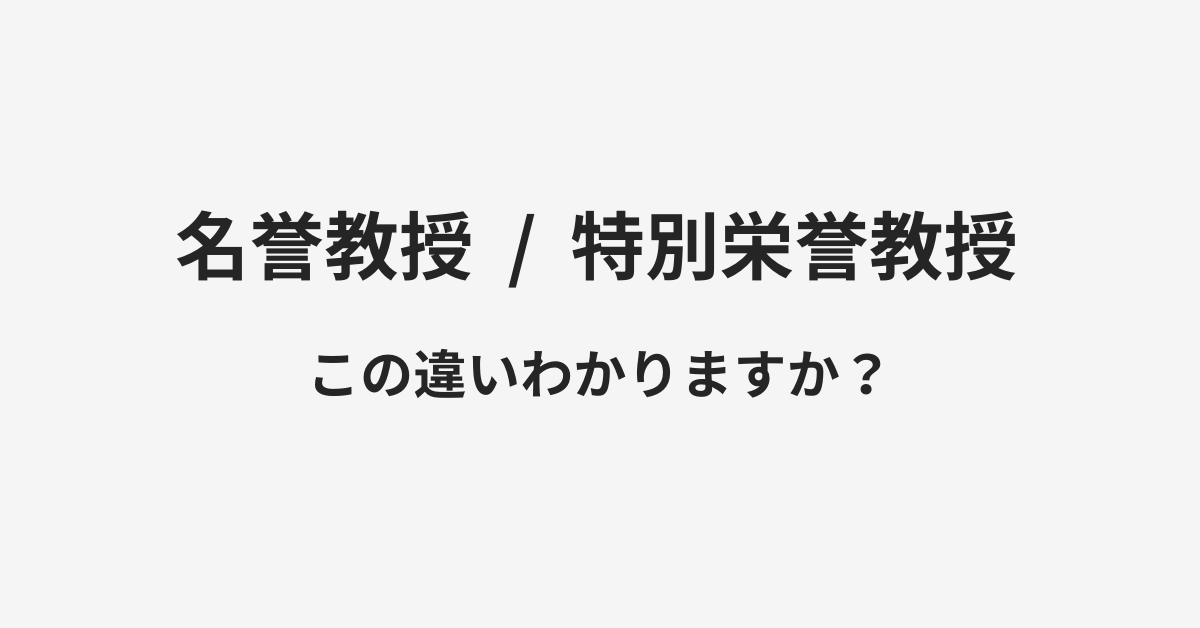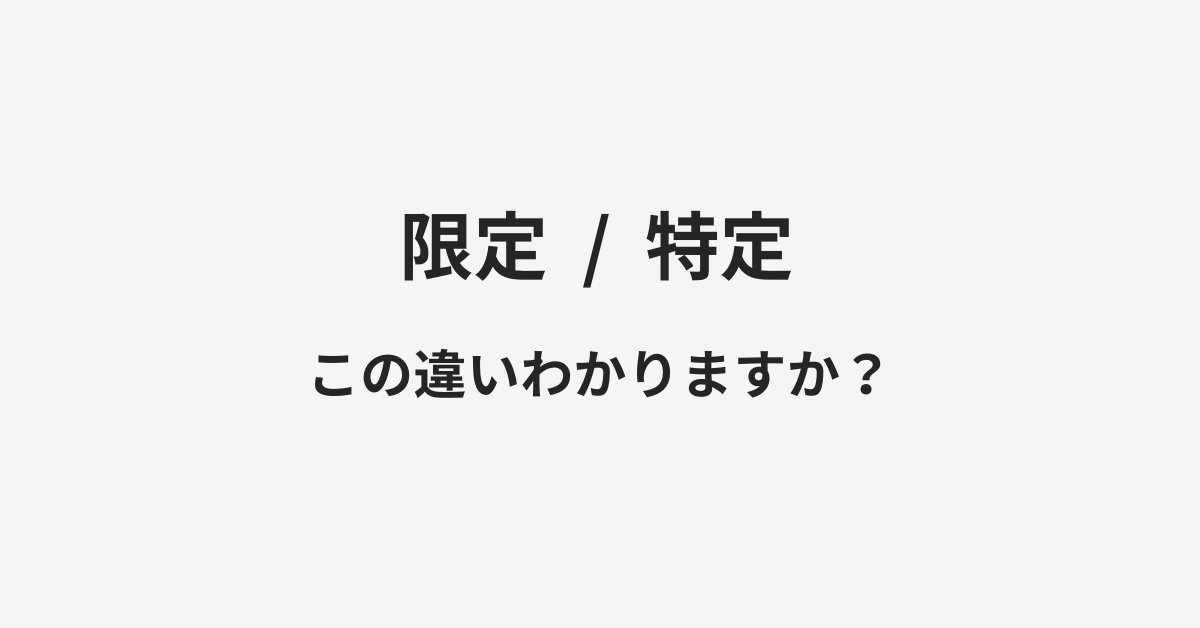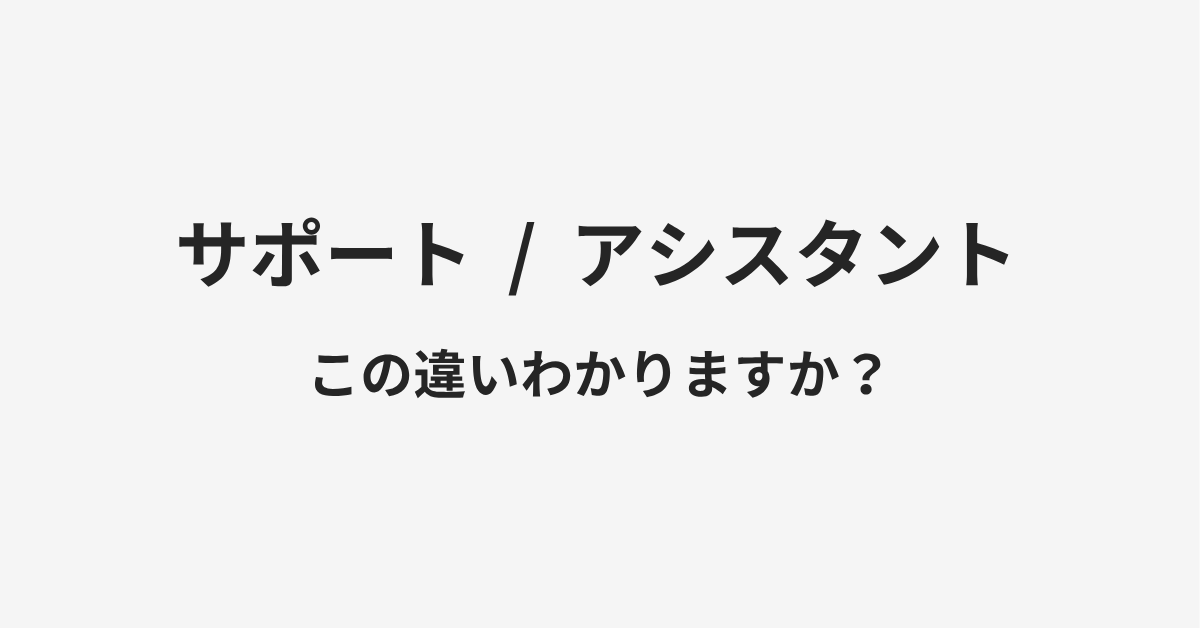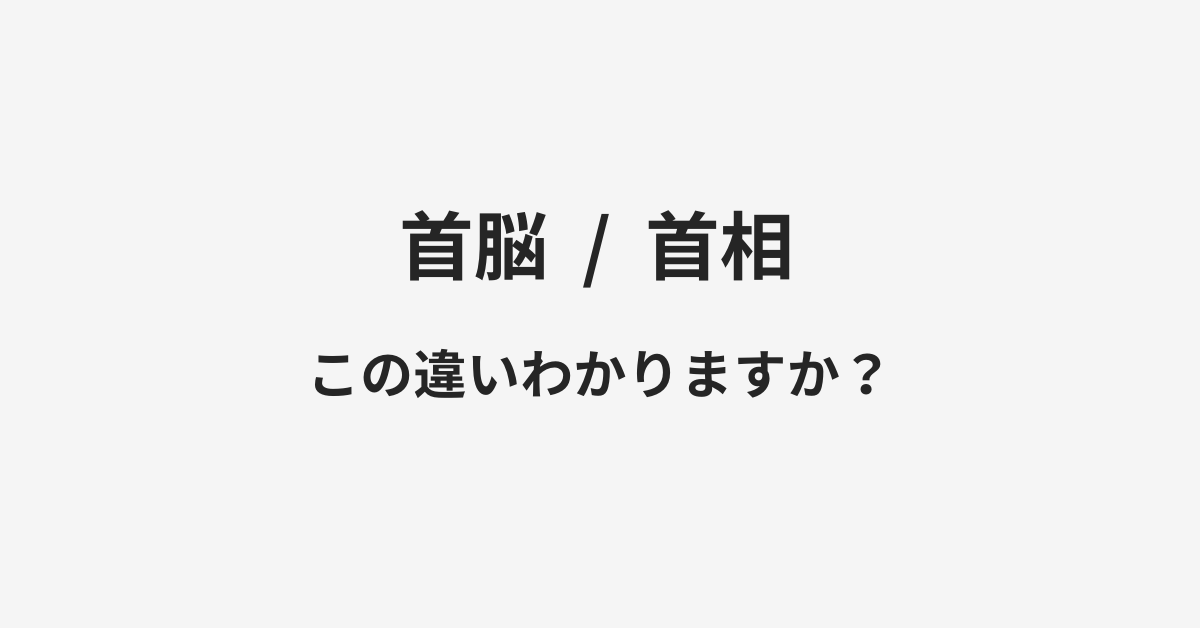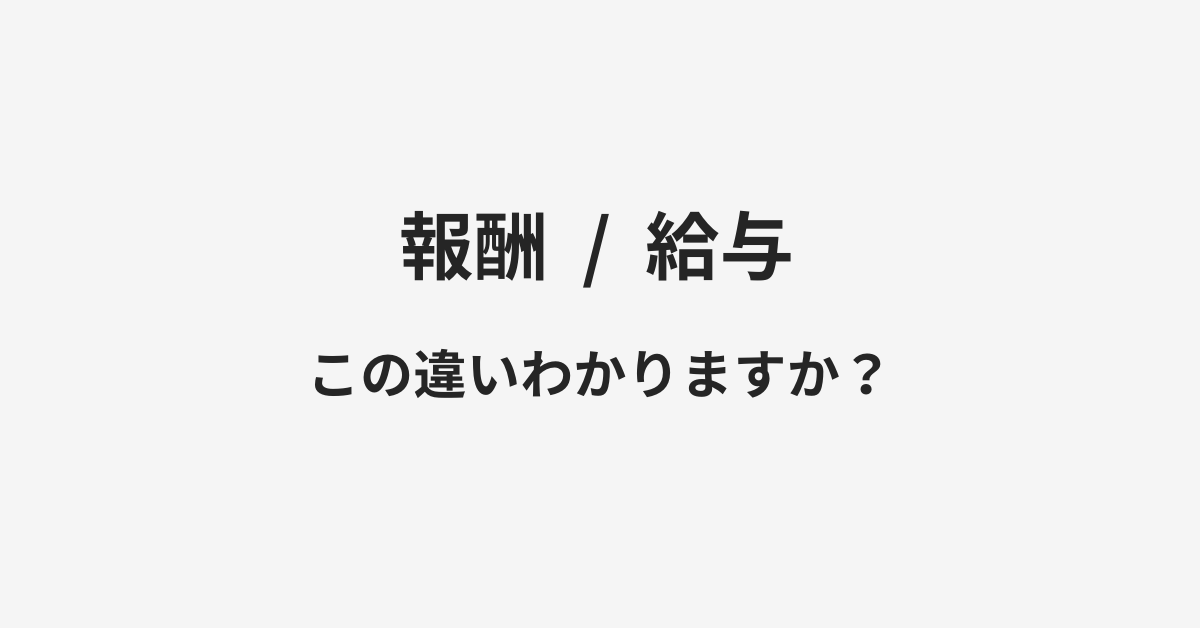【退職】と【離職】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
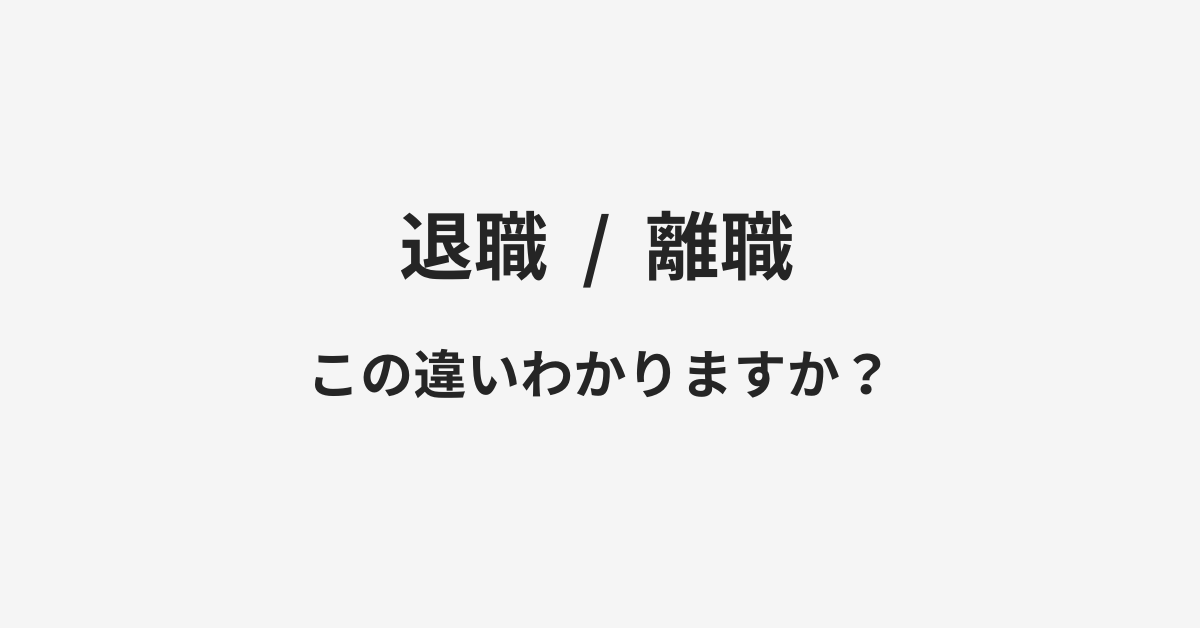
退職と離職の分かりやすい違い
退職と離職は、どちらも会社を辞めることを表す言葉ですが、使い方に違いがあります。退職は、自分の意思で会社を辞めるときによく使われる言葉です。
離職は、会社を辞めること全般を指し、統計や公的な書類でよく使われます。人事の仕事をする人や、転職を考えている人は、この違いを理解しておくことで、適切な言葉選びができるようになります。
退職とは?
退職とは、労働者が雇用関係を終了させることを指し、主に自己都合や定年により職を離れる場合に使用される言葉です。一般的に自発的な意思に基づく離職を指すことが多く、退職願、退職届、退職金、退職手続きなど、実務的な場面で頻繁に使用されます。
会社都合による解雇の場合でも退職と表現することがありますが、多くは労働者側からの申し出による雇用関係の終了を意味します。
企業の人事部門では、退職者への対応、退職手続きの管理、退職理由の分析などが重要な業務となっており、組織の人材マネジメントにおいて欠かせない概念です。
退職の例文
- ( 1 ) 来月末での退職を希望していますが、引き継ぎ期間は十分に確保します。
- ( 2 ) 定年退職後も、嘱託社員として働き続ける選択肢があります。
- ( 3 ) 退職金の計算方法について、人事部から詳しい説明を受けました。
- ( 4 ) 円満退職のためには、早めの意思表示と丁寧な引き継ぎが大切です。
- ( 5 ) 退職届は、退職希望日の1か月前までに提出する必要があります。
- ( 6 ) キャリアアップのための退職は、前向きな選択として受け入れられています。
退職の会話例
離職とは?
離職とは、何らかの理由により職を離れることを指す包括的な用語で、退職、解雇、雇止め、倒産など、雇用関係が終了するすべての状況を含みます。厚生労働省の統計や雇用保険制度などで使用される公式な用語で、離職率、離職票、離職理由などの形で用いられます。
自発的な退職も会社都合の解雇も含むため、より中立的で客観的な表現として、統計調査や学術研究で好まれます。
人事戦略においては、離職率の分析や離職防止策の立案が重要な課題となっており、従業員の定着率向上のための施策検討に欠かせない指標となっています。
離職の例文
- ( 1 ) 今年度の離職率は8.5%で、業界平均を下回っています。
- ( 2 ) 離職票は、雇用保険の手続きに必要な重要書類です。
- ( 3 ) 若手社員の離職防止策として、メンター制度を導入しました。
- ( 4 ) 離職理由の分析結果から、労働環境の改善が急務とわかりました。
- ( 5 ) 産業別の離職率統計を見ると、サービス業が最も高い傾向にあります。
- ( 6 ) 離職者へのヒアリングを通じて、組織の課題を把握することができます。
離職の会話例
退職と離職の違いまとめ
退職と離職は、実質的には似た意味を持ちますが、使用される文脈と含まれる範囲に違いがあります。退職は主に個人の行為として、離職は統計的・制度的な観点から使用されることが多いです。
人事実務では、従業員との対話では退職、統計分析や公的手続きでは離職を使うなど、状況に応じた使い分けが求められます。
どちらの言葉も組織の人材管理において重要な概念であり、適切な理解と運用が必要です。
退職と離職の読み方
- 退職(ひらがな):たいしょく
- 退職(ローマ字):taishoku
- 離職(ひらがな):りしょく
- 離職(ローマ字):rishoku