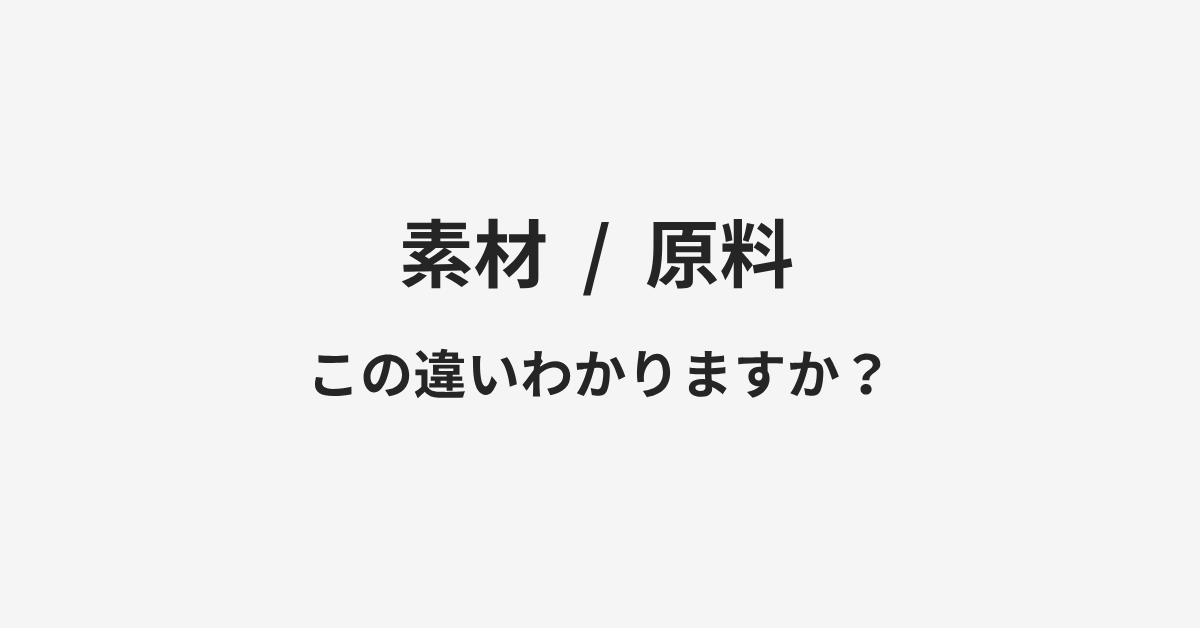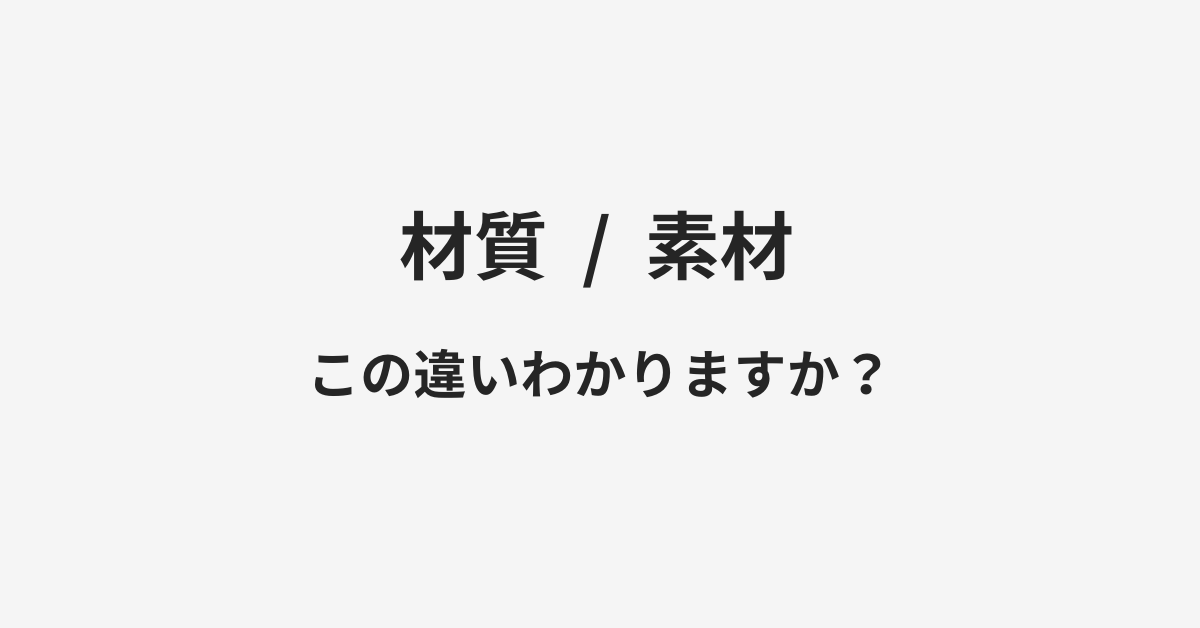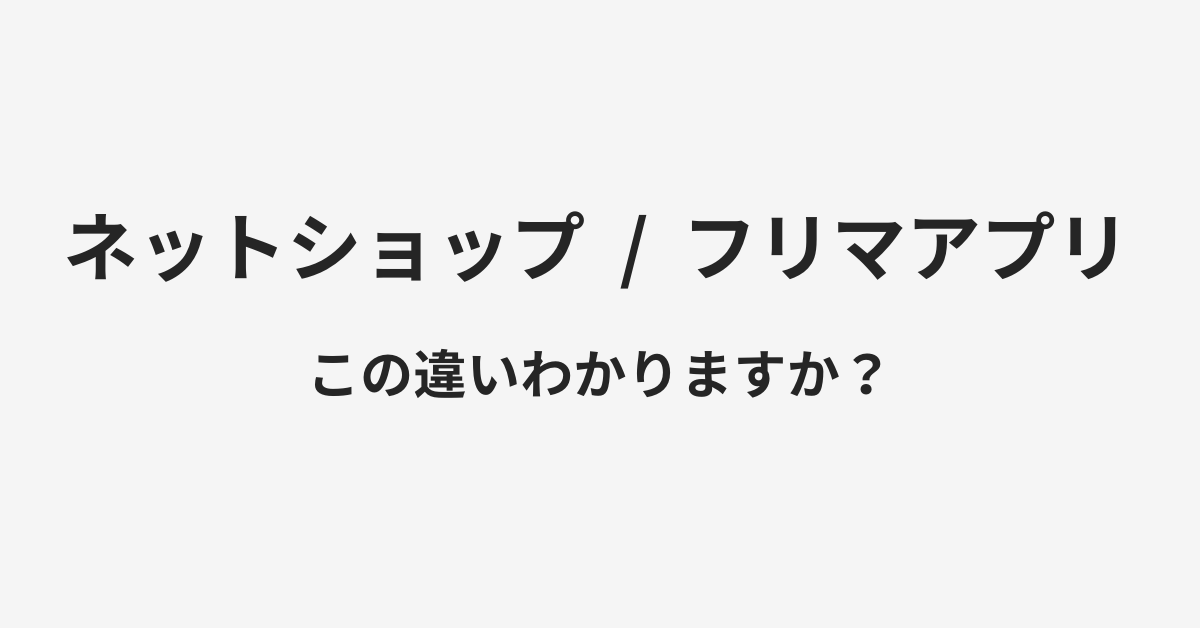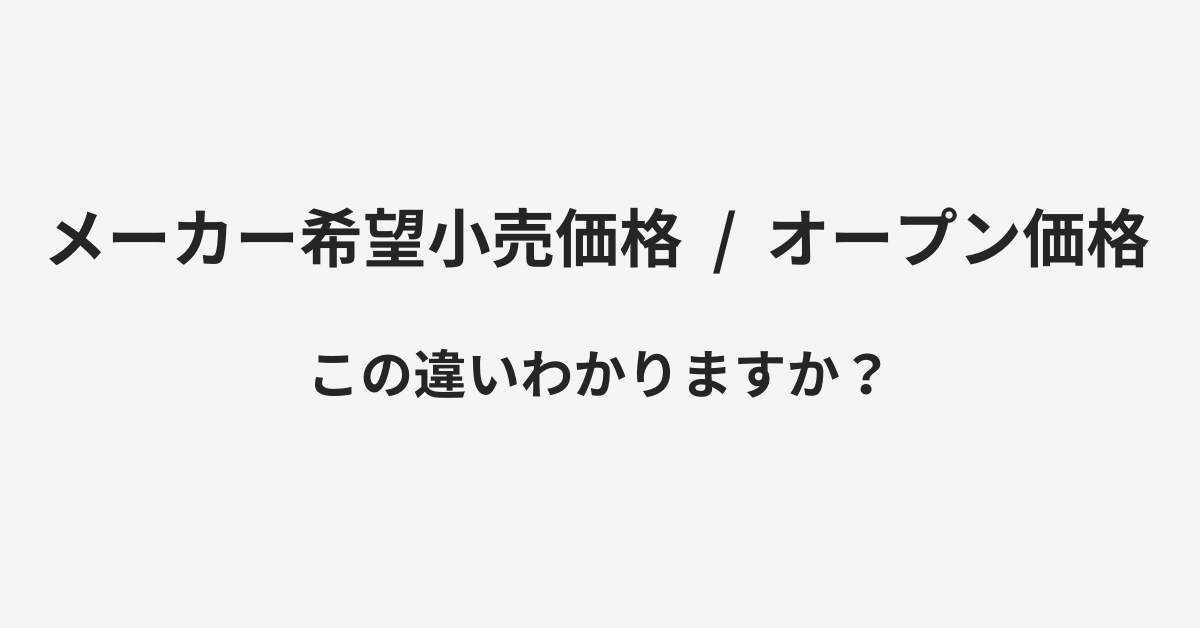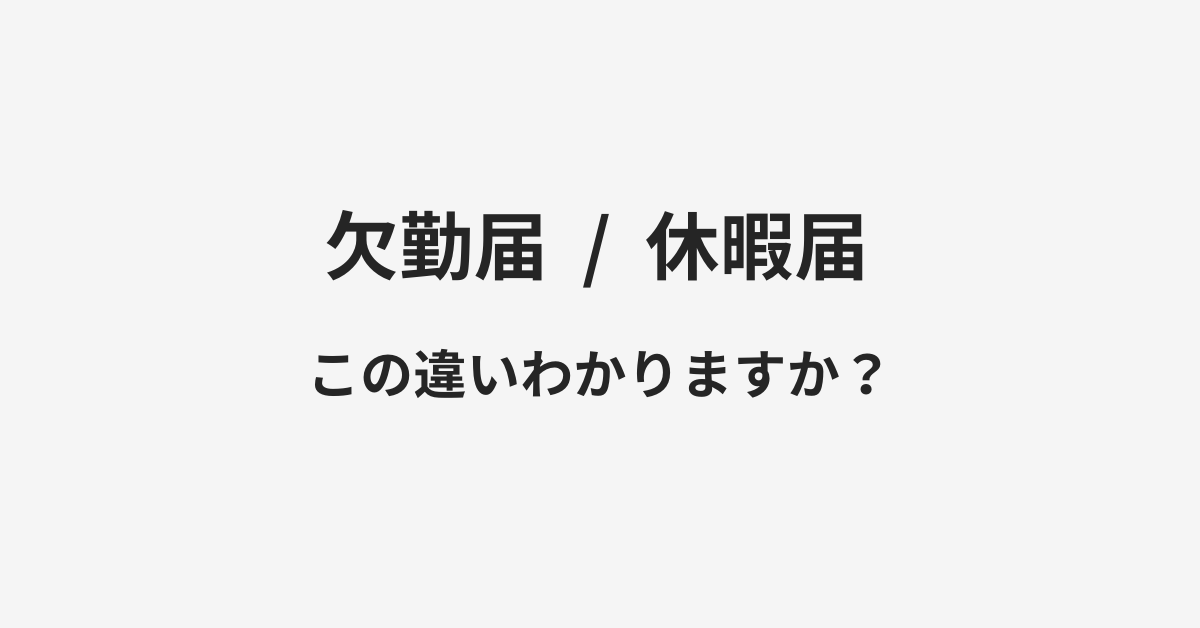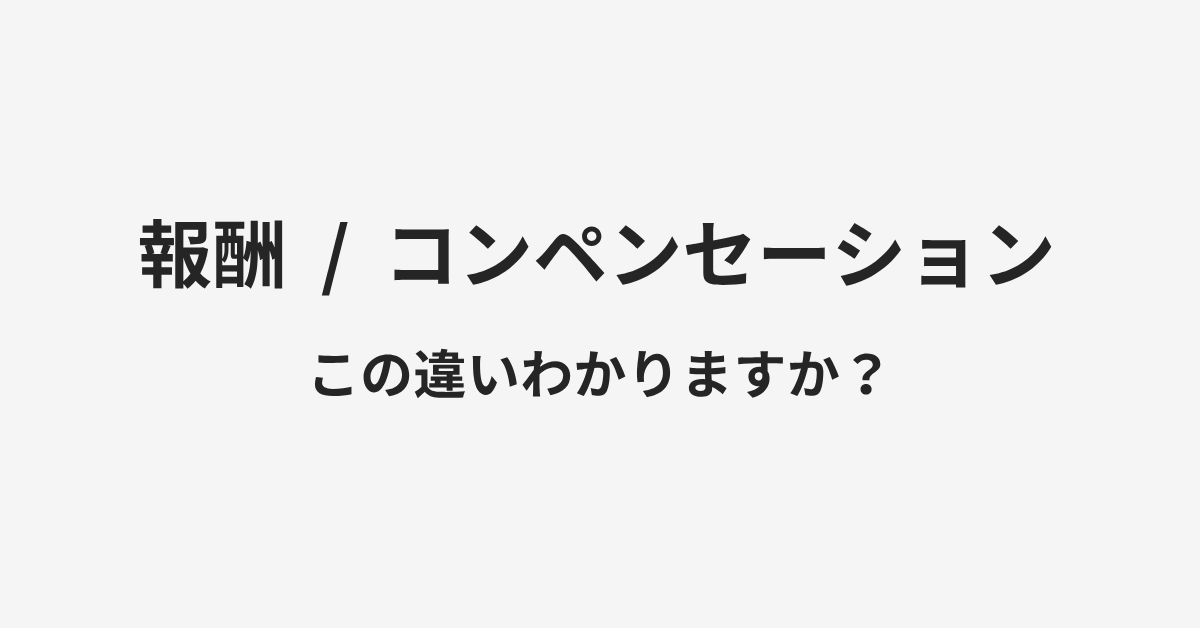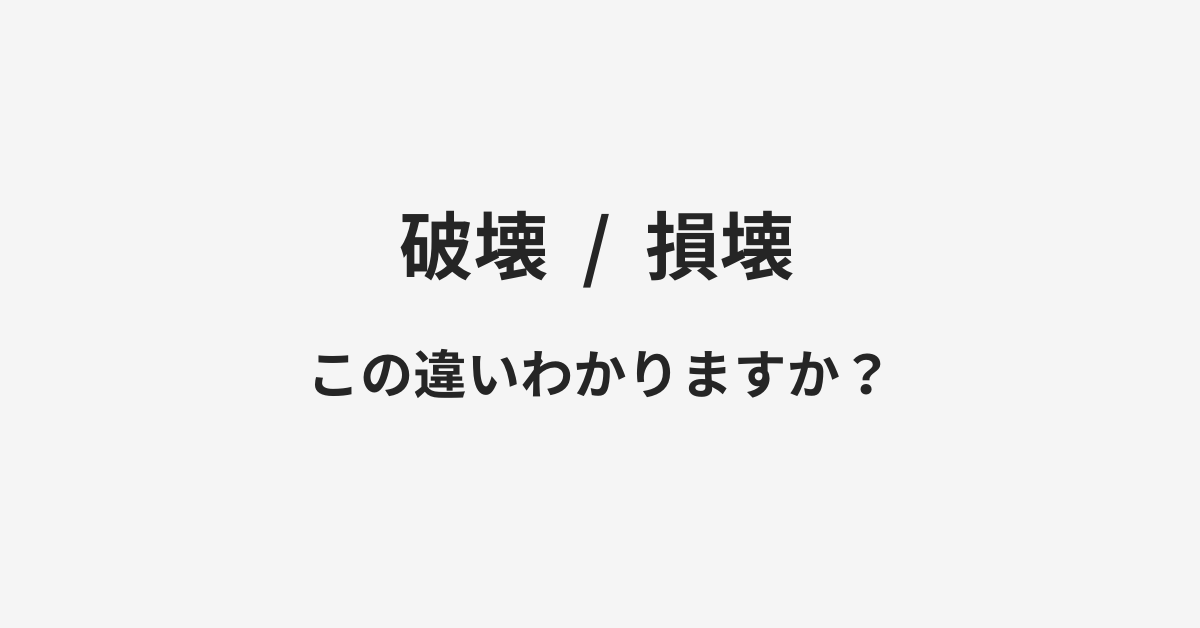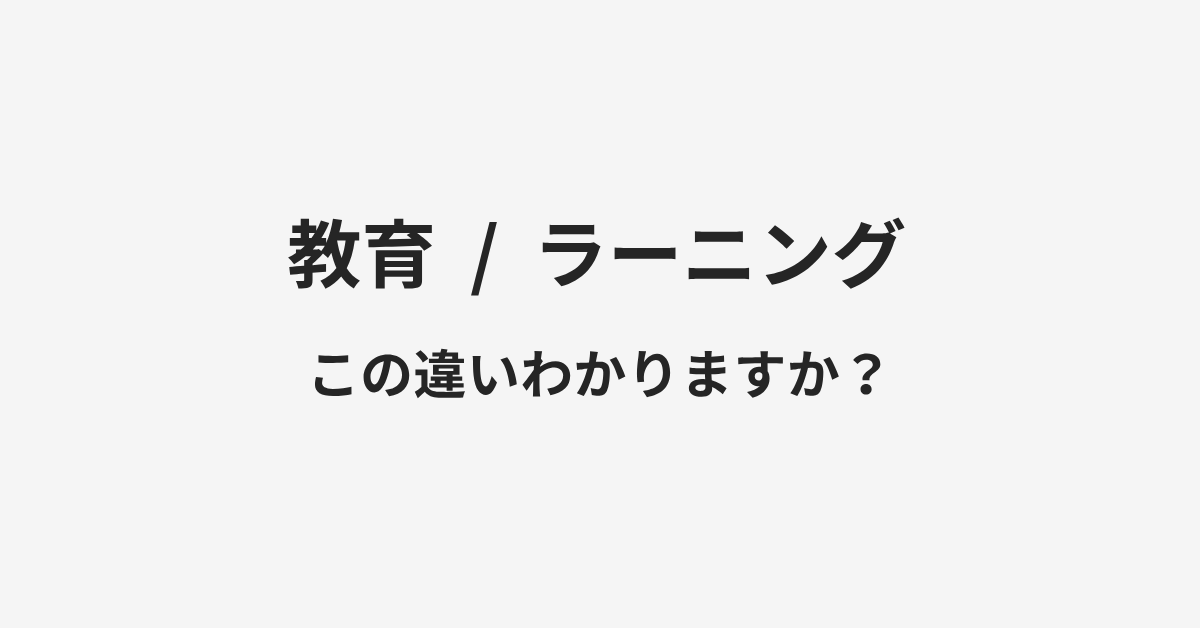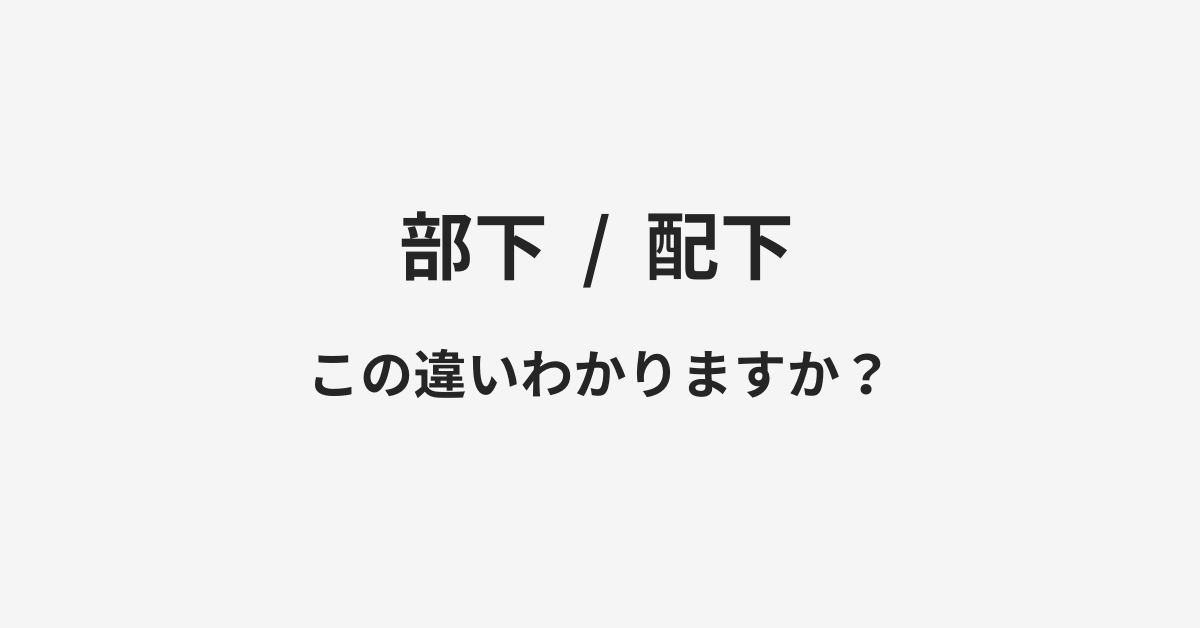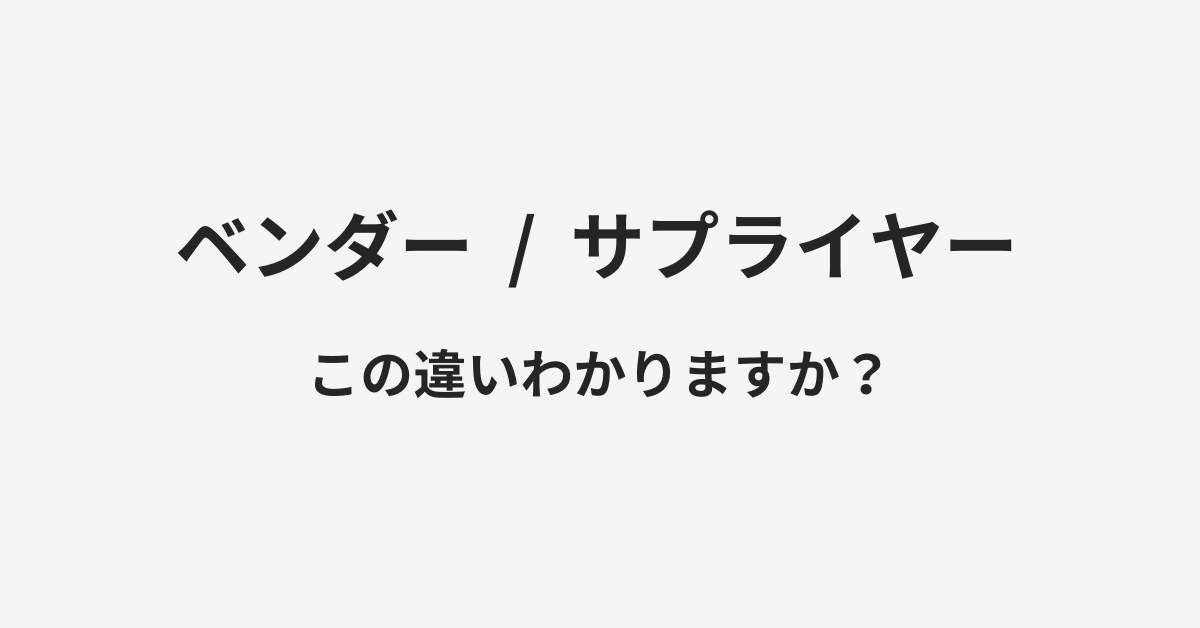【作製】と【制作】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
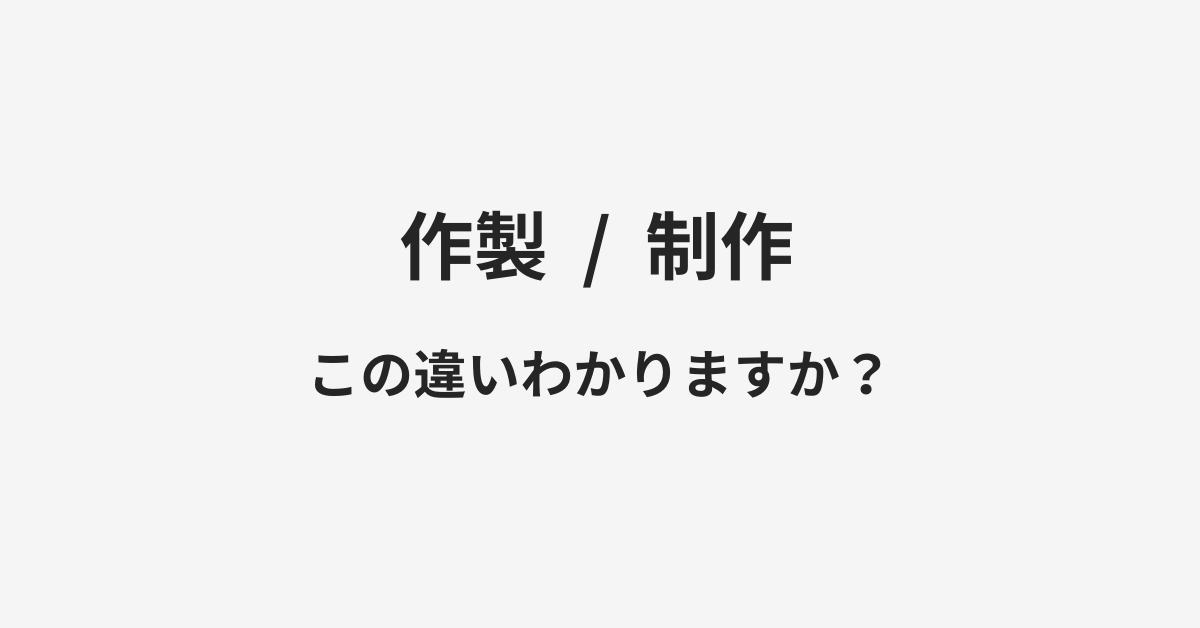
作製と制作の分かりやすい違い
作製と制作は、どちらもつくることを表しますが、作る対象と目的に違いがあります。作製は実用的な物品や道具を物理的に作ることで、制作は創造的・芸術的な作品やコンテンツを作ることを指します。
前者は機能性重視、後者は創造性重視です。
ビジネスにおいて、この使い分けを理解することは、業務内容を正確に伝える上で重要です。
作製とは?
作製とは、設計図や仕様書に基づいて、実用的な物品、機器、部品、試作品などを物理的に作り出すことを指します。製造業、研究開発、エンジニアリング分野で多用され、試験装置を作製するプロトタイプを作製するのように使われます。機能性と品質が重視されます。
ビジネスにおいて作製は、技術力と品質管理能力を示す重要な活動です。作製工程には、材料選定、加工、組立、検査などが含まれ、QCD(品質・コスト・納期)の管理が求められます。作製記録の管理は、トレーサビリティ確保にも不可欠です。
デジタル化により、3Dプリンターでの試作品作製、AIを活用した設計最適化など、作製プロセスも進化しています。しかし、職人的な技術や経験が必要な作製作業も依然として重要で、技術伝承が課題となっています。
作製の例文
- ( 1 ) 新製品の試作品を作製し、性能評価を実施しました。
- ( 2 ) 実験装置を自社で作製することで、研究開発コストを削減しました。
- ( 3 ) 治具を作製して、生産工程の効率化を図りました。
- ( 4 ) カスタムメイドの測定器を作製し、品質管理を強化しています。
- ( 5 ) 3Dプリンターで部品を作製し、開発期間を短縮しました。
- ( 6 ) 仕様書に基づいてサンプルを作製し、顧客承認を得ました。
作製の会話例
制作とは?
制作とは、映像、音楽、出版物、ウェブサイト、広告など、創造的・芸術的な作品やコンテンツを作り出すことを指します。クリエイティブ産業、メディア業界、広告業界で主に使用され、CM制作番組制作コンテンツ制作のように表現されます。
制作プロセスは、企画、構成、演出、編集など創造的な要素が中心で、クリエイターの感性と技術が融合します。制作物の価値は、独創性、メッセージ性、感動や共感を生む力で評価されます。著作権管理も制作業務の重要な要素です。
デジタル時代の制作は、マルチメディア対応、インタラクティブ性、リアルタイム配信など、新たな可能性が広がっています。AI活用による制作支援も進み、効率化と創造性の両立が模索されています。
制作の例文
- ( 1 ) 新商品のプロモーション動画を制作中です。
- ( 2 ) ウェブサイトの制作を外部のクリエイティブエージェンシーに委託しました。
- ( 3 ) 社内報の制作チームを立ち上げ、情報発信を強化しています。
- ( 4 ) 展示会用のパンフレットを制作し、ブランディングを図りました。
- ( 5 ) 研修用のeラーニングコンテンツを制作しています。
- ( 6 ) 創立記念の記録映像を制作し、企業文化の継承に活用します。
制作の会話例
作製と制作の違いまとめ
作製と制作の根本的な違いは、アウトプットの性質にあります。作製は機能を持つ実用品、制作は表現や感動を伝える作品を生み出します。業界による使い分けも明確で、製造業や研究開発では作製、クリエイティブ業界では制作を使用します。
資料を作成は一般的ですが、装置を作製動画を制作となります。実務では、この違いを意識することで、業務の性質を正確に伝えられます。
技術的な物づくりは作製、創造的な物づくりは制作という使い分けが基本です。
作製と制作の読み方
- 作製(ひらがな):さくせい
- 作製(ローマ字):sakusei
- 制作(ひらがな):せいさく
- 制作(ローマ字):seisaku