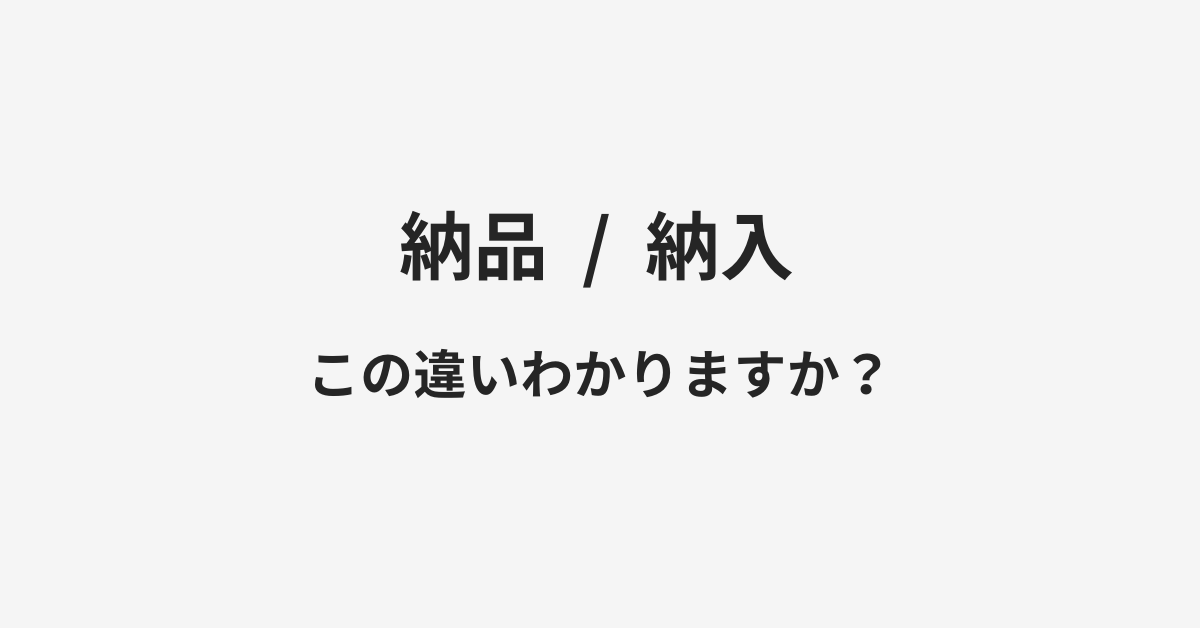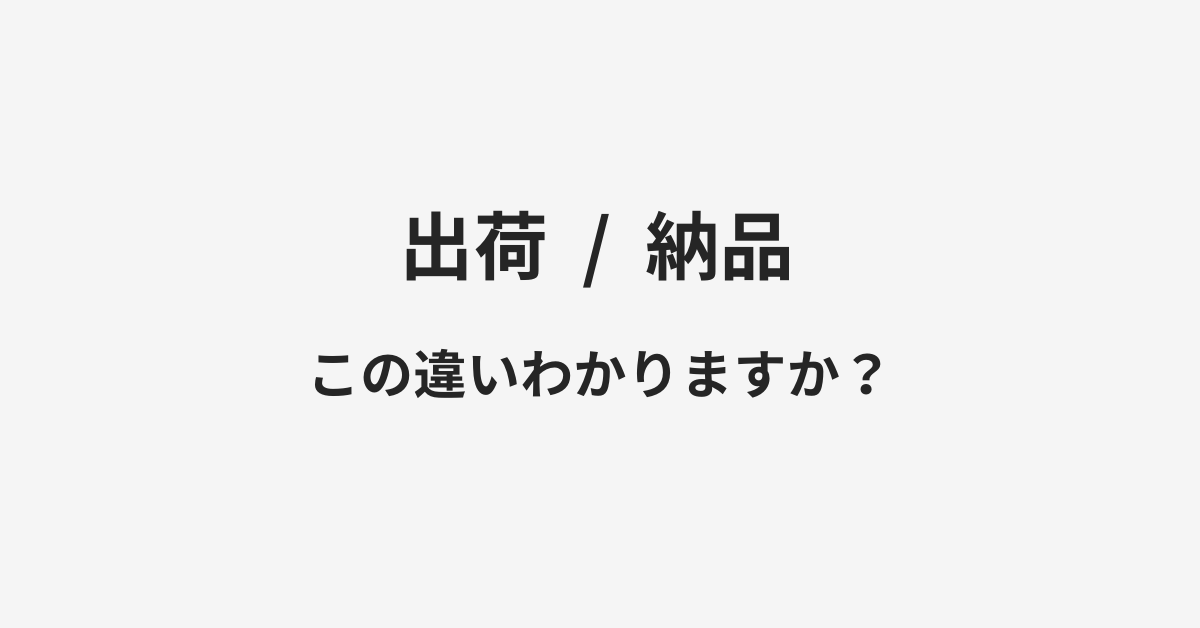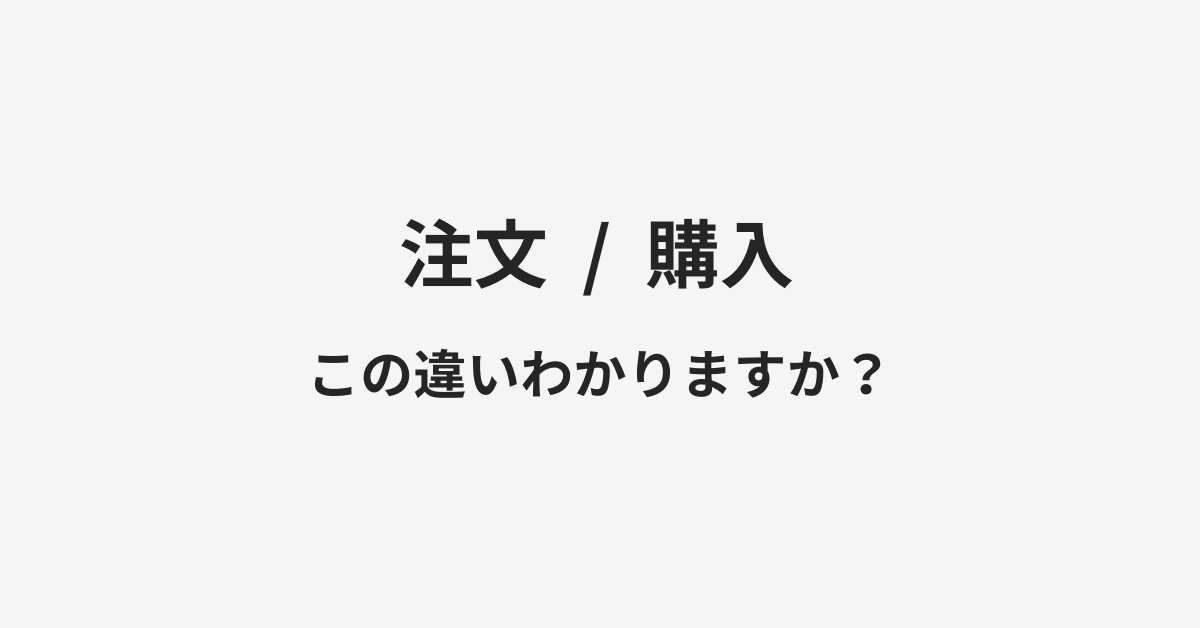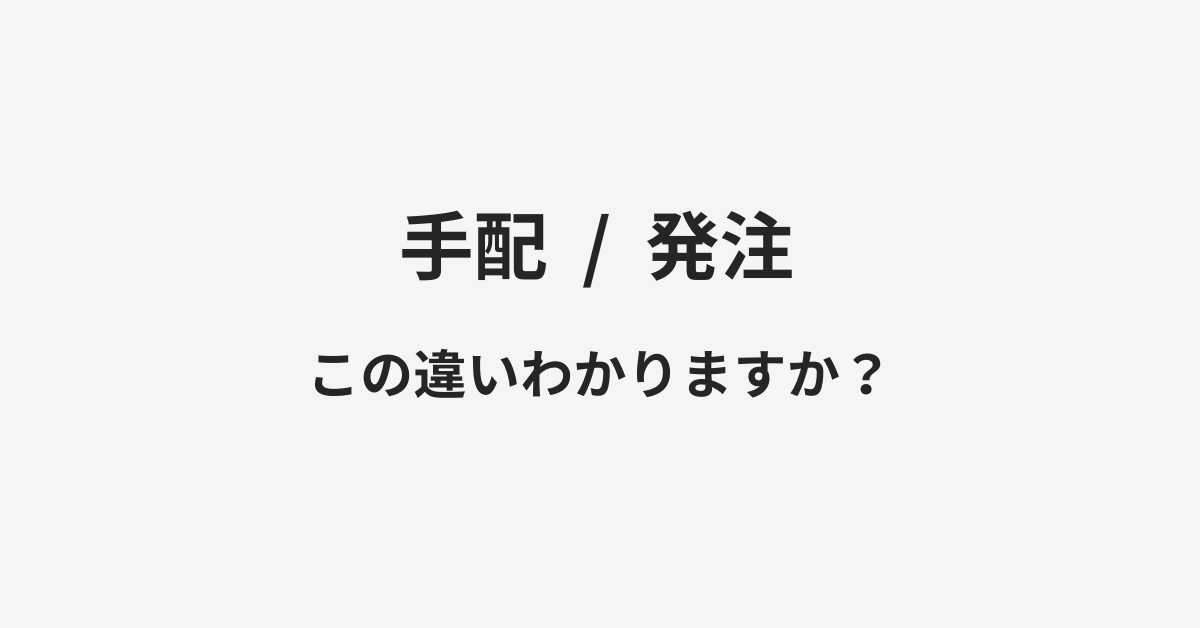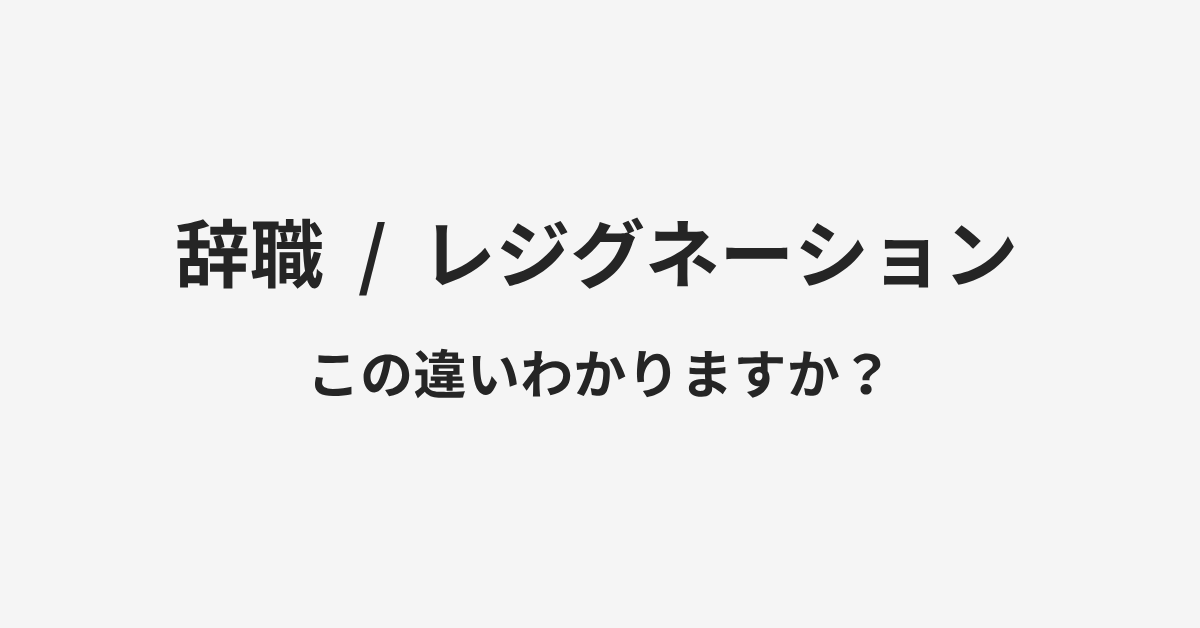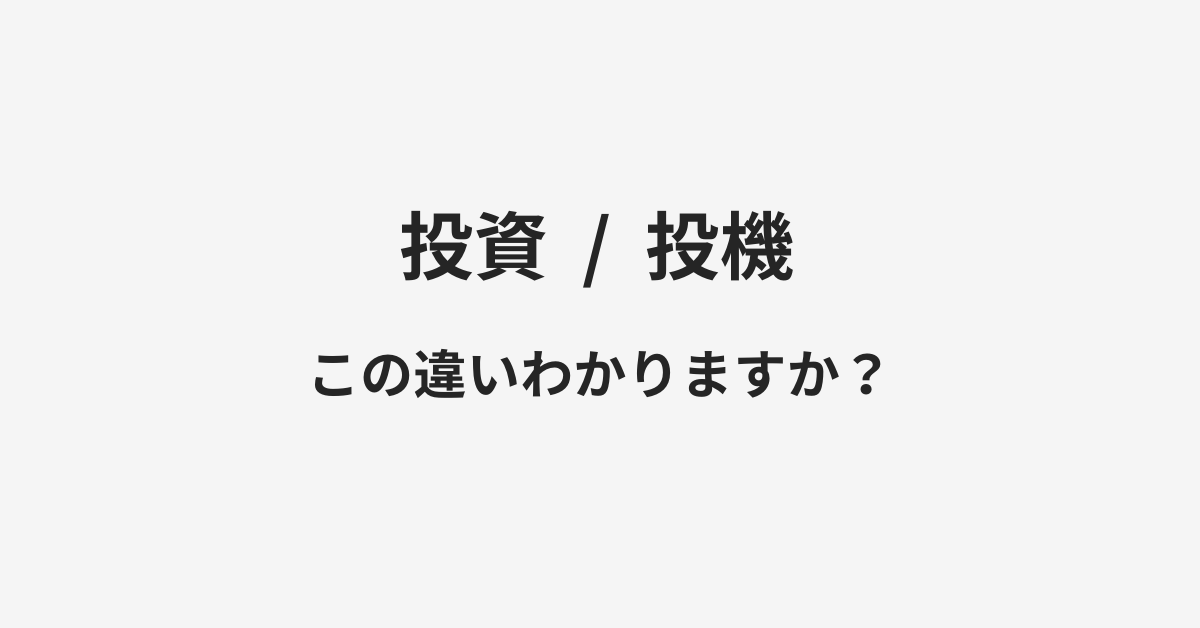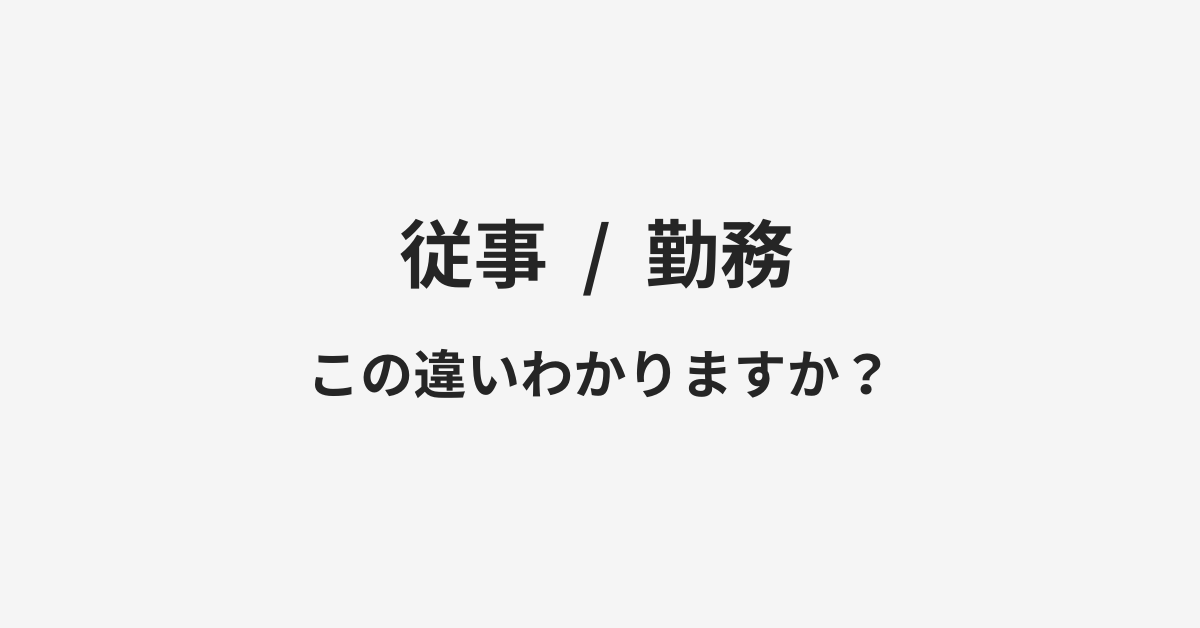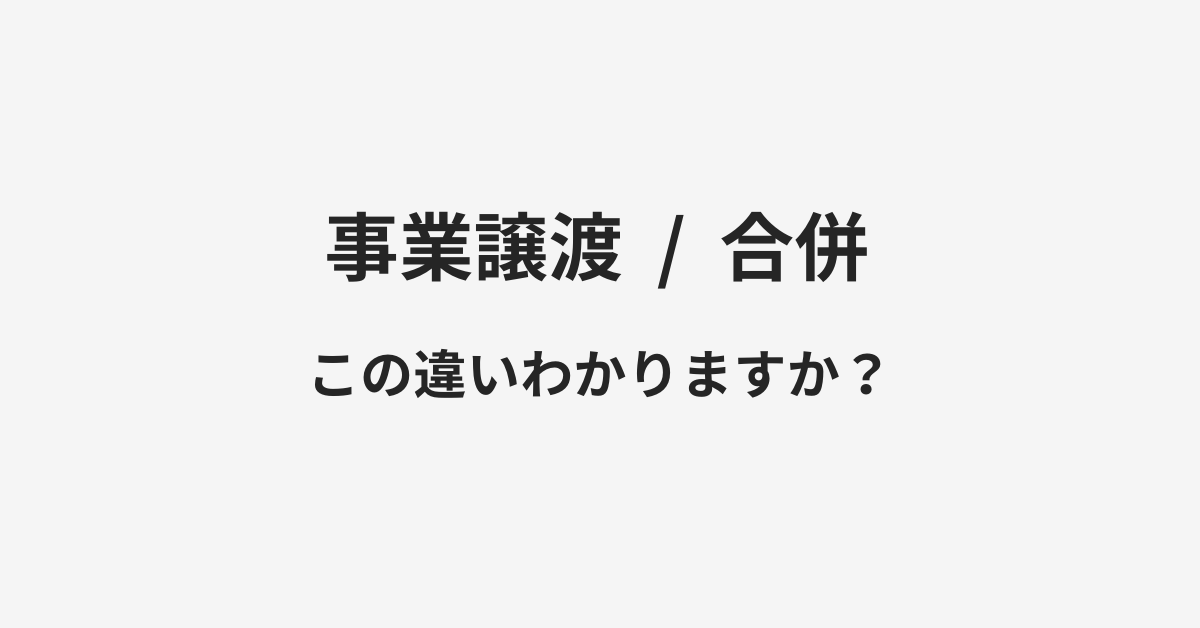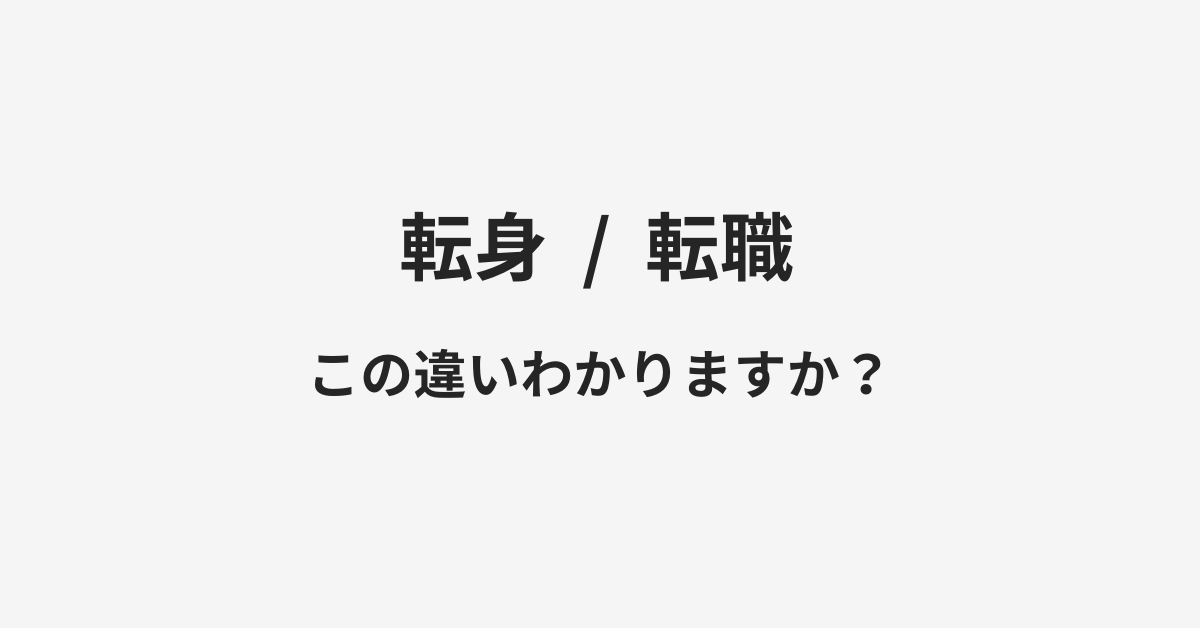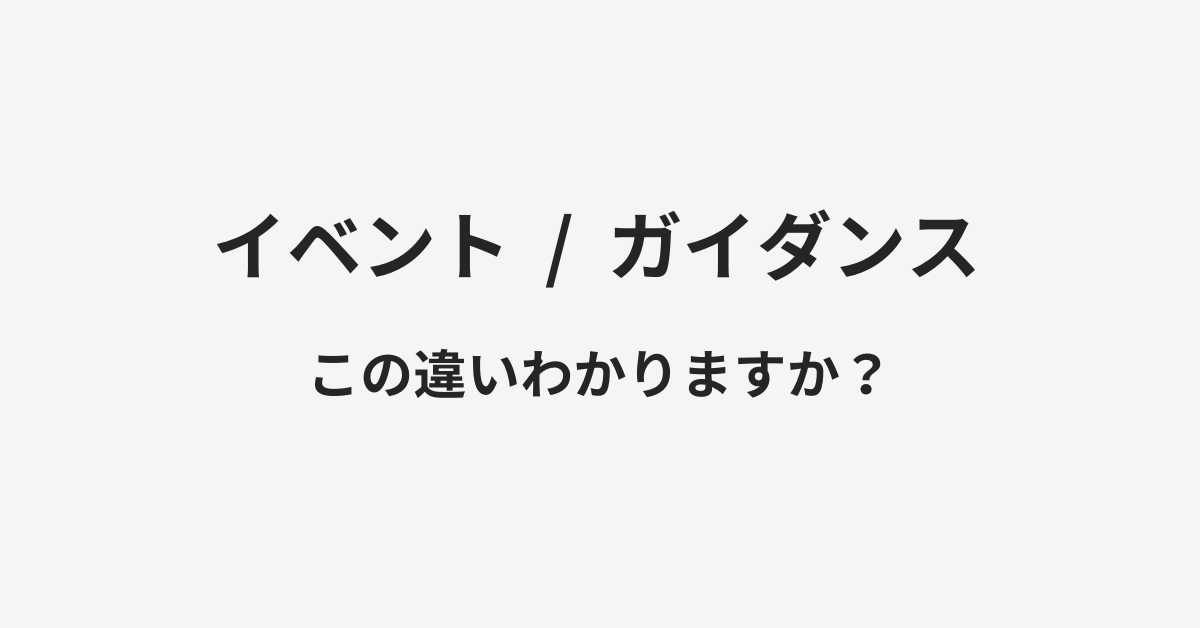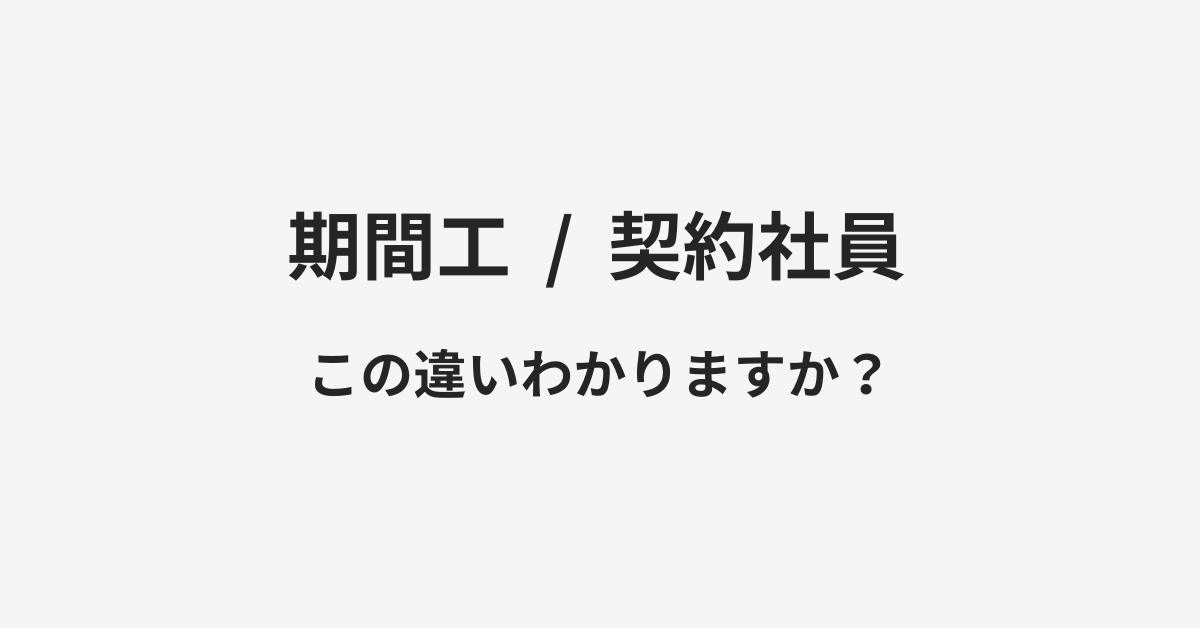【入荷】と【仕入】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
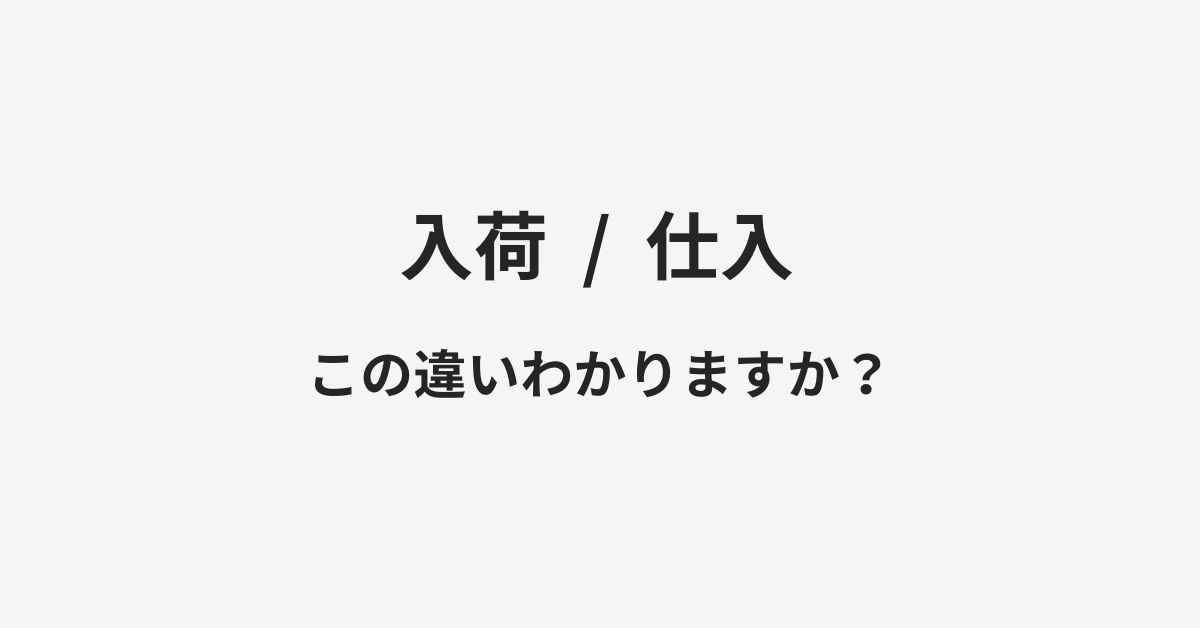
入荷と仕入の分かりやすい違い
入荷と仕入は、商品調達プロセスの異なる段階を表す言葉です。仕入は商品を購入する意思決定と発注の段階で、経営判断を伴う戦略的な活動です。
入荷は発注した商品が実際に届く物流の段階で、在庫管理の起点となる実務的な作業です。
入荷とは?
入荷とは、発注した商品や材料が実際に倉庫や店舗に到着し、受け入れる作業を指します。物流プロセスの一環として、検品、数量確認、品質チェック、在庫計上などの実務的な作業が含まれます。入荷予定日の管理、入荷遅延への対応なども重要な業務です。
本日入荷、入荷待ちなど、商品の物理的な到着状況を表す際に使用されます。小売業では、入荷情報を顧客に伝えることで、販売機会の創出にもつながります。適切な入荷管理は、在庫切れの防止と過剰在庫の抑制に不可欠です。
入荷作業の効率化は、物流コストの削減と顧客サービスの向上に直結します。バーコード管理やRFIDの活用など、デジタル化も進んでいます。
入荷の例文
- ( 1 ) 明日、新商品が入荷予定です。
- ( 2 ) 入荷検品で不良品を発見しました。
- ( 3 ) 入荷遅延により、販売計画の見直しが必要です。
- ( 4 ) 大量入荷に備えて、倉庫スペースを確保しました。
- ( 5 ) 入荷処理の自動化により、作業時間が半減しました。
- ( 6 ) 入荷スケジュールを店頭スタッフと共有します。
入荷の会話例
仕入とは?
仕入とは、商品や原材料を購入する行為全般を指し、調達戦略の立案から発注までの一連のプロセスを含みます。仕入先の選定、価格交渉、支払条件の設定、品質基準の確認など、経営判断を伴う重要な業務です。仕入原価は利益率に直接影響するため、コスト管理の要となります。
仕入値、仕入先、仕入担当など、購買活動の様々な側面で使用されます。適切な仕入により、品質の確保、安定供給、コスト競争力の向上が実現します。市場動向の把握、為替変動への対応など、高度な判断力が求められます。
戦略的な仕入は、企業の競争優位性を左右する重要な機能です。サプライチェーンマネジメントの観点からも、持続可能な仕入体制の構築が求められています。
仕入の例文
- ( 1 ) 海外からの仕入を拡大する計画です。
- ( 2 ) 仕入原価の上昇に対して、対策を検討中です。
- ( 3 ) 新規仕入先の開拓に成功しました。
- ( 4 ) 仕入条件の改善により、利益率が向上しました。
- ( 5 ) シーズン商品の仕入時期を見直します。
- ( 6 ) 仕入担当者向けの交渉スキル研修を実施します。
仕入の会話例
入荷と仕入の違いまとめ
入荷と仕入は、商品調達における異なるフェーズを表す重要な概念です。
仕入は何を、どこから、いくらで買うかという戦略的判断、入荷はいつ、どのように受け取るかという実務的作業です。
両者を適切に管理することで、効率的な在庫管理と収益性の向上が実現します。
入荷と仕入の読み方
- 入荷(ひらがな):にゅうか
- 入荷(ローマ字):nyuuka
- 仕入(ひらがな):しいれ
- 仕入(ローマ字):shiire