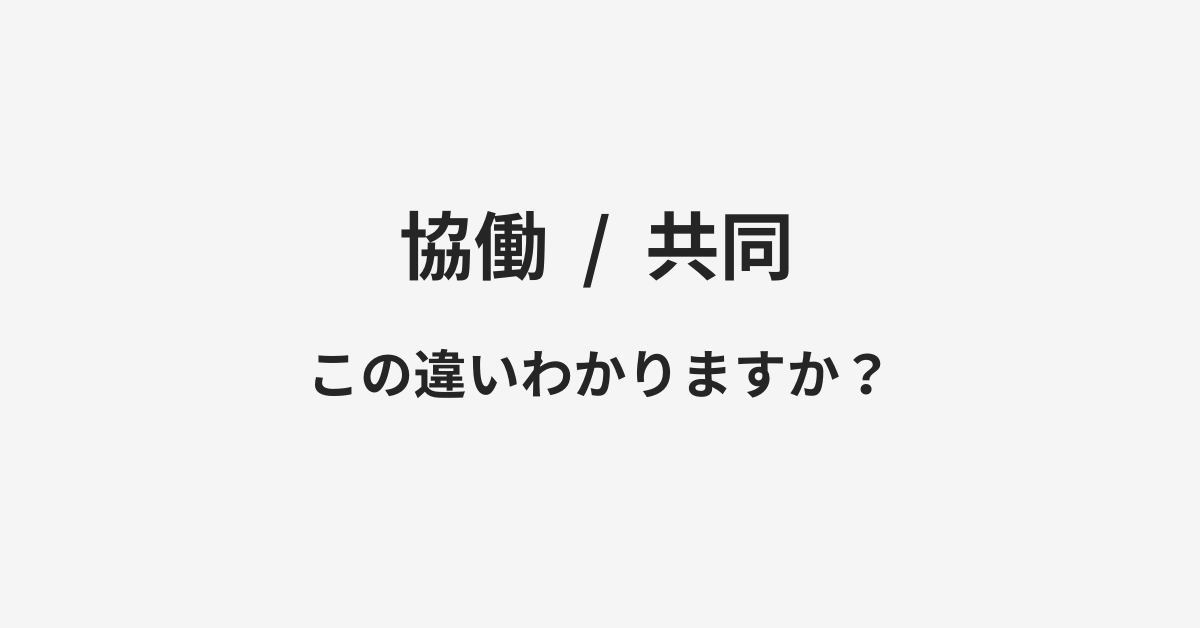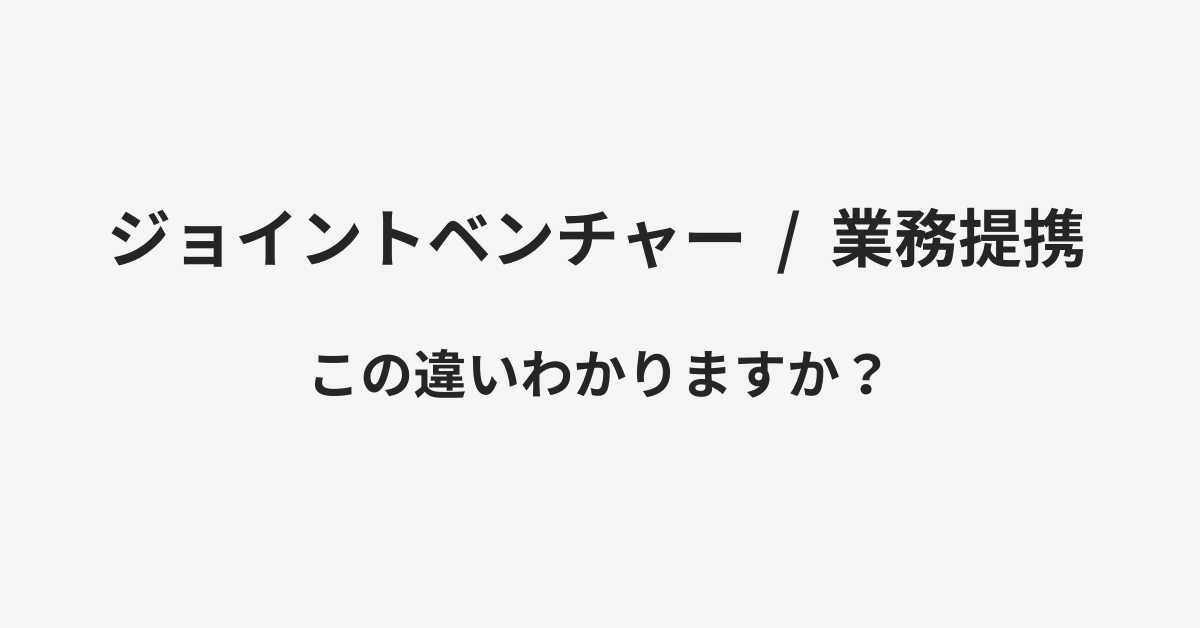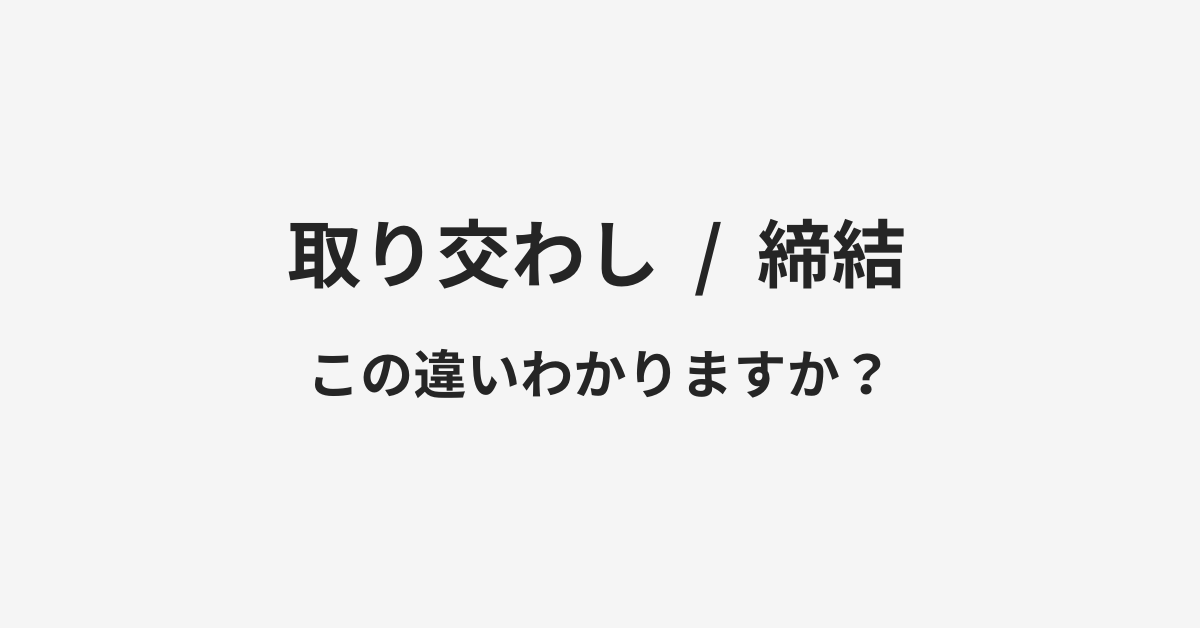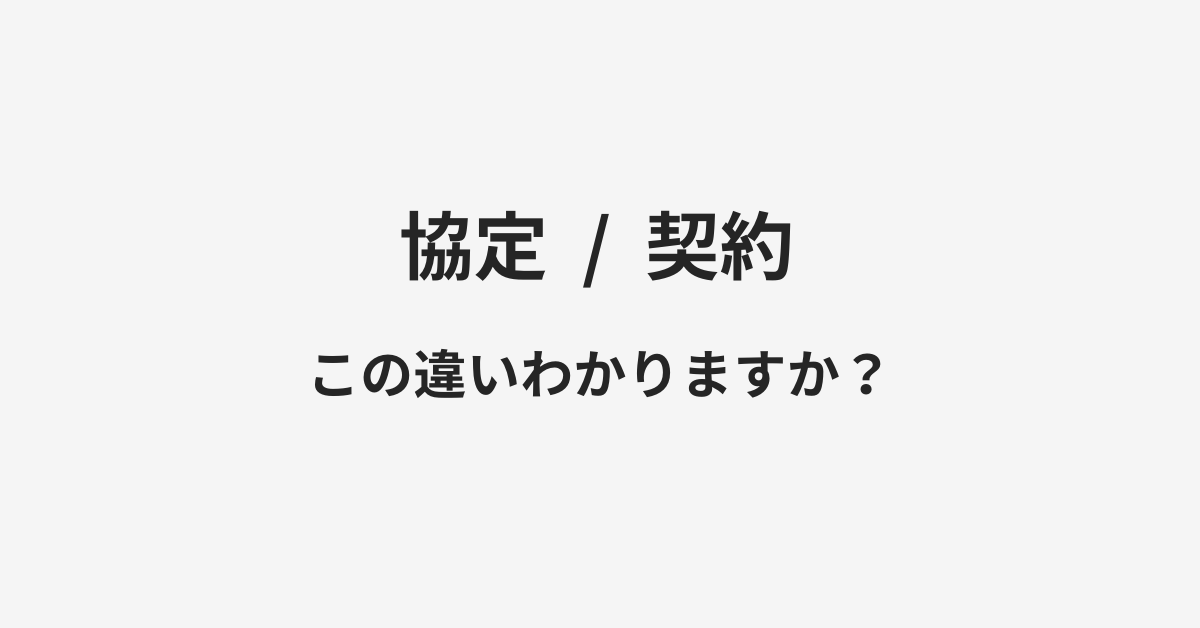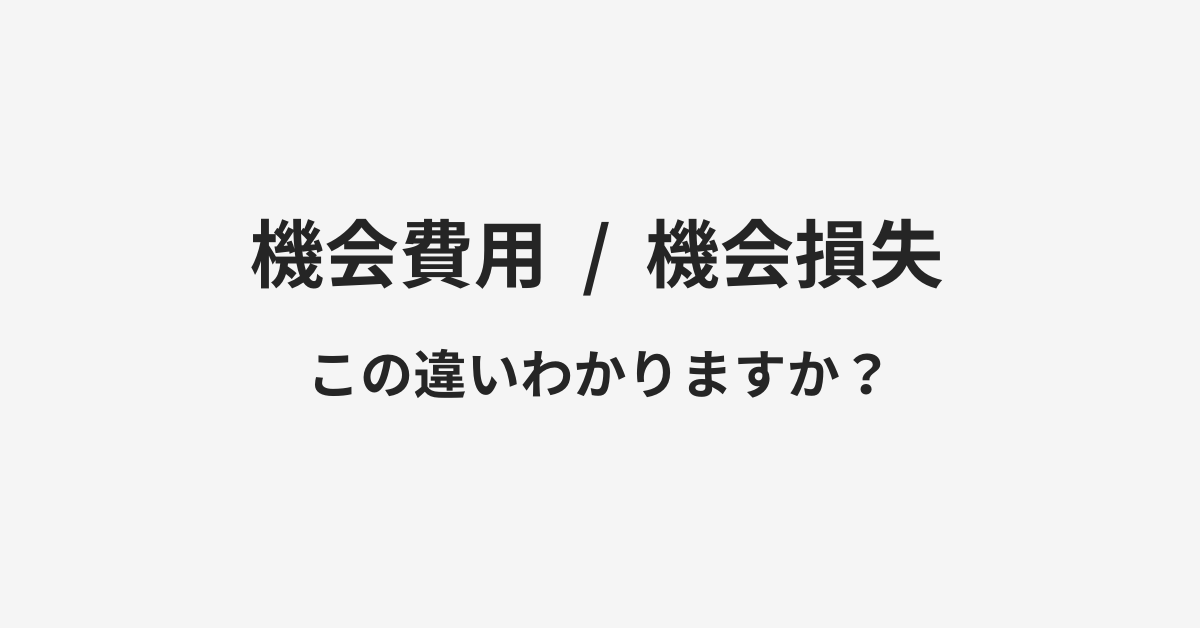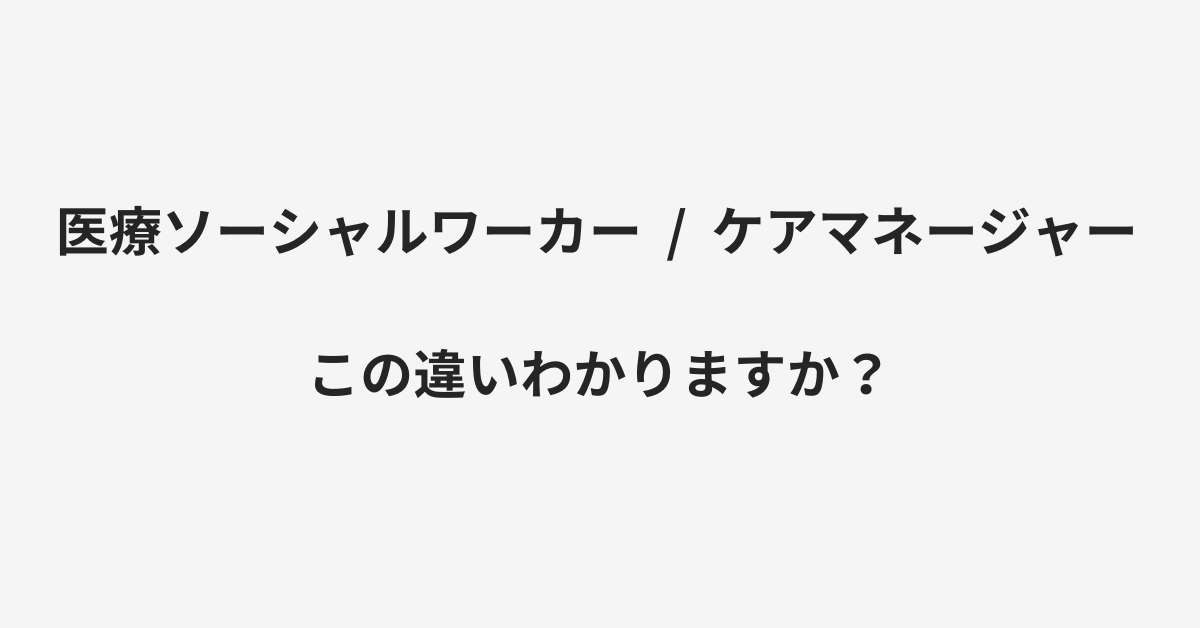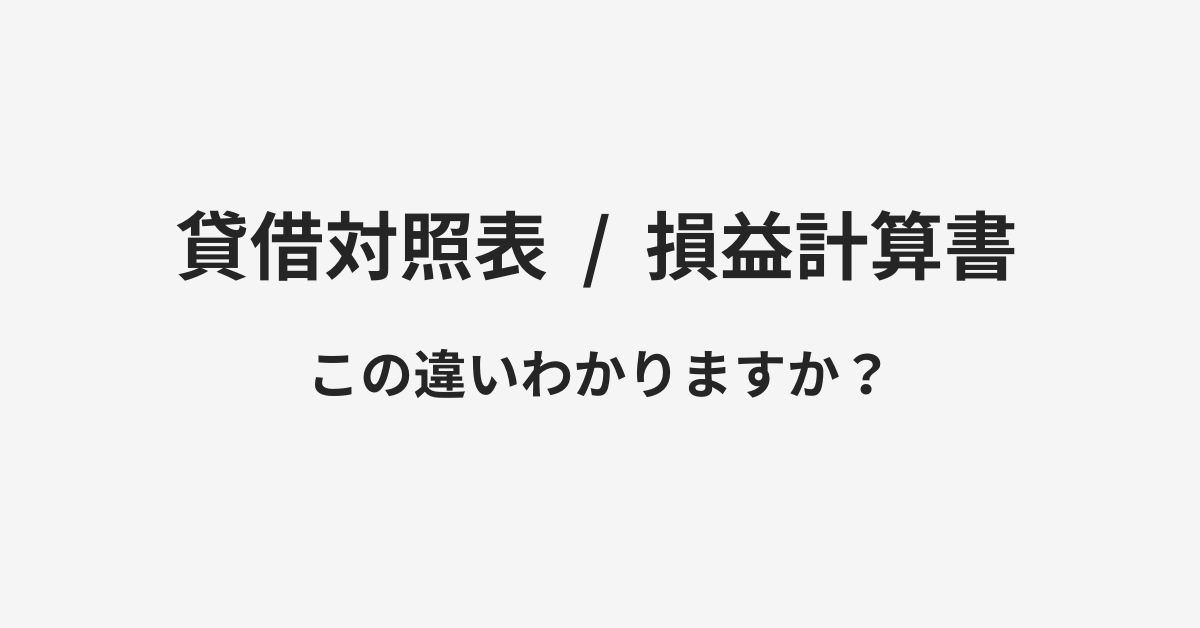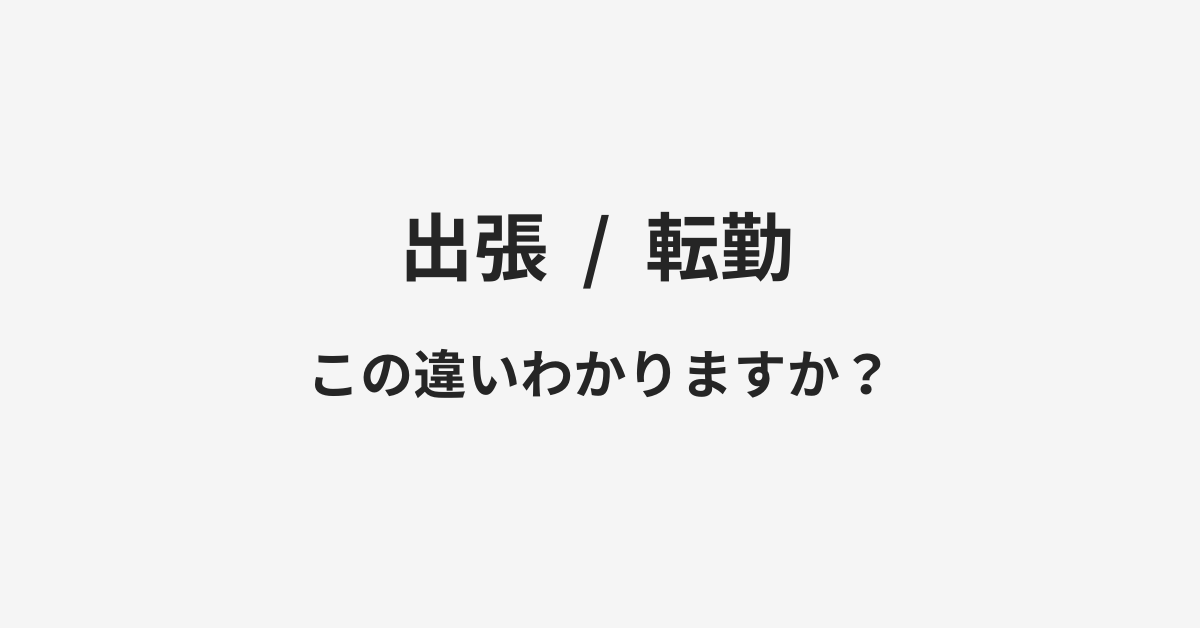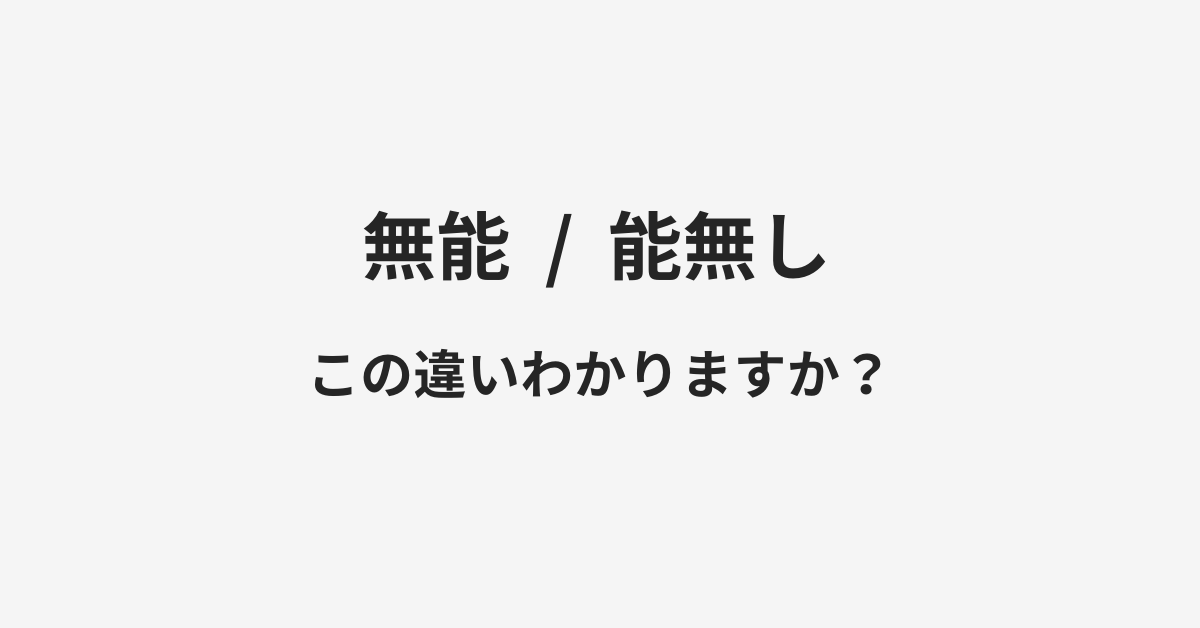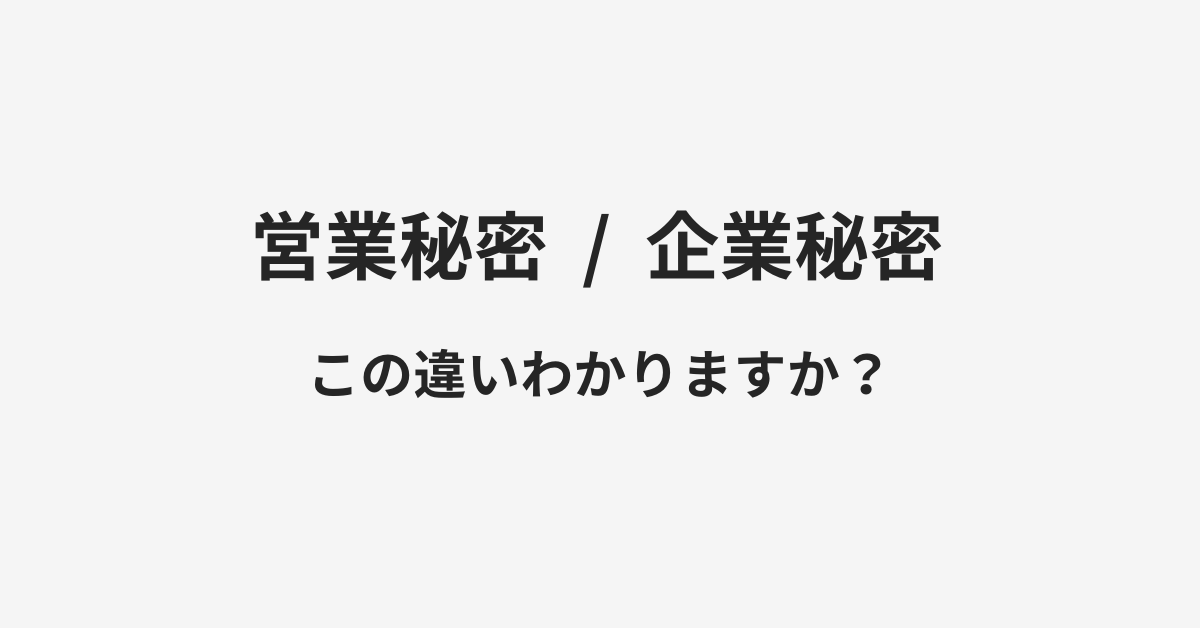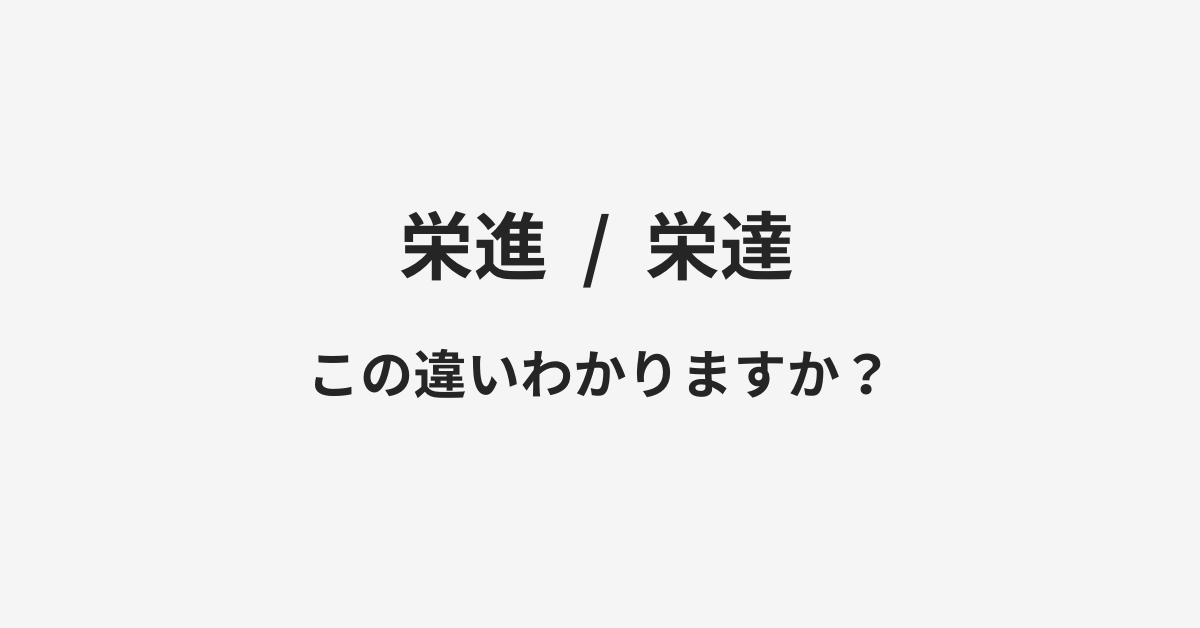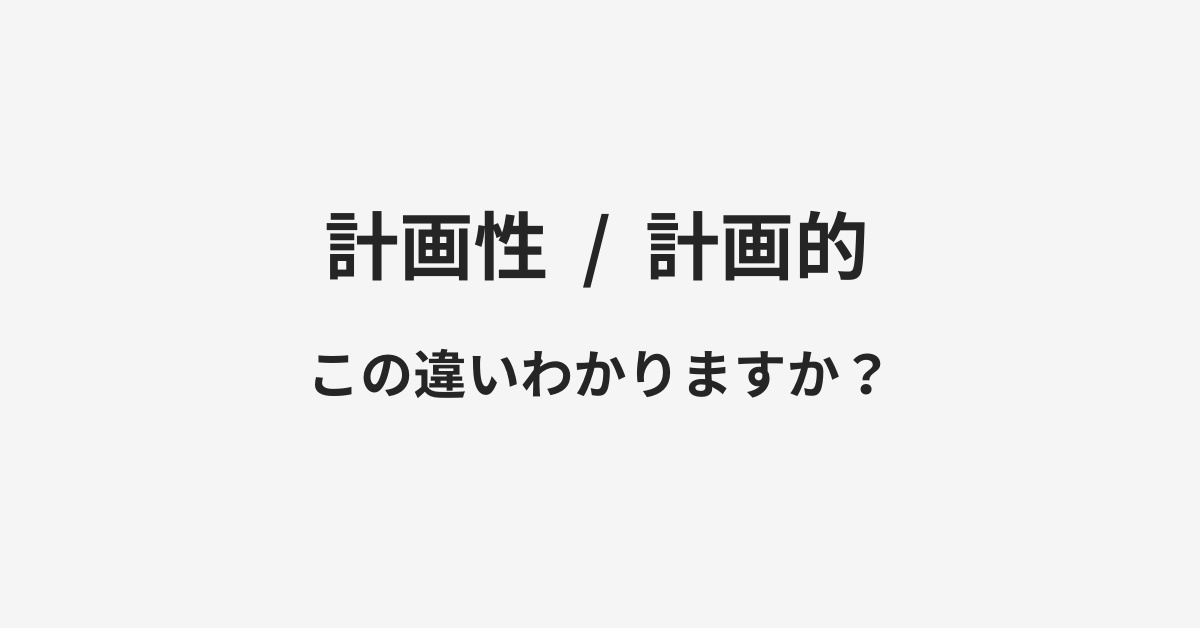【協商】と【同盟】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
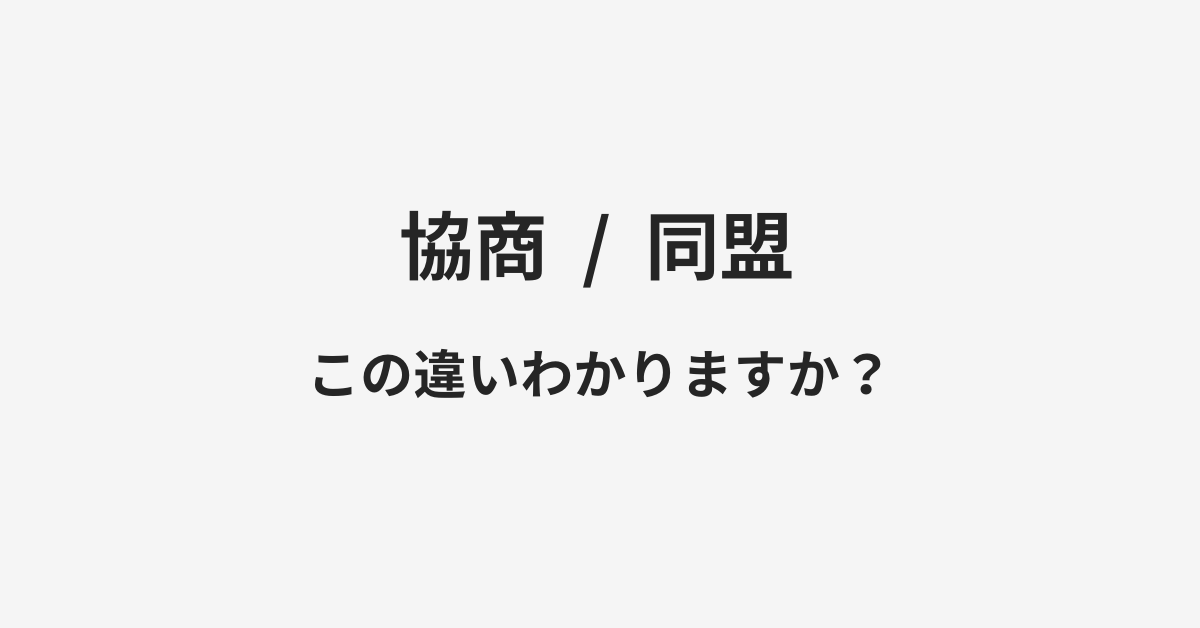
協商と同盟の分かりやすい違い
協商と同盟の主な違いは、目的と関係性の性質にあります。
協商は、利害関係のある当事者間で、対話を通じて合意形成を目指すプロセスを指すのに対し、同盟は、共通の目的や利益を持つ者同士が、相互支援や協力関係を築くことを指します。
協商は一時的な問題解決のための手段であることが多いのに対し、同盟は比較的長期的な関係性を築くことを目的とすることが多いです。
協商とは?
協商とは、利害関係のある当事者間で、対話と交渉を通じて合意形成を目指すプロセスを指します。協商は、各当事者の立場や要求を踏まえつつ、互いに受け入れ可能な解決策を見出すことを目的とします。
協商では、当事者間の意見の相違を明確にし、建設的な議論を重ねることが重要です。歩み寄りや妥協が必要な場面もありますが、Win-Winの関係を目指すことが協商の基本的な姿勢だと言えます。協商は、外交、ビジネス、労使関係など、様々な場面で用いられる手法です。協商を効果的に進めるには、当事者間の信頼関係の構築と、冷静かつ論理的なコミュニケーションが不可欠です。
協商は、一時的な問題解決のための手段であることが多く、合意が形成された後は、各当事者が独立した立場に戻ることが一般的です。
協商の例文
- ( 1 ) 労使間の協商が成立し、ストライキは回避された。
- ( 2 ) 両国の外交官は、貿易問題について協商を重ねた。
- ( 3 ) プロジェクトチームは、予算配分をめぐって協商を行った。
- ( 4 ) 企業間の協商の結果、新たな業務提携が実現した。
- ( 5 ) 地域住民と自治体は、公園の利用方法について協商した。
- ( 6 ) 著作権者と出版社は、ロイヤルの割合について協商を進めている。
協商の会話例
同盟とは?
同盟とは、共通の目的や利益を持つ者同士が、相互支援や協力関係を築くことを指します。同盟は、政治、軍事、経済、社会活動など、様々な分野で見られる関係性です。
同盟国間では、安全保障や経済発展などの面で、緊密な協力体制が敷かれることが一般的です。同盟は、単独では達成が難しい目標に向けて、複数の主体が力を合わせることで、より大きな効果を生み出すことを目的としています。
同盟関係の構築には、価値観の共有と強固な信頼関係が不可欠です。同盟は、比較的長期的な関係性を築くことを目的とすることが多く、同盟国間では、定期的な情報交換や協議が行われます。ただし、同盟関係は永続的なものではなく、国際情勢の変化や利害の対立などによって、解消されることもあります。
同盟の例文
- ( 1 ) 我が国とX国との同盟関係は、地域の平和と安定に欠かせないものだと考えます。
- ( 2 ) 日米同盟は、両国の安全保障において重要な役割を果たしている。
- ( 3 ) EU加盟国は、経済的な同盟関係を築いている。
- ( 4 ) 環境保護団体は、地球温暖化対策で同盟を組んだ。
- ( 5 ) 複数の政党が選挙で同盟を組み、連立政権を樹立した。
- ( 6 ) 同業者間で同盟を結び、共同事業を展開する企業が増えている。
同盟の会話例
協商と同盟の違いまとめ
協商と同盟の違いは、目的と関係性の性質にあります。協商は、利害関係のある当事者間で、対話を通じて合意形成を目指すプロセスを指すのに対し、同盟は、共通の目的や利益を持つ者同士が、相互支援や協力関係を築くことを指します。
協商は一時的な問題解決のための手段であることが多いのに対し、同盟は比較的長期的な関係性を築くことを目的とすることが多いです。
両者に共通するのは、当事者間の信頼関係の重要性です。協商と同盟は、国家間、組織間、個人間など、様々なレベルで見られる関係性であり、それぞれの場面で適切に用いられることで、円滑な問題解決と安定的な関係構築に寄与すると言えます。
協商と同盟の読み方
- 協商(ひらがな):きょうしょう
- 協商(ローマ字):kyōshō
- 同盟(ひらがな):どうめい
- 同盟(ローマ字):dōmei