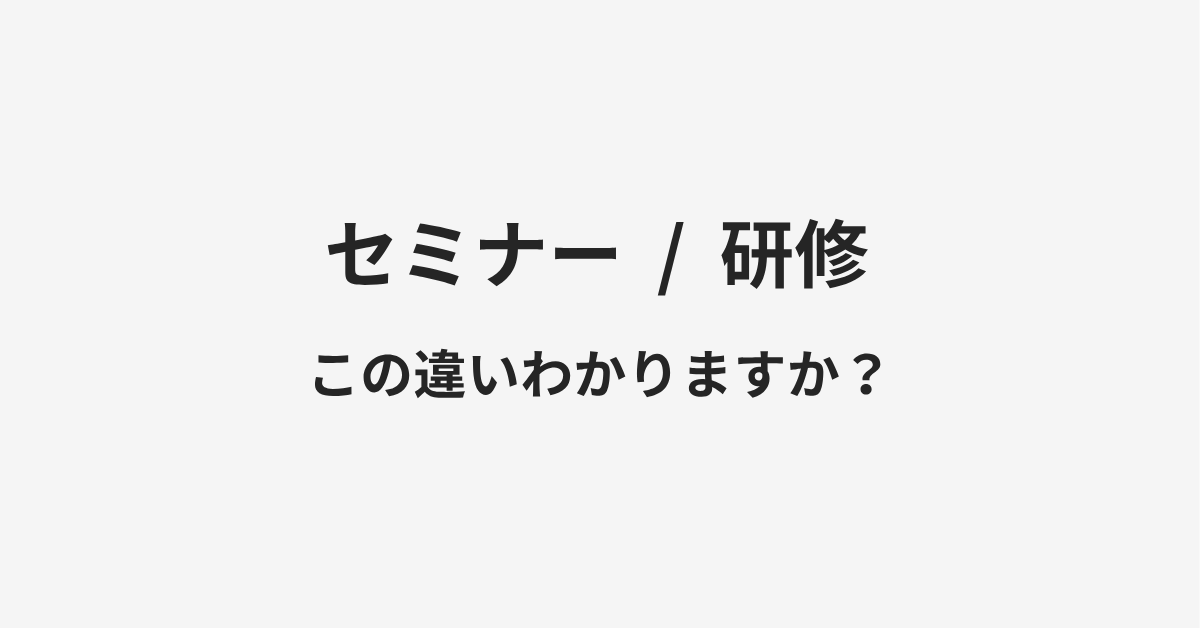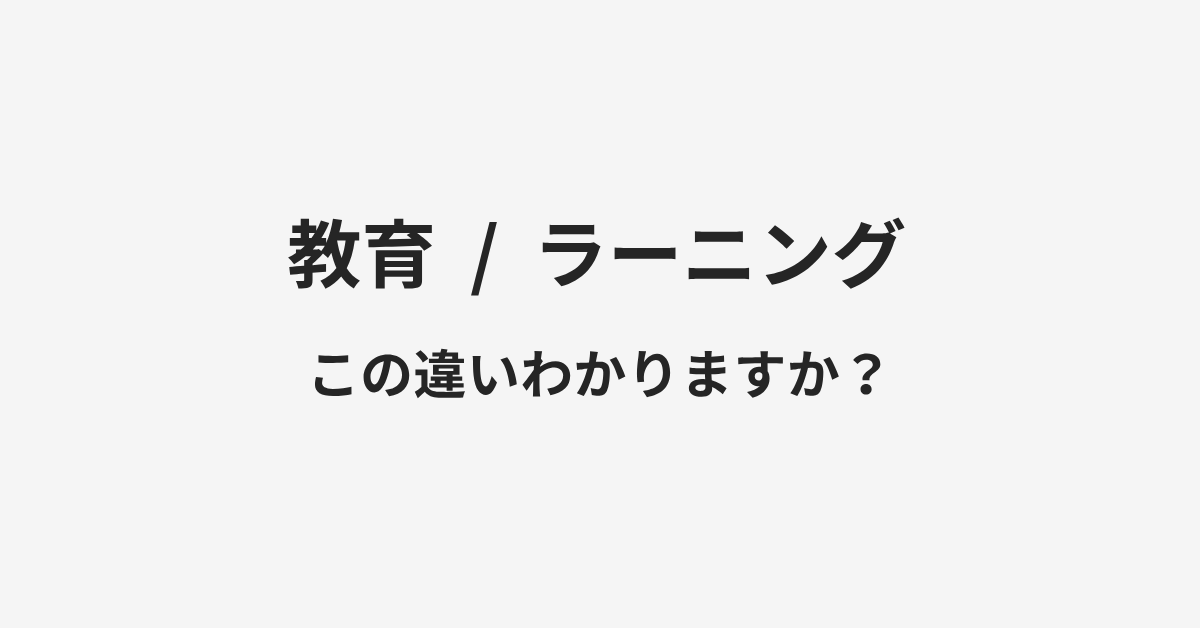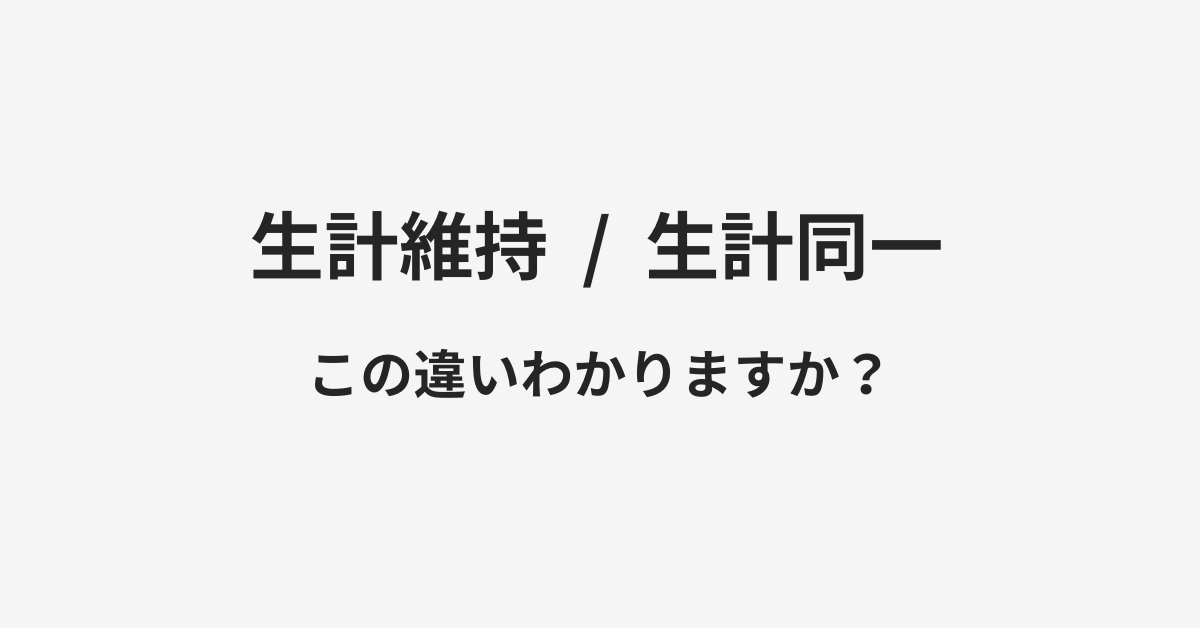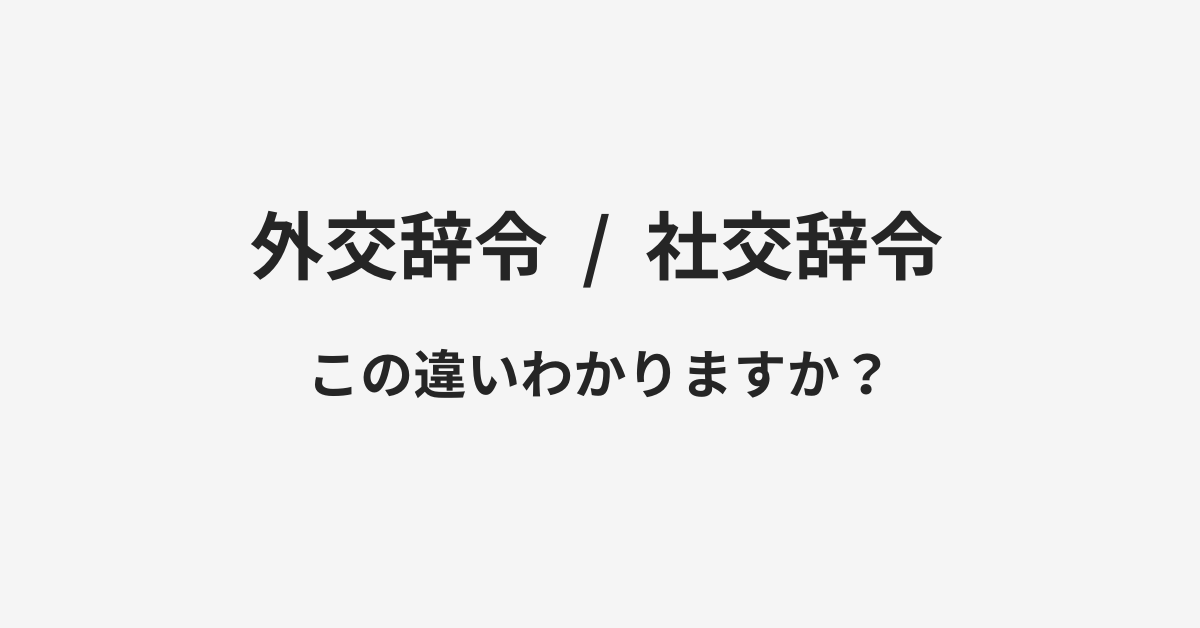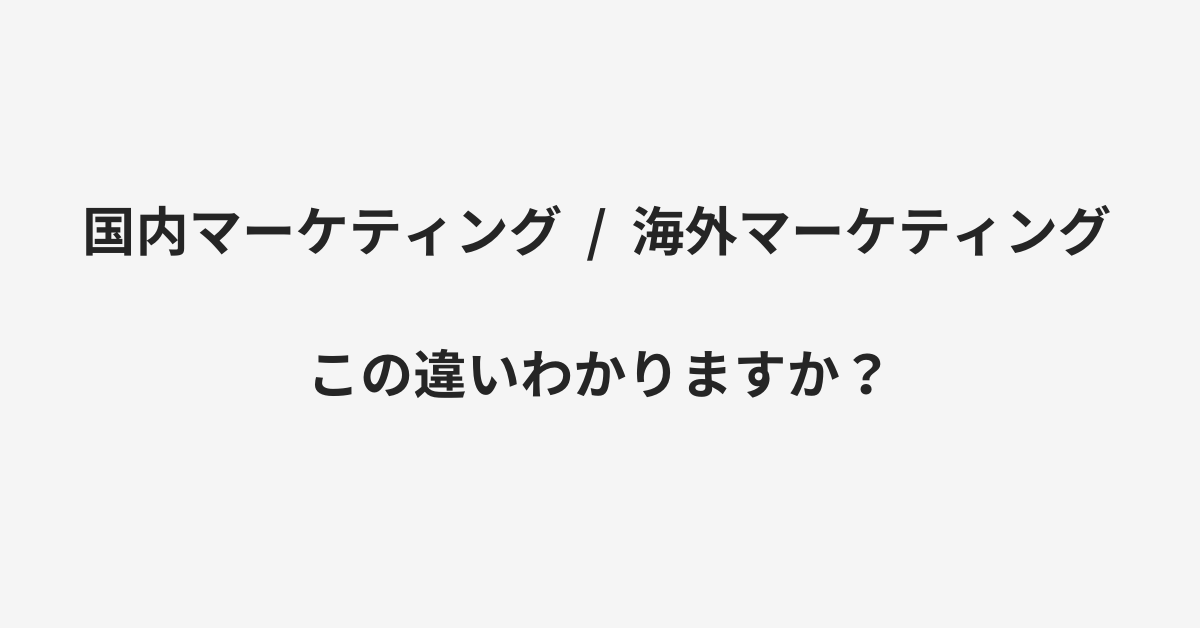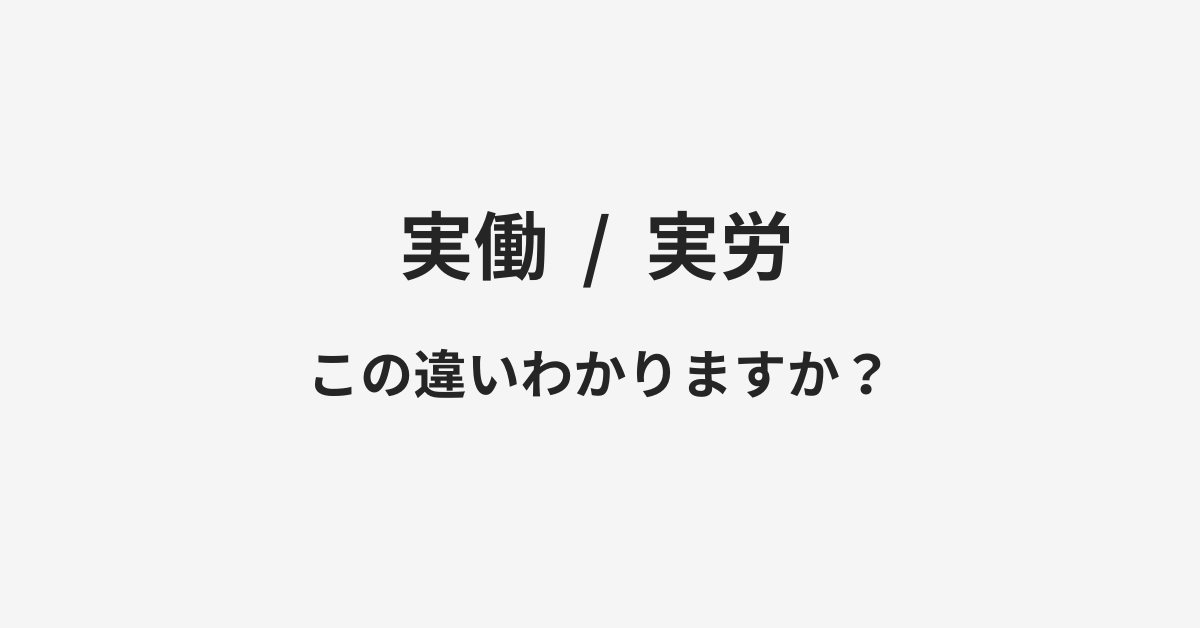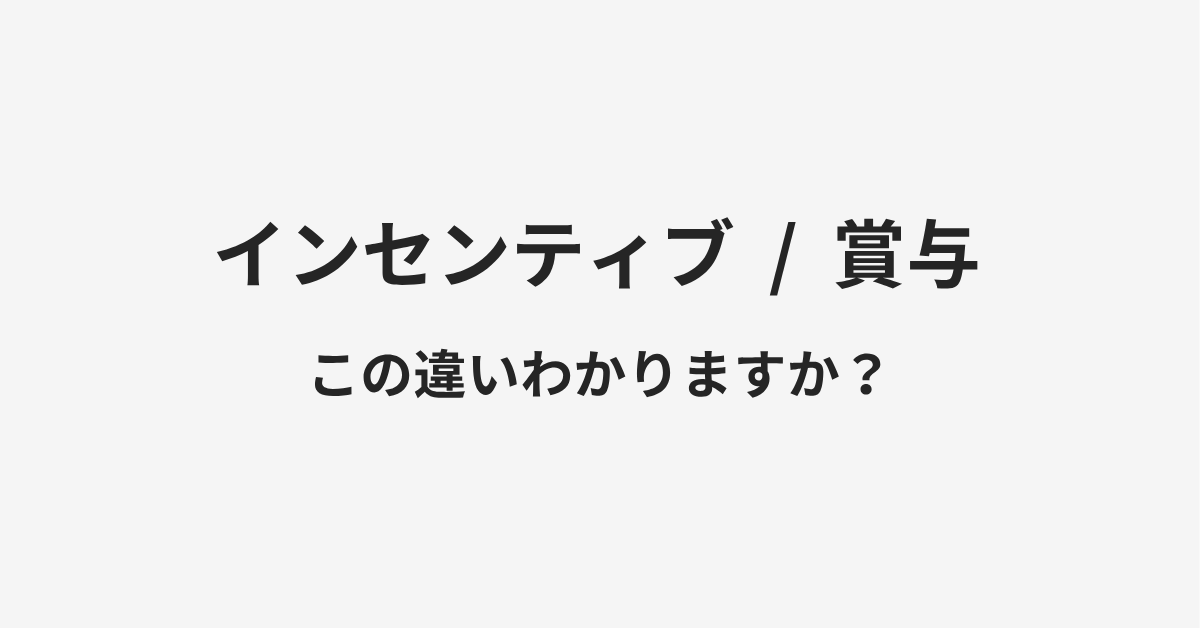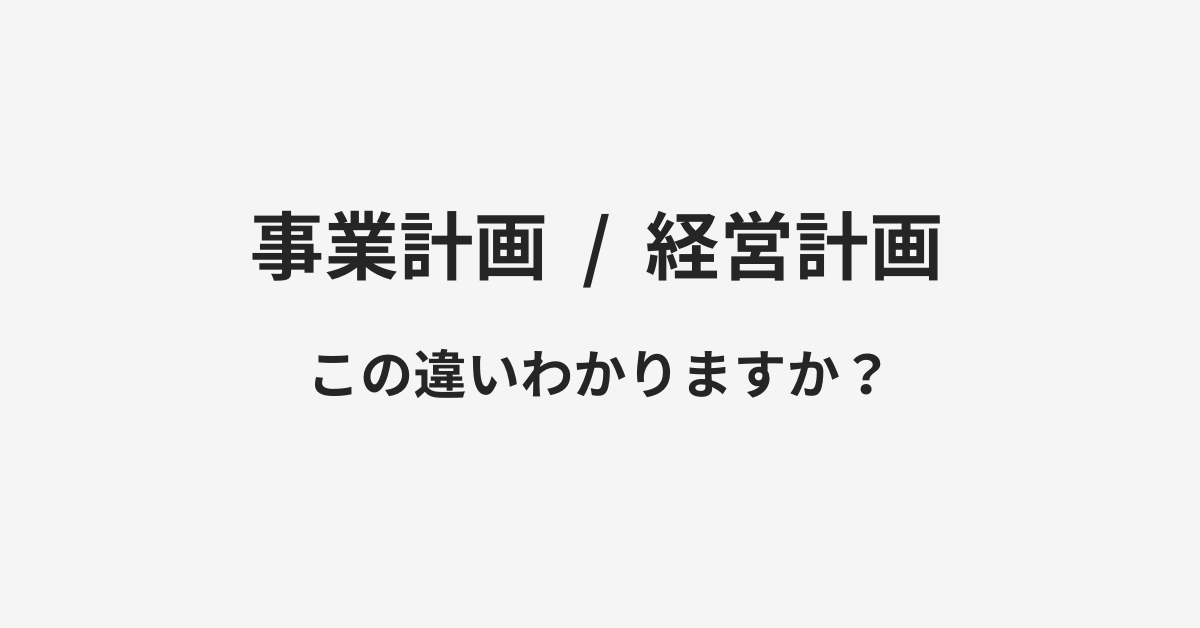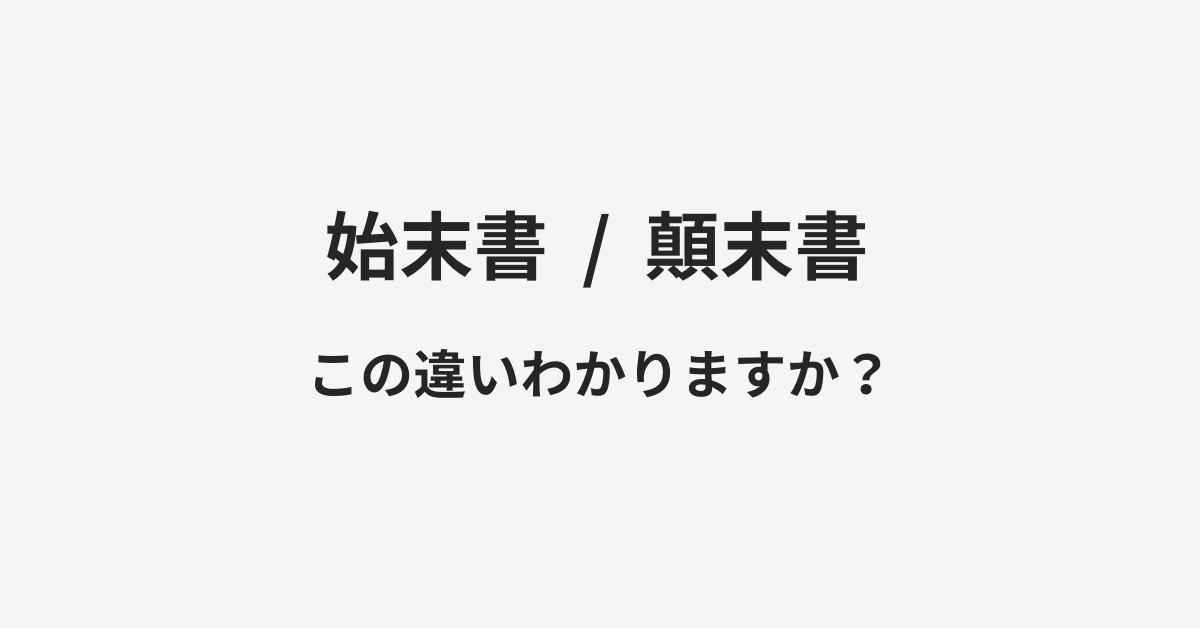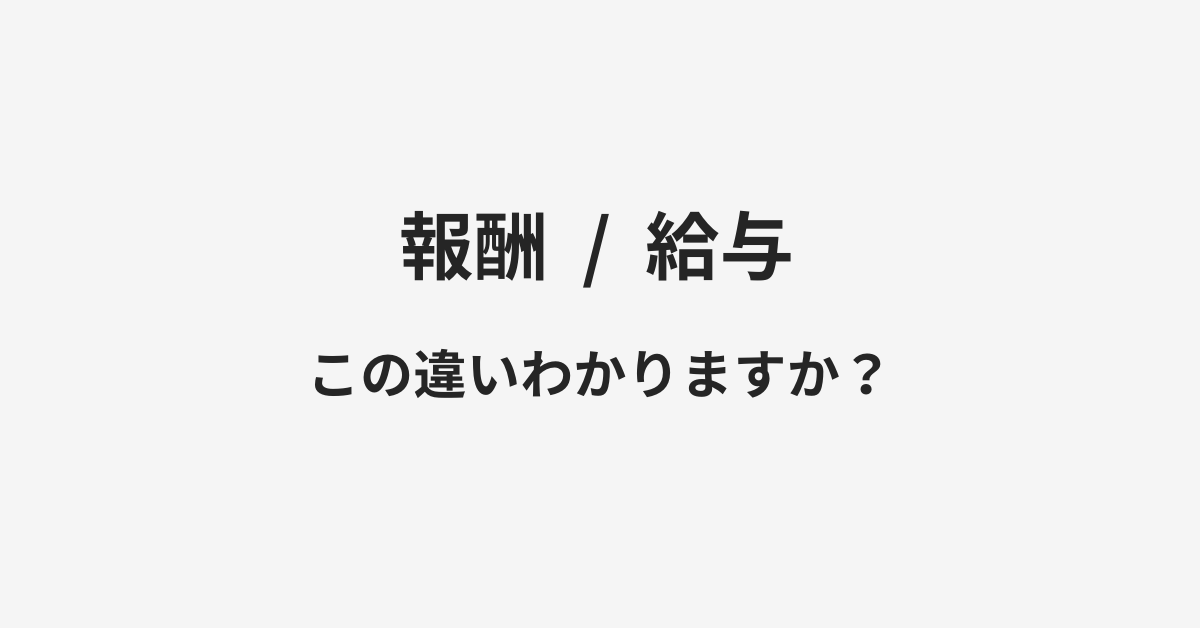【教訓】と【対策】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
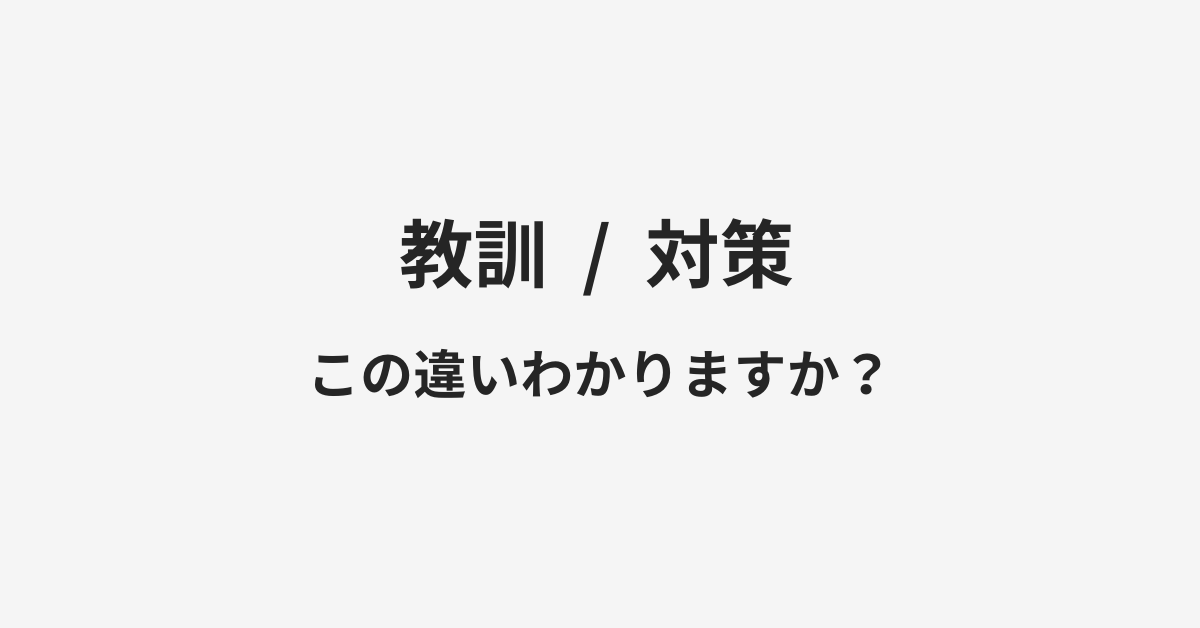
教訓と対策の分かりやすい違い
教訓と対策は、どちらも問題解決に関わる言葉ですが、その性質と使い方が異なります。教訓は、失敗や成功の経験から学んだ大切な教えや戒めのことです。
例えば、準備不足は失敗のもとという学びが教訓です。一方、対策は、問題を解決するための具体的な方法や行動計画です。例えば、事前にチェックリストを作成するという行動が対策です。
つまり、教訓は経験から学んだこと、対策は問題を解決する方法という違いがあります。
教訓とは?
教訓とは、過去の出来事や経験から得られる教えや戒めであり、将来同様の状況に直面した際の指針となる知恵や原則を指します。ビジネスにおいては、プロジェクトの失敗、成功事例、事故、トラブルなどから抽出される学びが教訓となり、組織の知的資産として蓄積されます。
教訓の特徴は、具体的な事象から普遍的な原則を導き出す点にあります。例えば、情報共有不足によるプロジェクト遅延という事象から、ステークホルダー間の定期的なコミュニケーションが不可欠という教訓を得ます。教訓は組織学習の基盤となり、ナレッジマネジメントの重要な要素です。
効果的な教訓の活用には、事例の文書化、定期的な振り返り(レトロスペクティブ)、教訓データベースの構築、研修での共有などが必要です。単なる反省に終わらせず、組織全体の行動変容につなげることが重要です。
教訓の例文
- ( 1 ) 前回のシステム障害から、バックアップ体制の重要性という教訓を得ました。
- ( 2 ) 顧客クレームの分析から、初期対応の迅速性が信頼回復の鍵という教訓が明らかになりました。
- ( 3 ) 失注案件の振り返りで、競合分析の不足という教訓を全営業チームで共有しました。
- ( 4 ) 成功プロジェクトから、アジャイル開発の有効性という教訓を標準化しました。
- ( 5 ) 過去の教訓を活かし、リスク管理体制を抜本的に見直すことにしました。
- ( 6 ) 他社の失敗事例から教訓を学び、同様の過ちを回避する仕組みを構築しました。
教訓の会話例
対策とは?
対策とは、現在または将来予想される問題、課題、リスクに対して、それを解決、軽減、回避するための具体的な方法や行動計画を指します。ビジネスにおいては、品質問題、セキュリティリスク、業績不振、競合対応など、様々な局面で対策の立案と実行が求められます。効果的な対策の要件は、具体性、実行可能性、測定可能性、期限設定、責任者の明確化です。
対策は、応急対策(暫定処置)、恒久対策(根本原因への対処)、予防対策(再発防止)に分類され、状況に応じて使い分けます。PDCAサイクルに基づく対策の実施と効果検証が重要です。
対策立案のプロセスは、問題の特定、原因分析(なぜなぜ分析、特性要因図)、対策案の検討、優先順位付け、実行計画策定、モニタリングという流れで進めます。リスクマネジメントの観点から、事前の予防対策と事後の是正対策の両面からアプローチすることが求められます。
対策の例文
- ( 1 ) 品質問題への対策として、検査工程を2段階に増やすことを決定しました。
- ( 2 ) 情報漏えい対策として、全社員に暗号化ソフトの使用を義務付けました。
- ( 3 ) 売上減少への対策として、新規顧客開拓と既存顧客の深耕を並行して進めます。
- ( 4 ) サイバー攻撃対策として、24時間監視体制とインシデント対応チームを設置しました。
- ( 5 ) 人材流出対策として、キャリアパス明確化と処遇改善を実施します。
- ( 6 ) コロナ対策として策定したBCPが、他の災害時にも有効であることが実証されました。
対策の会話例
教訓と対策の違いまとめ
教訓と対策の違いを理解することは、組織の問題解決能力向上に不可欠です。教訓は抽象的な学び、対策は具体的な行動という基本的な違いを押さえた上で、両者を連携させることが重要です。実務では、過去の教訓を活かして効果的な対策を立案し、対策の実施結果から新たな教訓を得るという循環的なプロセスが理想的です。
教訓なき対策は場当たり的になりやすく、対策なき教訓は机上の空論に終わります。また、教訓は組織の文化や価値観に影響を与える長期的な資産であり、対策は即効性のある問題解決手段という時間軸の違いもあります。
両者をバランスよく活用することで、組織の持続的な改善が実現できます。
教訓と対策の読み方
- 教訓(ひらがな):きょうくん
- 教訓(ローマ字):kyoukunn
- 対策(ひらがな):たいさく
- 対策(ローマ字):taisaku