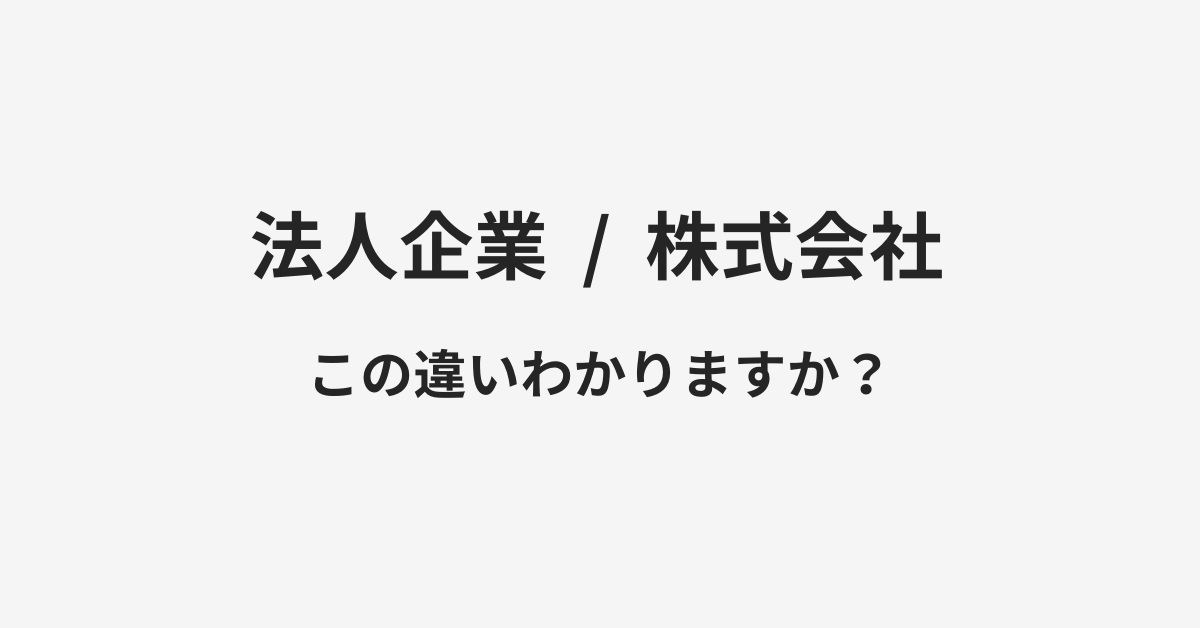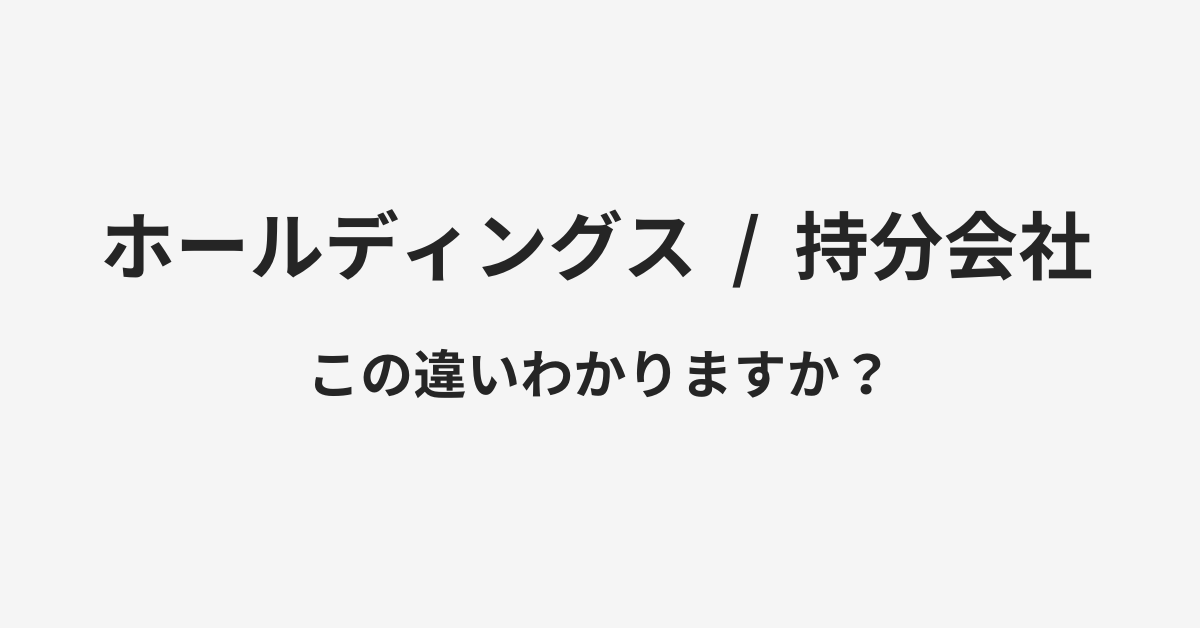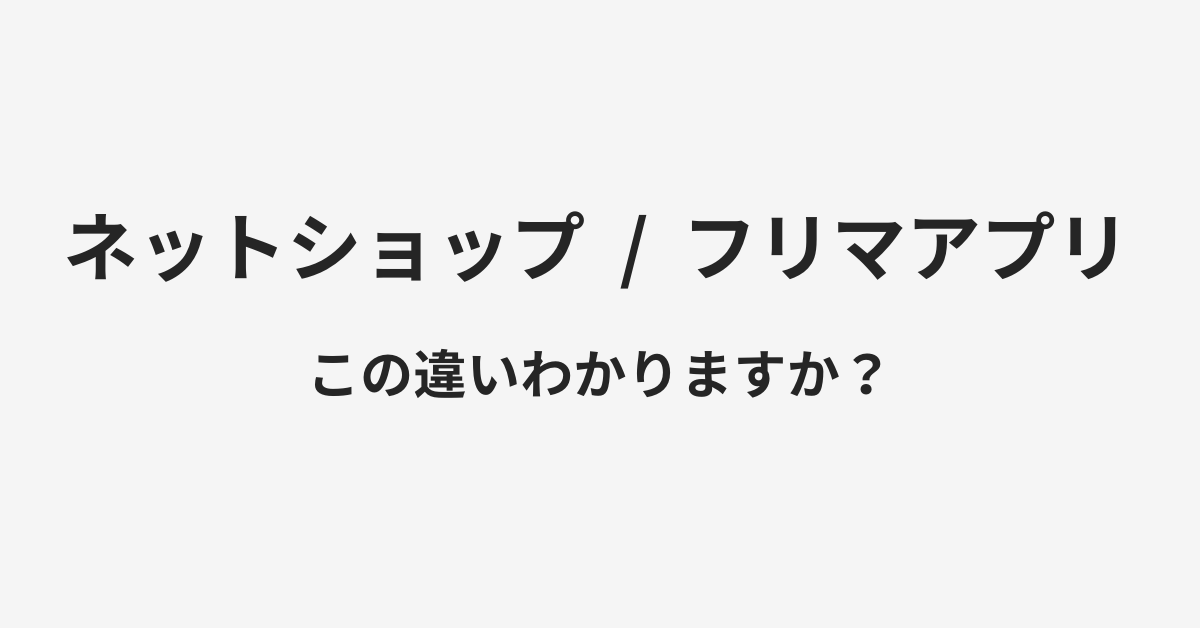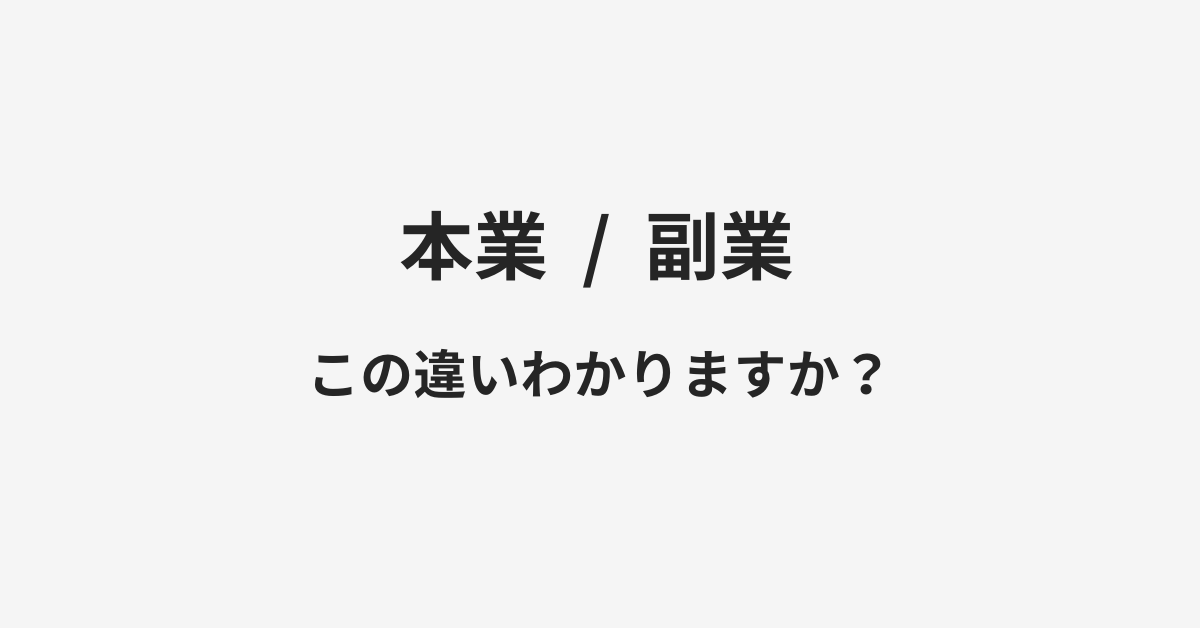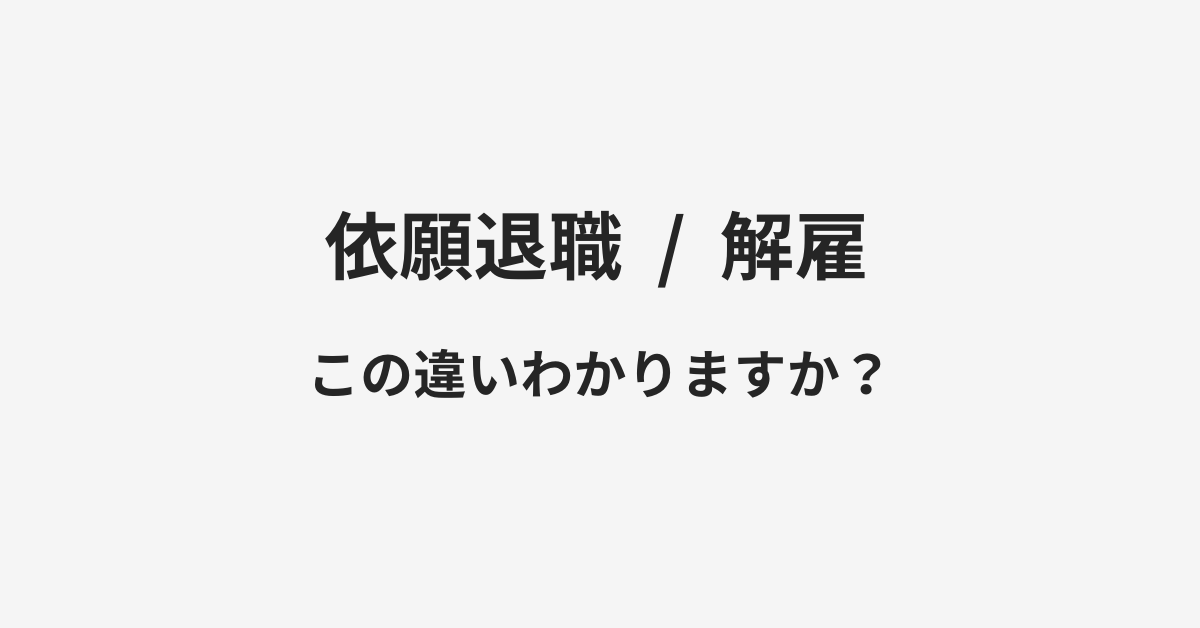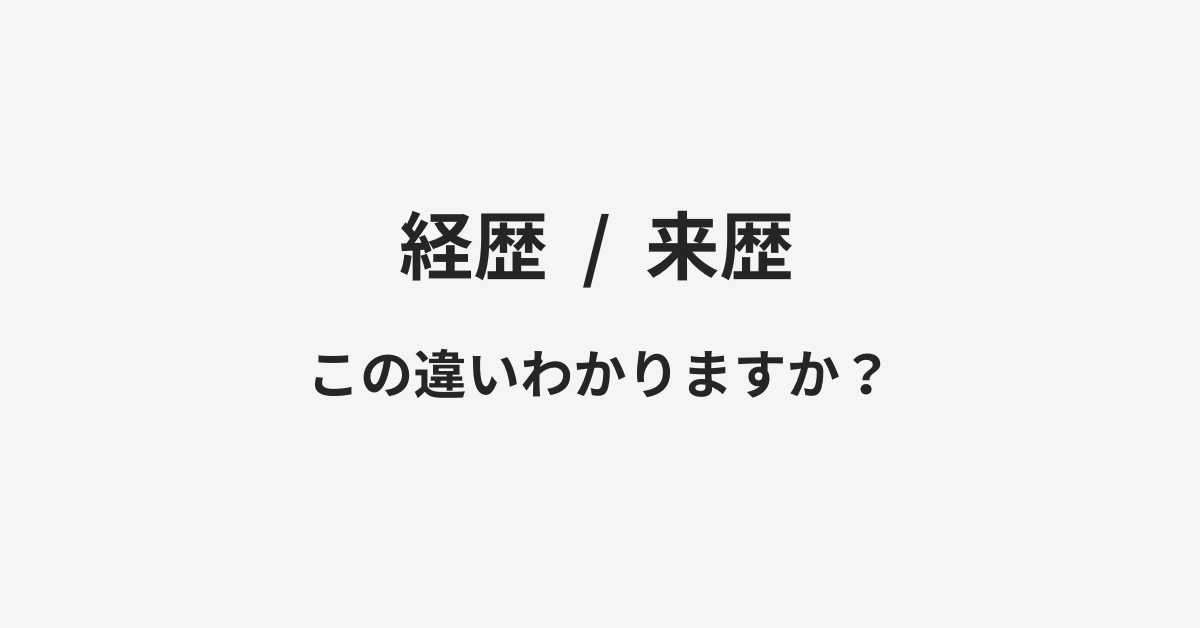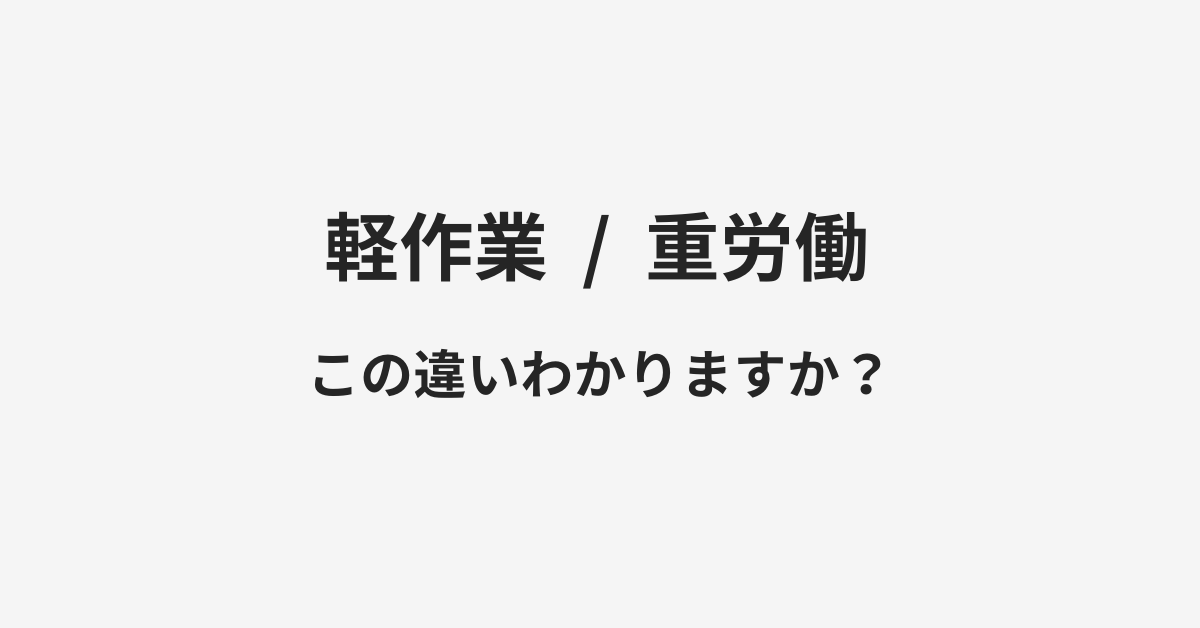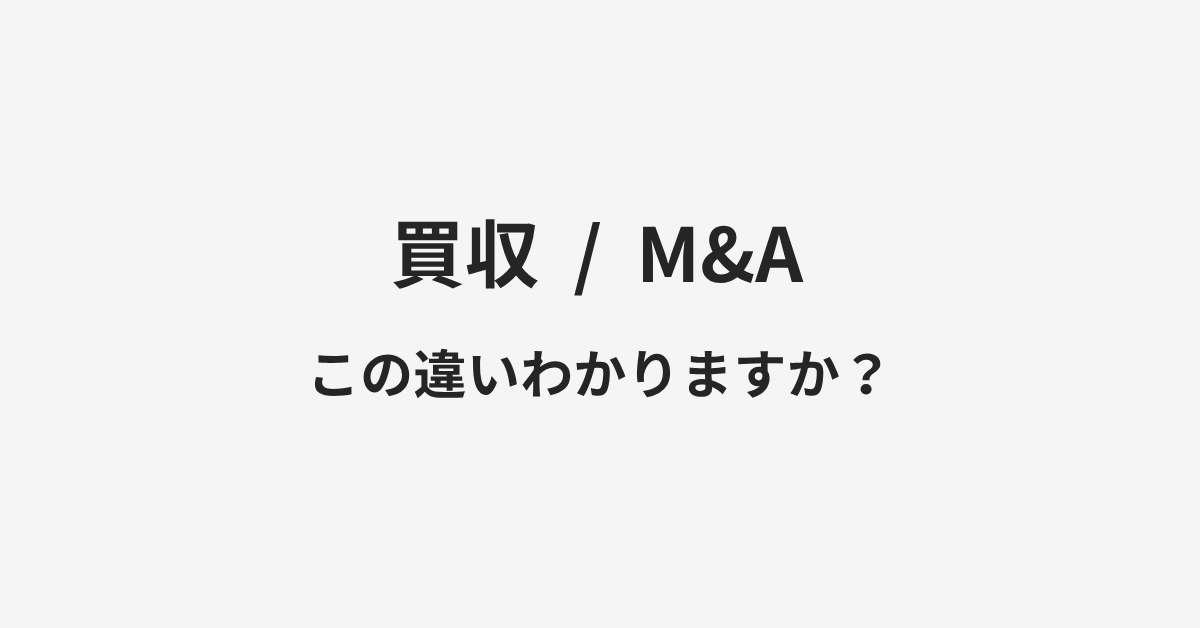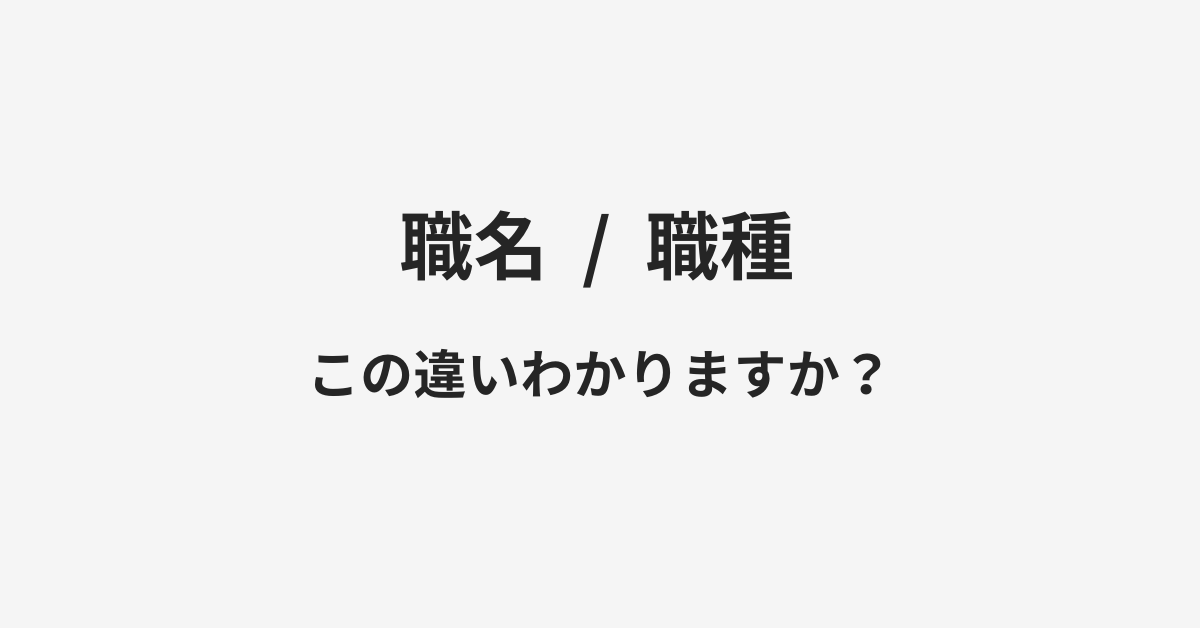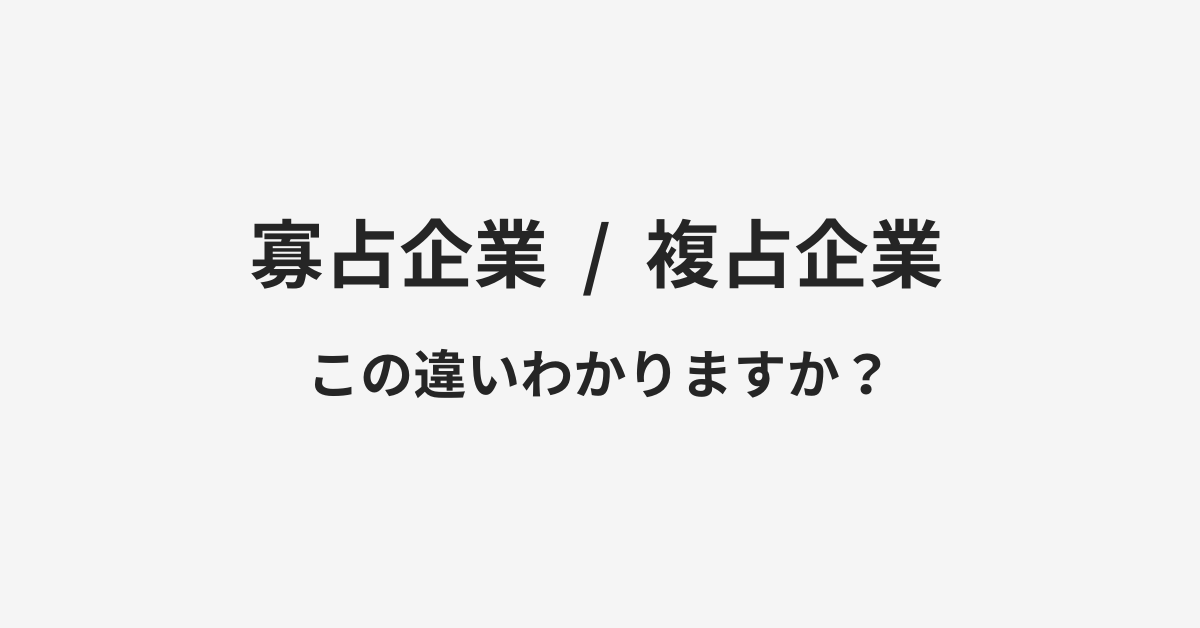【ジョイントベンチャー】と【業務提携】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
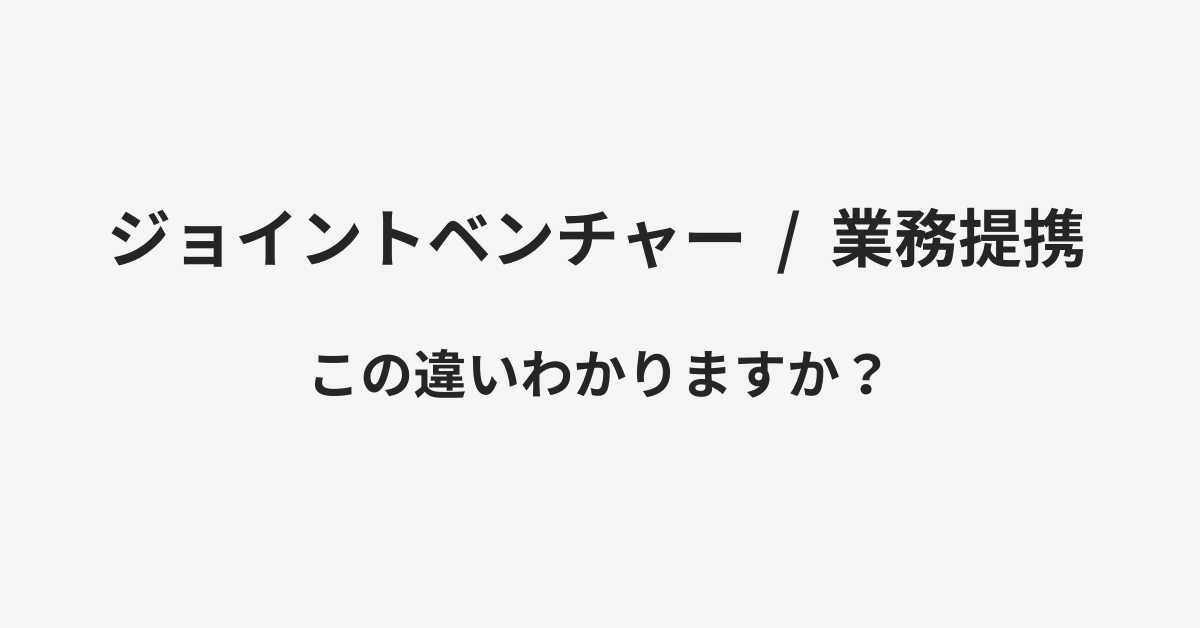
- ビジネス
- # ジョイントベンチャー
- # 業務提携
- 言葉の違い
ジョイントベンチャーと業務提携の分かりやすい違い
ジョイントベンチャーと業務提携は、どちらも企業間の協力関係ですが、組織形態が異なります。
ジョイントベンチャーは共同出資による新会社設立を伴う深い統合です。
業務提携は独立性を保ちながら特定分野で協力する、より緩やかな関係です。
ジョイントベンチャーとは?
ジョイントベンチャー(JV)とは、複数の企業が共同出資して新たな事業体(合弁会社)を設立する事業形態です。出資比率に応じて経営権や利益配分が決まり、リスクと成果を共有します。異なる強みを持つ企業が資本・技術・人材を持ち寄ることで、単独では困難な事業展開が可能になります。
海外進出時に現地企業とJVを組むケースが多く、現地の規制対応や市場知識を活用できます。ただし、意思決定に時間がかかる、企業文化の違いによる摩擦、撤退時の複雑さなどのデメリットもあります。
JVを設立する、50:50のジョイントベンチャーのように、共同出資による新会社設立を表現する際に使用される言葉です。
ジョイントベンチャーの例文
- ( 1 ) 大手自動車メーカーとIT企業がジョイントベンチャーを設立し、自動運転技術を開発する。
- ( 2 ) 海外市場進出のため、現地企業と50:50のジョイントベンチャーを組んだ。
- ( 3 ) ジョイントベンチャーの経営方針について、出資企業間で協議を重ねている。
- ( 4 ) JV設立により、両社の技術とノウハウを融合した新サービスが誕生した。
- ( 5 ) ジョイントベンチャーの解消には、複雑な手続きと時間を要する。
- ( 6 ) 政府規制により、外資100%が認められない国ではJVが有効な選択肢となる。
ジョイントベンチャーの会話例
業務提携とは?
業務提携とは、独立した企業同士が、資本関係を持たずに特定の事業分野で協力する契約関係です。技術提携、販売提携、生産提携、共同開発など様々な形態があり、各社の強みを活かした相互補完的な関係を構築します。
契約書により提携内容や期間を定めます。業務提携は比較的柔軟で、必要に応じて提携内容を変更したり解消したりすることが容易です。独立性を保ちながら協力できるため、リスクを抑えつつシナジー効果を追求できます。
一方、拘束力が弱く、機密情報の管理にも注意が必要です。業務提携を締結する、包括的業務提携のように、企業間の協力契約を表現する際に使用される言葉です。
業務提携の例文
- ( 1 ) 物流会社と業務提携を結び、配送コストの削減を実現した。
- ( 2 ) AI技術に関する業務提携により、両社の開発スピードが向上した。
- ( 3 ) 販売チャネルの相互利用を目的とした業務提携契約を締結した。
- ( 4 ) 業務提携先との定期的な情報交換会を実施している。
- ( 5 ) 競合他社との業務提携は、独占禁止法に抵触しないよう注意が必要だ。
- ( 6 ) 業務提携を足がかりに、将来的な資本提携も視野に入れている。
業務提携の会話例
ジョイントベンチャーと業務提携の違いまとめ
ジョイントベンチャーと業務提携は、企業間協力の深さと形態に大きな違いがあります。ジョイントベンチャーは資本を伴う深い統合で、新会社設立によりリスクと利益を共有します。
業務提携は独立性を保った協力関係で、契約に基づく柔軟な協業が可能です。
事業の性質や目的に応じて、適切な協力形態を選択することが重要です。
ジョイントベンチャーと業務提携の読み方
- ジョイントベンチャー(ひらがな):じょいんとべんちゃー
- ジョイントベンチャー(ローマ字):joinntobenncha-
- 業務提携(ひらがな):ぎょうむていけい
- 業務提携(ローマ字):gyoumuteikei