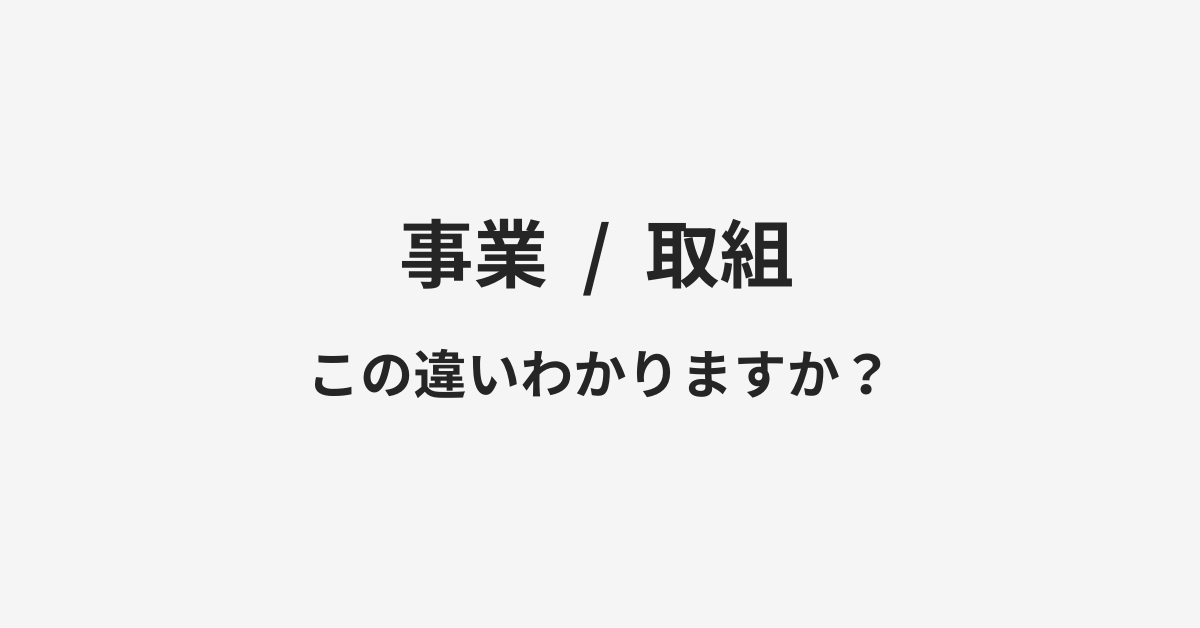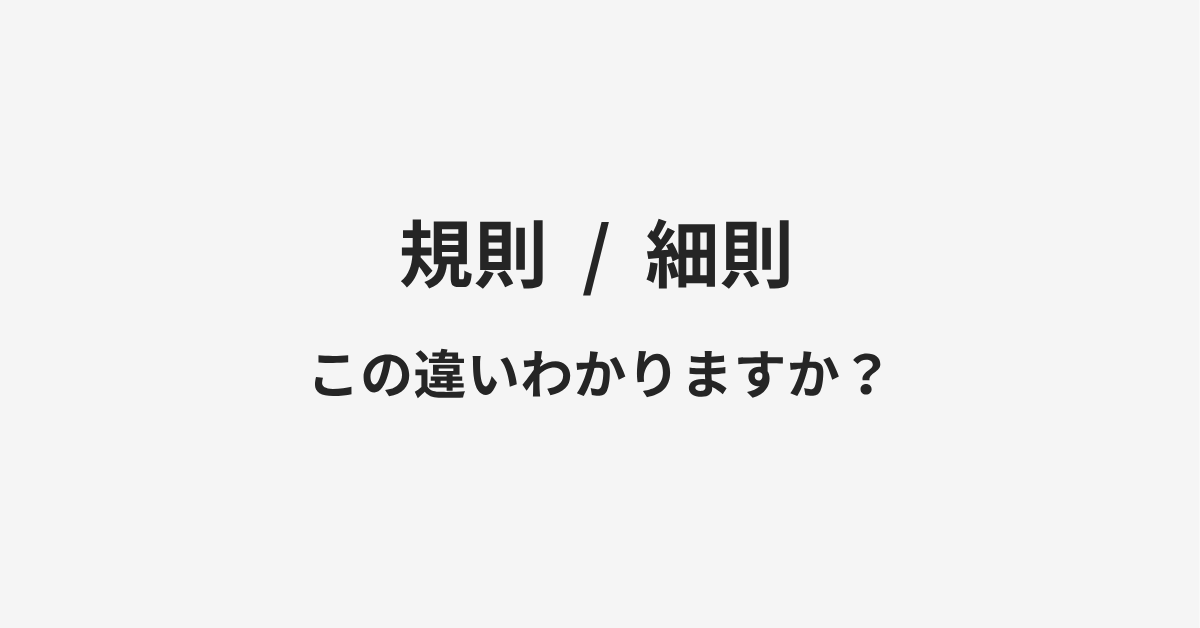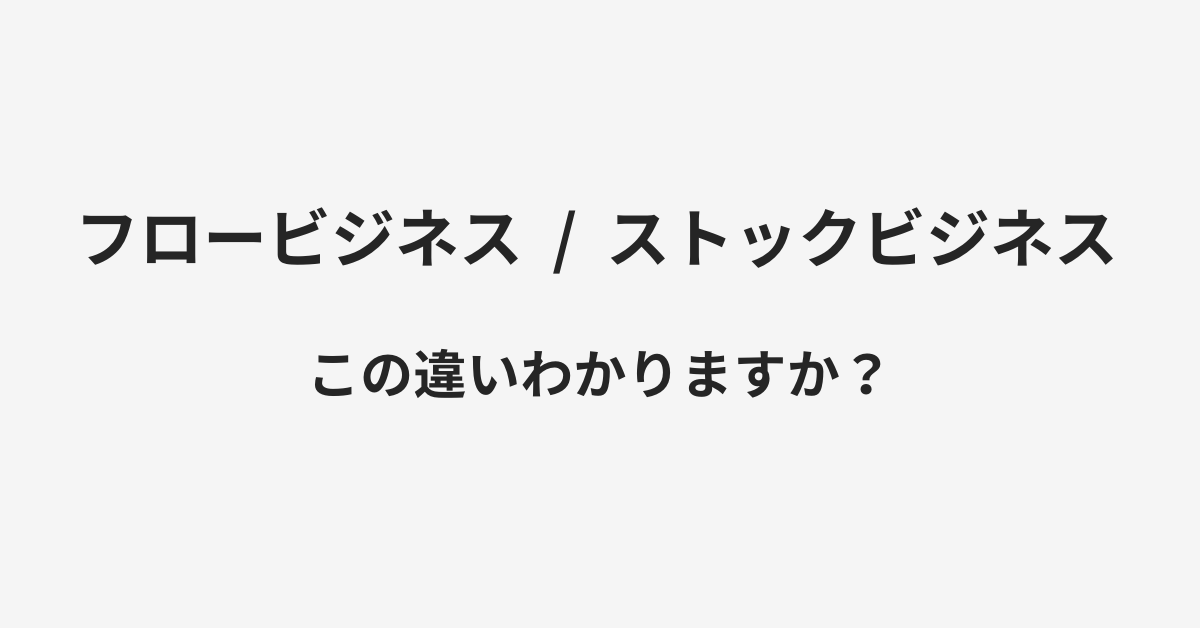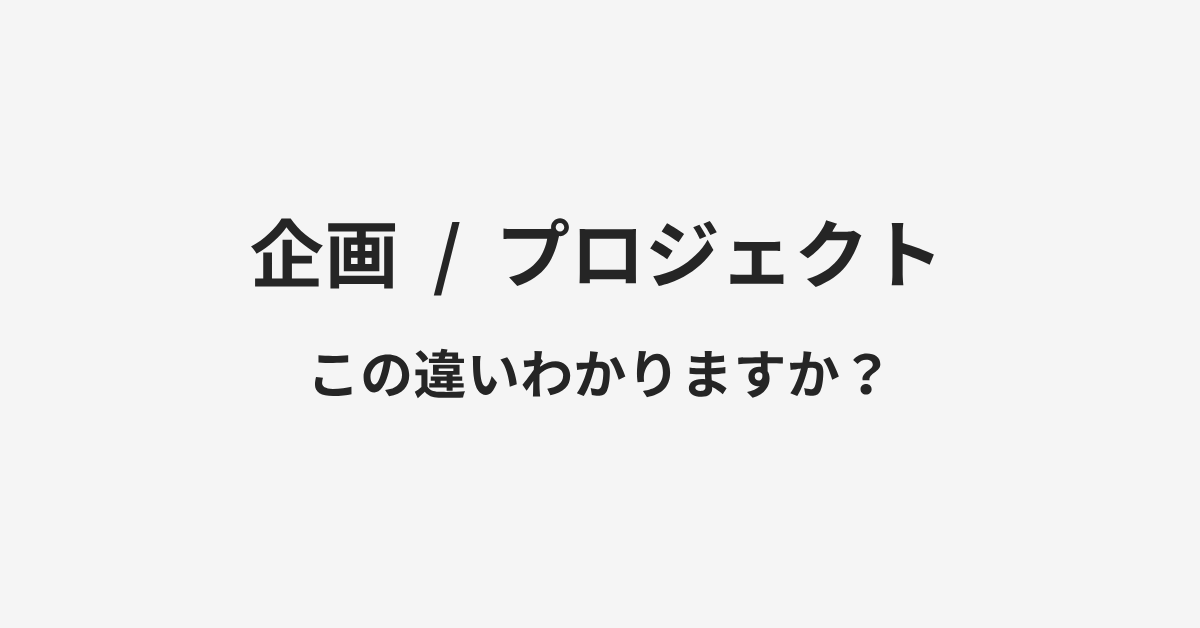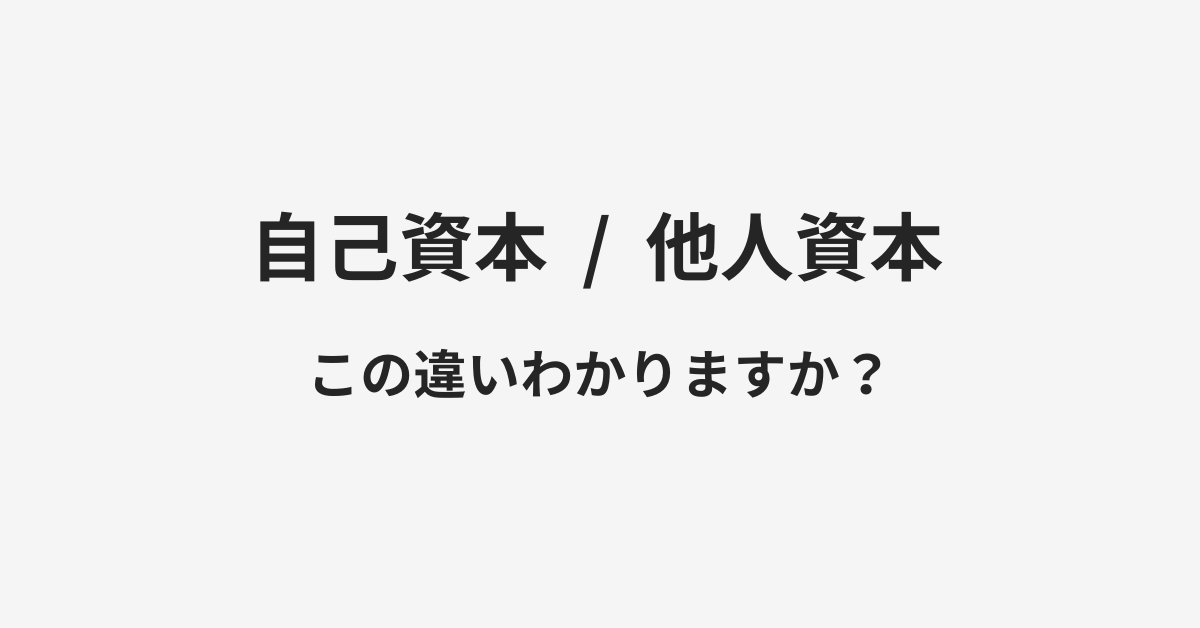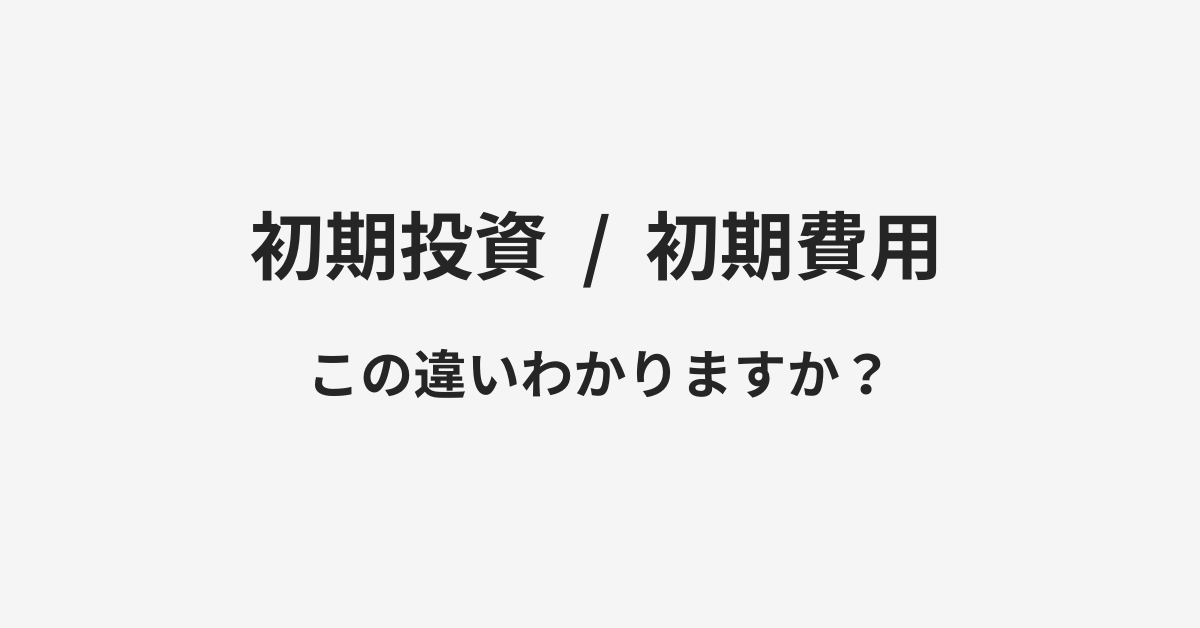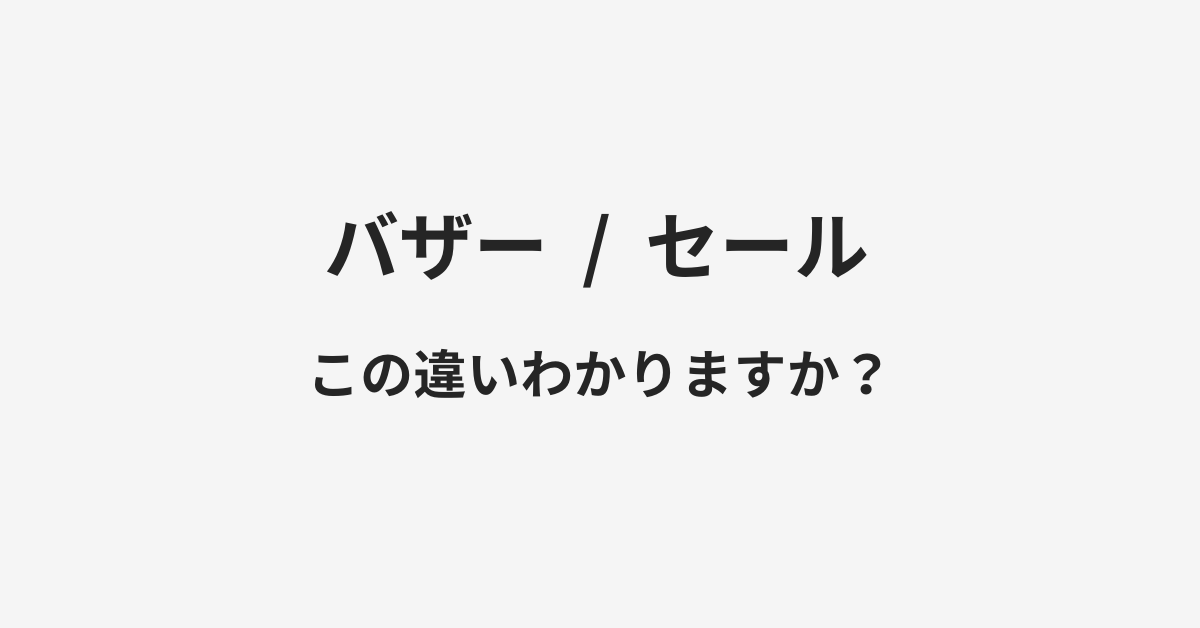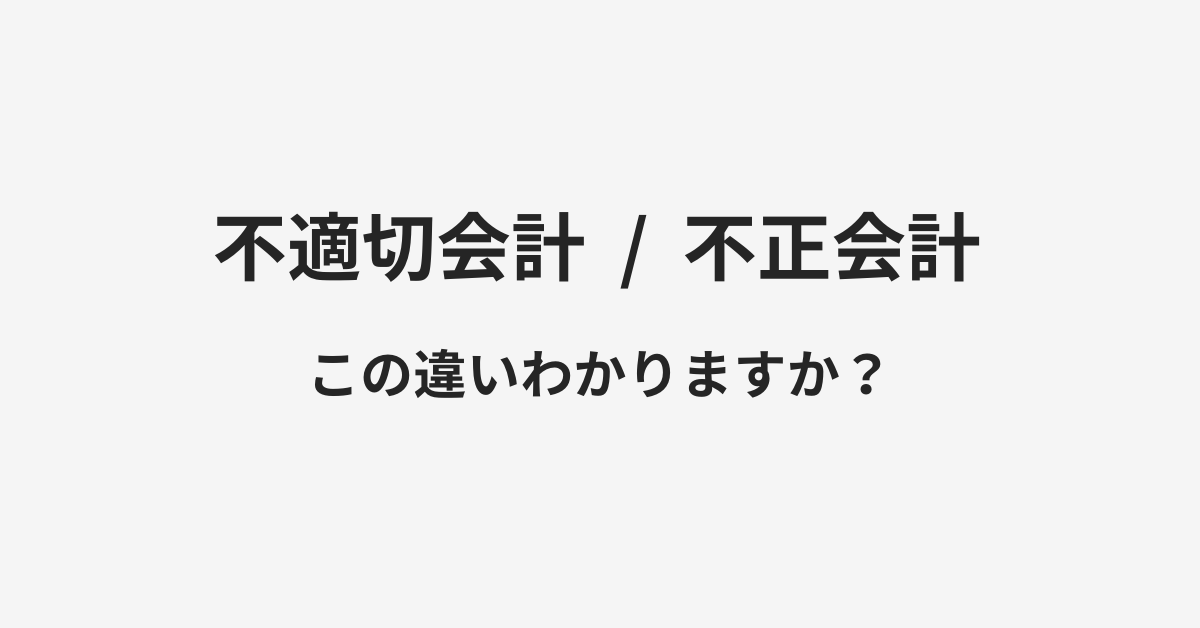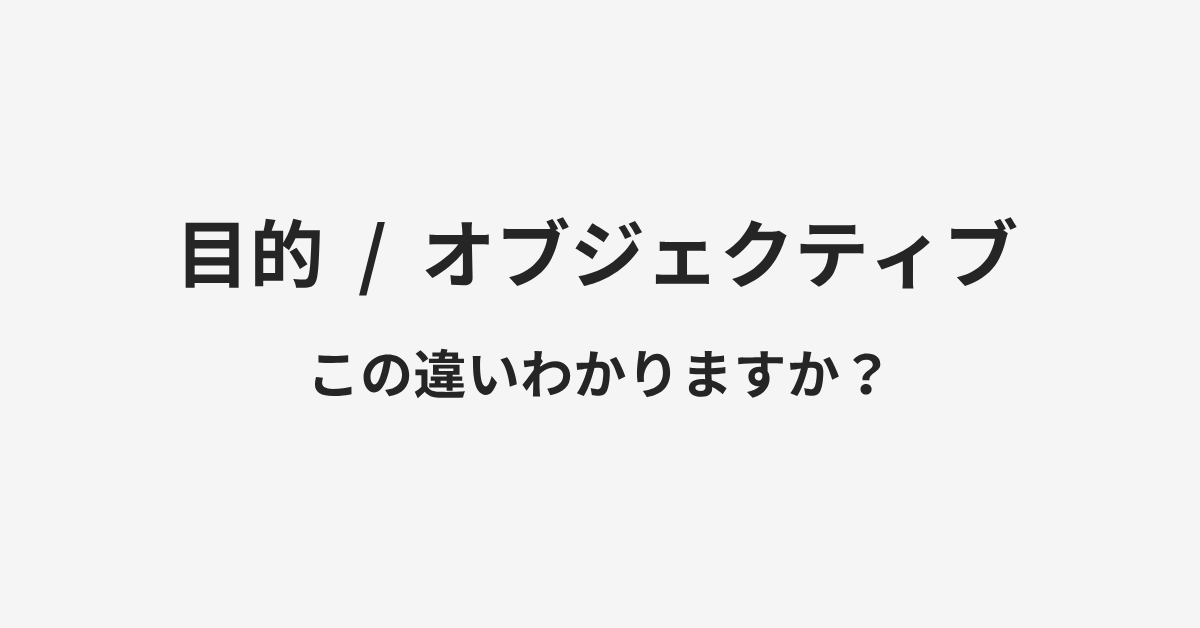【事業資金】と【運転資金】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
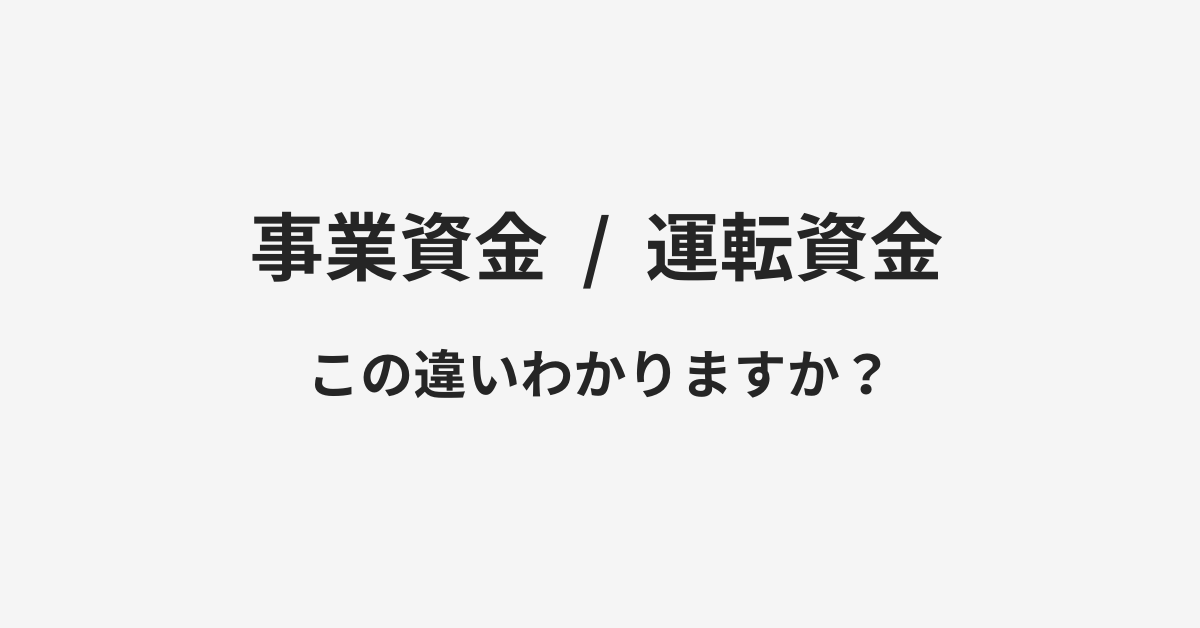
事業資金と運転資金の分かりやすい違い
事業資金と運転資金は、どちらも企業経営に必要な資金ですが、その範囲と用途に大きな違いがあります。事業資金は設備投資や運転資金を含む事業全体に必要な資金の総称で、運転資金は仕入れや人件費など日常業務に必要な資金です。
前者は包括的、後者は日常的という性質の違いがあります。
資金調達や財務管理において、この違いを理解することは、適切な資金計画と健全な経営の実現に不可欠です。
事業資金とは?
事業資金とは、企業が事業を開始・継続・拡大するために必要な資金の総称で、設備資金と運転資金の両方を含む包括的な概念です。開業時の初期投資、設備購入、店舗改装、事業拡大投資、日常的な営業活動費用など、事業に関わるあらゆる資金需要を指します。創業資金、設備投資資金、運転資金、つなぎ資金などが含まれます。
事業資金の調達方法は、自己資金、金融機関融資、公的融資(日本政策金融公庫など)、補助金・助成金、投資家からの出資、クラウドファンディングなど多岐にわたります。必要額は事業規模や業種により大きく異なり、製造業では設備資金の比重が高く、サービス業では運転資金の比重が高い傾向があります。
適切な事業資金計画は、企業の成長と安定に不可欠です。過少な資金は成長機会の喪失、過大な資金は金利負担増加につながるため、事業計画に基づいた適正な資金調達が重要です。
事業資金の例文
- ( 1 ) 新規事業立ち上げのため、事業資金3000万円の調達を計画しています。
- ( 2 ) 事業資金の内訳は、設備資金2000万円、運転資金1000万円です。
- ( 3 ) 日本政策金融公庫から事業資金の融資を受けることができました。
- ( 4 ) 事業資金計画書を作成し、銀行との融資交渉に臨みます。
- ( 5 ) クラウドファンディングで事業資金の一部を調達しました。
- ( 6 ) 事業資金の返済計画を綿密に立て、キャッシュフローを管理しています。
事業資金の会話例
運転資金とは?
運転資金とは、企業が日常的な事業活動を行うために必要な短期的な資金で、仕入代金、人件費、家賃、光熱費などの経常的な支出に充てられます。売上代金回収までの期間と仕入代金支払いまでの期間の差(キャッシュコンバージョンサイクル)により必要額が決まります。一般的に売上債権+棚卸資産-仕入債務で算出されます。
運転資金の特徴は、継続的に必要で、事業規模に比例して増減することです。季節変動がある業種では、繁忙期に運転資金需要が増大します。不足すると仕入れができない、給与が払えないなど、黒字倒産のリスクもあります。そのため、月商の3〜6か月分の運転資金確保が推奨されます。
運転資金の調達は、短期借入金、当座貸越、手形割引、ファクタリングなどの短期資金調達が一般的です。回転率の向上、在庫圧縮、回収サイト短縮、支払サイト延長などにより、必要運転資金を削減することも重要な経営課題です。
運転資金の例文
- ( 1 ) 売上増加に伴い、運転資金の需要が高まっています。
- ( 2 ) 運転資金不足により、仕入れ代金の支払いに苦慮しています。
- ( 3 ) 銀行から運転資金として500万円の当座貸越枠を設定してもらいました。
- ( 4 ) 運転資金の回転率を改善し、資金効率を高めています。
- ( 5 ) 季節変動に備えて、十分な運転資金を確保しています。
- ( 6 ) ファクタリングを活用して、運転資金を調達しました。
運転資金の会話例
事業資金と運転資金の違いまとめ
事業資金と運転資金の最大の違いは、包含関係と用途です。事業資金は運転資金を含む上位概念で、運転資金は事業資金の一部です。設備投資は事業資金には含まれますが、運転資金には含まれません。
資金の性質も異なり、事業資金は長期・短期両方の資金需要を含みますが、運転資金は主に短期的な資金需要です。返済期間も、設備資金部分は長期、運転資金部分は短期という違いがあります。資金調達の際は、用途に応じた適切な調達方法を選択することが重要です。
設備投資なら長期借入、運転資金なら短期借入や当座貸越というように、資金の性質に合わせた調達が財務の健全性につながります。
事業資金と運転資金の読み方
- 事業資金(ひらがな):じぎょうしきん
- 事業資金(ローマ字):jigyoushikinn
- 運転資金(ひらがな):うんてんしきん
- 運転資金(ローマ字):unntennshikinn