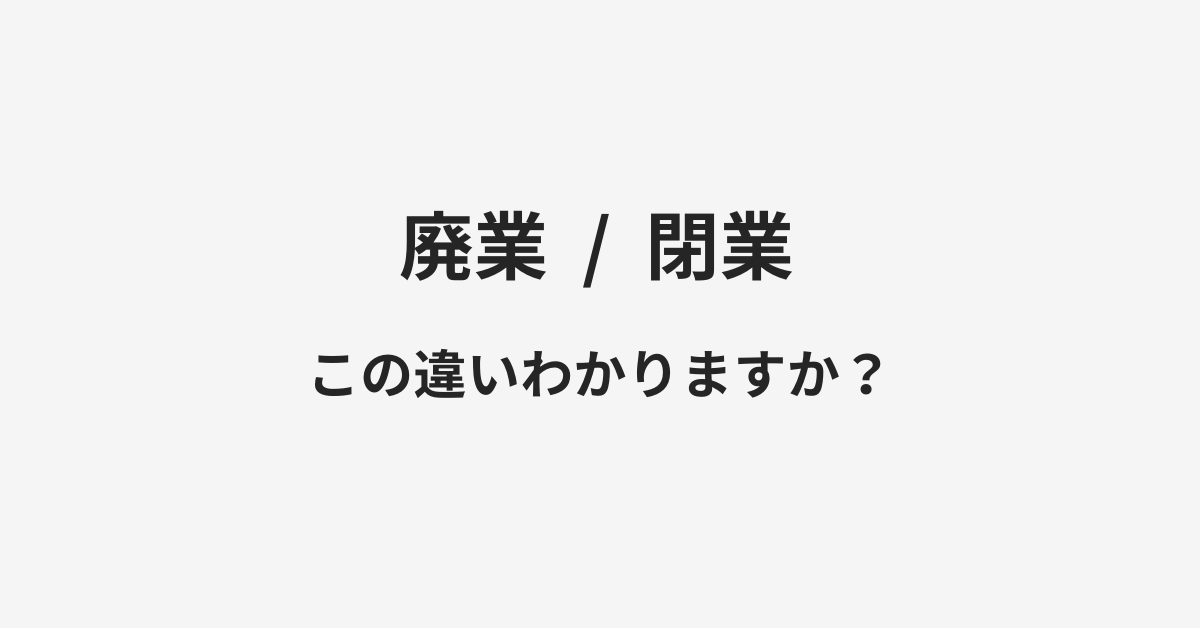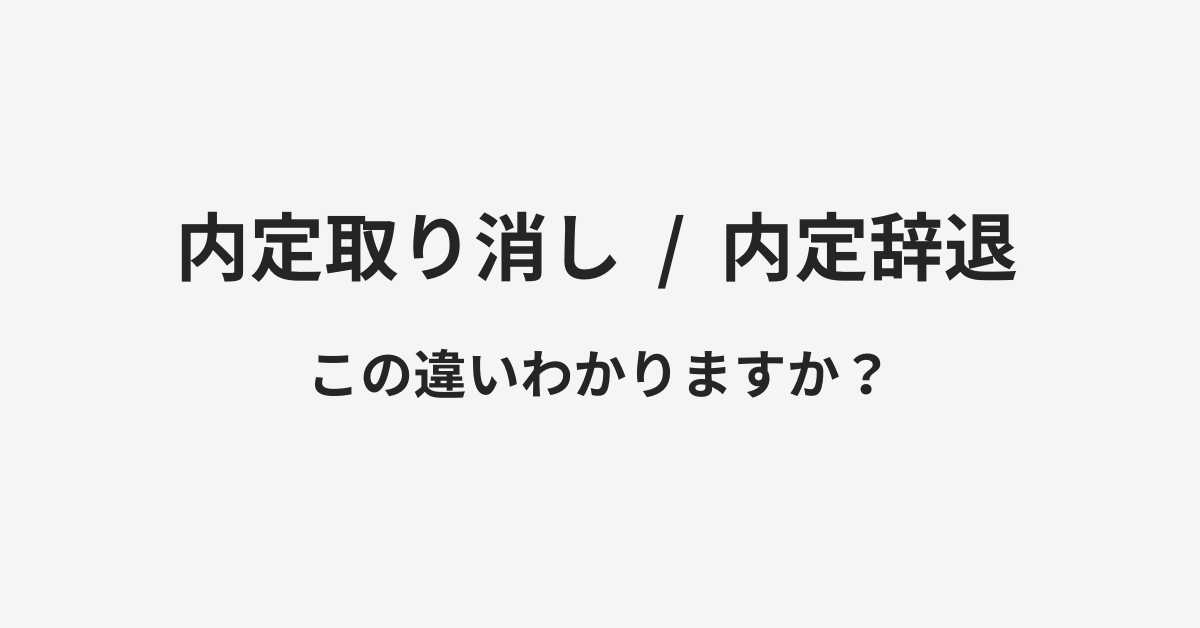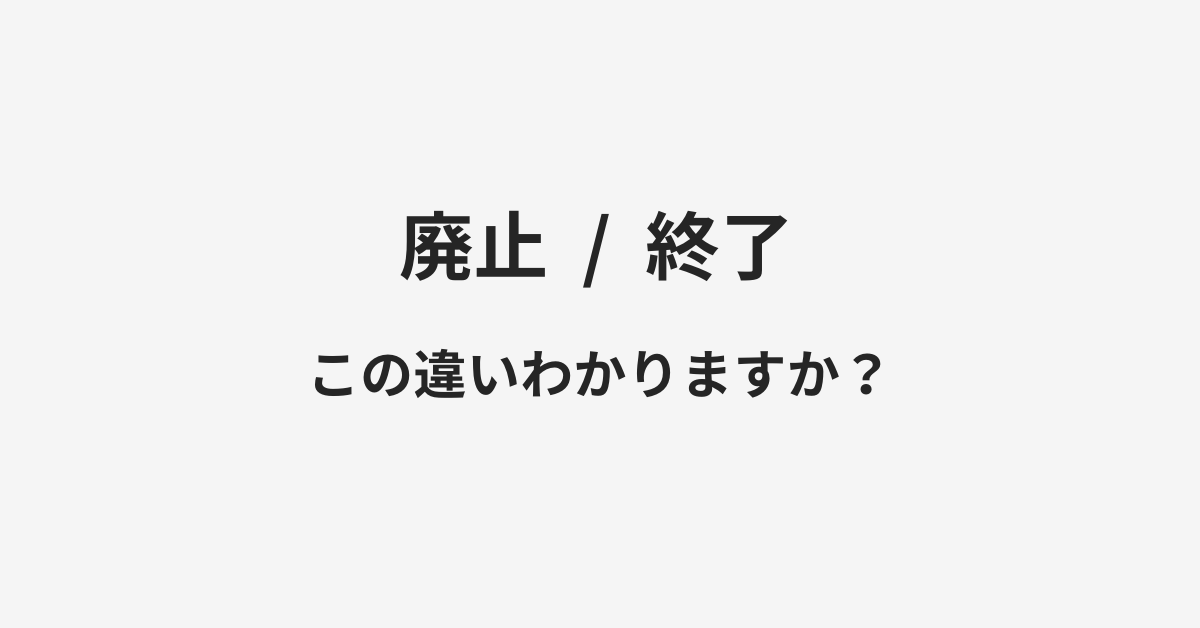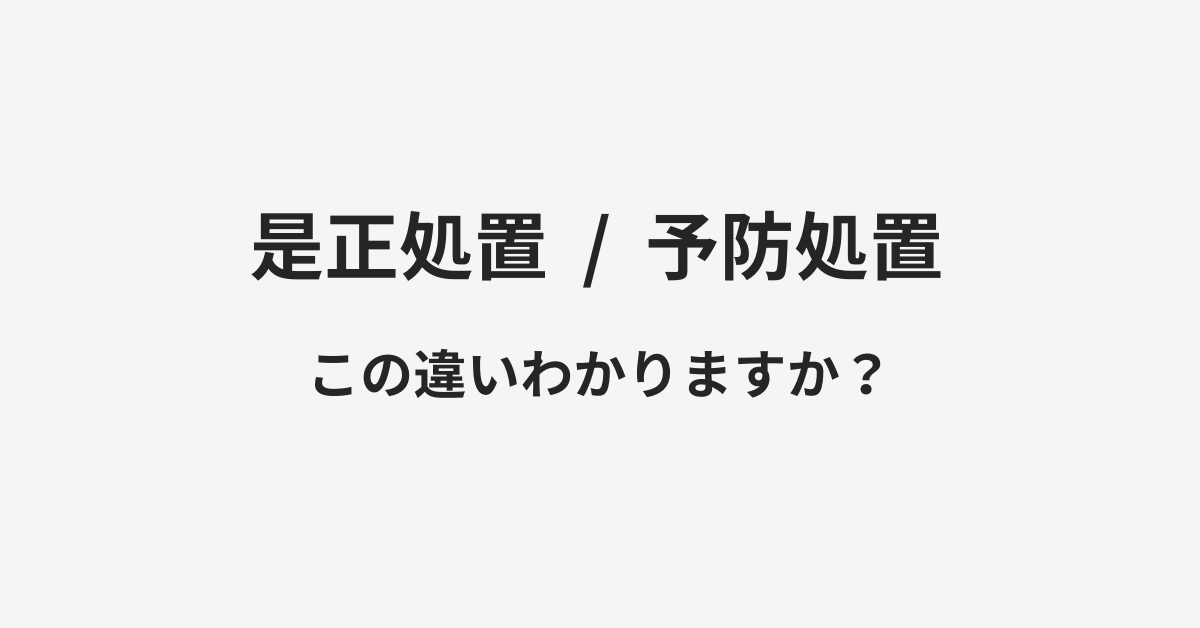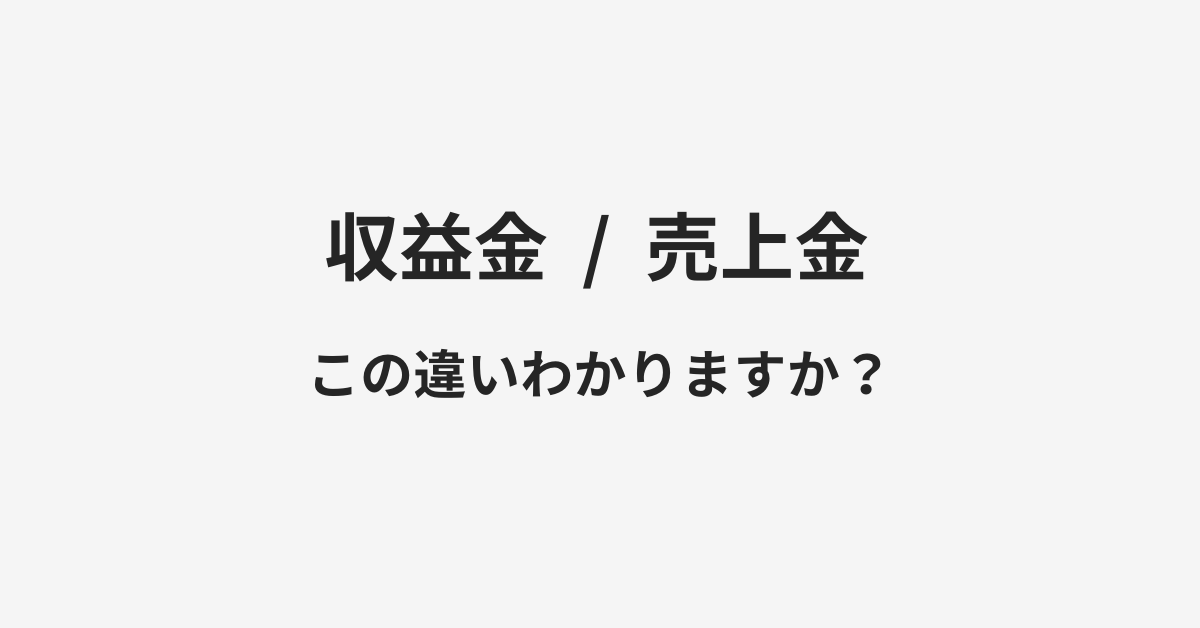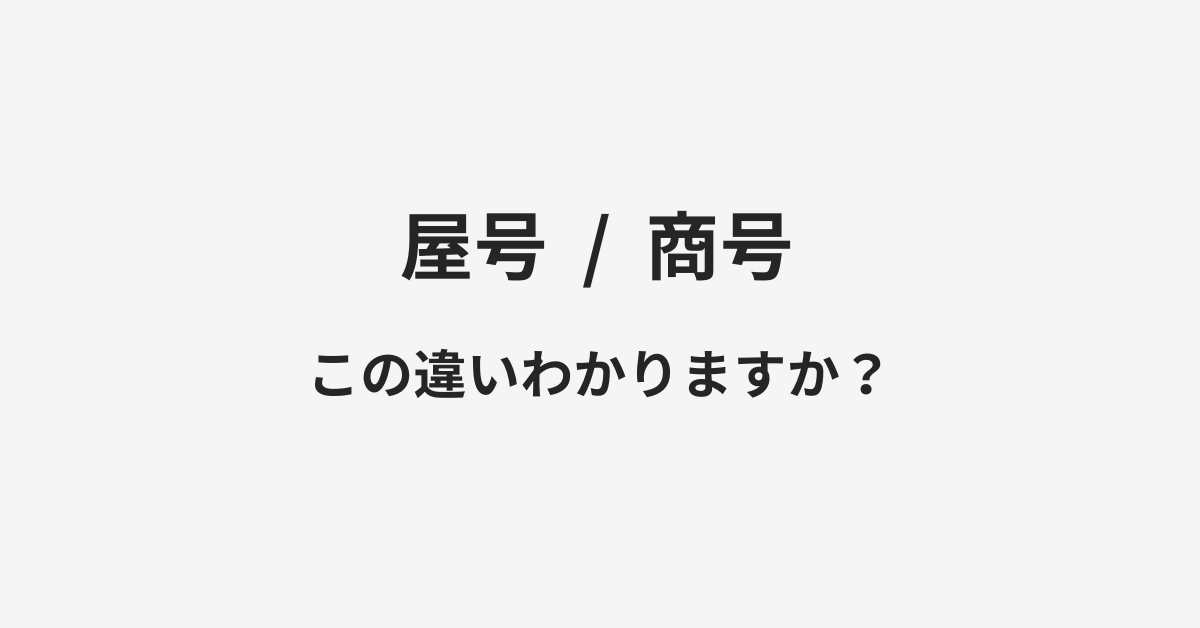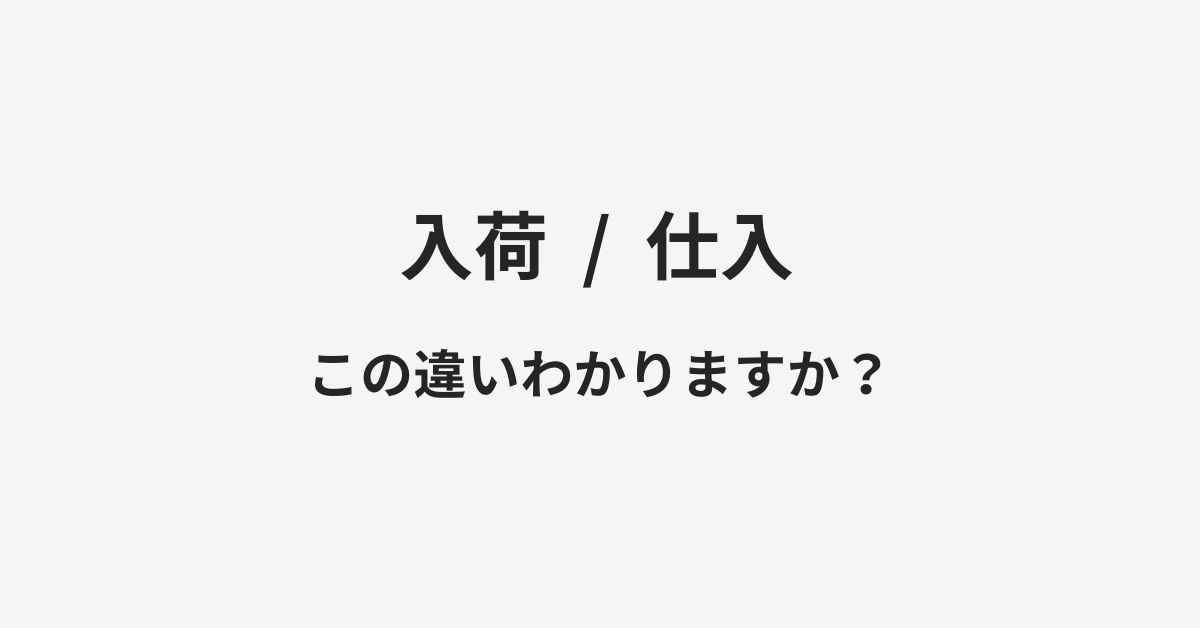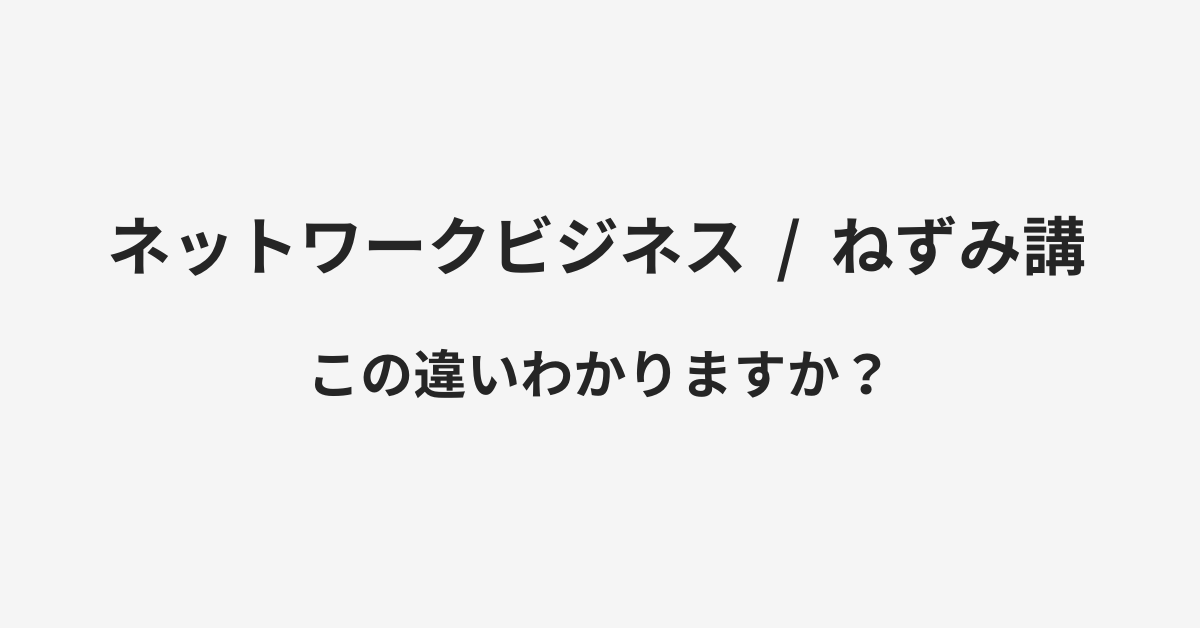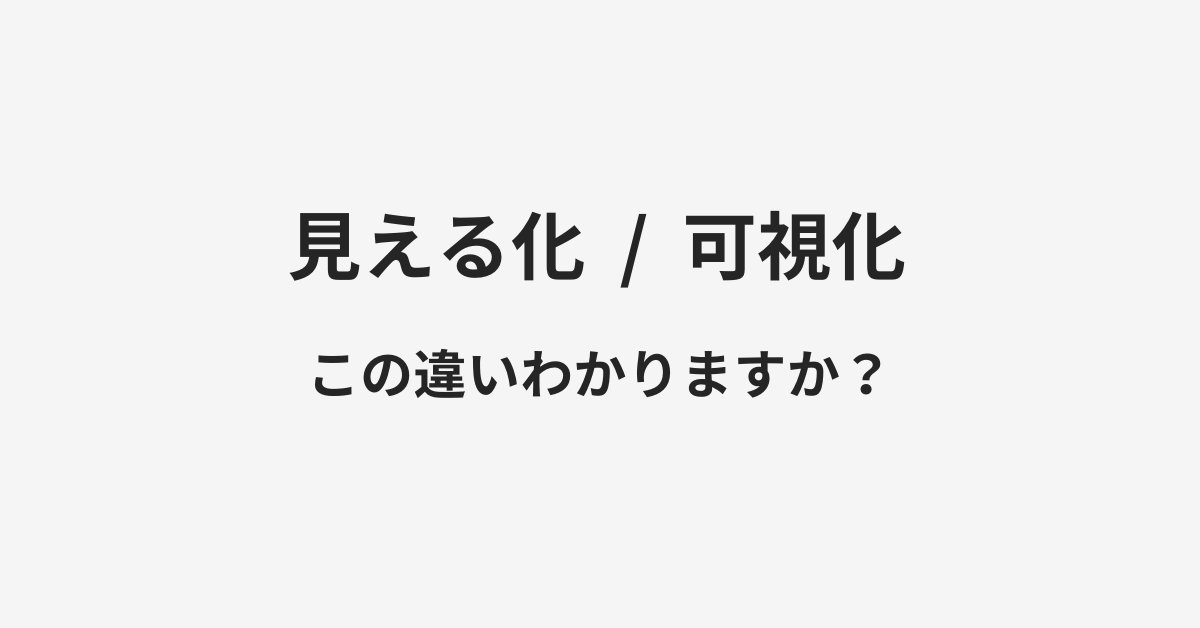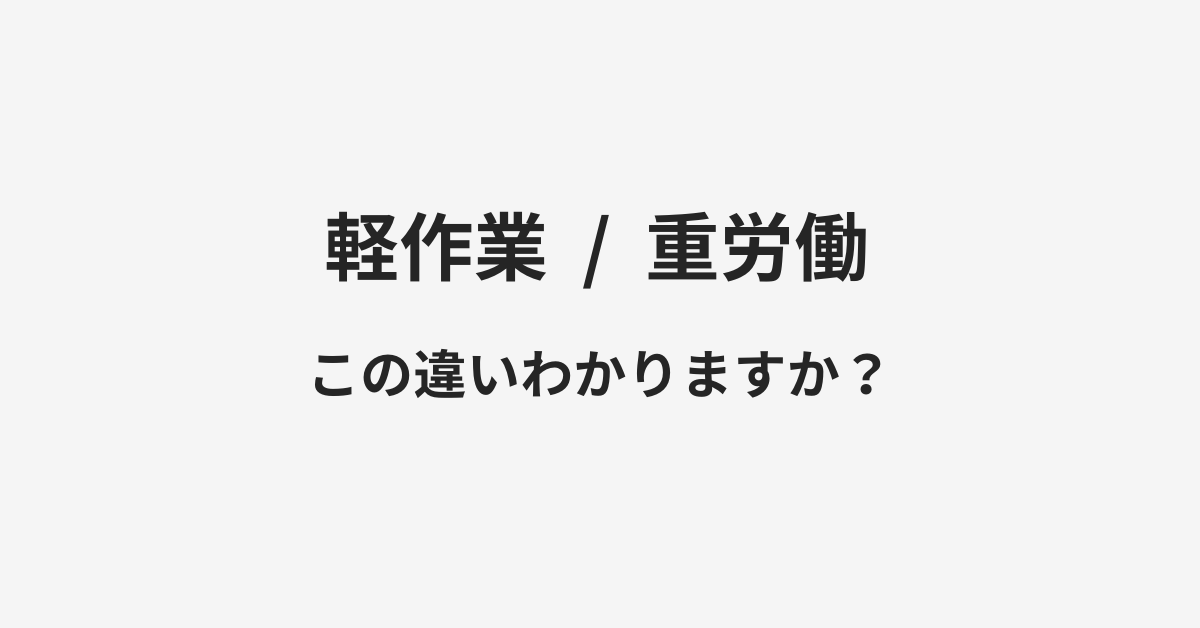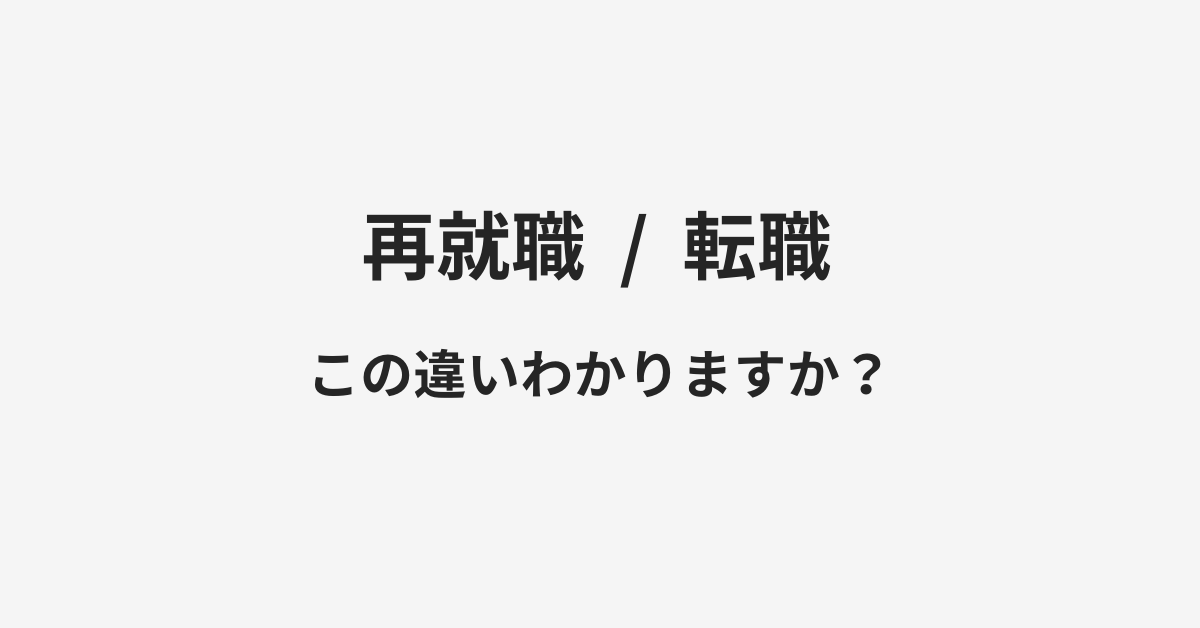【廃業】と【破産】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
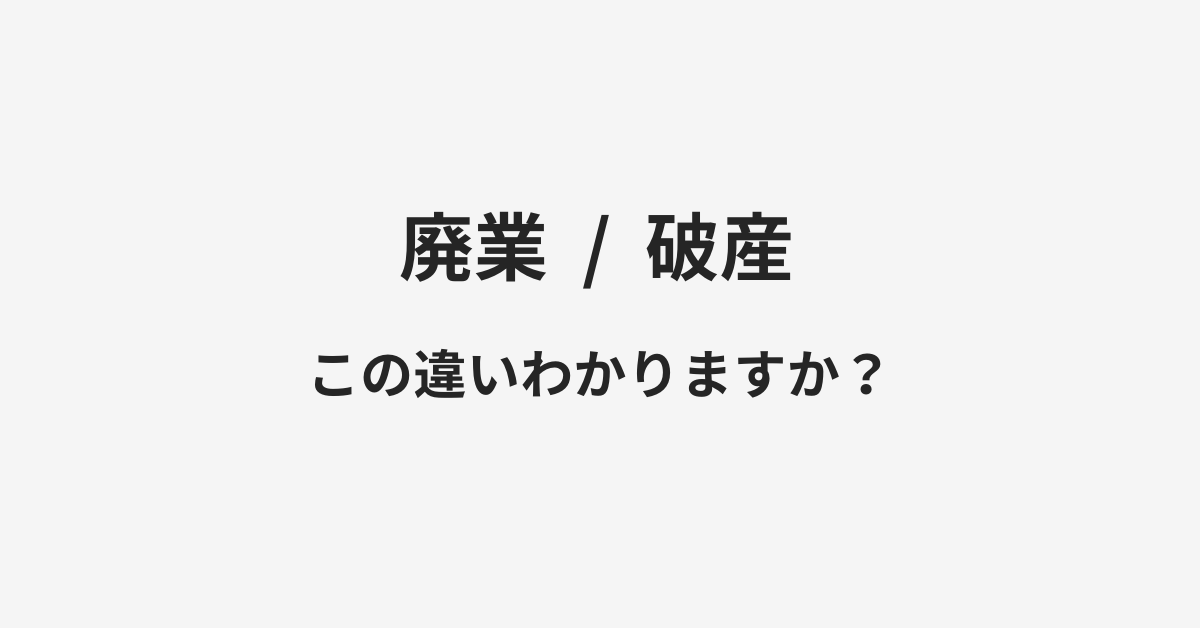
廃業と破産の分かりやすい違い
廃業と破産は、どちらも事業の終了を意味しますが、その原因と手続きに大きな違いがあります。廃業は経営者の判断による自主的な事業終了で、破産は債務返済不能による法的な強制終了です。
前者は円満な終了が可能、後者は債権者保護のための法的手続きという違いがあります。
事業経営において、この違いを理解することは、適切な撤退戦略の選択と関係者への影響を最小化するために重要です。
廃業とは?
廃業とは、個人事業主や法人が自らの意思で事業活動を終了することです。後継者不在、健康上の理由、事業環境の変化、計画的な引退などが主な理由です。債務を完済できる状態で行うため、取引先や従業員への影響を最小限に抑えることができます。税務署への廃業届提出、許認可の返納、従業員の雇用終了手続きなどが必要です。
廃業のプロセスは、事業の清算、在庫・資産の処分、債権債務の整理、各種契約の解除、行政手続きなどを含みます。計画的に進めることで、円満な事業終了が可能です。事業承継やM&Aという選択肢もあり、廃業以外の方法で事業価値を残すことも検討されます。
日本では中小企業の後継者不足により、黒字でも廃業するケースが増えています。これは社会的な損失でもあるため、事業承継支援や第三者への売却支援など、廃業以外の選択肢を提供する取り組みも進んでいます。
廃業の例文
- ( 1 ) 高齢のため、来年3月での廃業を決意しました。
- ( 2 ) 計画的な廃業により、全従業員の再就職先を確保できました。
- ( 3 ) 廃業前に顧客リストを同業他社に引き継ぎ、サービス継続を図りました。
- ( 4 ) 黒字廃業でしたが、後継者不在のためやむを得ない決断でした。
- ( 5 ) 廃業手続きをスムーズに進めるため、専門家のサポートを受けています。
- ( 6 ) 廃業ではなく、事業承継の可能性を最後まで探りました。
廃業の会話例
破産とは?
破産とは、債務者が債務を返済できない状態(支払不能)になった際に、裁判所の監督下で財産を清算し、債権者に公平に配分する法的手続きです。自己破産(債務者自身の申立て)と債権者破産(債権者の申立て)があります。破産手続開始決定により、破産管財人が選任され、財産の管理・換価・配当を行います。
破産の効果として、法人は解散・消滅し、個人は免責により債務から解放される可能性があります。ただし、税金や養育費など一部の債務は免責されません。また、一定期間、特定の職業に就けない、クレジットカードが作れないなどの制約があります。信用情報機関に登録され、金融取引に影響が出ます。
破産は最終手段であり、任意整理、個人再生、民事再生など他の債務整理方法も検討すべきです。早期の相談により、破産を回避できる可能性もあります。経営者には、資金繰りの悪化を早期に察知し、適切な対応を取ることが求められます。
破産の例文
- ( 1 ) 資金繰りの悪化により、破産申立てを余儀なくされました。
- ( 2 ) 破産管財人の指導の下、資産の換価処分を進めています。
- ( 3 ) 破産手続き開始決定を受け、全ての事業活動を停止しました。
- ( 4 ) 連鎖破産を防ぐため、取引先への早期連絡を心がけました。
- ( 5 ) 破産に至った原因を分析し、今後の教訓としています。
- ( 6 ) 個人破産後、免責決定を受けて再スタートを切りました。
破産の会話例
廃業と破産の違いまとめ
廃業と破産の決定的な違いは、自主性と財務状態です。廃業は債務を完済できる状態での自主的終了、破産は債務超過による強制的終了という明確な違いがあります。手続きも大きく異なり、廃業は経営者主導で進められますが、破産は裁判所の管理下で破産管財人が手続きを進めます。
社会的な影響も、廃業は最小限に抑えられますが、破産は信用失墜など大きな影響があります。
経営者は、財務状況を常に把握し、破産に至る前に廃業や事業承継などの選択肢を検討することが重要です。早期の決断が、関係者への影響を最小化します。
廃業と破産の読み方
- 廃業(ひらがな):はいぎょう
- 廃業(ローマ字):haigyou
- 破産(ひらがな):はさん
- 破産(ローマ字):hasann