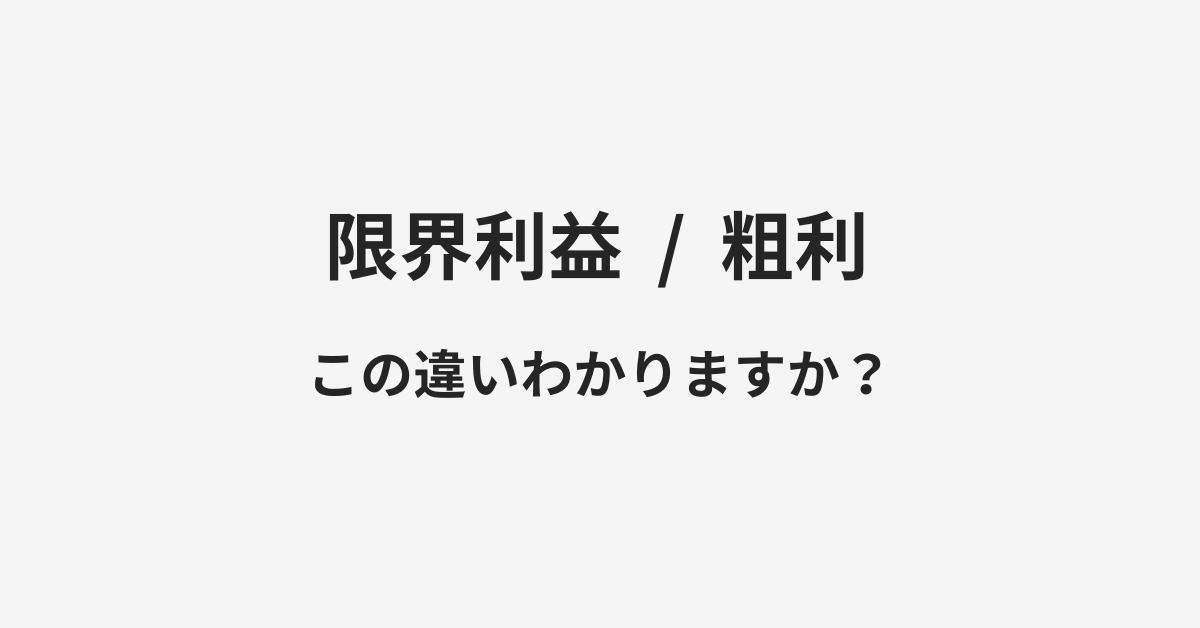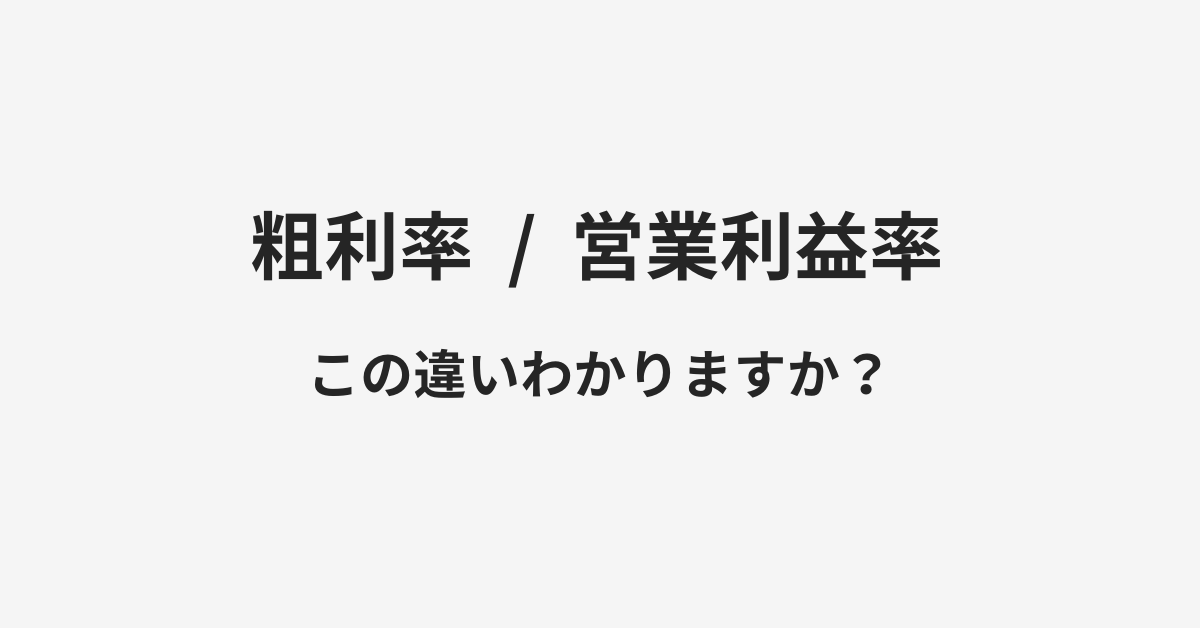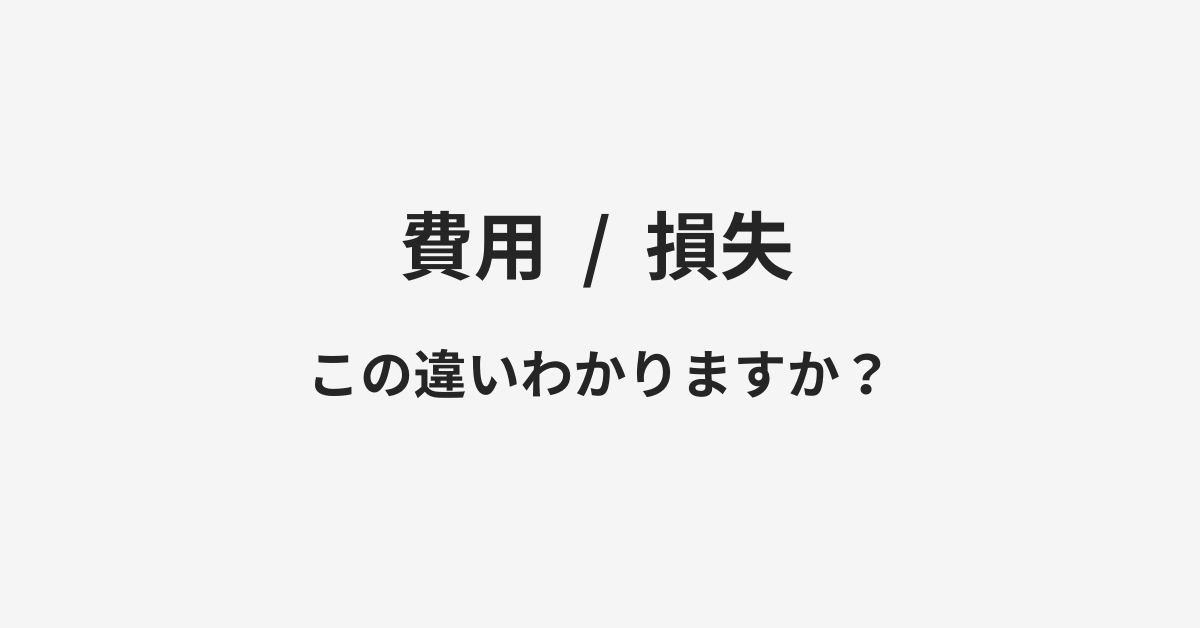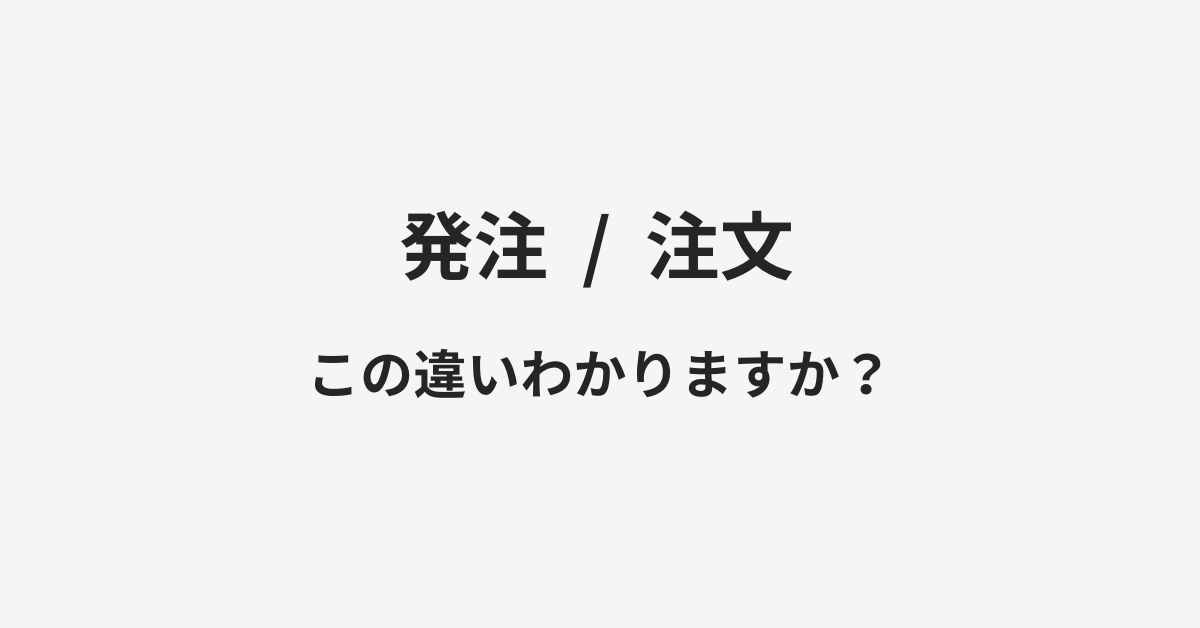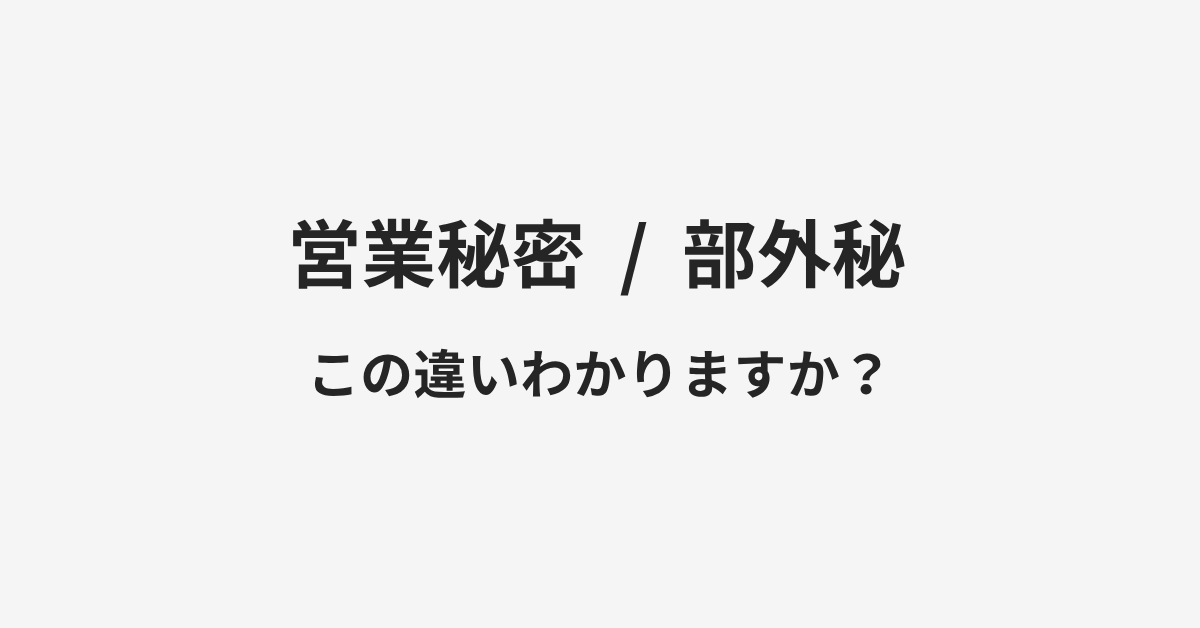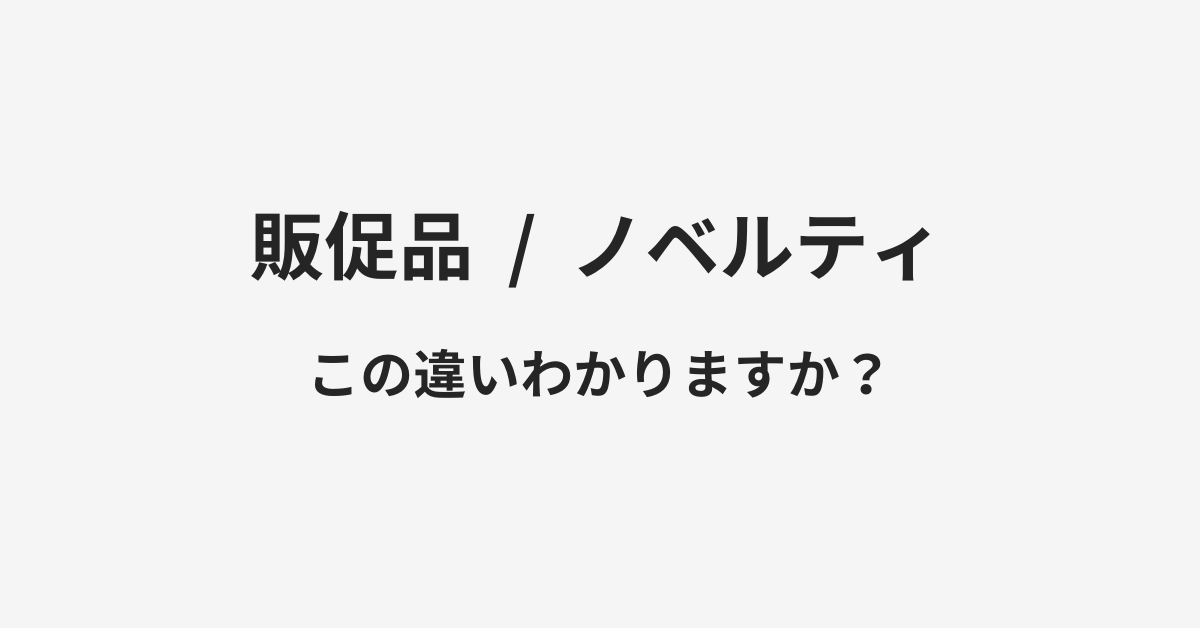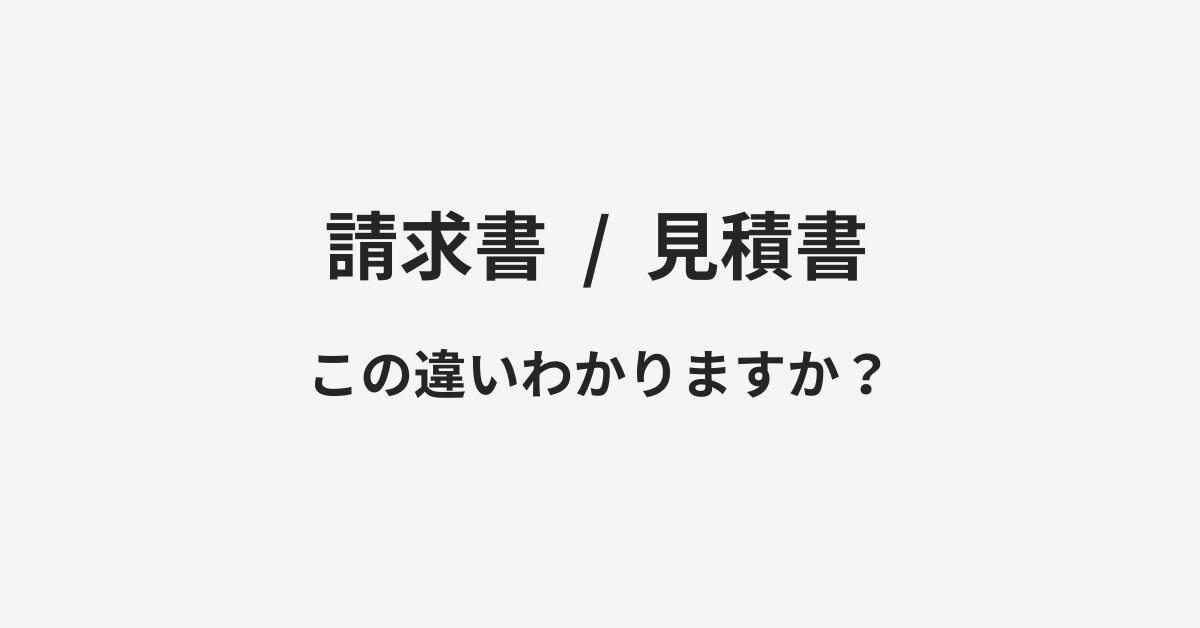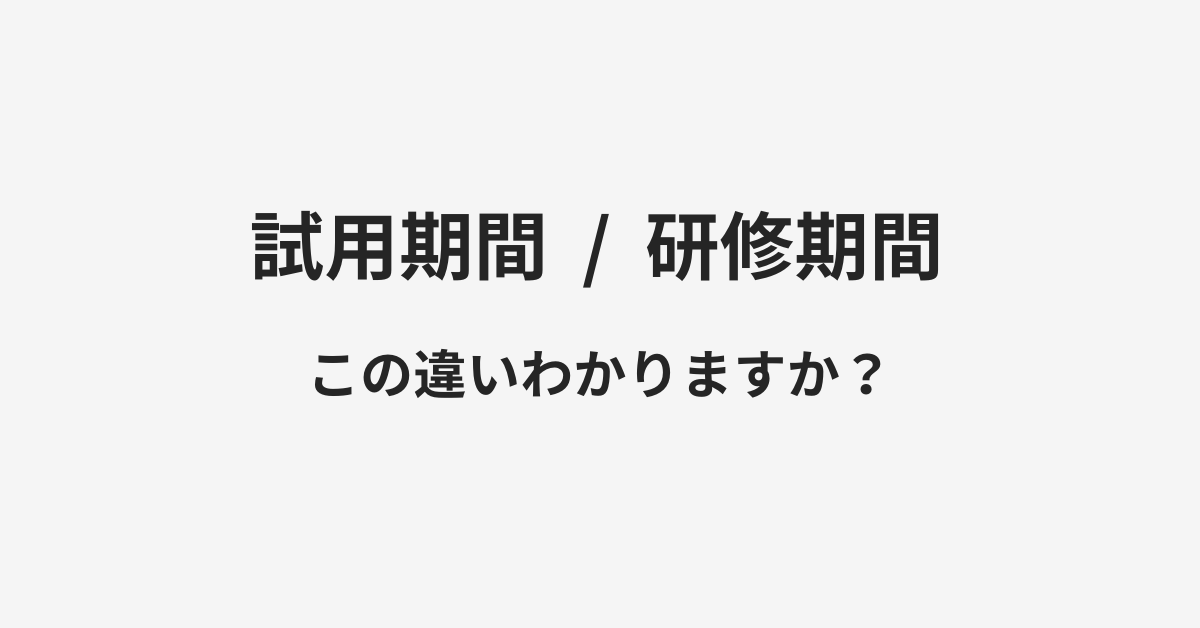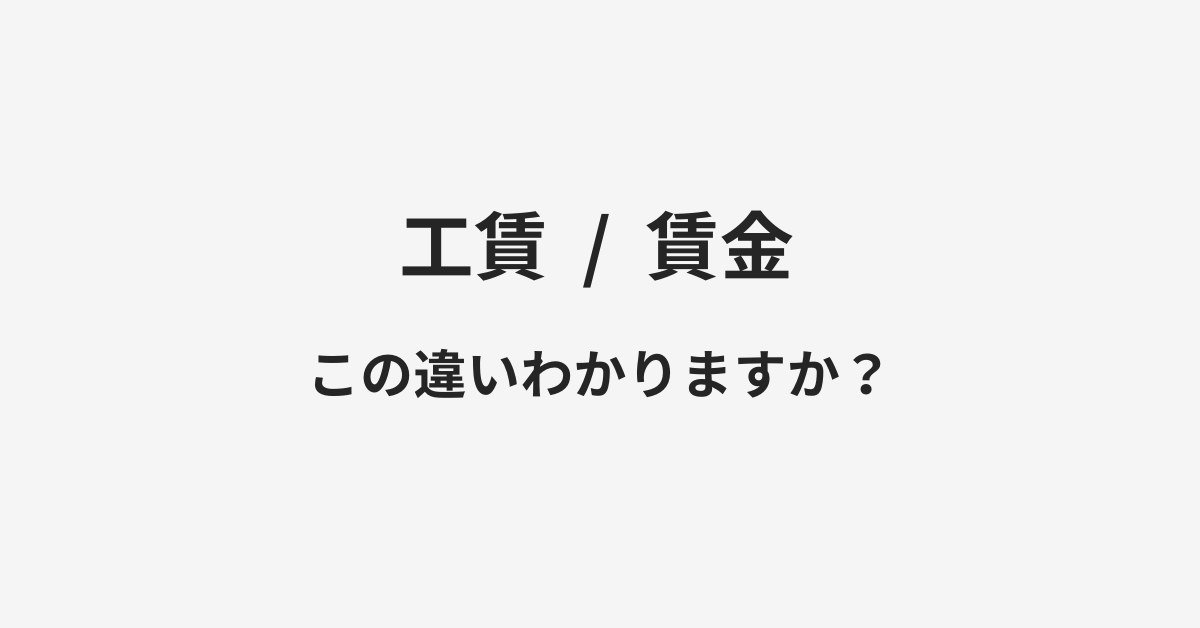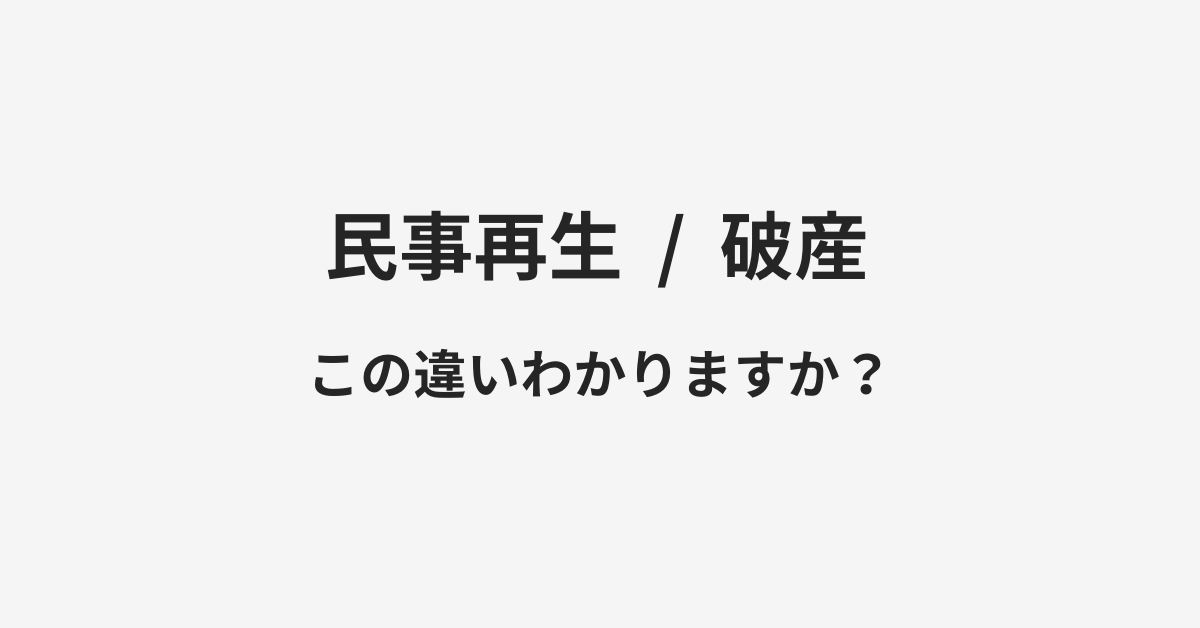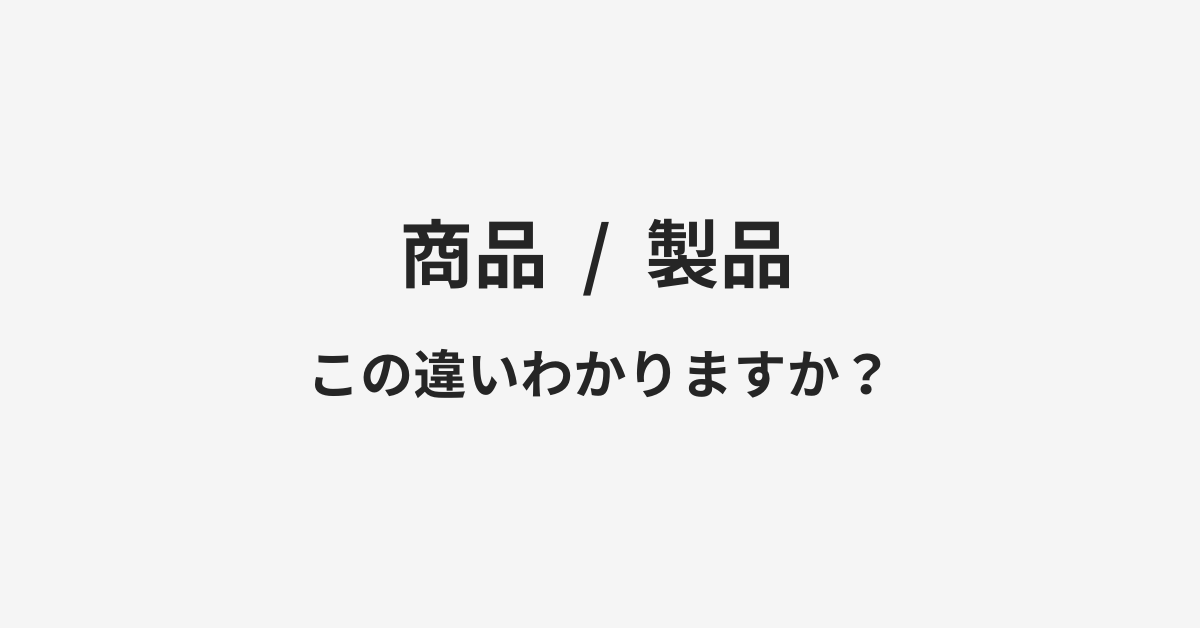【粗利】と【営業利益】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
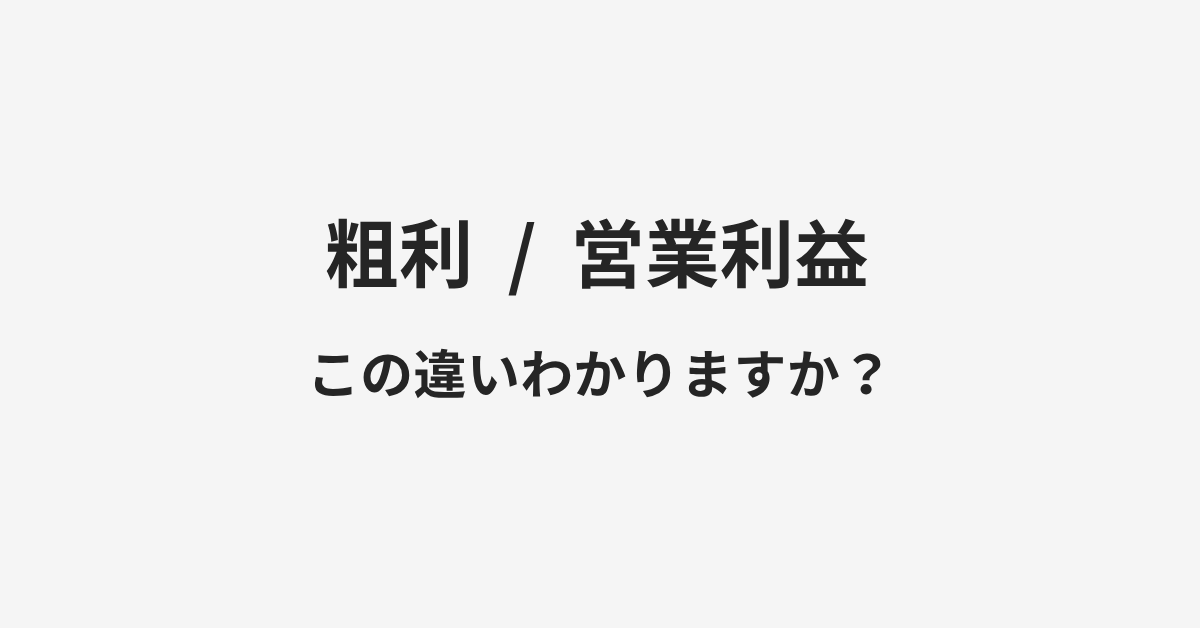
粗利と営業利益の分かりやすい違い
粗利と営業利益は、どちらも会社の儲けを表す言葉ですが、計算方法と意味が異なります。粗利(売上総利益)は、売上から商品の仕入れ値や製造にかかった費用だけを引いた金額です。
例えば、1000円で売った商品の仕入れ値が600円なら、粗利は400円です。営業利益は、その粗利から人件費や家賃などの経費をさらに引いた金額です。
つまり、粗利は商品でどれだけ儲けたか、営業利益は会社の本業でどれだけ儲けたかを表します。
粗利とは?
粗利(売上総利益)とは、売上高から売上原価を差し引いた利益で、企業が提供する商品やサービスの基本的な収益力を示す指標です。製造業では製造原価、小売業では仕入原価、サービス業では直接的なサービス提供コストを売上から引いて算出します。粗利率(粗利÷売上高)は業種により大きく異なり、製造業で20-30%、小売業で20-40%、飲食業で60-70%程度が一般的です。
粗利は商品やサービスの競争力、価格設定の適切性、仕入れや製造の効率性を反映します。粗利が高いということは、付加価値の高い商品・サービスを提供できているか、効率的な原価管理ができていることを意味します。
ただし、粗利が高くても販管費が過大であれば最終的な利益は確保できません。粗利の改善には、販売価格の見直し、仕入原価の削減、製造効率の向上、商品ミックスの最適化などの手法があります。特に、高粗利商品の販売比率を高めることは、収益性向上の重要な戦略となります。
粗利の例文
- ( 1 ) 新商品の投入により、粗利率が前年の25%から28%に改善しました。
- ( 2 ) 粗利は確保できていますが、販促費の増加により営業利益への貢献は限定的です。
- ( 3 ) 原材料費の高騰により粗利が圧迫されているため、販売価格の見直しを検討します。
- ( 4 ) 高粗利商品の販売強化により、全体の粗利額が前年比15%増加しました。
- ( 5 ) 粗利管理を商品カテゴリー別に細分化し、収益性の見える化を実現しました。
- ( 6 ) 競合との価格競争により粗利率が低下傾向にあり、差別化戦略が急務です。
粗利の会話例
営業利益とは?
営業利益とは、企業の本業から生み出される利益で、売上総利益(粗利)から販売費及び一般管理費(販管費)を差し引いて算出されます。販管費には、人件費、賃借料、広告宣伝費、減価償却費など、商品の販売や企業運営に必要な費用が含まれます。営業利益率(営業利益÷売上高)は企業の本業の収益力を測る重要な指標です。
営業利益は、企業が継続的に事業を行う力を示す指標として、投資家や金融機関から重視されます。営業利益がプラスということは、本業で稼ぐ力があることを意味し、企業の競争力や経営効率を反映します。一般的に、営業利益率は製造業で5-10%、小売業で2-5%、IT企業で10-20%程度が目安とされています。
営業利益の改善には、売上高の増加、粗利率の向上に加えて、販管費の適正化が不可欠です。特に固定費の削減、業務効率化による人件費の適正化、マーケティング費用の効果的な配分などが重要な経営課題となります。
営業利益の例文
- ( 1 ) 今四半期の営業利益は売上増加と経費削減の両輪により、計画を10%上回りました。
- ( 2 ) 営業利益率5%の目標達成に向けて、全部門で販管費の見直しを進めています。
- ( 3 ) 売上は横ばいでしたが、業務効率化により営業利益は前年比20%増を達成しました。
- ( 4 ) 営業利益の改善のため、不採算店舗の閉鎖と優良店舗への資源集中を決定しました。
- ( 5 ) IT投資による業務自動化で人件費を削減し、営業利益率が2ポイント向上しました。
- ( 6 ) 各事業部の営業利益貢献度を分析し、経営資源の最適配分を実施します。
営業利益の会話例
粗利と営業利益の違いまとめ
粗利と営業利益の違いを理解することは、企業の収益構造を分析する上で極めて重要です。粗利は商品・サービスの直接的な収益力を、営業利益は経費管理も含めた総合的な本業の収益力を示すという違いがあります。
実務では、粗利の確保は商品戦略や価格戦略の要であり、営業利益の確保は経営全体の効率性の証となります。高い粗利を維持しながら、適切な販管費管理により営業利益を最大化することが、健全な経営の基本です。
財務分析では、粗利率の推移で商品力の変化を、営業利益率の推移で経営効率の変化を把握できます。両指標を組み合わせることで、企業の収益力を多面的に評価することが可能となります。
粗利と営業利益の読み方
- 粗利(ひらがな):あらり
- 粗利(ローマ字):arari
- 営業利益(ひらがな):えいぎょうりえき
- 営業利益(ローマ字):eigyourieki