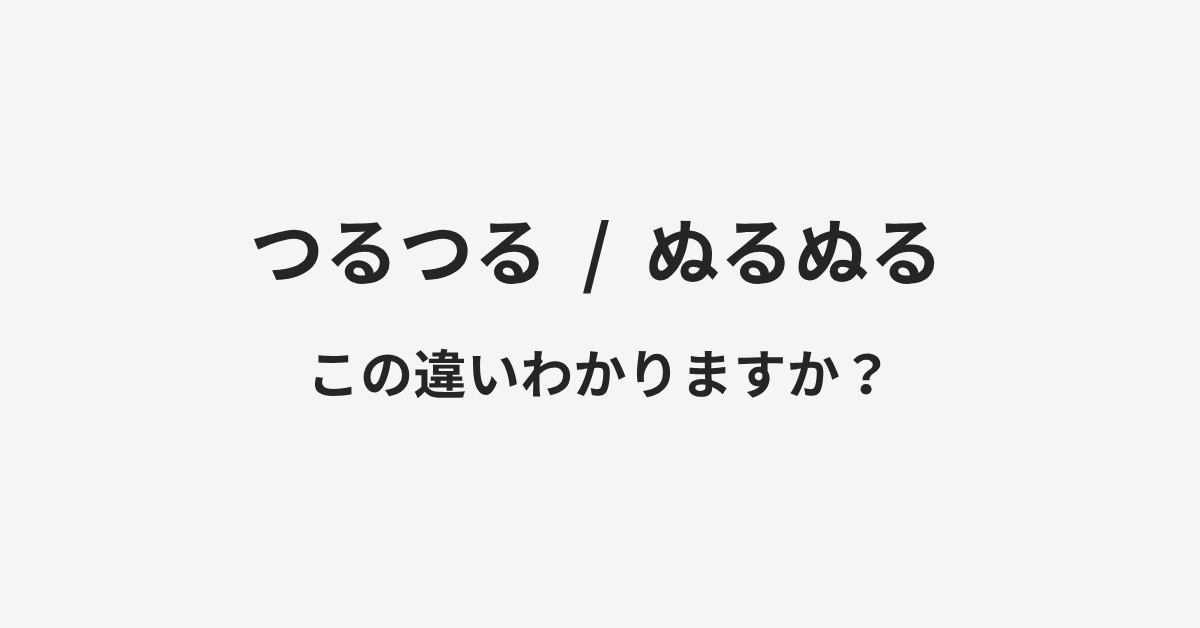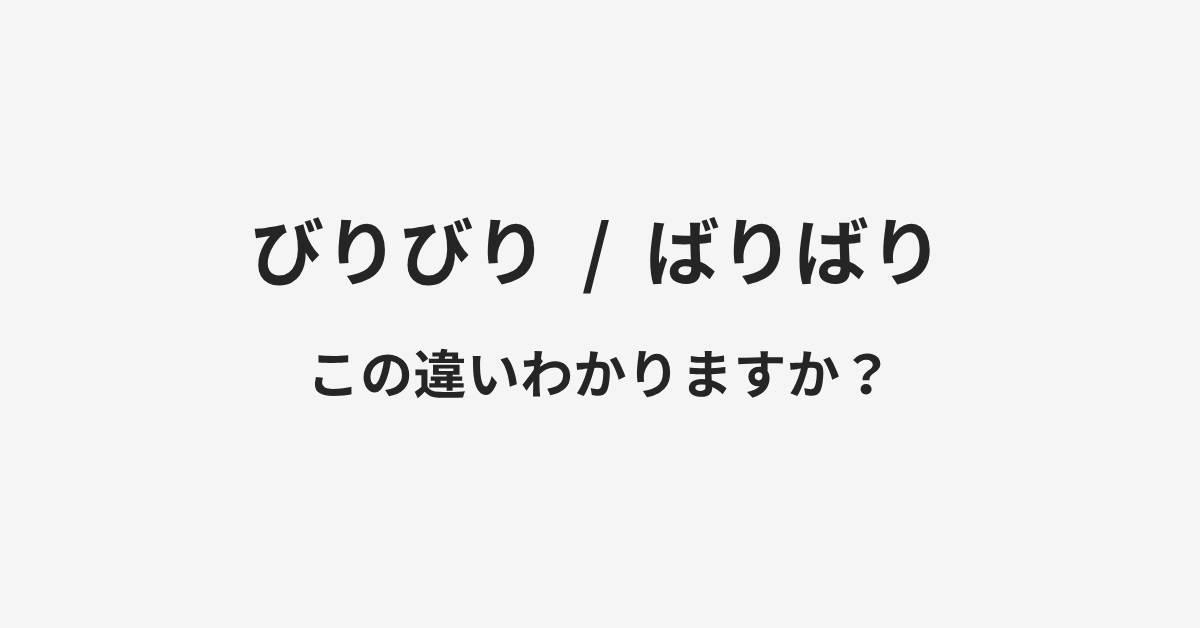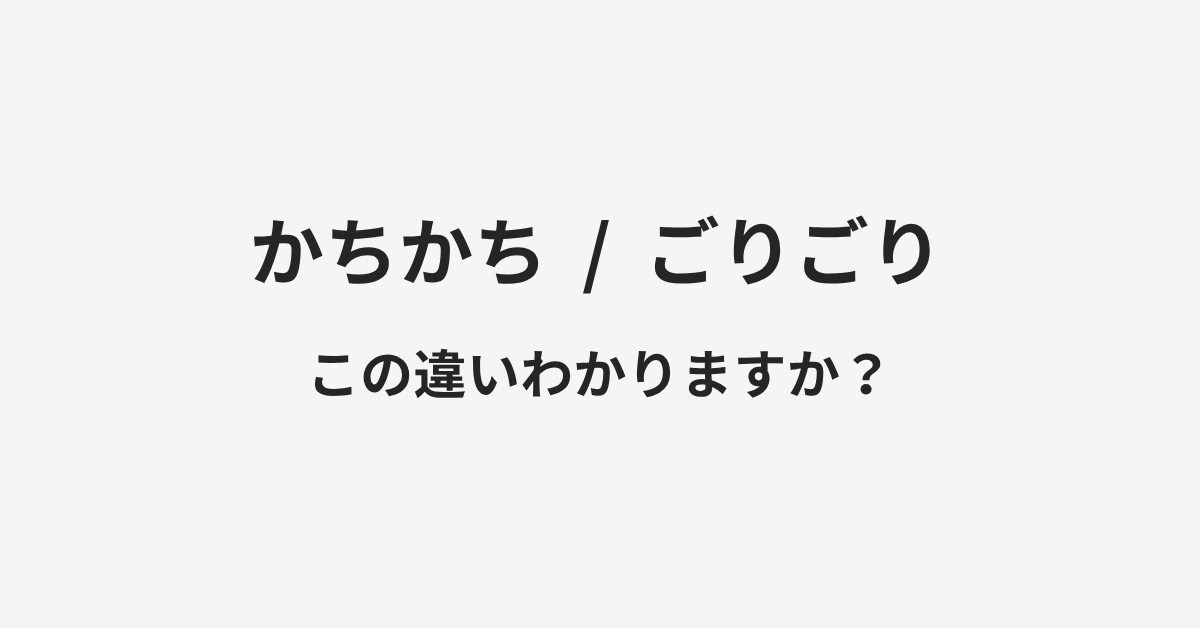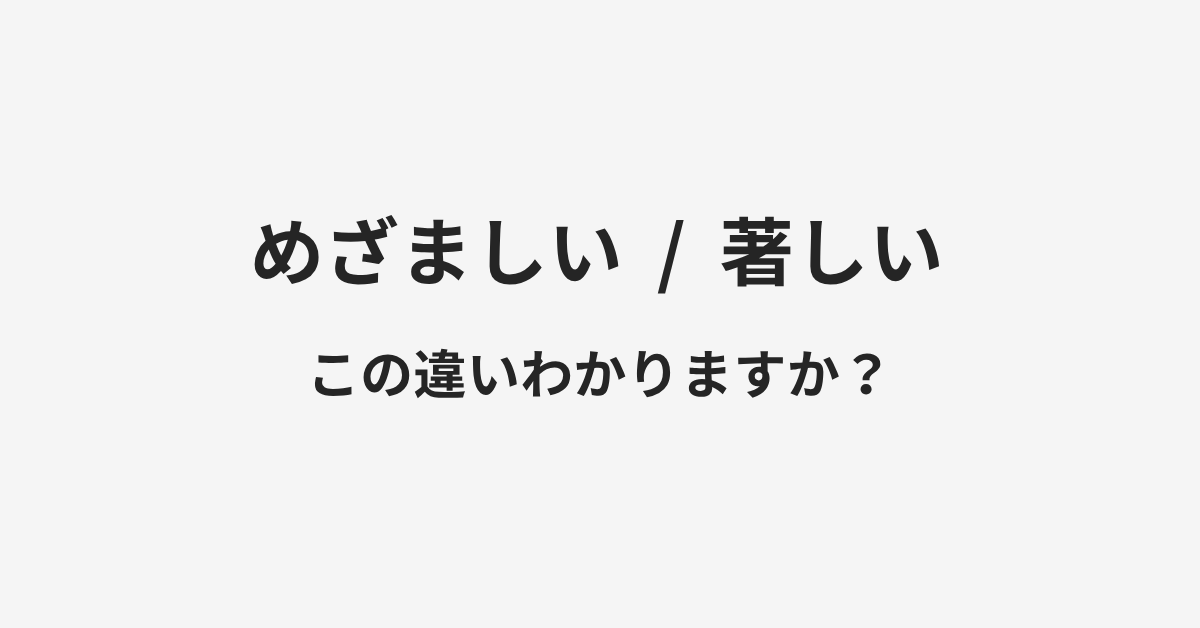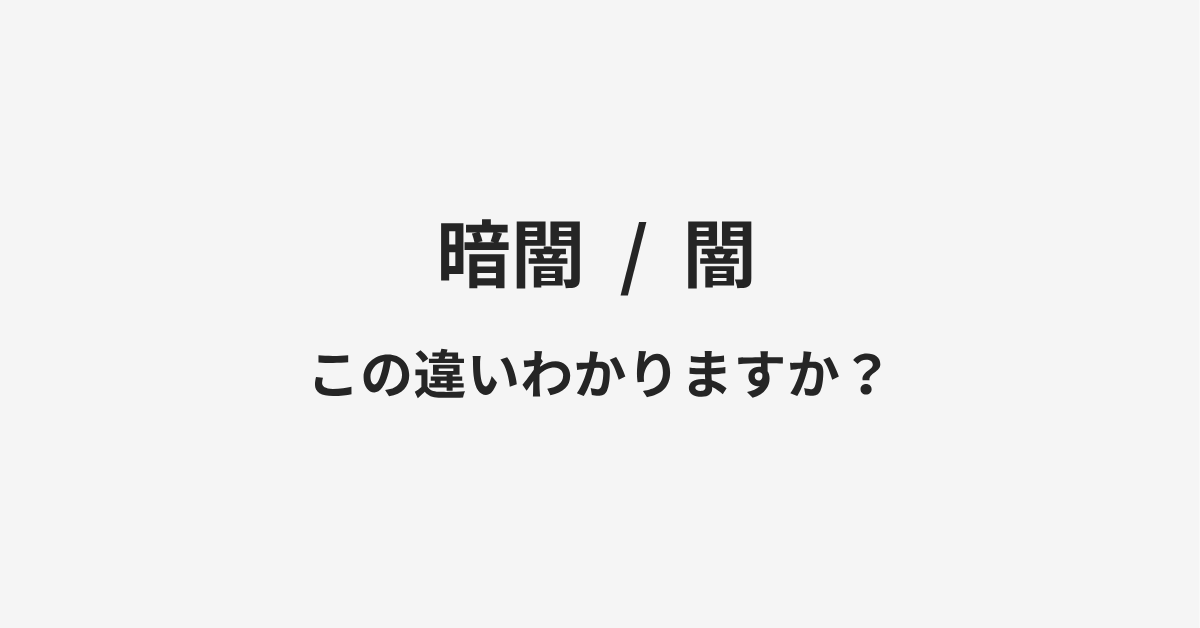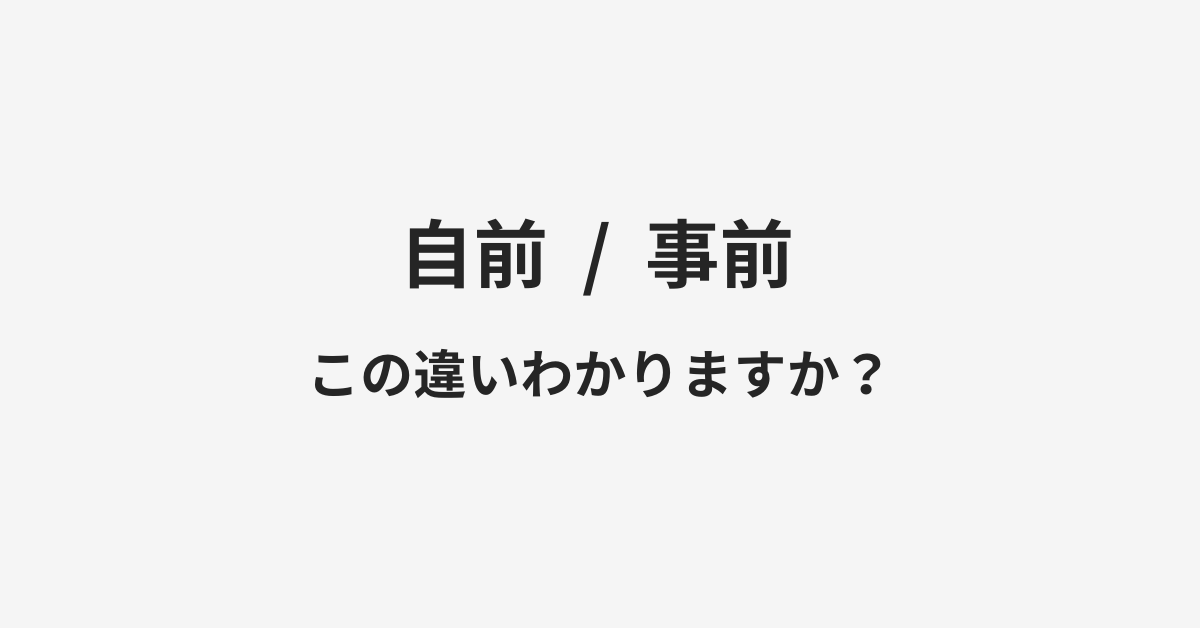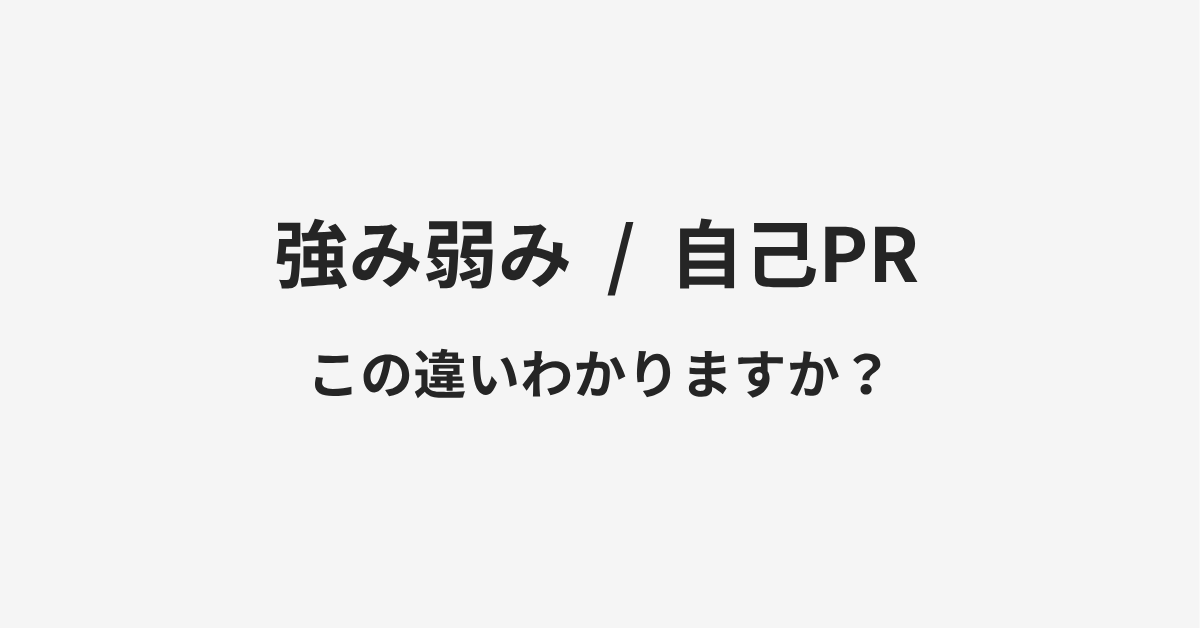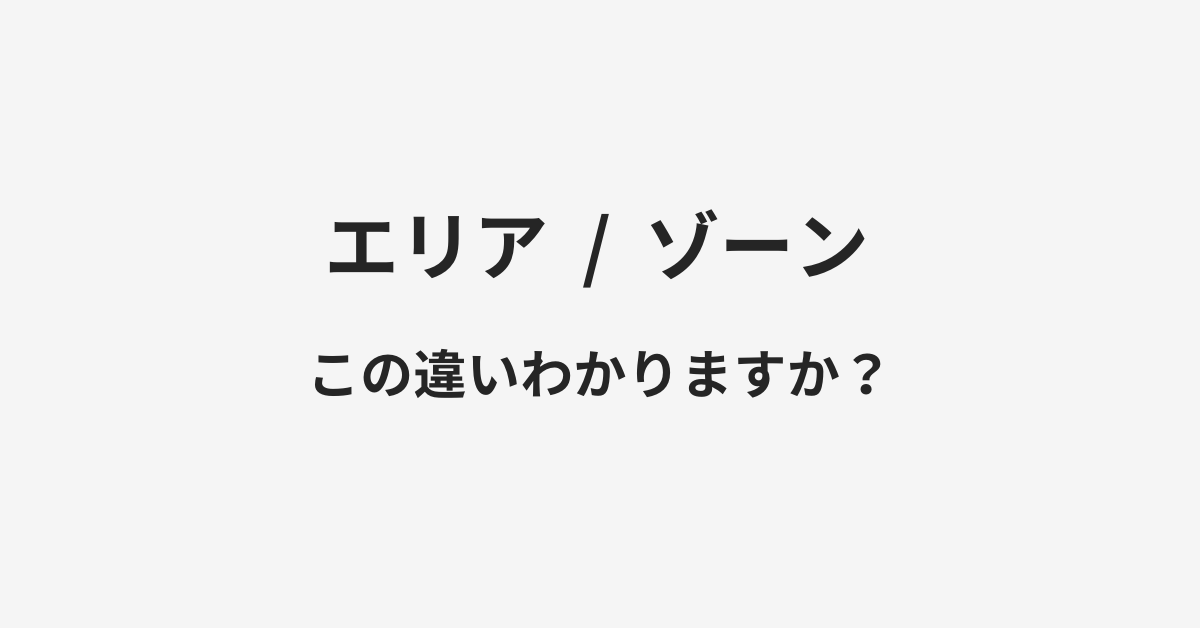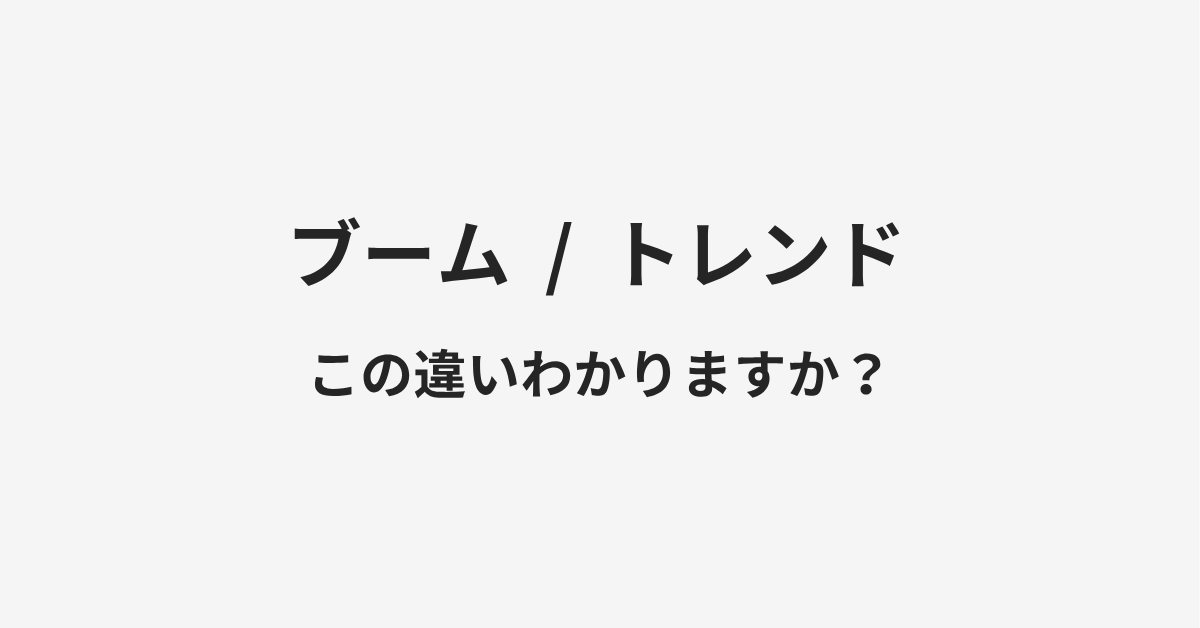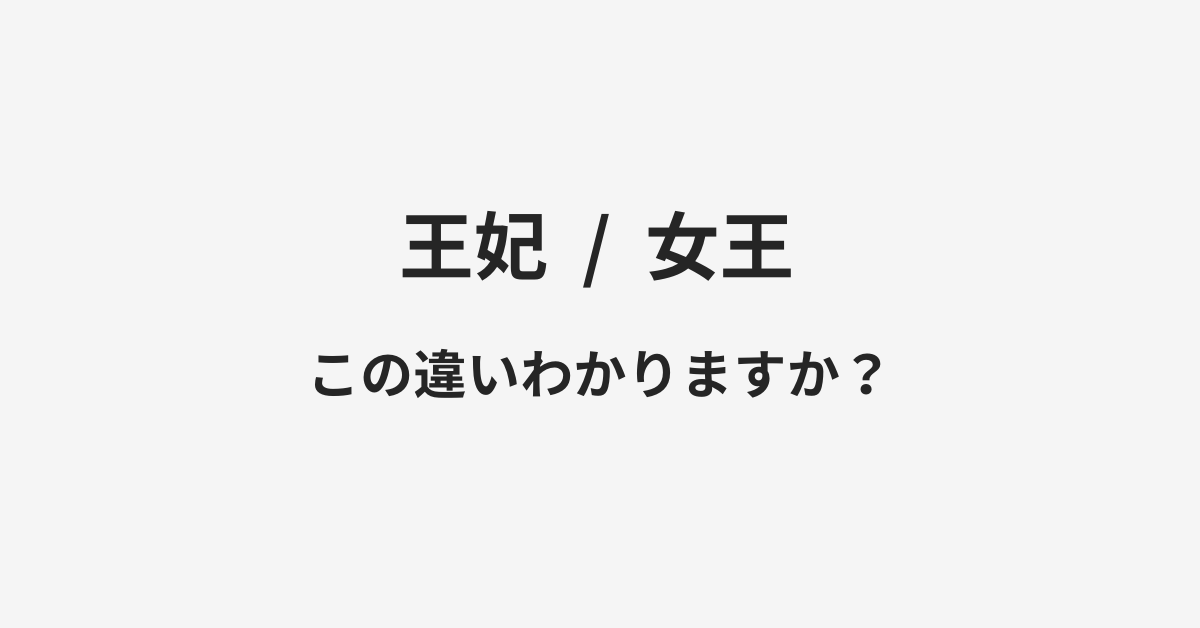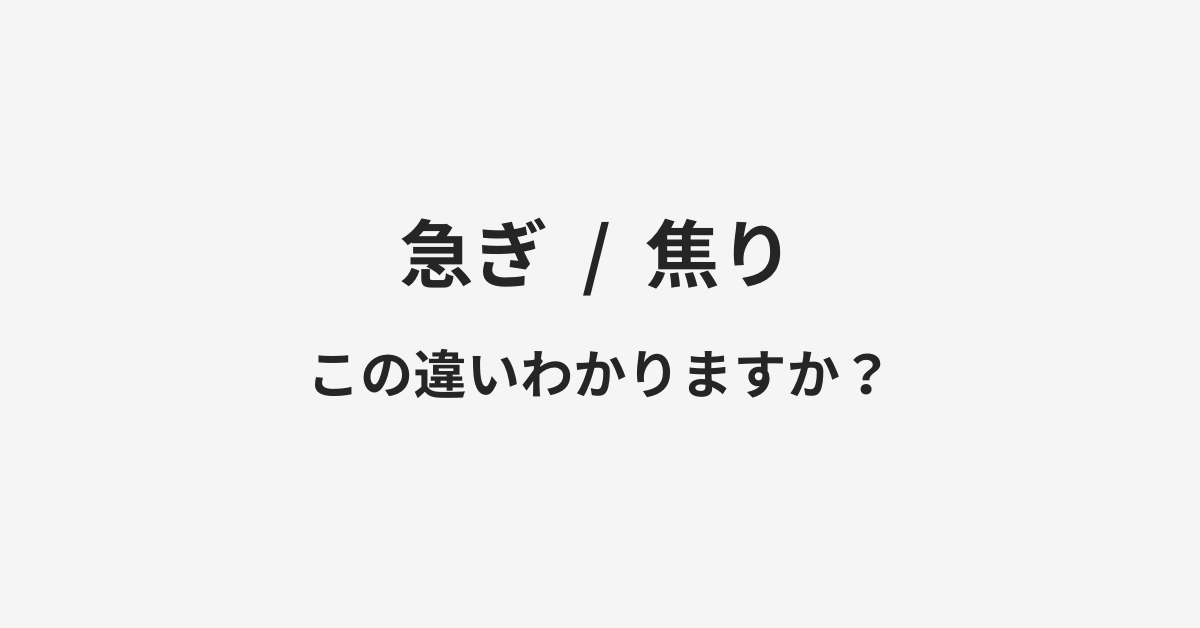【べたべた】と【ねばねば】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
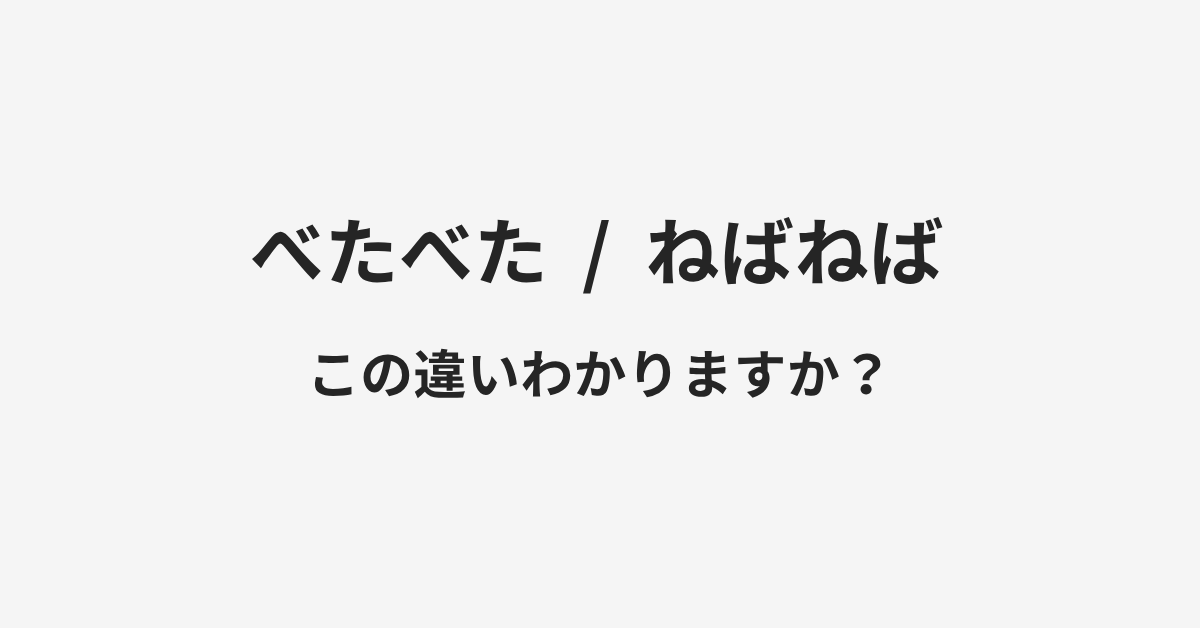
べたべたとねばねばの分かりやすい違い
べたべたとねばねばは、どちらも粘り気を表す擬態語ですが、粘り方の質が異なります。べたべたは表面が粘着質で触ると不快な感触を表し、主に汚れやべたつきを示します。
一方、ねばねばは糸を引くような粘り気を表し、納豆のように伸びる粘性を示します。日常生活では、手がべたべたする、納豆がねばねばするなど、粘り気の種類に応じて使い分けることで、より正確に感触を表現できます。
べたべたとは?
べたべたは、表面に粘着質のものが付いて、触ると不快な感触がする様子を表す擬態語です。油分や糖分などで汚れた状態を表現し、清潔でない印象を与えることが多いです。日常生活では、汗をかいた肌、油で汚れた手、こぼれたジュースで汚れたテーブル、髪の毛のべたつき、湿気の多い日の不快感などに使われます。
早く洗い流したくなるような状態を表します。
べたべたという表現は、不快な粘着感を的確に表現し、清潔さが失われた状態を示します。日常生活でよく遭遇する不快感を表す、誰もが共感できる表現です。
べたべたの例文
- ( 1 ) 手がべたべたして気持ち悪い。
- ( 2 ) 汗で体がべたべたする。
- ( 3 ) テーブルがジュースでべたべただ。
- ( 4 ) 髪がべたべたして洗いたい。
- ( 5 ) 湿気で肌がべたべたする。
- ( 6 ) 油でフライパンがべたべたしている。
べたべたの会話例
ねばねばとは?
ねばねばは、糸を引くような粘り気がある様子を表す擬態語です。主に食べ物の粘性を表現し、健康的で栄養価が高い印象を与えることが多く、日本食の特徴的な食感を表します。
日常生活では、納豆、オクラ、山芋、めかぶ、なめこなどの食材や、粘性のある液体に使われます。箸で持ち上げると糸を引くような、特徴的な粘り方を表現する言葉です。ねばねばという表現は、日本の食文化に深く根ざした言葉で、健康に良いとされる食材の特徴を表します。
独特の食感を楽しむ日本人の感性を表現する、文化的な意味も持つ言葉です。
ねばねばの例文
- ( 1 ) 納豆がねばねばと糸を引く。
- ( 2 ) オクラのねばねばが体に良い。
- ( 3 ) 山芋をすってねばねばにした。
- ( 4 ) めかぶのねばねば感が好きだ。
- ( 5 ) なめこ汁がねばねばして美味しい。
- ( 6 ) ねばねば食材は健康に良い。
ねばねばの会話例
べたべたとねばねばの違いまとめ
べたべたとねばねばは、どちらも粘り気を表しますが、質が異なります。べたべたは不快な表面的粘着を、ねばねばは糸を引く健康的な粘りを表現します。
粘り気の種類に応じて使い分けることで、より正確に感触を伝えることができます。日常会話では、汚れた感じはべたべた、食べ物の粘りはねばねばを使うなど、状況に合わせて選ぶことで、適切な表現ができます。
べたべたとねばねばの読み方
- べたべた(ひらがな):べたべた
- べたべた(ローマ字):betabeta
- ねばねば(ひらがな):ねばねば
- ねばねば(ローマ字):nebaneba