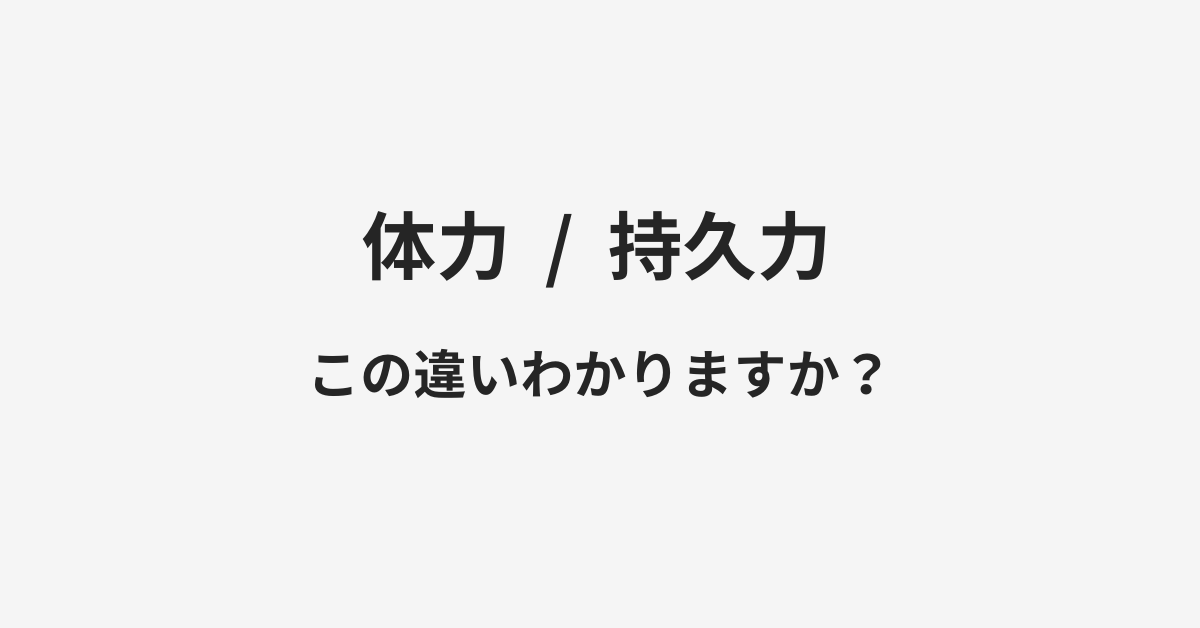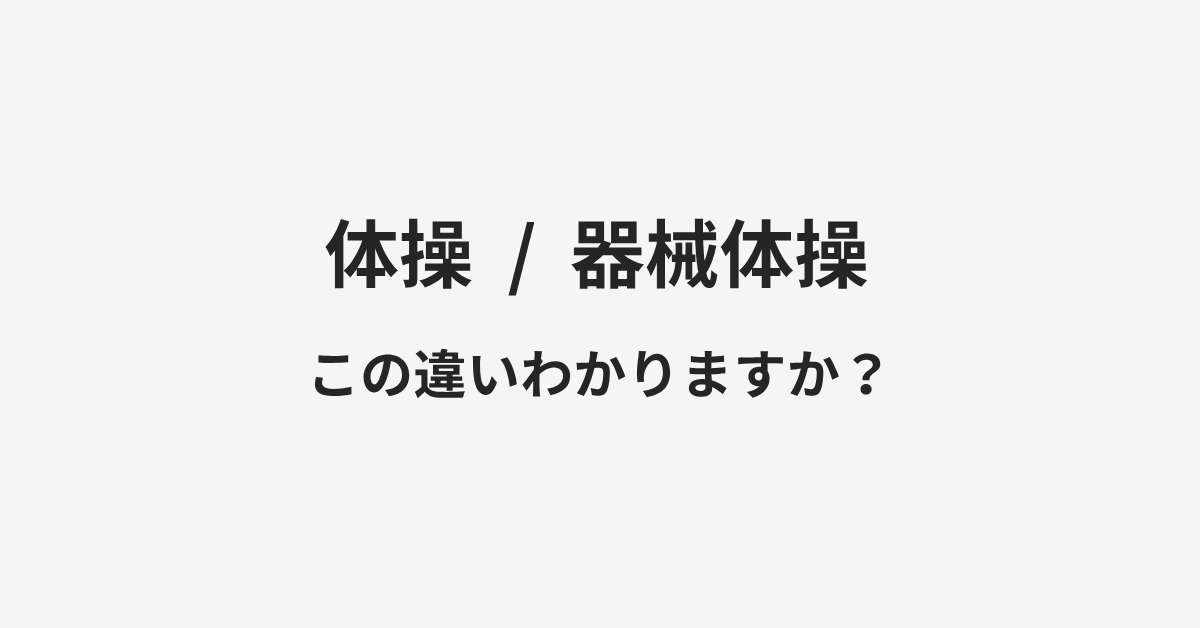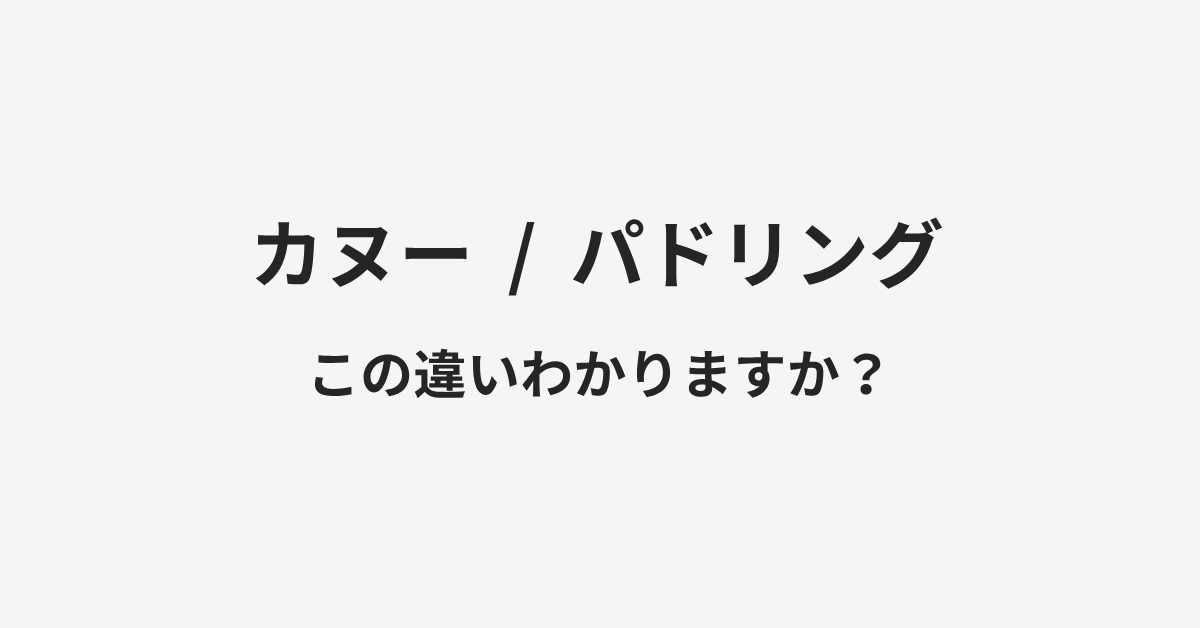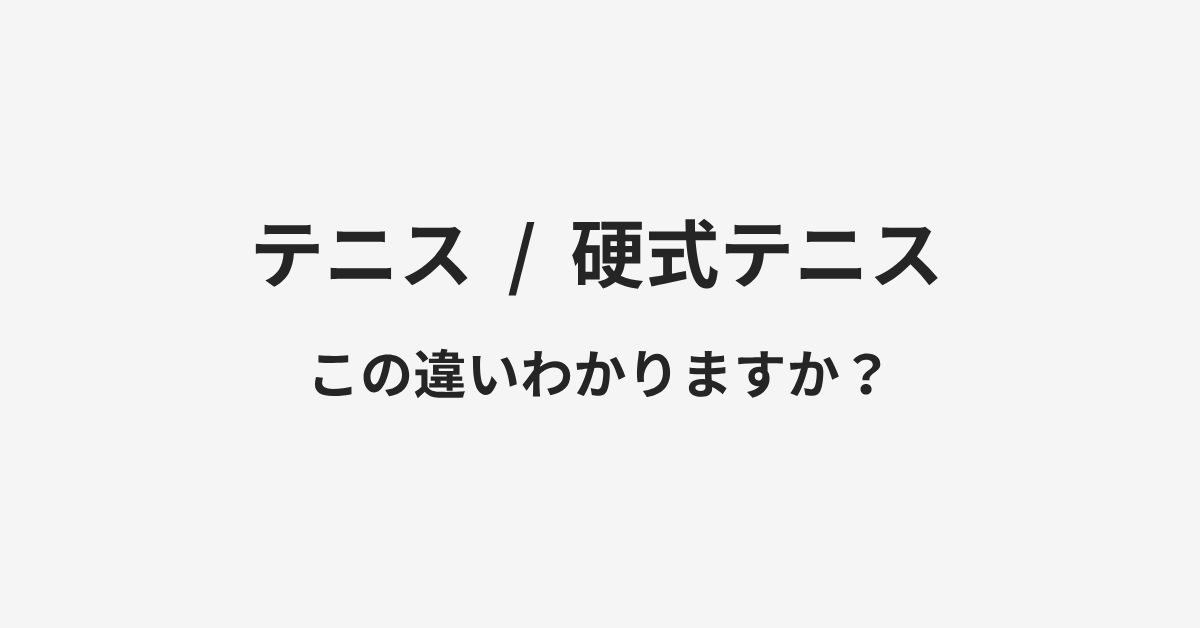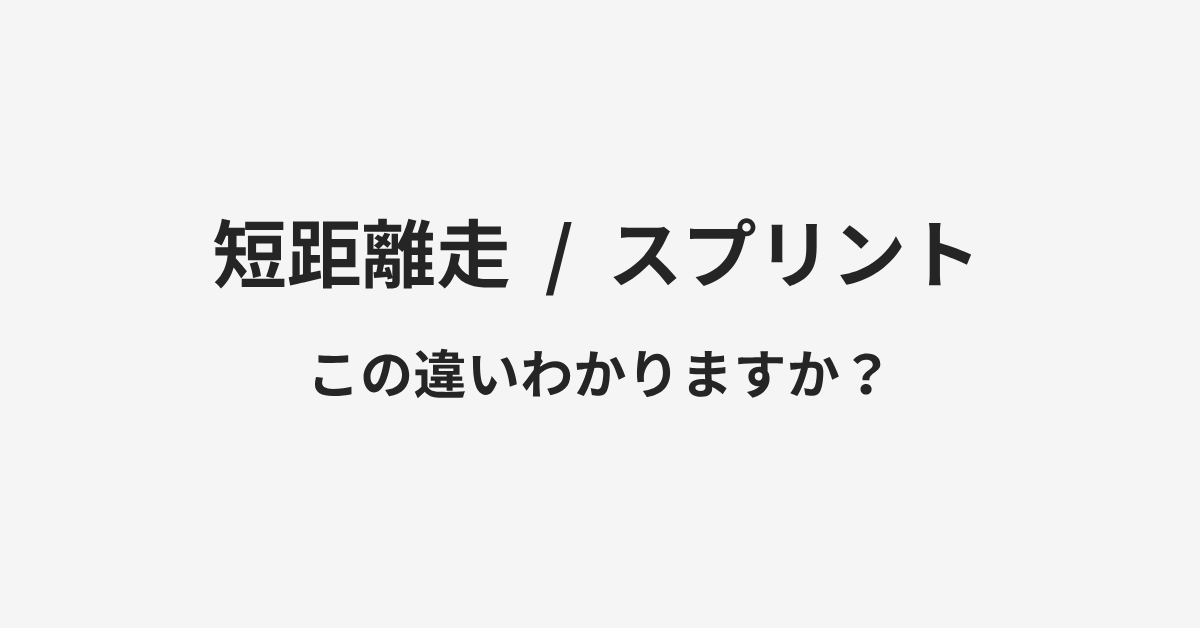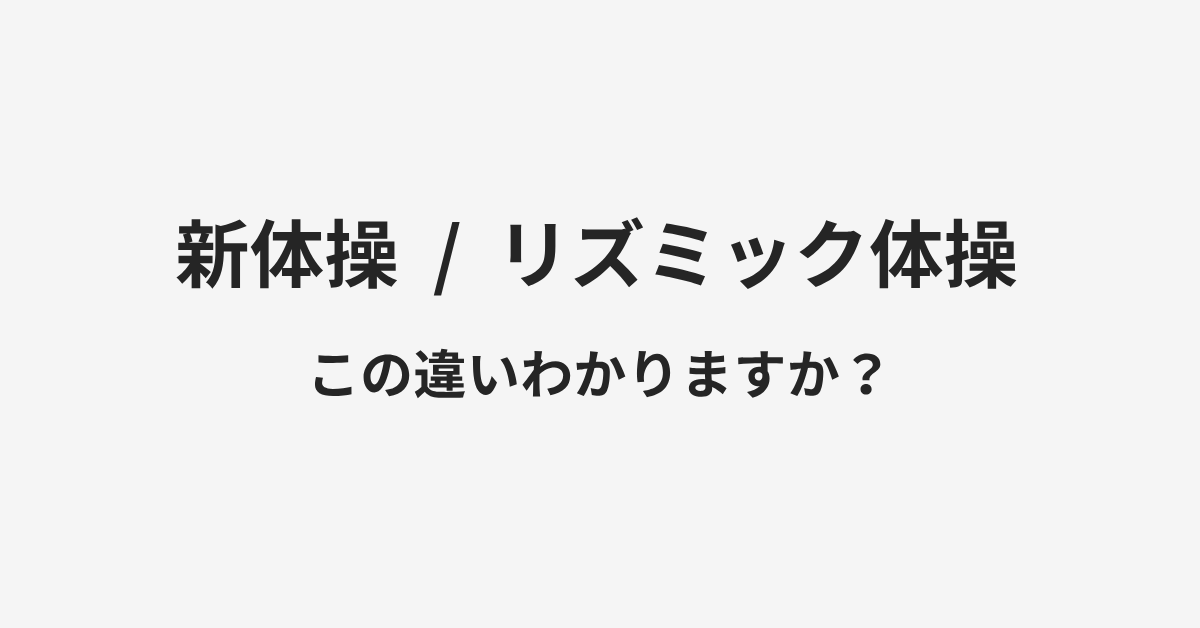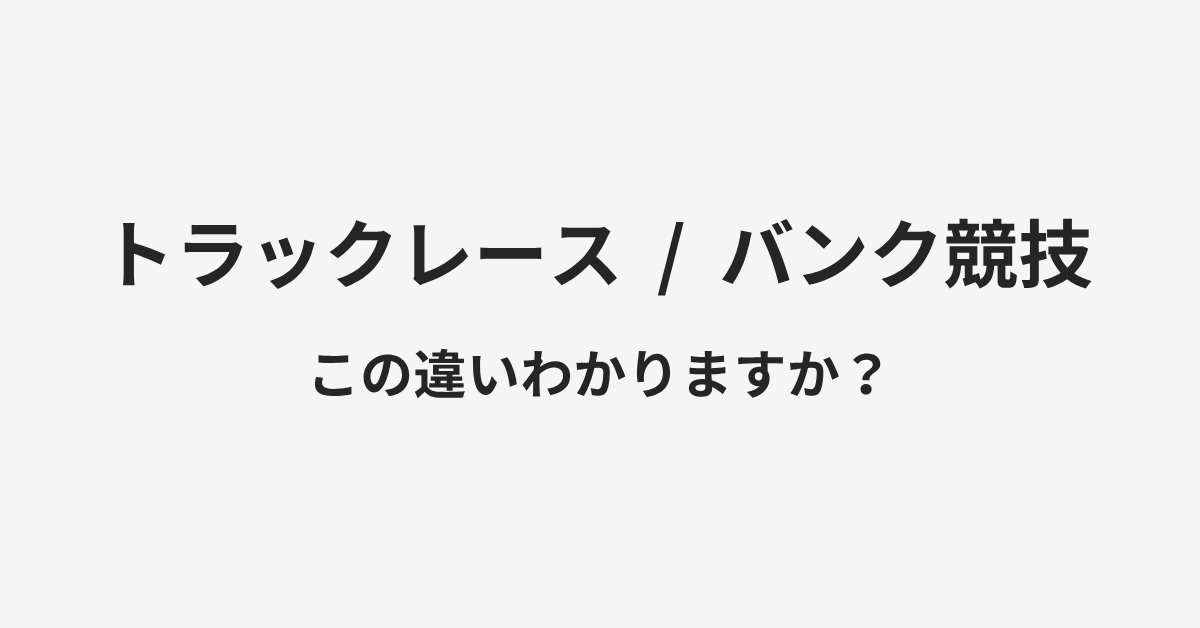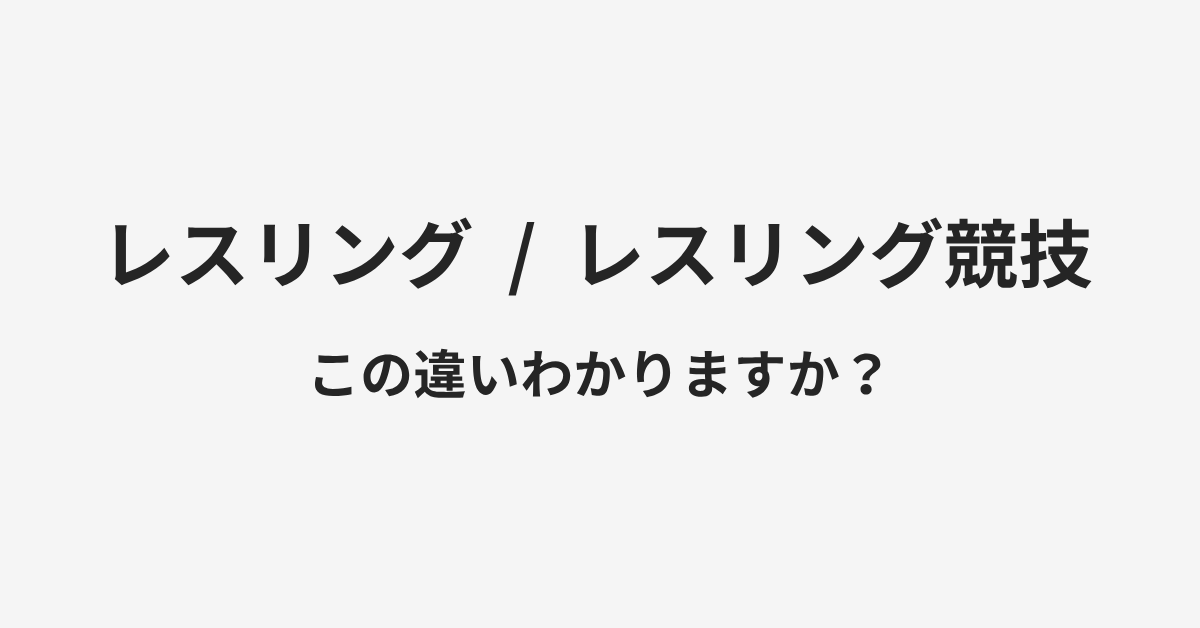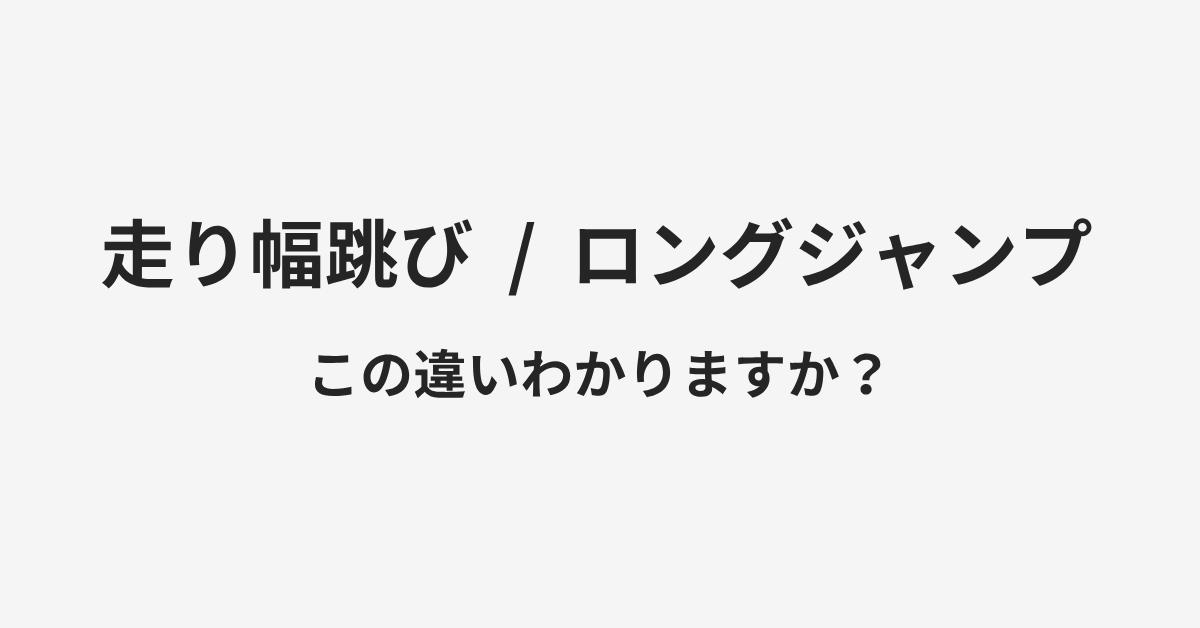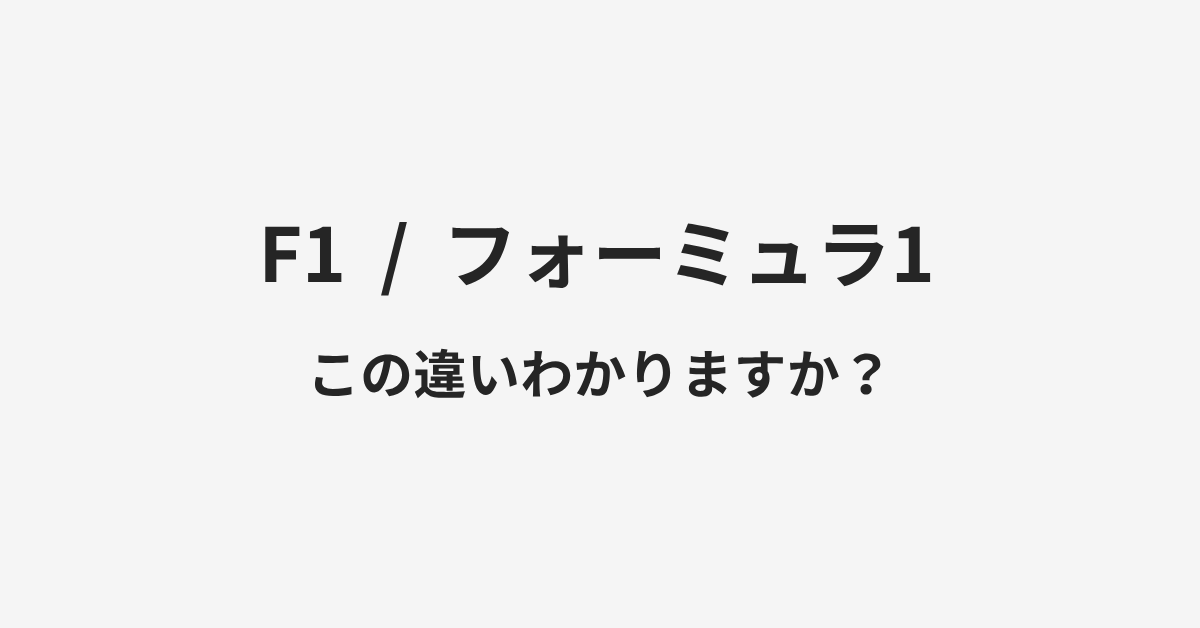【フィットネス】と【運動習慣】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
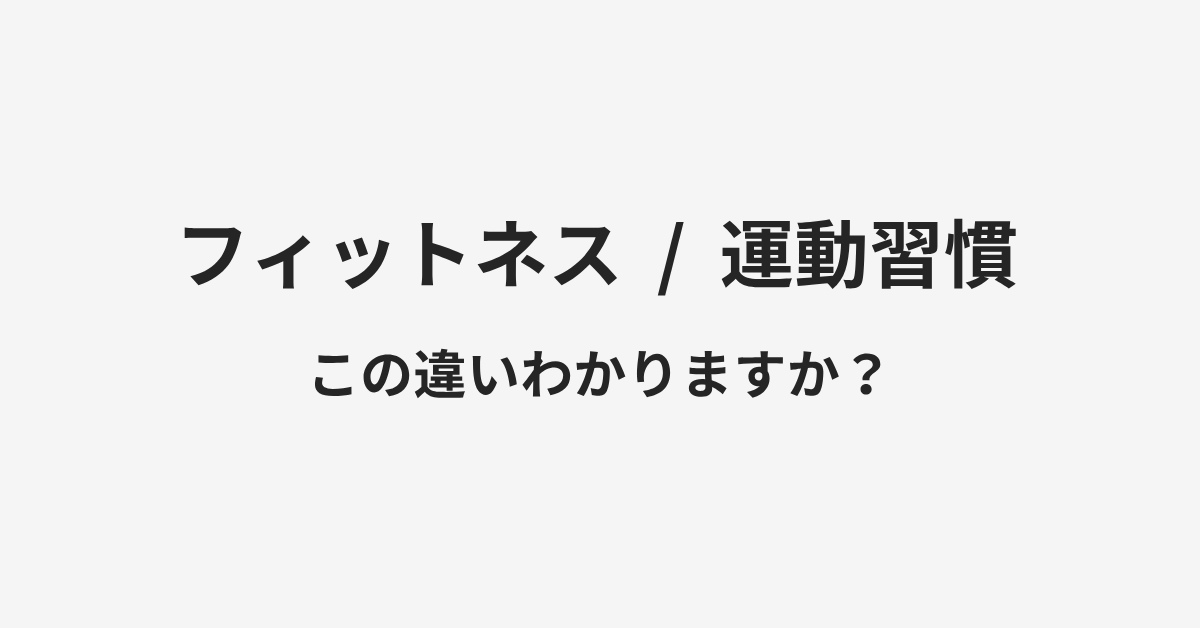
フィットネスと運動習慣の分かりやすい違い
フィットネスと運動習慣は関連はありますが、概念の範囲と焦点が異なります。フィットネスは健康や体力向上のための活動全般とその文化・産業を指します。
運動習慣は、個人が定期的に運動を行う行動パターンに焦点を当てた表現です。スポーツビジネスでは、産業やサービスを語る際はフィットネス、個人の健康行動を語る際は運動習慣という使い分けが適切です。
フィットネスとは?
フィットネスは、英語のFitnessから来た言葉で、健康で活動的な生活を送るための体力・健康状態、およびそれを向上させる活動全般を指します。有酸素運動、筋力トレーニング、柔軟性向上、栄養管理など、包括的なアプローチが特徴です。単なる運動を超えて、ライフスタイルとしての側面も含みます。
日本のフィットネス産業は、約4500億円の市場規模を持ち、フィットネスクラブ、24時間ジム、パーソナルトレーニング、オンラインフィットネスなど、多様なサービスが展開されています。特にコロナ禍以降、ホームフィットネスやデジタルフィットネスが急成長し、新たなビジネスモデルが生まれています。
フィットネスは文化としても定着しており、フィットネスウェア、サプリメント、フィットネス機器など、関連産業も巨大です。SNSでのフィットネスインフルエンサーの影響力も大きく、若い世代を中心にフィットネスがファッションやライフスタイルの一部となっています。
フィットネスの例文
- ( 1 ) 新しいフィットネスクラブがオープンしました。
- ( 2 ) 最新設備を備えたフィットネス施設は、地域の健康拠点になります。
- ( 3 ) フィットネスアプリの開発を進めています。
- ( 4 ) 自宅でできるフィットネスプログラムの需要は高まっています。
- ( 5 ) 企業のフィットネス補助制度を導入しました。
- ( 6 ) 従業員のフィットネス活動支援は、健康経営の一環です。
フィットネスの会話例
運動習慣とは?
運動習慣は、定期的かつ継続的に運動を行う生活パターンを指す日本語の表現です。週に何回、どのくらいの時間運動するかという行動面に焦点を当てており、健康維持・増進のための基本的な生活習慣として位置づけられます。厚生労働省の健康日本21でも、運動習慣の定着が重要な目標とされています。
運動習慣の形成は、個人の健康管理において重要な要素です。週2回以上、1回30分以上の運動を継続的に行うことが推奨されており、これには散歩、ジョギング、水泳、体操など、様々な活動が含まれます。習慣化することで、生活の一部として自然に運動できるようになることが目標です。
企業の健康経営や自治体の健康施策では、運動習慣の定着支援が重要なテーマとなっています。歩数計の配布、運動教室の開催、インセンティブプログラムなど、様々な取り組みが行われています。医療費削減の観点からも、運動習慣の普及は社会的課題として認識されています。
運動習慣の例文
- ( 1 ) 社員の運動習慣調査を実施します。
- ( 2 ) 運動習慣の実態把握は、健康施策立案の第一歩です。
- ( 3 ) 運動習慣を身につけるコツを教えてください。
- ( 4 ) 小さく始めて徐々に増やすことが、運動習慣定着の秘訣です。
- ( 5 ) 地域の運動習慣向上プログラムを開始しました。
- ( 6 ) 住民の運動習慣改善は、医療費削減にもつながります。
運動習慣の会話例
フィットネスと運動習慣の違いまとめ
フィットネスと運動習慣は、産業・文化と個人の行動という異なる視点を持つ関連概念です。フィットネスは商業的でライフスタイル的な側面が強く、運動習慣は健康行動としての側面が強いです。
両者は補完関係にあり、フィットネス産業が運動習慣の形成を支援する構造になっています。
スポーツビジネスでは、BtoCサービスではフィットネス、健康施策では運動習慣という使い分けが効果的です。
フィットネスと運動習慣の読み方
- フィットネス(ひらがな):ふぃっとねす
- フィットネス(ローマ字):fittonesu
- 運動習慣(ひらがな):うんどうしゅうかん
- 運動習慣(ローマ字):unndoushuukann