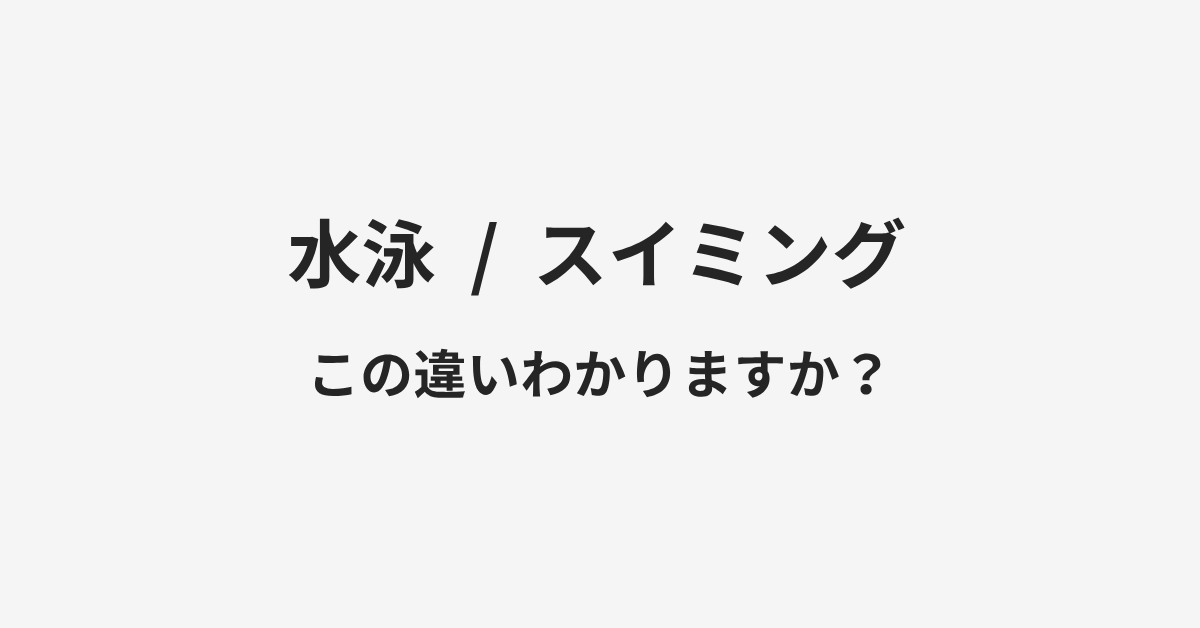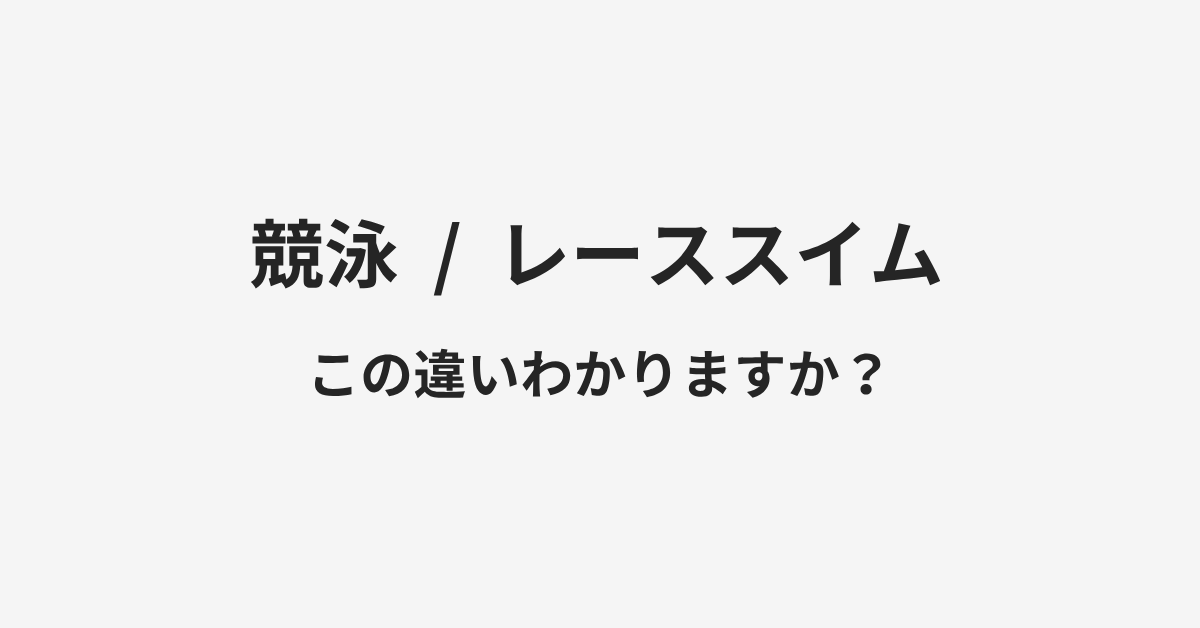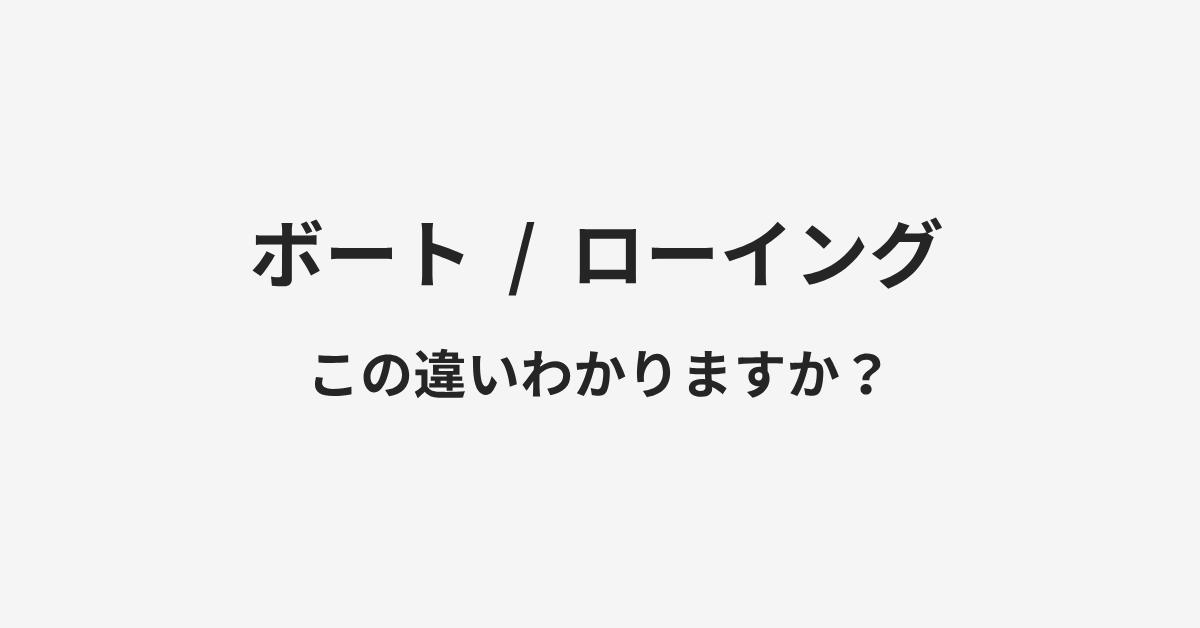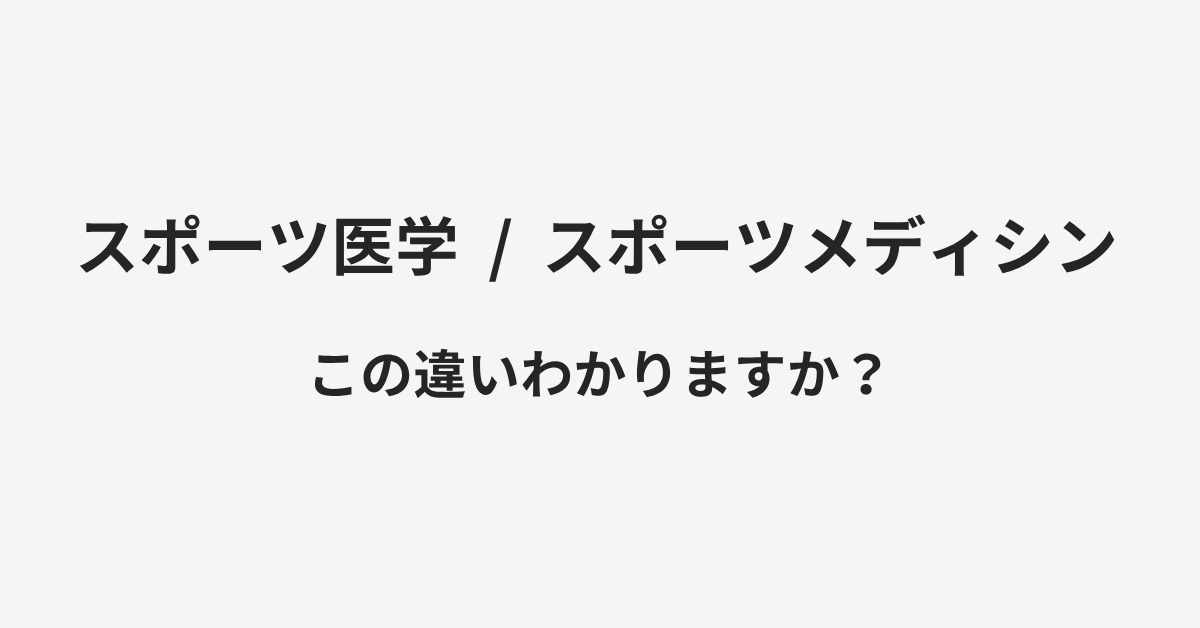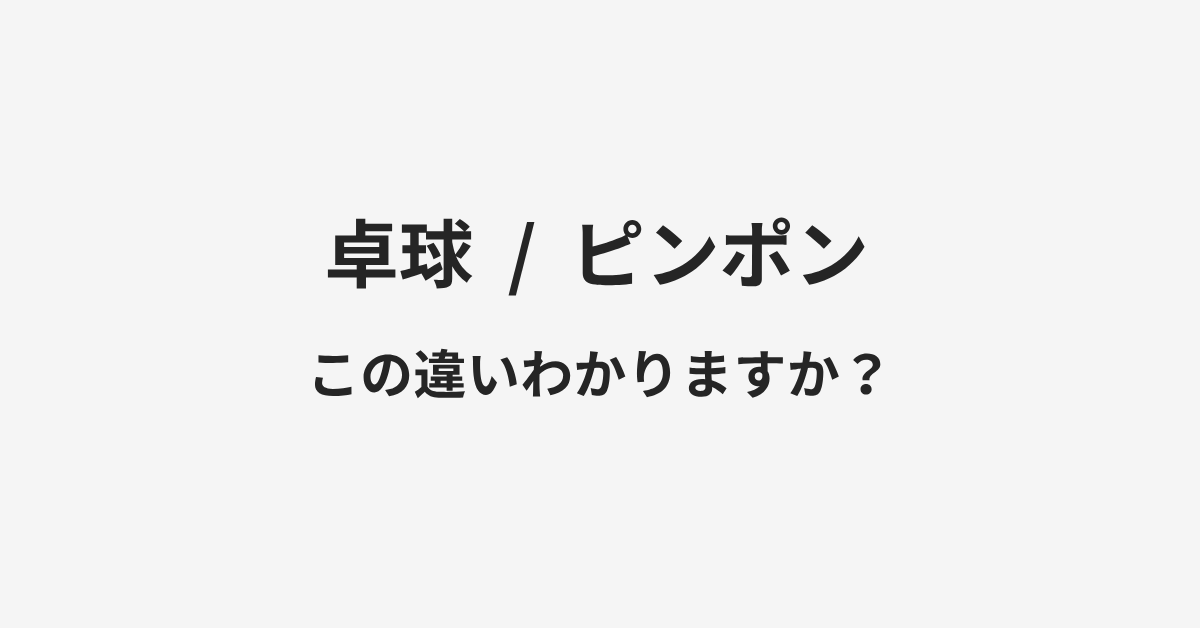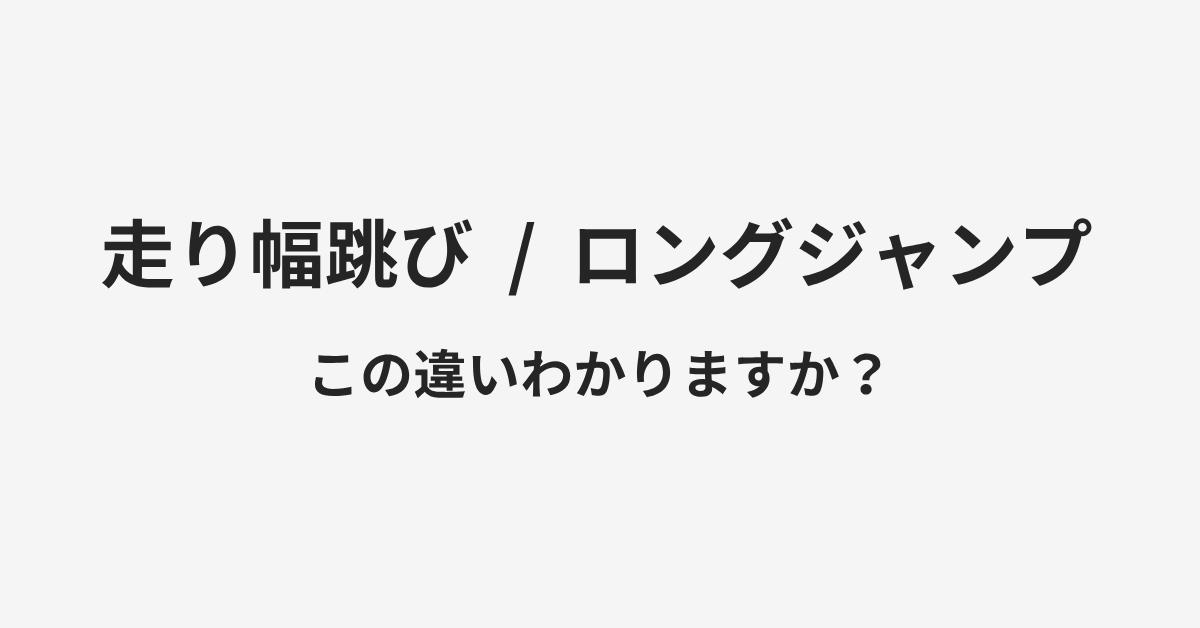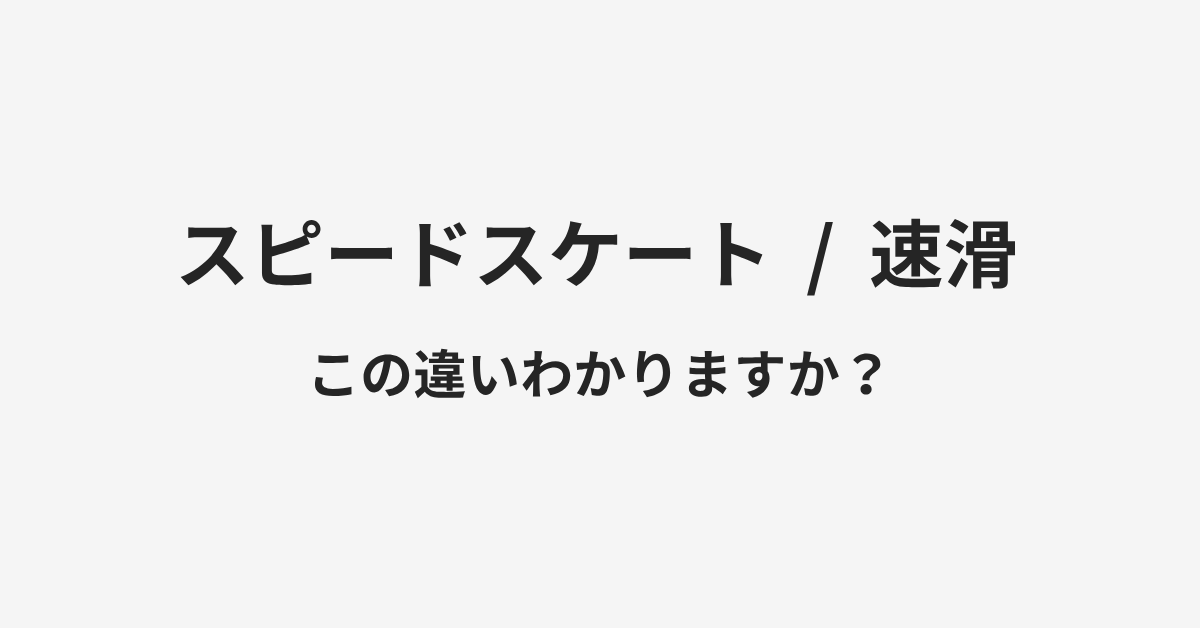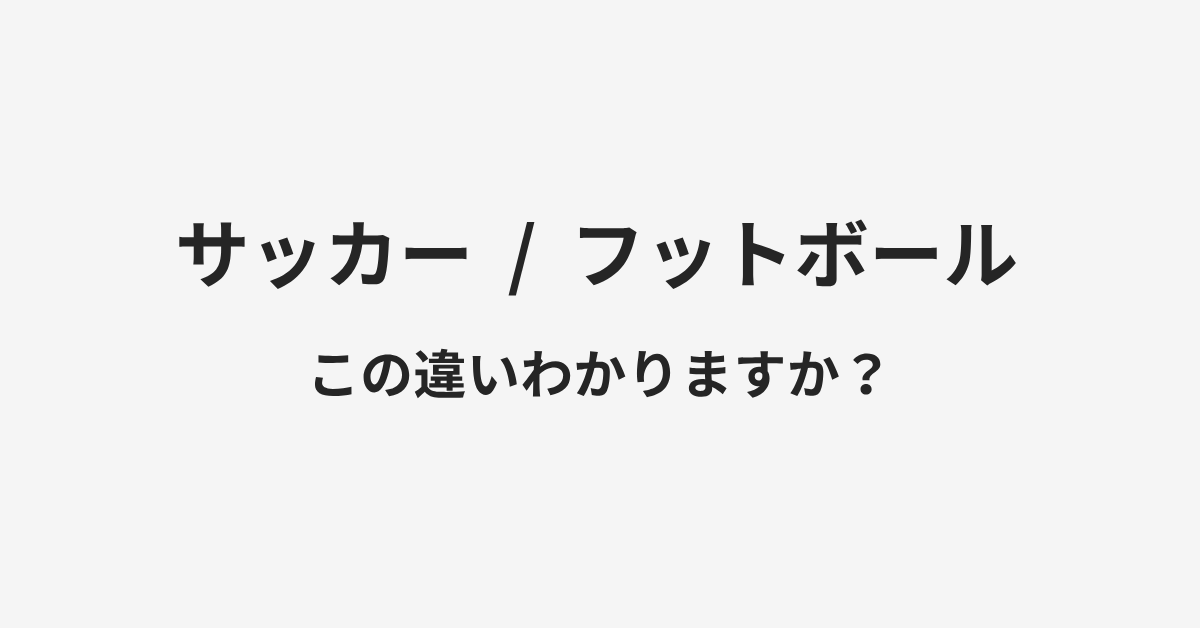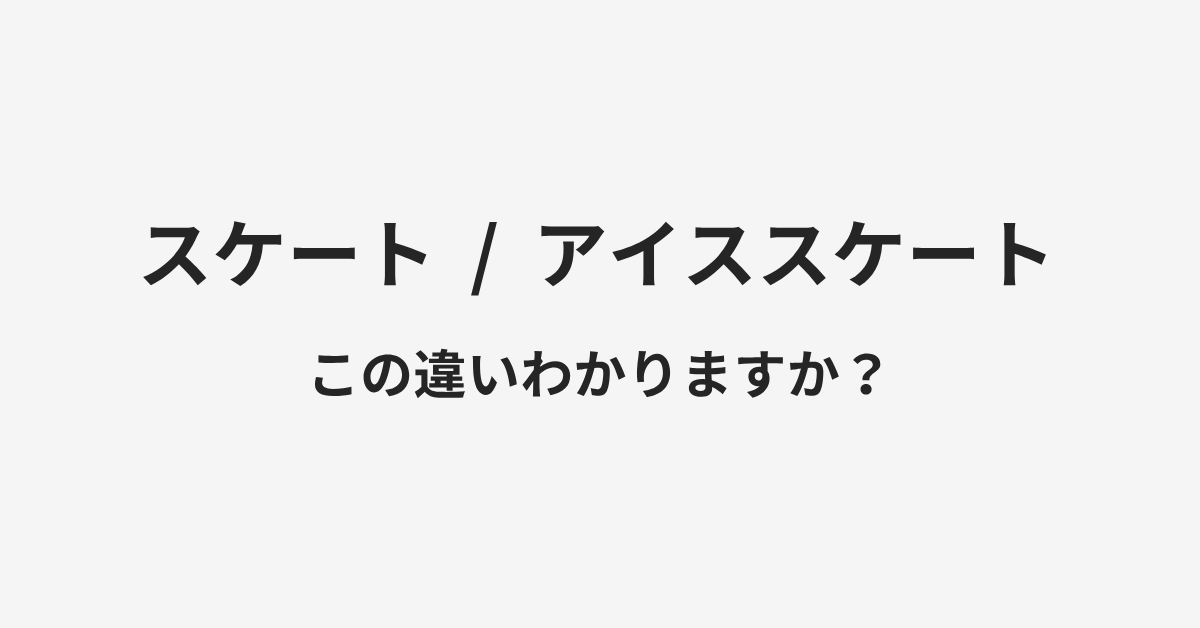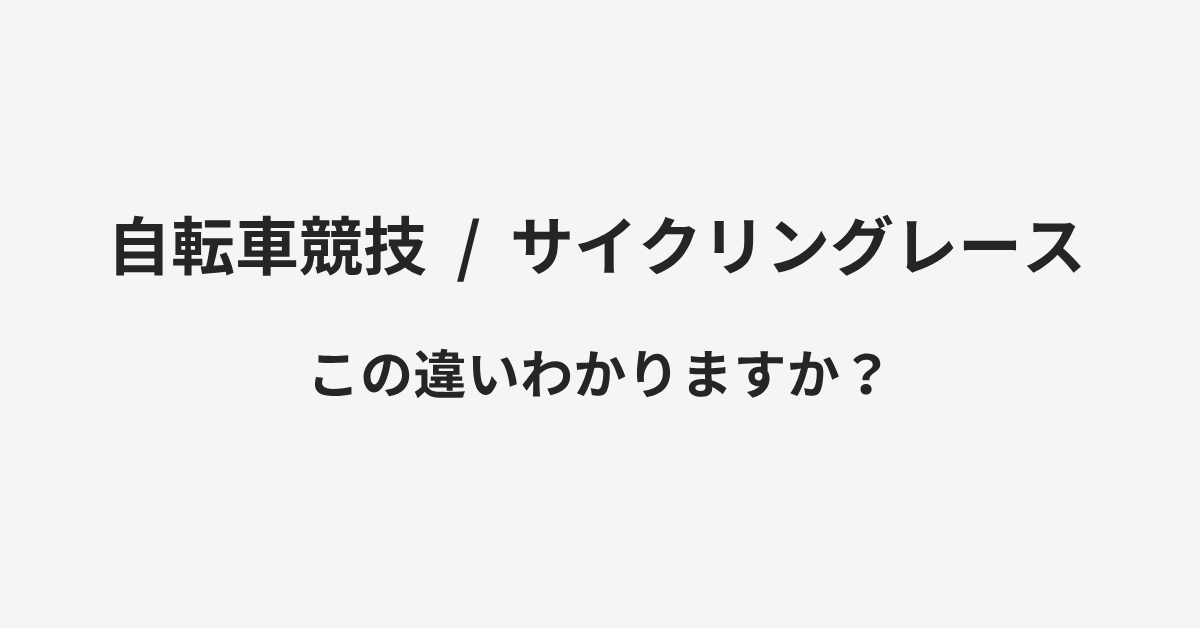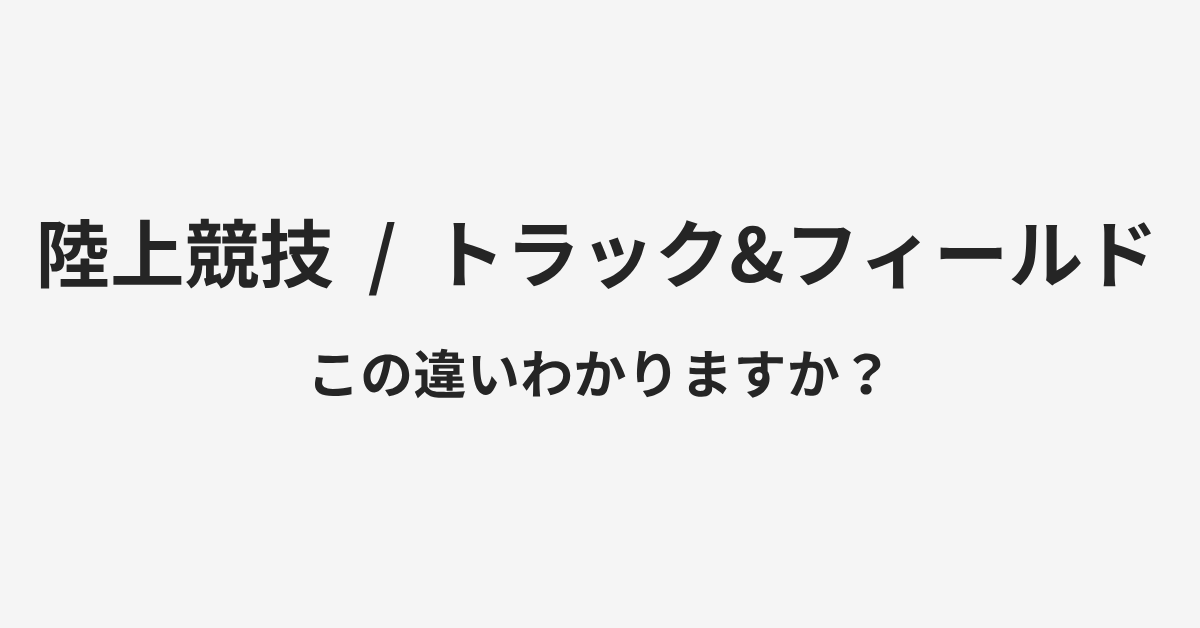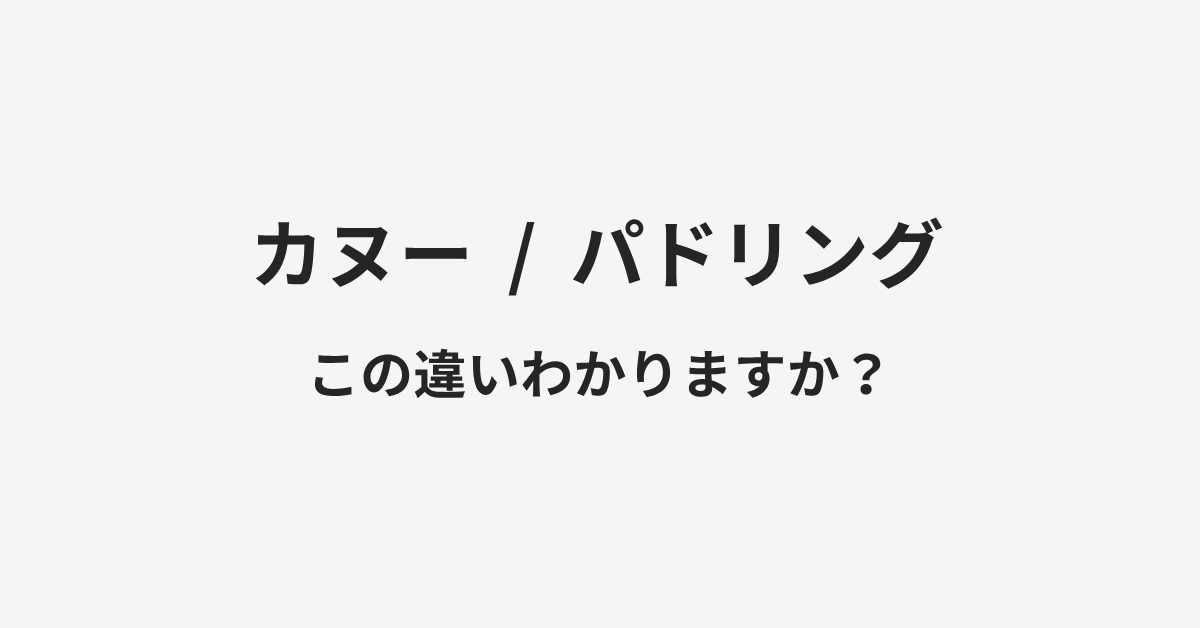【サーフィン】と【波乗り】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
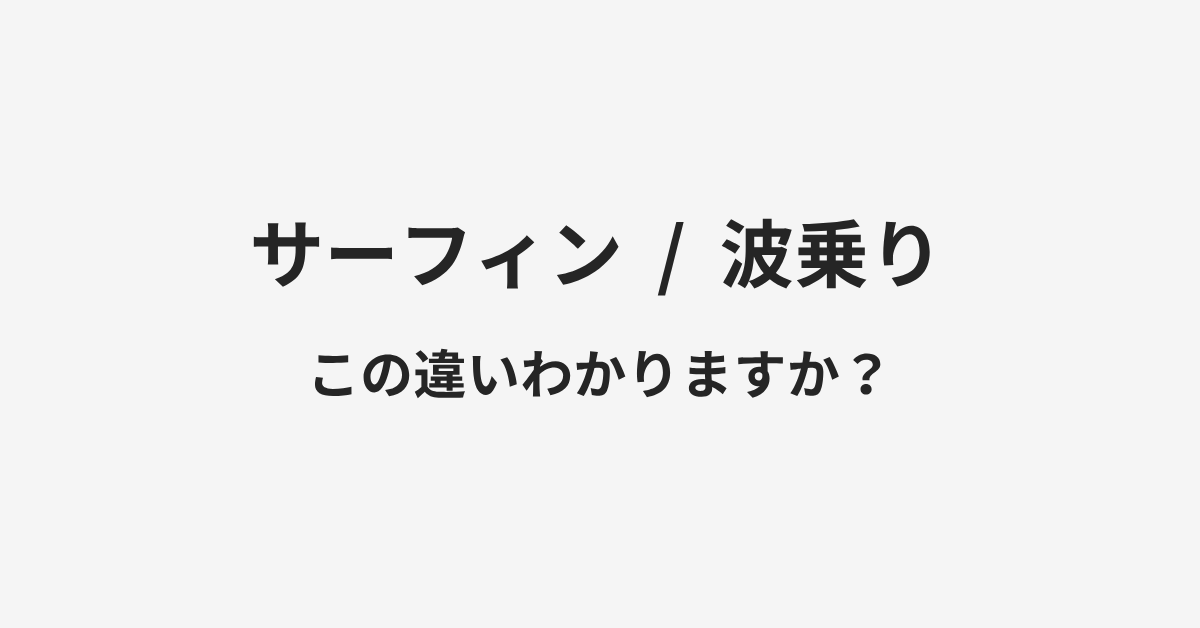
サーフィンと波乗りの分かりやすい違い
サーフィンと波乗りは同じ海のスポーツを指しますが、国際性と文化的ニュアンスが異なります。サーフィンは英語由来の国際的な呼称で、オリンピック種目名でもあります。
波乗りは日本語の表現で、より詩的で親しみやすい印象を与えます。スポーツビジネスでは、公式競技や国際的な文脈ではサーフィン、日本の文化的側面を強調する場合は波乗りという使い分けが見られます。
サーフィンとは?
サーフィンは、サーフボードに乗って波に乗るウォータースポーツです。ハワイ発祥の文化として世界中に広まり、2020年東京オリンピックから正式種目となりました。ショートボード、ロングボード、ビッグウェーブなど様々なスタイルがあり、波の状態を読む力、バランス感覚、瞬発力が求められます。日本のサーフィンは、1960年代から本格的に始まり、現在では約200万人の愛好者がいるとされています。
千葉、湘南、宮崎などが主要なサーフポイントで、プロサーファーも多数活躍しています。日本サーフィン連盟(NSA)が競技を統括し、国内大会から世界大会への選手派遣まで行っています。ビジネス面では、サーフィンは大きな産業を形成しています。
サーフボード、ウェットスーツ、アクセサリーの製造販売、サーフショップ、スクール運営、サーフトリップツアーなど多岐にわたります。また、サーフィンのライフスタイルを提案するアパレルブランドも人気で、ファッション業界とも密接に関連しています。
サーフィンの例文
- ( 1 ) プロサーフィン大会の日本開催が決定しました。
- ( 2 ) 世界トップのサーフィン技術を間近で見られる貴重な機会です。
- ( 3 ) サーフィンスクールの生徒募集を開始します。
- ( 4 ) 初心者でも安全にサーフィンを楽しめる環境を提供します。
- ( 5 ) オリンピックサーフィン競技の会場整備が進んでいます。
- ( 6 ) 国際基準のサーフィン施設は、地域活性化にも貢献します。
サーフィンの会話例
波乗りとは?
波乗りは、サーフィンを日本語で表現した言葉で、文字通り波に乗るという意味です。この表現には、自然と一体になるという東洋的な思想が込められており、単なるスポーツを超えた精神的な側面を含んでいます。日本の海の文化と結びついた、詩的で哲学的な響きがあります。日本では古くから、漁師が舟で波を乗り越える技術を波乗りと呼んでいました。
現代のサーフィンが伝わってからも、この言葉が使われるようになり、特に年配の方や伝統を重視する文脈では、波乗りという表現が好まれます。地域によっては、サーフィンよりも波乗りの方が通じやすい場合もあります。
文化的には、波乗りという表現は日本独自のサーフィン文化を表しています。波乗り道のような精神性を重視する考え方や、自然への畏敬の念を持つ日本的なアプローチを示す際に使われます。ただし、競技やビジネスの場面では、国際的に通用するサーフィンが一般的です。
波乗りの例文
- ( 1 ) 地元の波乗り文化を次世代に伝えたいです。
- ( 2 ) 日本独自の波乗りの精神性は、大切な文化遺産です。
- ( 3 ) 波乗り体験ツアーを企画しています。
- ( 4 ) 自然と一体になる波乗りの魅力を、多くの人に伝えたいです。
- ( 5 ) 昔から波乗りが盛んな地域です。
- ( 6 ) 伝統的な波乗り文化は、地域の誇りですね。
波乗りの会話例
サーフィンと波乗りの違いまとめ
サーフィンと波乗りは、国際的呼称と日本的表現という違いがある同じスポーツです。公式競技やビジネスシーンではサーフィン、日本の文化的文脈や親しみやすさを演出する場合は波乗りが適切です。
使い分けることで、対象に応じた効果的なコミュニケーションが可能になります。
スポーツビジネスでは、グローバル展開にはサーフィン、地域密着や日本らしさの表現には波乗りという戦略的な使い分けが有効です。
サーフィンと波乗りの読み方
- サーフィン(ひらがな):さーふぃん
- サーフィン(ローマ字):sa-finn
- 波乗り(ひらがな):なみのり
- 波乗り(ローマ字):naminori