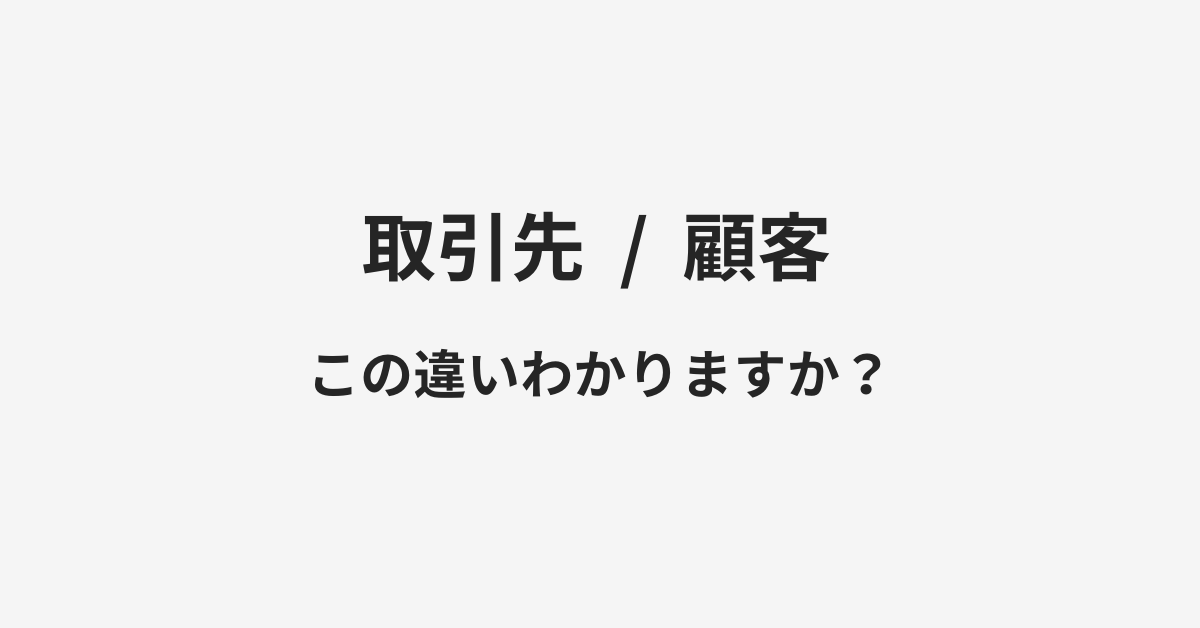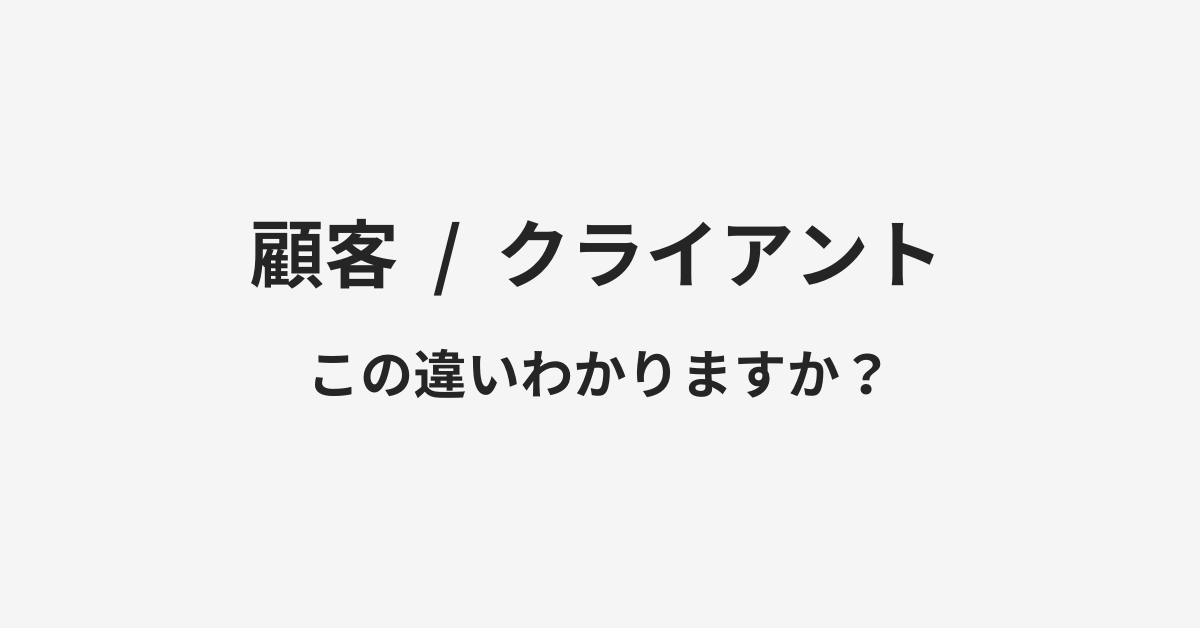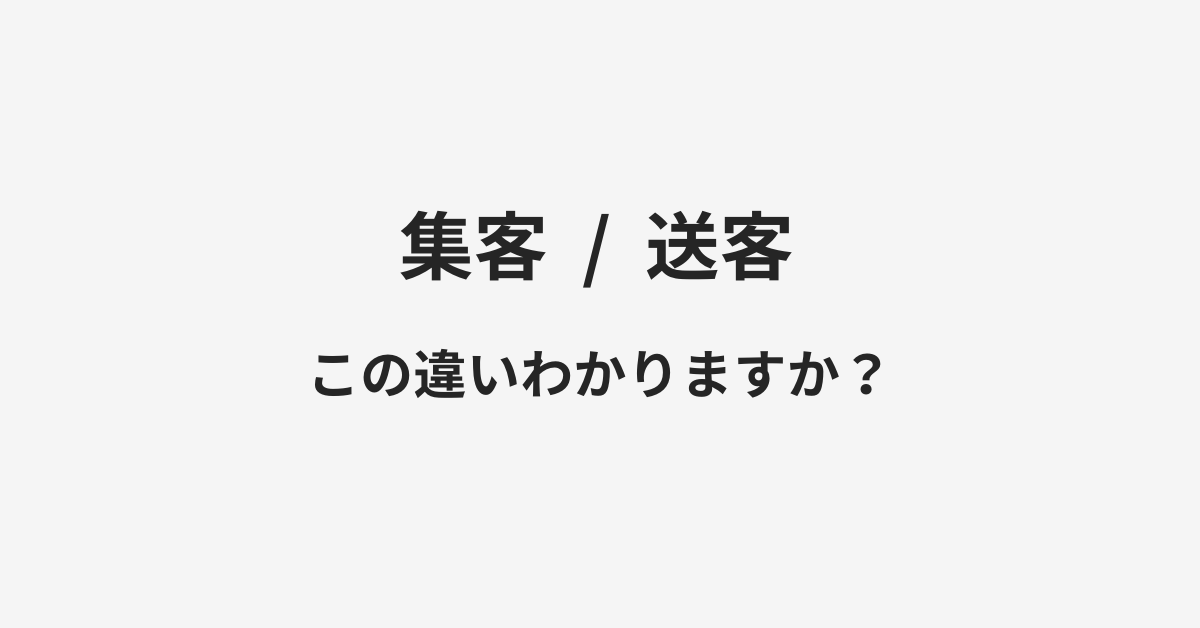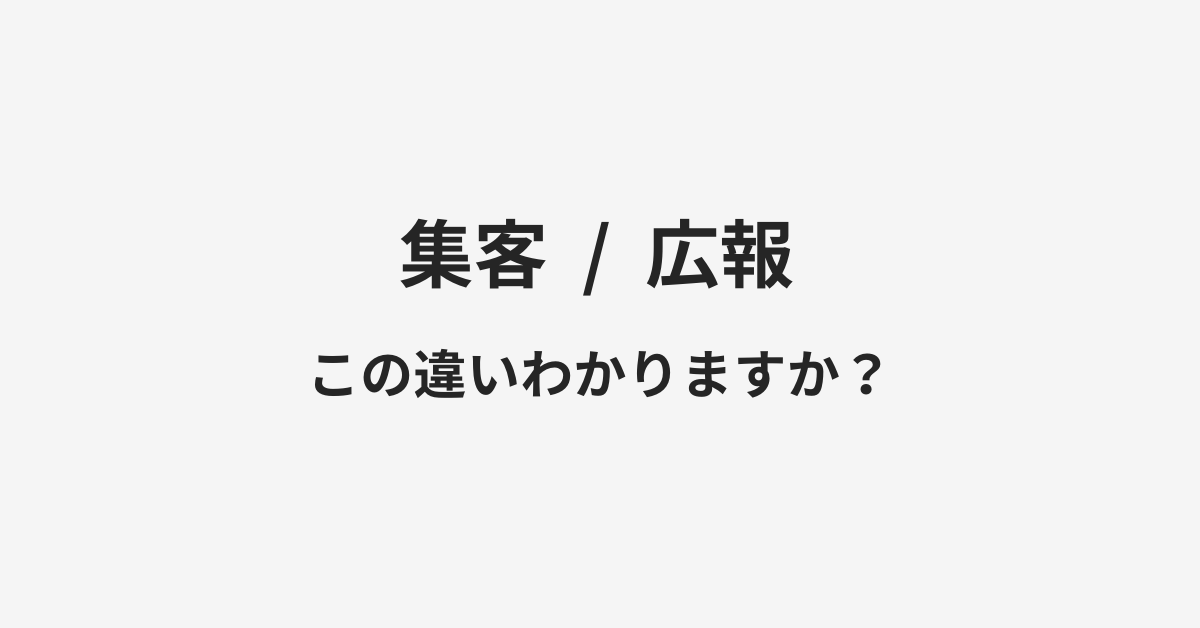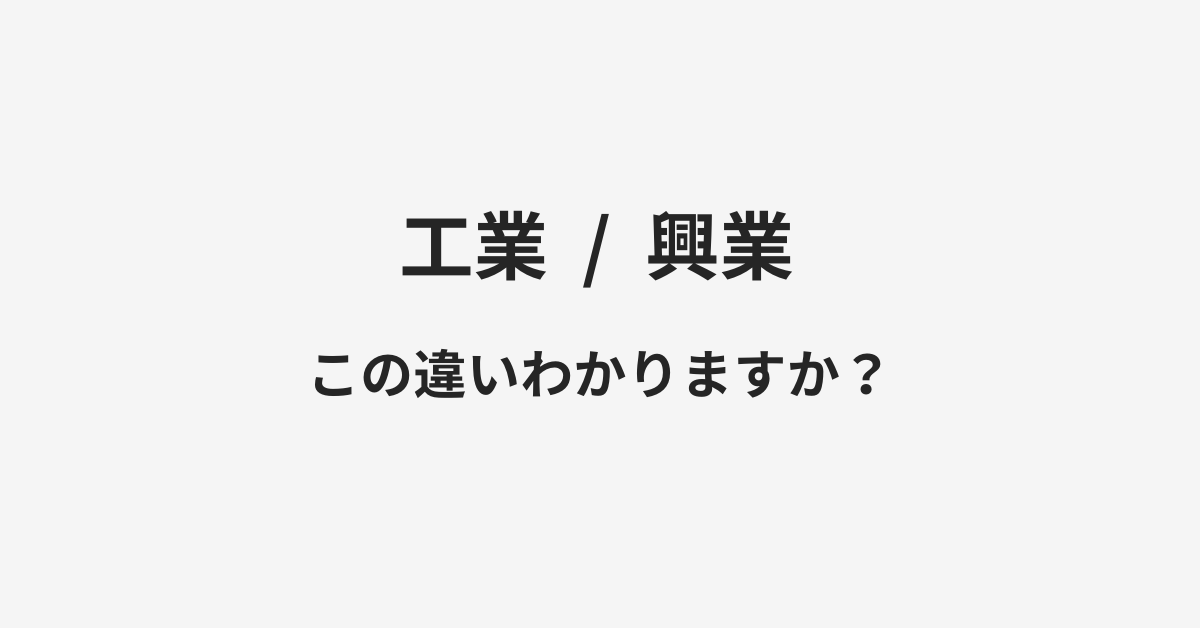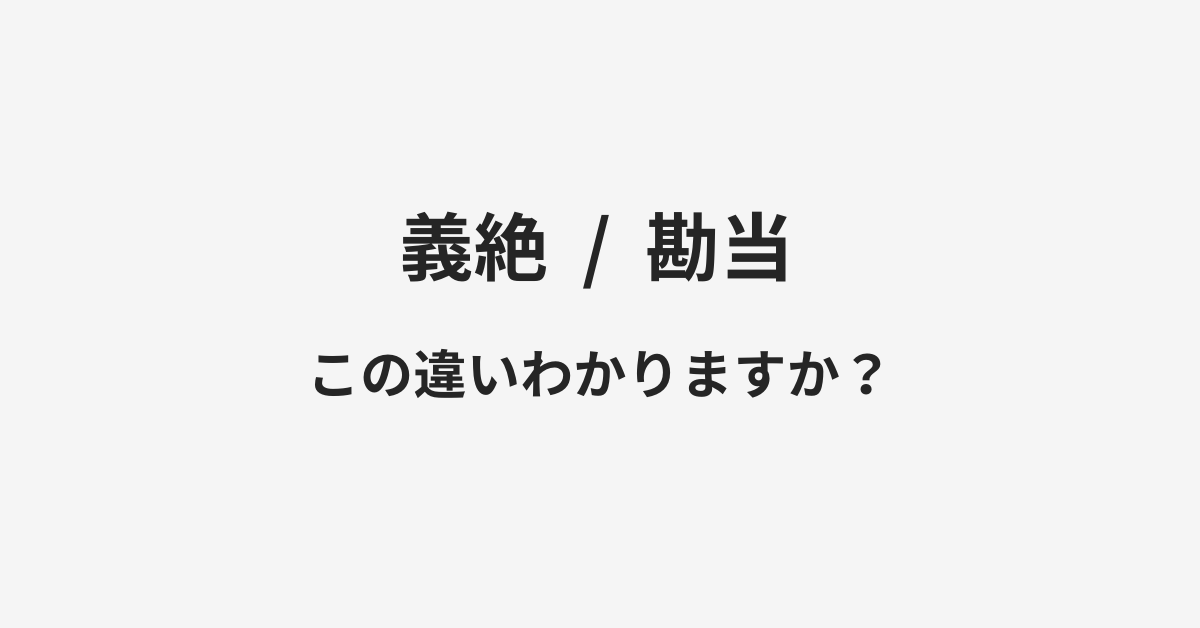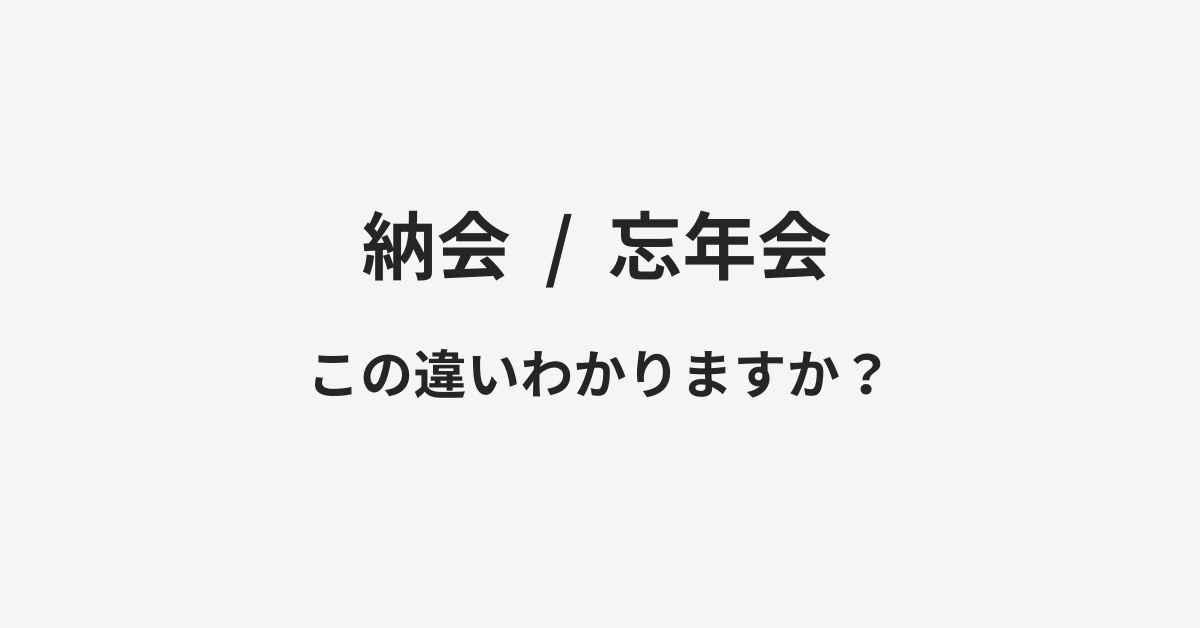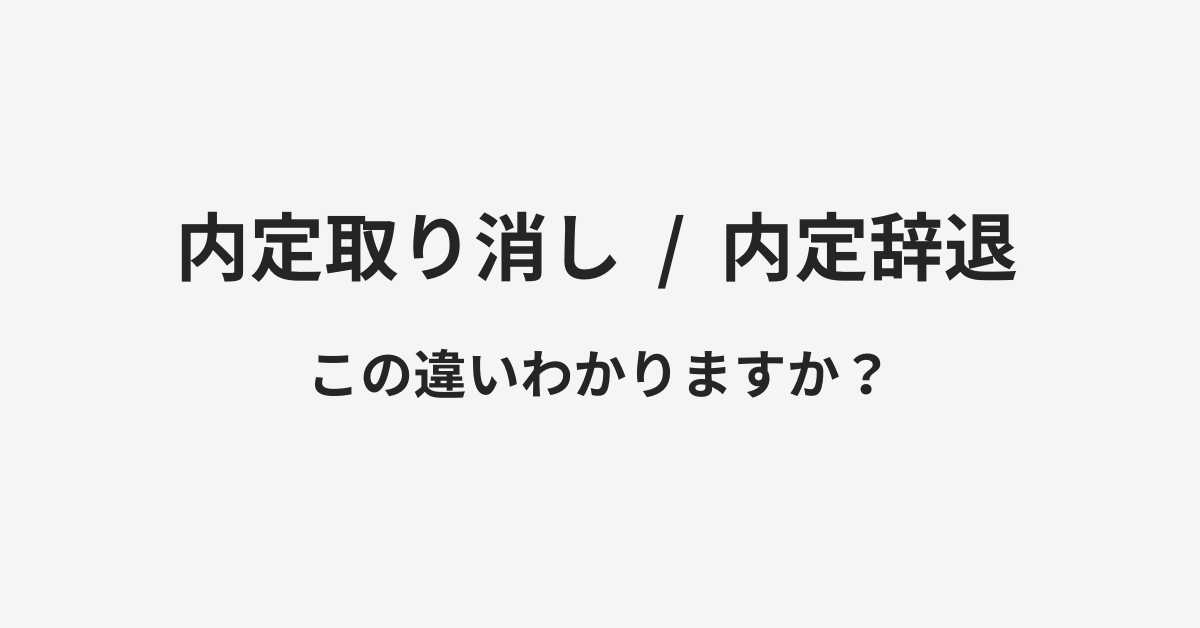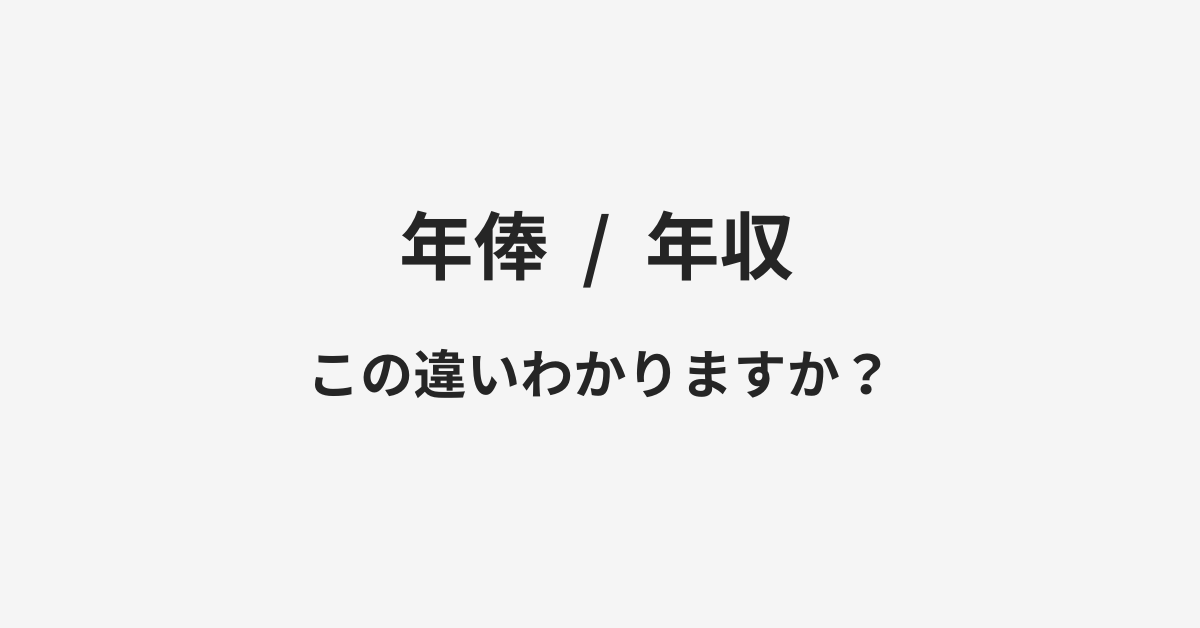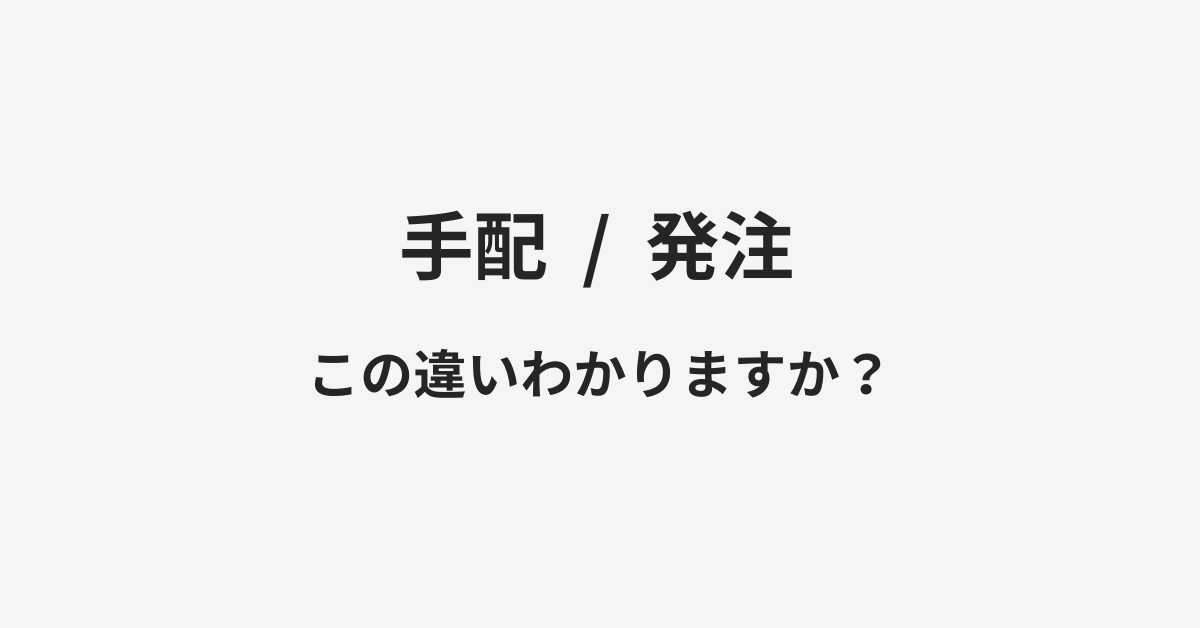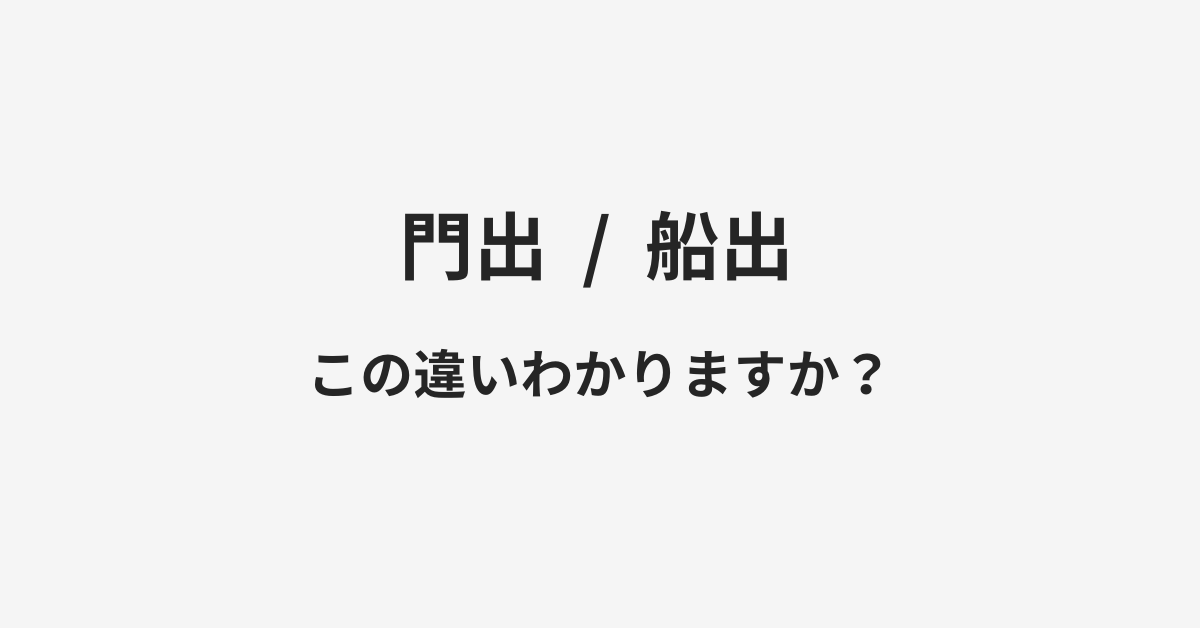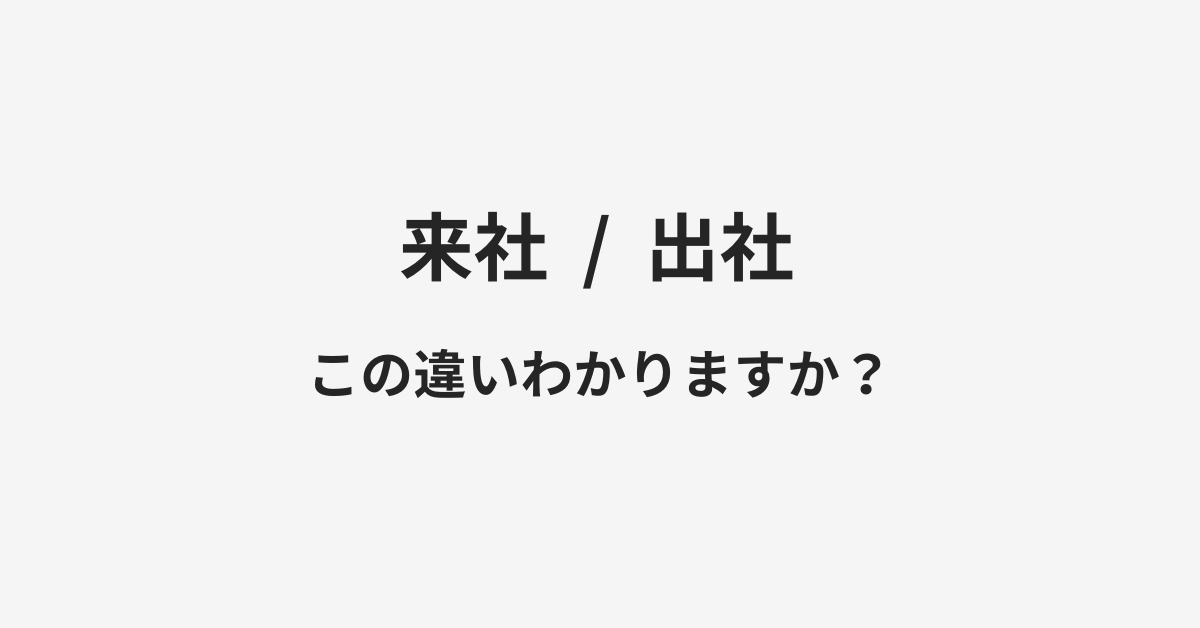【常連客】と【得意客】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
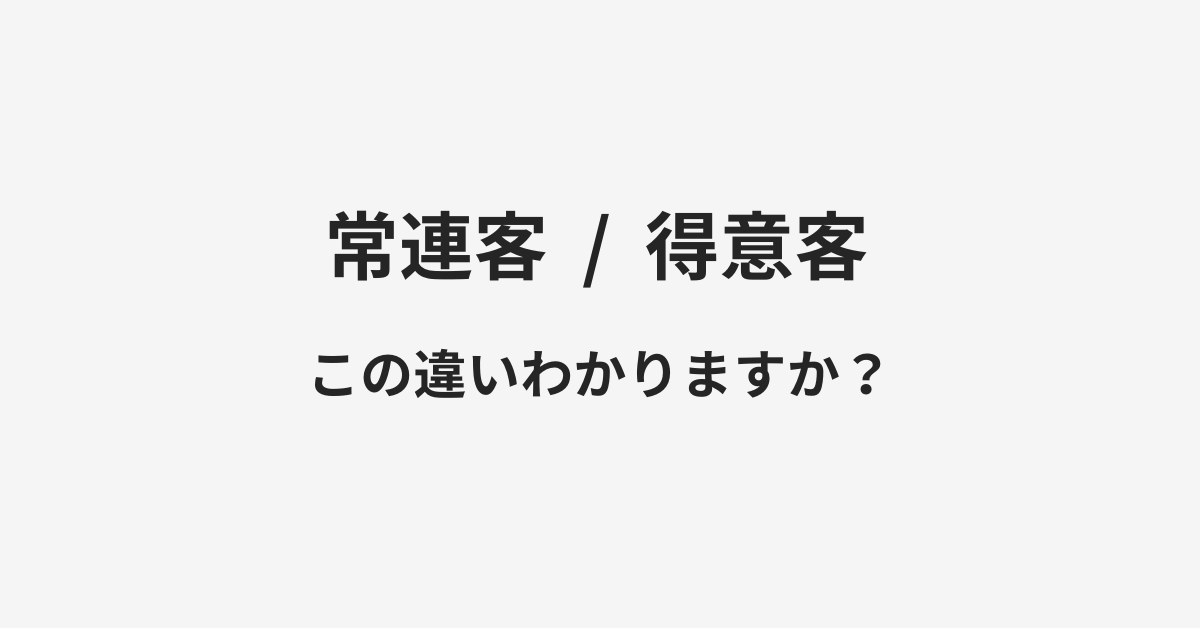
常連客と得意客の分かりやすい違い
常連客と得意客は、どちらも重要な顧客を表しますが、その評価基準と関係性に違いがあります。
常連客は来店頻度が高く親密な関係の顧客で、得意客は取引金額が大きく売上に貢献する顧客です。前者は頻度と親密性、後者は金額と重要性を重視します。
顧客管理において、この違いを理解することは、適切なサービス提供と効果的な営業戦略の立案に重要です。
常連客とは?
常連客とは、店舗やサービスを頻繁に利用する馴染みの顧客を指します。飲食店、美容院、小売店などで多く使われ、定期的な来店により店側と親密な関係を築いている顧客です。来店頻度は高いが、必ずしも購買金額が大きいとは限らず、むしろ顔なじみという関係性が重視されます。
常連客の特徴は、商品・サービスへの愛着、スタッフとの信頼関係、口コミによる新規顧客紹介などです。常連客は安定的な売上基盤となり、新メニューのフィードバック、繁閑の平準化などにも貢献します。常連客優遇として、サービスの提供、新商品の先行案内などが行われます。
デジタル時代でも常連客の価値は高く、ポイントカードやアプリによる来店履歴管理、パーソナライズされたサービス提供により、常連客との関係強化が図られています。
常連客の例文
- ( 1 ) あの常連客は毎週木曜日に必ず来店されます。
- ( 2 ) 常連客の好みを把握し、パーソナライズされたサービスを提供しています。
- ( 3 ) 新規客を常連客に育てることが、安定経営の鍵です。
- ( 4 ) 常連客限定の特別メニューを用意しました。
- ( 5 ) 20年来の常連客からの紹介で、新規顧客が増えています。
- ( 6 ) 常連客との会話から、新商品のアイデアが生まれました。
常連客の会話例
得意客とは?
得意客とは、取引金額が大きく、企業の売上・利益に大きく貢献する重要顧客を指します。B2Bビジネスでは得意先とも呼ばれ、継続的かつ大口の取引を行う顧客です。パレートの法則でいう売上の80%を生み出す20%の顧客に該当することが多く、特別な対応が求められます。
得意客の特徴は、高い購買力、安定的な取引、長期的な関係性です。企業は得意客に対して、専任担当者の配置、特別価格の提供、優先的なサービス、カスタマイズ対応などを行います。得意客の維持・拡大は、経営の安定性に直結する重要課題です。
CRM(顧客関係管理)では、得意客をキーアカウントとして特別管理し、売上分析、ニーズ把握、満足度向上に努めます。得意客の離反は経営に大きな影響を与えるため、リスク管理も重要です。
得意客の例文
- ( 1 ) A社は当社の得意客で、年間売上の30%を占めています。
- ( 2 ) 得意客への対応を最優先し、専任チームを配置しました。
- ( 3 ) 得意客の要望に応えるため、カスタマイズ製品を開発しています。
- ( 4 ) 得意客向けの特別価格を設定し、長期契約を締結しました。
- ( 5 ) 得意客の業績悪化により、当社の売上にも影響が出ています。
- ( 6 ) 新たな得意客開拓のため、大手企業への提案を強化しています。
得意客の会話例
常連客と得意客の違いまとめ
常連客と得意客の主な違いは、評価の基準にあります。常連客は来店頻度と親密性、得意客は取引金額と収益貢献度で判断されます。
関係性も異なり、常連客は感情的なつながりが強く、得意客はビジネス上の重要性が高いです。小規模店舗では常連客、大企業では得意客という使い分けも一般的です。
顧客戦略では、両者への対応を使い分けることが重要です。常連客には親密なサービス、得意客には付加価値の高いサービスを提供し、それぞれの特性に応じた関係構築を図ります。
常連客と得意客の読み方
- 常連客(ひらがな):じょうれんきゃく
- 常連客(ローマ字):jourennkyaku
- 得意客(ひらがな):とくいきゃく
- 得意客(ローマ字):tokuikyaku