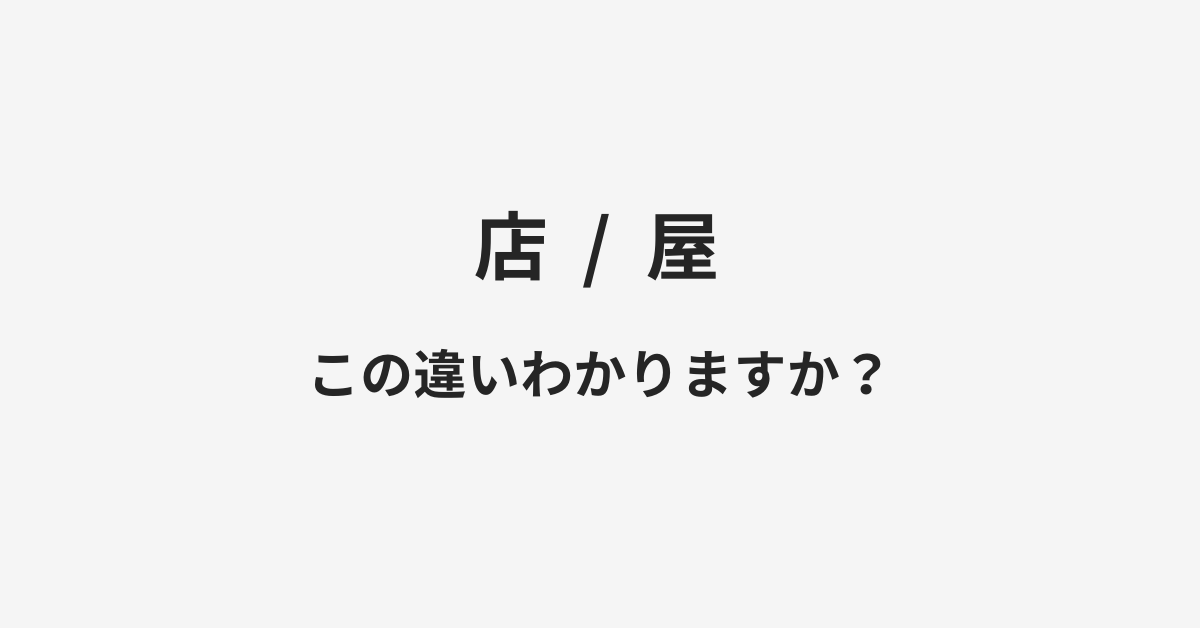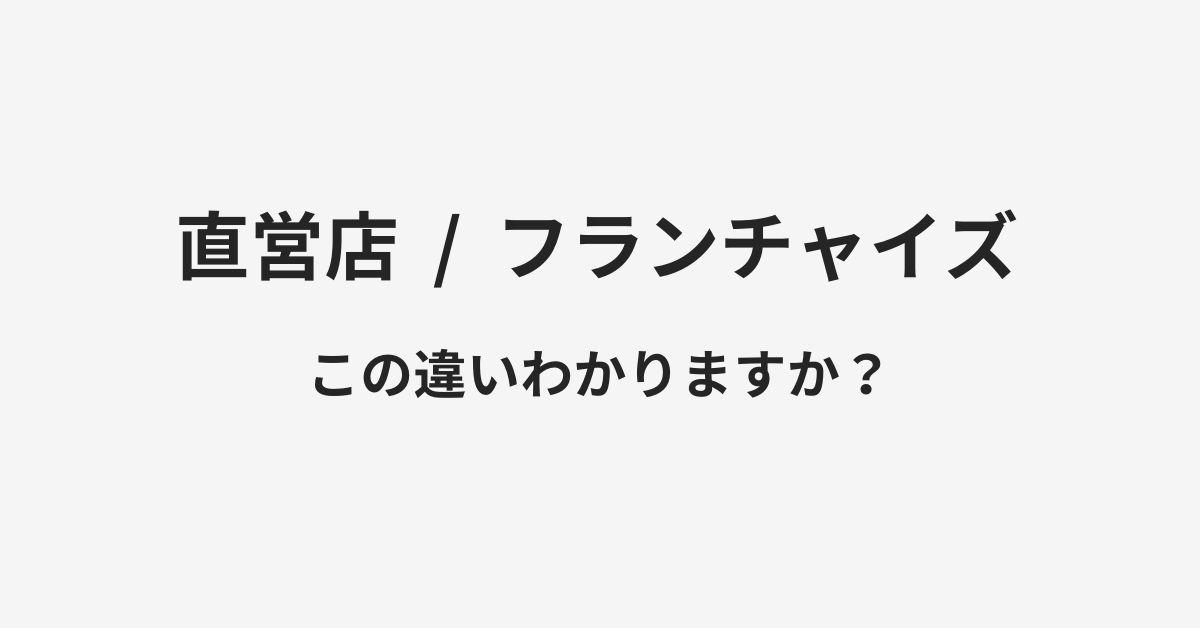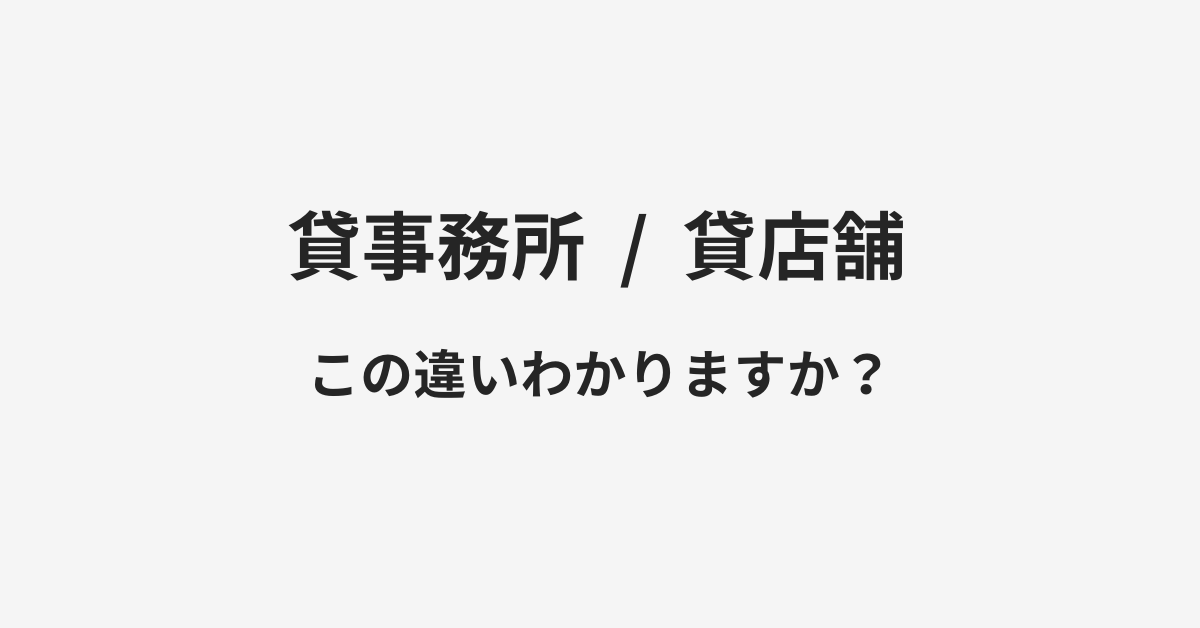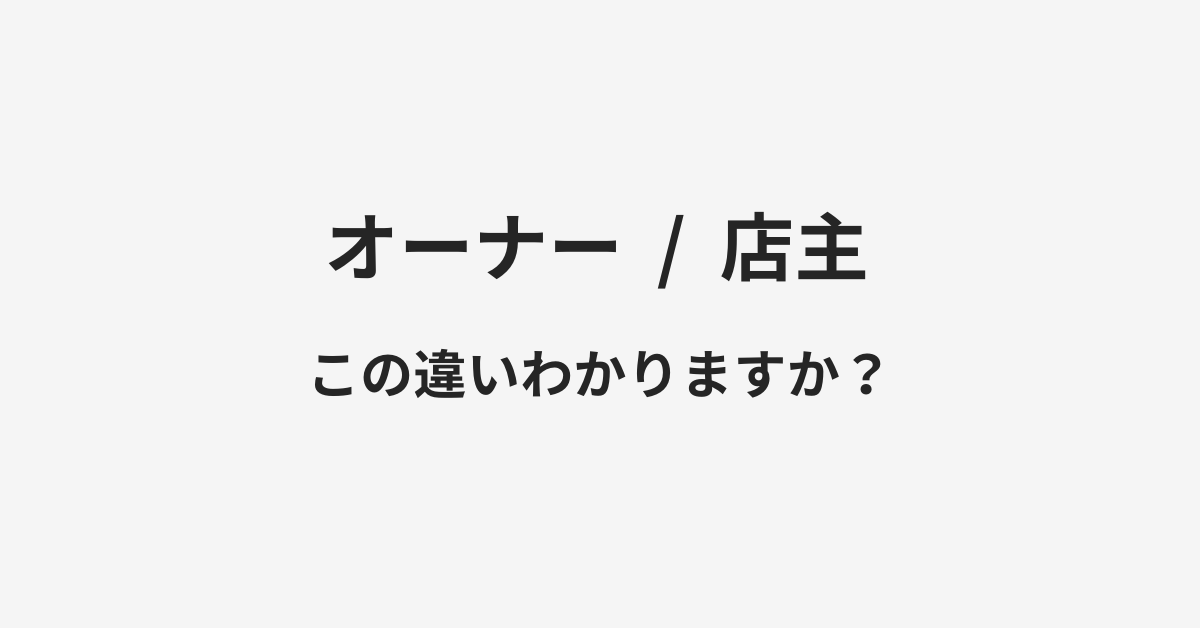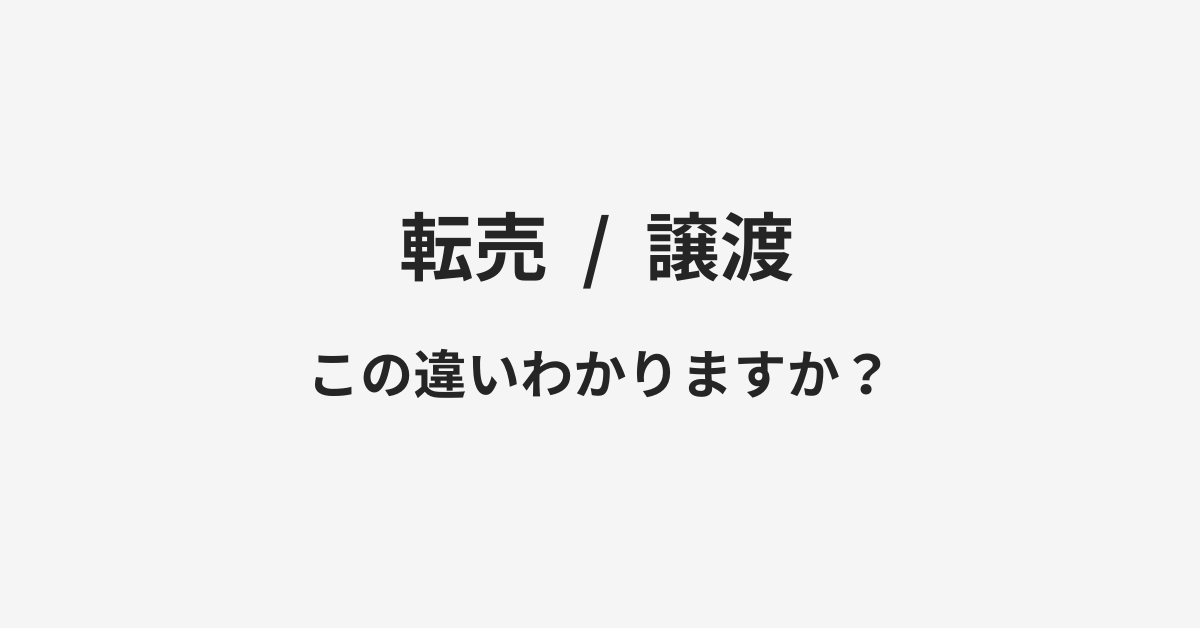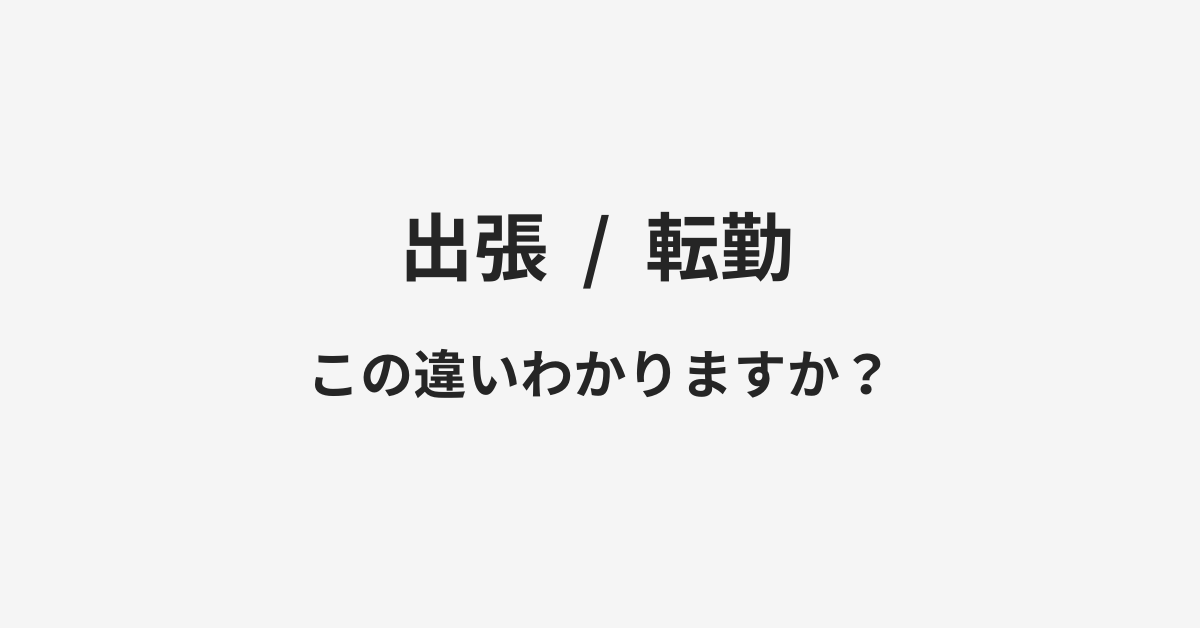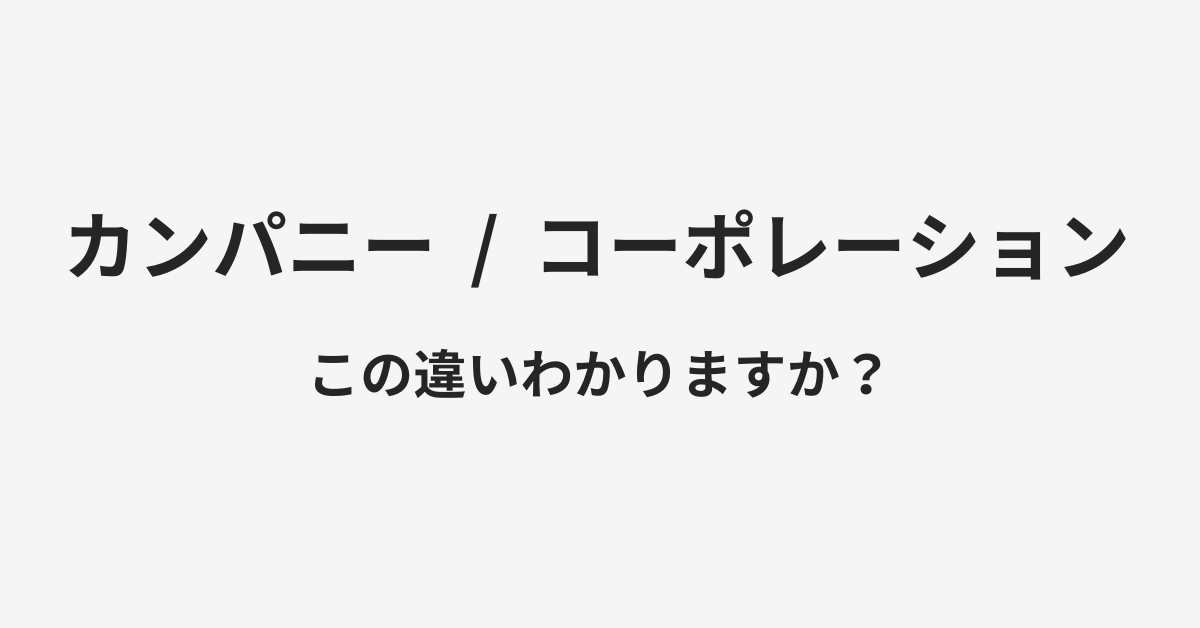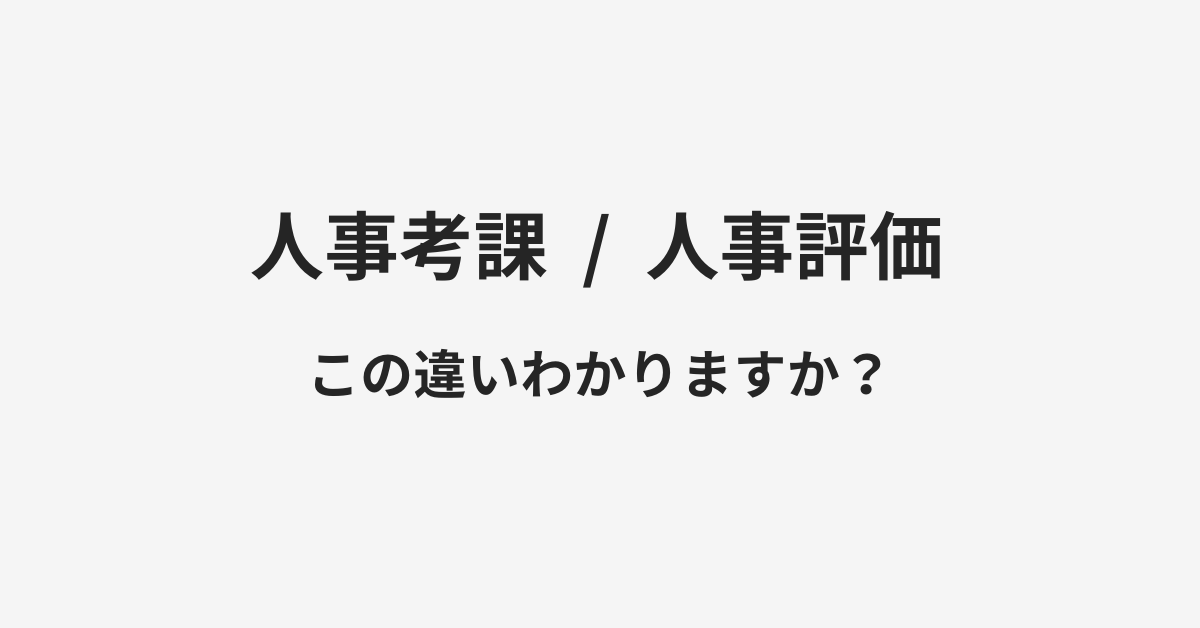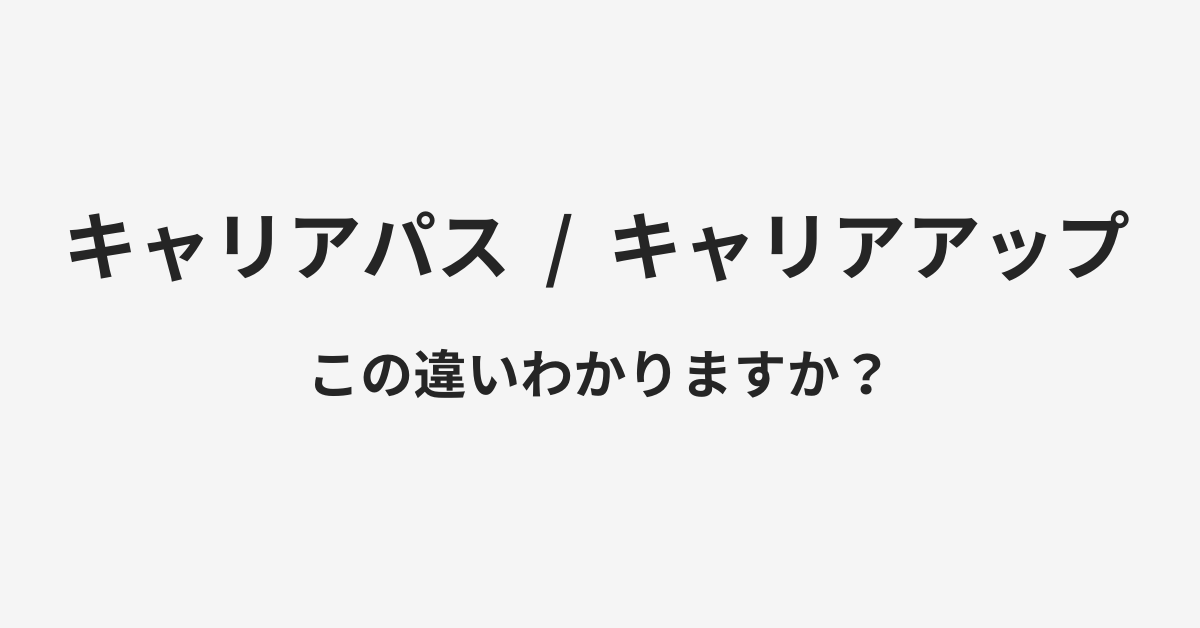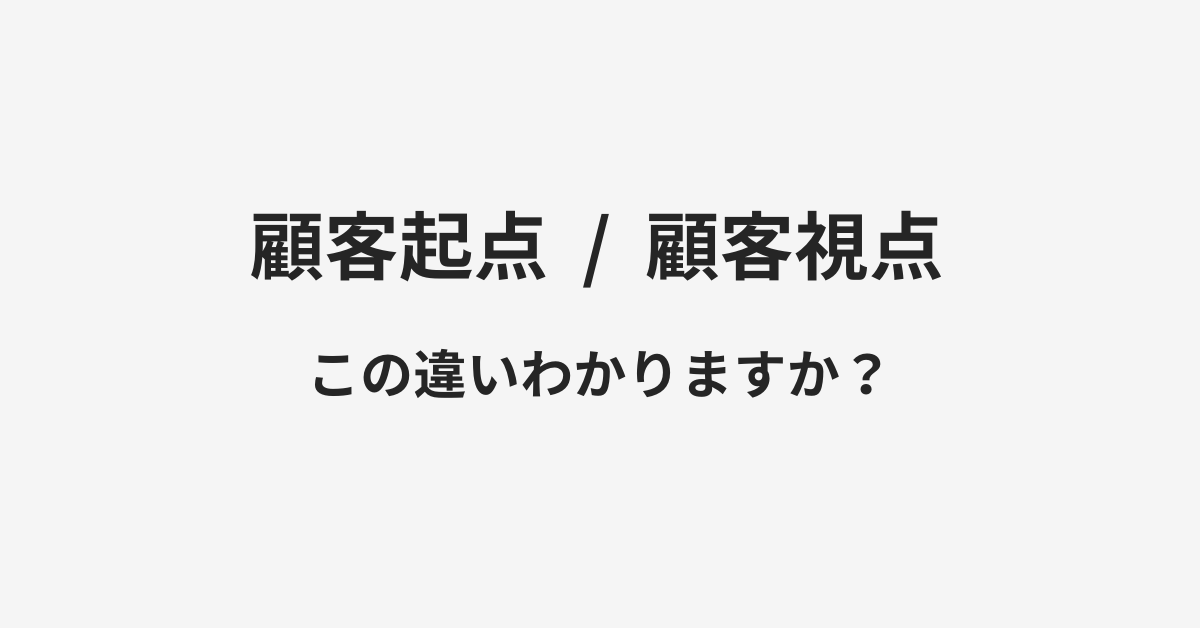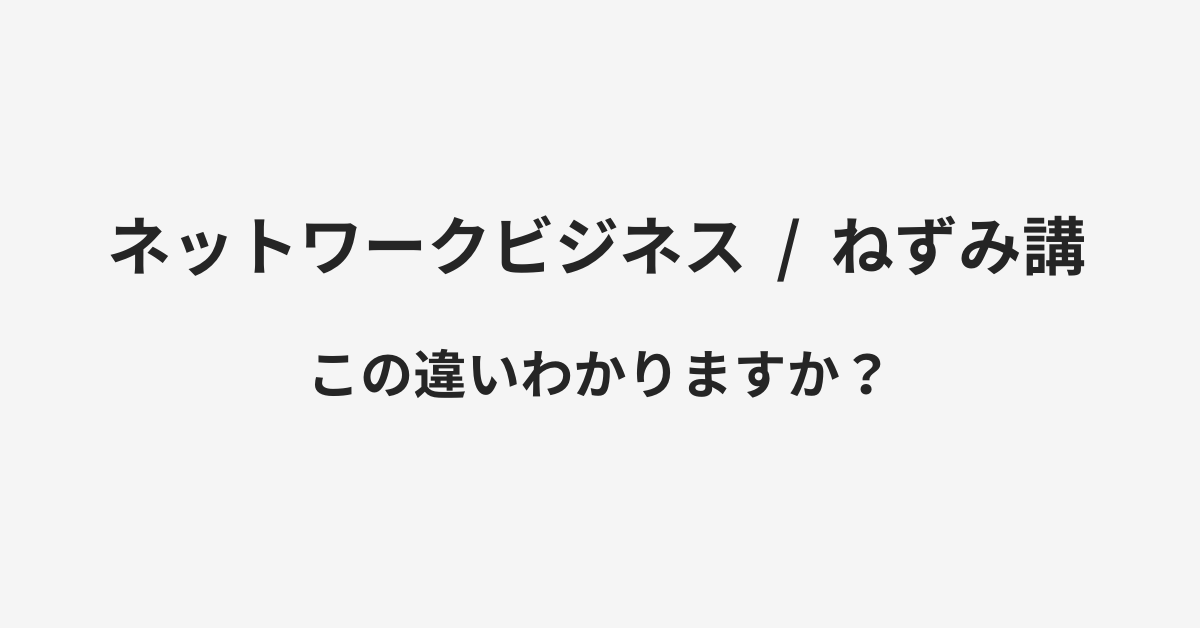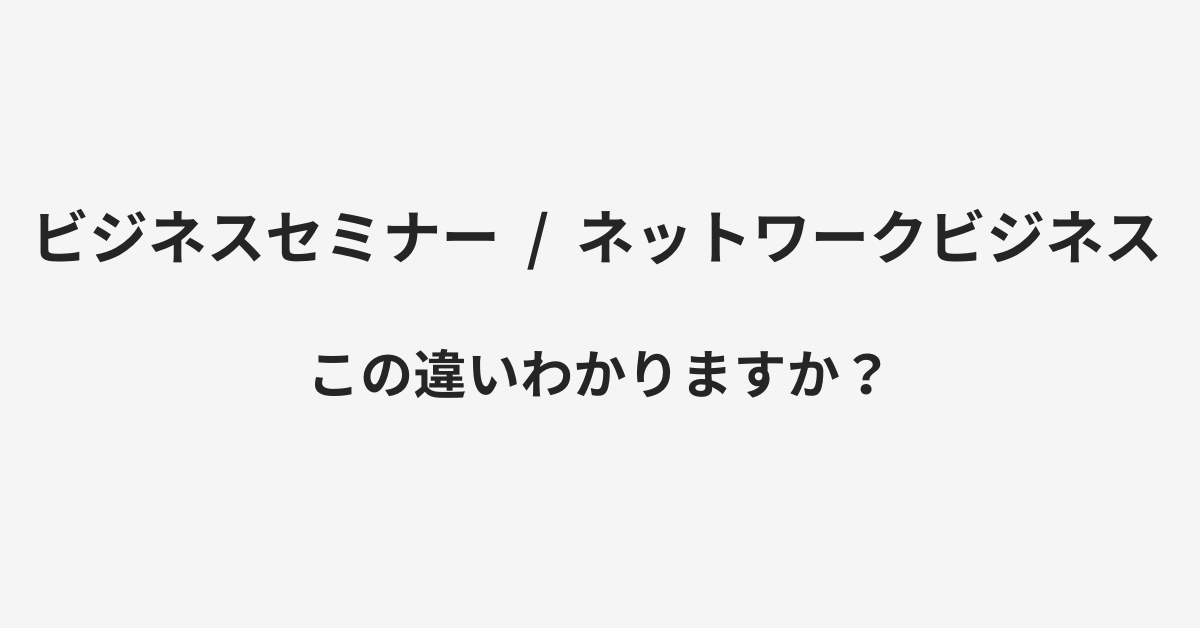【テナント】と【店舗】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
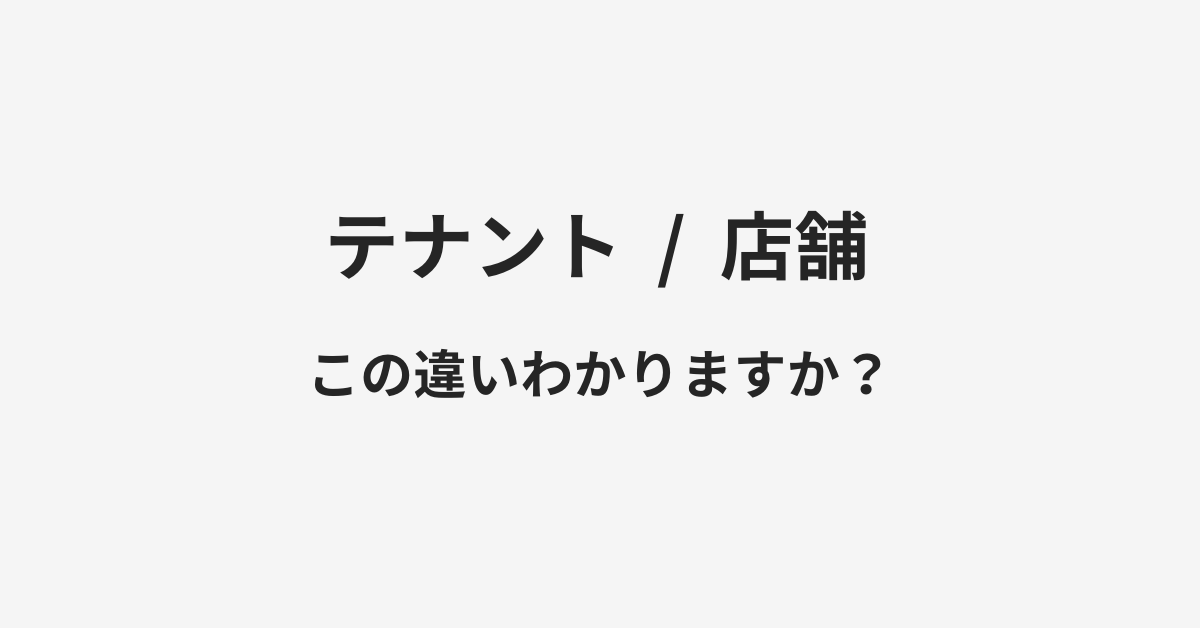
テナントと店舗の分かりやすい違い
テナントと店舗は、商業施設でよく使われる言葉ですが、それぞれ異なる側面を表しています。
テナントは建物や商業施設の一部を借りて営業する事業者のことで、賃貸借契約の当事者としての立場を強調します。一方、店舗は実際に商品やサービスを提供する物理的な営業場所を指します。
ビジネスにおいては、不動産取引や商業施設の運営で、この違いを理解して適切に使い分けることが重要です。
テナントとは?
テナントとは、商業ビルやショッピングセンター、百貨店などの建物の一部を賃借して事業を営む借主(賃借人)を指します。不動産用語として使用され、オーナー(賃貸人)との契約関係における立場を表します。
テナントは賃料、共益費、保証金などの契約条件に基づいて入居し、定められた区画で営業活動を行います。商業施設側はテナントミックスという戦略で、相乗効果の高い組み合わせを考慮してテナントを誘致します。
ビジネスにおいては、テナント契約の交渉、売上歩合賃料の設定、退去時の原状回復など、様々な法的・経済的な側面があり、事業計画において重要な要素となります。
テナントの例文
- ( 1 ) 新規テナントの誘致により、商業施設の集客力が向上しました。
- ( 2 ) 優良テナントの退去を防ぐため、賃料交渉に応じることにしました。
- ( 3 ) テナント契約更新時に、売上歩合賃料の見直しを行います。
- ( 4 ) キーテナントの撤退により、施設全体の売上が大幅に減少しました。
- ( 5 ) テナント向けの販促支援策を導入し、共存共栄を図っています。
- ( 6 ) 新規出店テナントの与信審査を慎重に実施する必要があります。
テナントの会話例
店舗とは?
店舗とは、商品の販売やサービスの提供を行う物理的な営業施設を指します。小売業、飲食業、サービス業など、顧客と直接接点を持つ事業の拠点として機能し、ブランドイメージの体現や顧客体験の提供の場となります。
店舗は立地、面積、レイアウト、内装デザインなど、様々な要素で構成され、これらが売上や顧客満足度に直接影響します。自社所有の場合もあれば、賃借する場合もあり、後者の場合はテナントとして入居することになります。
経営戦略上、店舗は売上を生み出す収益センターであると同時に、固定費の大きな部分を占めるコストセンターでもあります。店舗運営の効率化や収益性の向上は、事業成功の鍵となります。
店舗の例文
- ( 1 ) 旗艦店舗のリニューアルにより、ブランドイメージが向上しました。
- ( 2 ) 全国50店舗展開を目標に、出店計画を策定しています。
- ( 3 ) 不採算店舗の閉鎖により、全体の収益性が改善されました。
- ( 4 ) 新店舗の立地選定には、商圏分析データを活用しています。
- ( 5 ) 店舗運営マニュアルを改訂し、サービス品質の標準化を図ります。
- ( 6 ) 既存店舗の売上向上のため、改装投資を検討しています。
店舗の会話例
テナントと店舗の違いまとめ
テナントと店舗の最大の違いは、視点と用途にあります。テナントは賃貸借関係における借主としての立場を表し、店舗は営業活動を行う物理的な場所を指します。
実務では、テナント募集は貸主側の視点で使われ、店舗展開は事業者側の視点で使われることが多いです。同じ営業拠点でも、契約面ではテナント、運営面では店舗と呼び分けることがあります。
不動産取引、商業施設運営、小売業経営などの場面で、この違いを理解して適切に使い分けることが、円滑なビジネスコミュニケーションにつながります。
テナントと店舗の読み方
- テナント(ひらがな):てなんと
- テナント(ローマ字):tenannto
- 店舗(ひらがな):てんぽ
- 店舗(ローマ字):tennpo