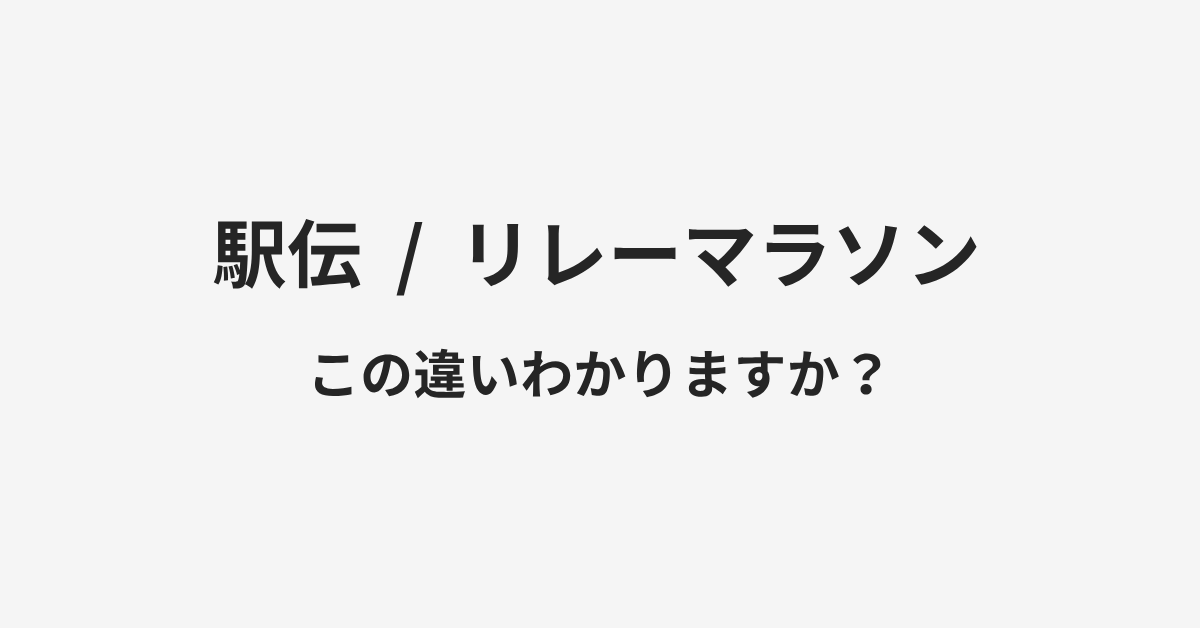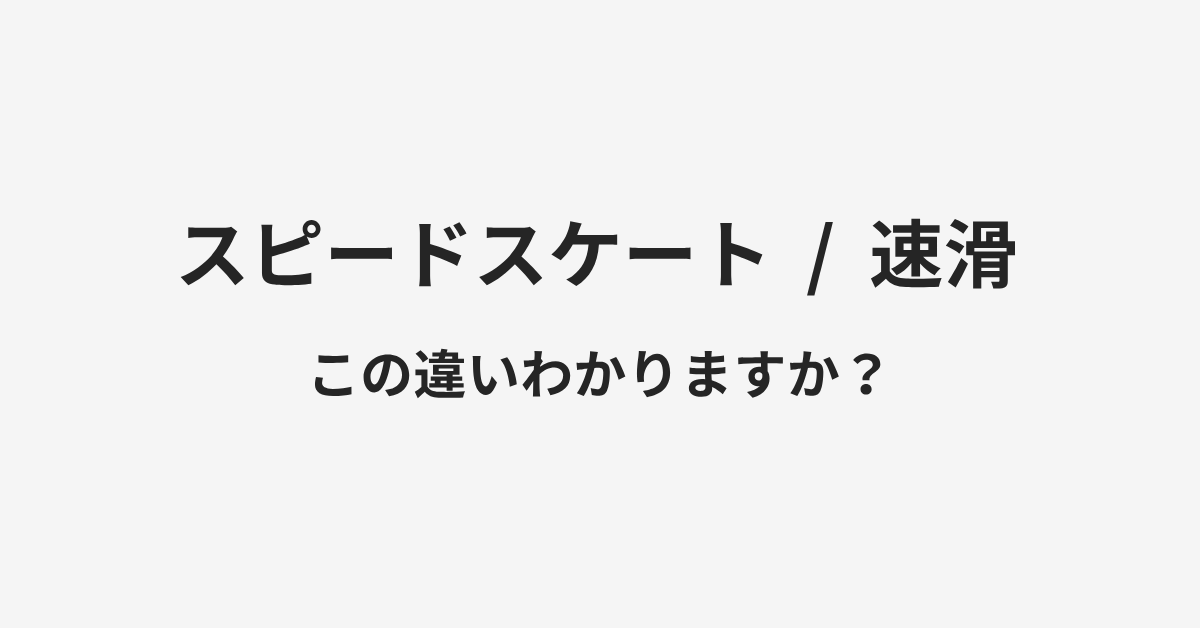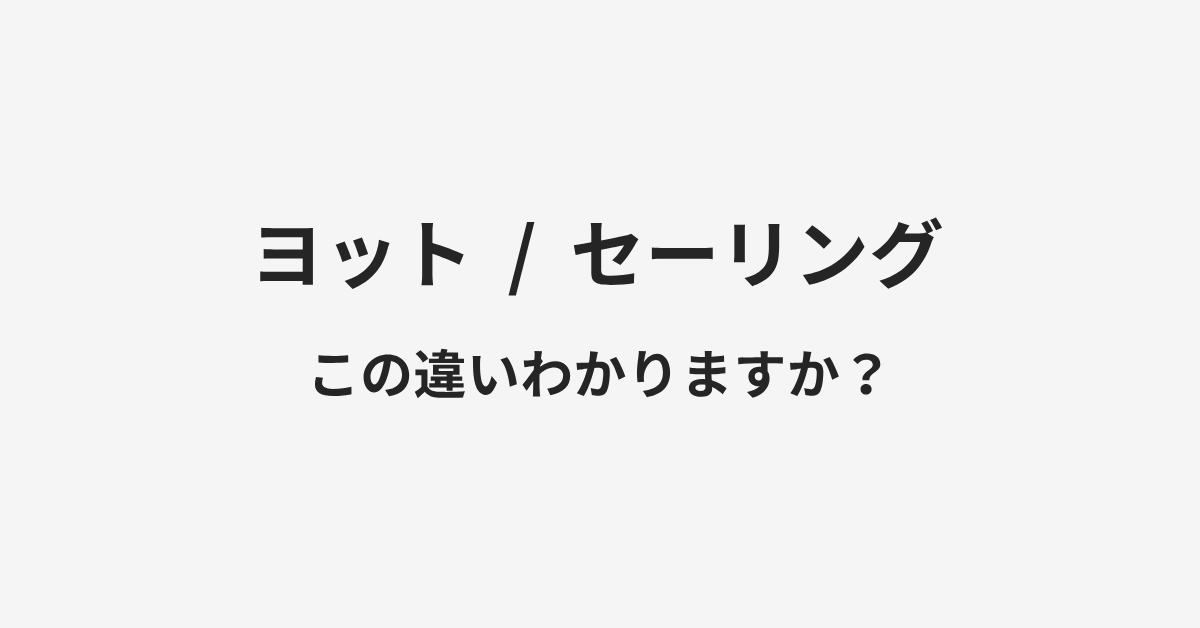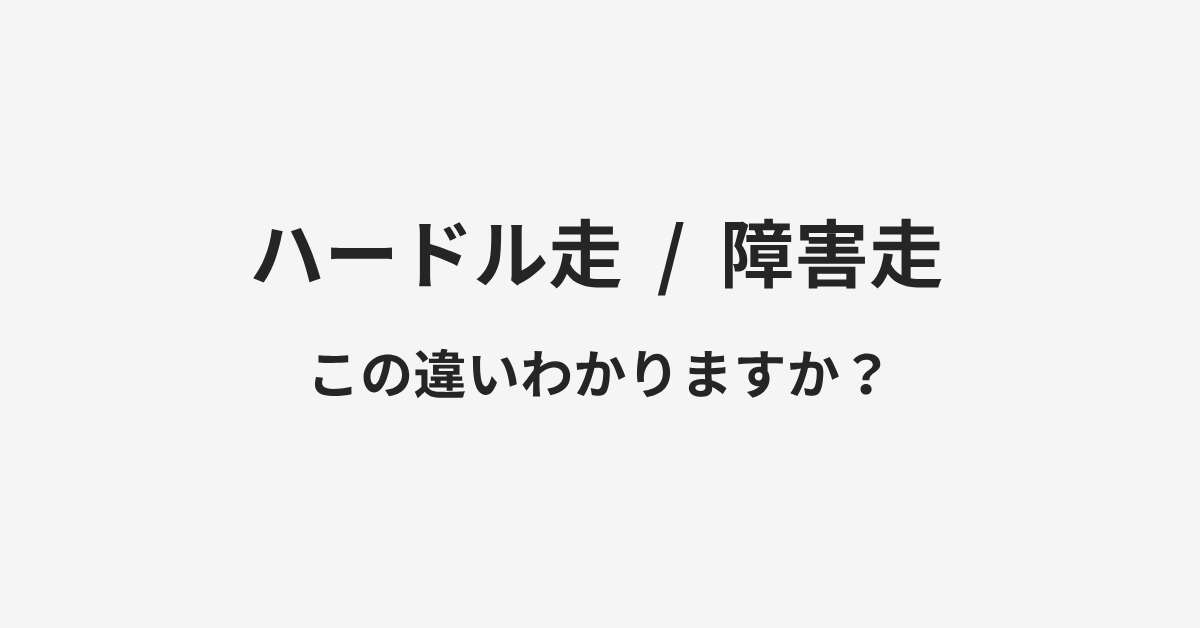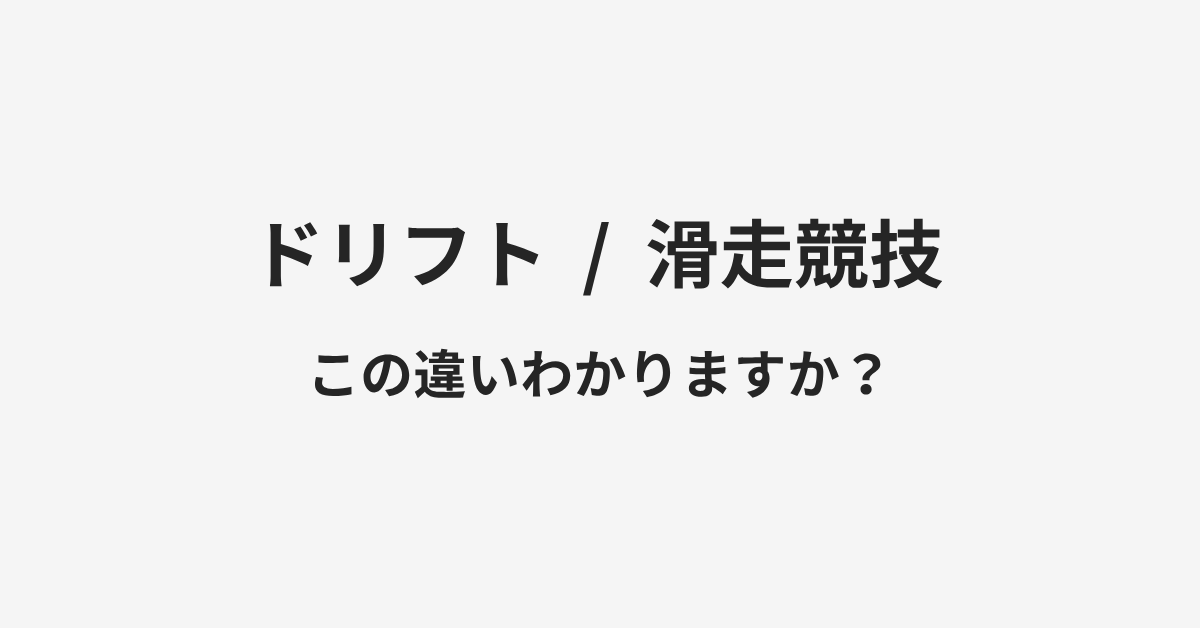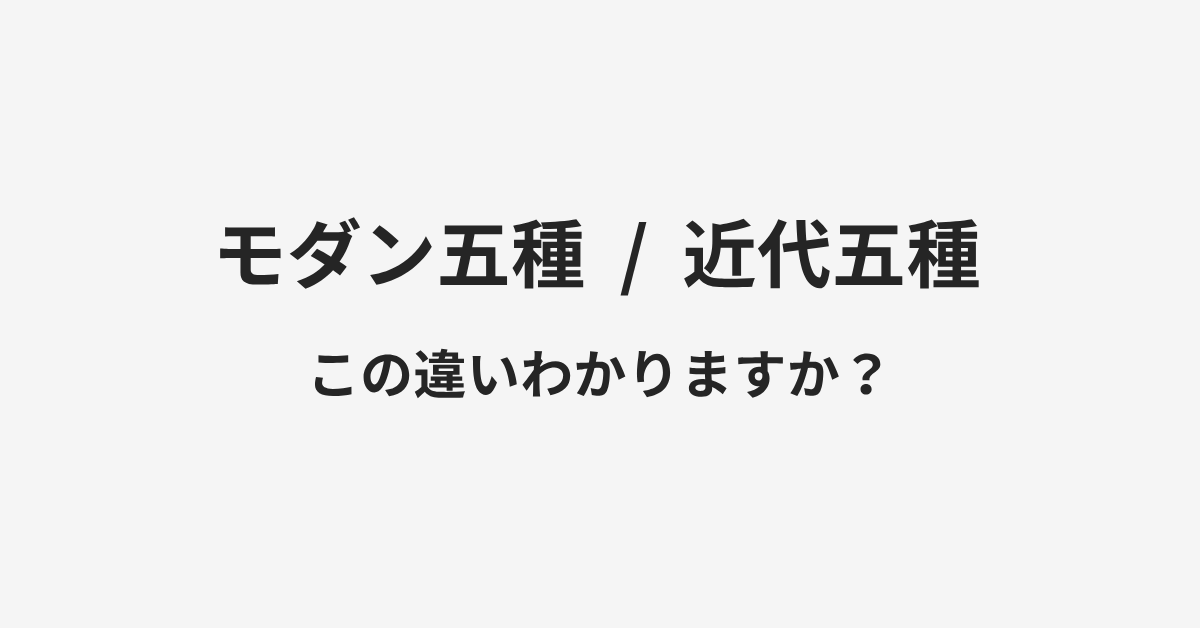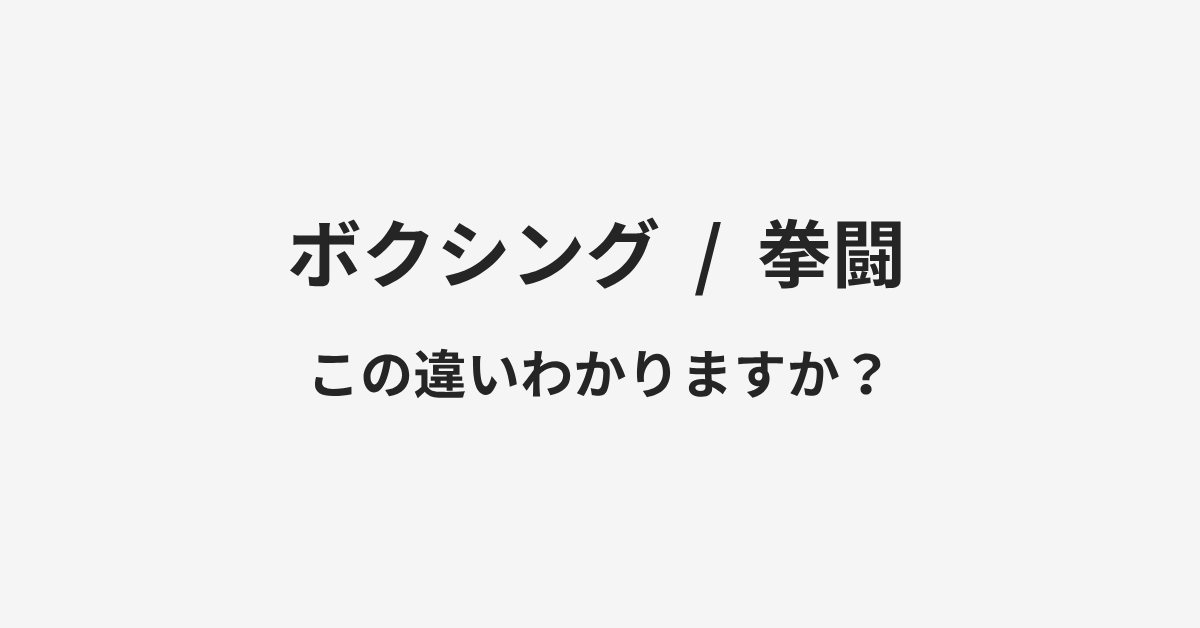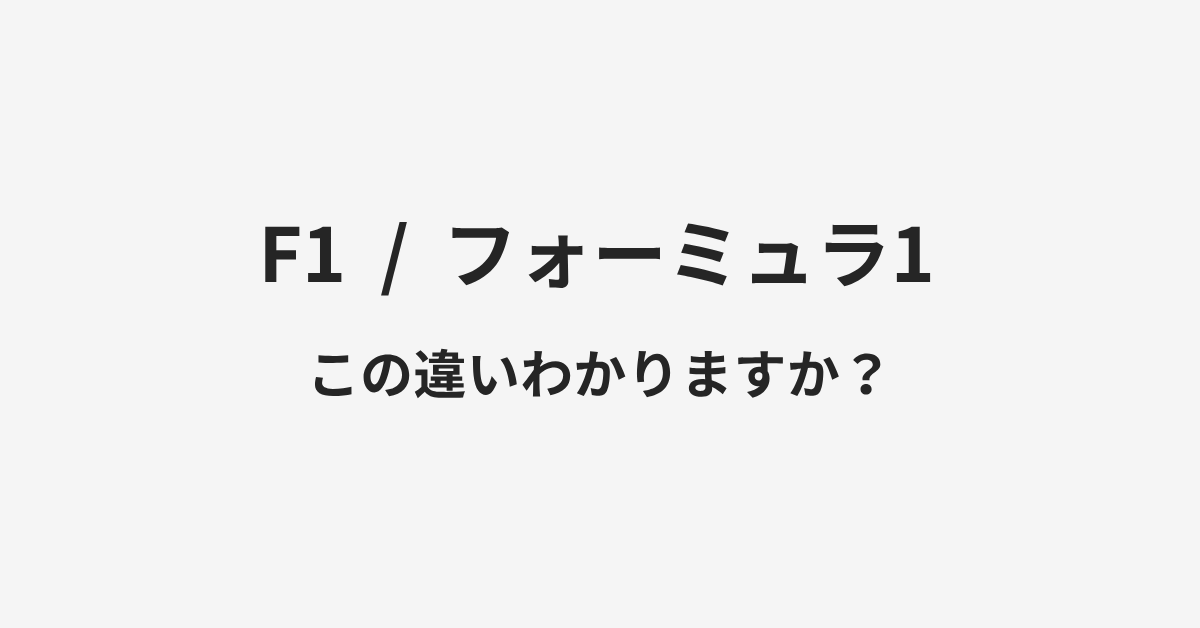【リカバリー】と【回復】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
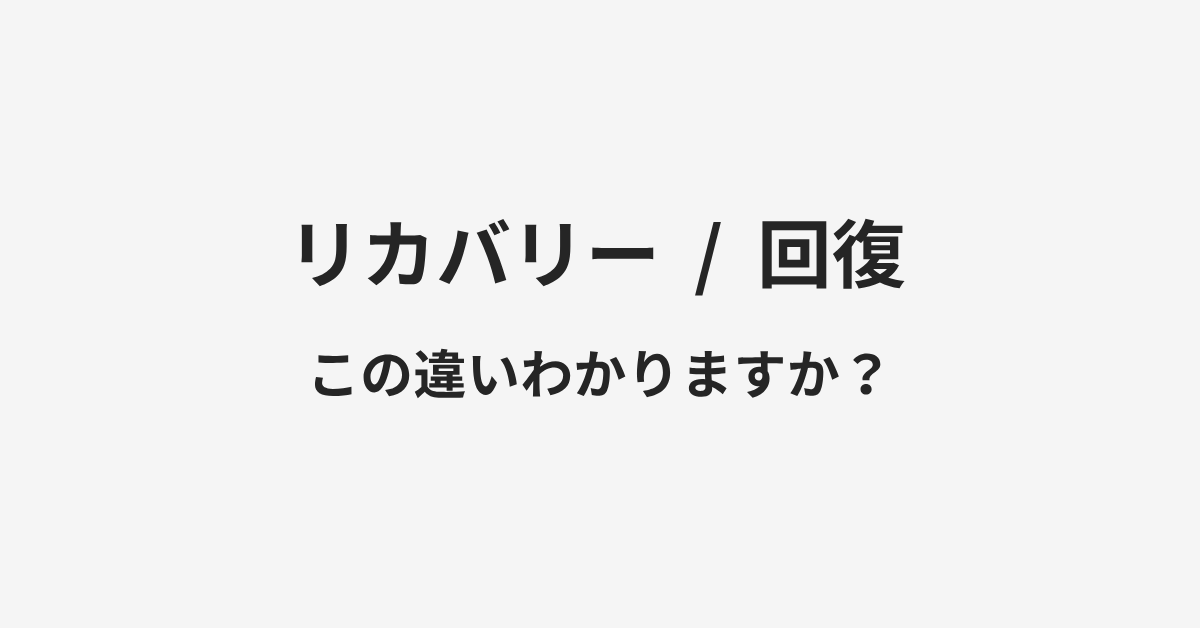
リカバリーと回復の分かりやすい違い
リカバリーと回復は似た意味ですが、能動性と専門性に違いがあります。リカバリーは英語由来で、積極的に回復を促進する戦略的なプロセスを指します。
回復は日本語で、自然に元の状態に戻ることを表す一般的な表現です。スポーツビジネスでは、専門的なサービスや製品ではリカバリー、一般的な文脈では回復という使い分けが効果的です。
リカバリーとは?
リカバリーは、トレーニングや競技で生じた身体的・精神的疲労から、積極的に回復を促進するプロセスと戦略を指します。アイスバス、コンプレッションウェア、マッサージガン、栄養補給、睡眠管理など、科学的根拠に基づいた様々な方法を組み合わせて実施します。単なる休息ではなく、次のパフォーマンスに向けた準備期間として位置づけられます。
現代スポーツでは、リカバリーはトレーニングと同等に重要視されています。リカバリーもトレーニングの一部という考え方が浸透し、リカバリー専門スタッフを置くチームも増えています。適切なリカバリーにより、オーバートレーニングを防ぎ、継続的なパフォーマンス向上が可能になります。ビジネス面では、リカバリー市場は急成長しています。
リカバリーウェア、リカバリードリンク、リカバリー機器(筋膜リリースガン、加圧装置など)、リカバリー施設(酸素カプセル、クライオセラピー)など、多様な製品・サービスが展開されています。一般のフィットネス愛好者にも浸透し、市場規模は拡大し続けています。
リカバリーの例文
- ( 1 ) 最新のリカバリープロトコルを導入しました。
- ( 2 ) 科学的なリカバリー戦略で、選手のパフォーマンスを最大化します。
- ( 3 ) リカバリールームを新設する計画です。
- ( 4 ) 専用のリカバリー施設は、チームの競争力向上に不可欠です。
- ( 5 ) リカバリードリンクの効果を教えてください。
- ( 6 ) 適切なタイミングでのリカバリー栄養補給は、回復を促進します。
リカバリーの会話例
回復とは?
回復は、疲労や損傷から元の健康な状態に戻ることを指す一般的な日本語です。疲労回復体力回復怪我からの回復など、幅広い文脈で使用されます。自然治癒力による受動的なプロセスを含み、時間の経過とともに起こる状態の改善を表現します。日本のスポーツ文化では、回復は古くから重要視されてきました。
休養も練習のうちという言葉があるように、適切な休息による回復の重要性は認識されています。温泉、マッサージ、鍼灸など、日本独自の回復方法も発展してきました。ただし、科学的な裏付けよりも経験則に基づく部分が多いのが特徴です。
回復という言葉は、その分かりやすさから、一般向けの説明では今でもよく使われます。回復力回復期間など、日常的に使われる表現も多く、専門知識がなくても理解しやすいメリットがあります。医療現場でも回復期リハビリなど、正式な用語として使用されています。
回復の例文
- ( 1 ) 試合後の回復に何日必要ですか?
- ( 2 ) 完全な回復には、通常48〜72時間かかります。
- ( 3 ) 疲労回復に効果的な方法はありますか?
- ( 4 ) 十分な睡眠と栄養が、疲労回復の基本です。
- ( 5 ) 怪我からの回復期間を短縮したいです。
- ( 6 ) 適切な治療とリハビリで、回復を早めることができます。
回復の会話例
リカバリーと回復の違いまとめ
リカバリーと回復は、能動的アプローチと受動的プロセスという違いがあります。リカバリーは戦略的で科学的、回復は自然で一般的な概念です。
プロスポーツや専門サービスではリカバリー、日常会話や一般向けでは回復が適切です。スポーツビジネスでは、付加価値の高いサービスにはリカバリー、基本的な概念説明には回復を使うことで、適切な価値訴求が可能になります。
リカバリーと回復の読み方
- リカバリー(ひらがな):りかばりー
- リカバリー(ローマ字):rikabari-
- 回復(ひらがな):かいふく
- 回復(ローマ字):kaifuku