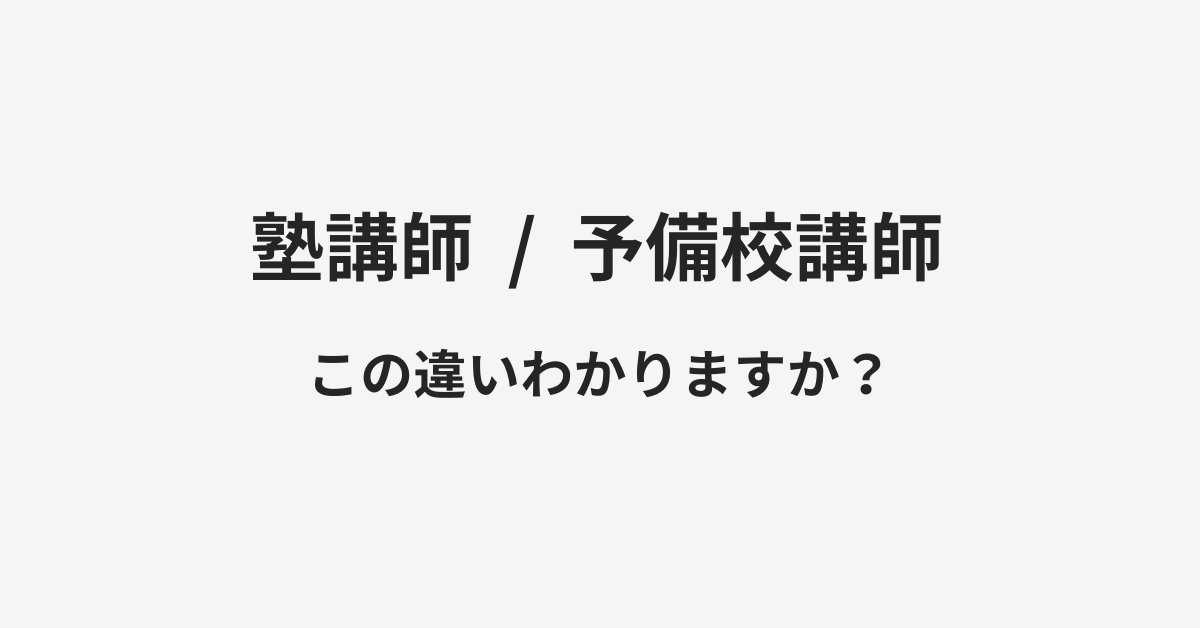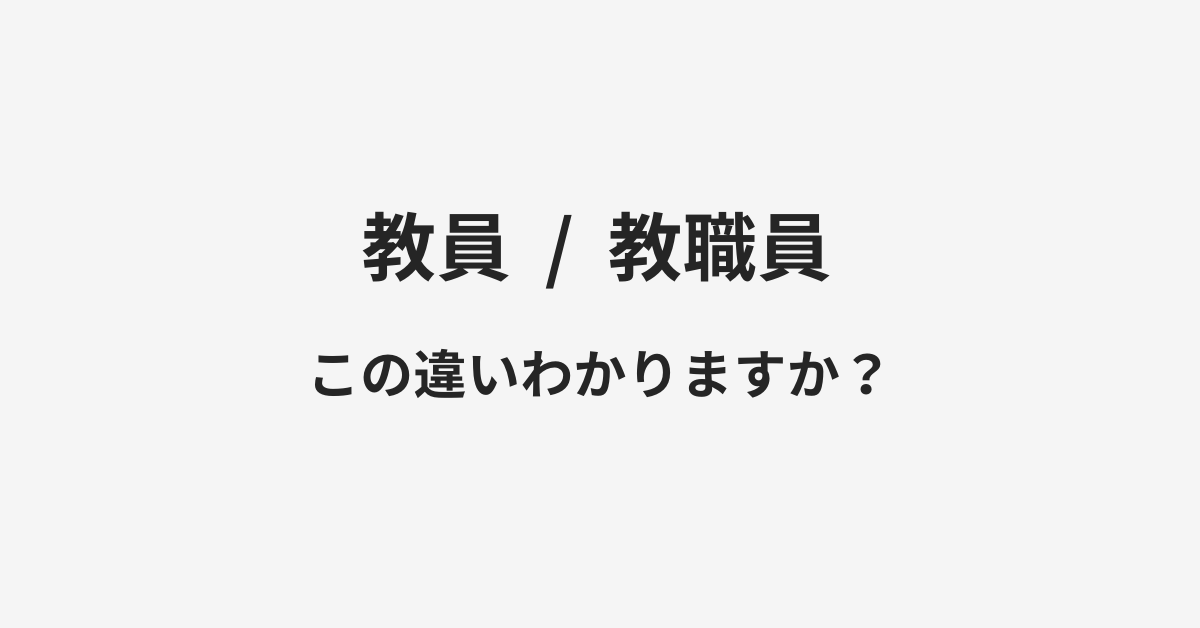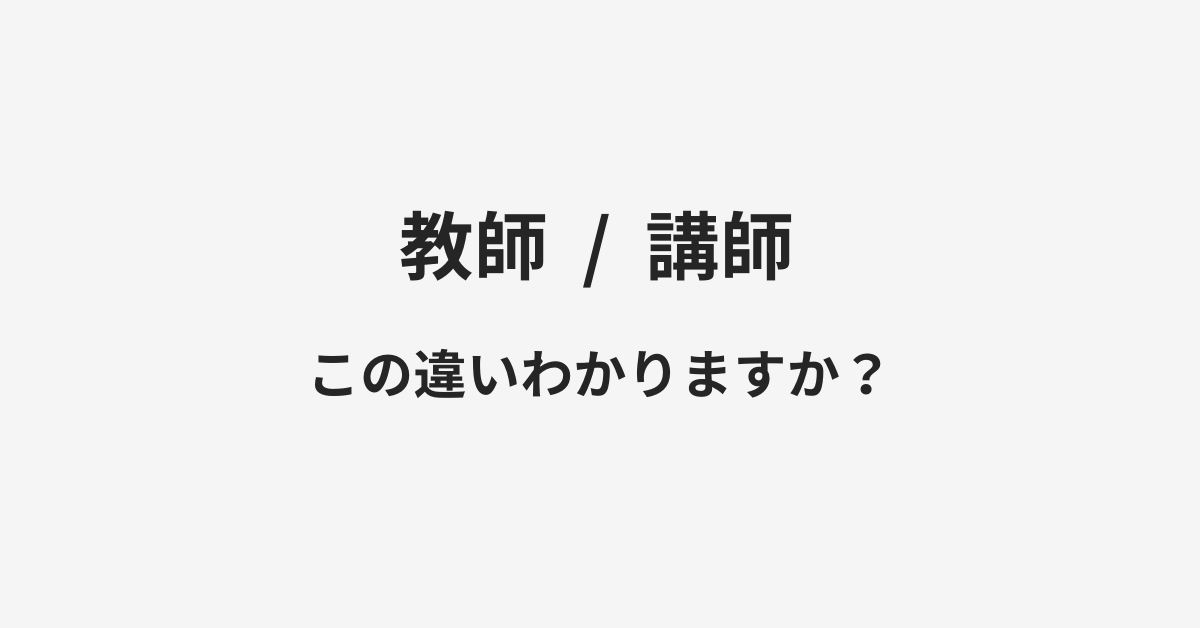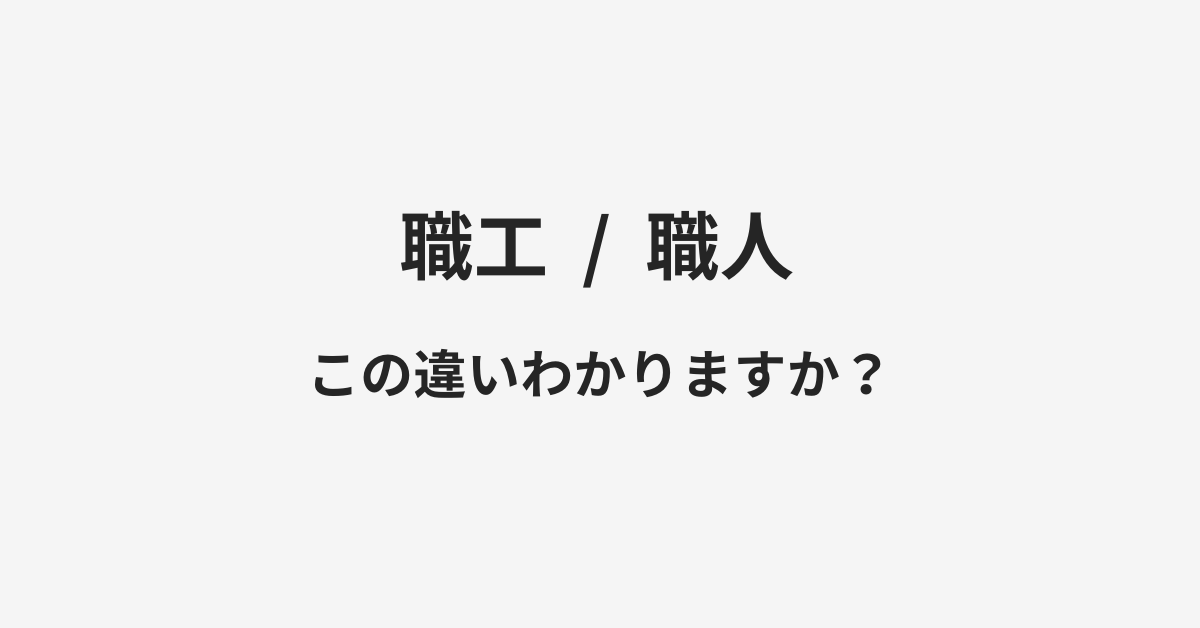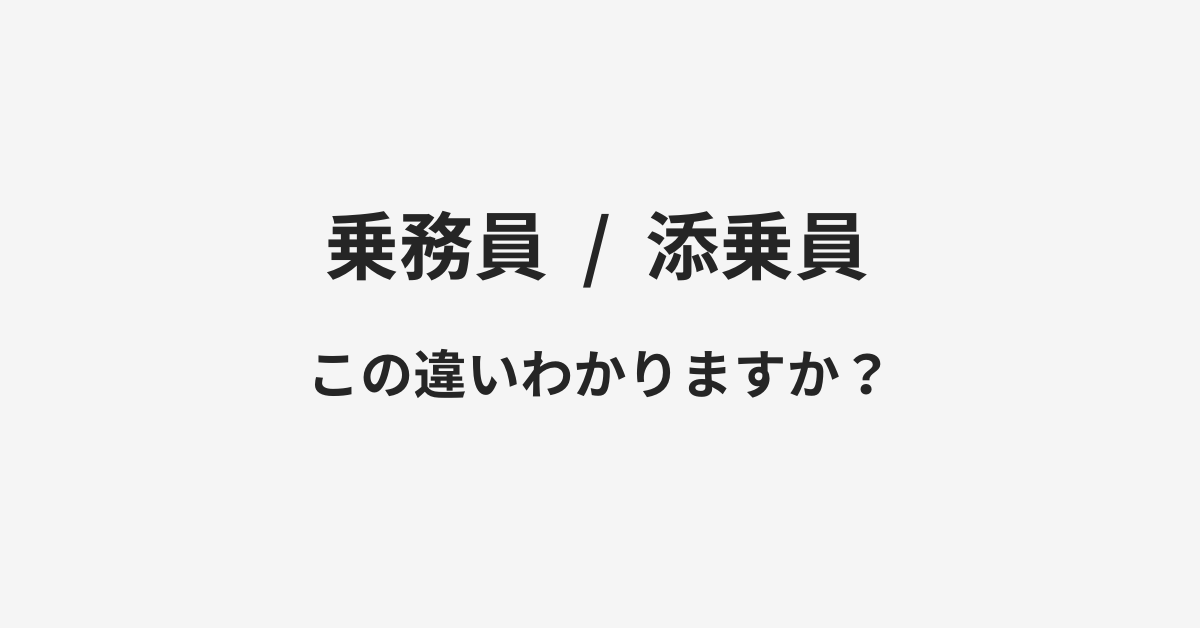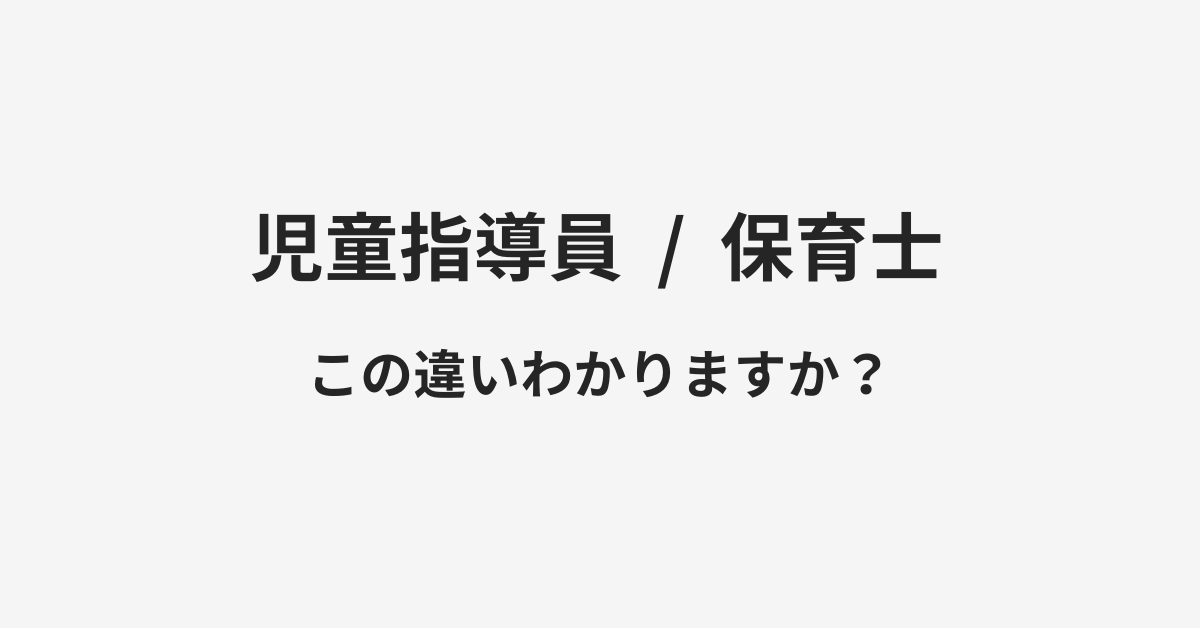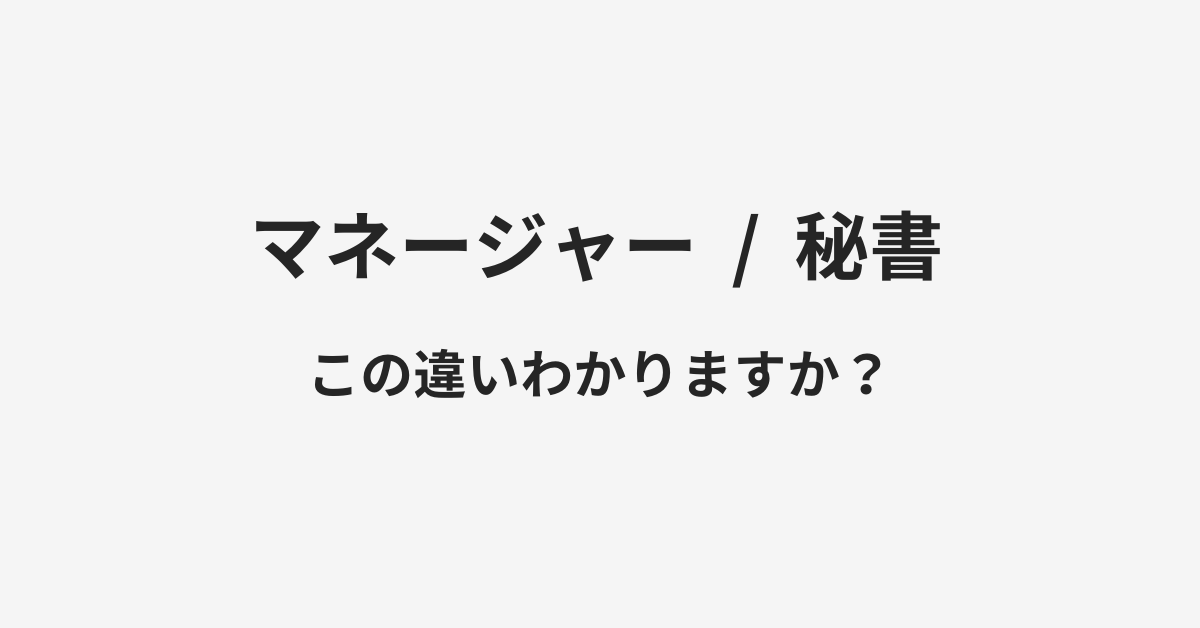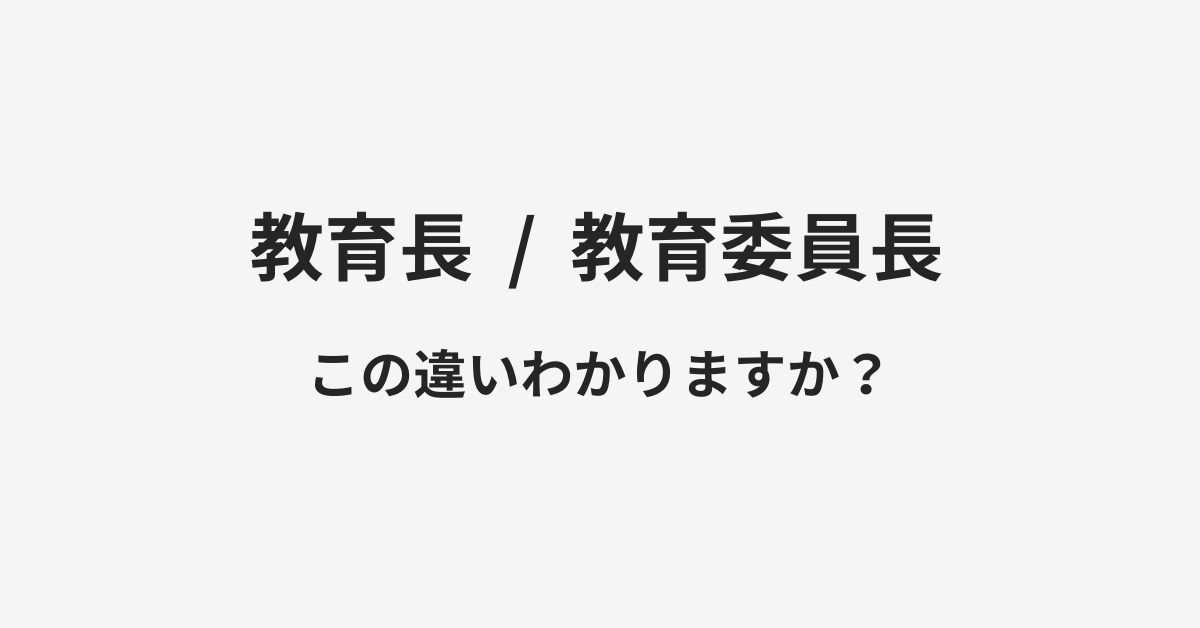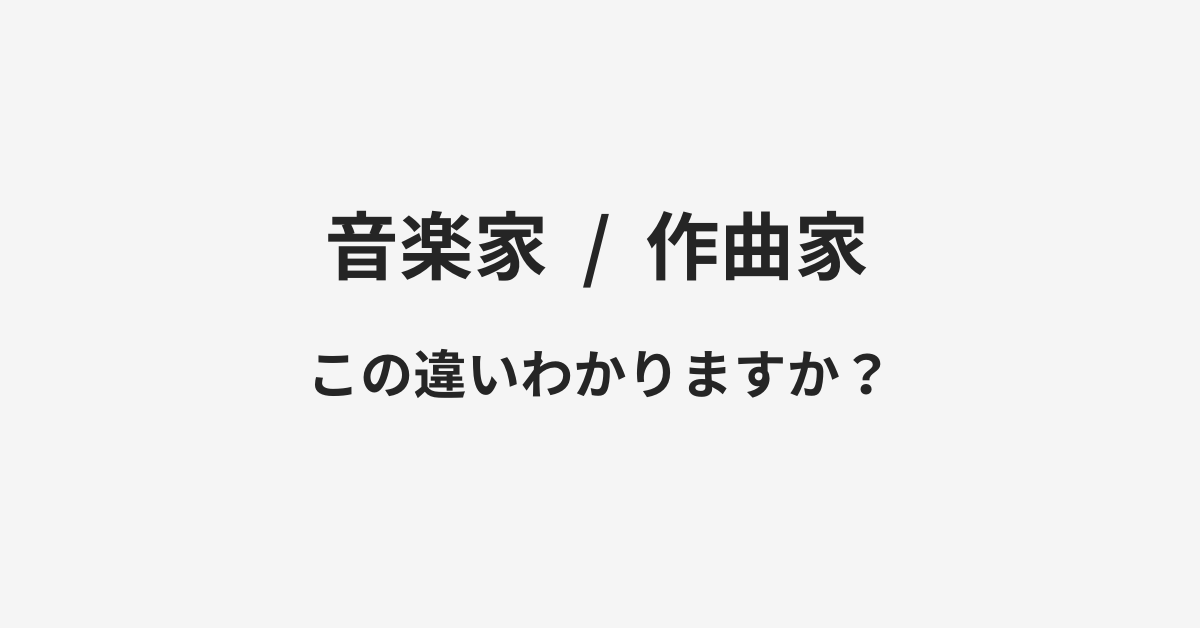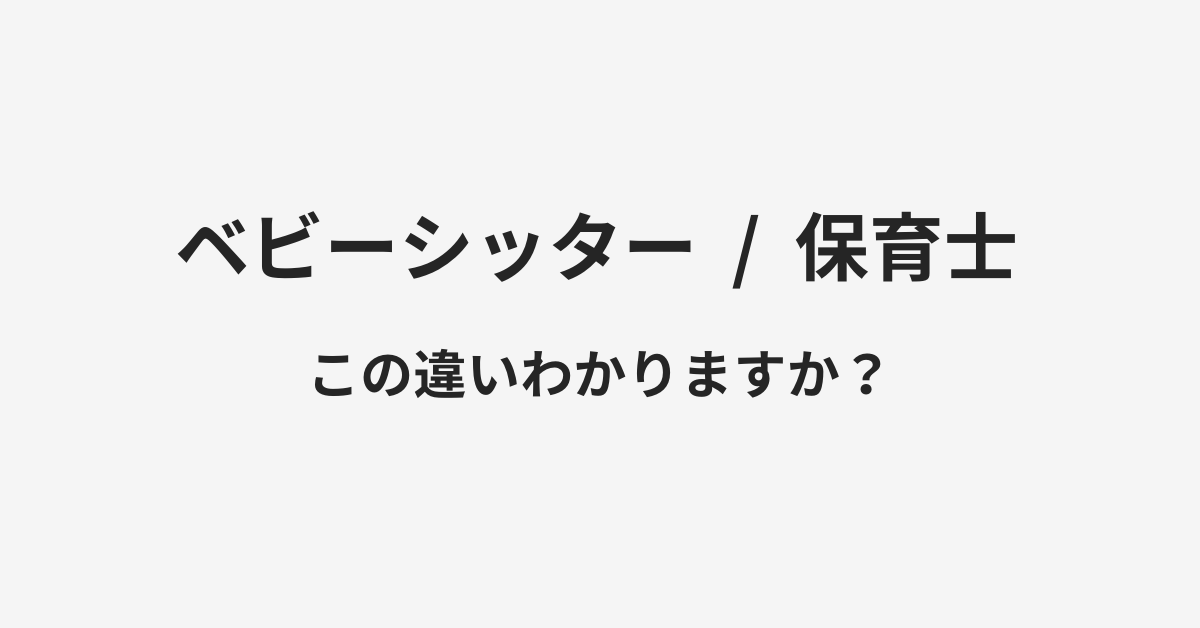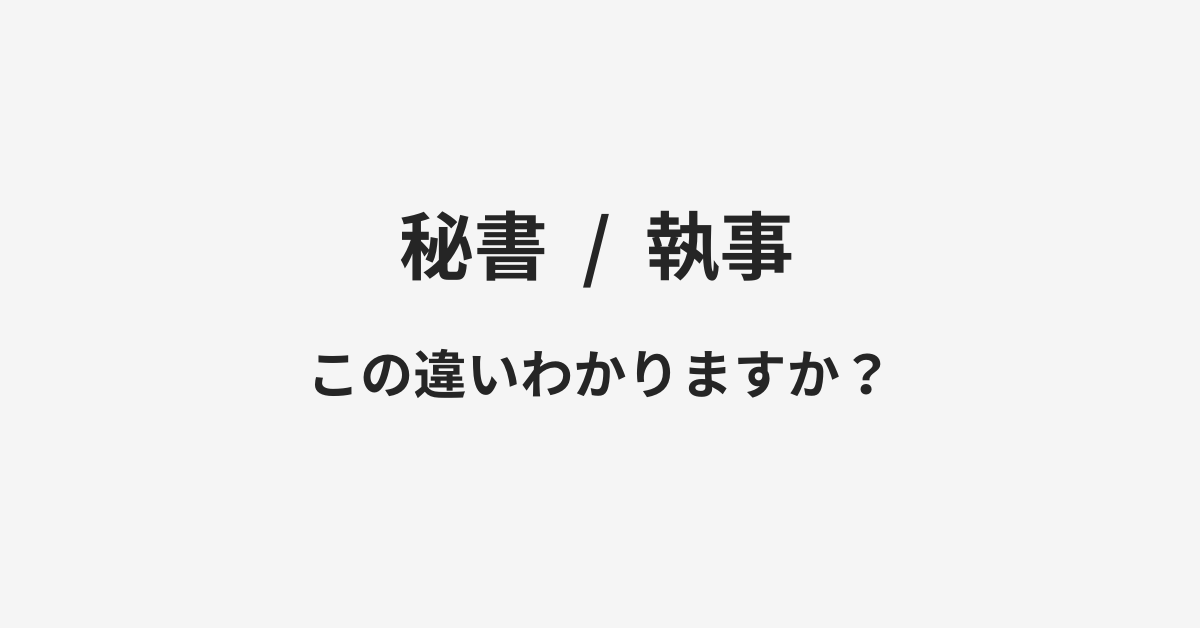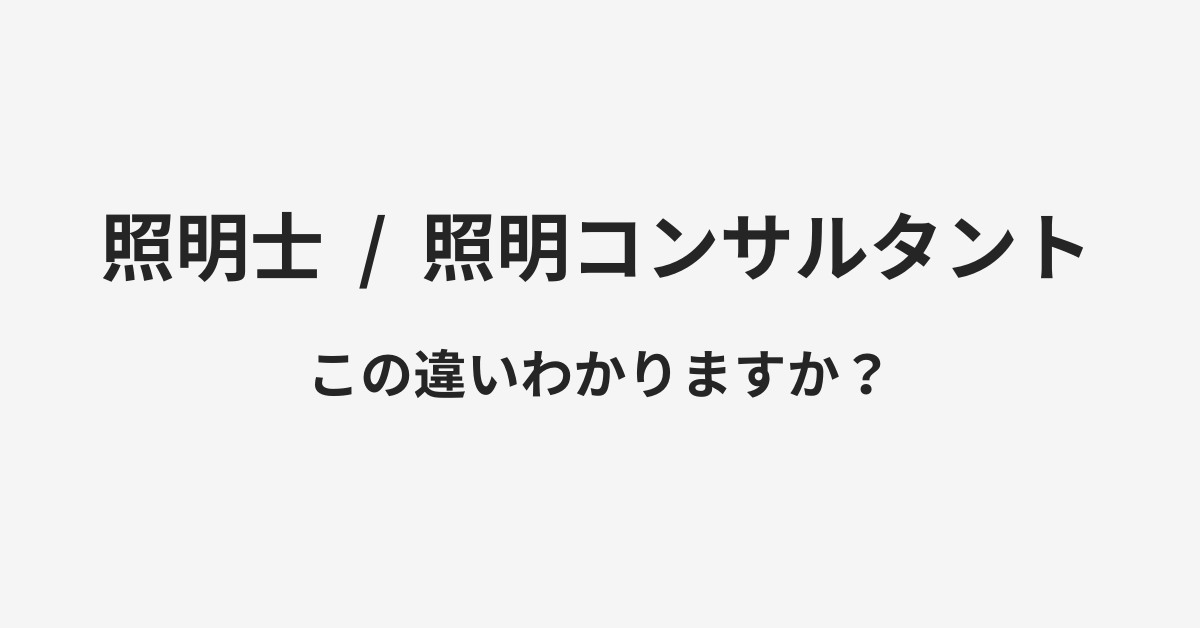【師匠】と【師範】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
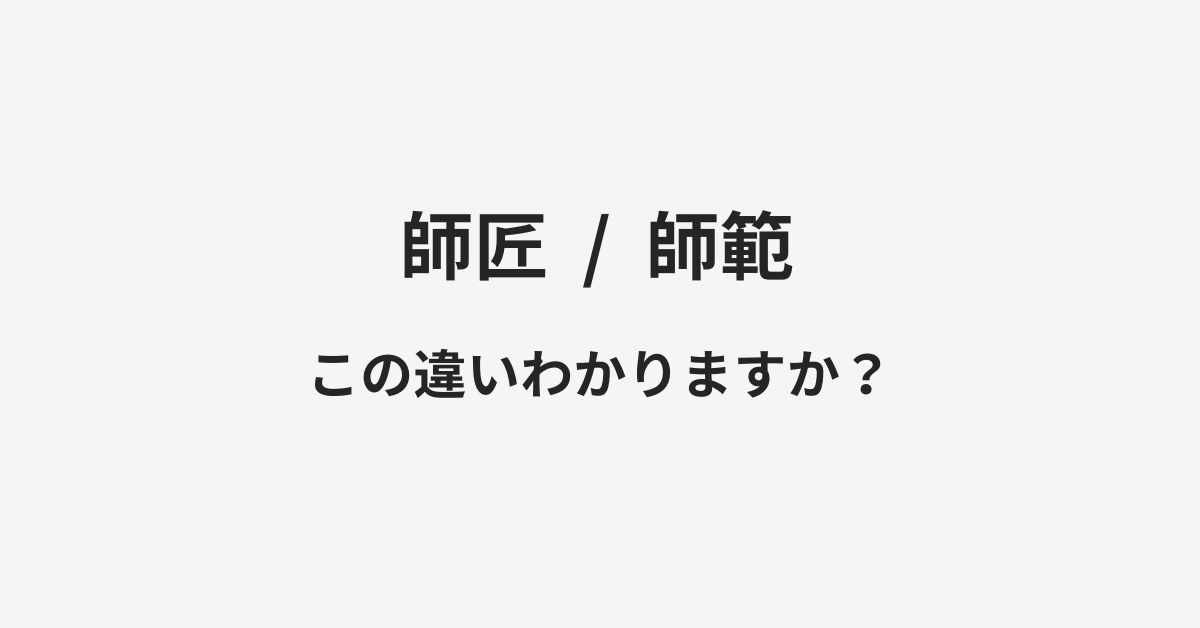
師匠と師範の分かりやすい違い
師匠と師範は、どちらも技術や芸を教える先生ですが、関係性と資格の有無が異なります。
師匠は、落語や大工など伝統的な職業で、弟子と親子のような深い関係を持ちながら技術を伝える人です。
一方、師範は空手や茶道などで、正式な資格を持って教室で指導する先生のことです。
師匠とは?
師匠とは、伝統芸能、職人、芸術などの分野で、弟子に技術や精神を直接伝授する指導者です。落語家、歌舞伎役者、大工、料理人などの世界で見られ、技術だけでなく、その道の生き方や哲学まで教えます。弟子との関係は深く、しばしば住み込みで修行することもあります。
師匠になるには、その道で一流の技術と実績を持ち、後進を育てる意欲と責任感が必要です。正式な資格はありませんが、業界での評価と信頼が重要です。弟子の育成は無報酬の場合も多く、技術の継承という使命感で行われます。
師匠として生計を立てるのは、本業の収入によります。有名な師匠なら、弟子からの月謝や後援会からの支援もありますが、多くは自身の芸や技術で稼ぎながら、弟子を育てています。日本の伝統文化継承に欠かせない存在です。
師匠の例文
- ( 1 ) 落語の師匠として、弟子たちに芸だけでなく人生の在り方も教えています。
- ( 2 ) 大工の師匠として、伝統技術を次世代に確実に伝承しています。
- ( 3 ) 料理人の師匠として、住み込みの弟子に厳しくも温かい指導をしています。
- ( 4 ) 師匠として、弟子の独立を見届けるのが何よりの喜びです。
- ( 5 ) 陶芸家の師匠として、技術と共に土と向き合う心も伝えています。
- ( 6 ) 三味線の師匠として、芸の厳しさと楽しさの両方を教えています。
師匠の会話例
師範とは?
師範とは、武道、茶道、華道などで、正式な教授資格を持つ指導者です。各流派や団体が定める審査や試験に合格し、指導者としての資格を認定された人を指します。道場や教室を開き、月謝制で生徒に指導を行います。技術指導に加え、礼儀作法や精神修養も重視します。
師範になるには、まず自身がその道を極め、段位や資格を取得した後、指導者養成課程を修了する必要があります。流派により異なりますが、通常10年以上の修行期間が必要です。指導技術、人格、流派への貢献度などが評価されます。
師範として道場や教室を運営すれば、月謝収入で生計を立てられます。生徒数により収入は変動しますが、人気師範なら年収500-1000万円以上も可能です。複数の支部を持つ師範もいます。日本文化の普及と継承に貢献する、やりがいのある職業です。
師範の例文
- ( 1 ) 空手道場の師範として、技術指導と精神修養の両立を心がけています。
- ( 2 ) 茶道の師範として、お点前だけでなく、もてなしの心を伝えています。
- ( 3 ) 柔道の師範として、地域の子どもたちに礼儀と強さを教えています。
- ( 4 ) 華道の師範として、流派の伝統を守りながら現代的な表現も追求しています。
- ( 5 ) 書道の師範として、美しい文字と共に日本文化の素晴らしさを伝えています。
- ( 6 ) 合気道の師範として、海外でも日本武道の精神を広めています。
師範の会話例
師匠と師範の違いまとめ
師匠と師範は、伝統的な技芸の指導者として異なる特徴を持つ存在です。
師匠は人間関係を重視した도제式教育、師範は制度化された資格に基づく教育という違いがあります。
どちらも日本の伝統文化継承に重要な役割を果たしていますが、師匠はより個人的で深い関係、師範はより組織的で広い指導という特徴があります。伝統を受け継ぐ方法として、それぞれに価値があります。
師匠と師範の読み方
- 師匠(ひらがな):ししょう
- 師匠(ローマ字):shishou
- 師範(ひらがな):しはん
- 師範(ローマ字):shihan