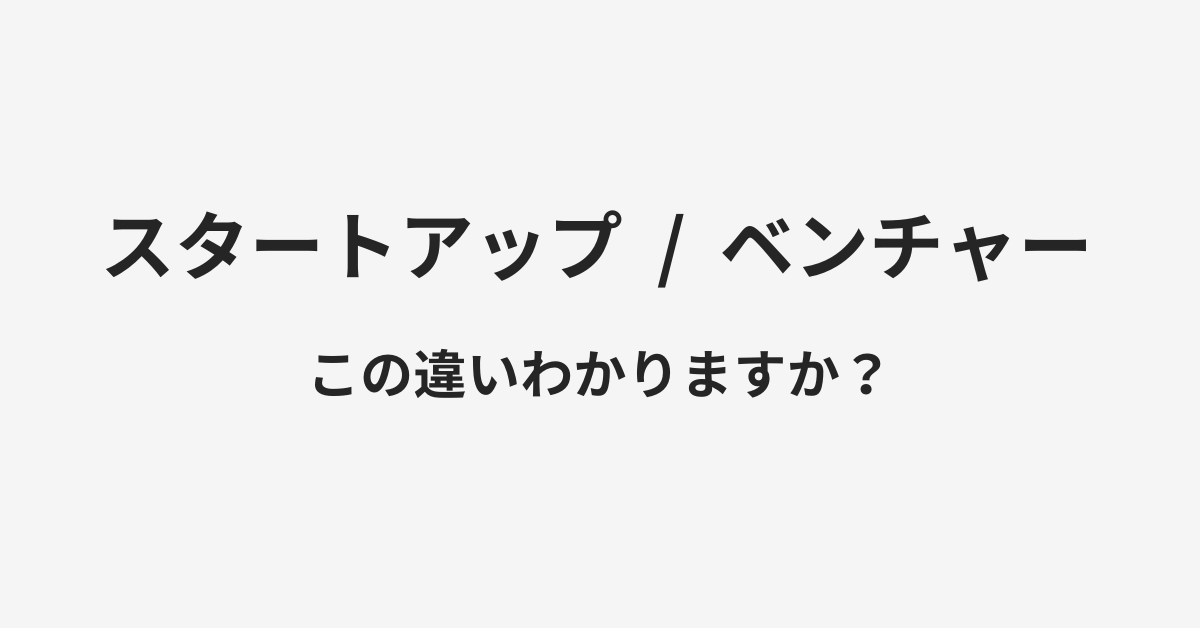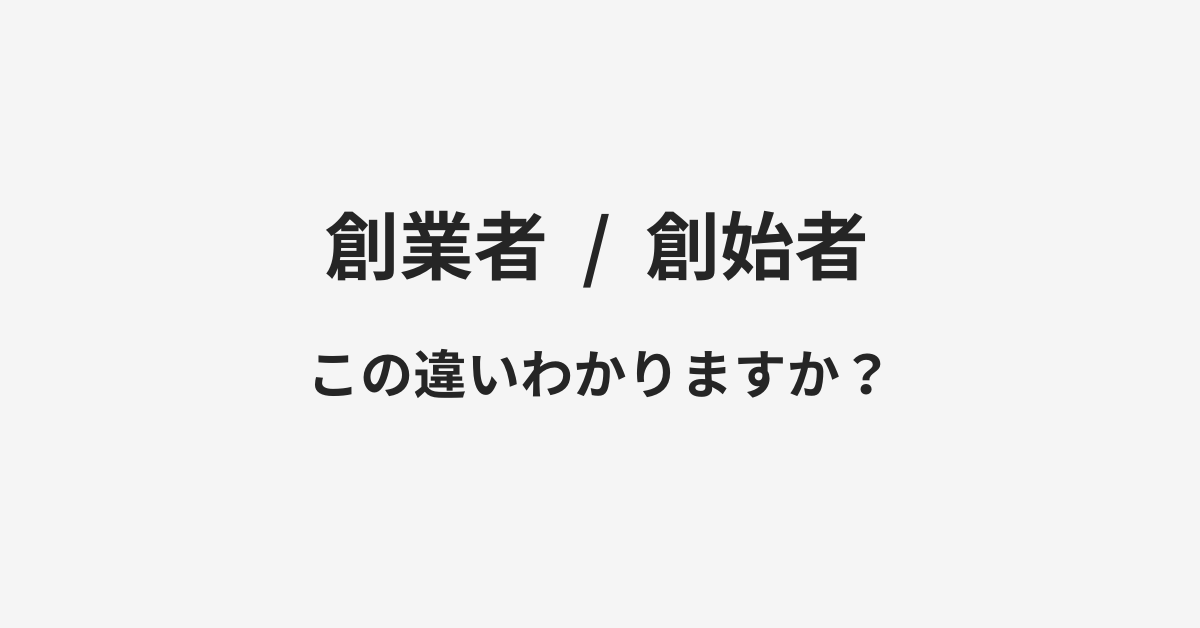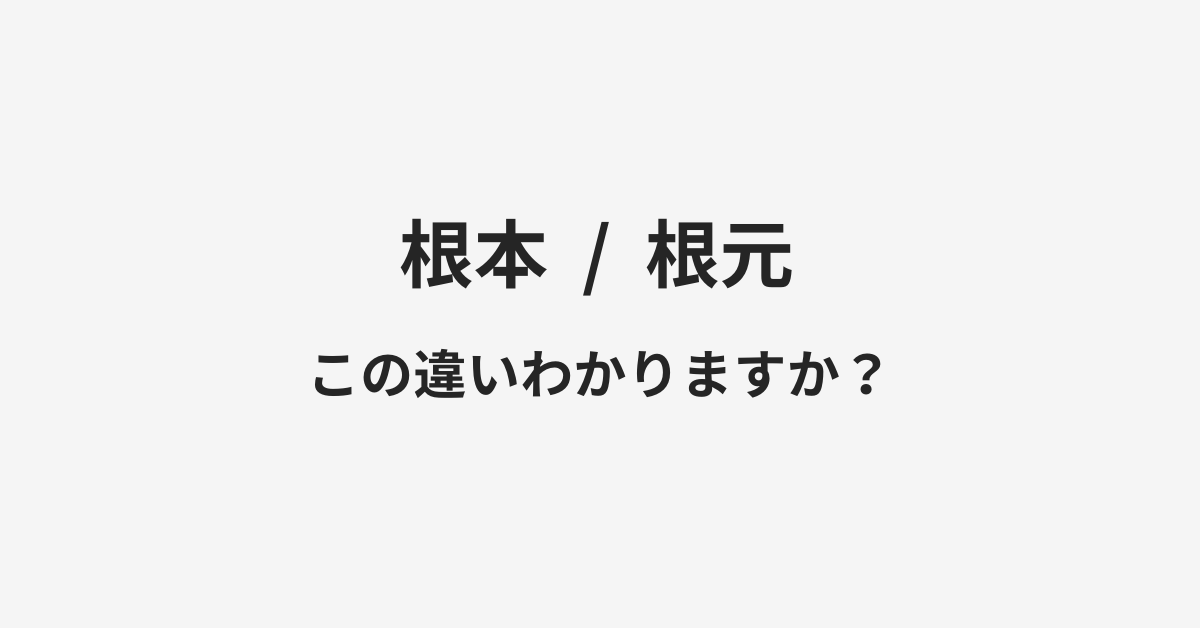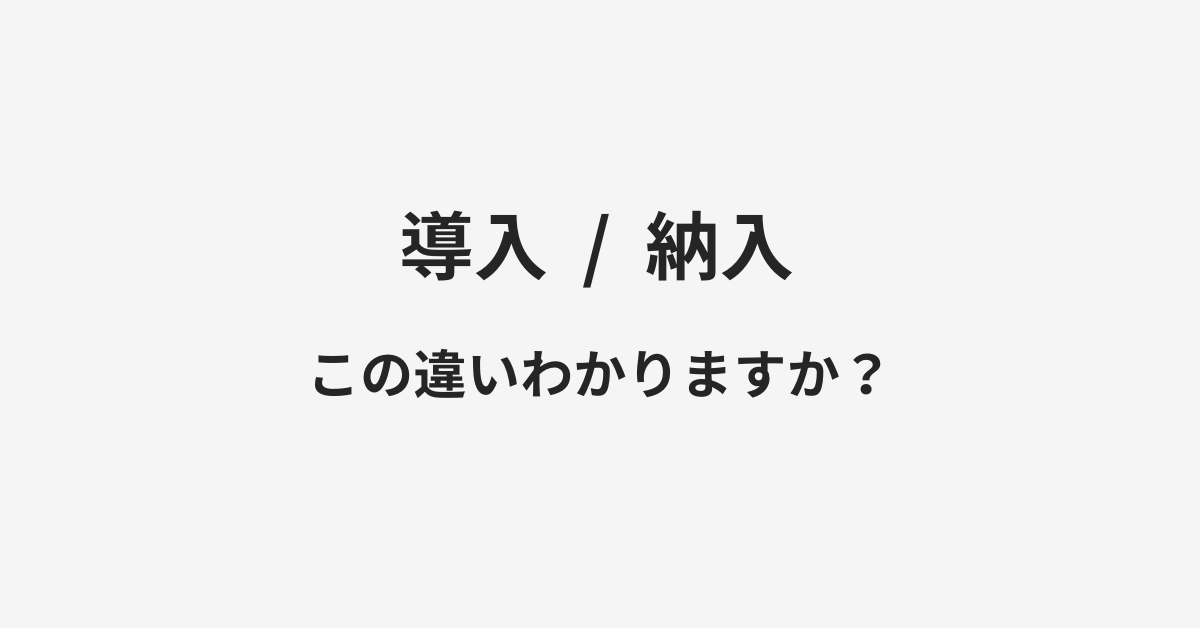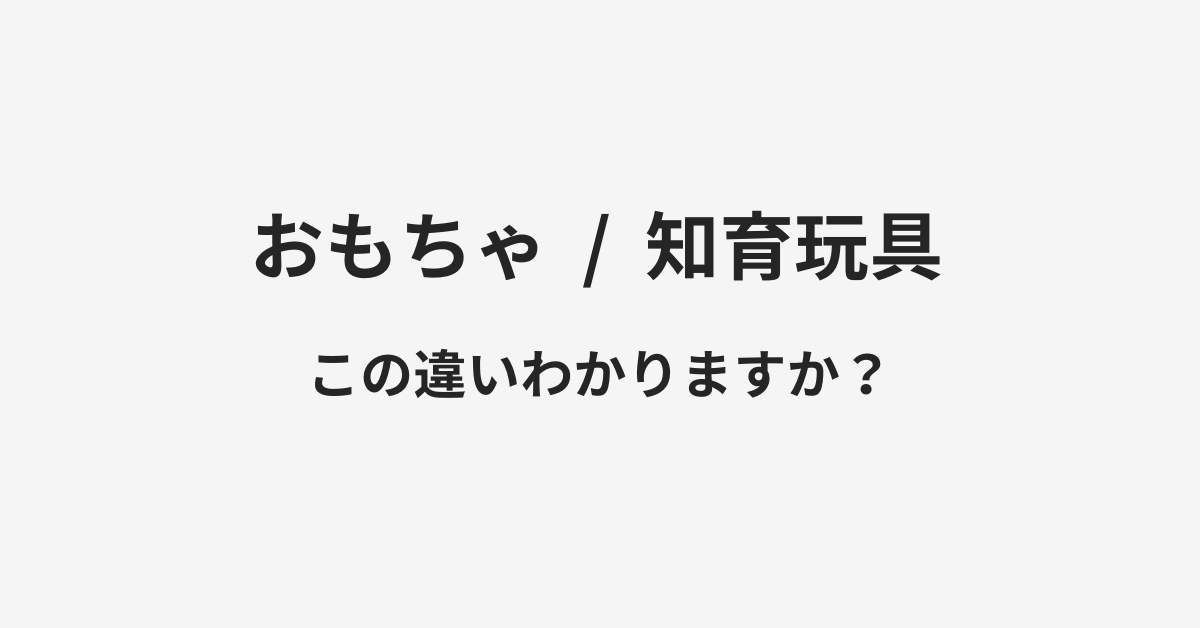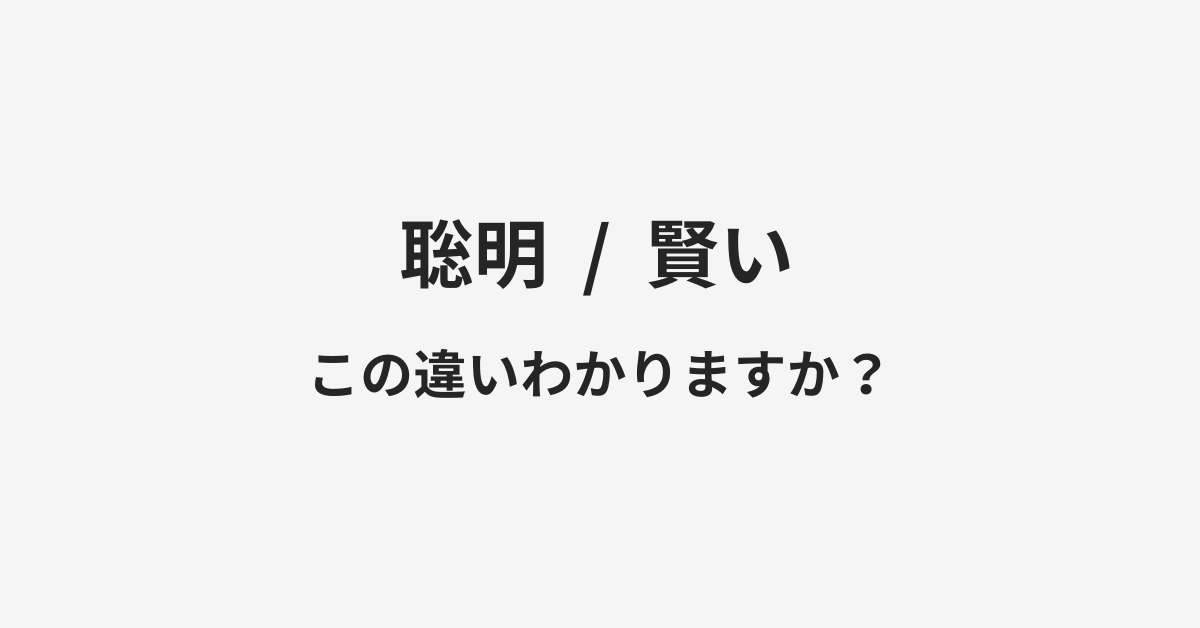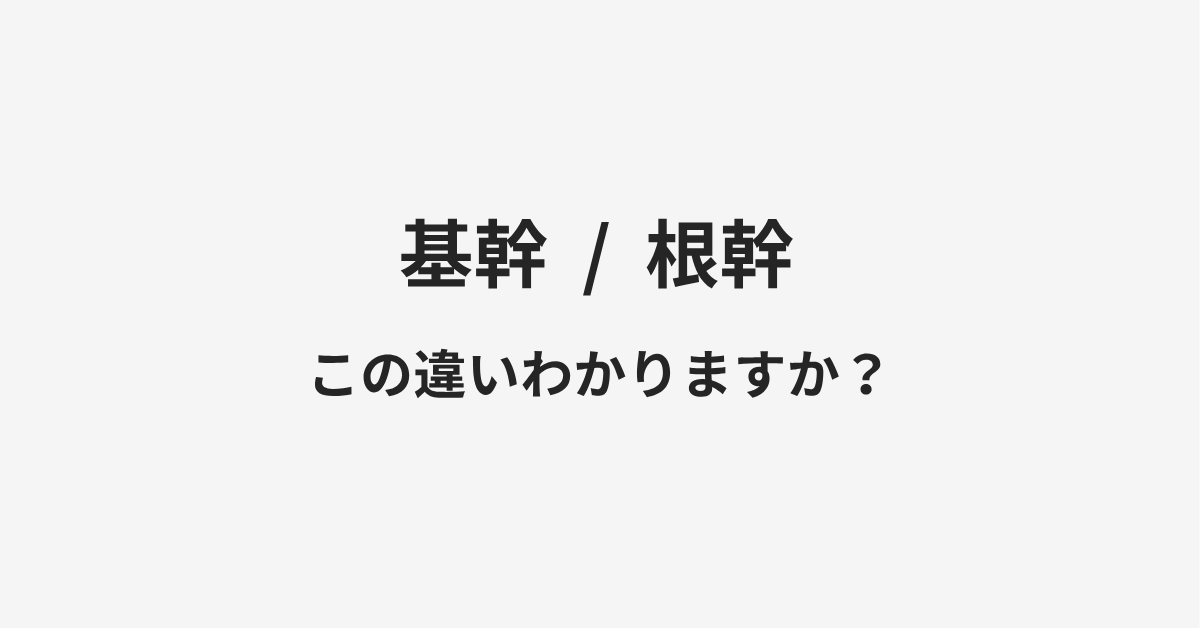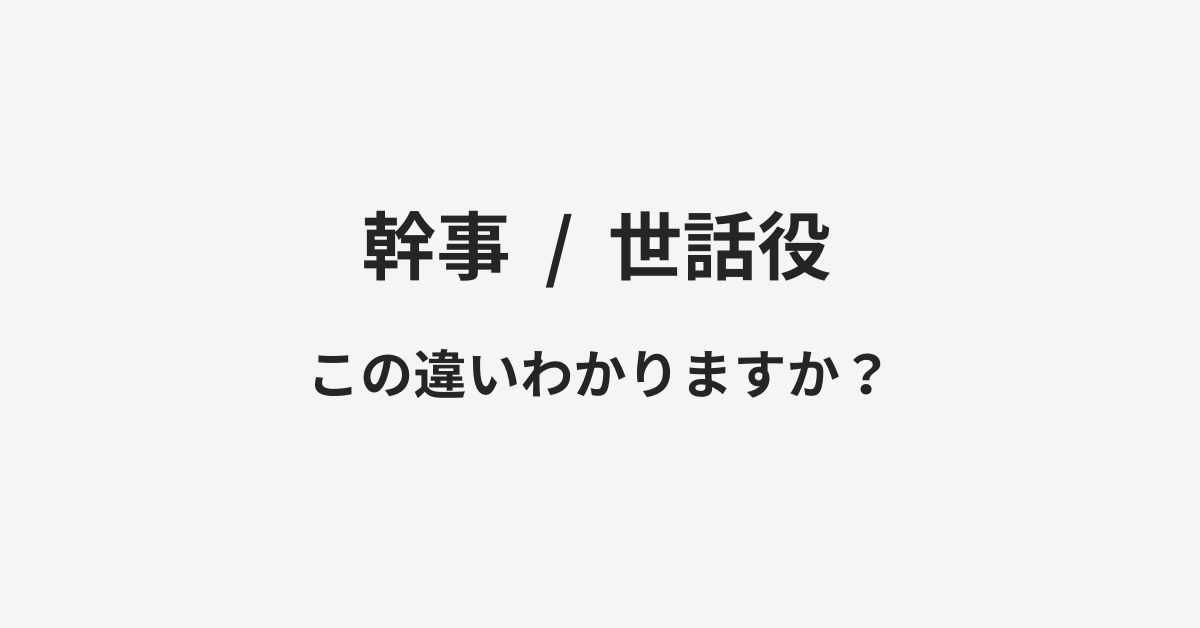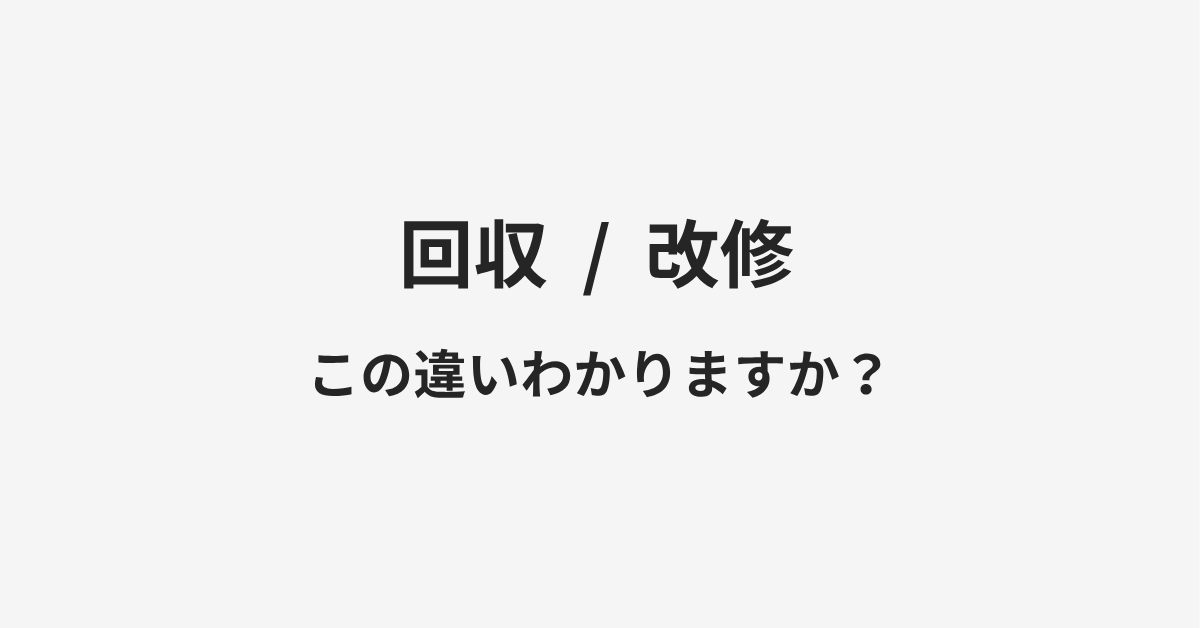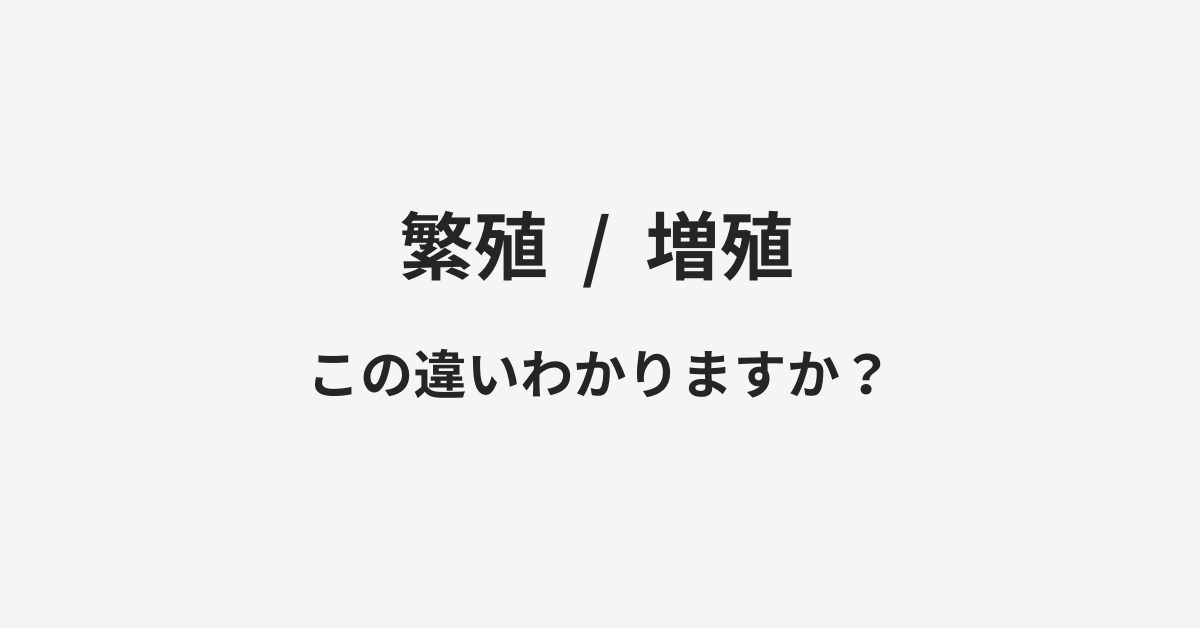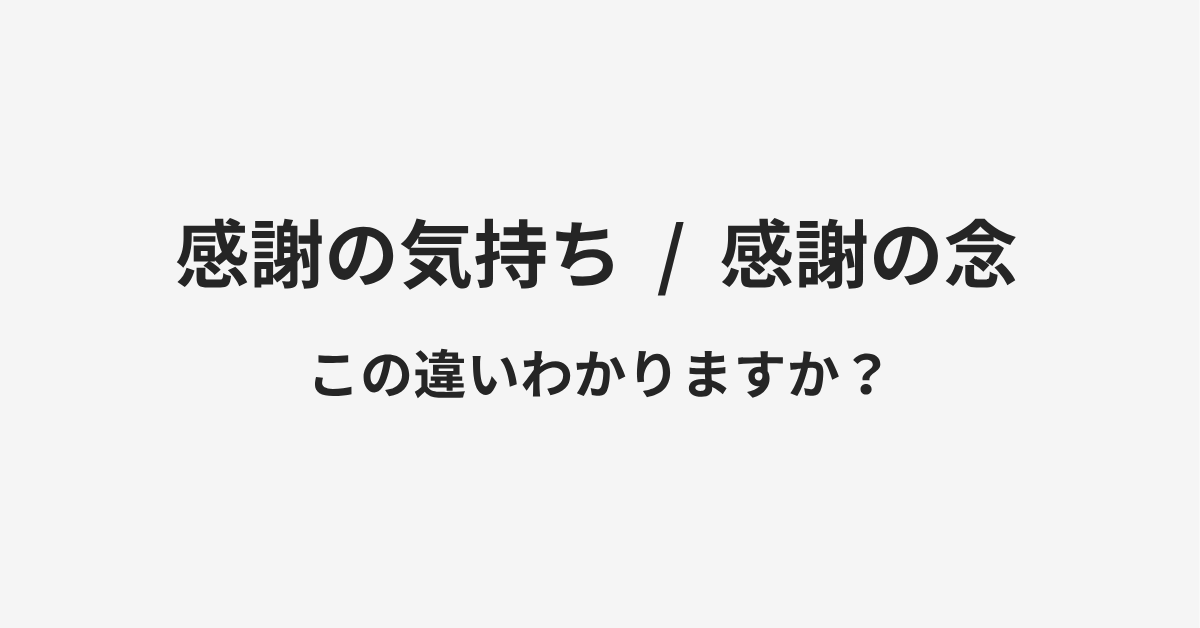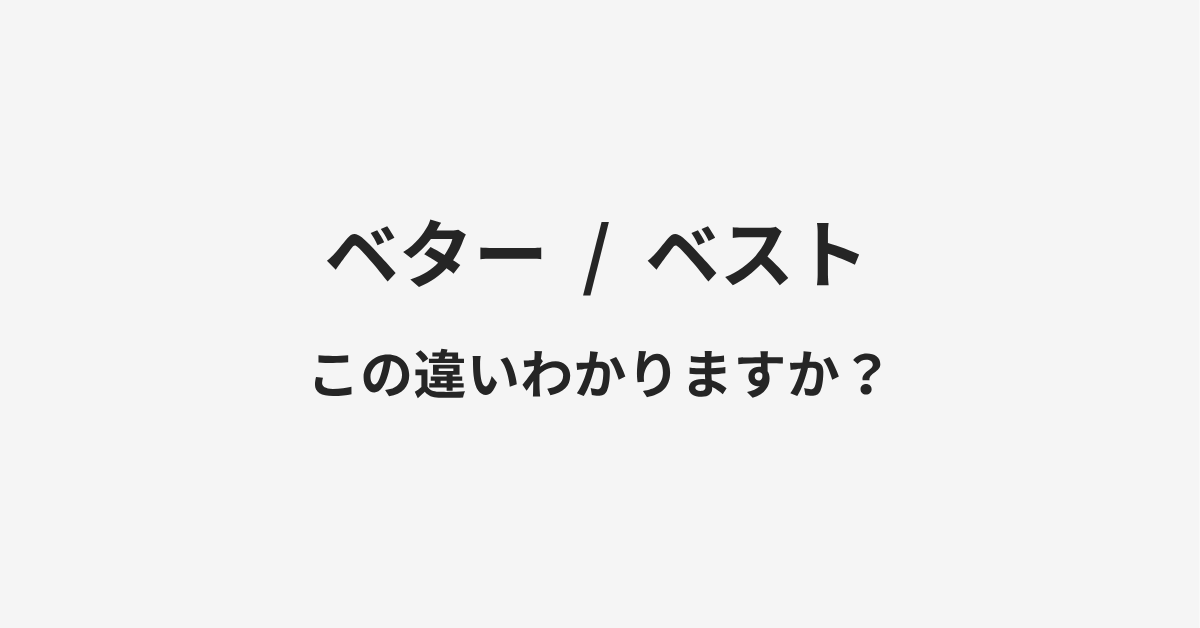【成り立ち】と【由来】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
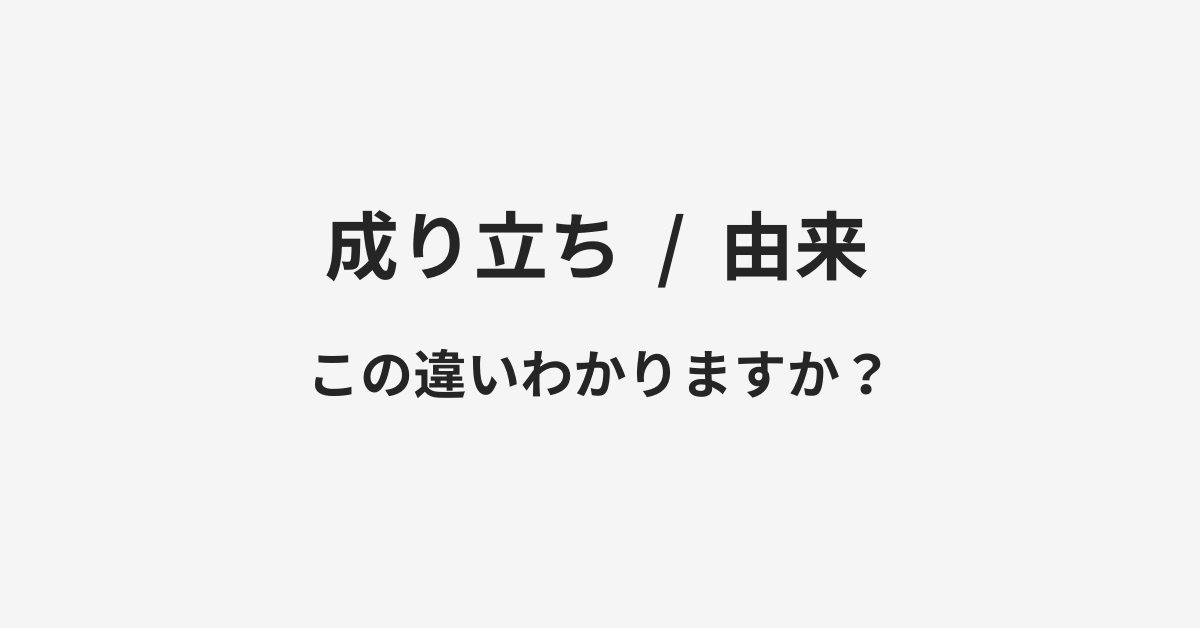
成り立ちと由来の分かりやすい違い
成り立ちと由来は、どちらも物事の背景を説明しますが、焦点が違います。
成り立ちは「この会社の成り立ち」のように、どのように作られたか、構成されているかを表します。由来は「地名の由来」のように、名前や習慣がどこから来たのか、起源を表します。
成り立ちは「形成過程」、由来は「起源・語源」という違いがあります。
成り立ちとは?
成り立ちとは、物事がどのような要素から構成され、どのような過程を経て現在の形になったかを表す言葉です。「会社の成り立ち」「社会の成り立ち」「言葉の成り立ち」など、構造や形成過程に焦点を当てた表現です。組織、制度、概念などが、どのように組み立てられているかを説明する際に使います。
成り立ちを理解することは、物事の本質を把握する上で重要です。例えば、漢字の成り立ちを知ると、なぜその形になったのか、部首の意味は何かなど、文字の構造が理解できます。企業の成り立ちを知れば、その企業の理念や強みが分かります。
「成り立つ」という動詞から派生した名詞で、完成に至るまでのプロセスや、現在の構成要素を重視する表現です。分析的、構造的な視点から物事を理解したい時に適した言葉です。
成り立ちの例文
- ( 1 ) この組織の成り立ちを説明します。
- ( 2 ) 日本語の文章の成り立ちは主語・述語が基本です。
- ( 3 ) 会社の成り立ちを知ると、企業理念が理解できます。
- ( 4 ) この制度の成り立ちには複雑な背景があります。
- ( 5 ) 漢字の成り立ちを学ぶと、覚えやすくなります。
- ( 6 ) チームの成り立ちから現在まで10年が経ちました。
成り立ちの会話例
由来とは?
由来とは、物事の起源、語源、そもそもの始まりを表す言葉です。「地名の由来」「風習の由来」「言葉の由来」など、なぜその名前になったのか、どこから伝わってきたのかという歴史的な起源を説明する際に使います。
由来は物語性があることが多く、伝説や言い伝え、歴史的な出来事と結びついていることがよくあります。例えば、「節分の由来は平安時代の宮中行事にある」「この地名の由来は、昔ここに大きな桜の木があったことから」など、過去のエピソードを含むことが特徴です。
由来を知ることで、現在の習慣や名称に込められた意味や、先人たちの思いを理解できます。文化的、歴史的な背景を重視し、「なぜ」「どこから」という疑問に答える表現として、教育や観光案内などでもよく使われます。
由来の例文
- ( 1 ) ひな祭りの由来は平安時代にさかのぼります。
- ( 2 ) この地名の由来は、昔の地形から来ています。
- ( 3 ) 「サンドイッチ」の由来はイギリスの伯爵の名前です。
- ( 4 ) お盆の由来を子供たちに教えました。
- ( 5 ) 校名の由来は、創立者の名前から取られています。
- ( 6 ) この言葉の由来を調べてみると面白い発見がありました。
由来の会話例
成り立ちと由来の違いまとめ
成り立ちと由来は、物事の背景を説明する視点が異なります。成り立ちは構造や形成過程に焦点を当て、どのように作られたか、何から構成されているかを説明します。
由来は起源や語源に焦点を当て、そもそもどこから始まったのか、なぜその名前なのかを説明します。成り立ちは「構造的説明」、由来は「歴史的説明」という違いがあります。
「日本語の成り立ち」は言語の構造、「お正月の由来」は習慣の起源というように使い分けます。
成り立ちと由来の読み方
- 成り立ち(ひらがな):なりたち
- 成り立ち(ローマ字):naritachi
- 由来(ひらがな):ゆらい
- 由来(ローマ字):yurai