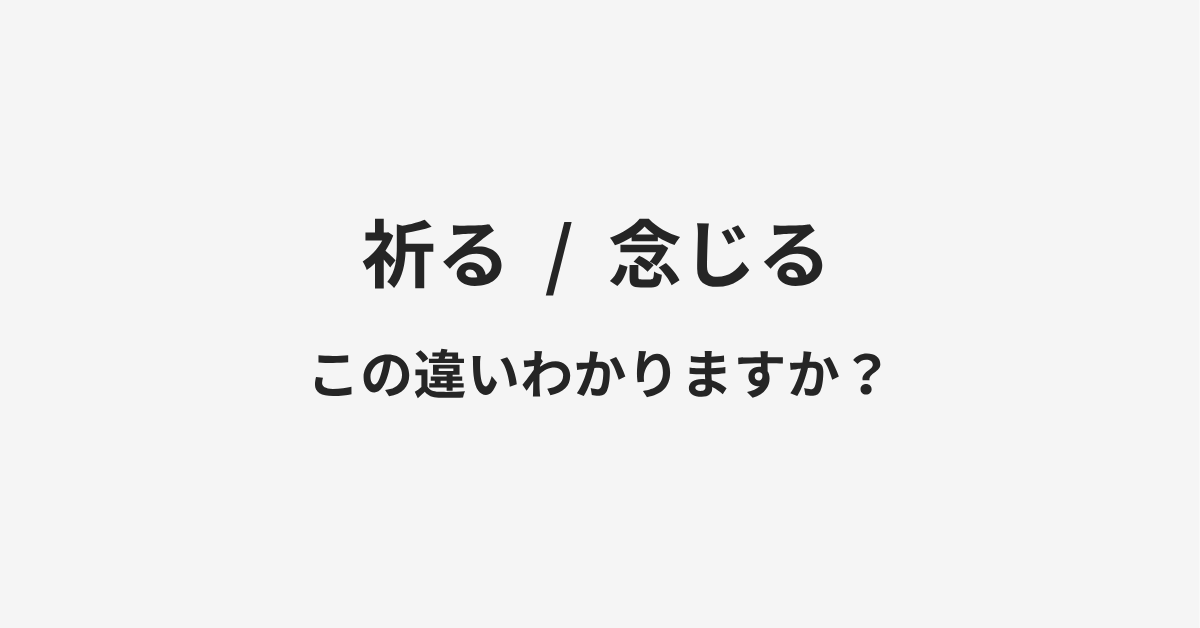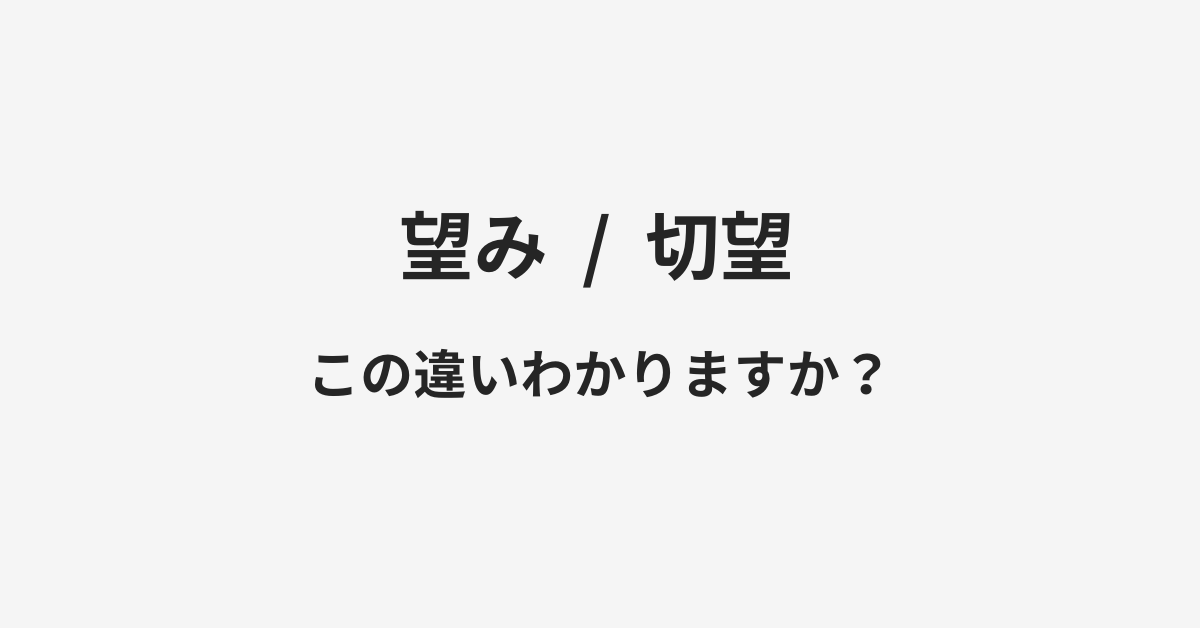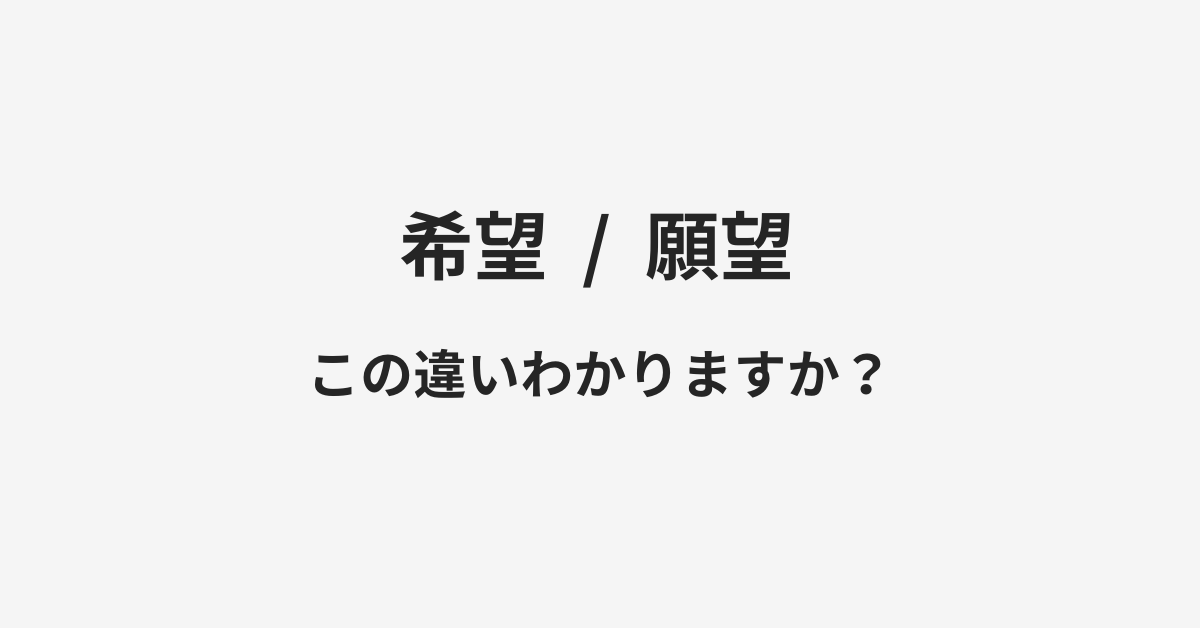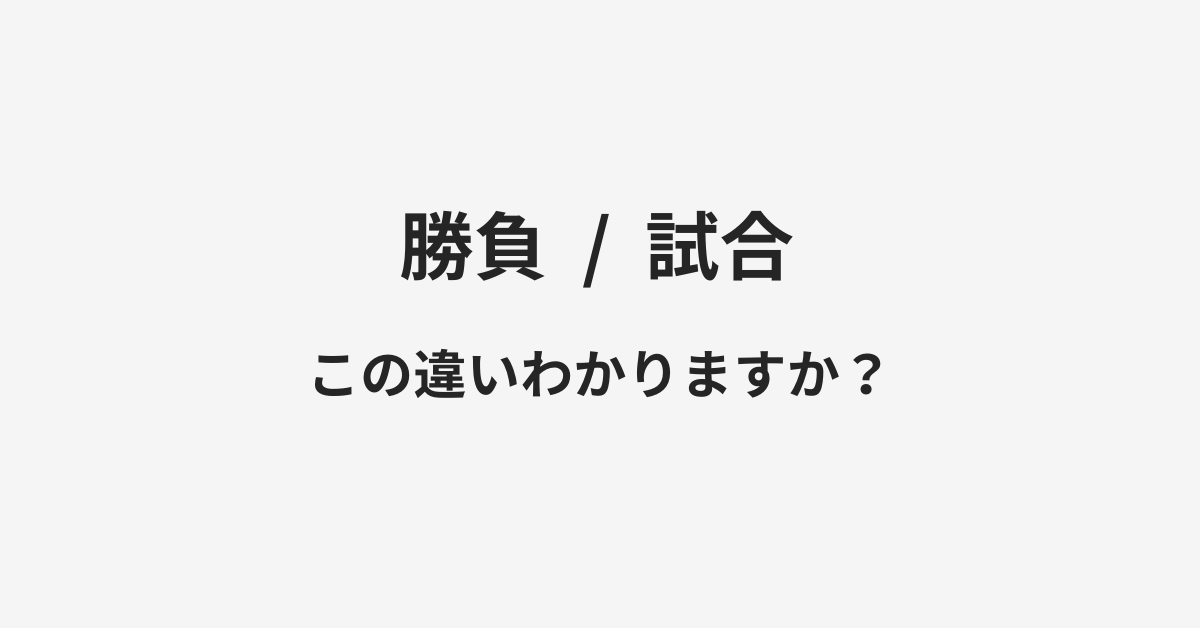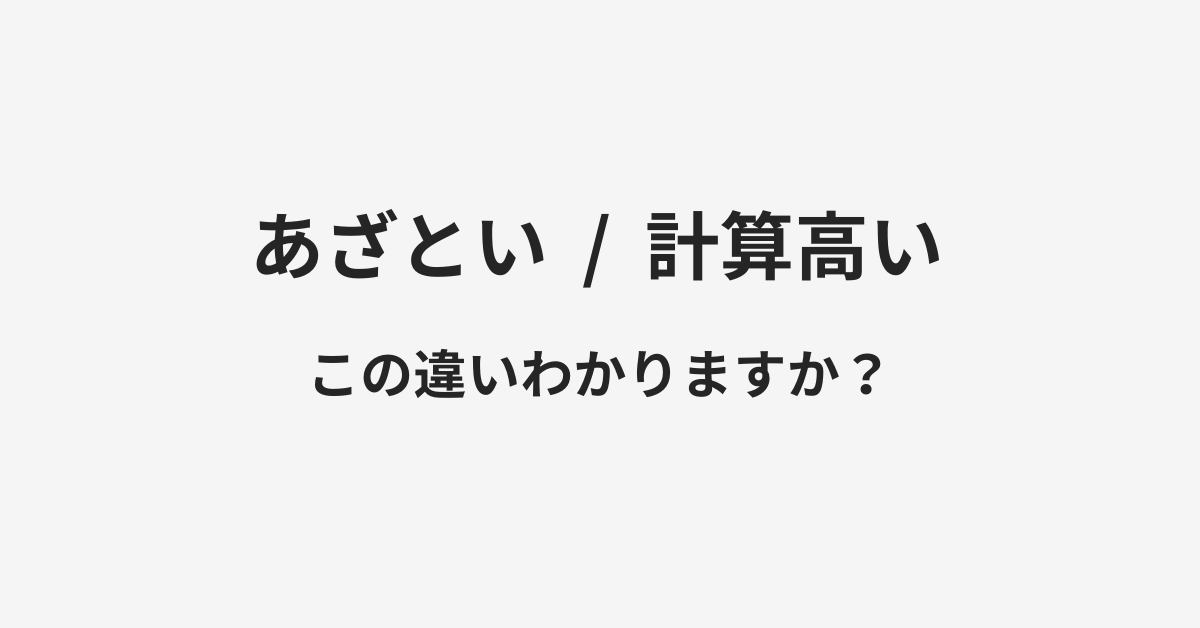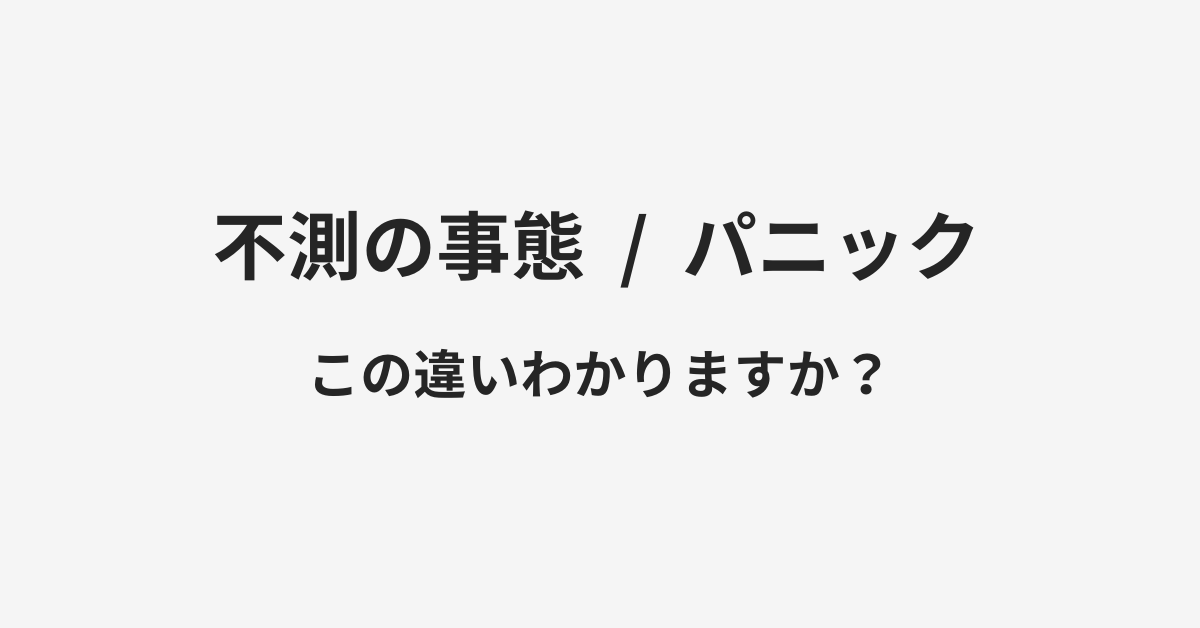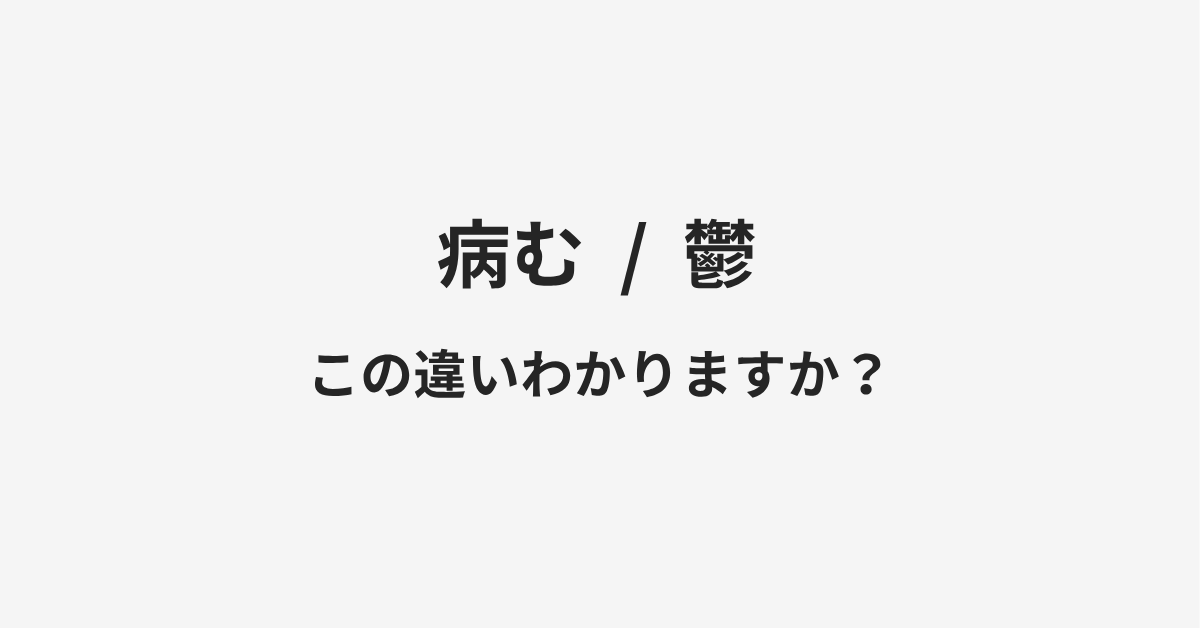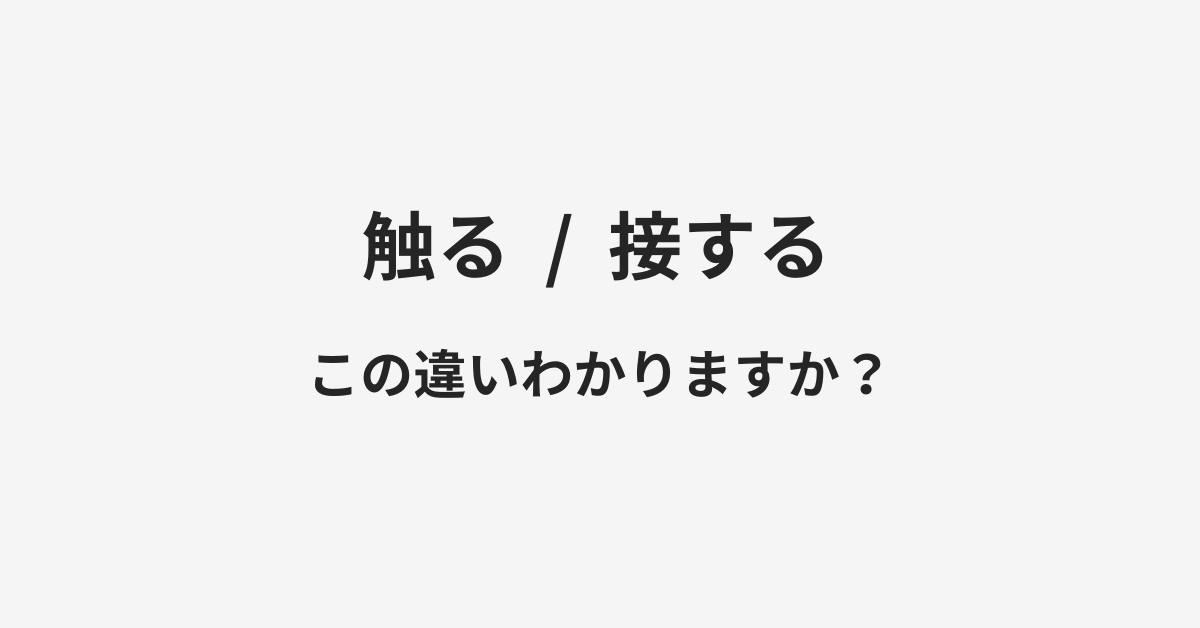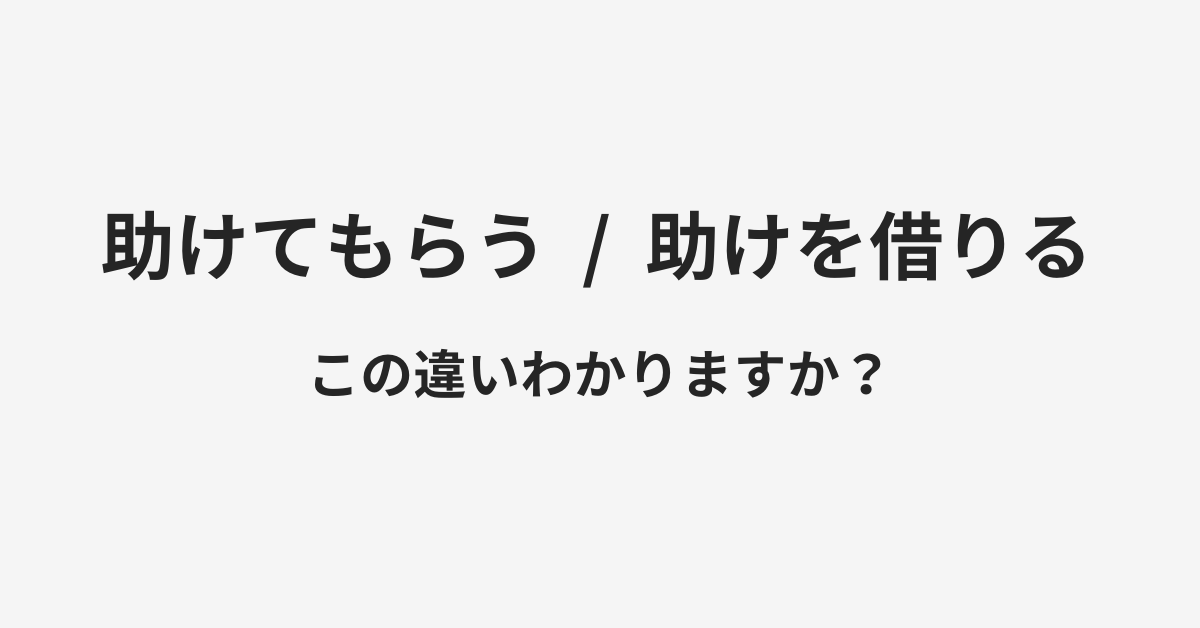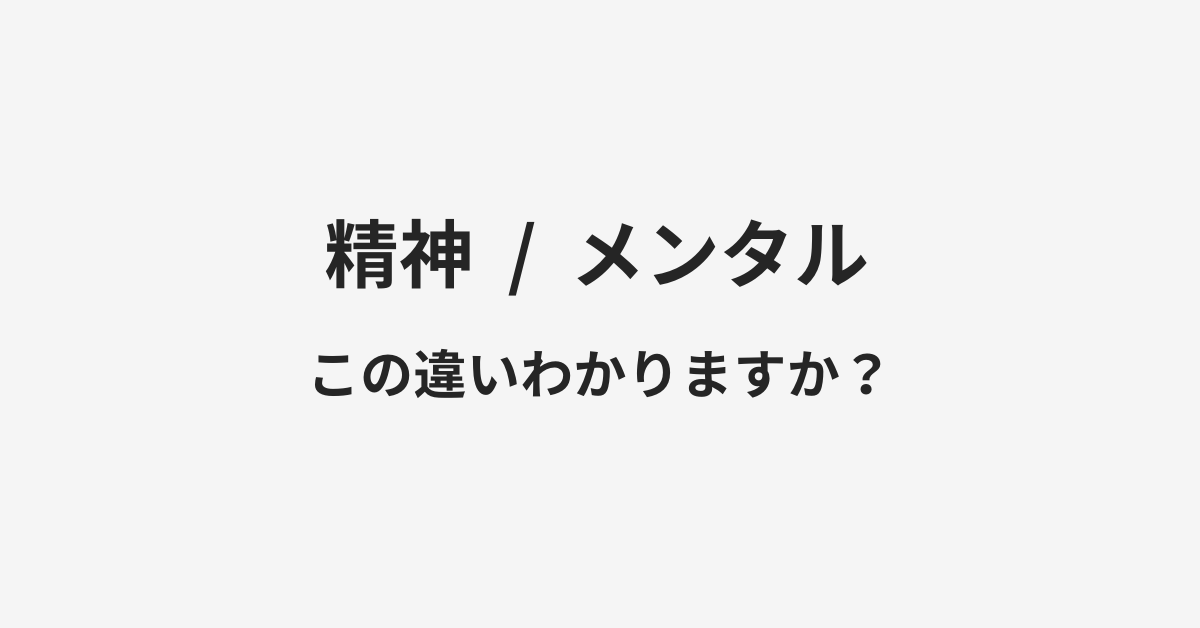【拝む】と【願う】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
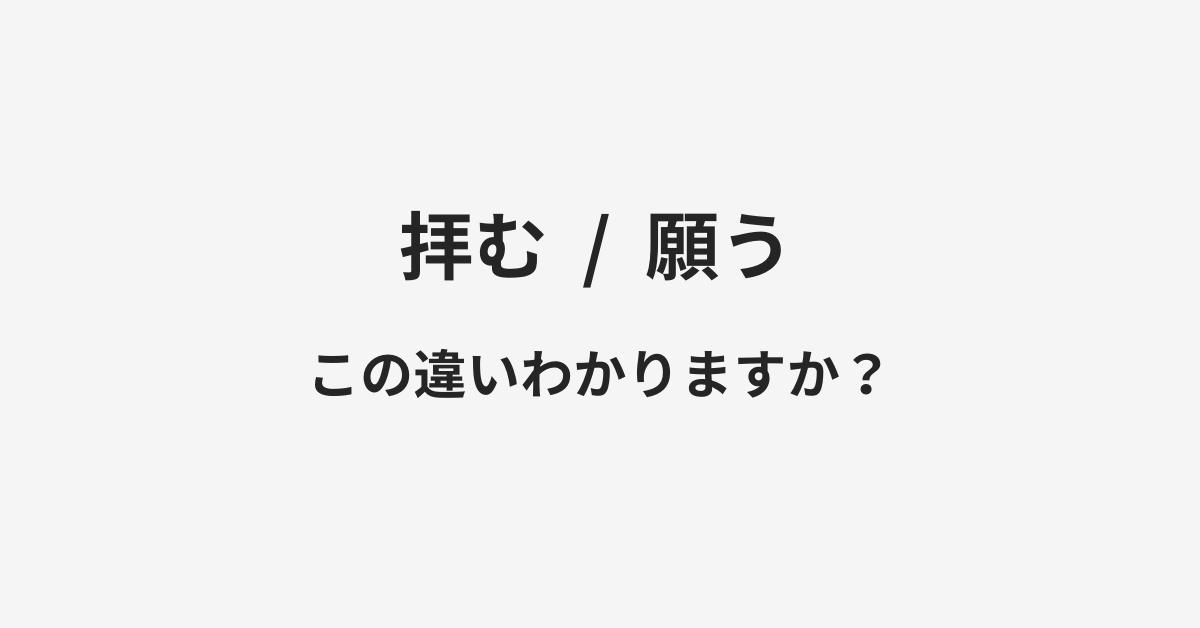
拝むと願うの分かりやすい違い
拝むと願うは、どちらも何かを望む気持ちを表しますが、表現方法と文脈が異なります。拝むは手を合わせるなどの身体的な動作を伴う祈りの行為で、宗教的・儀礼的な要素があります。
願うは心の中で望みを抱く内的な思いで、日常的に使われます。メンタルヘルスでは、拝む行為は儀式として心を落ち着かせ、願う気持ちは希望を維持する力となり、両方が心の健康に寄与します。
拝むとは?
拝むとは、手を合わせて祈る、頭を下げるなど、身体的な動作を伴って神仏や大いなる存在に祈願する行為を指します。宗教的・儀礼的な文脈で使われることが多く、敬虔な気持ちや切実な思いを形として表現します。また、相手に強くお願いする時にも使われる表現です。心理学的には、拝むという身体的な行為は、儀式行動として心理的な安定をもたらす効果があります。
決まった動作を行うことで、不安や混乱した気持ちを整理し、心を落ち着かせることができます。また、自分より大きな存在に委ねるという行為は、コントロールできない状況への対処法としても機能します。
メンタルヘルスの観点から、拝むという行為は重要なコーピング(対処)方法の一つです。宗教的な信念の有無にかかわらず、祈りの行為は希望を保ち、困難な状況でも前向きさを維持する助けとなります。ただし、過度に依存することなく、他の対処法と組み合わせることが大切です。
拝むの例文
- ( 1 ) 毎朝、家族の健康を拝むことで、一日を前向きに始められるようになりました。
- ( 2 ) 困難な時、神社で拝むことで心の重荷が軽くなる感覚があります。
- ( 3 ) 亡くなった人に手を合わせて拝む時間が、悲しみを癒す助けになっています。
- ( 4 ) 回復を拝む気持ちが、治療を続ける原動力になっています。
- ( 5 ) 自然に向かって拝むことで、謙虚な気持ちを取り戻せます。
- ( 6 ) 子どもの幸せを拝む瞬間が、親としての使命を再確認させてくれます。
拝むの会話例
願うとは?
願うとは、心の中で何かを望み、そうなってほしいと思う内的な感情や思考を表す言葉です。具体的な行動を伴わない場合も多く、日常的に使われる表現です。希望、期待、切望など、様々な強度の望みを包含し、必ずしも宗教的な文脈を必要としません。心理学的に見ると、願うという行為は希望を持つことと密接に関連しています。
希望は、目標達成への道筋を考え(経路思考)、その実現への意欲を持つ(動因思考)ことで構成されます。願いを持つことは、困難な状況でも前向きさを保ち、レジリエンスを高める重要な要素です。メンタルヘルスにおいて、願いを持つことは精神的な健康の指標でもあります。
うつ状態では願いや希望を持てなくなることが多いため、小さな願いでも持てることは回復の兆しといえます。現実的な願いと非現実的な願いのバランスを保ちながら、願いを行動につなげていくことが、心の健康維持に重要です。
願うの例文
- ( 1 ) 明日が今日より少しでも良くなることを願いながら、一日を終えています。
- ( 2 ) 友人の回復を心から願うことで、自分も前向きになれます。
- ( 3 ) 小さな願いを持ち続けることが、生きる希望につながっています。
- ( 4 ) 世界の平和を願う気持ちが、自分の心も穏やかにしてくれます。
- ( 5 ) 自分の成長を願うことで、日々の努力の意味を見出しています。
- ( 6 ) 誰かの幸せを願える自分でいることが、心の健康のバロメーターです。
願うの会話例
拝むと願うの違いまとめ
拝むと願うの違いは、表現の形と文脈にあります。拝むは身体的な祈りの行為、願うは内的な希望の思いです。メンタルヘルスでは、どちらも重要な役割を果たします。
拝む行為は儀式として心を安定させ、願う気持ちは希望を保つ原動力となります。
状況に応じて、これらを使い分けたり組み合わせたりすることで、心の健康を保つための多様な対処法となります。
拝むと願うの読み方
- 拝む(ひらがな):おがむ
- 拝む(ローマ字):ogamu
- 願う(ひらがな):ねがう
- 願う(ローマ字):negau