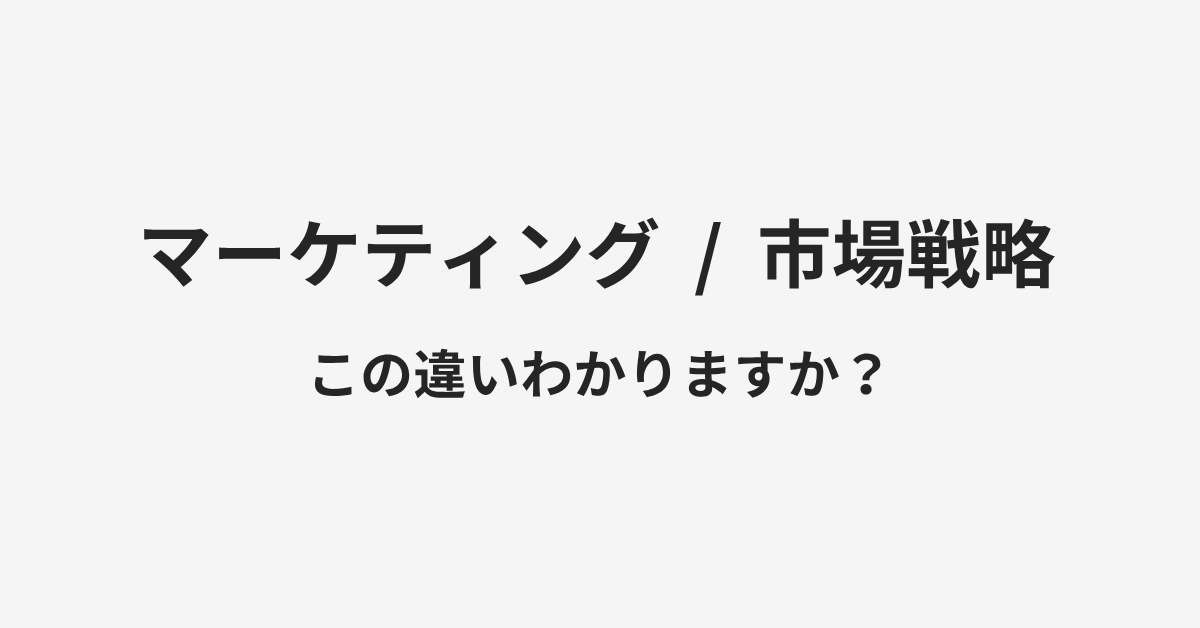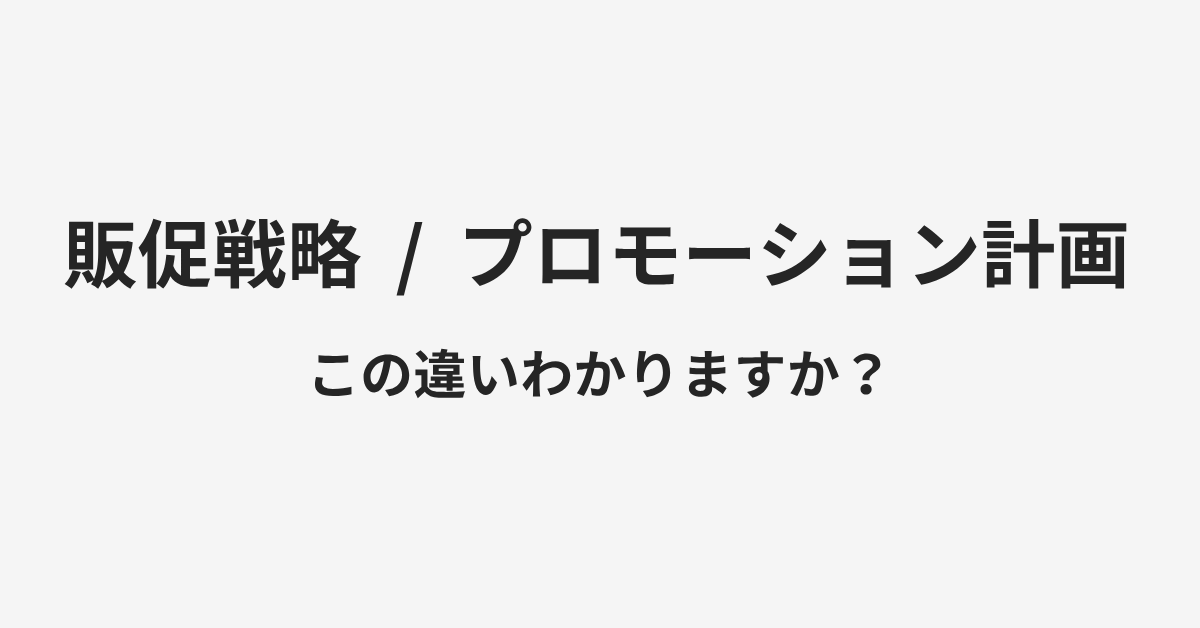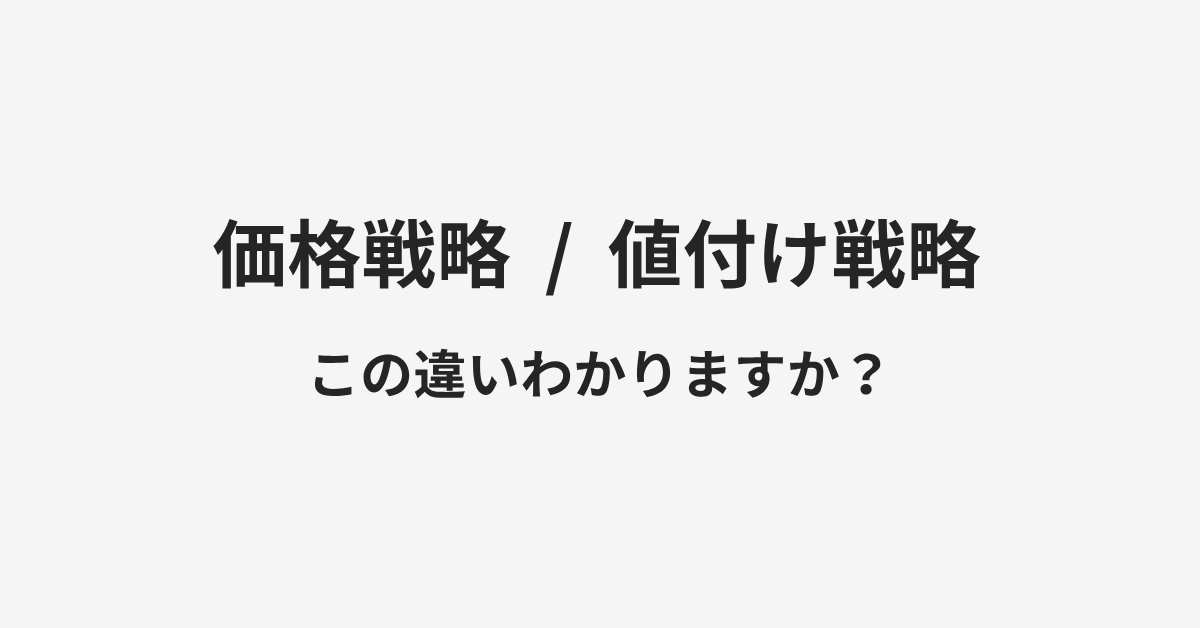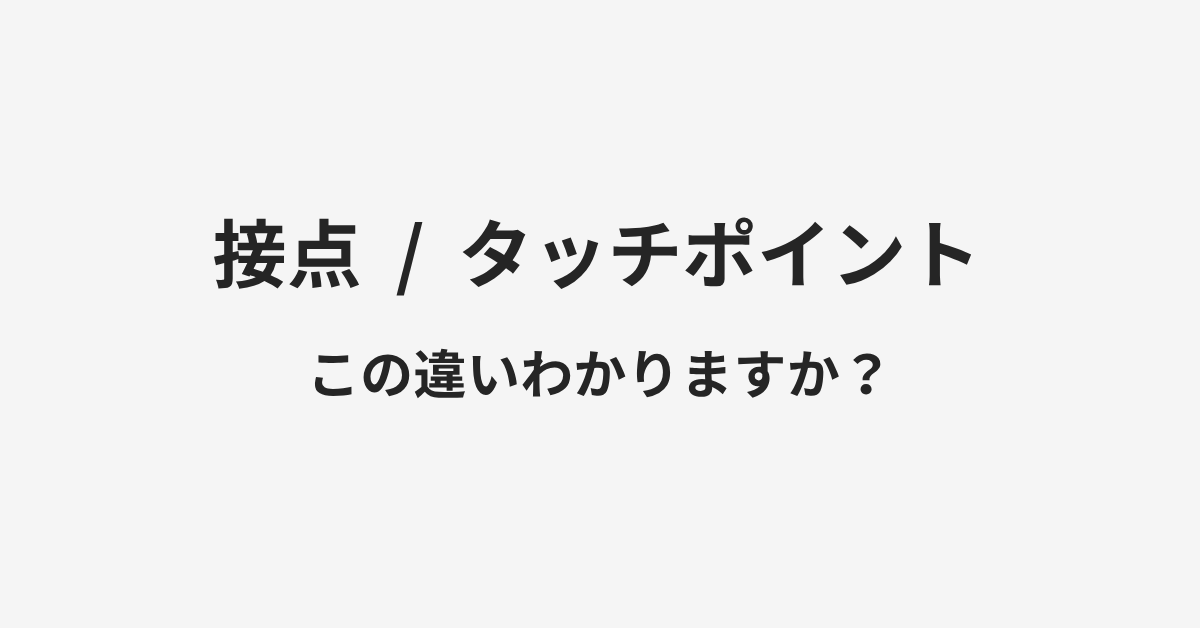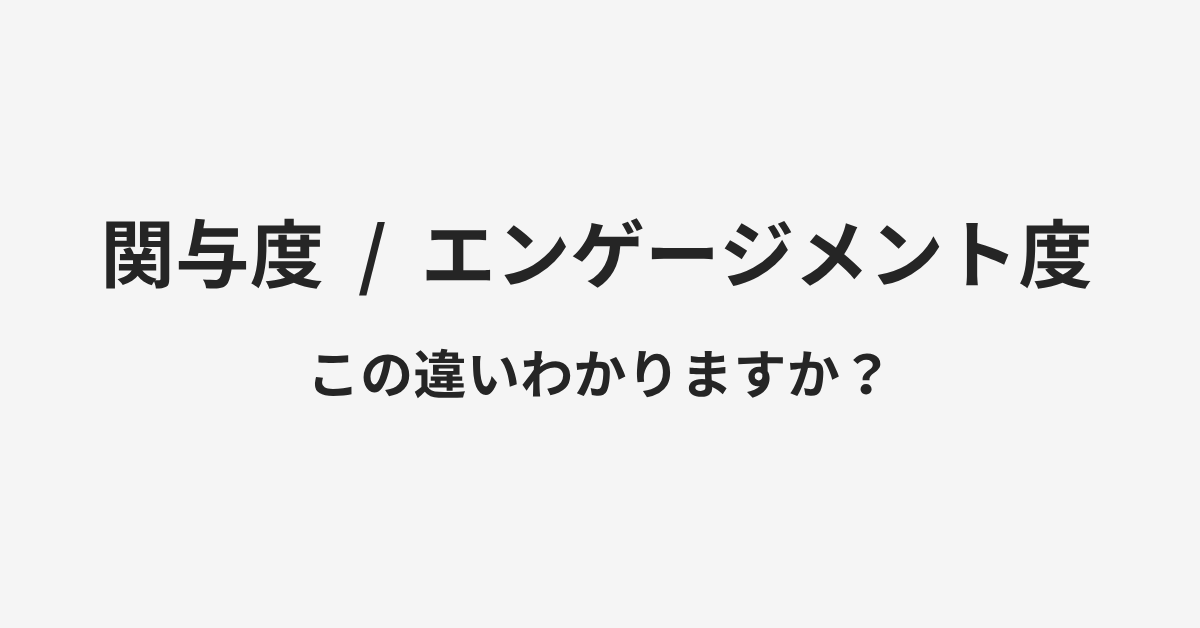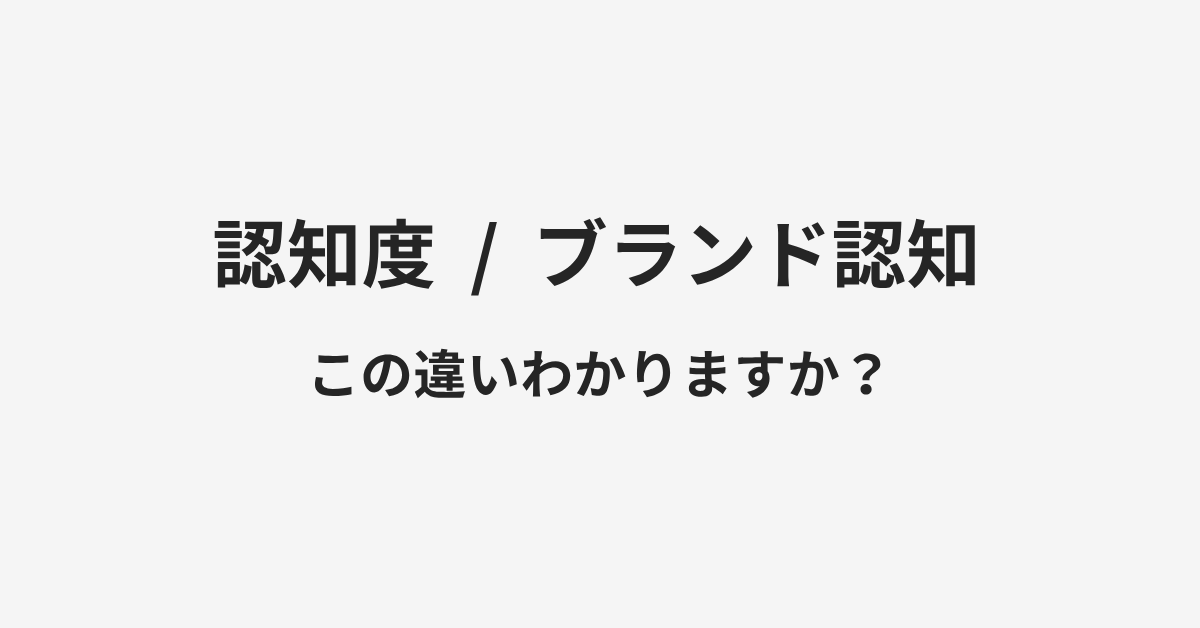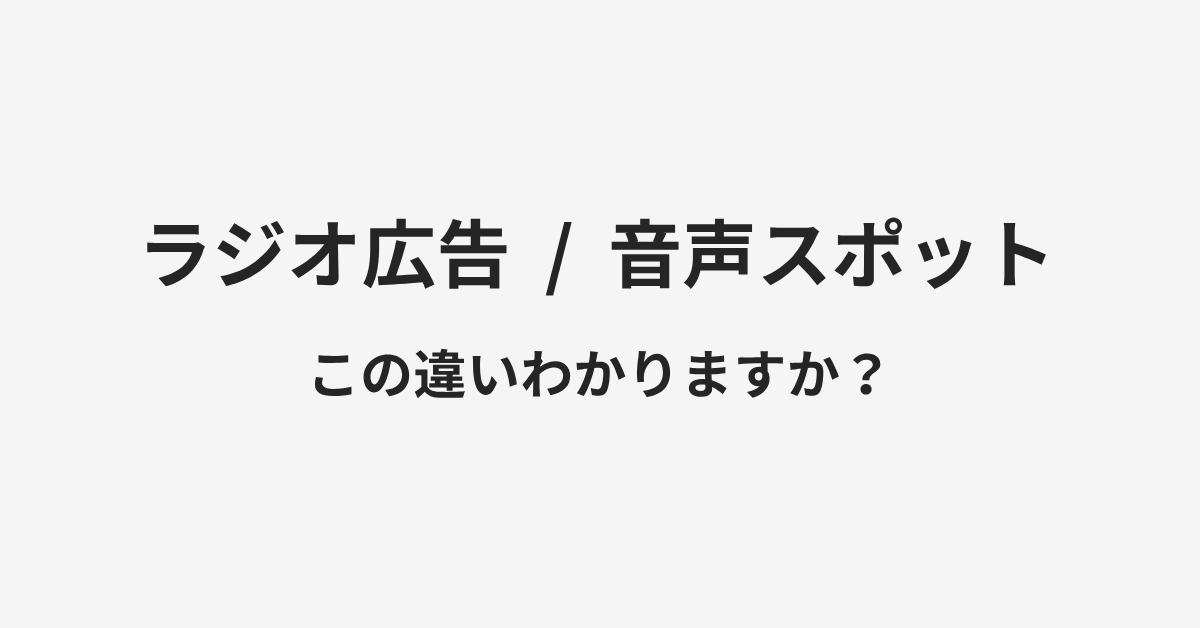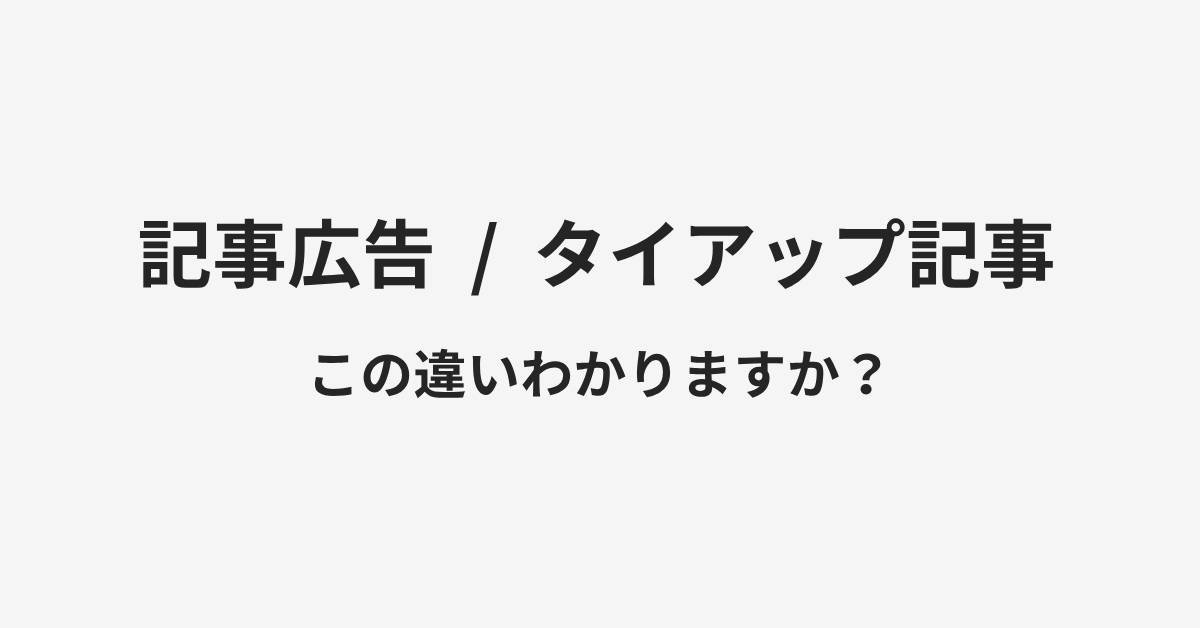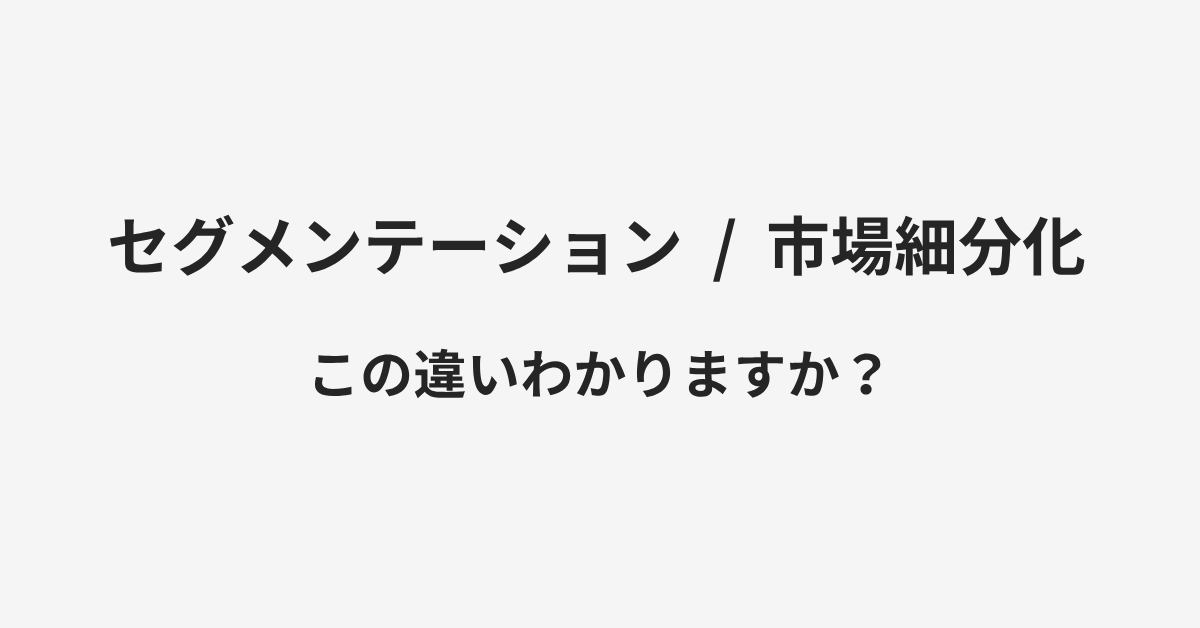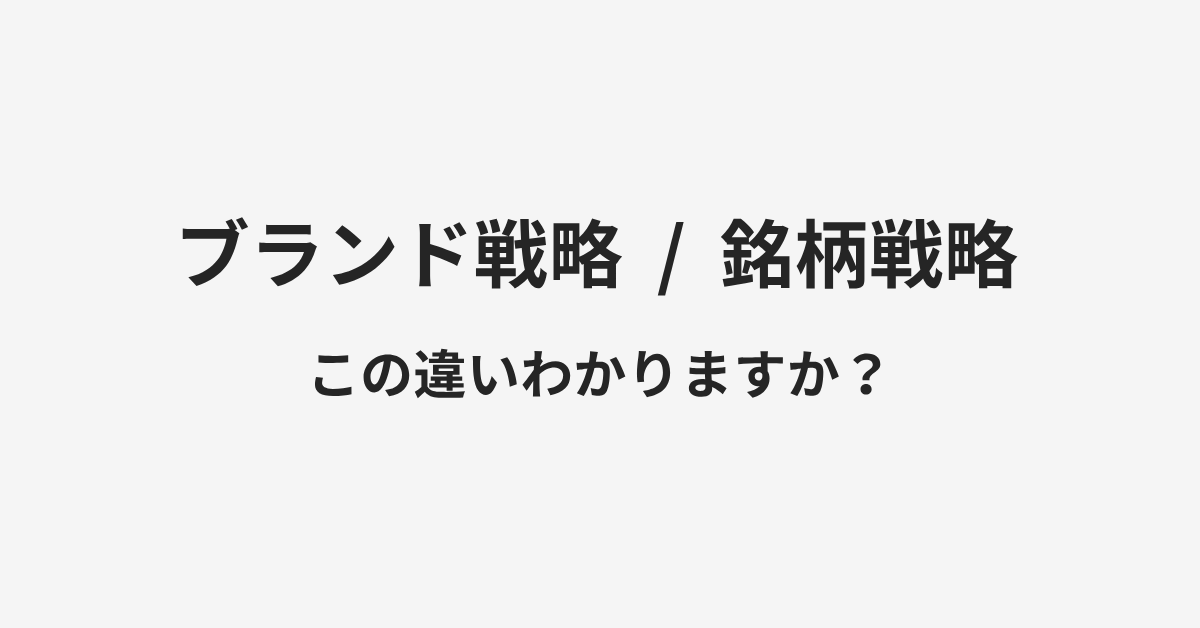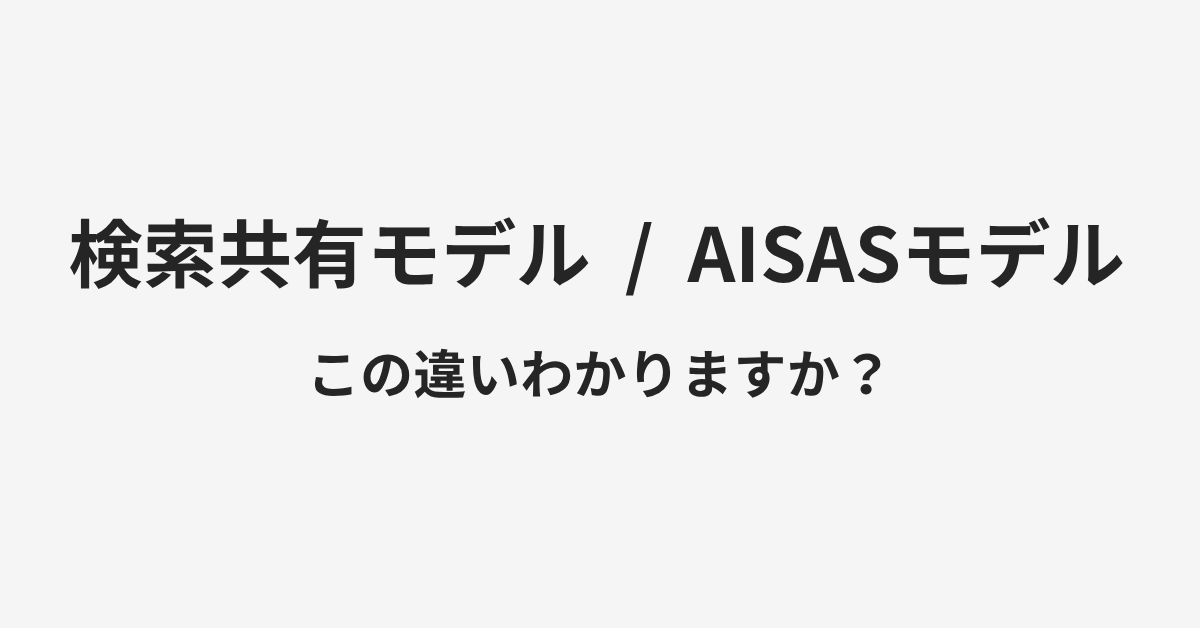【マーケミックス】と【4P戦略】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
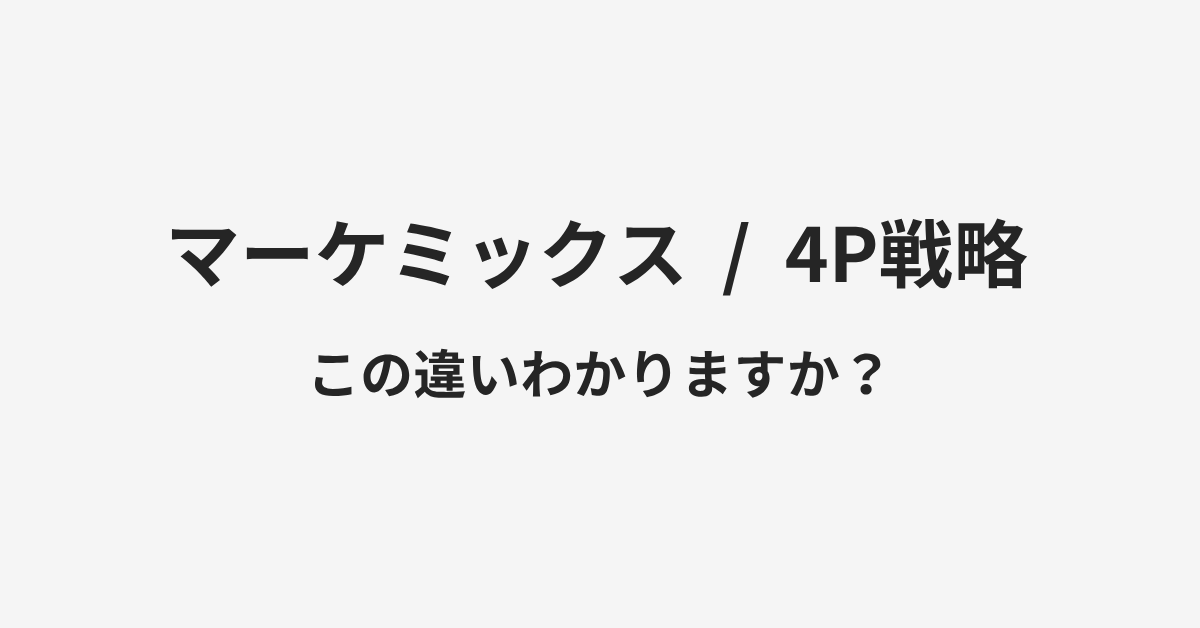
マーケミックスと4P戦略の分かりやすい違い
マーケミックスは、マーケティングで使ういろいろな手段を組み合わせることです。商品、価格、販売方法など、複数の要素をうまく混ぜ合わせます。
4P戦略は、マーケミックスの代表的な型で、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、販促(Promotion)の4つのPで構成されます。
マーケミックスが料理全体なら、4Pは基本レシピのようなものです。
マーケミックスとは?
マーケミックスとは、マーケティング目標を達成するために、企業がコントロール可能な複数のマーケティング要素を最適に組み合わせる概念です。顧客価値の創造と提供の総合的アプローチを表します。
伝統的な4P(製品・価格・流通・プロモーション)から、サービス業向けの7P、顧客視点の4Cなど、様々なフレームワークが派生しています。デジタル時代には新たな要素も加わっています。
効果的なマーケミックスは、各要素間の一貫性と相乗効果を重視します。市場環境や顧客ニーズの変化に応じて、継続的な最適化が求められる動的な概念です。
マーケミックスの例文
- ( 1 ) 新商品のマーケミックスを設計し、統合的な市場導入戦略を立案しました。
- ( 2 ) デジタルマーケミックスの最適化により、オンライン売上が倍増しました。
- ( 3 ) マーケミックスの見直しで、各施策の相乗効果が生まれました。
- ( 4 ) グローバルマーケミックスと現地適応のバランスを重視しています。
- ( 5 ) マーケミックスモデリングにより、投資配分を最適化できました。
- ( 6 ) 顧客体験を軸にしたマーケミックスの再構築を進めています。
マーケミックスの会話例
4P戦略とは?
4P戦略とは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)の4要素で構成される、最も基本的なマーケミックスのフレームワークです。1960年代にジェローム・マッカーシーが提唱しました。
各Pは相互に関連し、統合的に管理することで最大の効果を発揮します。製品戦略が価格を規定し、流通が顧客接点を決め、プロモーションが認知を高めるという連動性があります。
4Pは企業視点のフレームワークとして、現在も広く活用されています。ただし、顧客中心の時代には、4C(顧客価値・コスト・利便性・コミュニケーション)との併用も重要です。
4P戦略の例文
- ( 1 ) 4P戦略の徹底的な分析により、市場機会を発見しました。
- ( 2 ) 4P戦略の一貫性を高めたことで、ブランド力が向上しました。
- ( 3 ) 競合の4P戦略を分析し、差別化ポイントを明確にしました。
- ( 4 ) 4P戦略フレームワークを用いて、新規事業計画を策定しました。
- ( 5 ) 4P戦略の定期レビューにより、市場変化への対応力が向上しました。
- ( 6 ) 4P戦略に基づくKPI設定で、施策効果の測定が可能になりました。
4P戦略の会話例
マーケミックスと4P戦略の違いまとめ
マーケミックスは複数の要素を組み合わせる包括的概念、4P戦略はその代表的な実践フレームワークです。
4Pはマーケミックスの一種であり、最も普及している基本型といえます。現代では4Pを基礎としつつ、デジタル要素なども加えた拡張的なマーケミックスが求められています。
マーケミックスと4P戦略の読み方
- マーケミックス(ひらがな):まーけみっくす
- マーケミックス(ローマ字):ma-kemikkusu
- 4P戦略(ひらがな):よんぴーせんりゃく
- 4P戦略(ローマ字):yonnpi-sennryaku