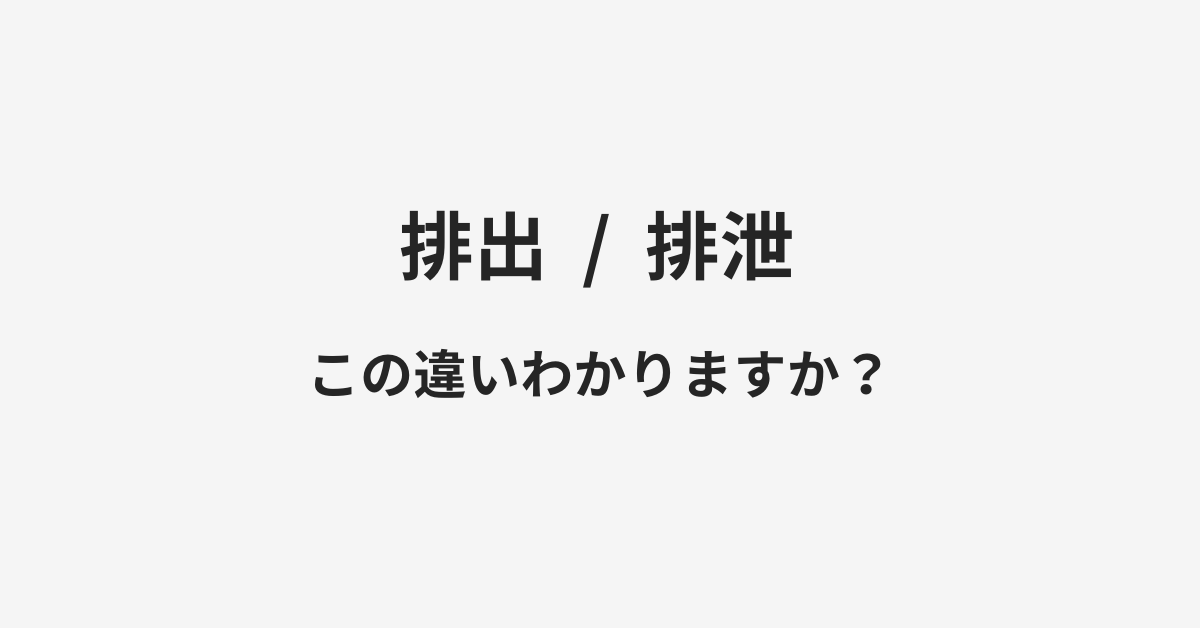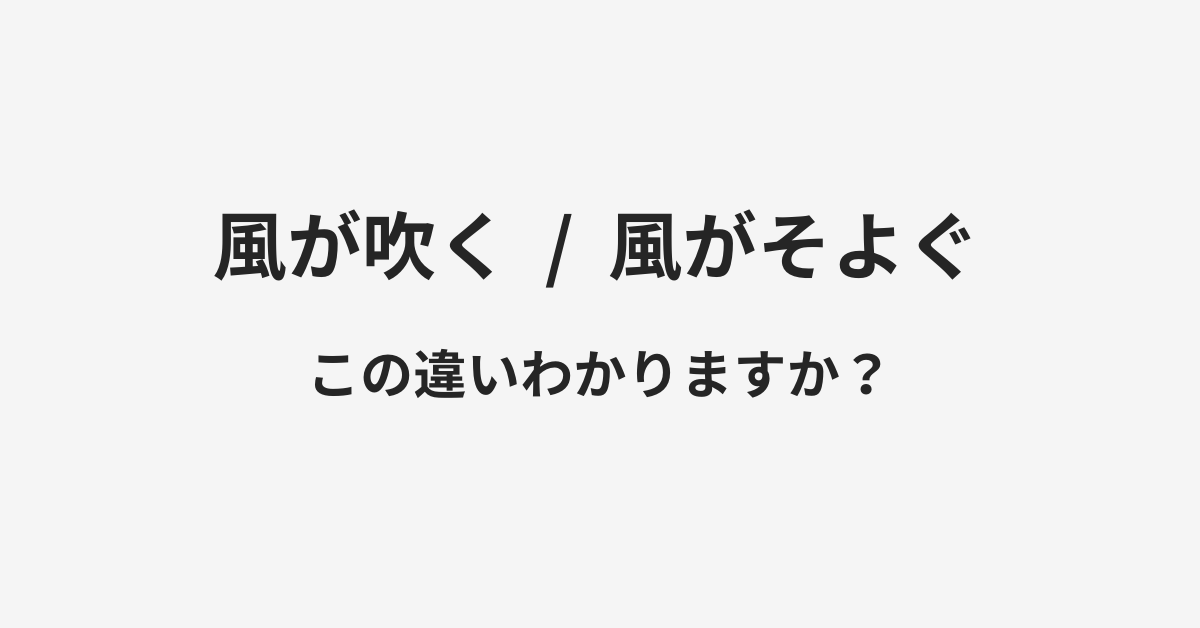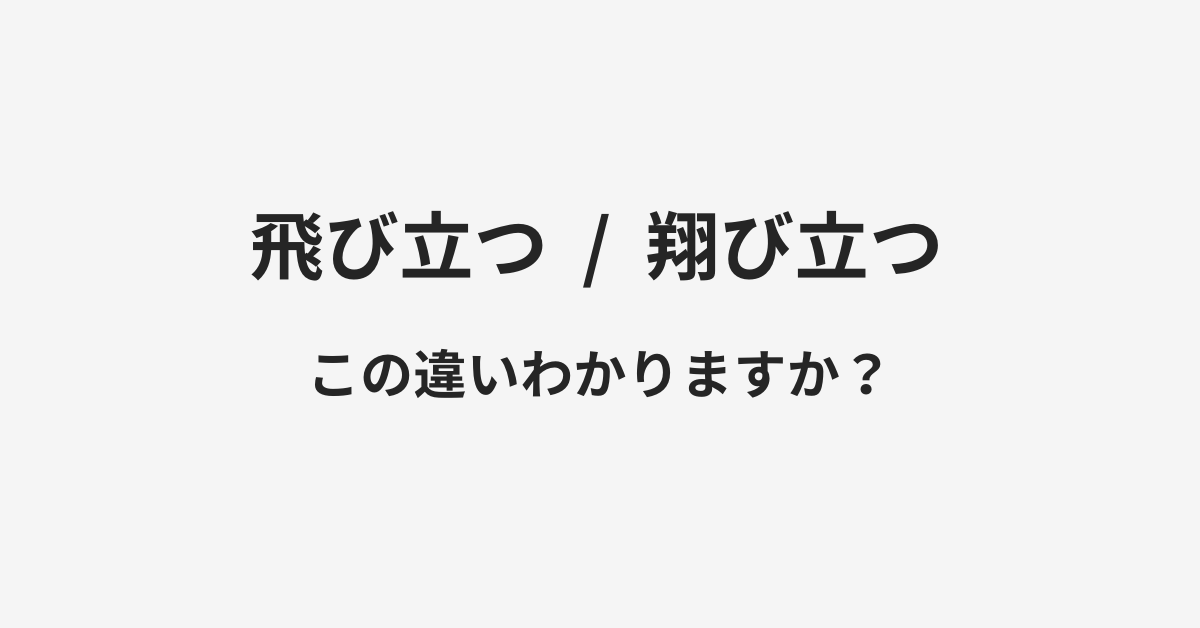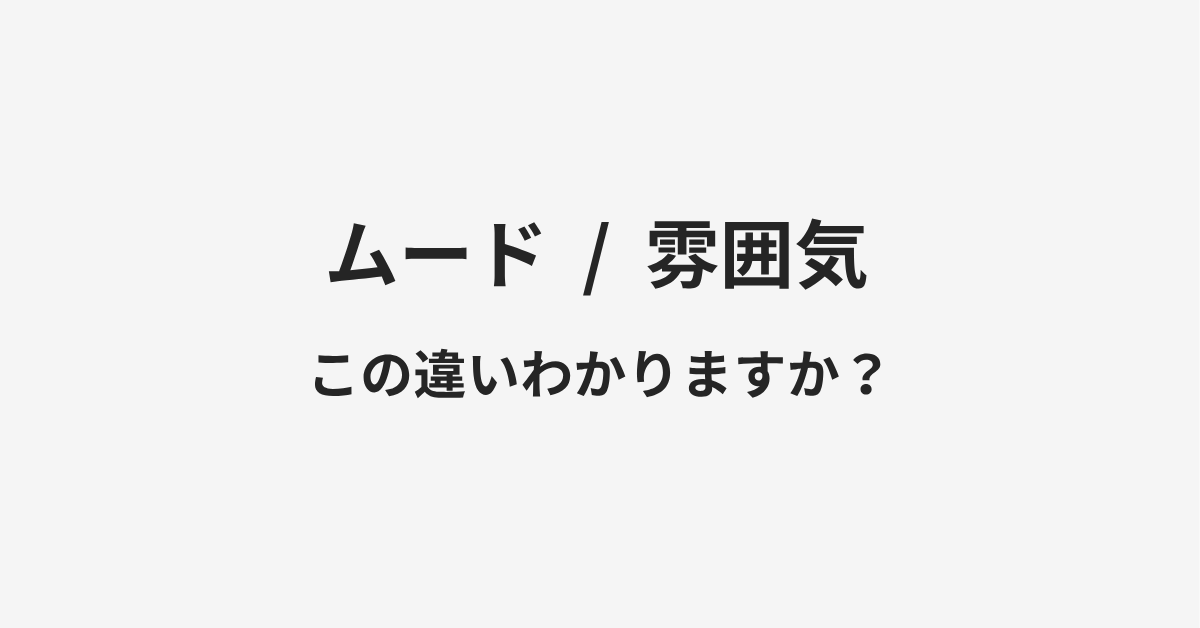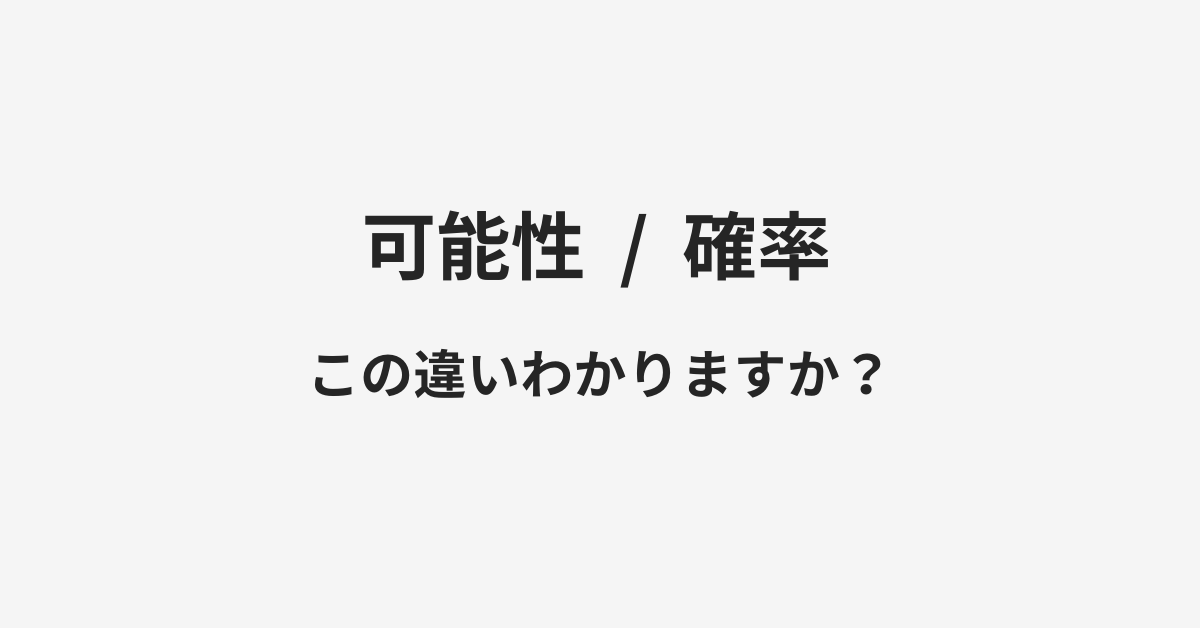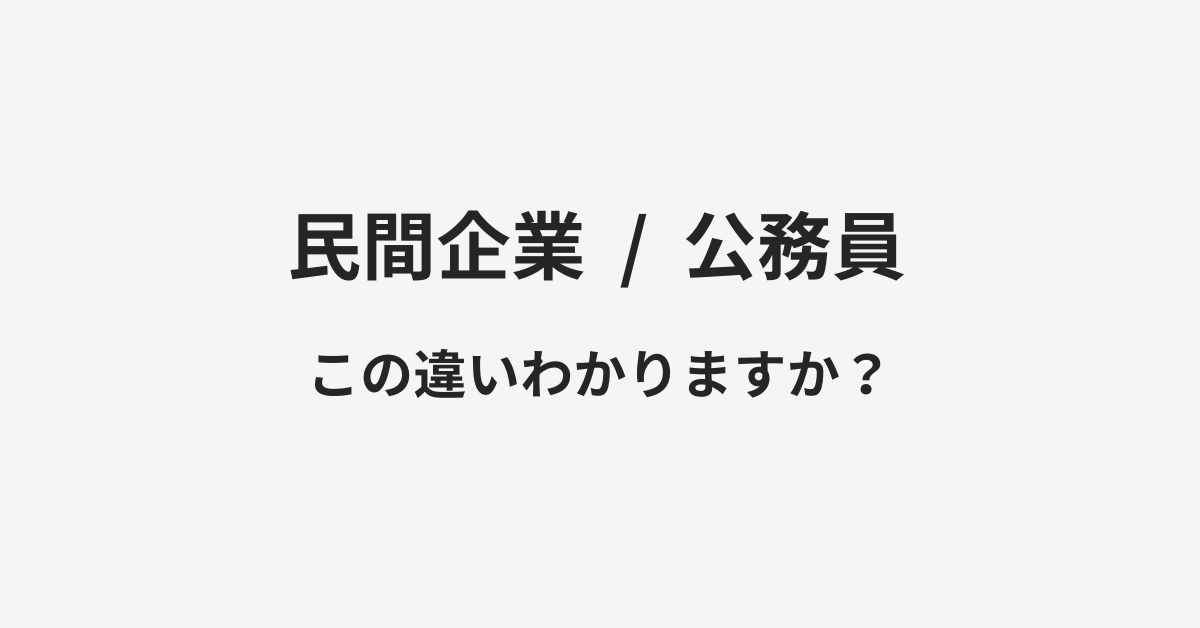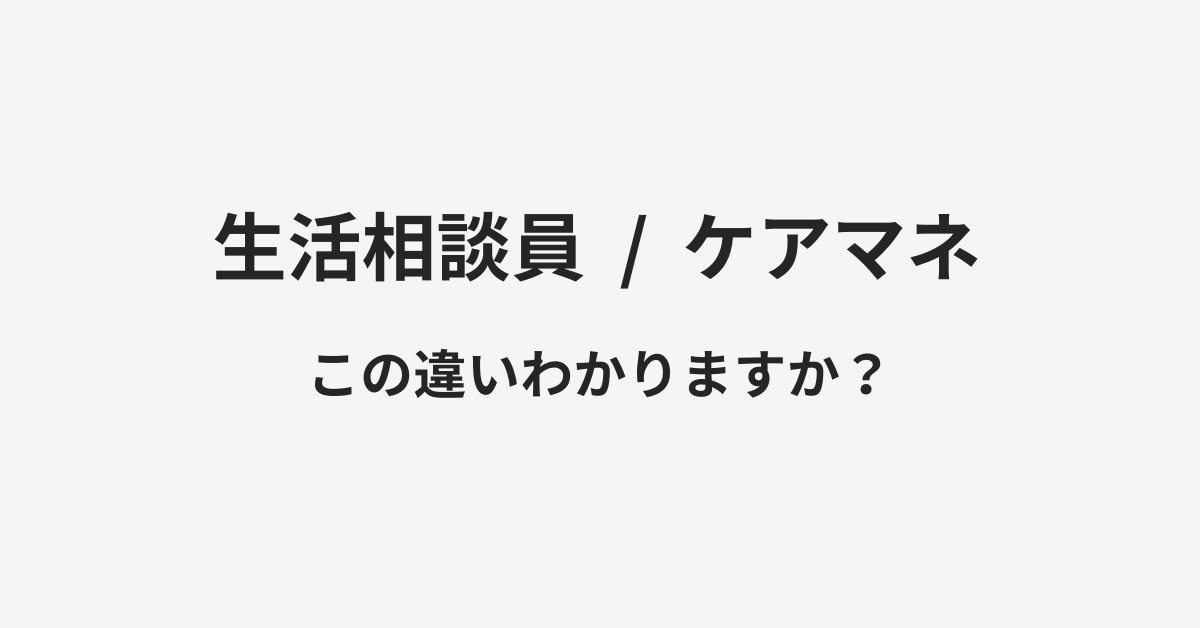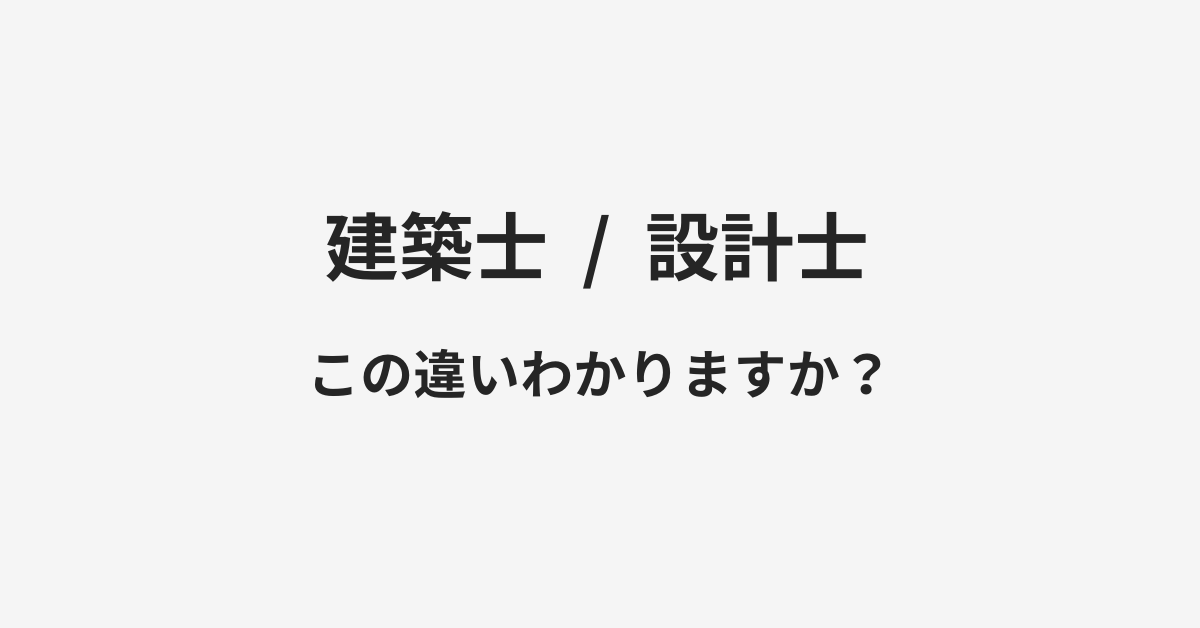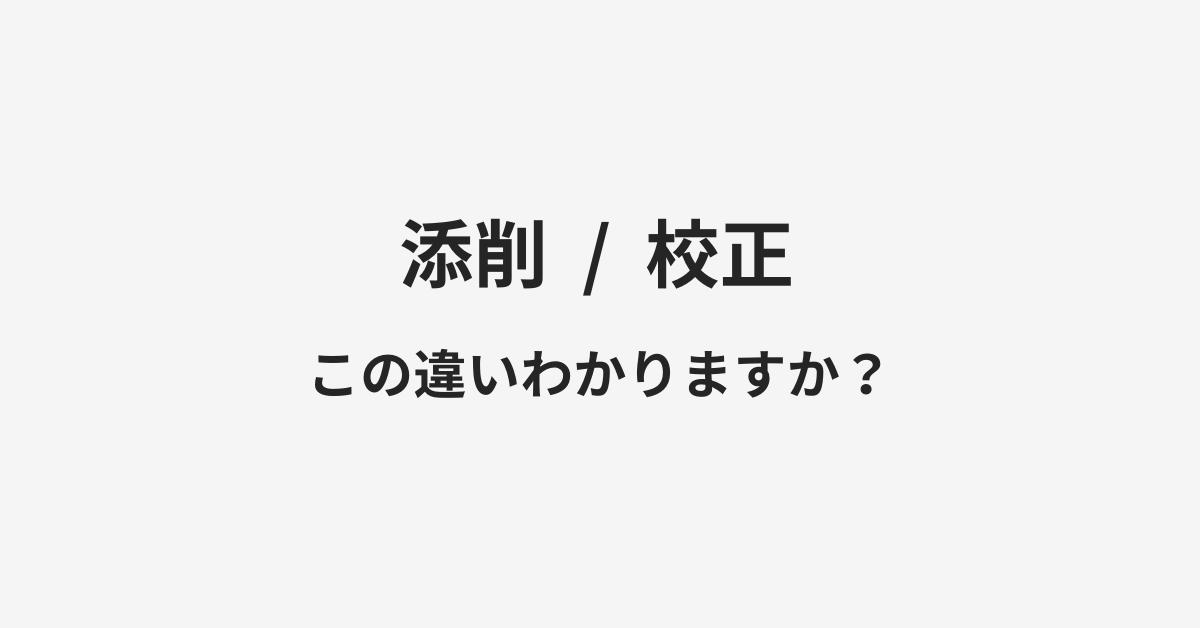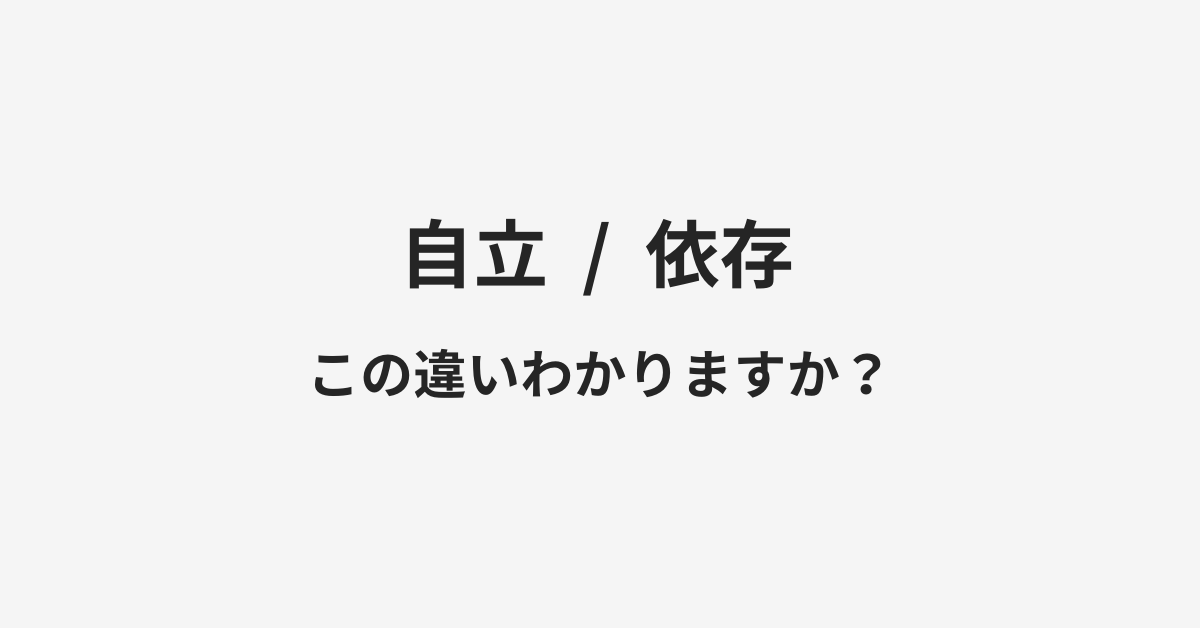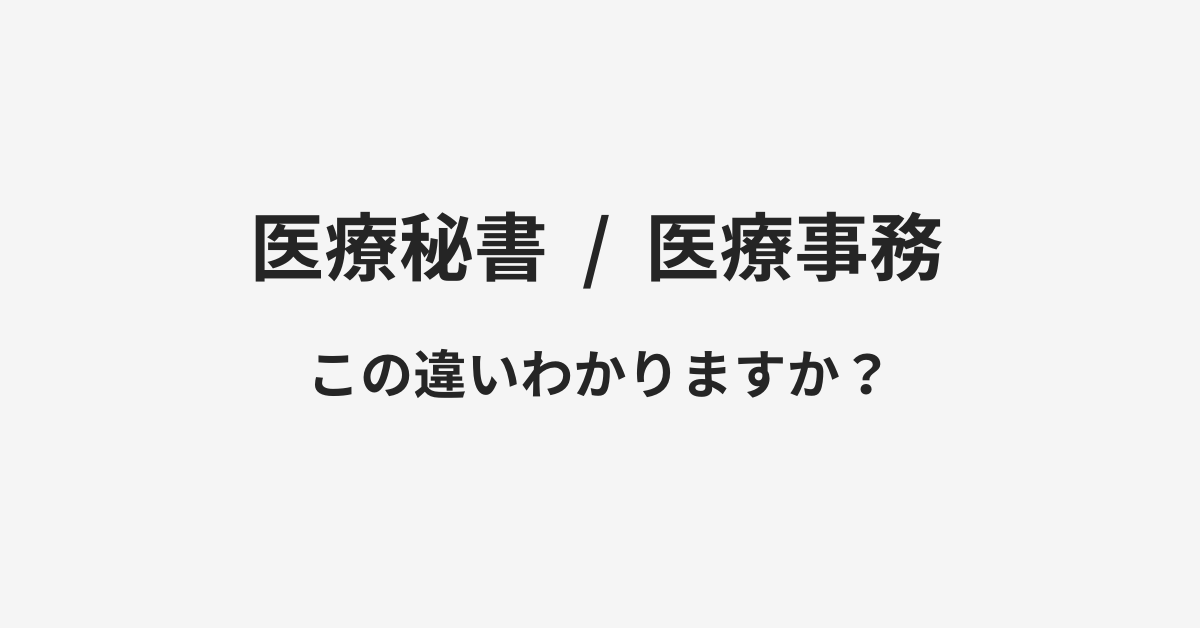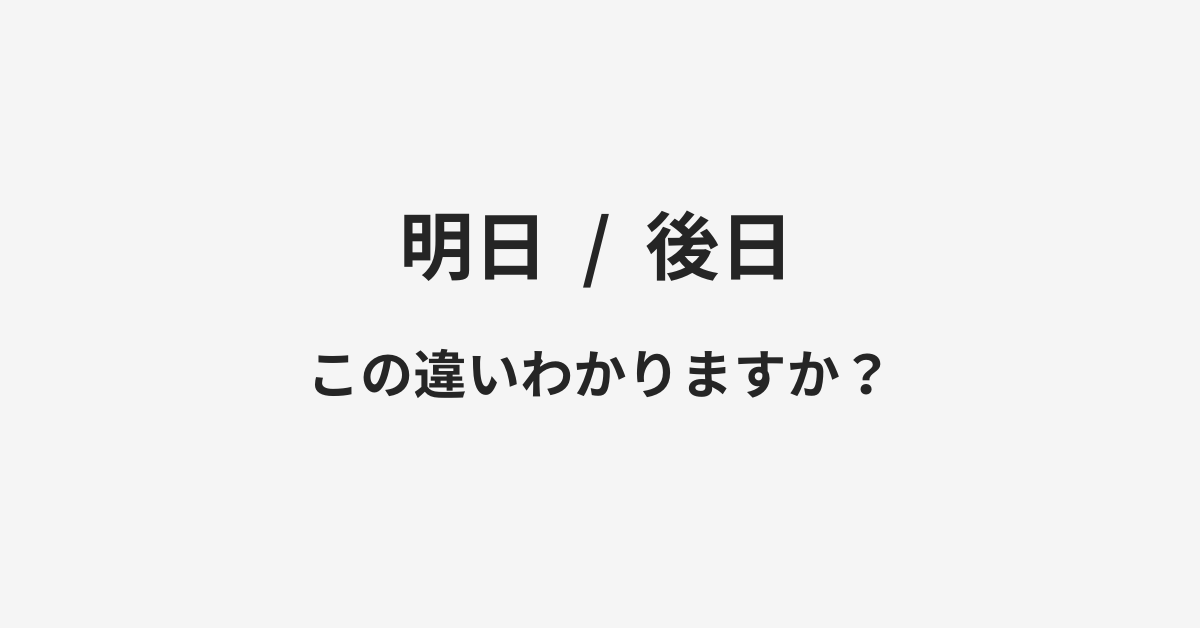【空気】と【気体】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
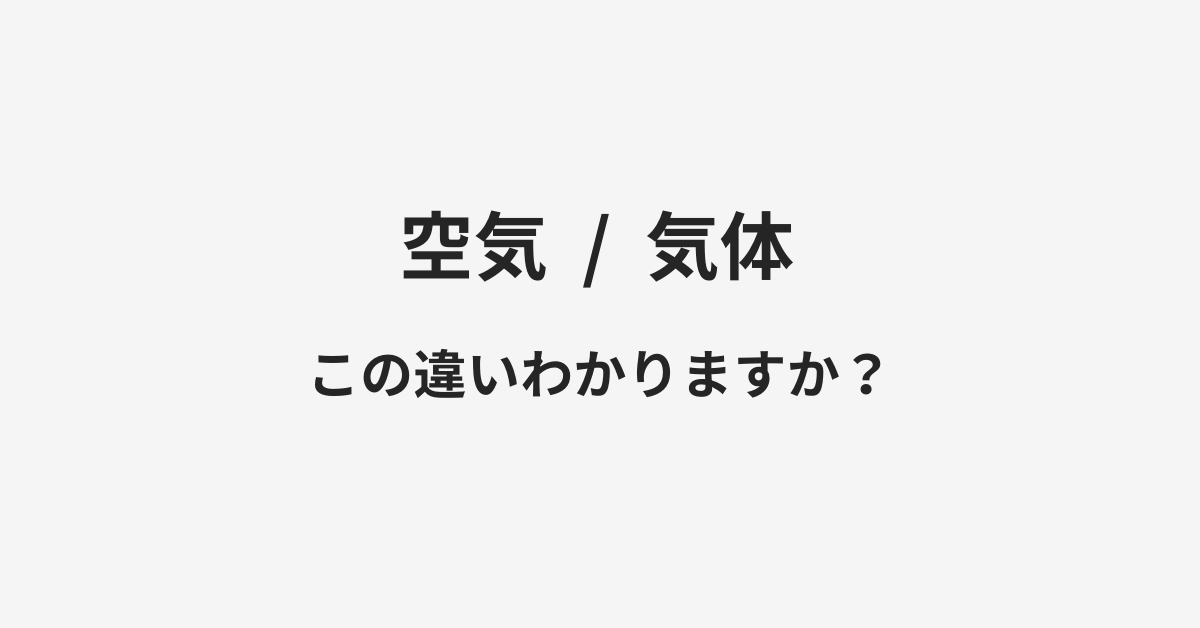
空気と気体の分かりやすい違い
空気と気体は、ともに物質の状態の一つですが、その意味合いには違いがあります。空気は、地球上の大気を構成する、主に窒素と酸素からなる気体の混合物を指します。
気体は、物質の三態(固体、液体、気体)の一つであり、分子の運動エネルギーが高く、分子間の距離が大きいため、容器の形状に沿って膨張する性質を持っています。
空気は特定の気体の混合物を指すのに対し、気体は物質の状態そのものを表す言葉だと言えます。
空気とは?
空気とは、地球上の大気を構成する、主に窒素と酸素からなる気体の混合物を指します。空気は、私たちが呼吸をするために欠かせない存在であり、生命の維持に直接関わっています。
空気は、音の伝達や燃焼の際の酸化剤としての役割も果たします。空気は、通常、無色・無臭・無味ですが、温度や圧力によって密度が変化し、流動的な性質を持っています。
空気は、大気圧の影響を受け、高度が上がるほど薄くなる性質があります。私たちの生活環境における空気は、窒素が約78%、酸素が約21%を占め、残りの1%にアルゴンなどの気体が含まれています。空気の組成は、生物の呼吸や燃焼などの現象に大きく影響を与えています。空気は、地球上のあらゆる場所に存在し、生命の維持や物理現象に欠かせない役割を果たしています。
空気の例文
- ( 1 ) 新鮮な空気を吸うために、森林浴に出かけた。
- ( 2 ) 空気が乾燥しているので、喉が痛くなってきた。
- ( 3 ) 高度が上がるにつれ、空気が薄くなってきた。
- ( 4 ) 空気中の酸素濃度が低下すると、燃焼が起こりにくくなる。
- ( 5 ) 汚染された空気を吸い続けると、健康に悪影響が出る可能性がある。
- ( 6 ) 空気の流れを利用して、風力発電を行っている。
空気の会話例
気体とは?
気体とは、物質の三態(固体、液体、気体)の一つであり、分子の運動エネルギーが高く、分子間の距離が大きいため、容器の形状に沿って膨張する性質を持っています。気体は、圧力と温度の変化に敏感で、圧力が高くなると体積が減少し、温度が高くなると体積が増加します。
気体は、混合しやすく、拡散しやすい性質を持っています。気体の種類は多岐にわたり、空気を構成する窒素や酸素をはじめ、水素、ヘリウム、二酸化炭素などが代表的な例です。気体は、その性質を利用して、様々な分野で応用されています。
ヘリウムガスは、浮力が大きいため、風船やアドバルーンに使用されます。また、水素ガスは、燃料電池の燃料として注目されています。気体は、物質の状態変化においても重要な役割を果たし、液体の蒸発や固体の昇華などの現象に関与しています。
気体の例文
- ( 1 ) 気体は、圧力と温度の変化に敏感なんだって。
- ( 2 ) ヘリウムガスを使って、風船を膨らませた。
- ( 3 ) 二酸化炭素は、温室効果ガスの一つである。
- ( 4 ) 気体の状態では、分子の運動エネルギーが高い。
- ( 5 ) 気体は、容器の形状に沿って膨張する性質を持つ。
- ( 6 ) 気体の圧力と温度は、密接に関係している。
気体の会話例
空気と気体の違いまとめ
空気と気体は、ともに物質の状態に関連する言葉ですが、その意味合いには違いがあります。空気は、地球上の大気を構成する、主に窒素と酸素からなる気体の混合物を指します。空気は、生命の維持に欠かせない存在であり、呼吸や燃焼など、様々な現象に関与しています。
気体は、物質の三態(固体、液体、気体)の一つであり、分子の運動エネルギーが高く、容器の形状に沿って膨張する性質を持っています。気体は、圧力と温度の変化に敏感で、混合しやすく、拡散しやすい性質を持っています。
気体は、ヘリウムガスや水素ガスなど、様々な種類があり、それぞれの特性を活かして応用されています。つまり、空気は特定の気体の混合物を指すのに対し、気体は物質の状態そのものを表す言葉だと言えます。両者は密接に関連していますが、空気は大気中の気体の混合物を、気体は物質の状態を表現するという点で異なります。
空気と気体の読み方
- 空気(ひらがな):くうき
- 空気(ローマ字):kūki
- 気体(ひらがな):きたい
- 気体(ローマ字):kitai