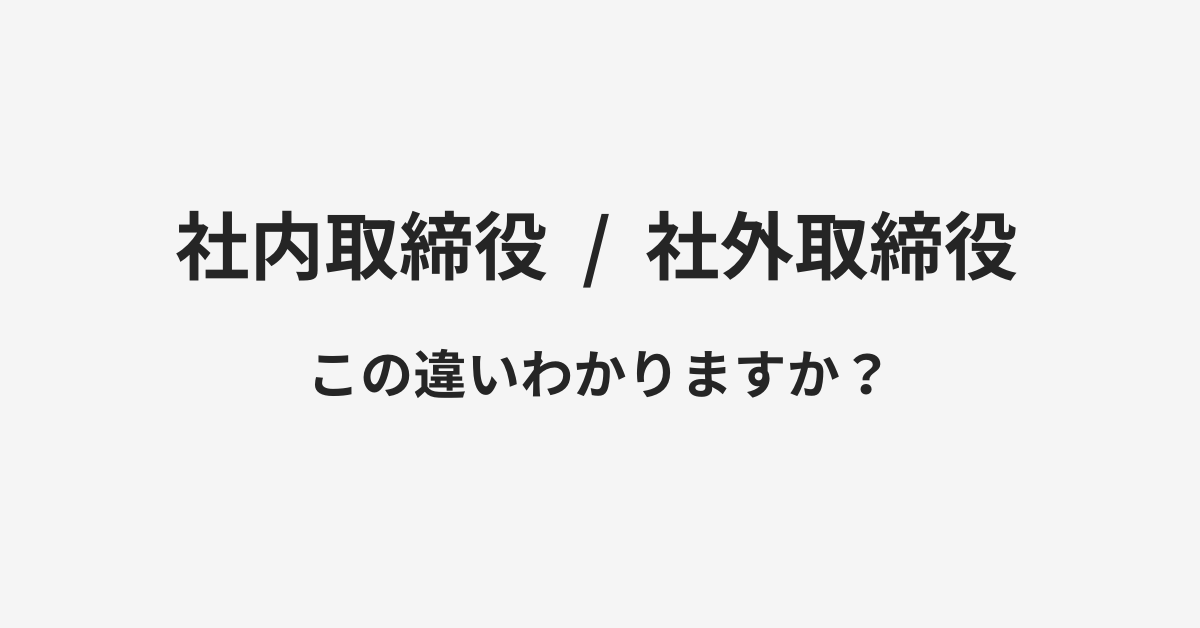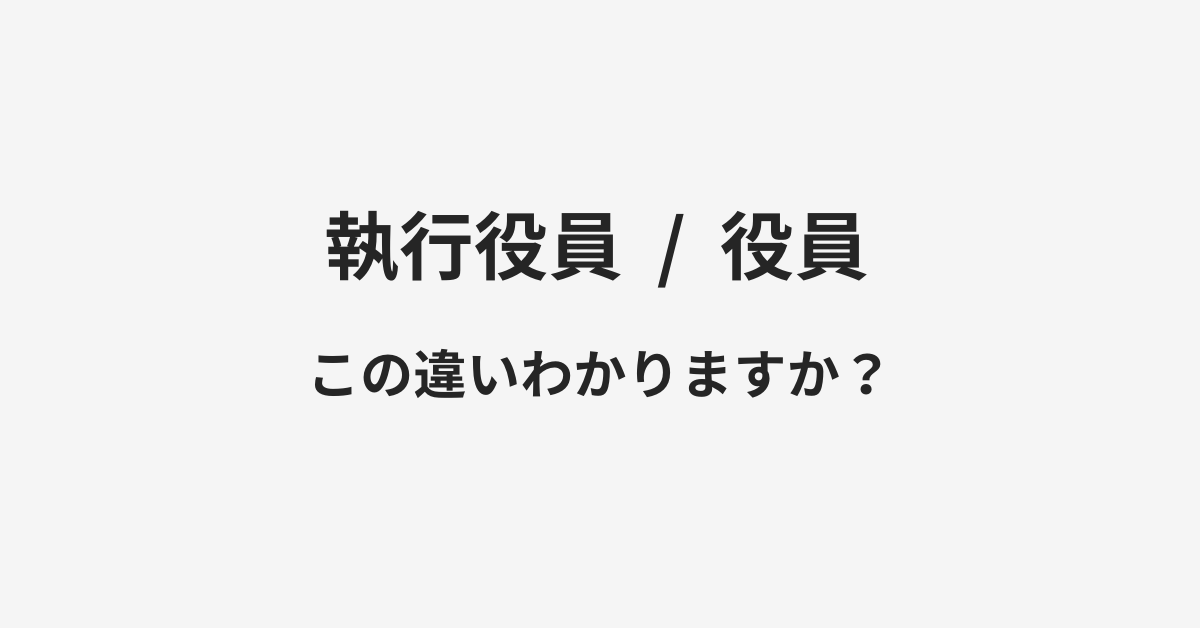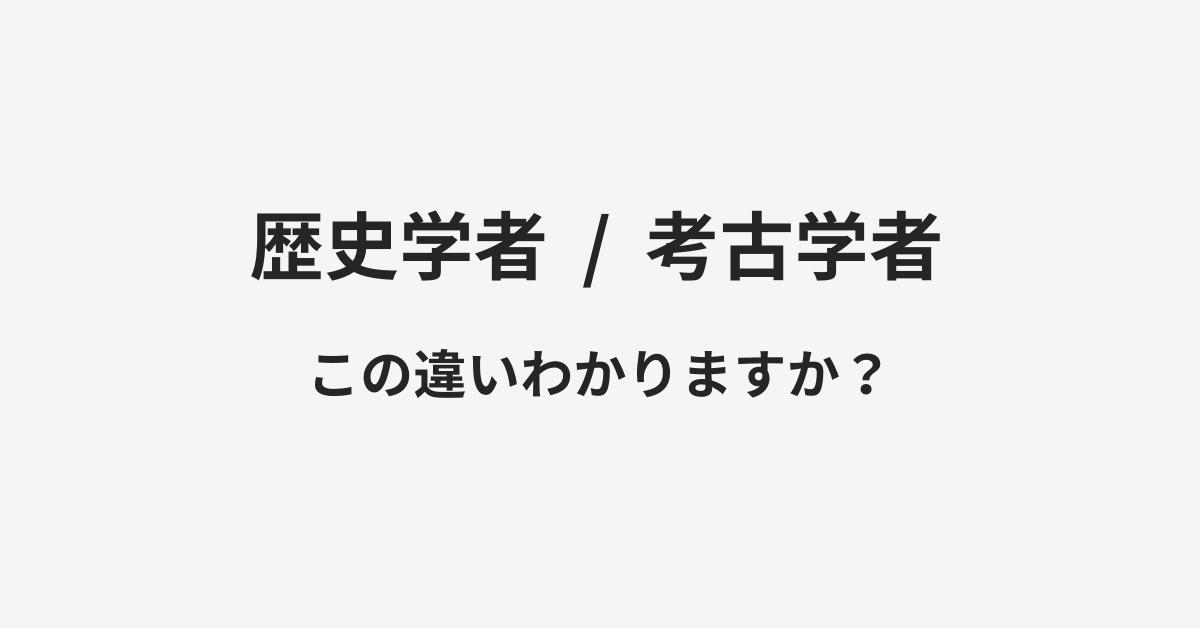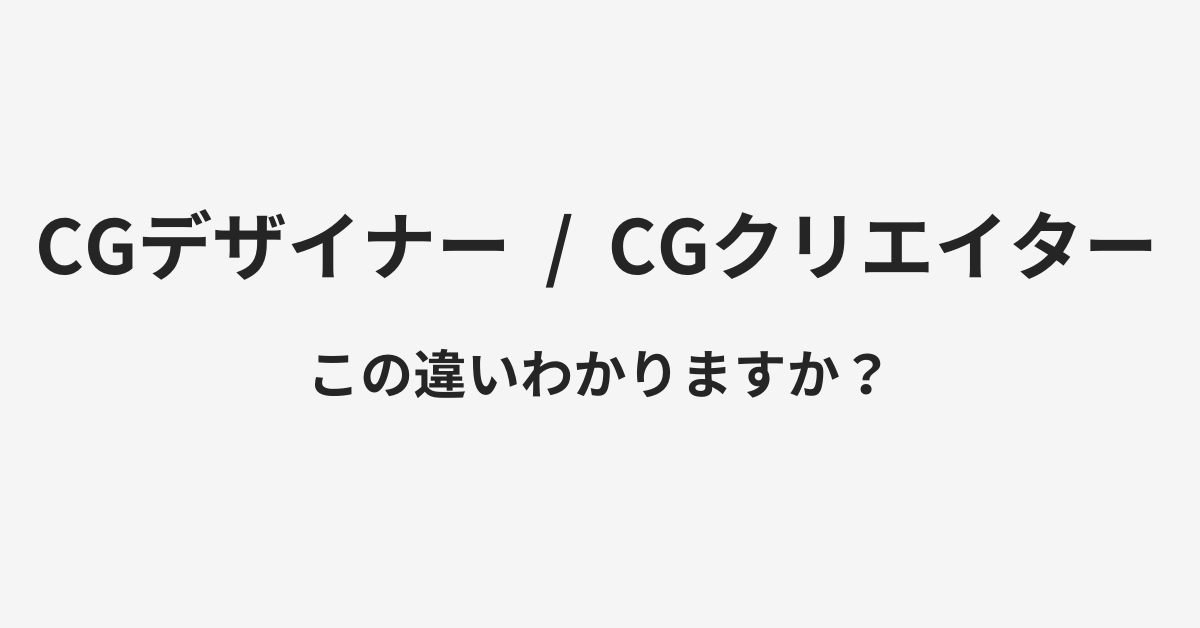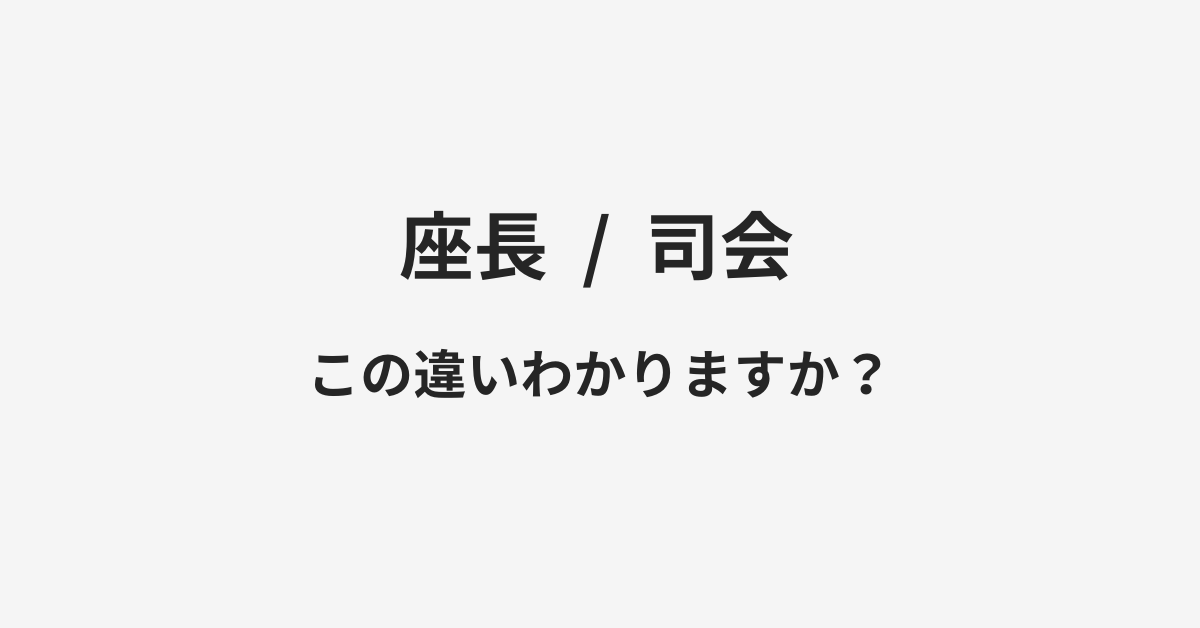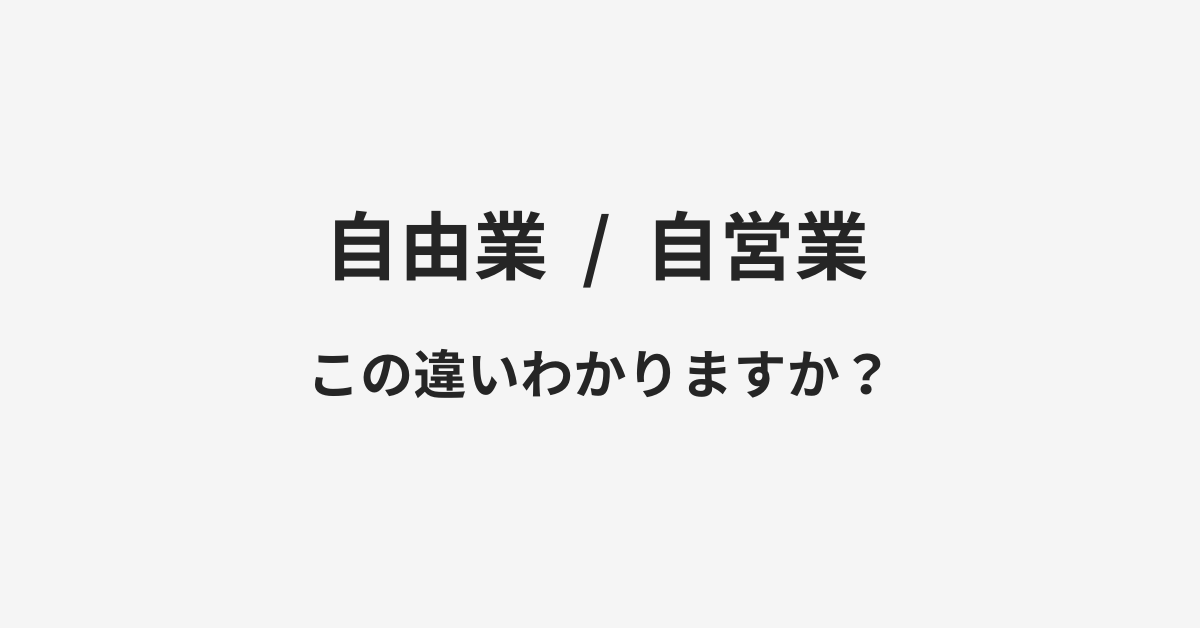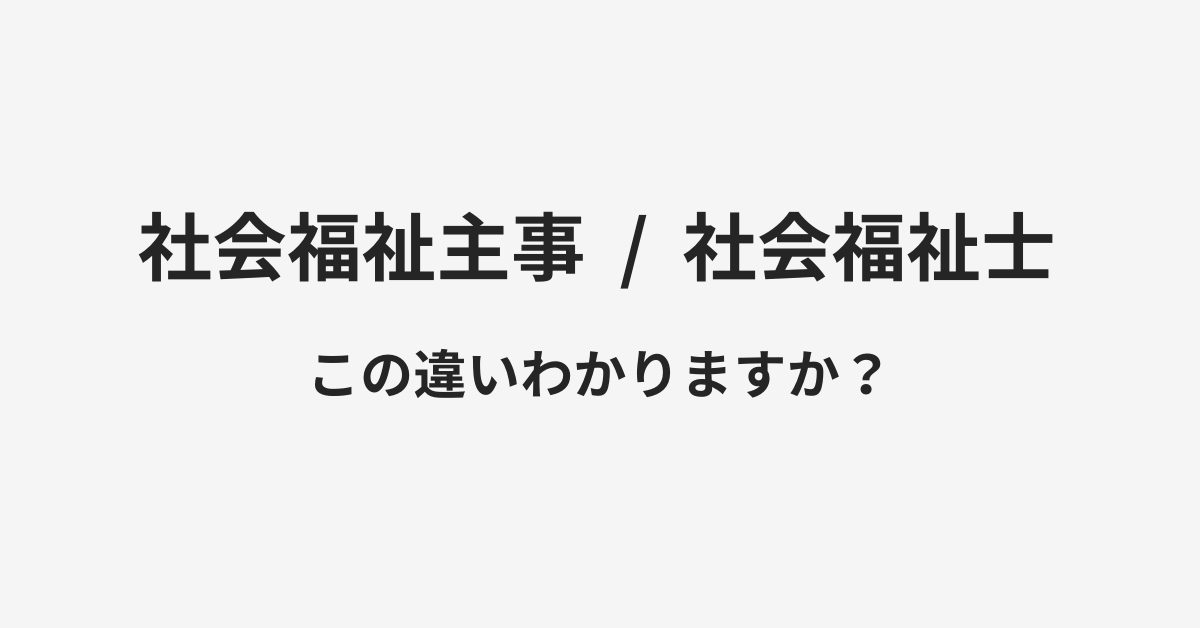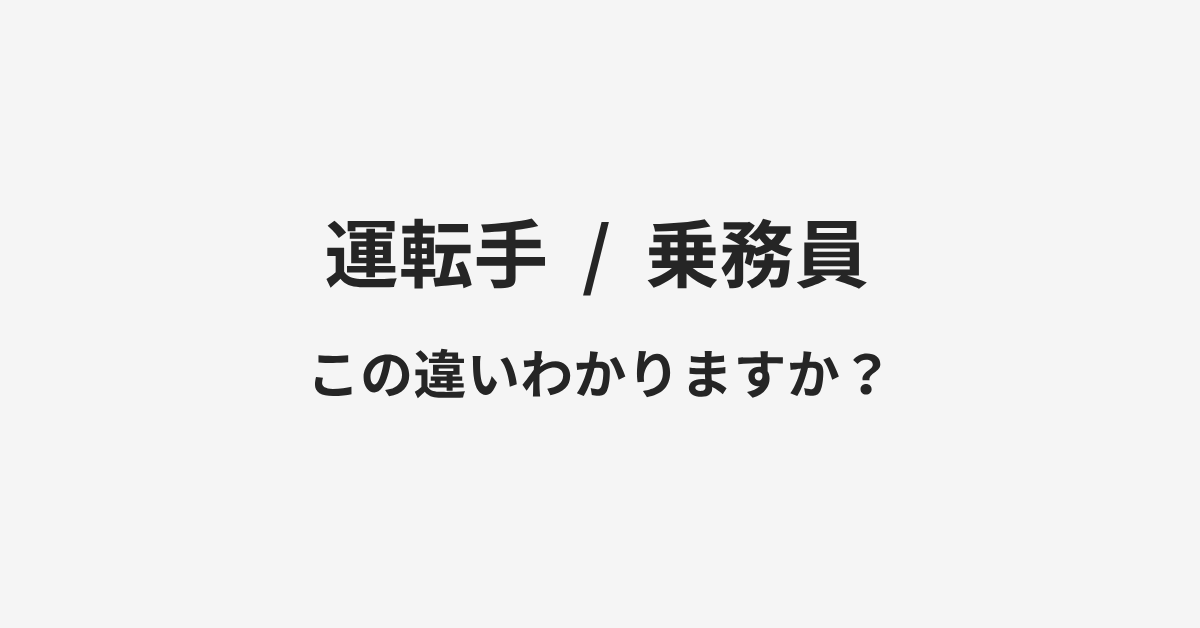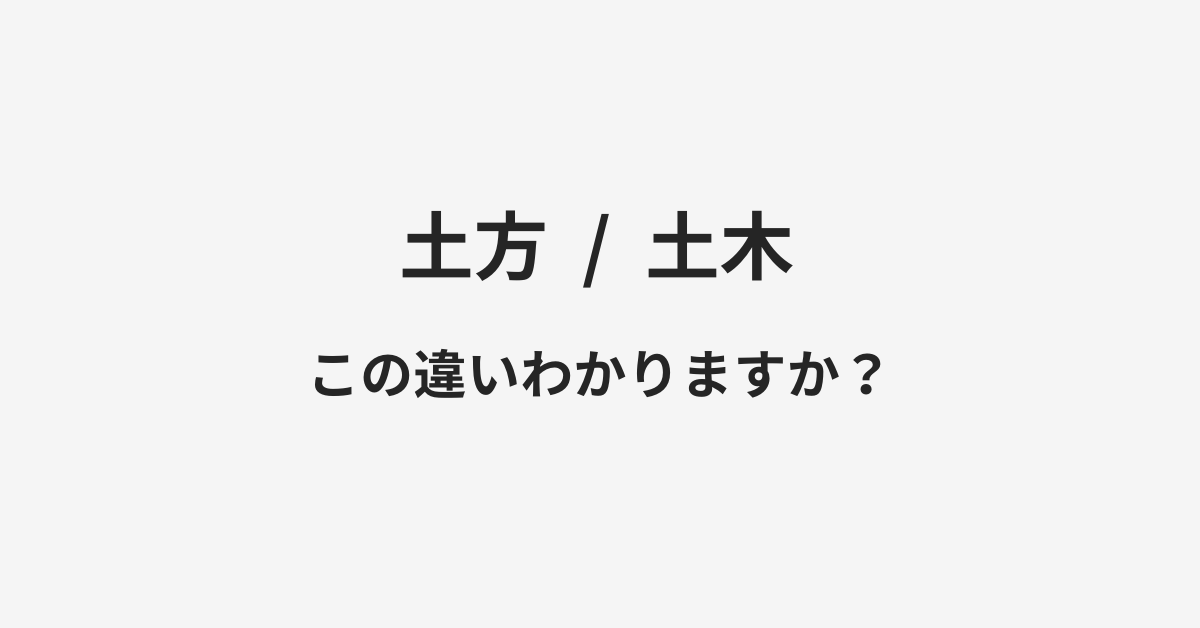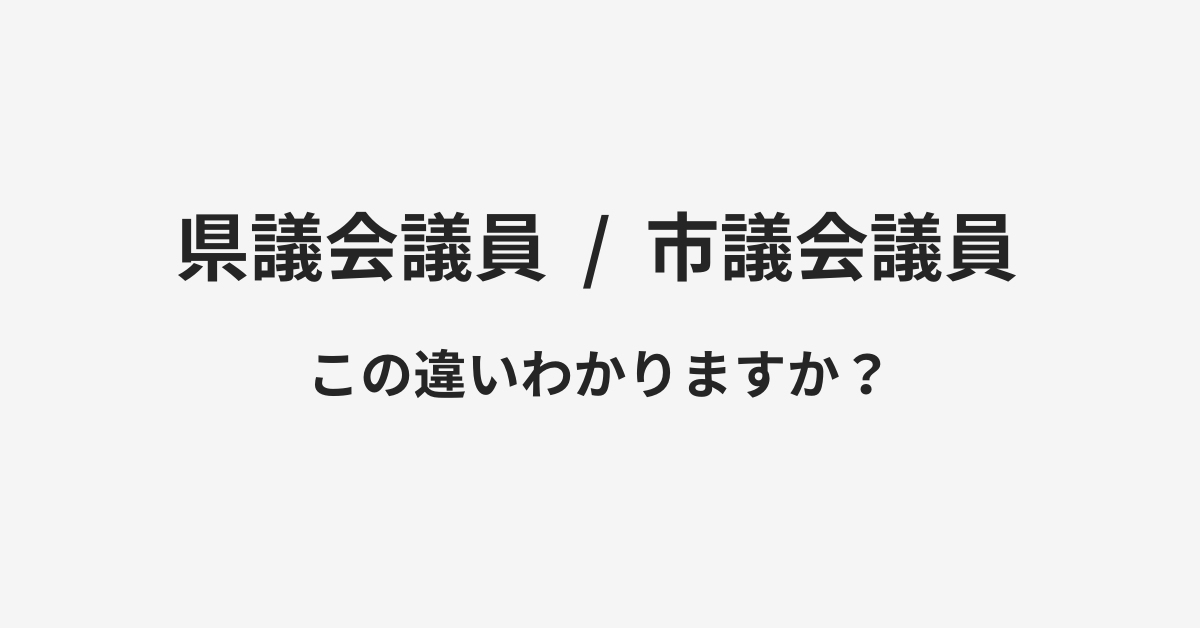【社外取締役】と【執行役員】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
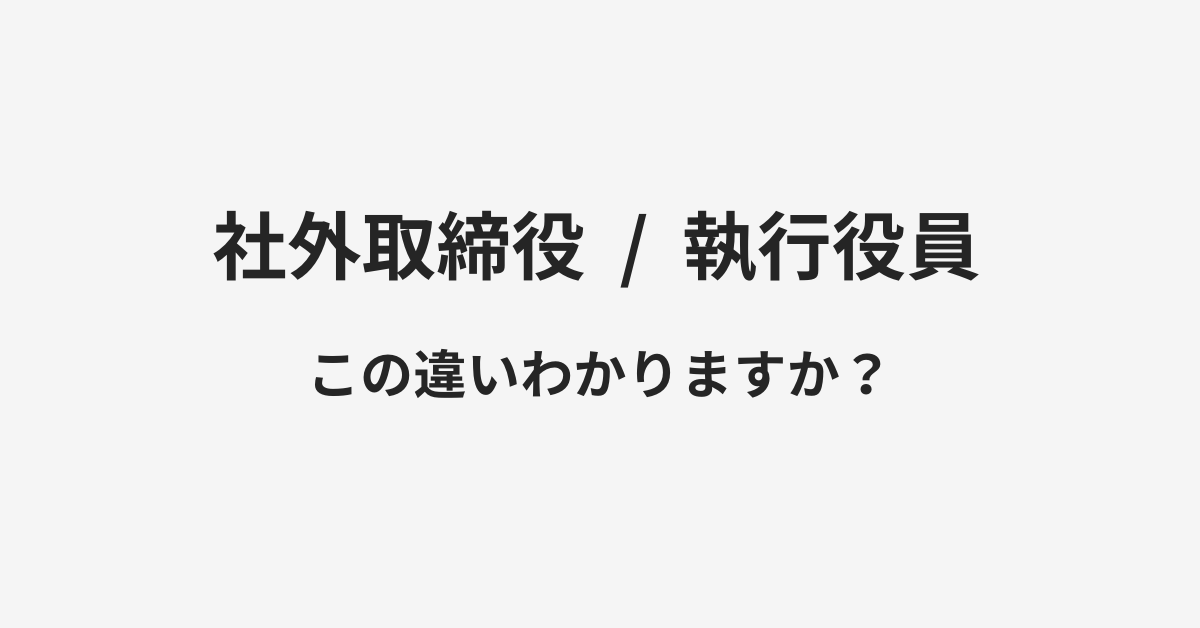
社外取締役と執行役員の分かりやすい違い
社外取締役と執行役員は、企業統治における役割が全く異なる役職です。社外取締役は、その会社の従業員ではない外部の人が就任する取締役で、経営の監督と助言を行います。
客観的な立場から経営をチェックする役割です。執行役員は、取締役会から業務執行を委任された社内の幹部で、実際の事業運営を担当します。
部門長などが兼務することも多いです。つまり、社外取締役は外部からの監督役、執行役員は内部の実行責任者という違いがあります。
社外取締役とは?
社外取締役とは、当該企業の業務執行に関与しない、独立した立場の取締役です。会社法で定められた機関であり、上場企業では複数名の選任が実質的に義務化されています。経営の透明性向上、利益相反の監視、少数株主保護、経営への助言などの役割を担い、コーポレートガバナンスの要となります。
社外取締役の要件は厳格で、過去10年間当該企業の従業員でないこと、主要取引先の関係者でないこと、近親者が役員でないことなどが定められています。他社の経営者、弁護士、会計士、学識者などが就任することが多く、その専門性と経験を活かした貢献が期待されます。
効果的な社外取締役の機能発揮には、情報アクセスの確保、取締役会での積極的な発言、独立した立場の維持が重要です。指名・報酬委員会の委員長を務めることも多く、経営の公正性確保に重要な役割を果たします。
社外取締役の例文
- ( 1 ) 新たに2名の社外取締役を招聘し、取締役会の独立性を高めました。
- ( 2 ) 社外取締役からの指摘により、ガバナンス体制を見直しました。
- ( 3 ) 女性の社外取締役を選任し、多様性を推進しています。
- ( 4 ) 社外取締役との定期的な情報交換会を設け、経営の透明性を確保しています。
- ( 5 ) 独立社外取締役が過半数を占める指名委員会を設置しました。
- ( 6 ) 社外取締役の専門知識が、新規事業の意思決定に貢献しています。
社外取締役の会話例
執行役員とは?
執行役員とは、取締役会から委任された業務執行を担当する役職で、法的には会社法上の機関ではなく、企業が任意で設置する役職です。経営の意思決定(取締役会)と業務執行(執行役員)を分離することで、経営の効率化と専門性の向上を図ります。執行役員制度は、特に大企業で広く採用されています。
執行役員の特徴は、特定の事業部門や機能の執行責任者として、現場に近い立場で迅速な意思決定と実行を行うことです。常務執行役員、専務執行役員などの階層があり、重要な執行役員は取締役を兼務することもあります。権限と責任が明確化され、業績に対する accountability が求められます。
執行役員制度のメリットは、取締役会のスリム化、意思決定の迅速化、専門性の活用、次世代経営者の育成などです。一方、取締役会との情報共有、権限の明確化、評価制度の整備などが課題となります。
執行役員の例文
- ( 1 ) 営業部門の執行役員として、売上目標の達成に全力を注いでいます。
- ( 2 ) 執行役員制度の導入により、意思決定スピードが向上しました。
- ( 3 ) 取締役兼執行役員として、経営と執行の橋渡し役を担っています。
- ( 4 ) 執行役員会議で、各部門の進捗を共有し、連携を強化しています。
- ( 5 ) 若手を執行役員に登用し、組織の活性化を図っています。
- ( 6 ) 執行役員の業績評価制度を見直し、成果主義を徹底しました。
執行役員の会話例
社外取締役と執行役員の違いまとめ
社外取締役と執行役員の違いを理解することは、現代的なコーポレートガバナンスの理解に不可欠です。社外取締役は監督、執行役員は執行という明確な役割分担があります。この分離は、経営の透明性と効率性を両立させるための仕組みです。
社外取締役が独立した立場から経営を監視し、執行役員が専門性を活かして事業を推進することで、健全な企業統治が実現されます。企業規模や業種により最適な体制は異なりますが、監督と執行の分離という基本原則は共通です。
両者が適切に機能することで、ステークホルダーの利益が守られ、企業価値の向上が図られます。
社外取締役と執行役員の読み方
- 社外取締役(ひらがな):しゃがいとりしまりやく
- 社外取締役(ローマ字):shagaitorishimariyaku
- 執行役員(ひらがな):しっこうやくいん
- 執行役員(ローマ字):shikkouyakuinn