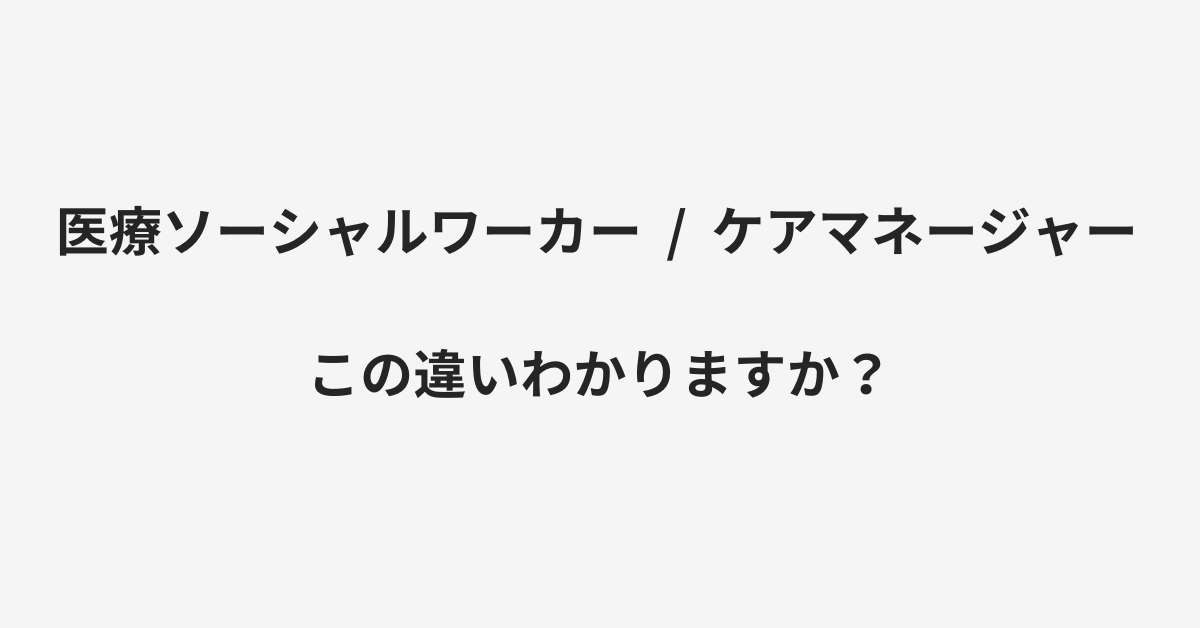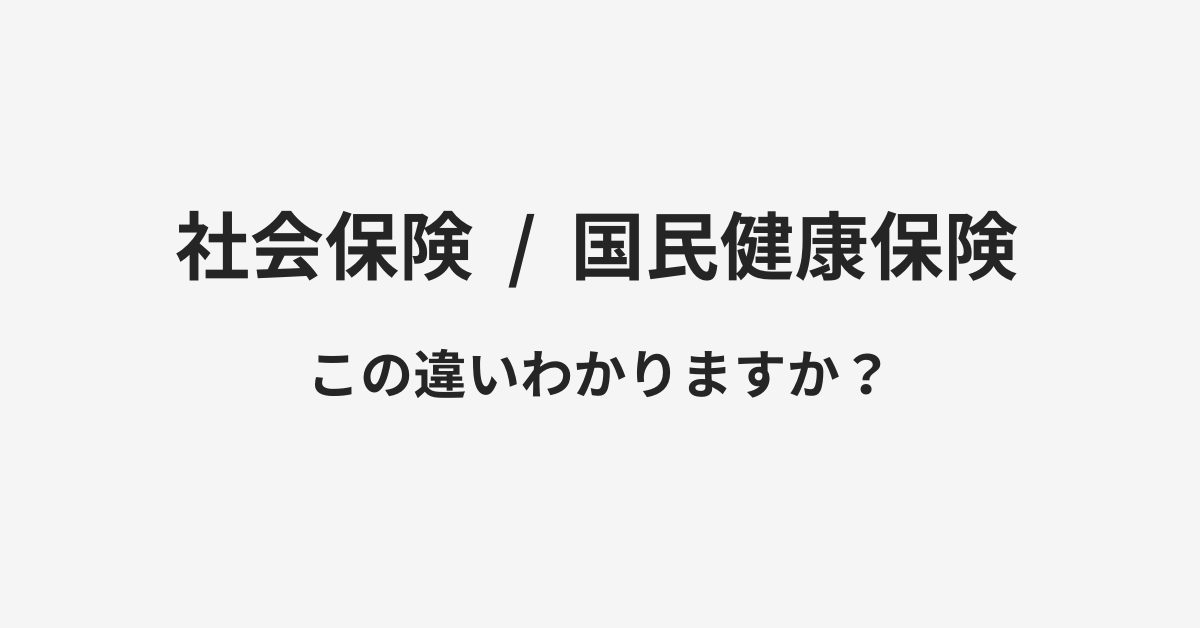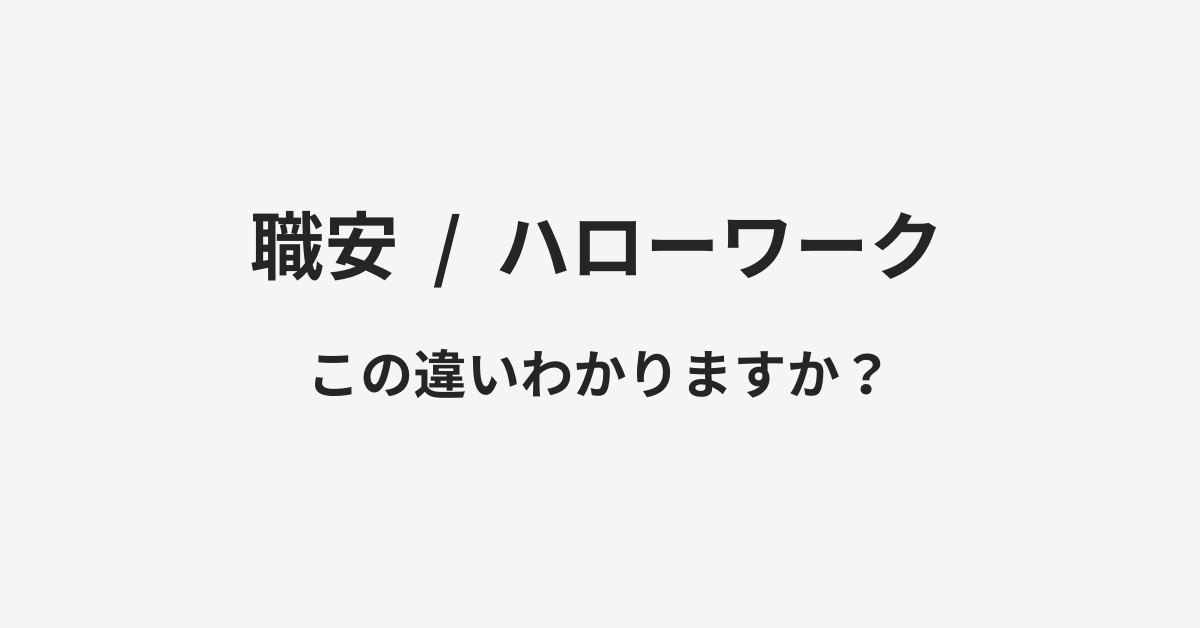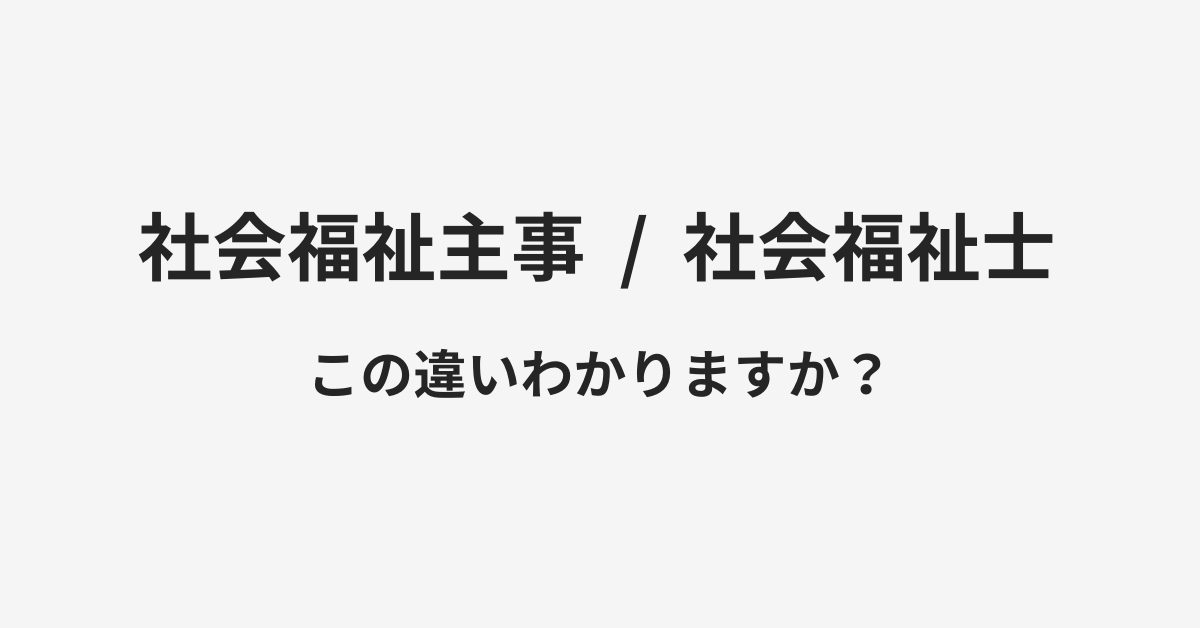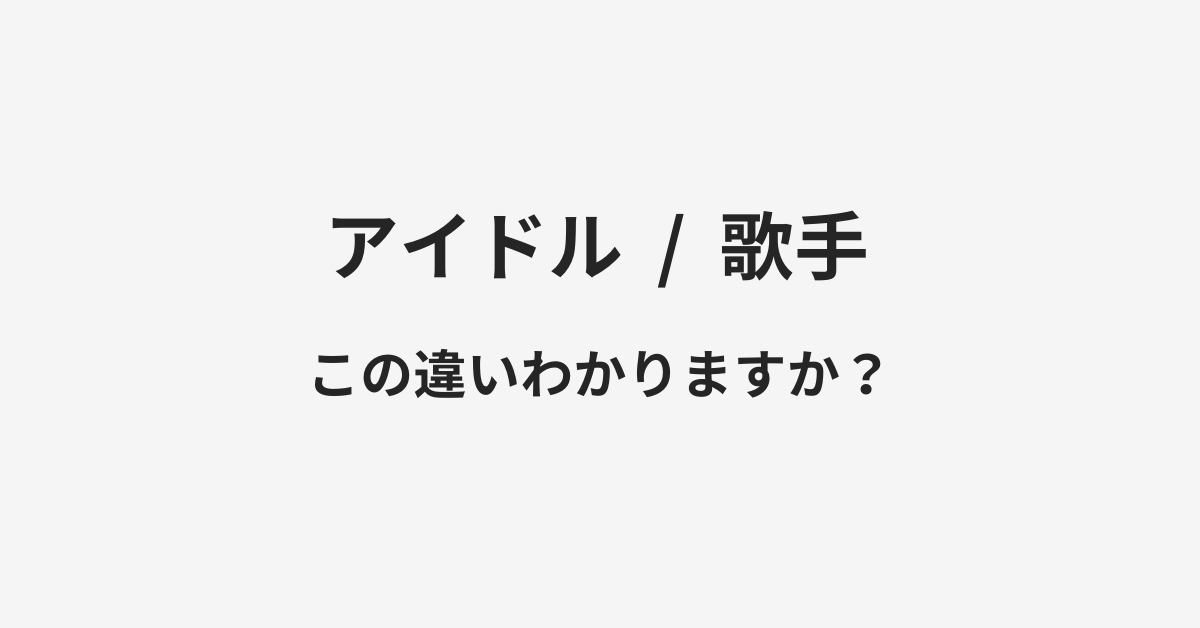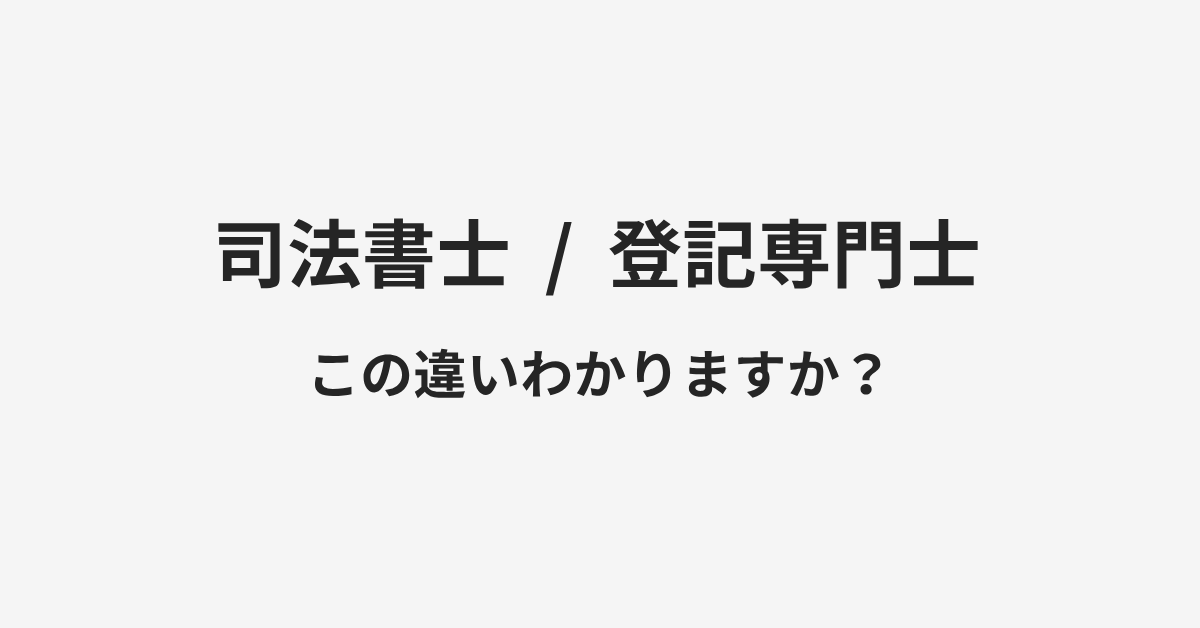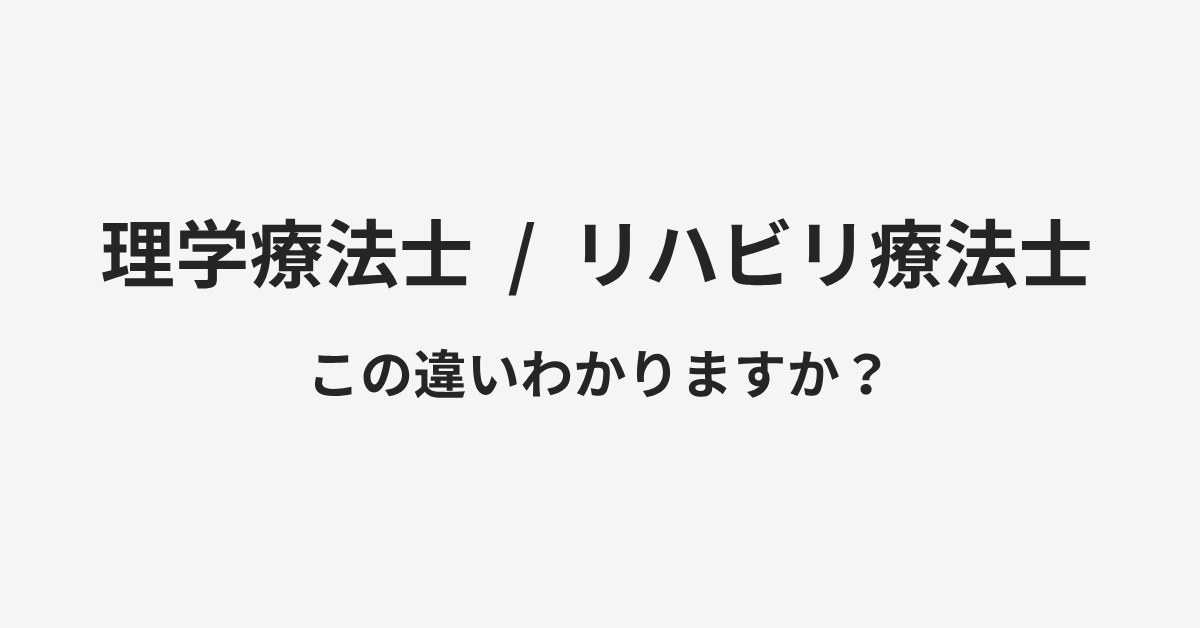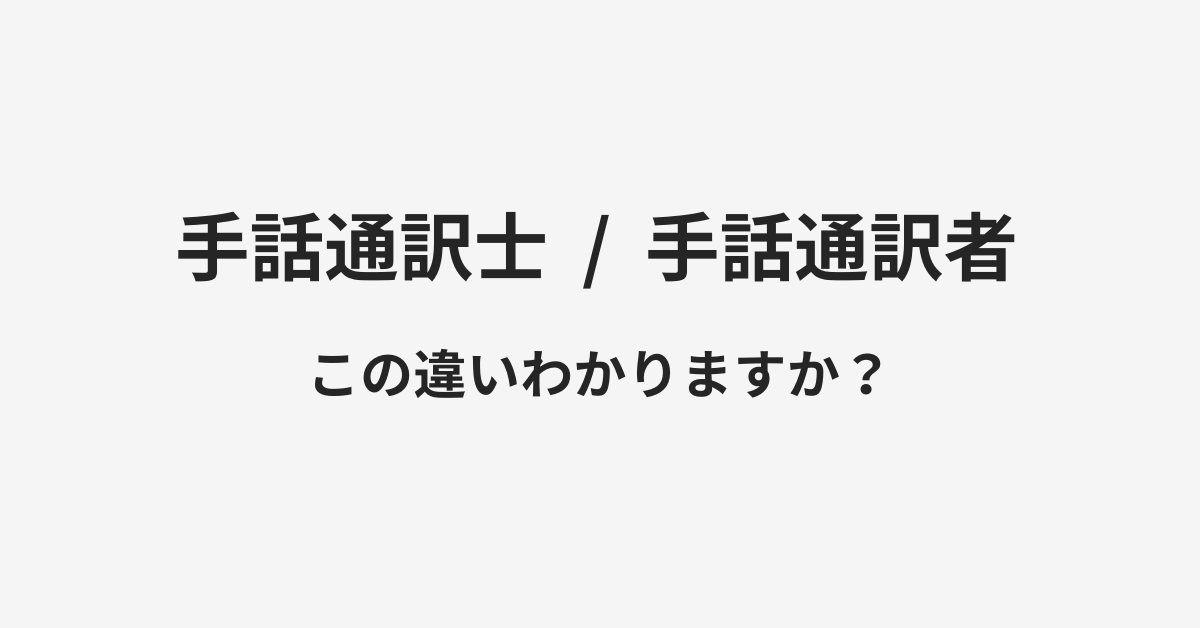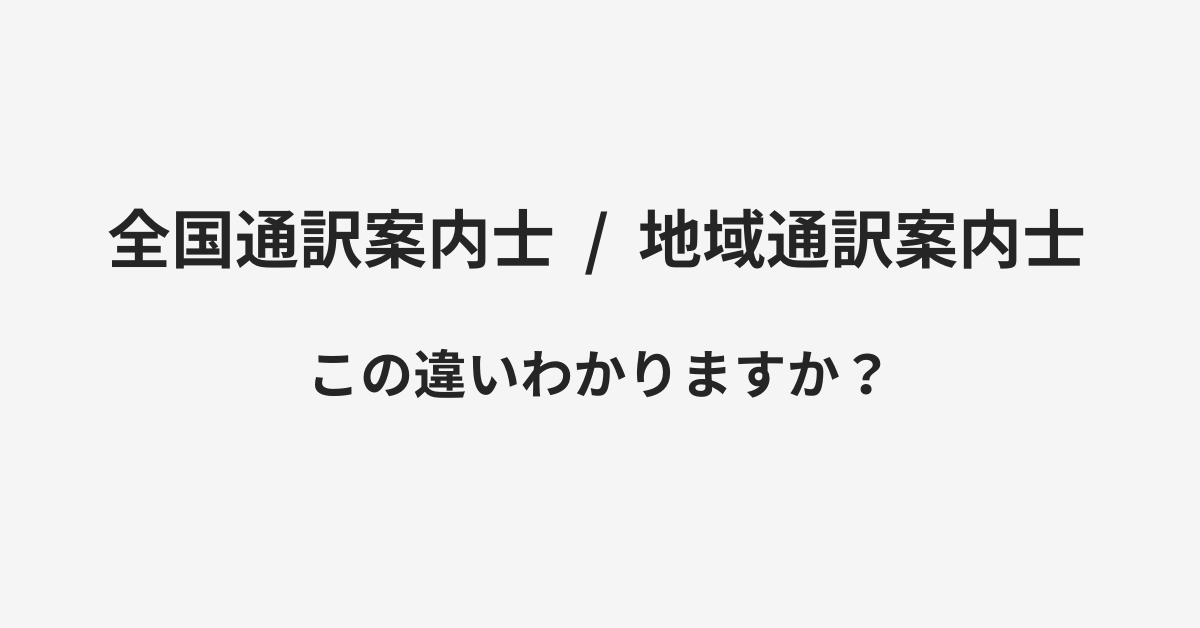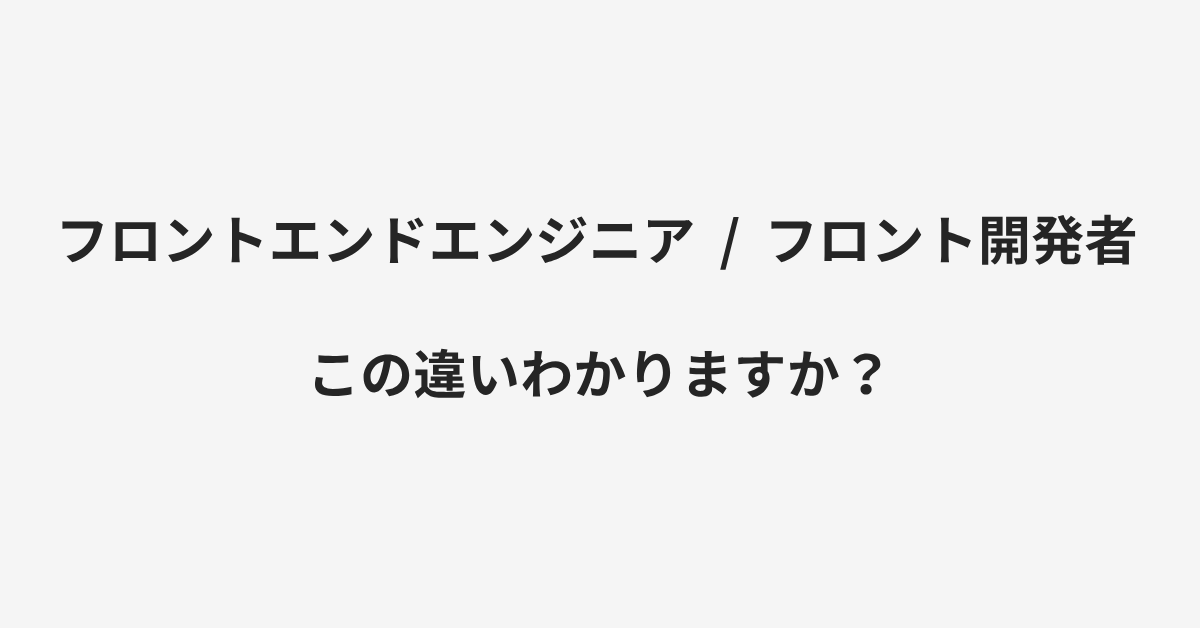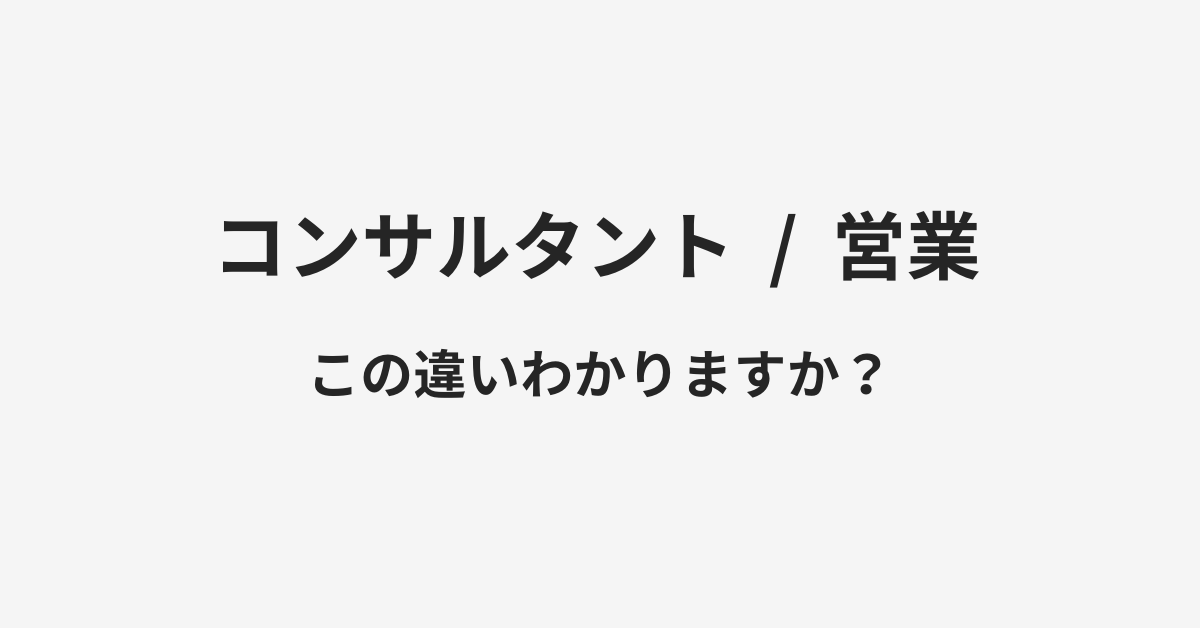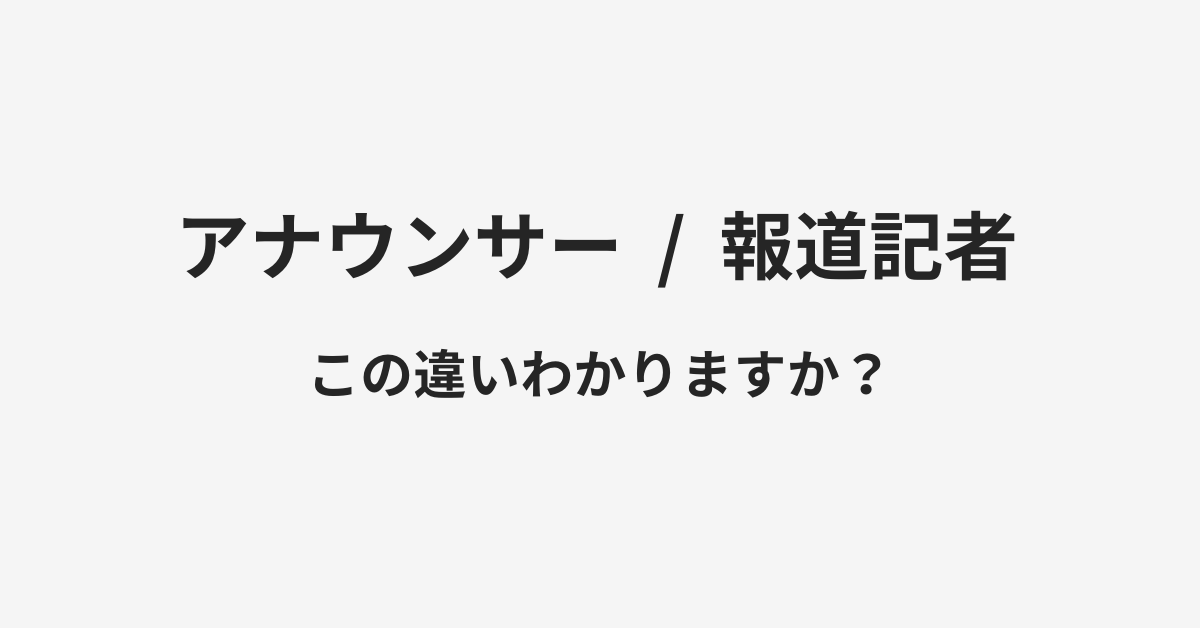【社労士】と【社会保険労務士】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
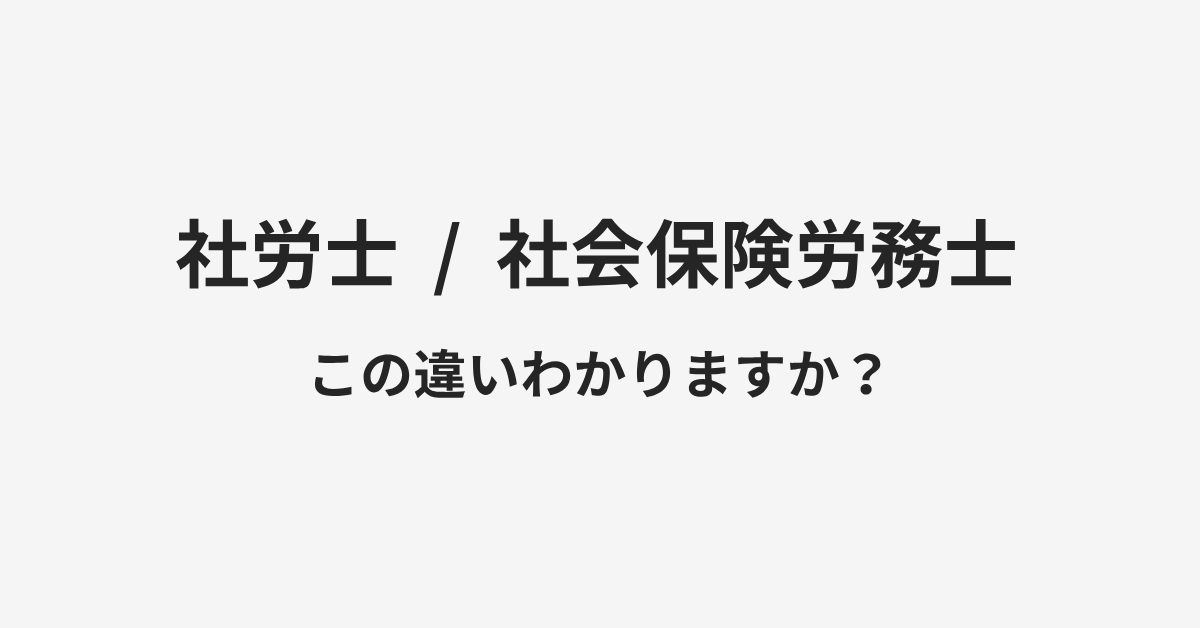
社労士と社会保険労務士の分かりやすい違い
社労士と社会保険労務士は、実は同じ資格を指す言葉で、略称と正式名称の違いです。社労士は社会保険労務士を短くした呼び方で、日常会話や一般的な場面でよく使われます。
覚えやすく親しみやすい表現です。社会保険労務士は法律で定められた正式な名前で、免許証や公的書類、正式な場面では必ずこちらを使います。
社労士とは?
社労士とは、社会保険労務士の略称で、労働・社会保険に関する法律の専門家として広く認知されている呼び方です。日常的な会話、名刺の肩書き、ウェブサイトの表記など、多くの場面で使用されます。親しみやすく覚えやすいため、一般的に定着しています。
社労士という略称は、全国社会保険労務士会連合会でも公式に認められており、社労士会社労士試験など、関連用語でも広く使用されています。メディアでも社労士表記が一般的で、社会的認知度も高い呼称です。
ただし、社労士はあくまで略称であるため、法的文書や正式な契約書、資格証明が必要な場面では、正式名称の社会保険労務士を使用する必要があります。TPOに応じた使い分けが重要です。
社労士の例文
- ( 1 ) 社労士として独立開業を考えていますが、準備期間はどのくらい必要ですか
- ( 2 ) 企業内社労士として働くメリットを教えてください
- ( 3 ) 社労士資格を活かして、どんなキャリアパスがありますか
- ( 4 ) 女性社労士として活躍するための強みは何ですか
- ( 5 ) 社労士の顧問契約の相場はどのくらいですか
- ( 6 ) AIやDXが進む中で、社労士の将来性はどうなりますか
社労士の会話例
社会保険労務士とは?
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づく国家資格の正式名称で、人事労務管理のコンサルティング、社会保険・労働保険の手続き代行、就業規則作成、労使紛争の代理などを行う専門職です。企業の働き方改革や労務コンプライアンスを支援する重要な役割を担っています。
社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格し、実務経験または事務指定講習を修了する必要があります。合格率約6%の難関試験で、労働法、社会保険法などの幅広い知識が求められます。
独立開業や企業内での活躍が可能です。正式名称として、登録証、事務所看板、契約書、裁判所提出書類などでは必ず社会保険労務士と表記します。平均年収は500-800万円で、専門分野や顧客層により大きく異なります。
社会保険労務士の例文
- ( 1 ) 社会保険労務士試験の効率的な勉強方法を教えてください
- ( 2 ) 社会保険労務士として開業する際の初期費用は?
- ( 3 ) 社会保険労務士と他の士業との連携方法は?
- ( 4 ) 社会保険労務士の登録に必要な実務経験とは?
- ( 5 ) 特定社会保険労務士になるメリットは何ですか
- ( 6 ) 社会保険労務士の継続教育について教えてください
社会保険労務士の会話例
社労士と社会保険労務士の違いまとめ
社労士と社会保険労務士の違いは、略称と正式名称の関係にあり、指す資格は完全に同一です。日常的には社労士、公式場面では社会保険労務士を使用します。使い分けの基準は、親しみやすさと正式性のバランスです。
クライアントとの会話では社労士、契約書や登録申請では社会保険労務士というように、相手と状況に応じて適切に選択します。
どちらの呼称も同じ専門性と信頼性を持つ資格を表しており、労務管理のプロフェッショナルとして、企業と働く人々を支える重要な役割に変わりはありません。
社労士と社会保険労務士の読み方
- 社労士(ひらがな):しゃろうし
- 社労士(ローマ字):sharoushi
- 社会保険労務士(ひらがな):しゃかいほけんろうむし
- 社会保険労務士(ローマ字):shakaihokennroumushi