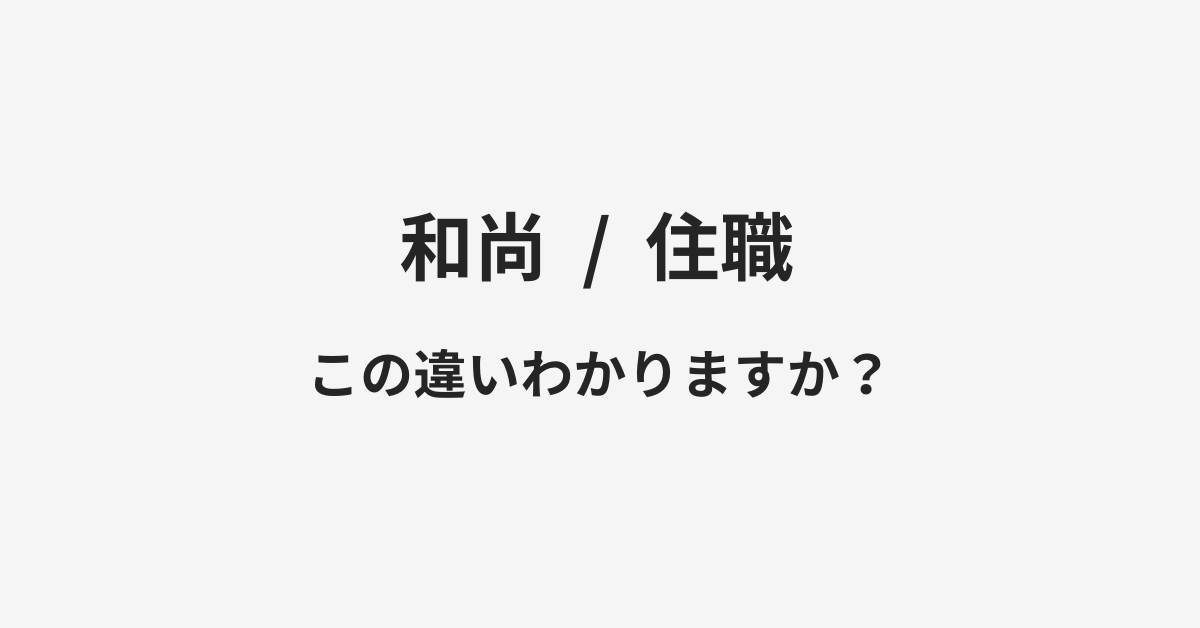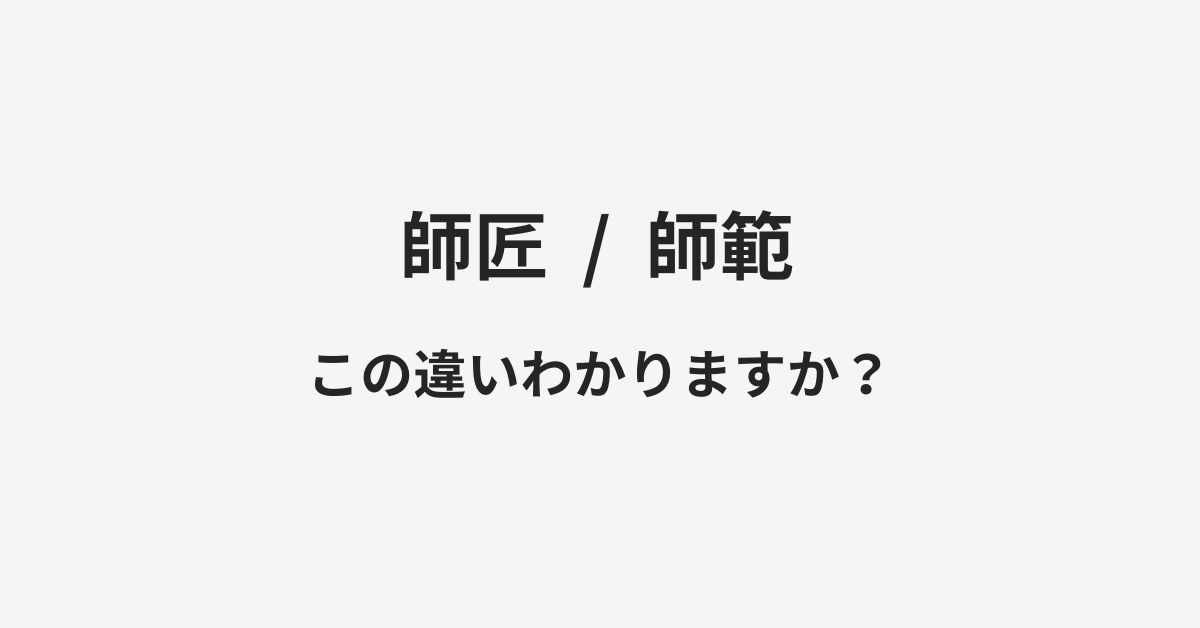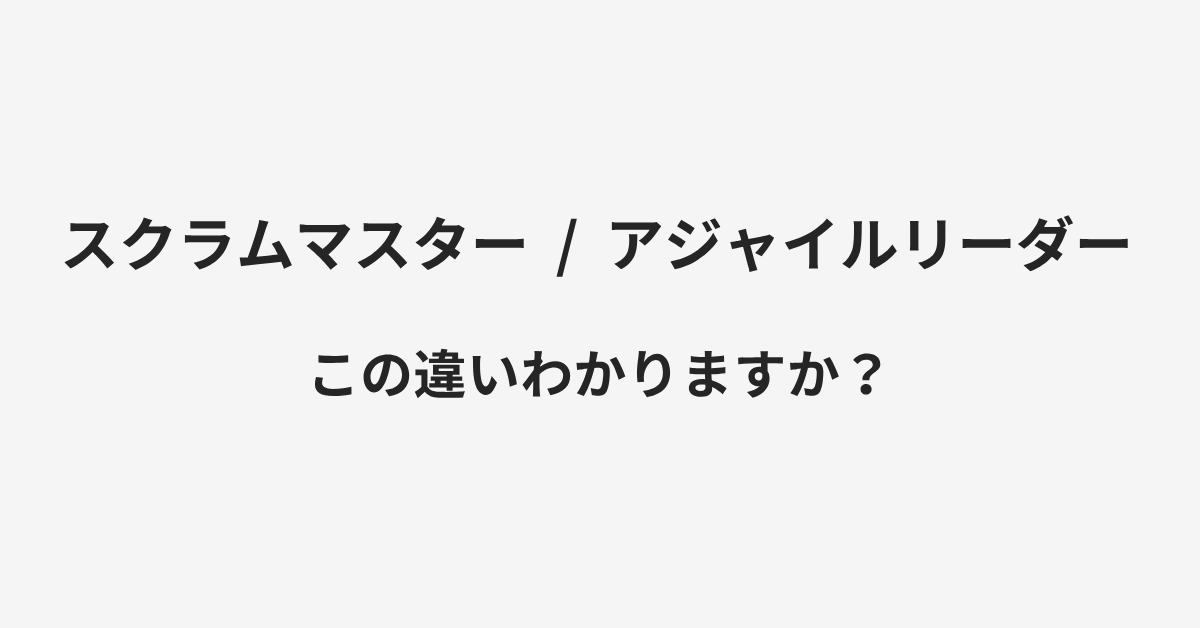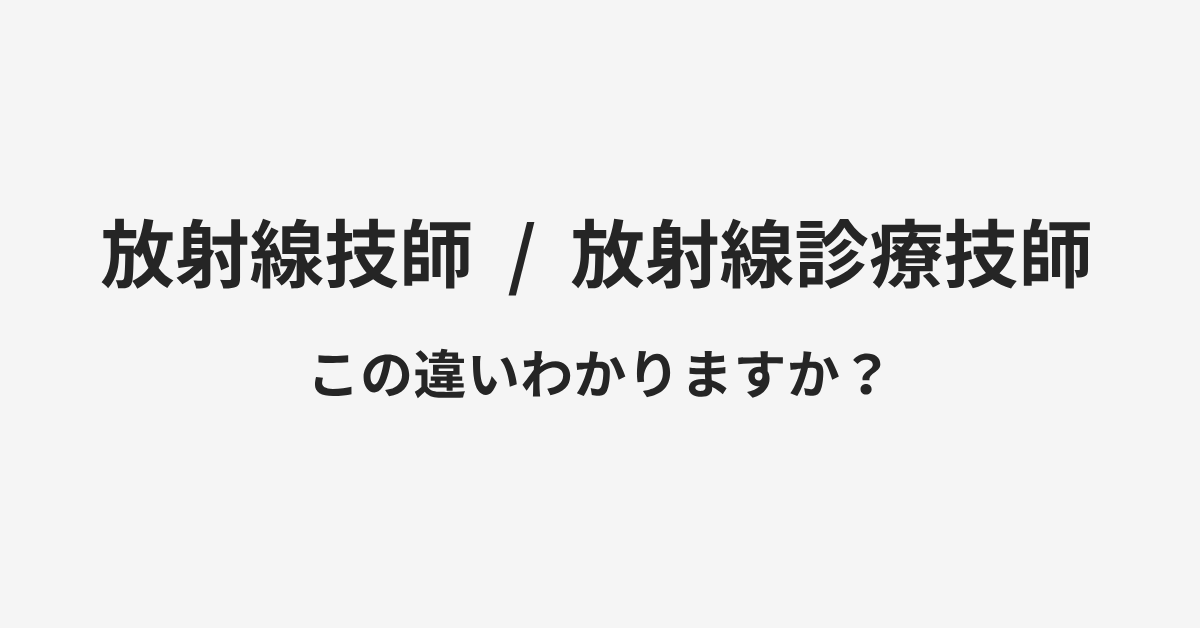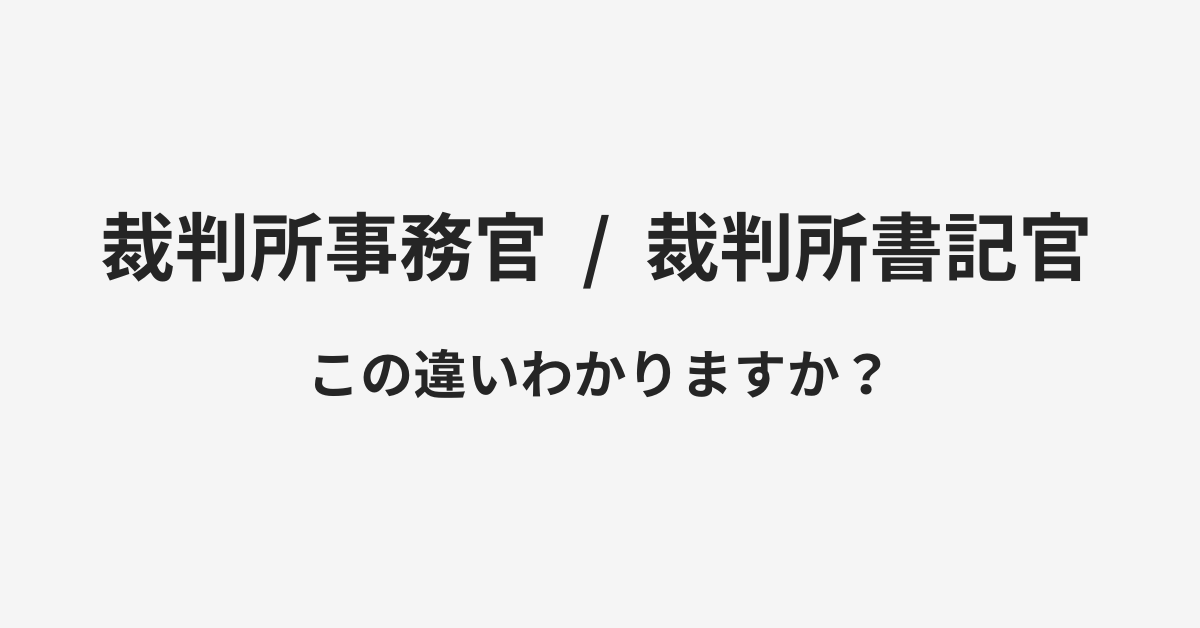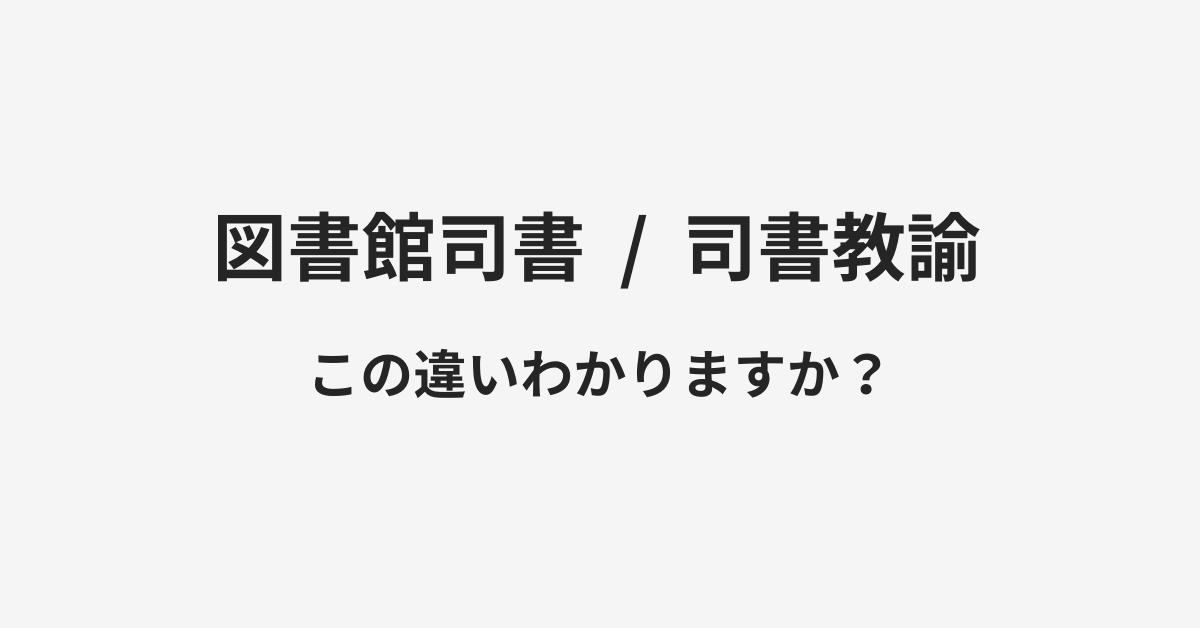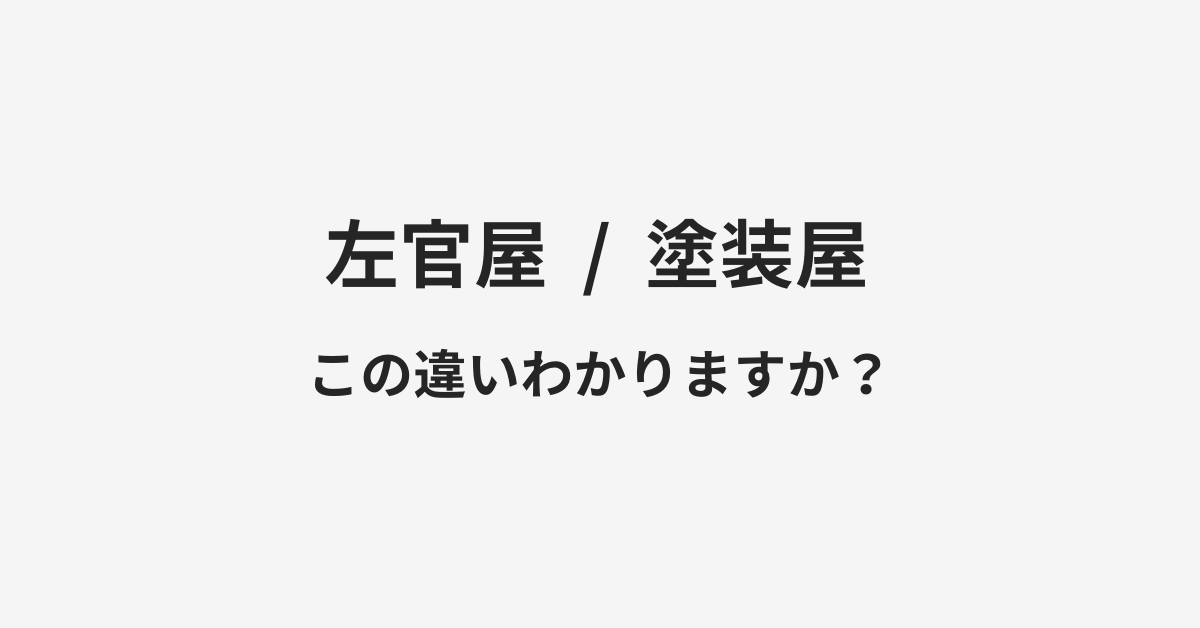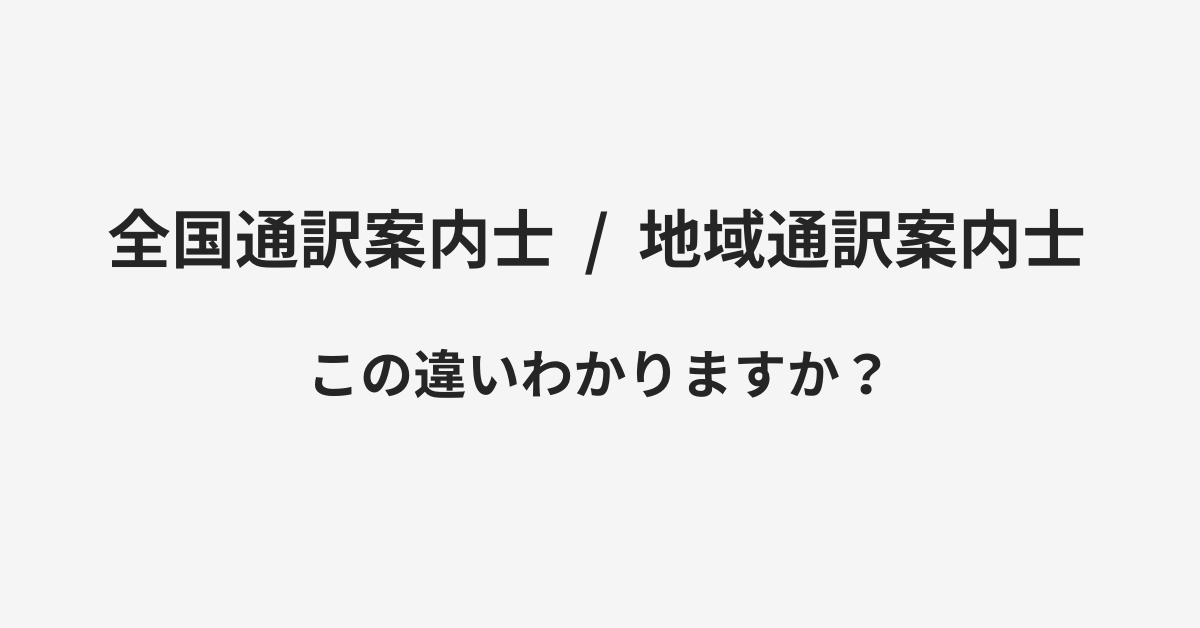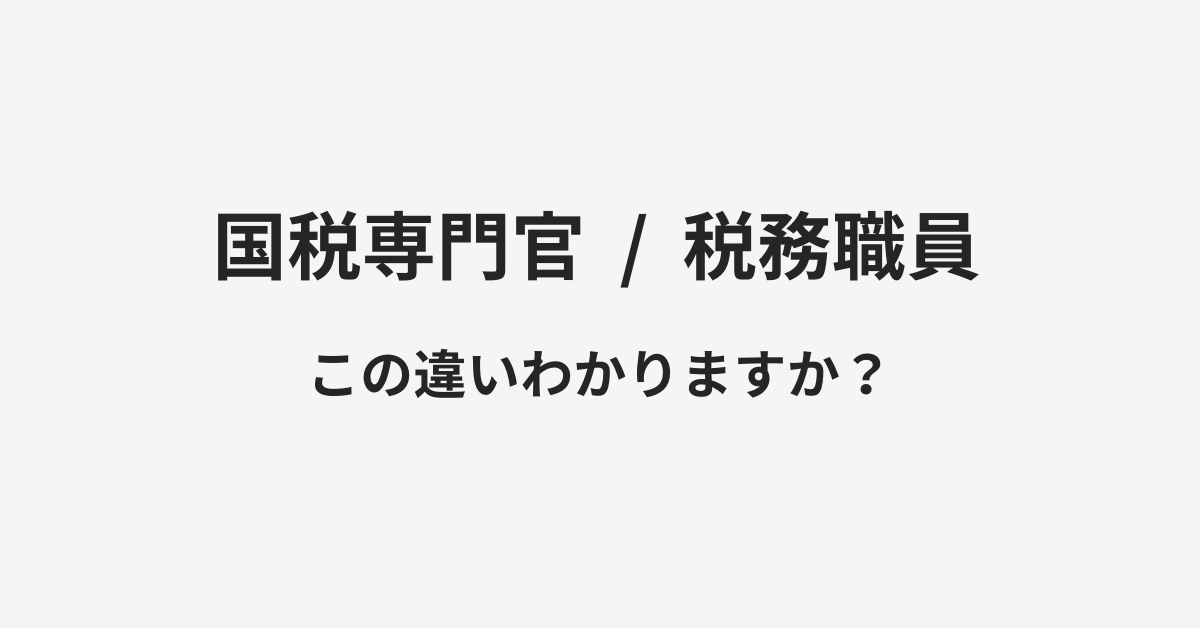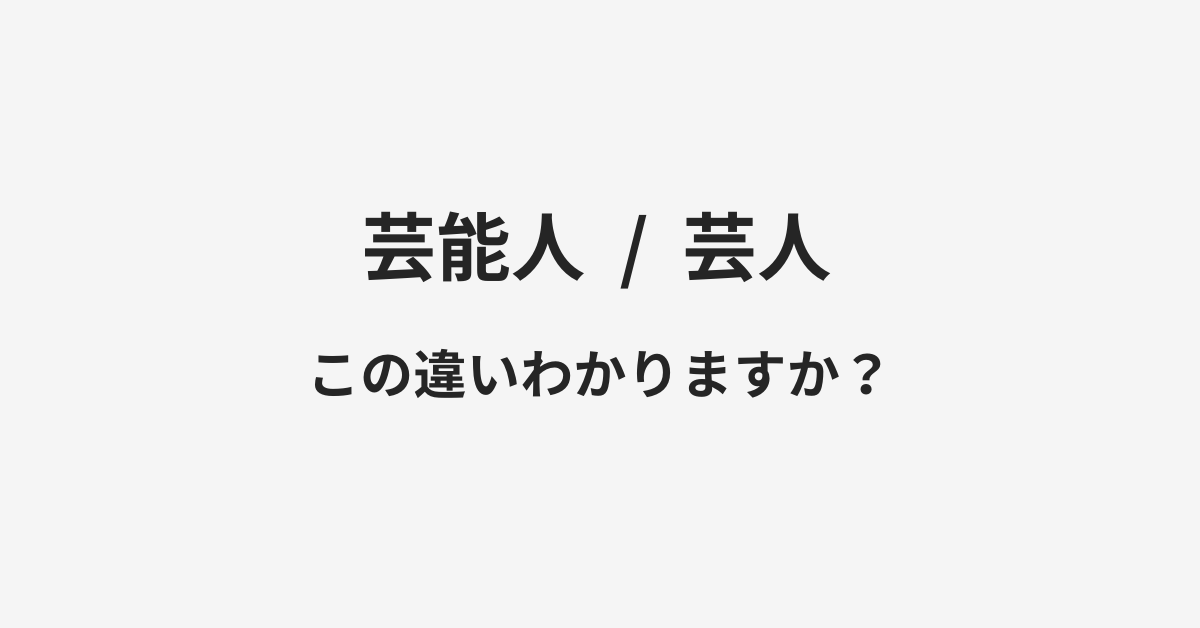【神主】と【宮司】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
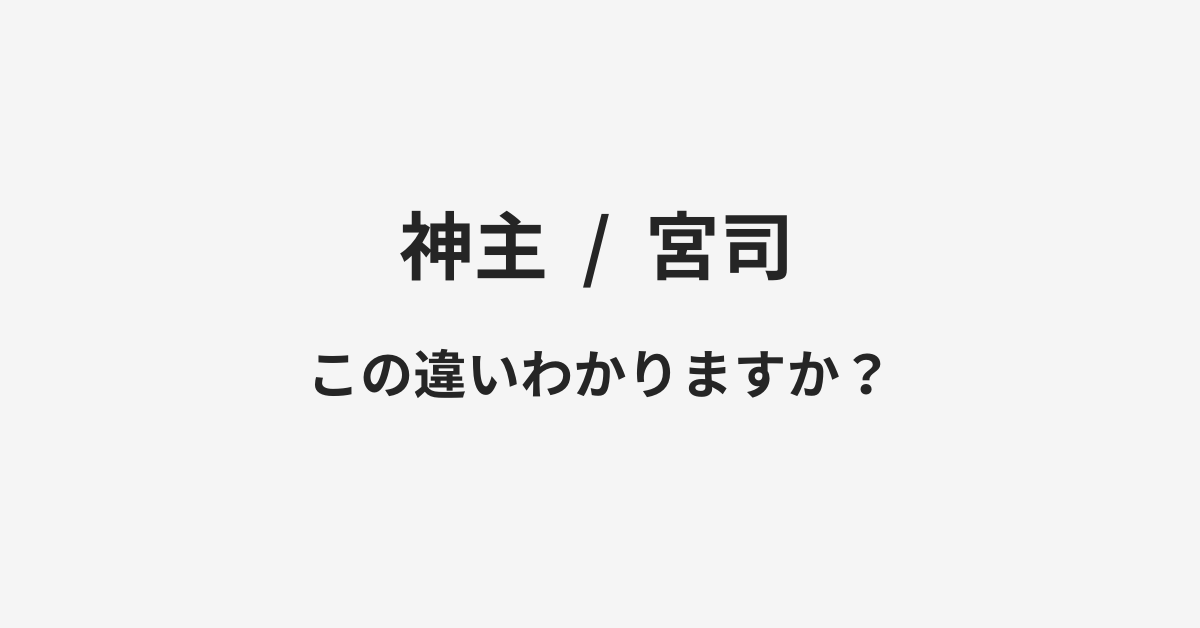
神主と宮司の分かりやすい違い
神主と宮司は、どちらも神社で働く神職ですが、立場と責任の大きさが異なります。神主は、神社で祈祷や祭事を行う神職全般を指す言葉で、いわば神社で働く人たちの総称です。
一方、宮司は神社の最高責任者で、会社でいえば社長のような立場の人を指す特別な役職名です。
神主とは?
神主(かんぬし)とは、神社に奉仕する神職の一般的な呼称で、正式には神職といいます。神前での祭祀、祈祷、お祓い、結婚式などの神事を執り行い、参拝者の願いを神様に取り次ぎます。また、神社の維持管理、氏子との交流、地域の伝統行事の継承なども重要な役割です。
神主になるには、神職養成機関(國學院大學、皇學館大学など)で学ぶか、各都道府県の神社庁が開催する神職養成講習会を修了し、神職資格を取得する必要があります。階位は初級から正階、権正階、明階、浄階まであり、経験と研修により昇進します。
全国に約8万の神社がありますが、専業で生活できる神社は限られており、多くは兼業です。年収は神社の規模により100-1000万円以上と幅があります。日本の伝統文化を守り伝える、精神的にも重要な職業です。
神主の例文
- ( 1 ) 神主として、毎日の祈祷や参拝者の対応に励んでいます。
- ( 2 ) 若手神主として、先輩方から祭式作法を学びながら修行しています。
- ( 3 ) 神主として地域の祭りを執り行い、伝統文化の継承に努めています。
- ( 4 ) 女性神主として、巫女さんの指導も担当しています。
- ( 5 ) 兼業神主として、平日は会社員、週末は神社で奉仕しています。
- ( 6 ) 神主として、神前結婚式の斎主を務めることも多くなりました。
神主の会話例
宮司とは?
宮司(ぐうじ)とは、神社の最高責任者で、神社の代表役員を務める神職の最高位です。神社の祭祀、運営、人事、財務など全般を統括し、氏子総代や地域との調整も行います。一つの神社に一人だけ存在し、その神社の顔として重要な役割を果たします。宮司になるには、まず神職資格を取得し、禰宜(ねぎ)、権宮司(ごんぐうじ)などを経て昇進するのが一般的です。
世襲制の神社も多いですが、実力と人望により外部から招聘されることもあります。明階以上の階位が必要で、神社本庁の任命を受けます。大規模神社の宮司は年収1000万円以上も可能ですが、小規模神社では200-500万円程度です。
伊勢神宮、明治神宮などの有名神社の宮司は、社会的地位も高く影響力があります。神社の伝統を守りながら、現代社会との調和を図る経営者的な能力も求められます。
宮司の例文
- ( 1 ) 宮司として、神社の運営全般と氏子総代との調整を行っています。
- ( 2 ) 三代目の宮司として、伝統を守りながら新しい取り組みも始めています。
- ( 3 ) 宮司として、神社の改修工事の資金集めに奔走しています。
- ( 4 ) 女性宮司として、全国でも珍しい立場で神社を守っています。
- ( 5 ) 宮司として、地域活性化のイベント企画にも積極的に関わっています。
- ( 6 ) 大規模神社の宮司として、多くの神職員をまとめる立場にあります。
宮司の会話例
神主と宮司の違いまとめ
神主と宮司は、神社における役割と地位の違いを表す神職の呼称です。神主は神職全般の総称、宮司は神社トップの役職名です。
すべての宮司は神主ですが、すべての神主が宮司ではありません。神職を目指す場合、まず神主として経験を積み、実力と人望を得て宮司を目指すのが一般的なキャリアパスです。
日本の伝統文化を守る、やりがいのある職業です。
神主と宮司の読み方
- 神主(ひらがな):かんぬし
- 神主(ローマ字):kannnushi
- 宮司(ひらがな):ぐうじ
- 宮司(ローマ字):guuji