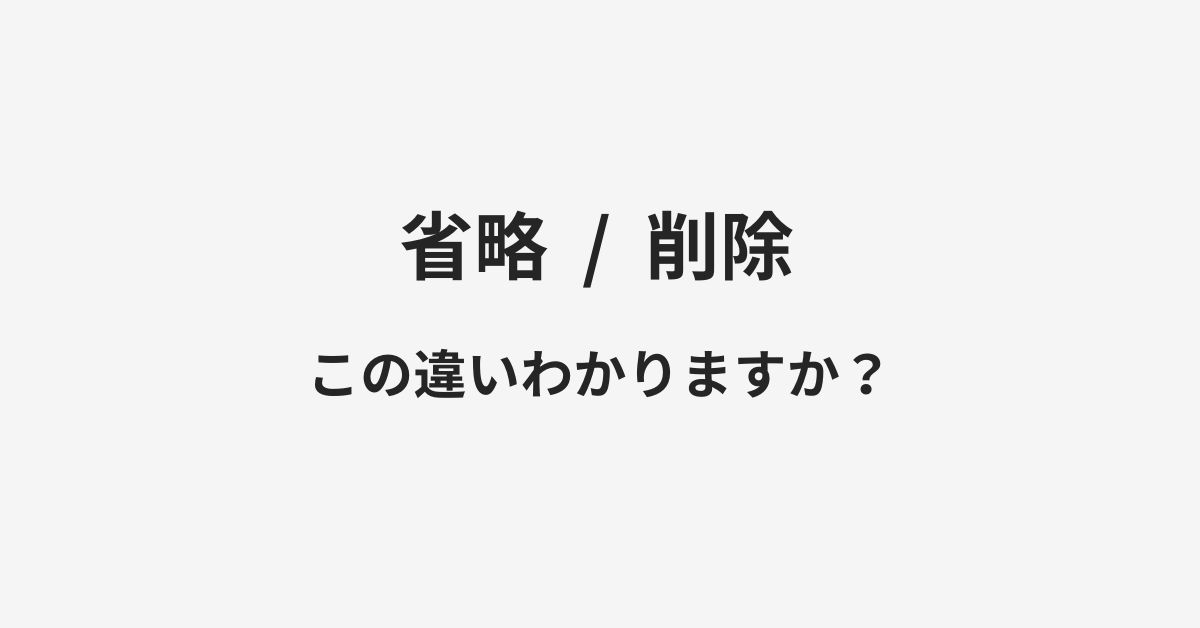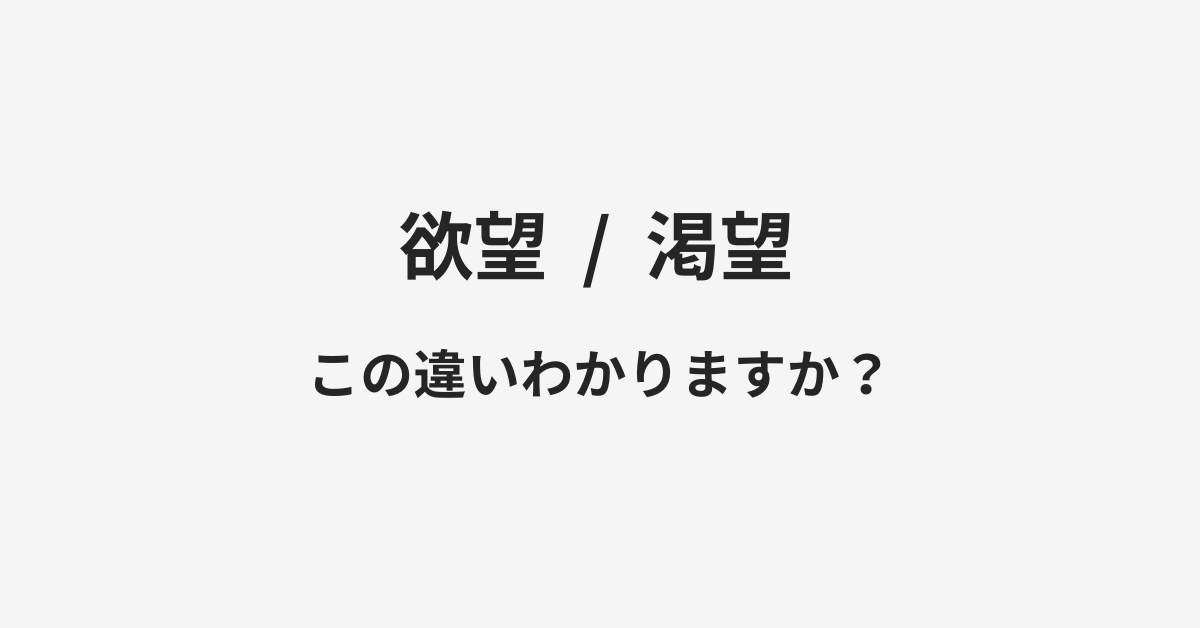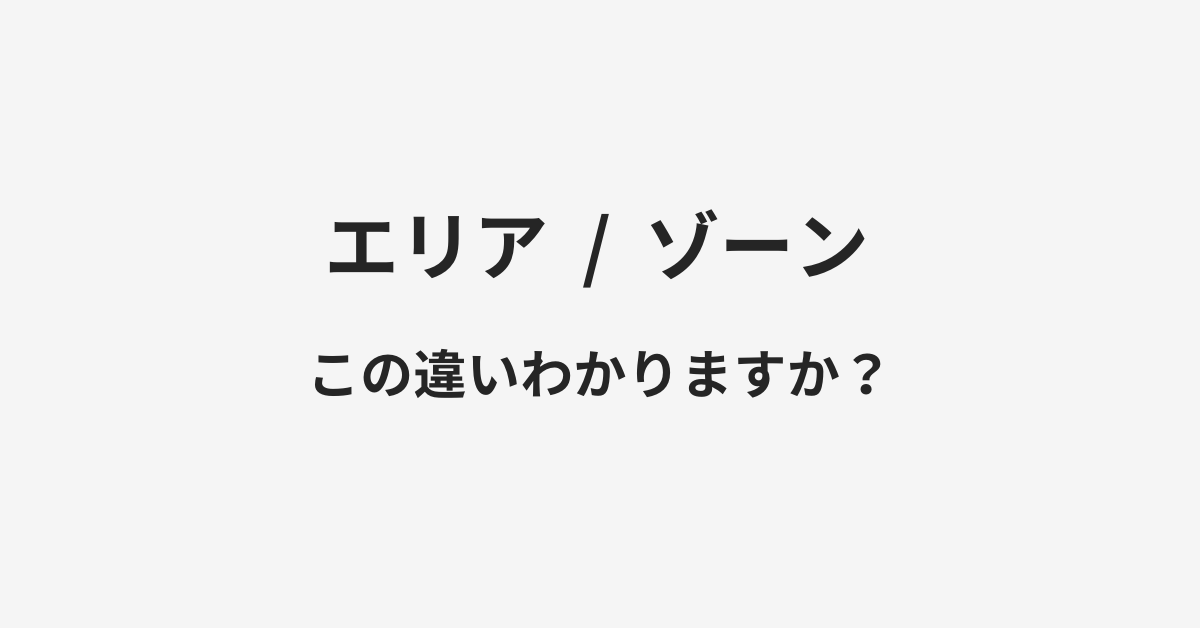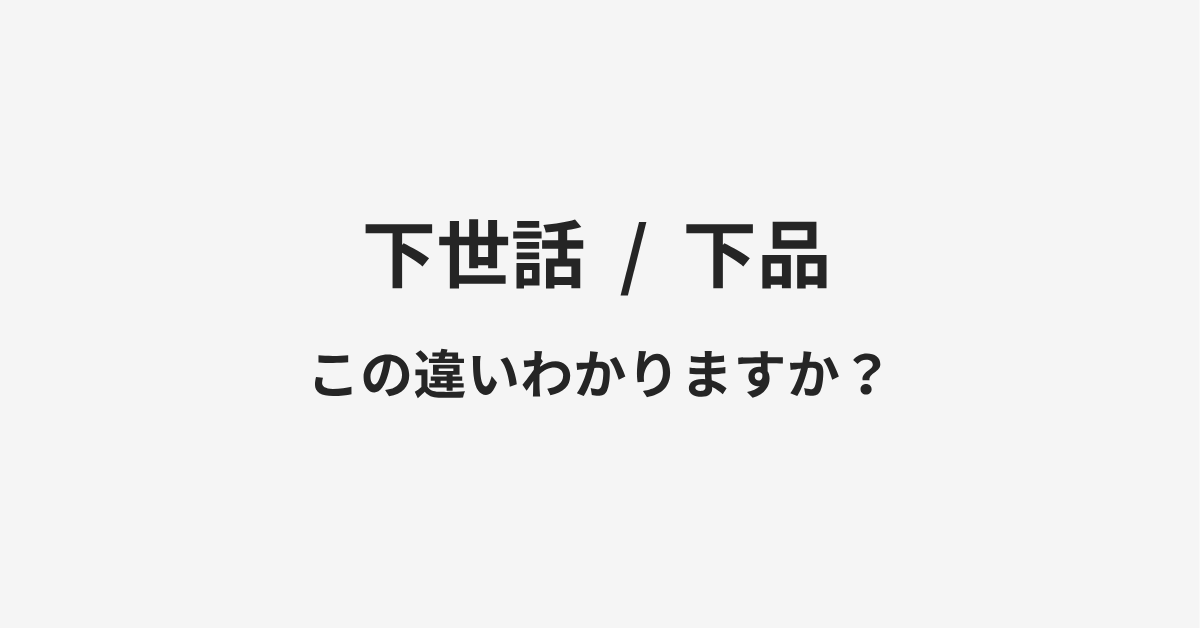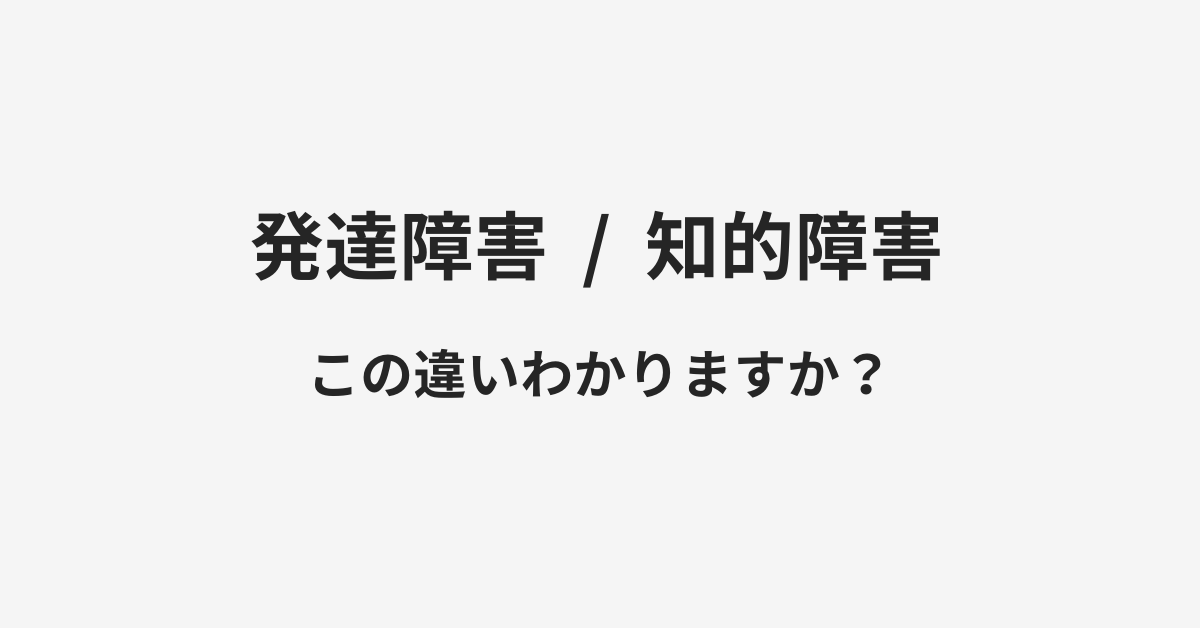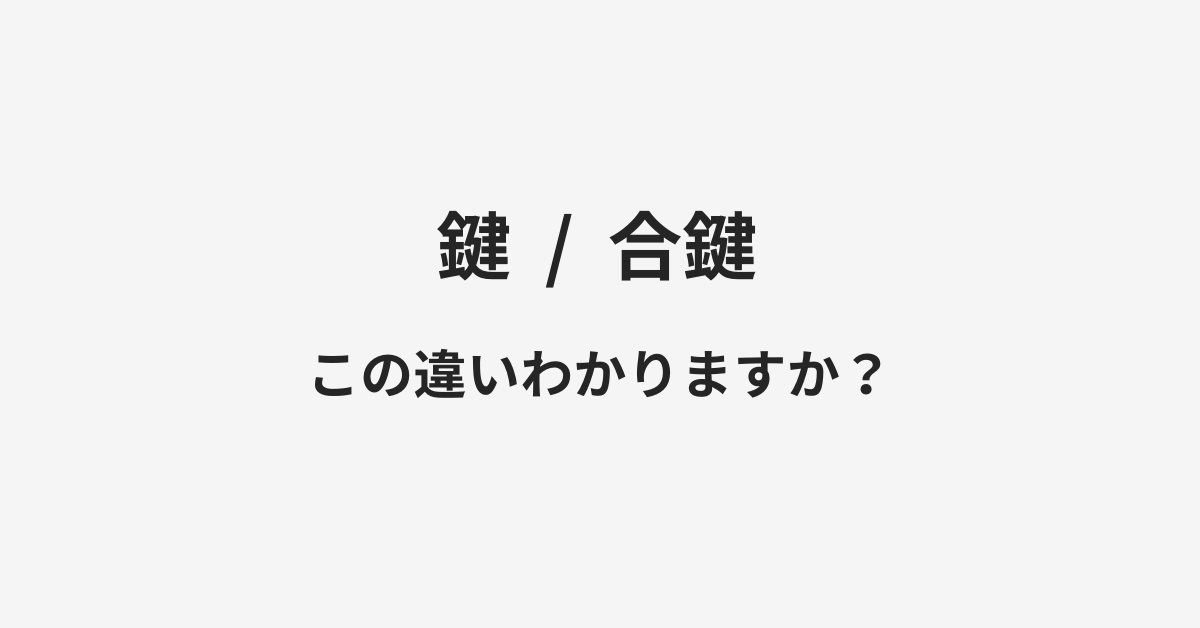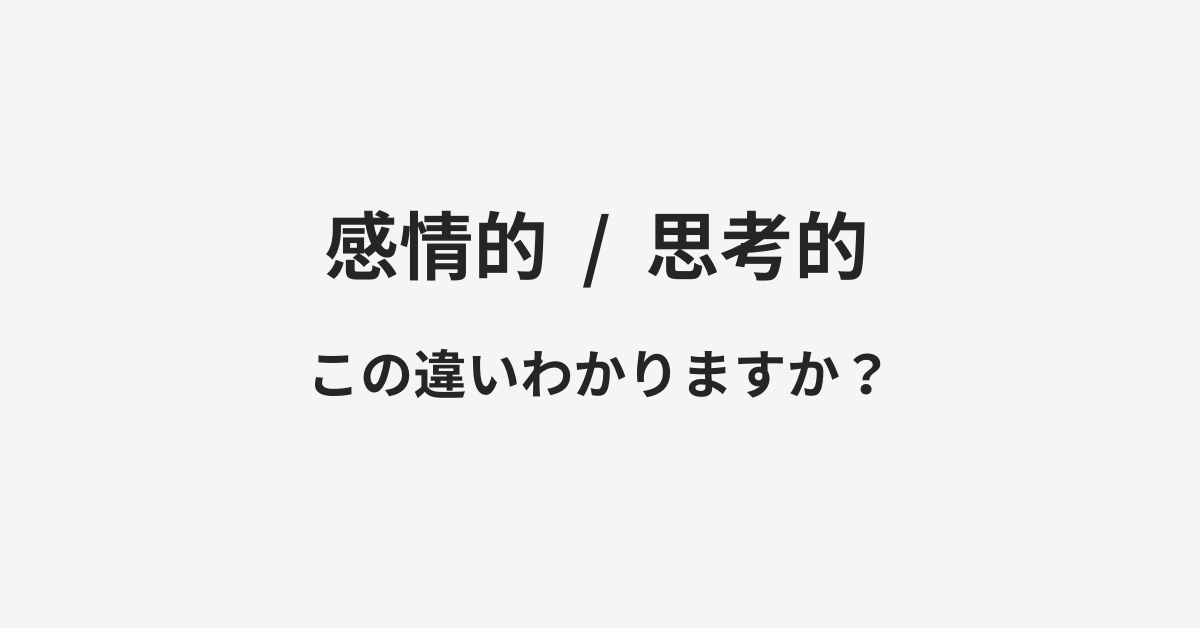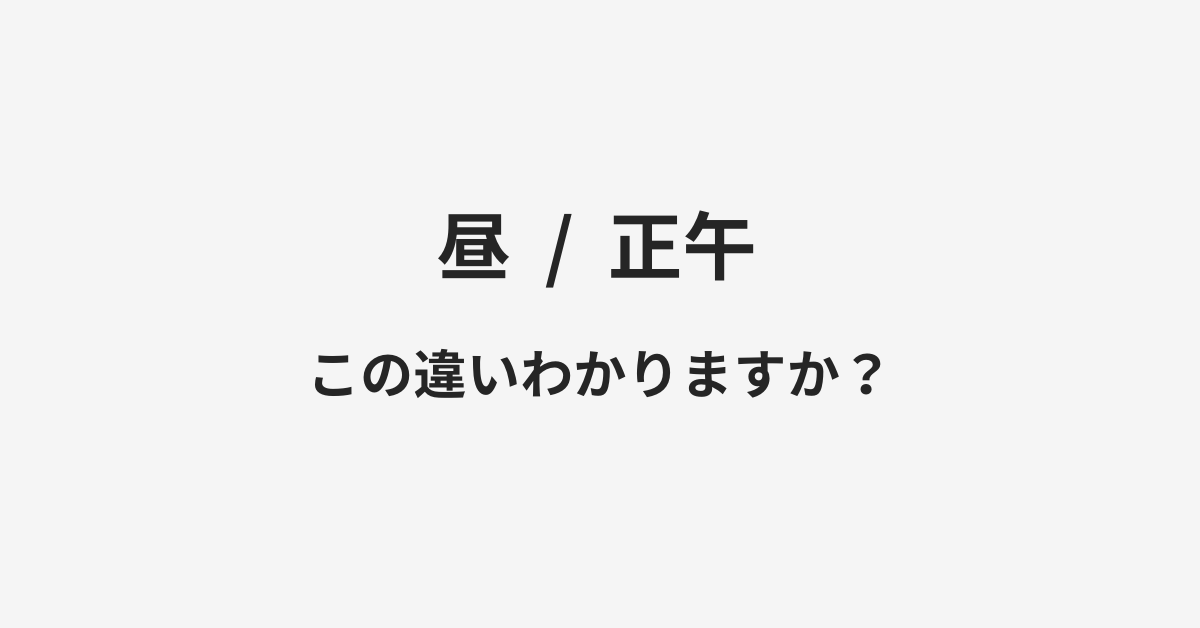【残り】と【残余】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
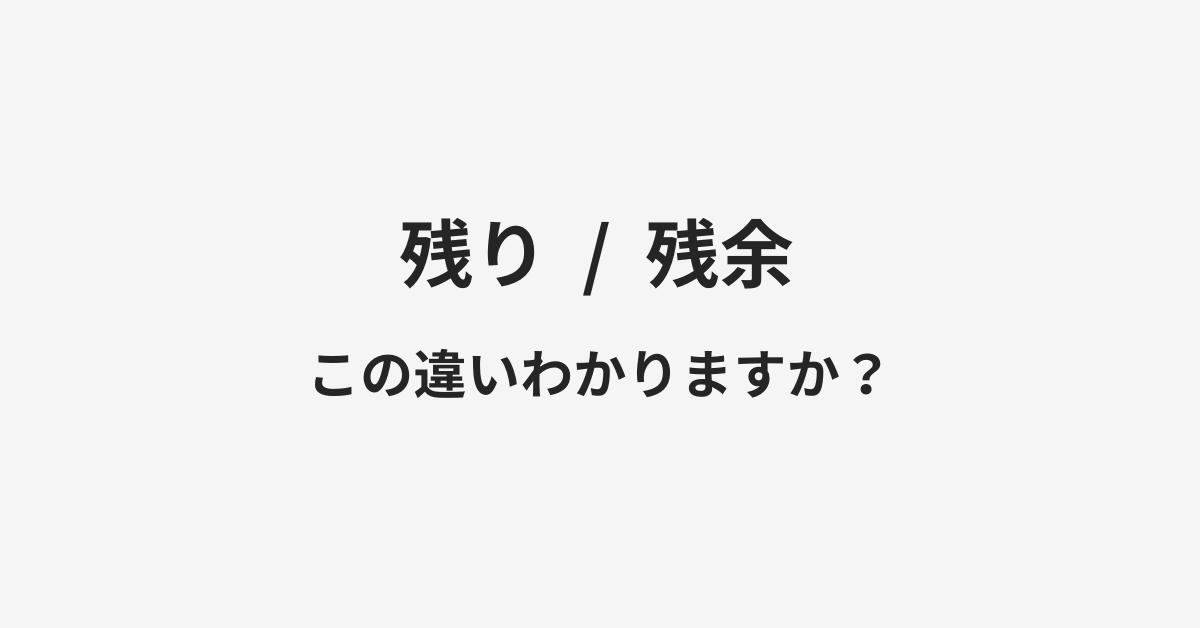
残りと残余の分かりやすい違い
残りと残余は、どちらも余ったものという意味ですが、使う場面の堅さが大きく違います。残りは残りのご飯、残り時間など日常会話でよく使う親しみやすい言葉です。
残余は残余財産、残余期間など、ビジネスや法律の場面で使う堅い言葉です。
普段の生活では残りを使い、公式な文書や専門的な話では残余を使うと覚えておくと良いでしょう。
残りとは?
残りとは、何かを使ったり取り除いたりした後に、まだ残っている部分のことを指します。食べ物の残り、お金の残り、時間の残りなど、日常生活のあらゆる場面で使われる親しみやすい言葉です。残り物、残り時間、残りの人生など、さまざまな言葉と組み合わせて使うことができ、具体的で分かりやすい表現として定着しています。
また、あと少しという意味合いも含んでおり、数量や時間の残量を表す際によく用いられます。
残りは話し言葉でも書き言葉でも広く使われ、子供から大人まで誰もが理解できる基本的な日本語です。カジュアルな会話から、ある程度フォーマルな場面まで幅広く使える便利な表現です。
残りの例文
- ( 1 ) 冷蔵庫に昨日の夕飯の残りがあるから、お昼はそれを食べよう。
- ( 2 ) 給料日まで残り一週間、節約して過ごさないといけません。
- ( 3 ) ケーキの残りは明日のおやつに取っておきましょう。
- ( 4 ) 宿題の残りを今日中に終わらせないと、明日提出できない。
- ( 5 ) 人生の残りの時間を、好きなことをして過ごしたいと思います。
- ( 6 ) 会議の残り時間で、来月の予定を確認しましょう。
残りの会話例
残余とは?
残余とは、全体から一部分を取り除いた後に残る部分を指す、やや形式的な言葉です。残余財産、残余価値、残余期間など、主にビジネス、法律、会計などの専門的な分野で使われることが多い表現です。日常会話ではあまり使われませんが、契約書や公的文書、学術論文などでは頻繁に登場します。
余りや残った部分という意味は残りと同じですが、より堅い印象を与え、正確性や厳密性が求められる場面で選ばれる言葉です。
残余は漢語的な表現で、文章に格調や専門性を持たせたい時に使われます。ビジネスメールや報告書、プレゼンテーションなど、フォーマルなコミュニケーションにおいて適切な言葉として認識されています。
残余の例文
- ( 1 ) 相続における残余財産の分配について、弁護士に相談しました。
- ( 2 ) プロジェクトの残余予算を、次期開発に充てることが決定されました。
- ( 3 ) 契約期間の残余日数は、正確に計算する必要があります。
- ( 4 ) 残余リスクの評価を行い、適切な対策を講じることが重要です。
- ( 5 ) 会計年度の残余期間における売上目標を設定しました。
- ( 6 ) 残余価値の算定には、専門的な知識が必要となります。
残余の会話例
残りと残余の違いまとめ
残りと残余は、基本的に同じ余ったものを表しますが、使用場面の formality(形式性)に大きな違いがあります。
残りは日常的で親しみやすい表現で、普段の会話や一般的な文章で広く使われます。残余は専門的で形式的な表現で、ビジネスや公的な場面で使われます。
迷った時は、友人や家族との会話なら残り、仕事や公式な場面なら残余を選ぶと適切です。
残りと残余の読み方
- 残り(ひらがな):のこり
- 残り(ローマ字):nokori
- 残余(ひらがな):ざんよ
- 残余(ローマ字):zannyo