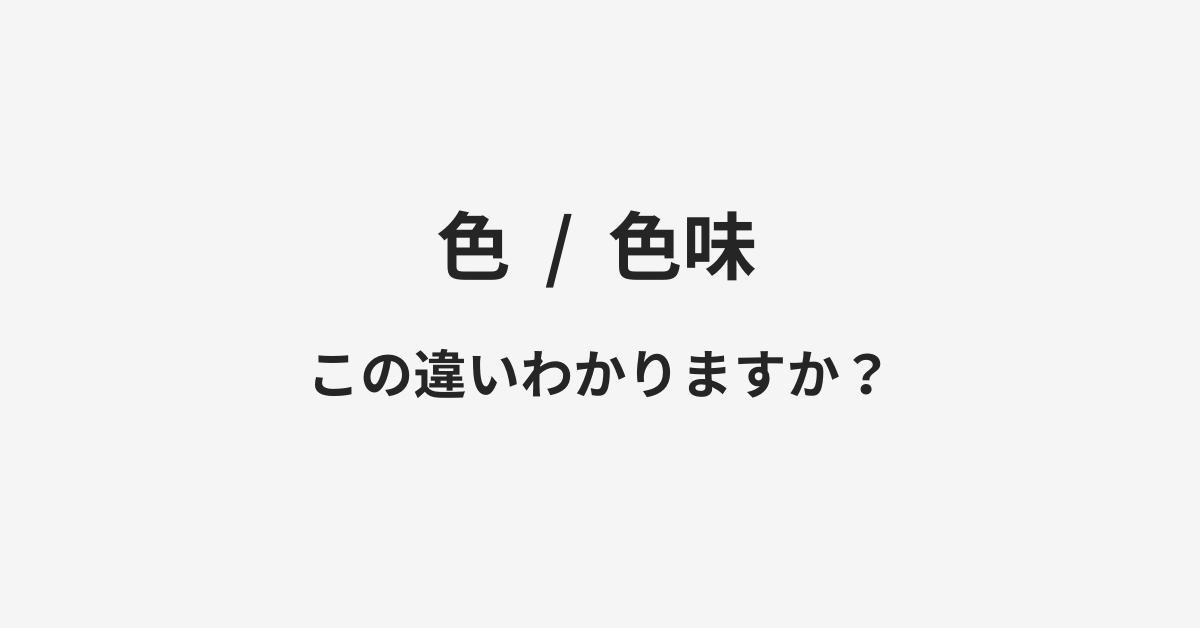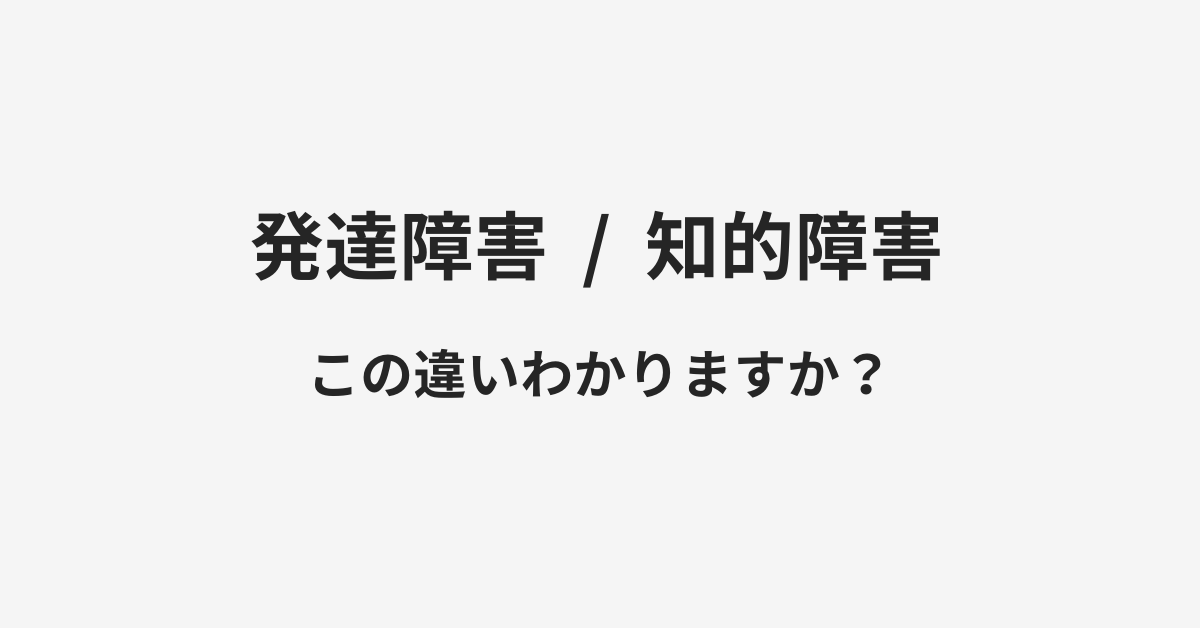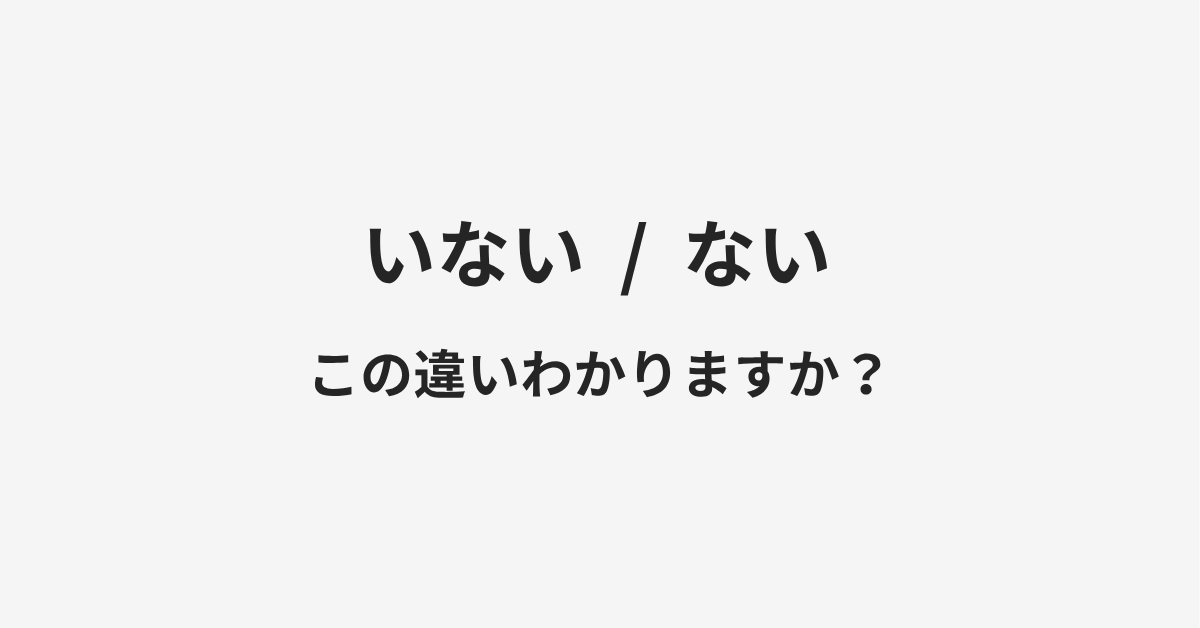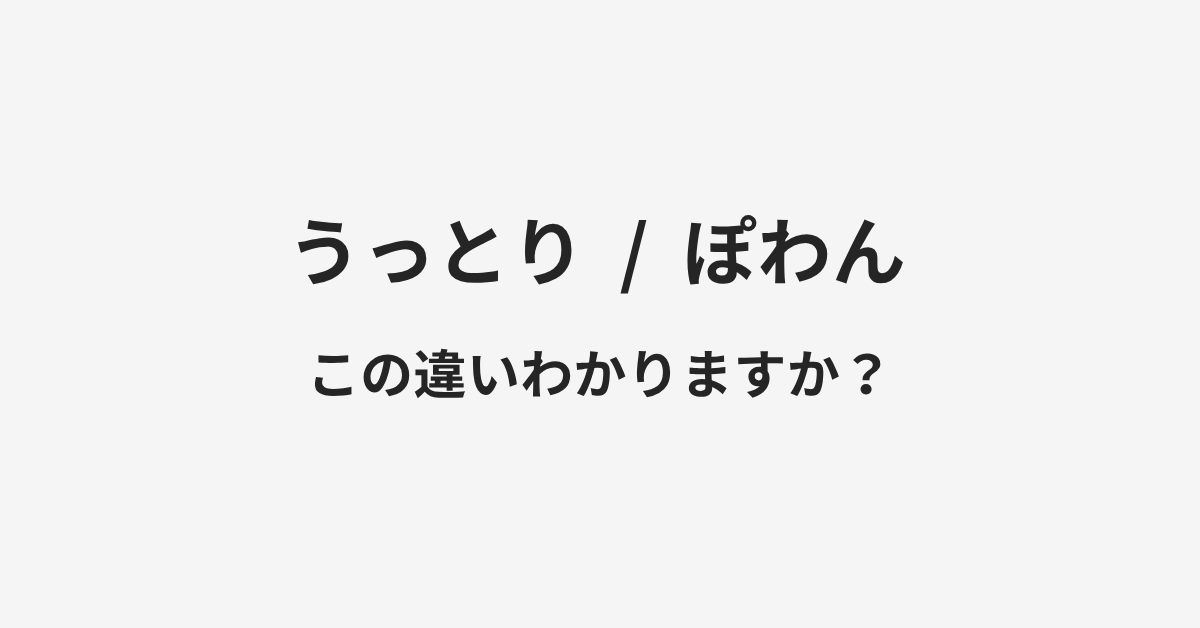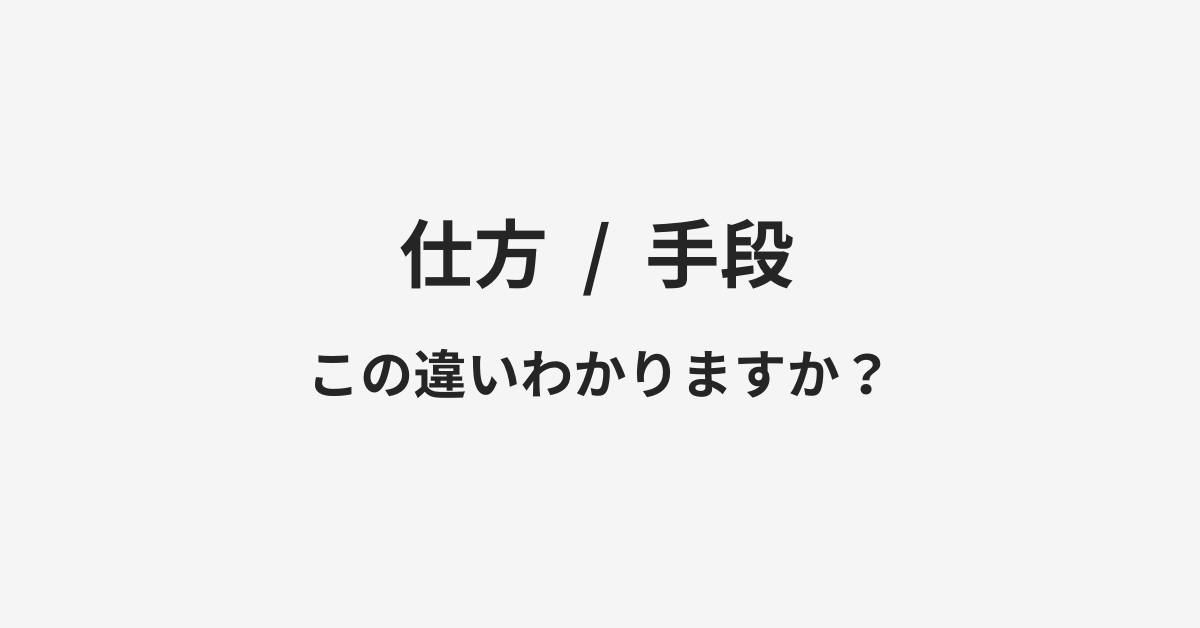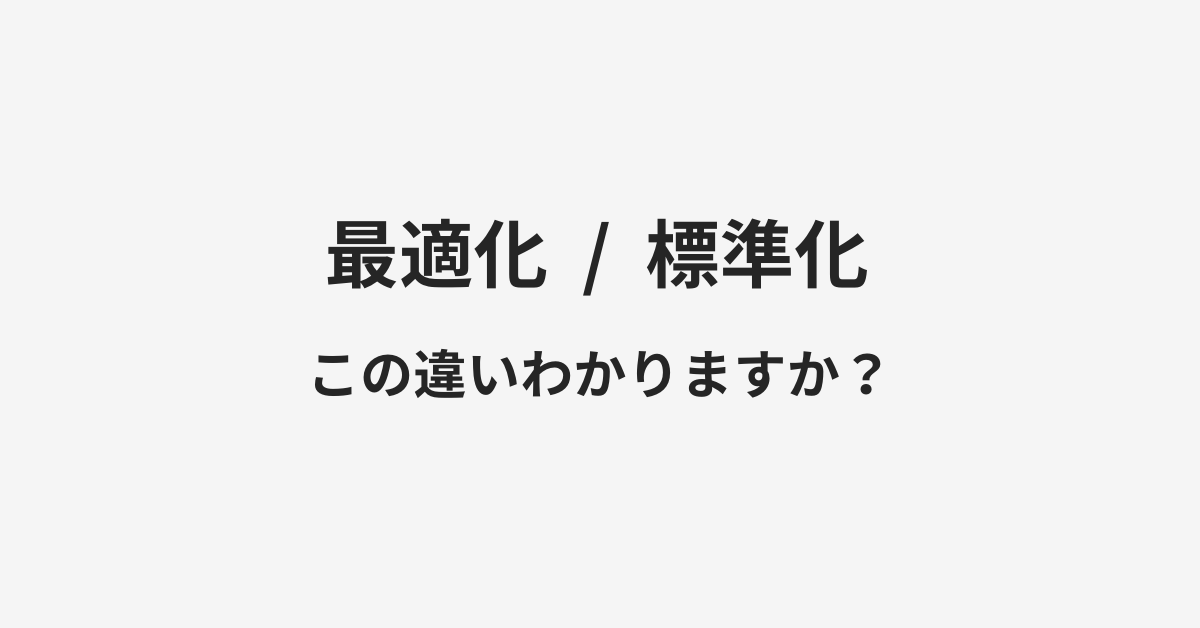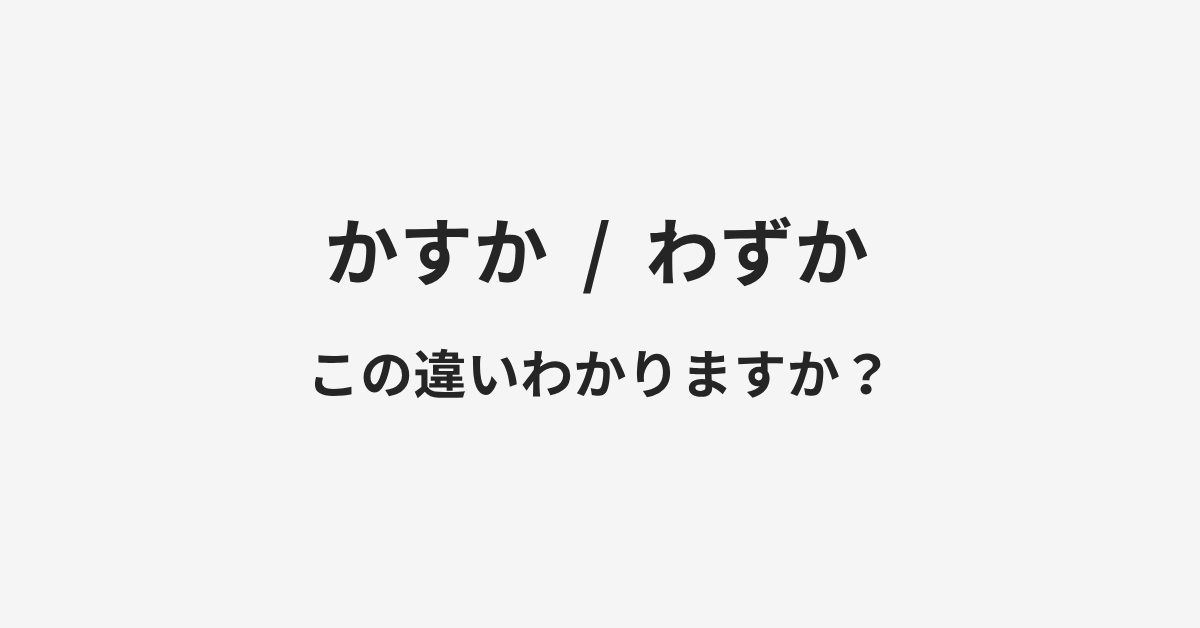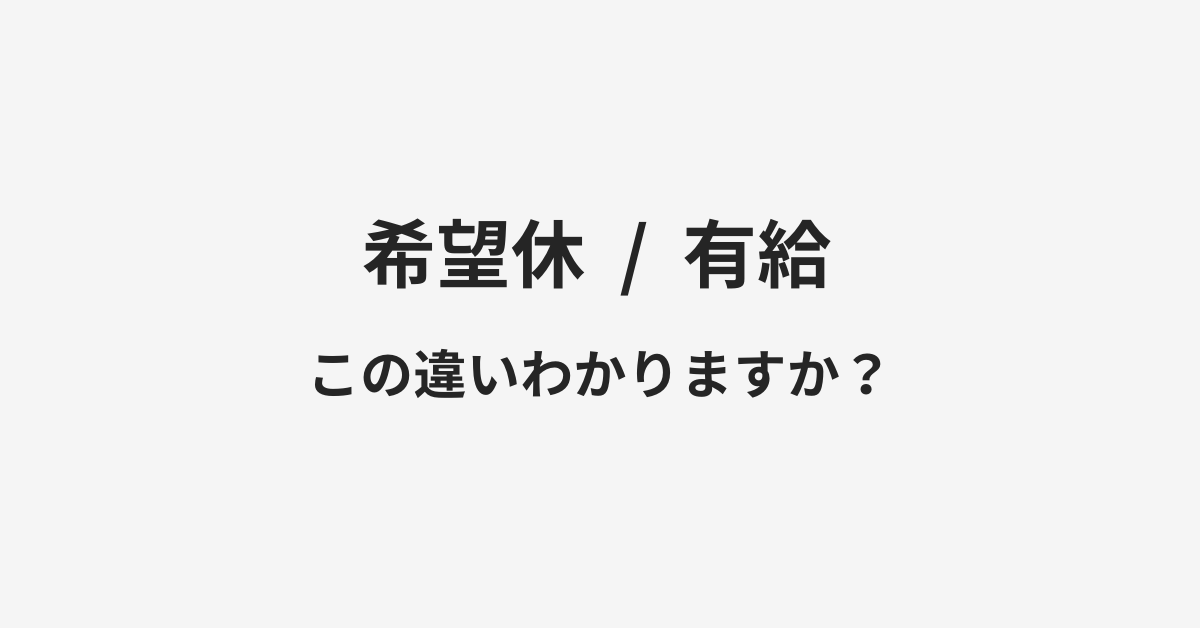【色合い】と【色相】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
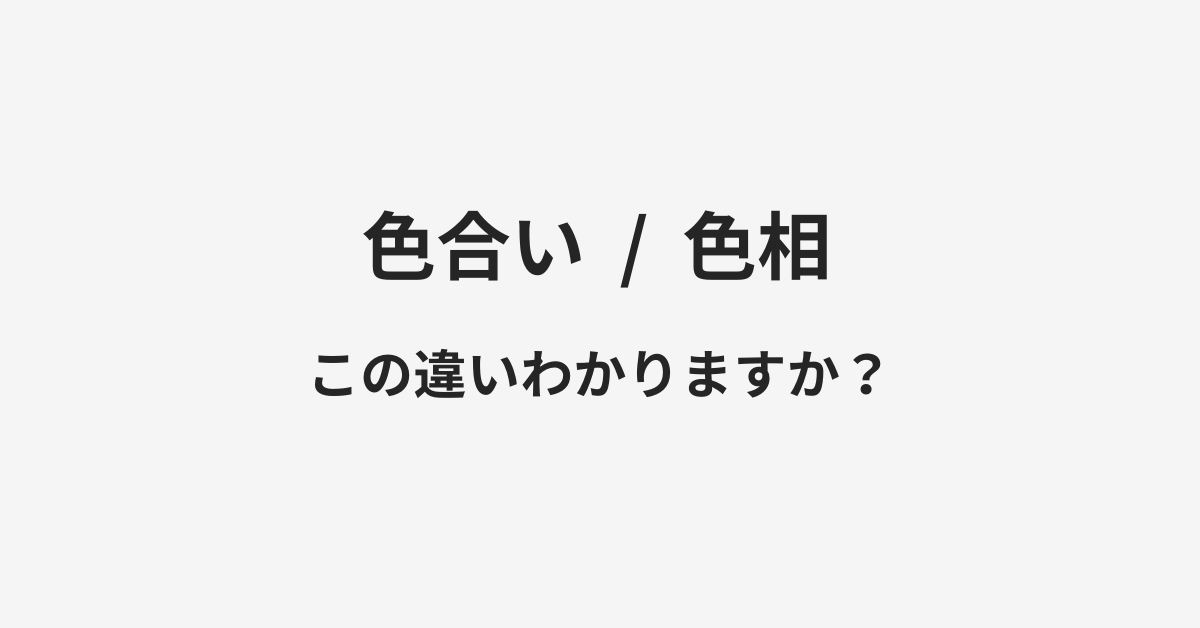
色合いと色相の分かりやすい違い
色合いと色相は、どちらも色に関する言葉ですが、使う場面と専門性が違います。色合いは秋の色合い、優しい色合いなど、色の雰囲気や調和を表す日常的な言葉です。
色相は赤、青、黄などの色の種類を示す専門用語で、美術やデザインで使われます。
色合いは雰囲気や調和、色相は色の種類という違いがあります。
色合いとは?
色合いとは、色の全体的な雰囲気、調和、濃淡、組み合わせなどを総合的に表現する言葉です。秋の色合い、パステル調の色合い、落ち着いた色合いなど、複数の色が作り出す印象や、色の濃さ薄さも含めた総合的な色彩の様子を指します。
日常会話でよく使われ、ファッション、インテリア、料理の見た目など、様々な場面で色の印象を伝える際に便利な表現です。この部屋の色合いは温かい、洋服の色合いを合わせるなど、感覚的で主観的な要素も含みます。
色合いは単一の色だけでなく、複数の色の組み合わせや、光の当たり方による変化も含む幅広い概念です。季節感や雰囲気を表現する際にも重要で、日本人の繊細な美意識を反映した言葉といえます。
色合いの例文
- ( 1 ) この絵の色合いがとても美しいですね。
- ( 2 ) 部屋の色合いを統一すると、落ち着いた空間になります。
- ( 3 ) 春らしい色合いの服を着たいです。
- ( 4 ) 夕焼けの色合いが日々違って見えます。
- ( 5 ) この料理、色合いも考えて盛り付けました。
- ( 6 ) 写真の色合いを少し明るく調整しました。
色合いの会話例
色相とは?
色相とは、色彩学における専門用語で、赤、橙、黄、緑、青、紫など、色の基本的な種類や性質を表します。色の三要素(色相、明度、彩度)の一つで、何色かを示す最も基本的な属性です。色相環という円形の図で表現され、虹の色の順番に並んでいます。
美術、デザイン、印刷、ウェブデザインなどの専門分野では必須の概念で、正確な色の指定や調整に使われます。例えば、色相を少し赤寄りにする、補色の色相を選ぶなど、技術的な色の調整で用いられます。
一般の人には馴染みが薄い言葉ですが、スマートフォンの写真編集アプリなどで色相・彩度という項目を見たことがある人も多いでしょう。色相を理解することで、より正確で効果的な色使いができるようになります。
色相の例文
- ( 1 ) 赤の色相から少しオレンジ寄りに調整してください。
- ( 2 ) 色相環で隣り合う色を類似色相といいます。
- ( 3 ) この画像の色相を変更して、別の雰囲気にしました。
- ( 4 ) 緑の色相には、黄緑から青緑まで幅があります。
- ( 5 ) 色相・彩度・明度を調整して、理想の色を作ります。
- ( 6 ) 補色は色相環で正反対に位置する色のことです。
色相の会話例
色合いと色相の違いまとめ
色合いと色相は、色を表現する際の日常語と専門用語という違いがあります。色合いは色の雰囲気や調和、濃淡を含む総合的な印象を表す日常的な表現です。
色相は色の基本的な種類を示す色彩学の専門用語で、赤・青・黄などの純粋な色の分類を指します。色合いは感覚的・総合的、色相は科学的・分析的という違いがあります。
優しい色合いの服は日常表現、色相環で反対側の色は専門的表現というように使い分けます。
色合いと色相の読み方
- 色合い(ひらがな):いろあい
- 色合い(ローマ字):iroai
- 色相(ひらがな):しきそう
- 色相(ローマ字):shikisou