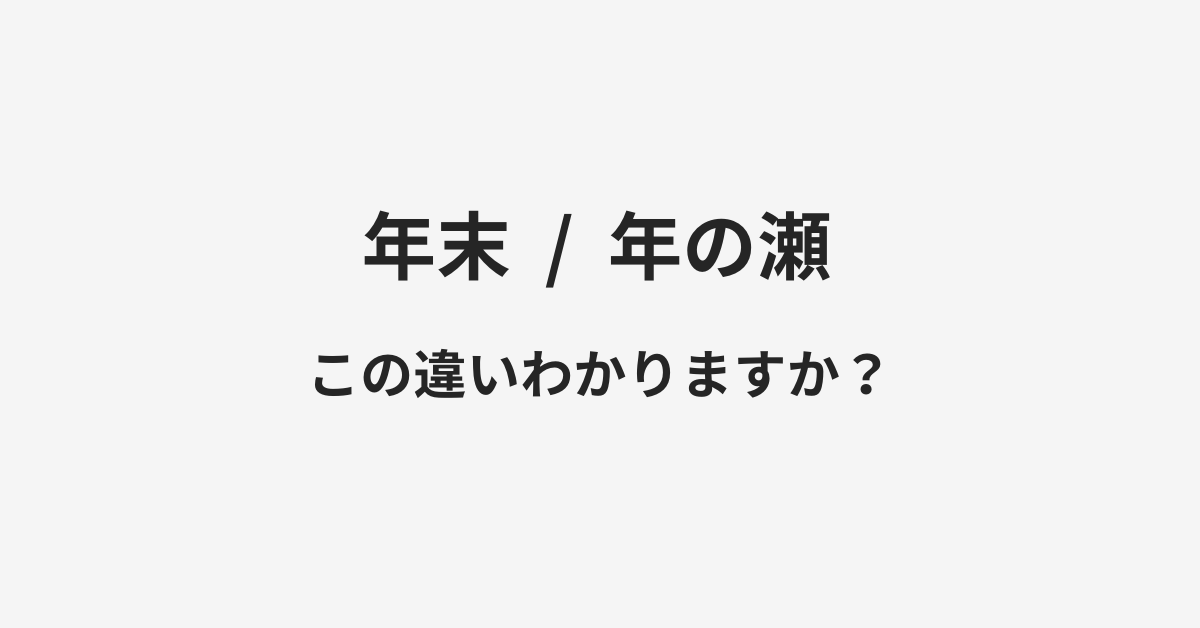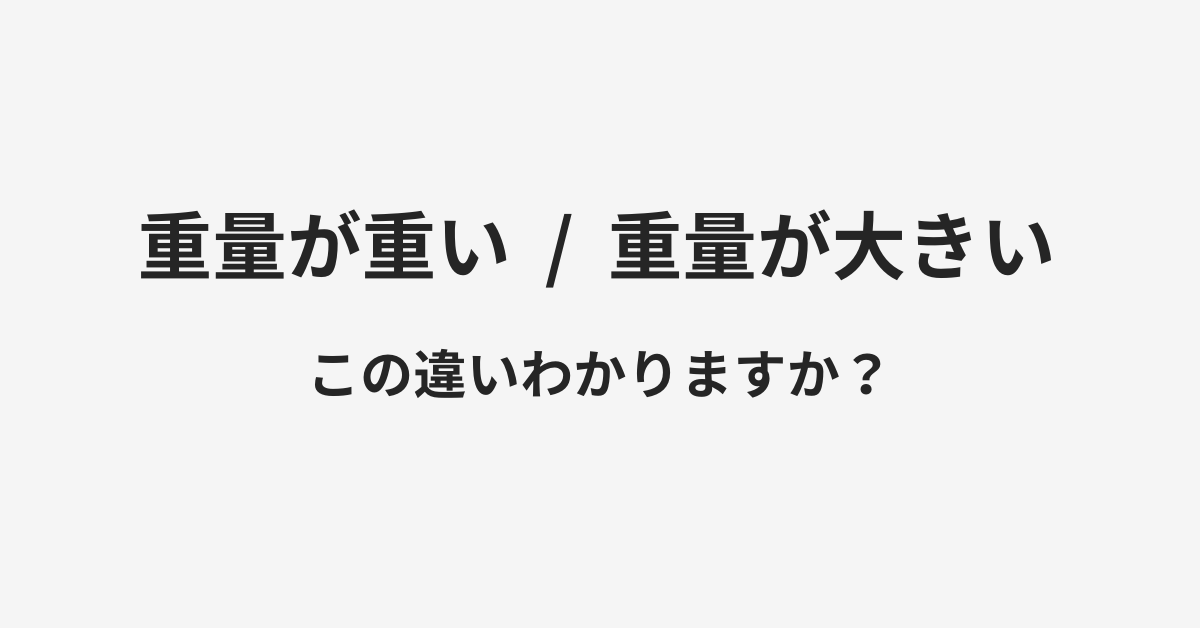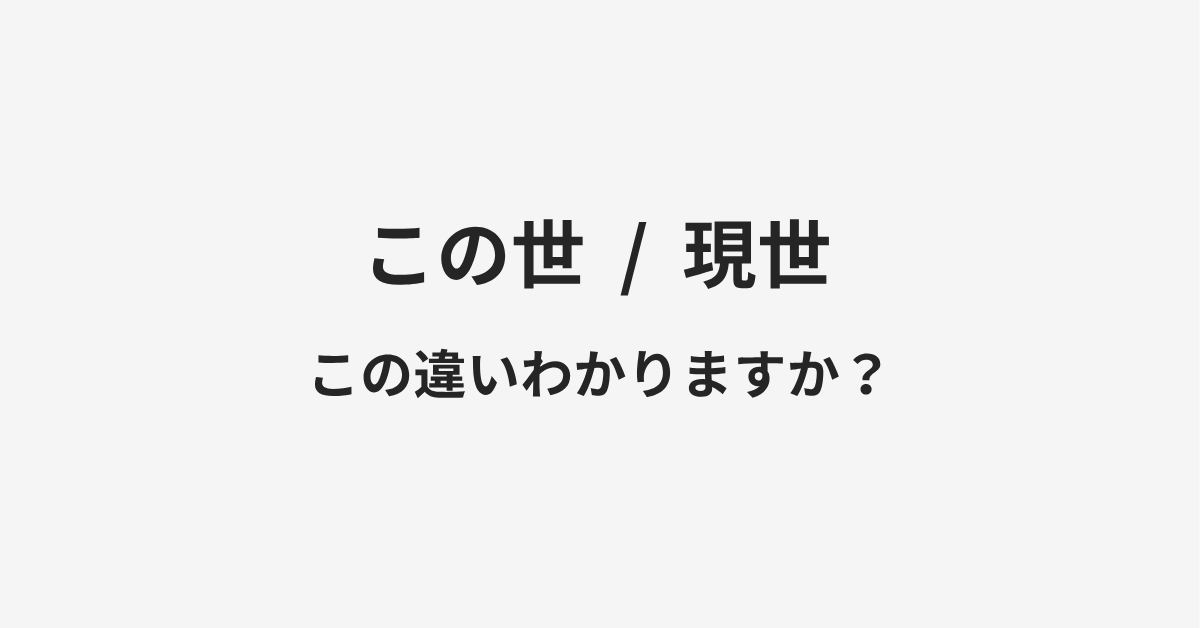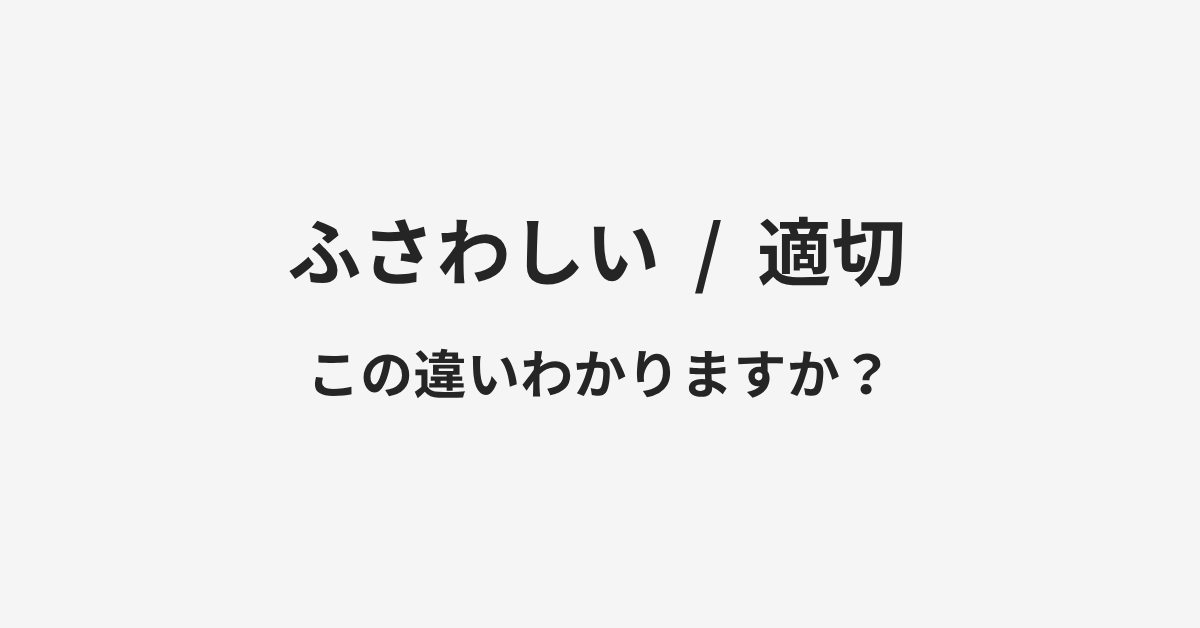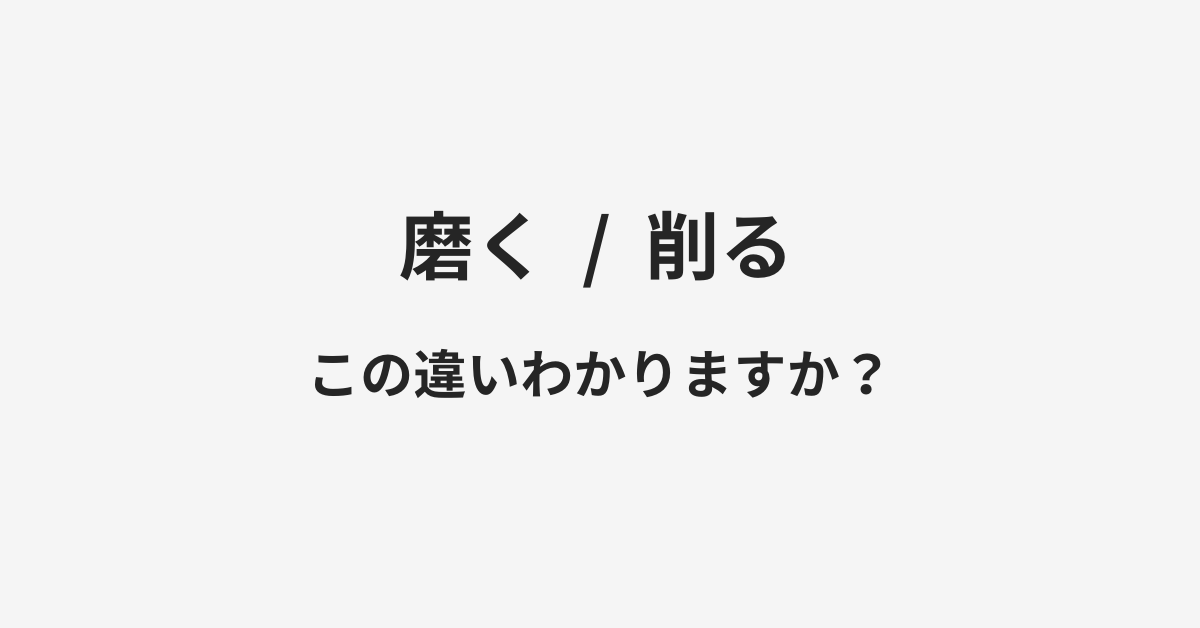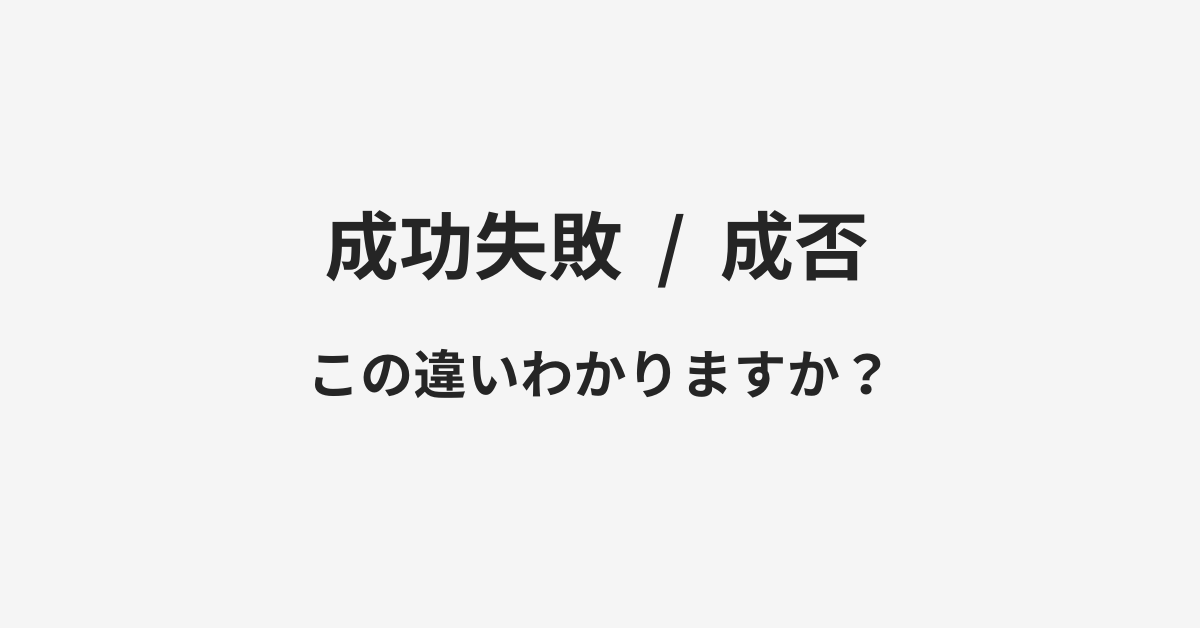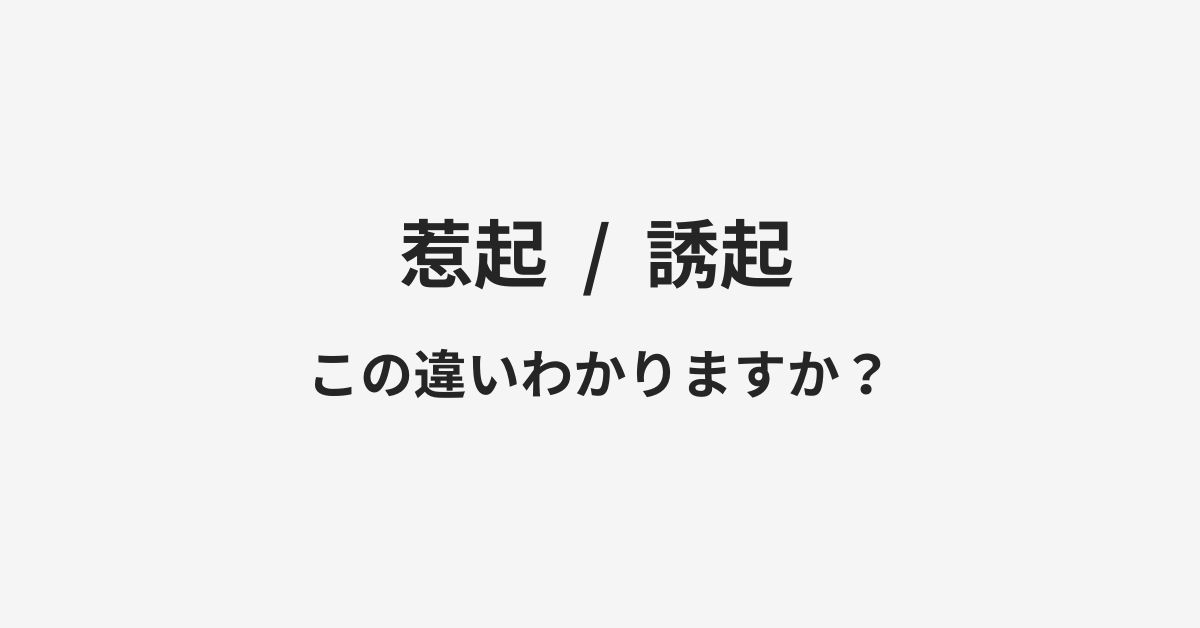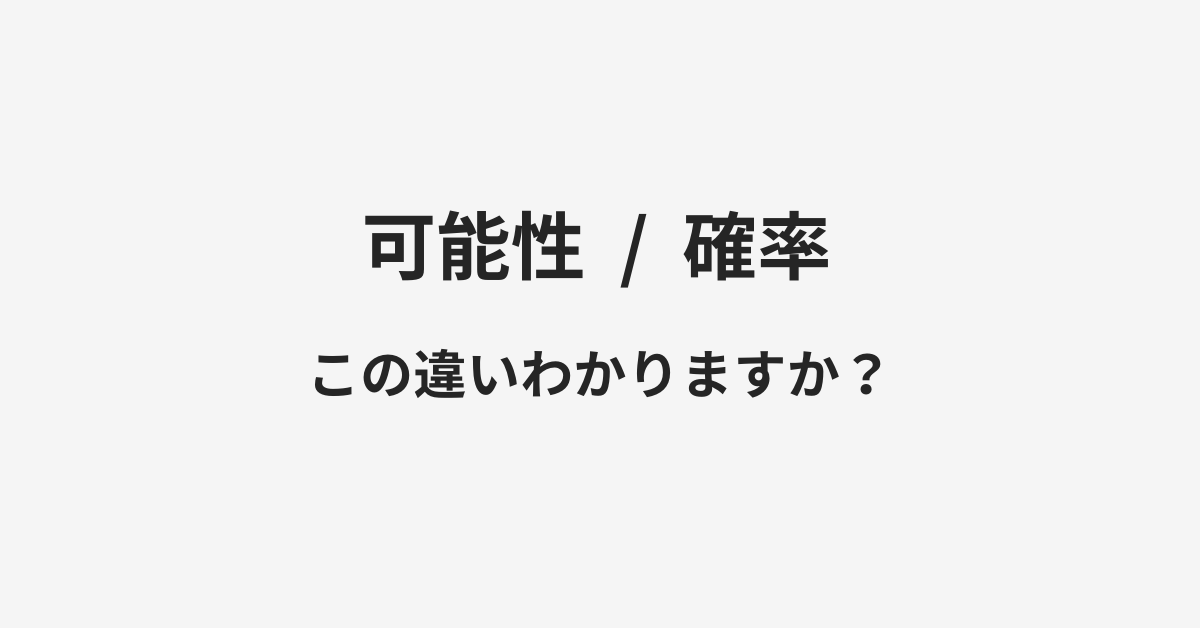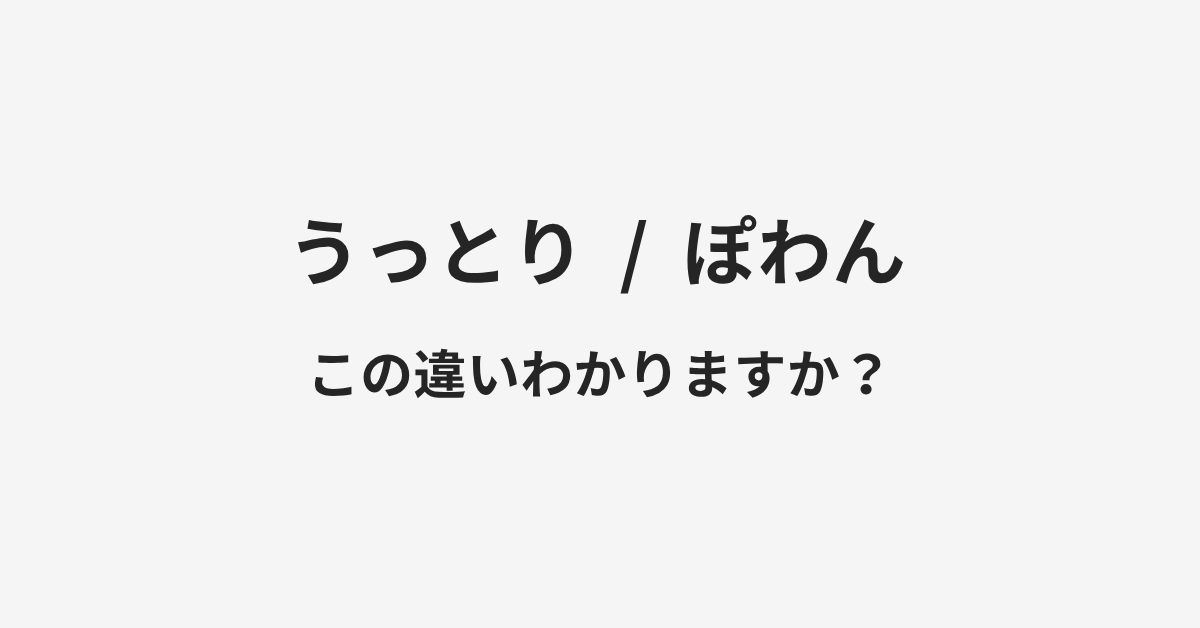【冬】と【冬場】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
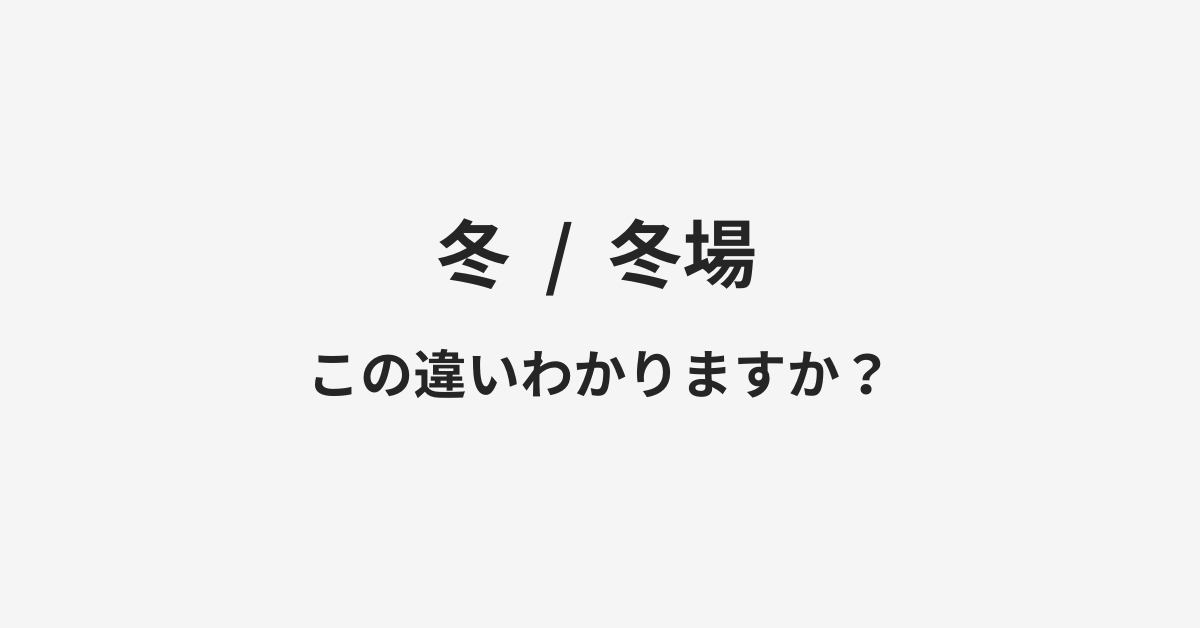
冬と冬場の分かりやすい違い
冬と冬場は、どちらも寒い季節を表しますが、使い方が少し違います。冬は、春夏秋冬の四季の一つで、12月から2月頃の季節そのものを指します。
冬が来た、冬の景色のように使います。冬場は冬の期間、冬の時期という意味で、その期間中であることを強調するときに使います。
冬場の電気代のように使います。冬は季節の名前、冬場は期間を表す言い方という違いがあります。
冬とは?
冬とは、四季の一つで、一年で最も寒い季節を指します。日本では一般的に12月から2月頃を指し、気象学的には12月から2月、天文学的には冬至から春分までとされます。
冬の寒さ、冬休み、冬景色のように、季節そのものや、その季節特有の現象、風物を表現する際に使います。詩的、文学的な表現にもよく用いられます。
季節を表す基本的な言葉として、天気予報、カレンダー、俳句など幅広い場面で使われ、日本の四季の美しさを表現する重要な言葉です。
冬の例文
- ( 1 ) 今年の冬は暖かい。
- ( 2 ) 冬の星座が美しく見える。
- ( 3 ) 冬が終わり、春が近づいている。
- ( 4 ) 冬の寒さが身にしみる。
- ( 5 ) 北海道の冬は厳しい。
- ( 6 ) 冬の風物詩といえば雪だるまだ。
冬の会話例
今年の冬は雪が多いらしいね。
そうみたい。冬の準備をしっかりしないと。
冬といえば、鍋料理が恋しくなるよ。
確かに!冬の楽しみの一つだね。
でも冬は寒くて苦手なんだ。
冬には冬の良さがあるよ。温泉とか最高じゃない?
冬場とは?
冬場とは、冬の期間、冬の時期を意味する言葉です。場という字が付くことで、その期間中であることや、期間全体を通じた状況を表現します。
冬場の売り上げ、冬場の対策のように、ビジネスや実用的な文脈で使われることが多く、期間中の継続的な状態や傾向を示す際に用います。
季節を時間的な幅として捉え、その期間における活動、対策、傾向などを論じる際に便利な表現です。話し言葉でも書き言葉でも使われます。
冬場の例文
- ( 1 ) 冬場の電気代が高くて困る。
- ( 2 ) 冬場は道路が凍結しやすい。
- ( 3 ) 冬場の売り上げが好調だ。
- ( 4 ) 冬場に備えて準備をする。
- ( 5 ) 冬場の乾燥対策が必要だ。
- ( 6 ) スキー場は冬場が繁忙期だ。
冬場の会話例
冬場の光熱費、去年より増えてない?
冬場は暖房費がかさむから仕方ないね。
冬場の節約方法を考えないと。
冬場は厚着をして、暖房の温度を下げるとか?
それもいいね。冬場の対策をしっかりしよう。
冬場を乗り切るための工夫が必要だね。
冬と冬場の違いまとめ
冬は季節そのもの、冬場は冬の期間を強調する表現という違いがあります。冬は冬が来たのように季節の到来を表し、冬場は冬場の売上のように期間中の状況を表します。
詩的表現には冬、実務的表現には冬場が適しています。
どちらも同じ季節を指しますが、冬は季節名、冬場は期間表現として使い分けましょう。
冬と冬場の読み方
- 冬(ひらがな):ふゆ
- 冬(ローマ字):fuyu
- 冬場(ひらがな):ふゆば
- 冬場(ローマ字):fuyuba