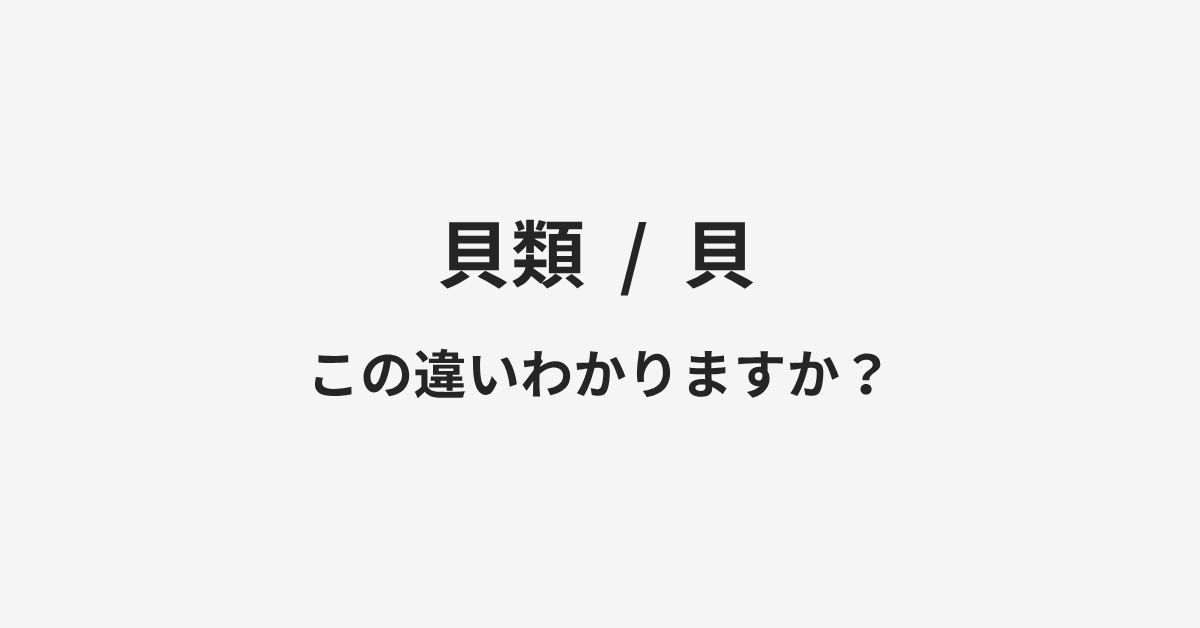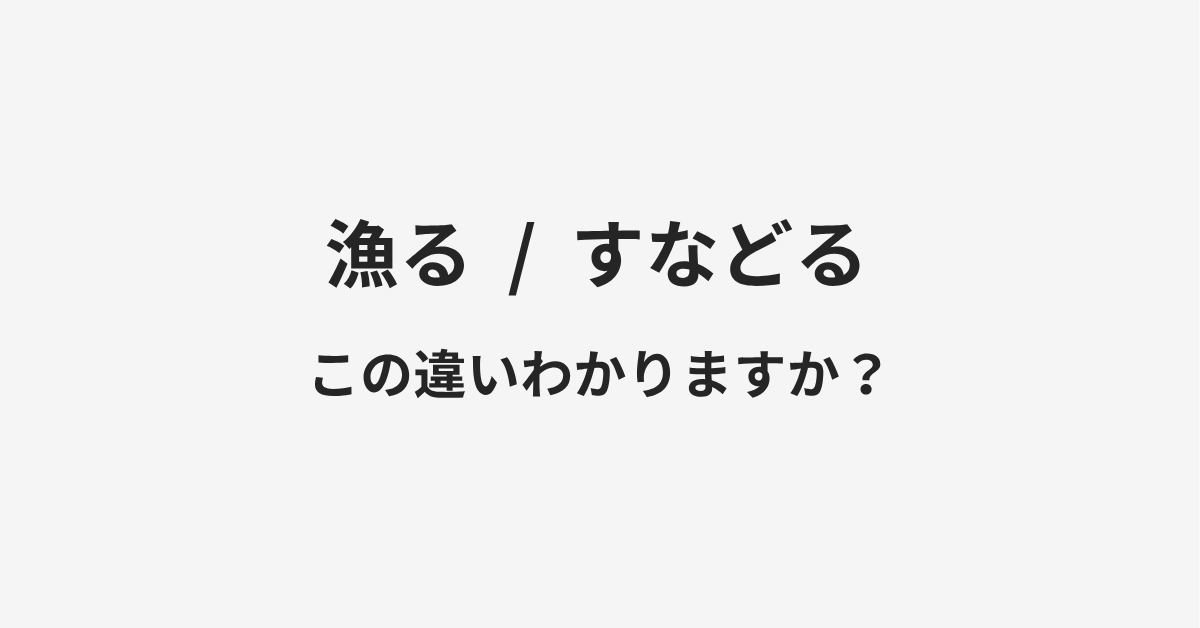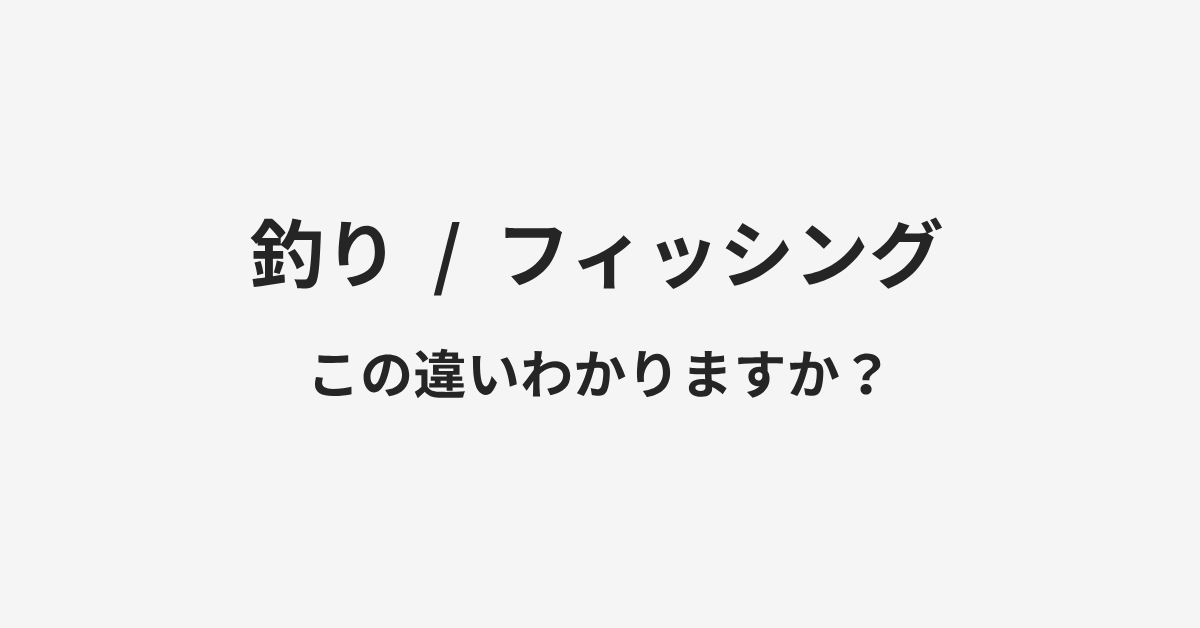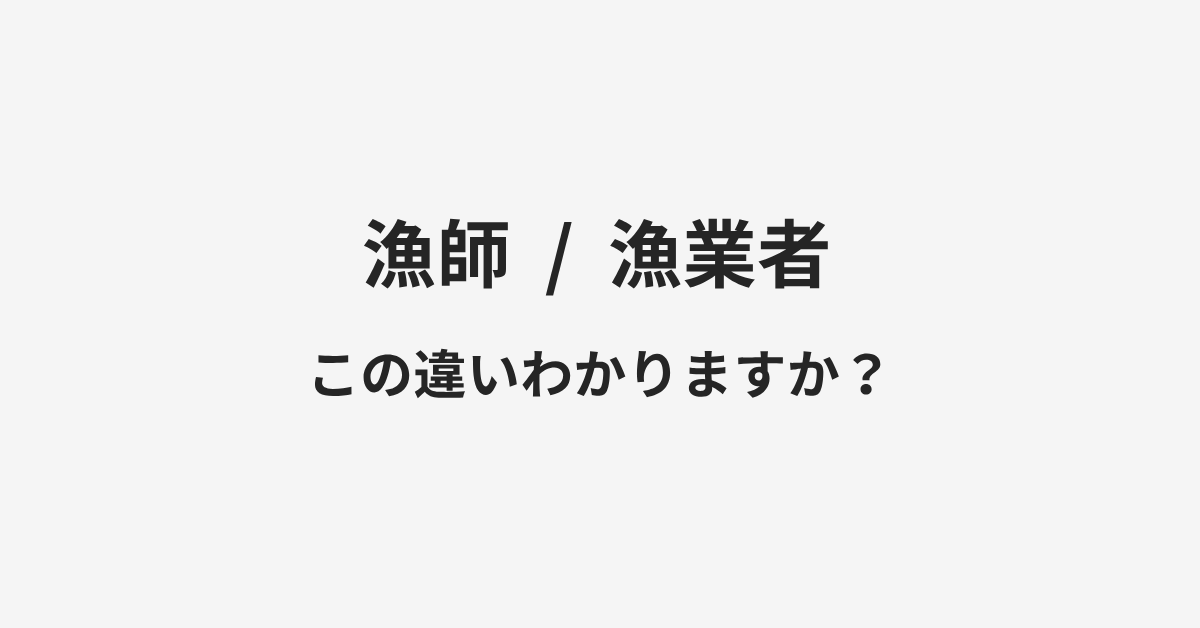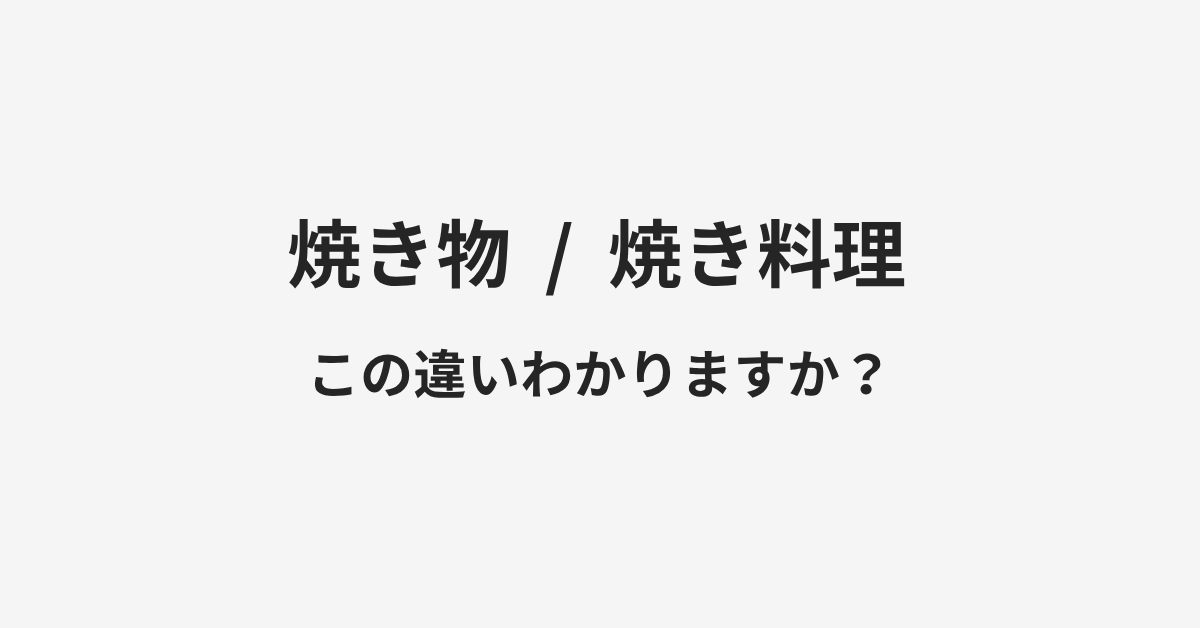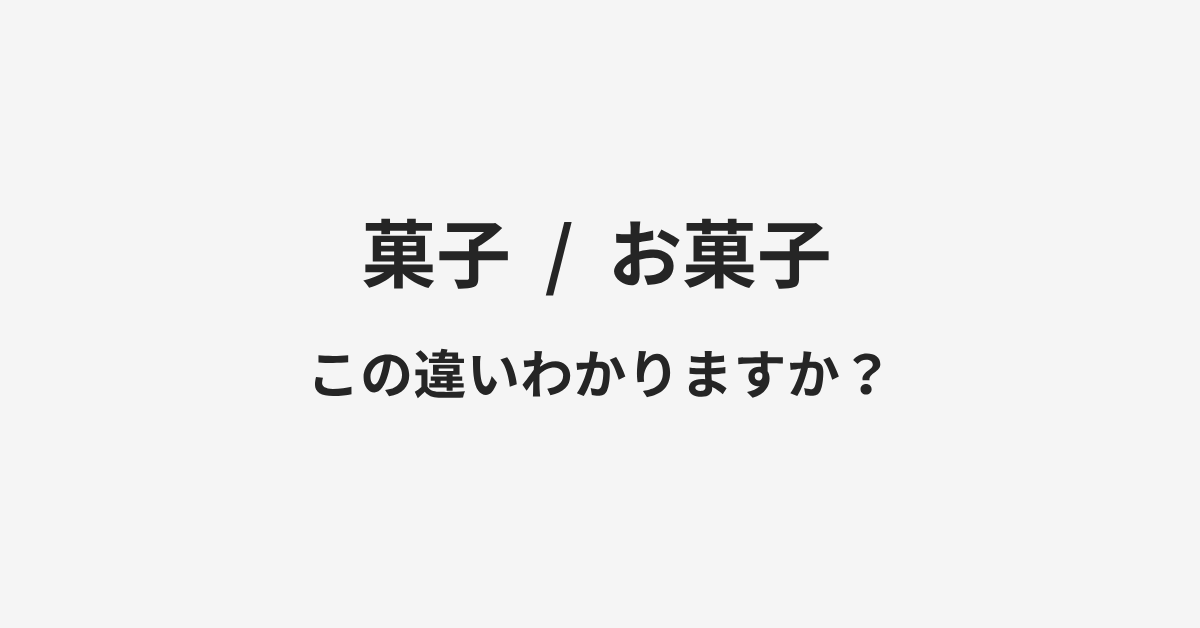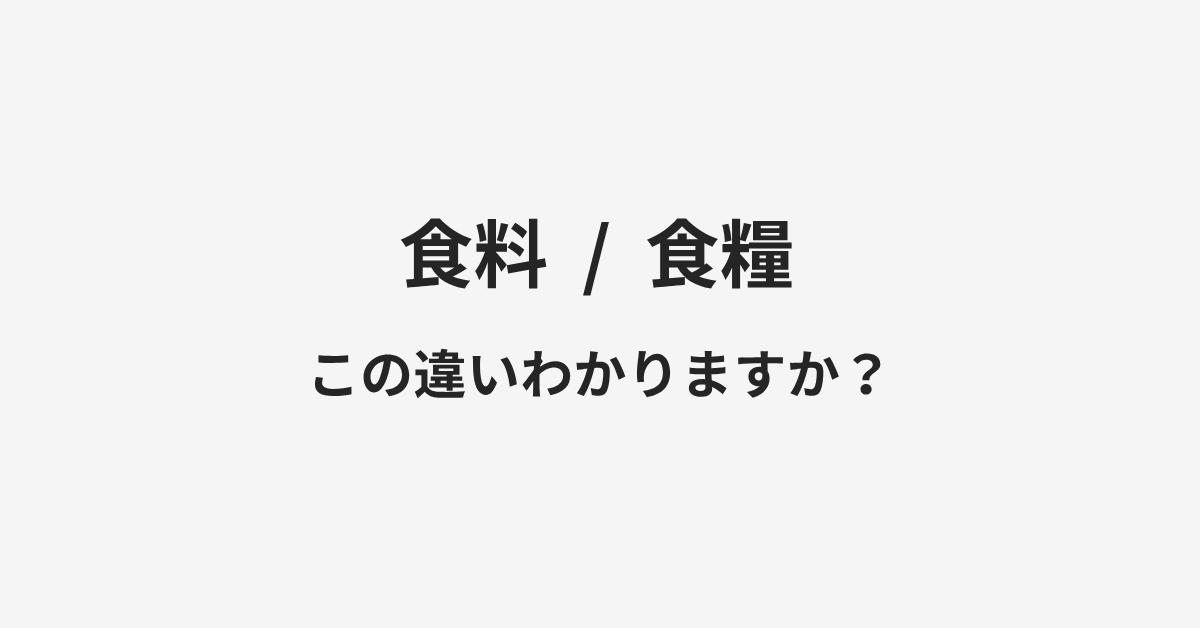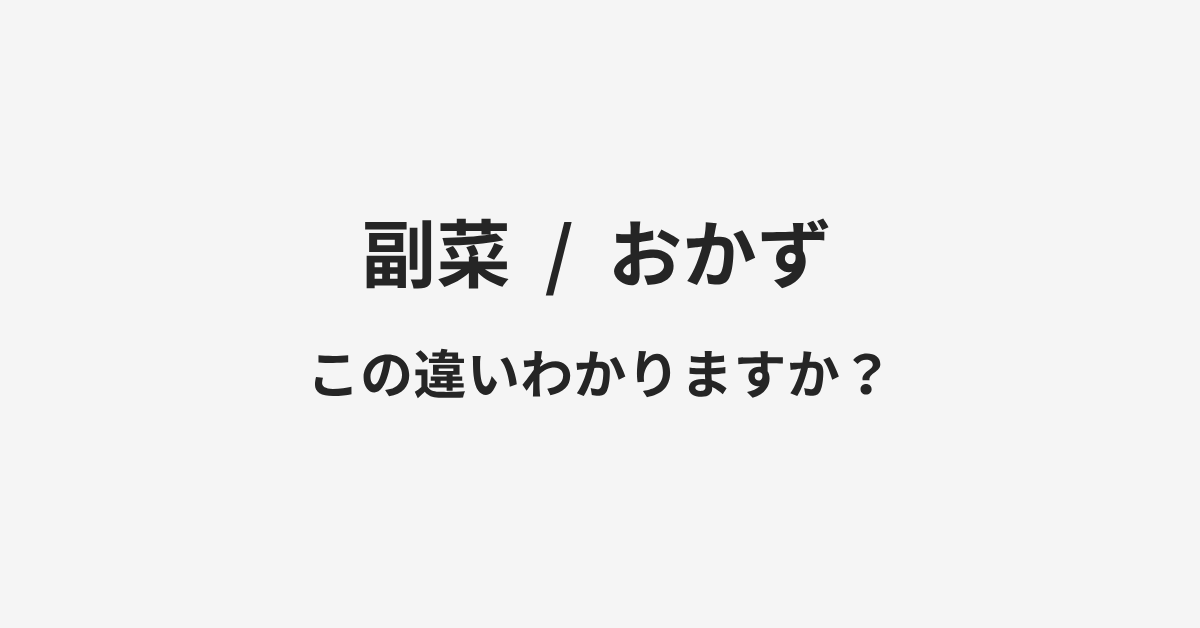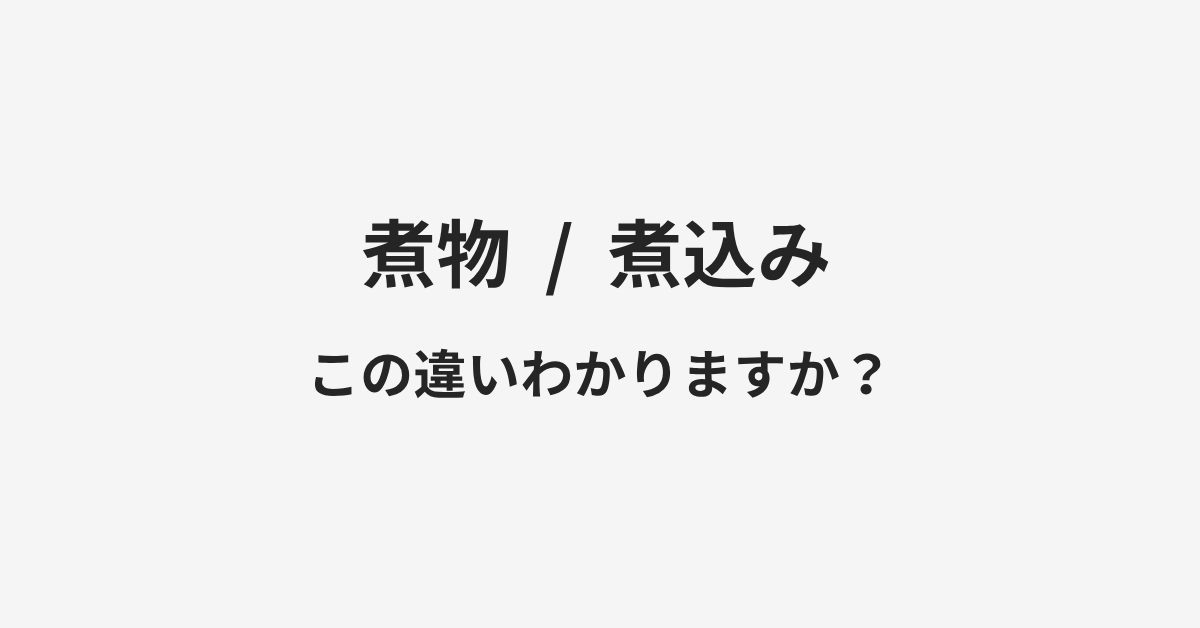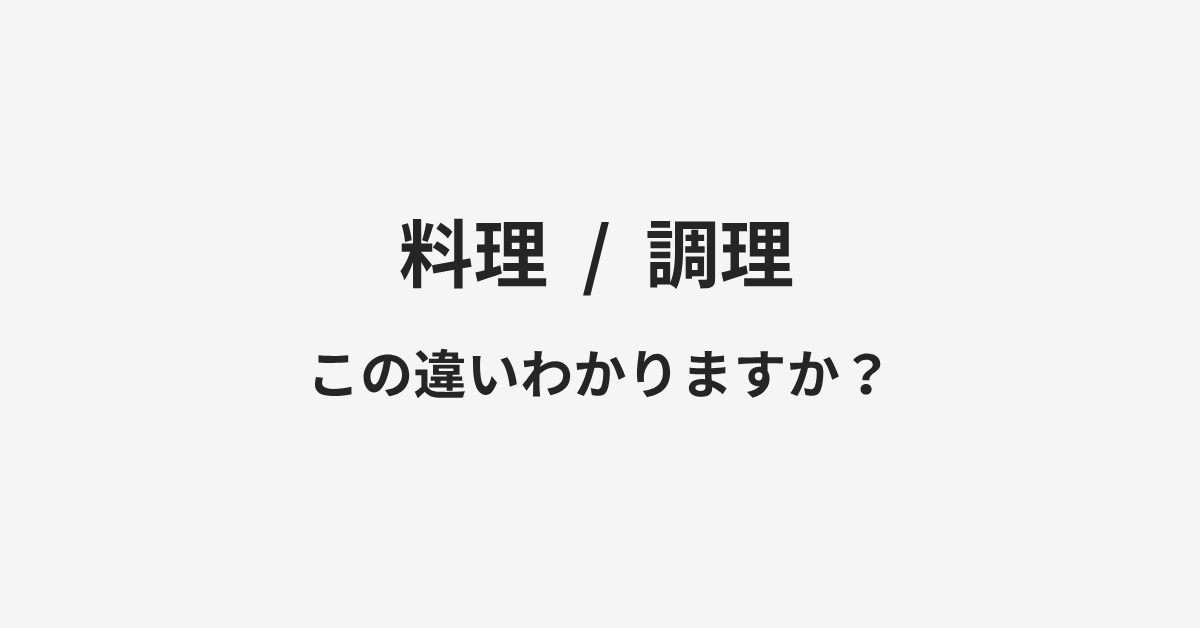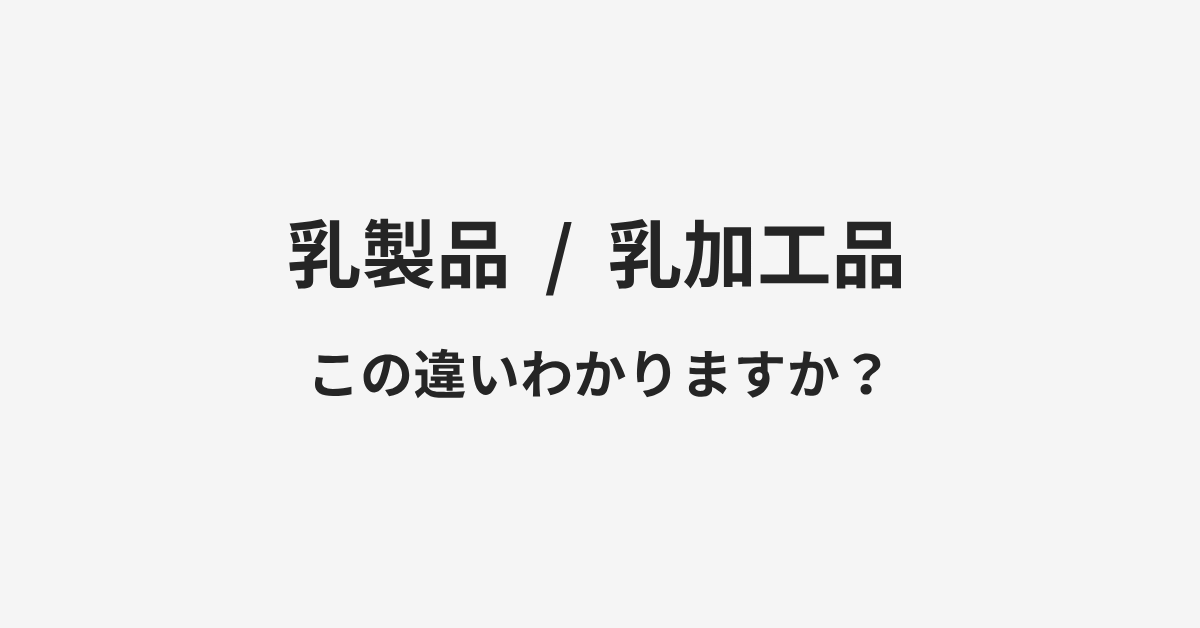【魚】と【魚類】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
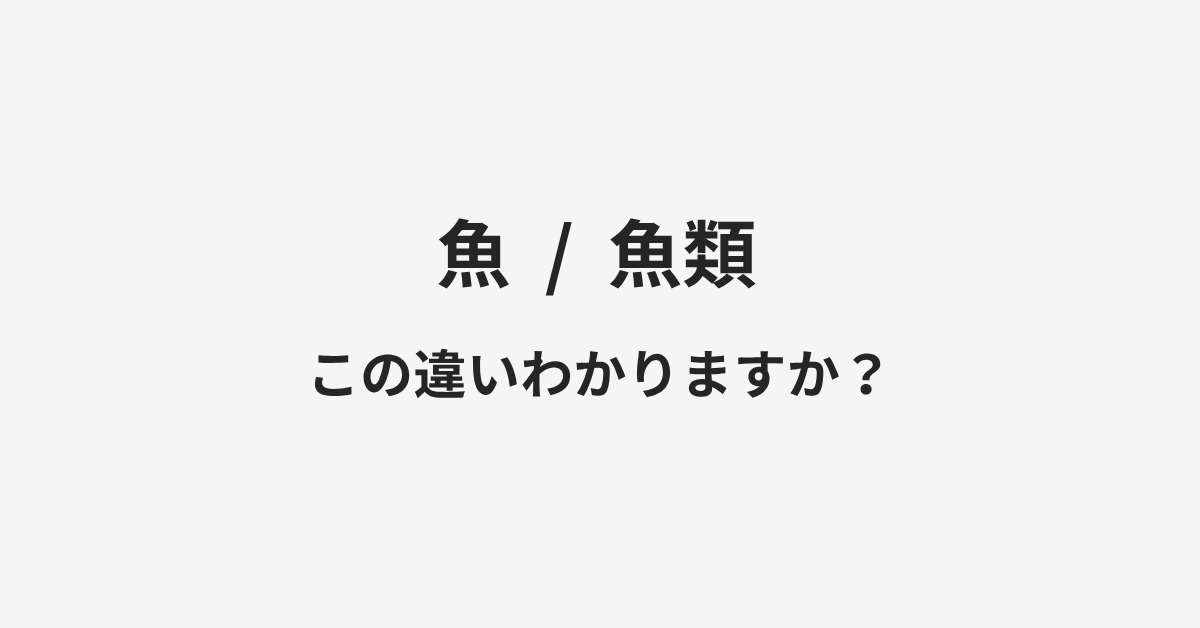
魚と魚類の分かりやすい違い
魚は、水中で暮らす脊椎動物で、食べ物として親しまれている一般的な呼び方です。
魚類は、魚を生物学的に分類した時の学術的な呼び方で、魚全体のグループを指します。
魚は個体・食材・日常語、魚類は分類群・学術語という違いがあります。
魚とは?
魚とは、水中に生息し、えらで呼吸し、ひれで泳ぐ脊椎動物の総称で、日本の食文化に欠かせない重要な食材です。魚を食べる、魚屋、魚料理など、日常的に最も使われる表現で、マグロ、サケ、サバ、タイなど、個々の種類や食材としての側面を強調する際に使用されます。
日本は海に囲まれた島国であり、魚は古来より重要なタンパク源として親しまれてきました。刺身、寿司、焼き魚、煮魚、干物など、多彩な調理法が発達し、季節ごとの旬の魚を楽しむ文化があります。DHA、EPA などの不飽和脂肪酸を豊富に含み、健康食材としても注目されています。
魚へんの漢字が多いことからも分かるように、日本人と魚の関係は深く、地域ごとに独特の魚食文化があります。近年では、資源管理や養殖技術の発展により、持続可能な魚食文化の構築が課題となっています。
魚の例文
- ( 1 ) 今日は新鮮な魚を買ってきました。
- ( 2 ) 魚をさばく技術を身につけたいです。
- ( 3 ) 子どもに魚の骨の取り方を教えています。
- ( 4 ) 旬の魚は、やはり美味しさが違います。
- ( 5 ) 魚中心の食生活で、健康的になりました。
- ( 6 ) 地元の魚を使った郷土料理が自慢です。
魚の会話例
魚類とは?
魚類とは、脊椎動物門の中で、主に水中で生活し、えら呼吸を行い、ひれを持つ動物群の生物学的分類名です。魚類図鑑、魚類学、魚類の進化など、学術的・専門的な文脈で使用され、分類学上は軟骨魚類と硬骨魚類に大別されます。魚類という用語は、個体ではなく集合的な概念を表し、魚類の生態、魚類資源、魚類相(その地域に生息する魚の種類構成)など、より包括的で科学的な議論の際に用いられます。
水産学、海洋生物学、環境科学などの分野では標準的な用語です。
食品表示や統計では魚類消費量、魚類加工品のように使われることもありますが、日常会話では堅い印象を与えるため、一般的には魚が好まれます。ただし、他の動物群と対比する際には哺乳類、鳥類、魚類のように使用されます。
魚類の例文
- ( 1 ) 魚類の栄養成分について研究しています。
- ( 2 ) 日本近海の魚類相は非常に豊富です。
- ( 3 ) 魚類資源の持続可能な利用が重要です。
- ( 4 ) 淡水魚類と海水魚類では、調理法が異なります。
- ( 5 ) 魚類アレルギーの方への配慮が必要です。
- ( 6 ) 魚類加工品の品質管理は厳格に行われています。
魚類の会話例
魚と魚類の違いまとめ
魚は個体や食材を指す日常語、魚類は生物学的分類を指す学術語という違いがあります。魚屋では新鮮な魚、研究論文では魚類の生態というように、日常と学術で明確に使い分けられます。
すべての魚は魚類に属しますが、魚類という言葉は個々の魚を指すのには適しません。
一般生活では魚で十分通じ、魚類は専門的な文脈での使用にとどまります。
魚と魚類の読み方
- 魚(ひらがな):さかな
- 魚(ローマ字):sakana
- 魚類(ひらがな):ぎょるい
- 魚類(ローマ字):gyorui