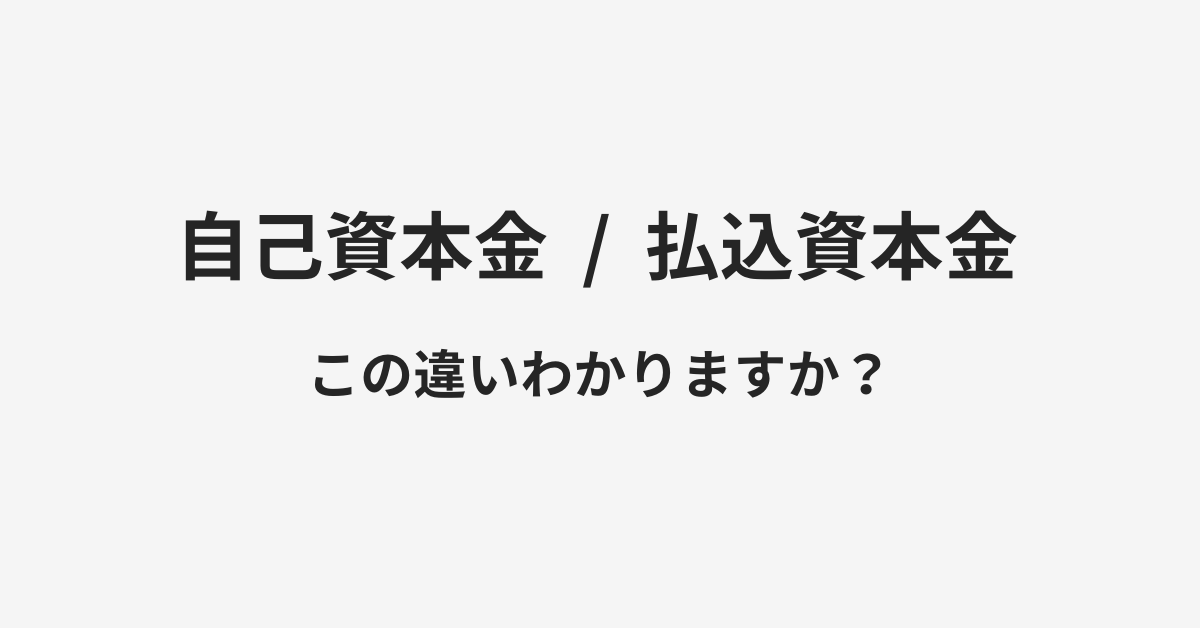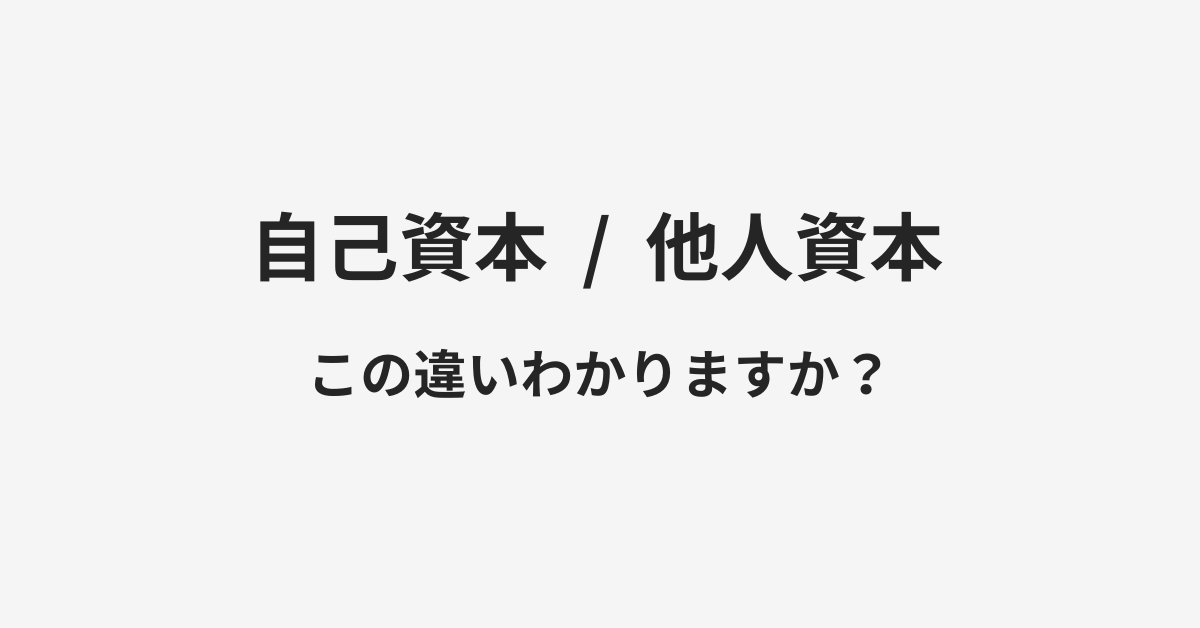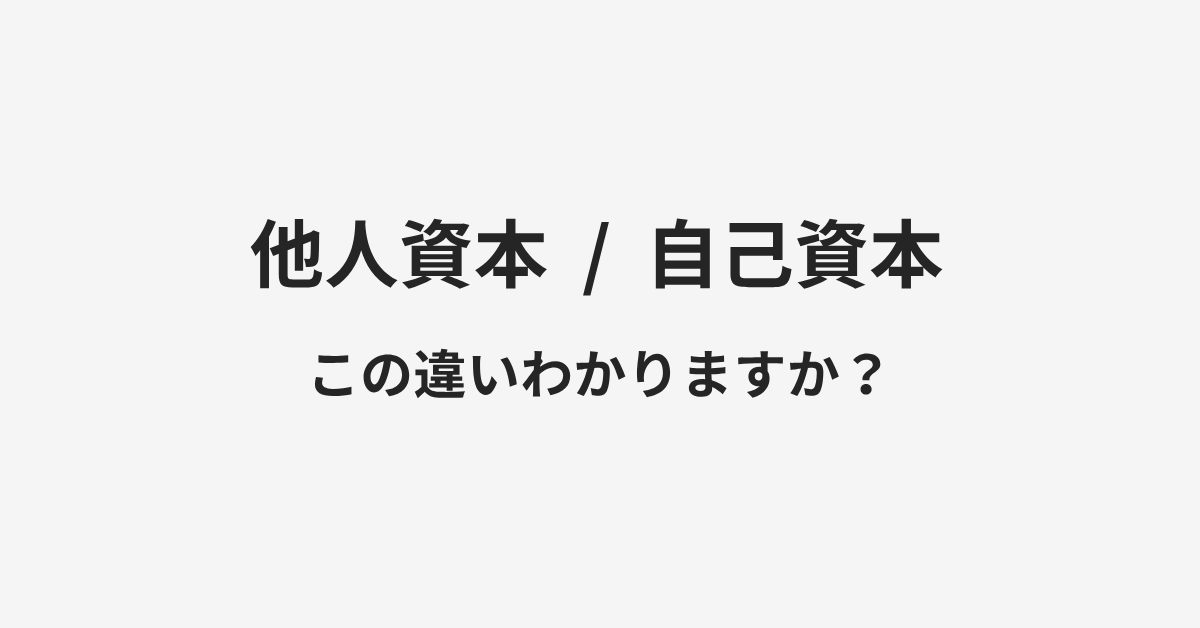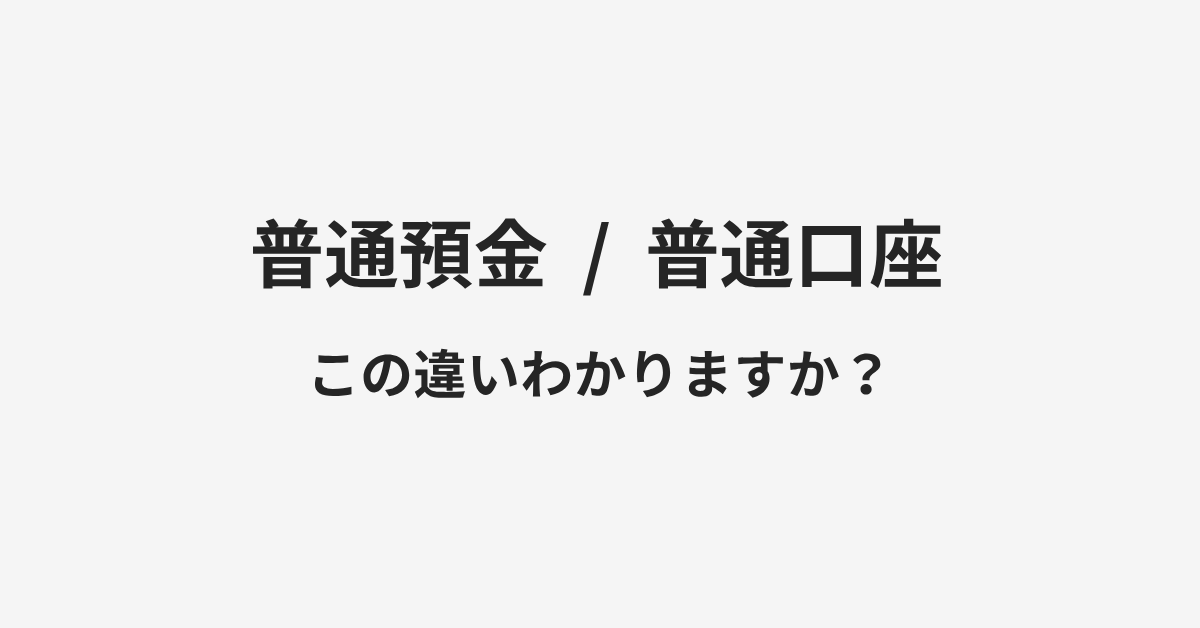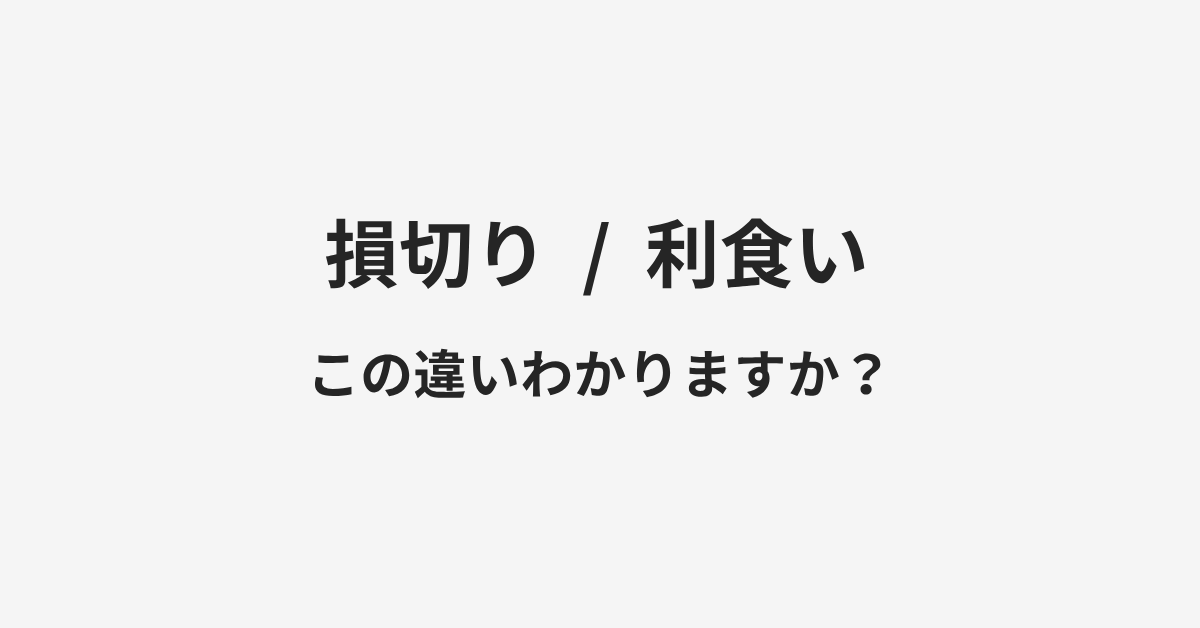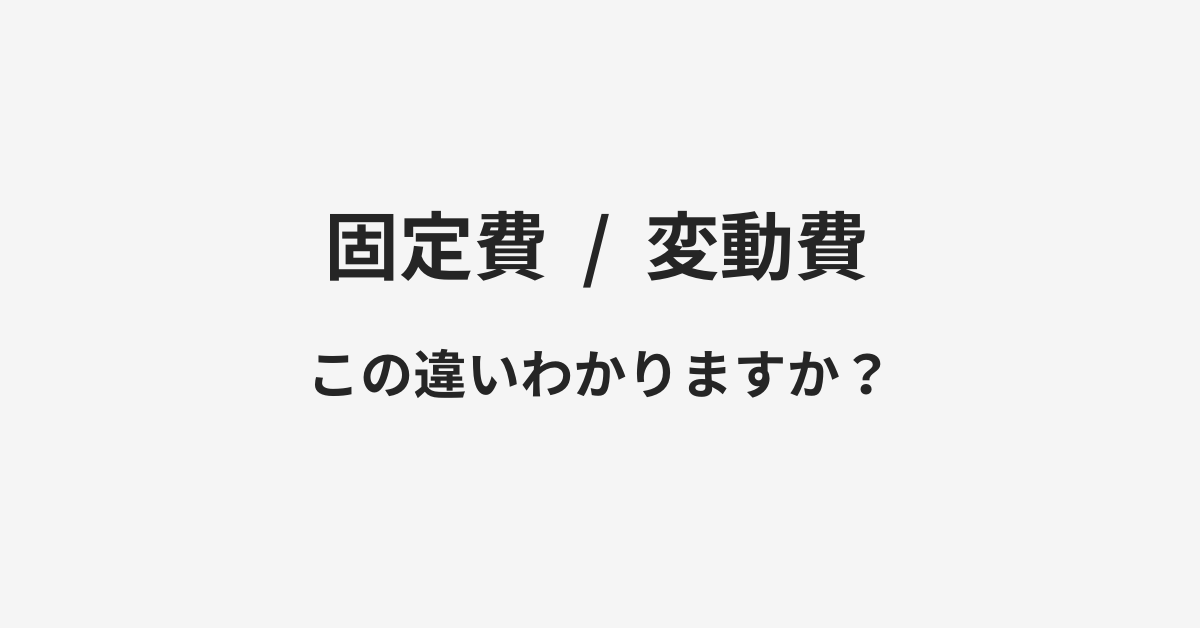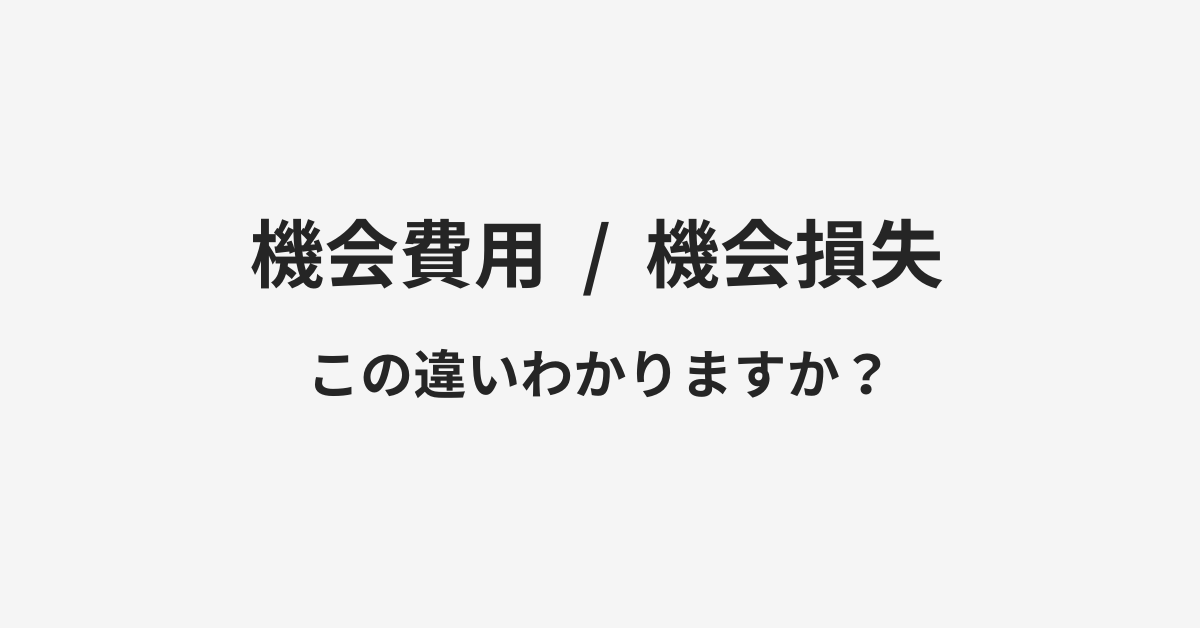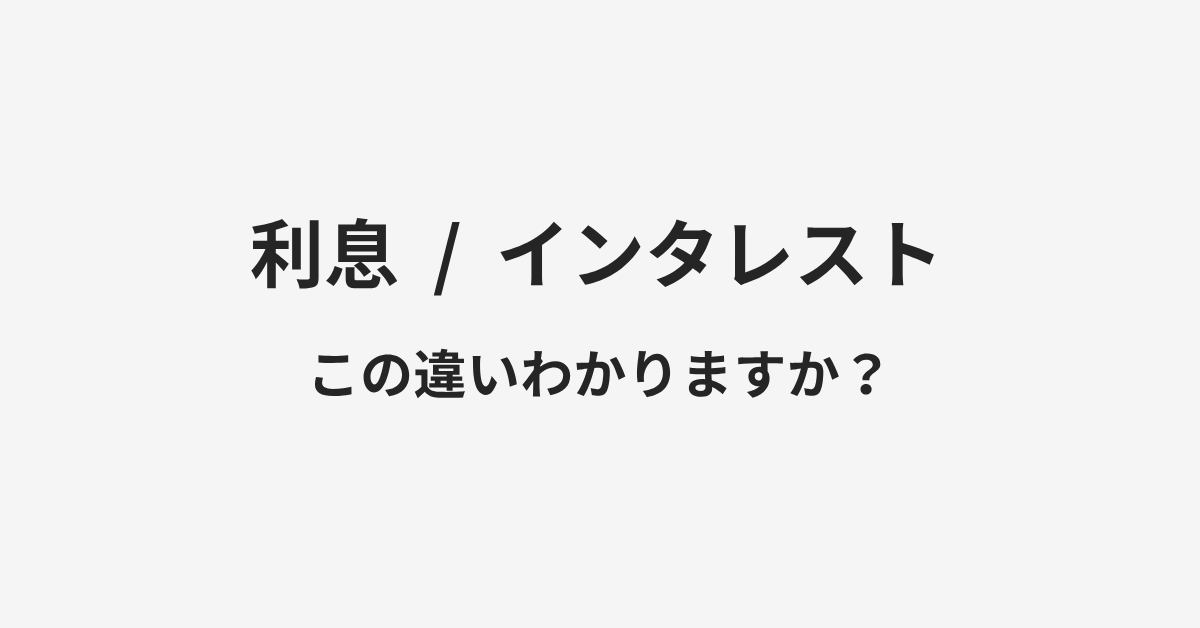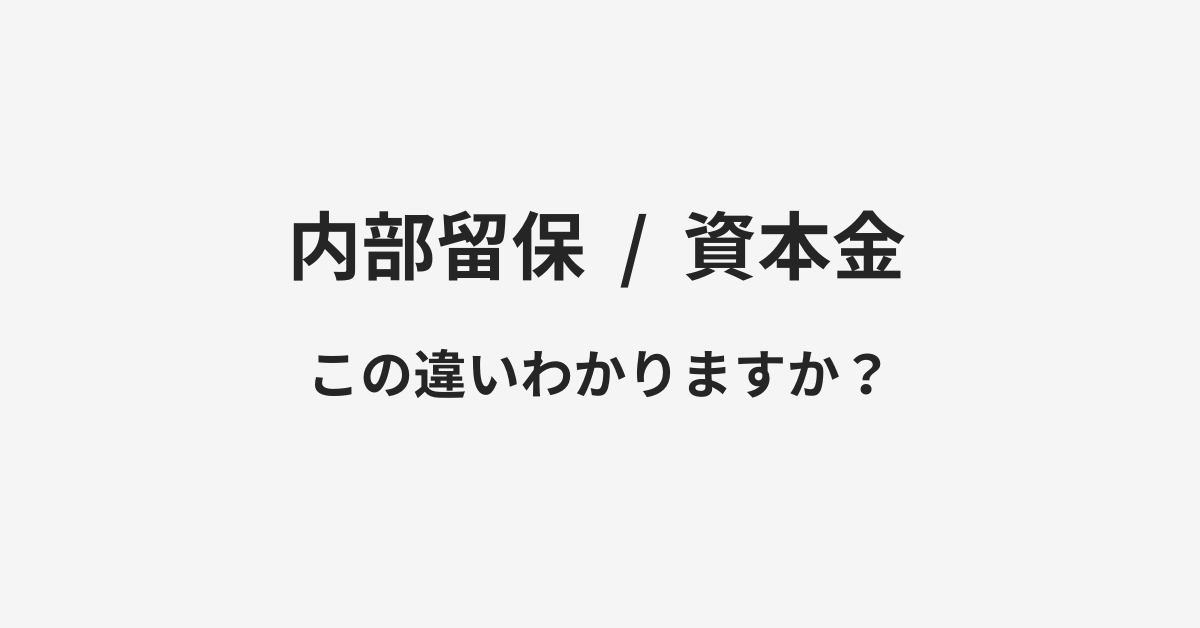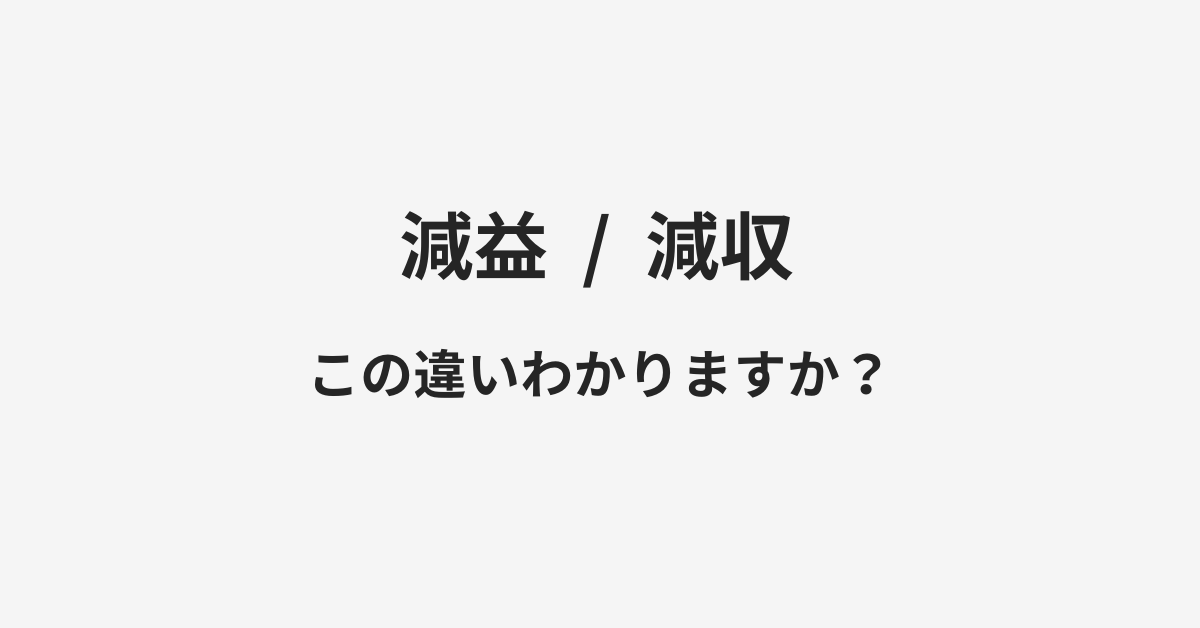【自己資本比率】と【株主資本比率】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
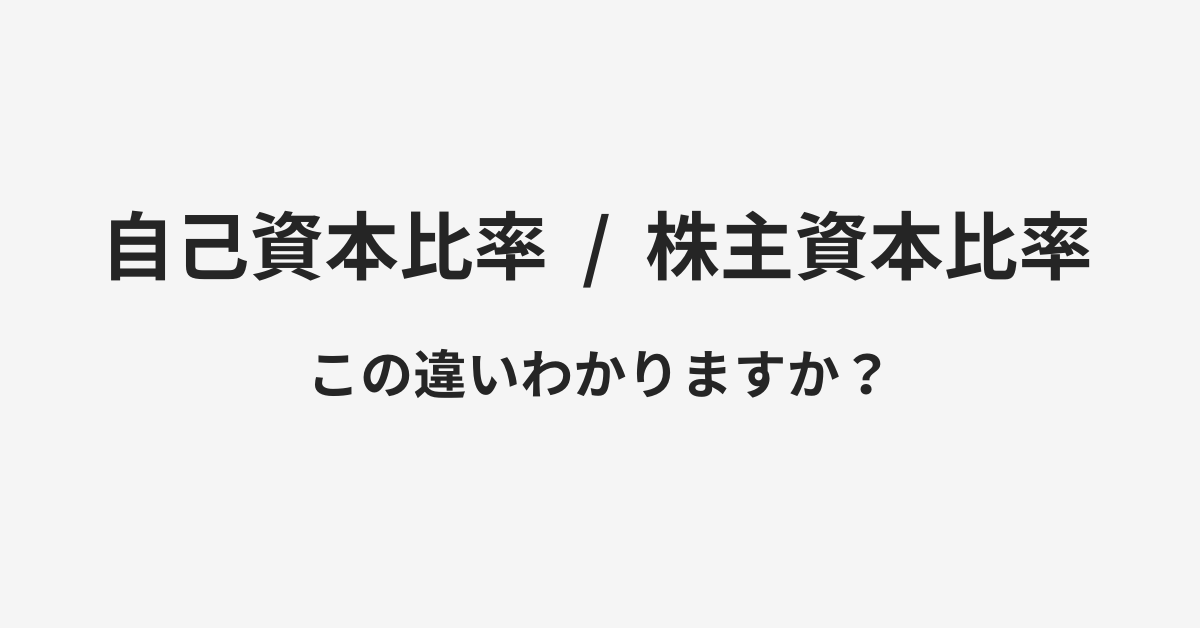
自己資本比率と株主資本比率の分かりやすい違い
自己資本比率と株主資本比率は、どちらも企業の財務健全性を示す指標ですが、計算に使う項目が異なります。
自己資本比率は純資産全体を使い、株主資本比率は株主に帰属する部分だけを使います。
一般的な財務分析では自己資本比率、より厳密な分析では株主資本比率を使用します。
自己資本比率とは?
自己資本比率とは、企業の総資産に占める純資産(自己資本)の割合を示す財務指標です。計算式は純資産÷総資産×100で表されます。純資産には、資本金、資本剰余金、利益剰余金に加えて、その他の包括利益累計額、新株予約権、非支配株主持分(旧少数株主持分)も含まれます。
企業の財務的な安定性や安全性を測る最も基本的な指標の一つです。自己資本比率が高いほど、借入金などの他人資本への依存度が低く、財務的に安定していると判断されます。一般的に30%以上あれば安全、50%以上なら優良企業とされます。ただし、業種によって適正水準は異なり、設備投資が多い製造業では低め、サービス業では高めになる傾向があります。
銀行融資の審査や投資判断では、必ず確認される指標です。自己資本比率の推移を見ることで、企業の成長性や経営の健全性を評価できます。急激な低下は、大型投資や業績悪化のサインである可能性があります。
自己資本比率の例文
- ( 1 ) 当社の自己資本比率は45%で、業界平均を上回る健全な水準を維持しています。
- ( 2 ) 自己資本比率を50%以上に高めるため、利益の内部留保を強化する方針です。
- ( 3 ) 買収により非支配株主持分が増加し、自己資本比率が3ポイント上昇しました。
- ( 4 ) 自己資本比率の改善により、銀行からの借入条件が有利になりました。
- ( 5 ) 四半期ごとに自己資本比率をモニタリングし、財務の健全性を確認しています。
- ( 6 ) 格付け機関は、自己資本比率を重要な評価項目の一つとしています。
自己資本比率の会話例
株主資本比率とは?
株主資本比率とは、企業の総資産に占める株主資本の割合を示す財務指標です。計算式は株主資本÷総資産×100で表されます。株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式(控除項目)で構成され、純粋に株主に帰属する部分のみを対象とします。新株予約権や非支配株主持分は含まれないため、自己資本比率よりも厳格な指標です。
株主資本比率は、株主の立場から見た企業の安全性を示します。この比率が高いほど、株主が拠出した資金と内部留保で事業を行っており、財務リスクが低いと評価されます。特に、親会社の株主にとって重要な指標で、連結財務諸表を分析する際に注目されます。
M&A(企業買収)や企業価値評価では、株主資本比率が重視されます。なぜなら、買収後に取得できる純粋な株主持分を示すからです。また、ROE(株主資本利益率)の計算にも使用され、株主資本の効率的な活用度を測る基礎となります。
株主資本比率の例文
- ( 1 ) 株主資本比率は42%で、純粋な株主持分による経営の安定性を示しています。
- ( 2 ) 新株予約権を除いた株主資本比率で見ると、より保守的な財務体質が分かります。
- ( 3 ) 連結ベースの株主資本比率を分析すると、グループ全体の財務構造が明確になります。
- ( 4 ) 株主資本比率の向上は、ROEとのバランスを考慮しながら進める必要があります。
- ( 5 ) 競合他社と株主資本比率を比較し、資本政策の見直しを検討しています。
- ( 6 ) 株主資本比率が高すぎると、レバレッジ効果を活用できていない可能性があります。
株主資本比率の会話例
自己資本比率と株主資本比率の違いまとめ
自己資本比率と株主資本比率は、どちらも企業の安全性を示す指標ですが、含まれる項目に違いがあります。自己資本比率の方が広い概念で、株主資本比率はより厳密な指標です。
一般的な信用調査では自己資本比率、株主向けの分析では株主資本比率が重視されます。
財務分析を行う際は、両方の指標を確認し、その差異から企業の資本構成の特徴を読み取ることが重要です。
自己資本比率と株主資本比率の読み方
- 自己資本比率(ひらがな):かぶぬししほんひりつ
- 自己資本比率(ローマ字):kabunushishihonnhiritsu