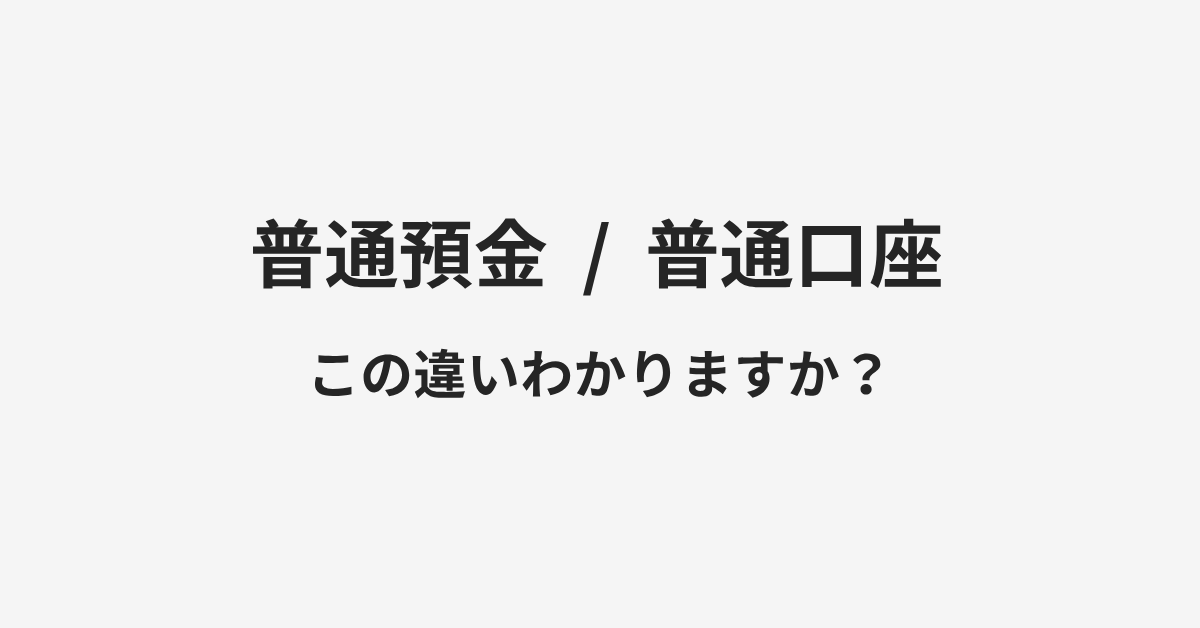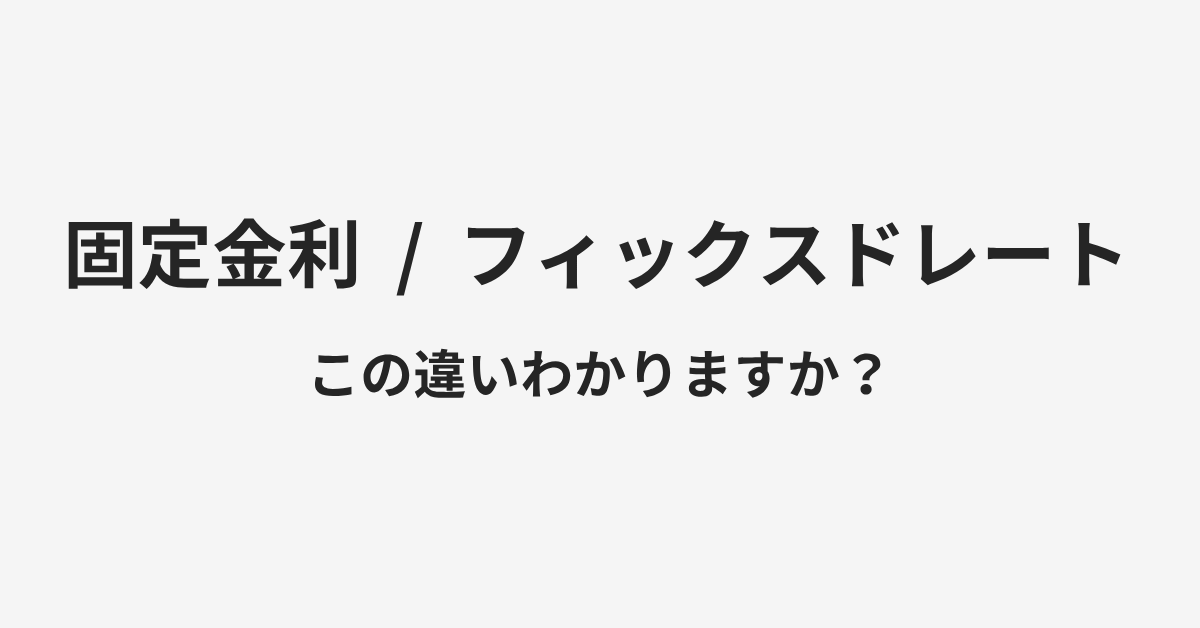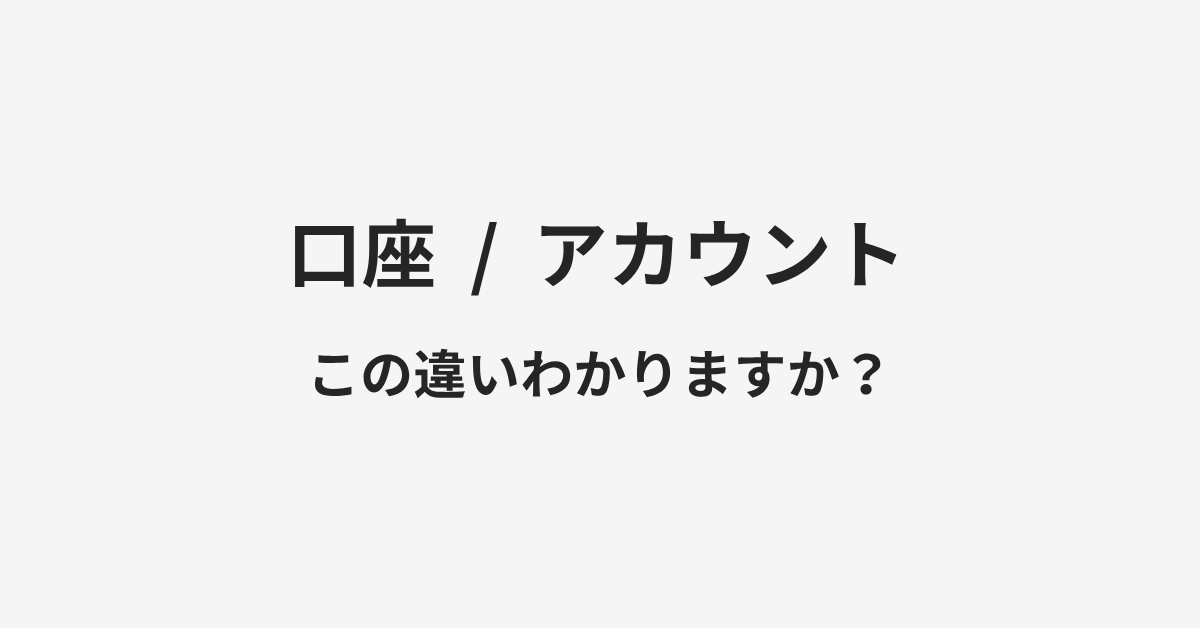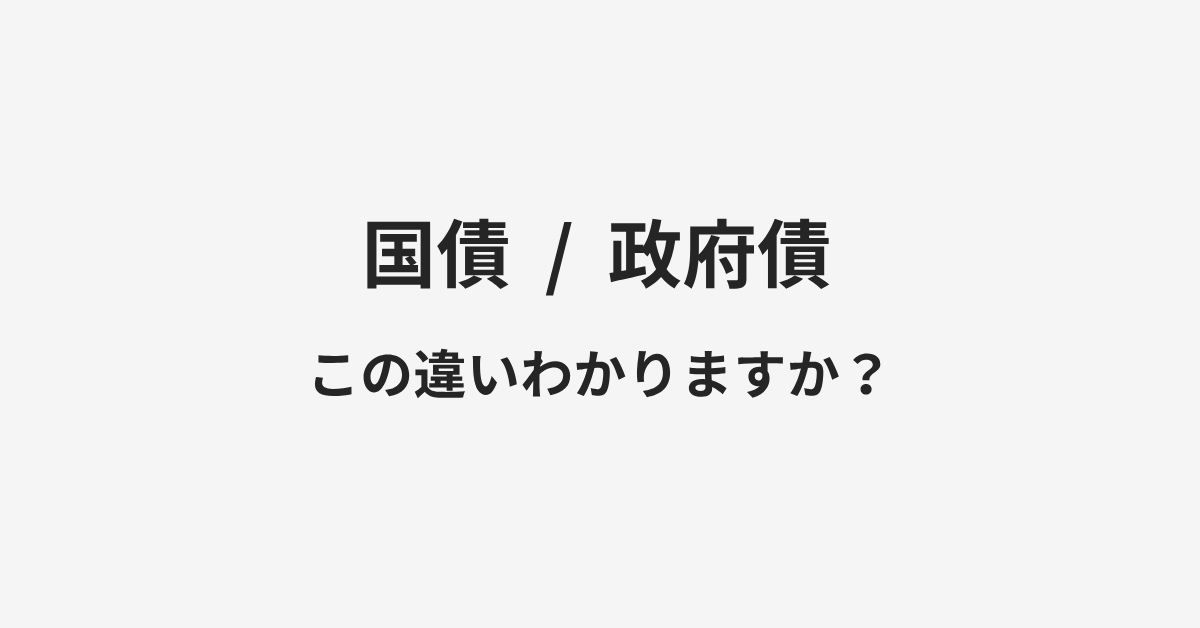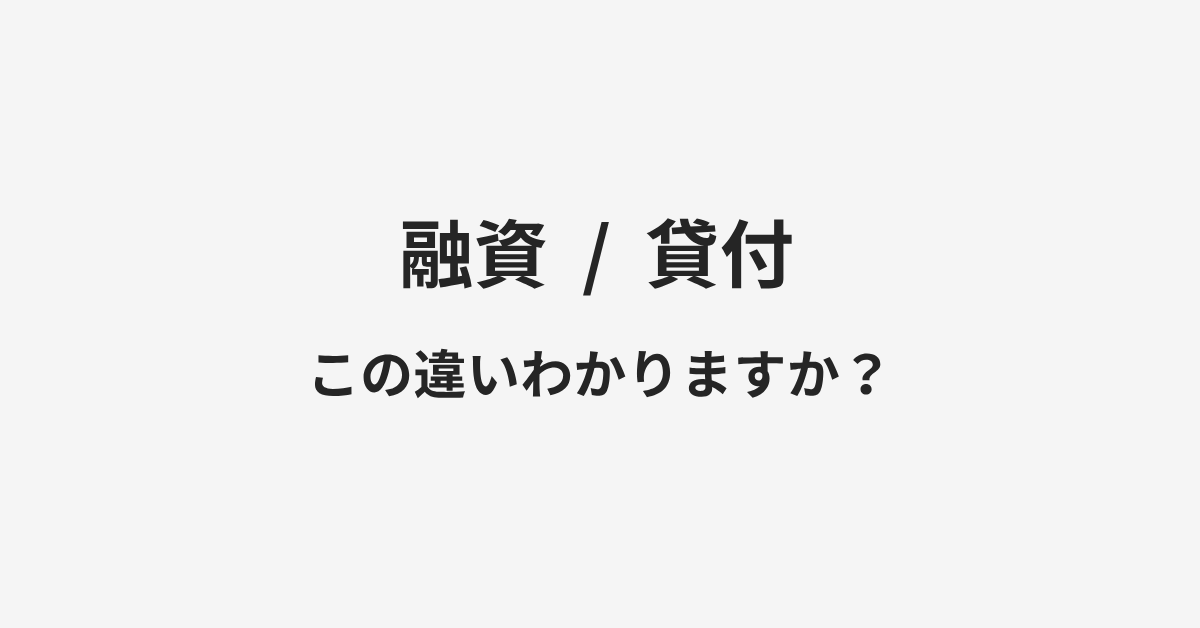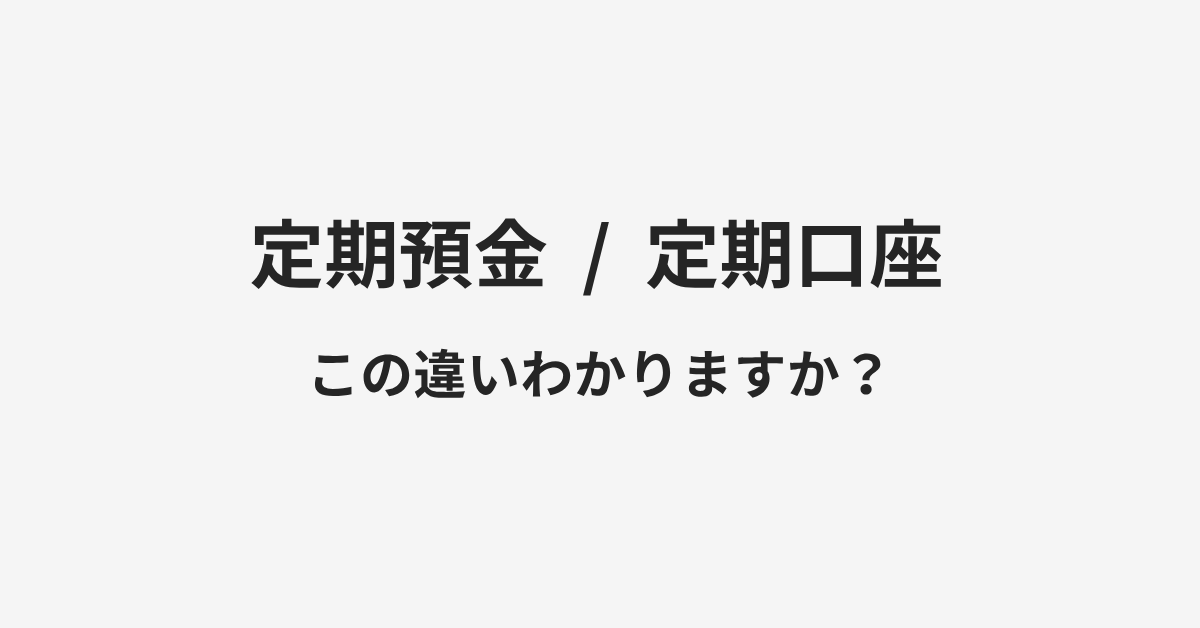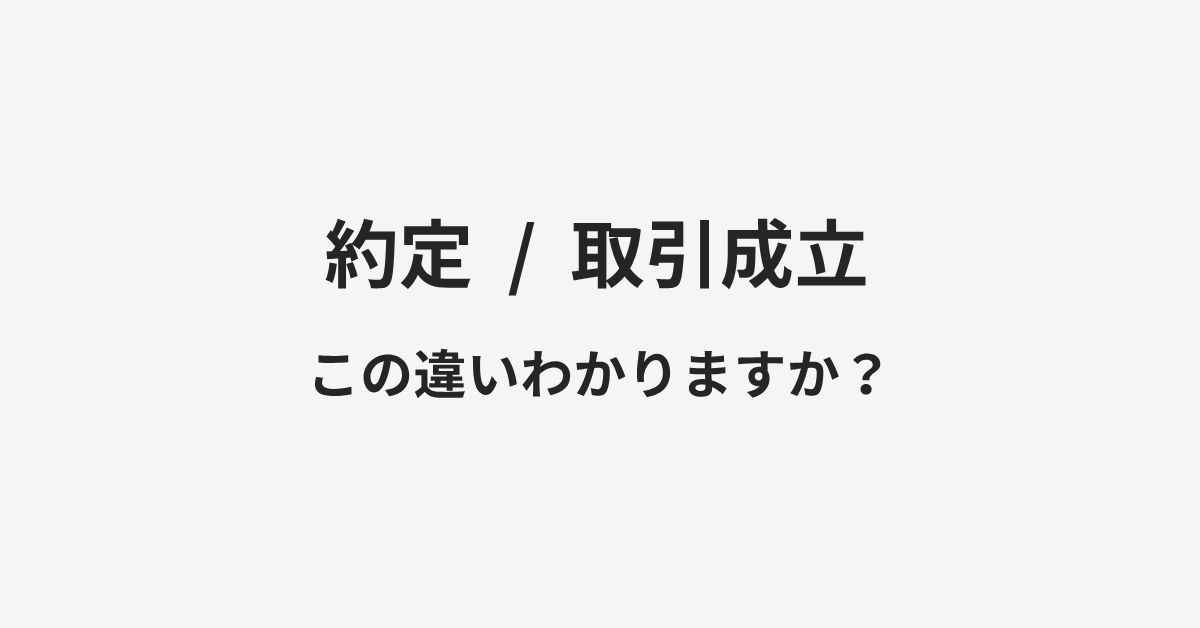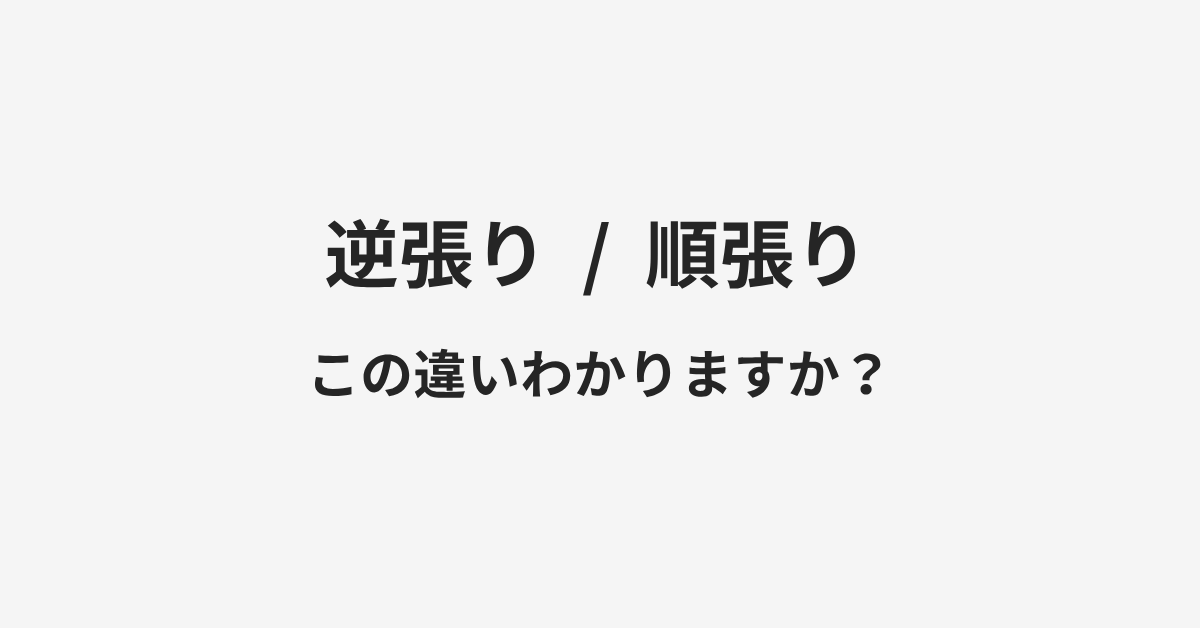【量的緩和】と【金融緩和】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
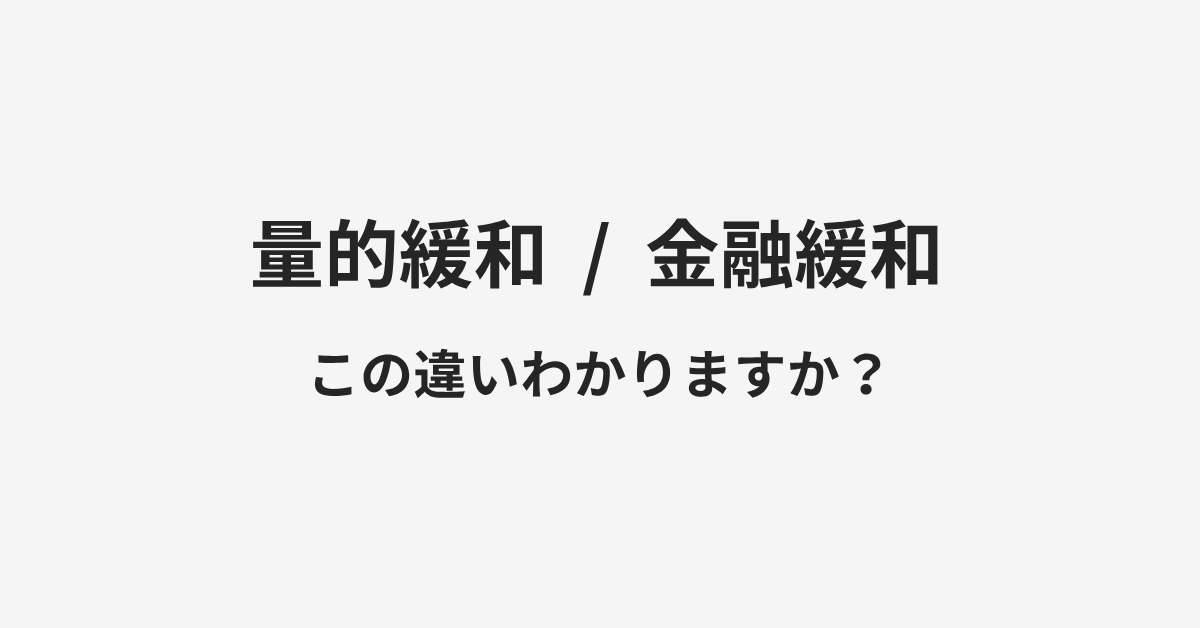
量的緩和と金融緩和の分かりやすい違い
量的緩和と金融緩和は、中央銀行が景気刺激のために行う政策ですが、範囲と手法に違いがあります。金融緩和は金利引き下げや資金供給増加など景気刺激策の総称で、量的緩和は金利がゼロ近辺でも実施できる、国債等の大量購入による特殊な緩和手法です。
金融業界では、中央銀行の政策動向が金利、為替、株価に大きな影響を与えるため、両政策の違いと効果を理解することが投資判断に不可欠です。
量的緩和とは?
量的緩和QE:Quantitative Easingとは、中央銀行が国債や社債などを大量に購入することで、市場に直接資金を供給する非伝統的な金融政策です。政策金利がゼロ近辺でも実施可能な点が特徴です。
日本銀行は2001年に世界で初めて量的緩和を導入し、リーマンショック後は米国FRBや欧州ECBも採用しました。中央銀行のバランスシート資産規模が大幅に拡大することから、異次元緩和とも呼ばれます。
量的緩和により長期金利が低下し、資産価格上昇や円安効果が期待されますが、過度な緩和は将来のインフレリスクや金融市場の歪みを生む可能性もあります。
量的緩和の例文
- ( 1 ) 日銀の量的緩和により、長期金利がマイナス圏で推移しています。
- ( 2 ) 量的緩和の規模縮小観測で、債券市場が動揺しています。
- ( 3 ) ETF購入も量的緩和の一環として実施されています。
- ( 4 ) 量的緩和の副作用として、金融機関の収益悪化が懸念されます。
- ( 5 ) 量的緩和の出口戦略が、市場の最大の関心事です。
- ( 6 ) 各国の量的緩和競争が、為替相場を不安定にしています。
量的緩和の会話例
金融緩和とは?
金融緩和とは、中央銀行が景気を刺激し物価安定を図るために、金融環境を緩和的にする政策の総称です。政策金利の引き下げ、預金準備率の引き下げ、公開市場操作による資金供給などが含まれます。
伝統的な金融緩和は金利操作が中心でしたが、ゼロ金利制約に直面すると、量的緩和やフォワードガイダンス将来の政策方針の明示など非伝統的手法も用いられます。
金融緩和は企業の資金調達コストを下げ、設備投資や消費を促進しますが、過度な緩和は資産バブルや通貨安競争を招く恐れもあり、適切な出口戦略が重要です。
金融緩和の例文
- ( 1 ) FRBの金融緩和により、米国株が史上最高値を更新しました。
- ( 2 ) 金融緩和の長期化で、資産バブルの懸念が高まっています。
- ( 3 ) 金融緩和から引き締めへの転換時期が注目されています。
- ( 4 ) 新興国は先進国の金融緩和の影響を大きく受けます。
- ( 5 ) 金融緩和により企業の資金調達環境が改善しました。
- ( 6 ) 過度な金融緩和は、将来の政策余地を狭める恐れがあります。
金融緩和の会話例
量的緩和と金融緩和の違いまとめ
量的緩和と金融緩和の関係は、具体的手法と総合概念の違いです。金融緩和という大きな枠組みの中に、伝統的な金利操作と非伝統的な量的緩和が含まれます。
量的緩和は、通常の金利政策が限界に達した際の特別な手段で、より直接的で大規模な市場介入を伴います。投資実務では、金融緩和局面では株式や不動産など リスク資産への投資が有利になりやすく、政策変更の兆候を早期に察知することが、ポートフォリオ管理の鍵となります。
量的緩和と金融緩和の読み方
- 量的緩和(ひらがな):りょうてきかんわ
- 量的緩和(ローマ字):ryoutekikannwa
- 金融緩和(ひらがな):きんゆうかんわ
- 金融緩和(ローマ字):kinnyuukannwa