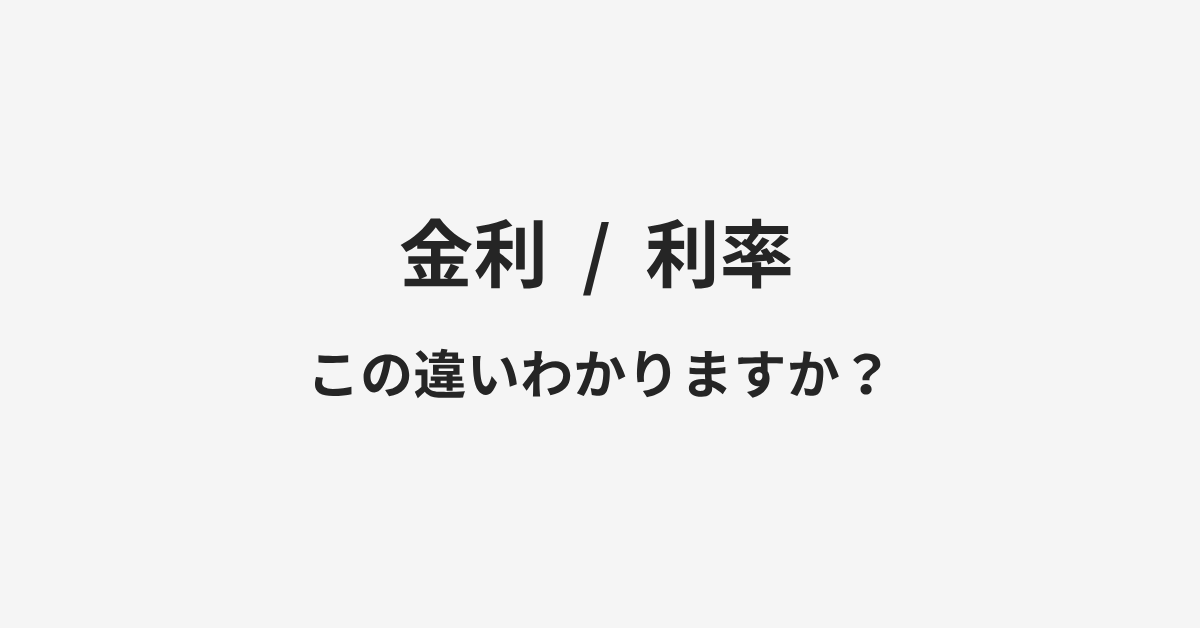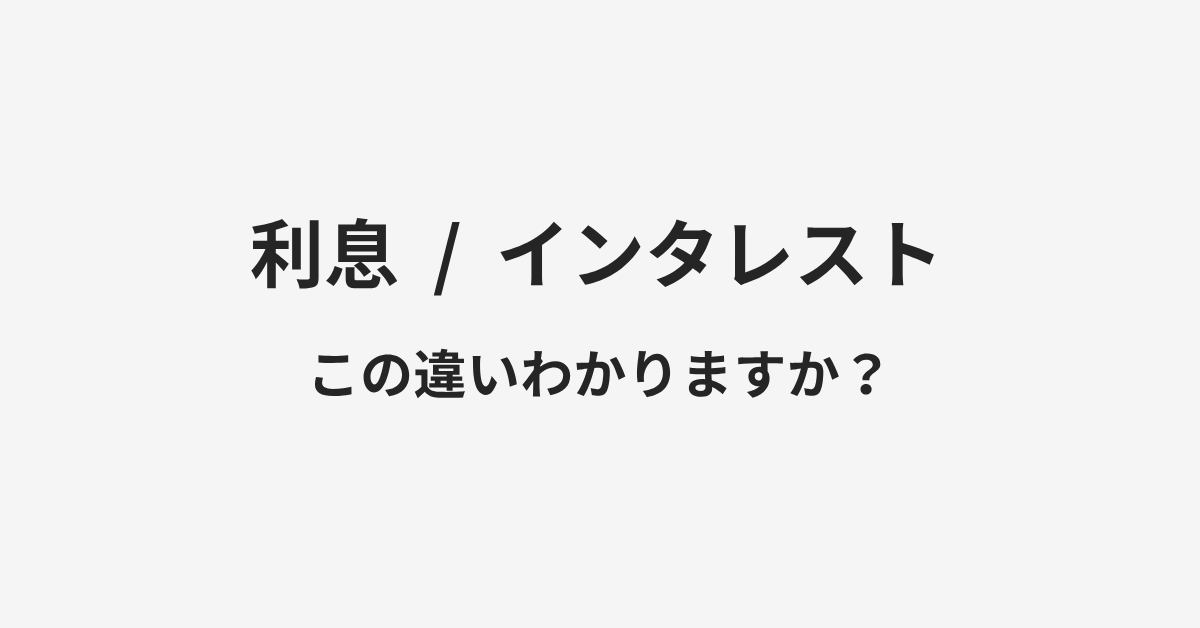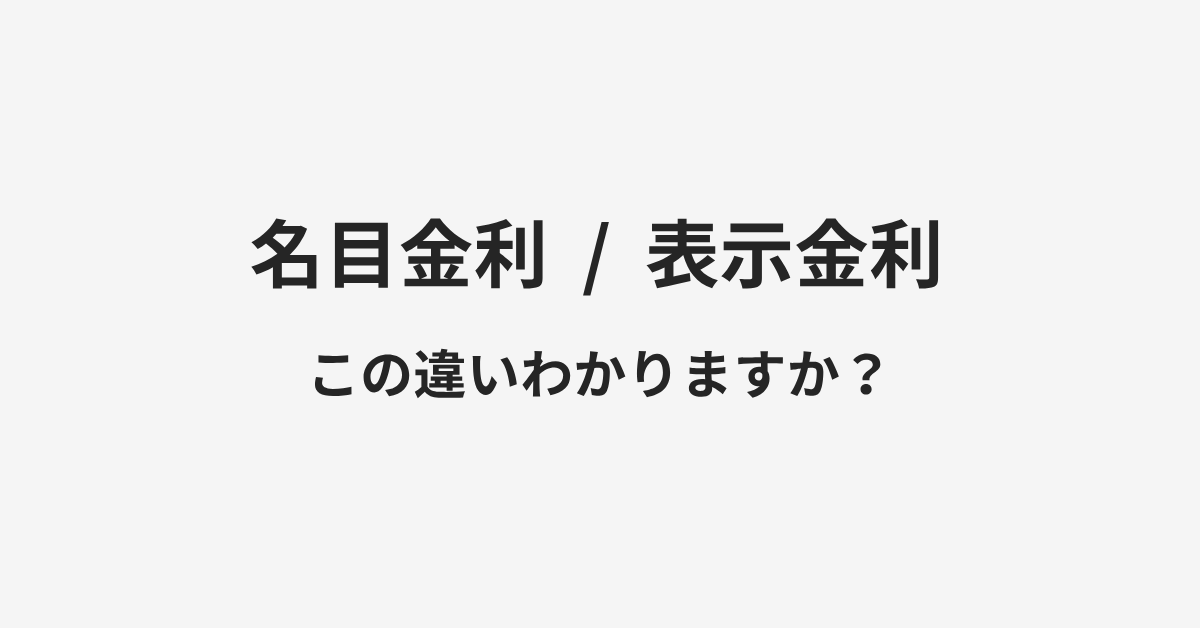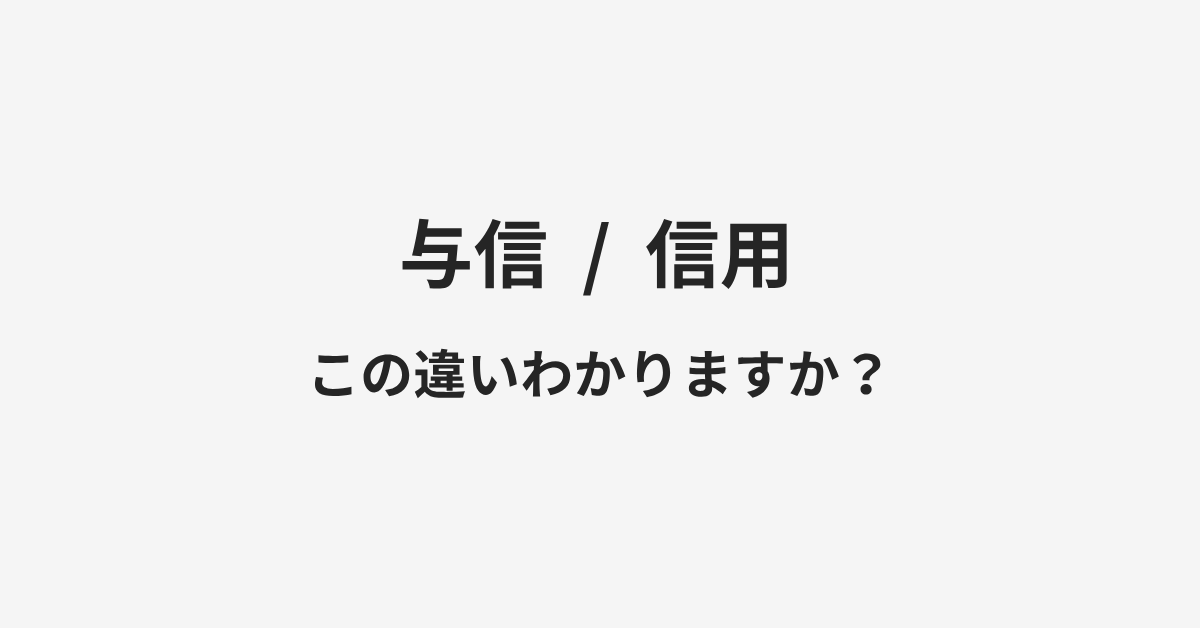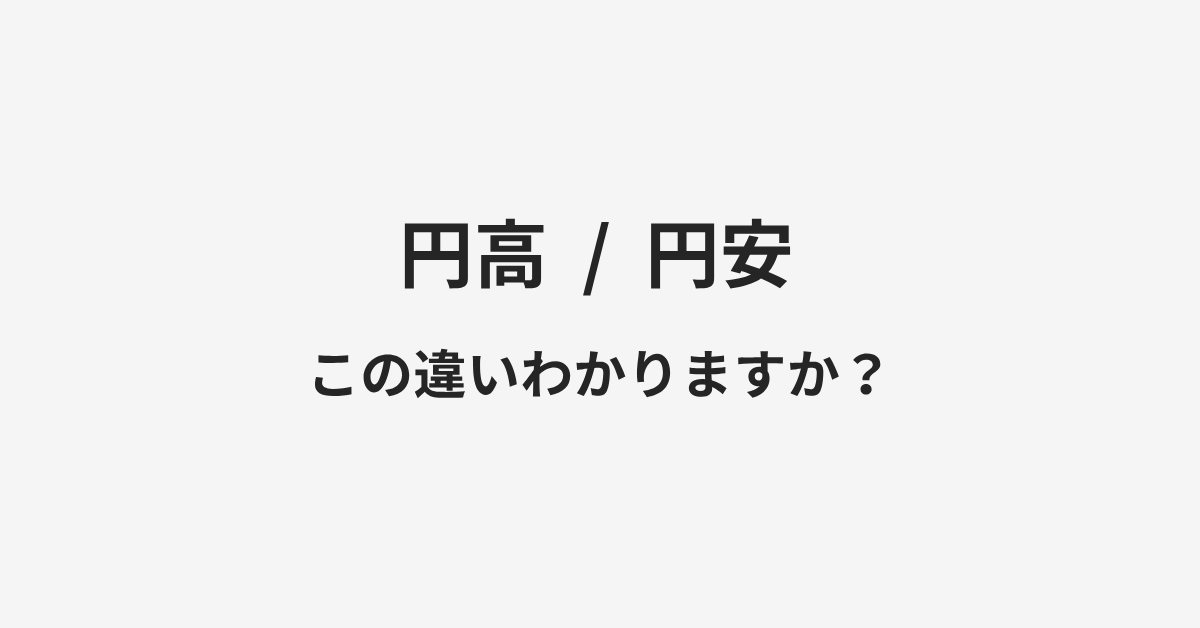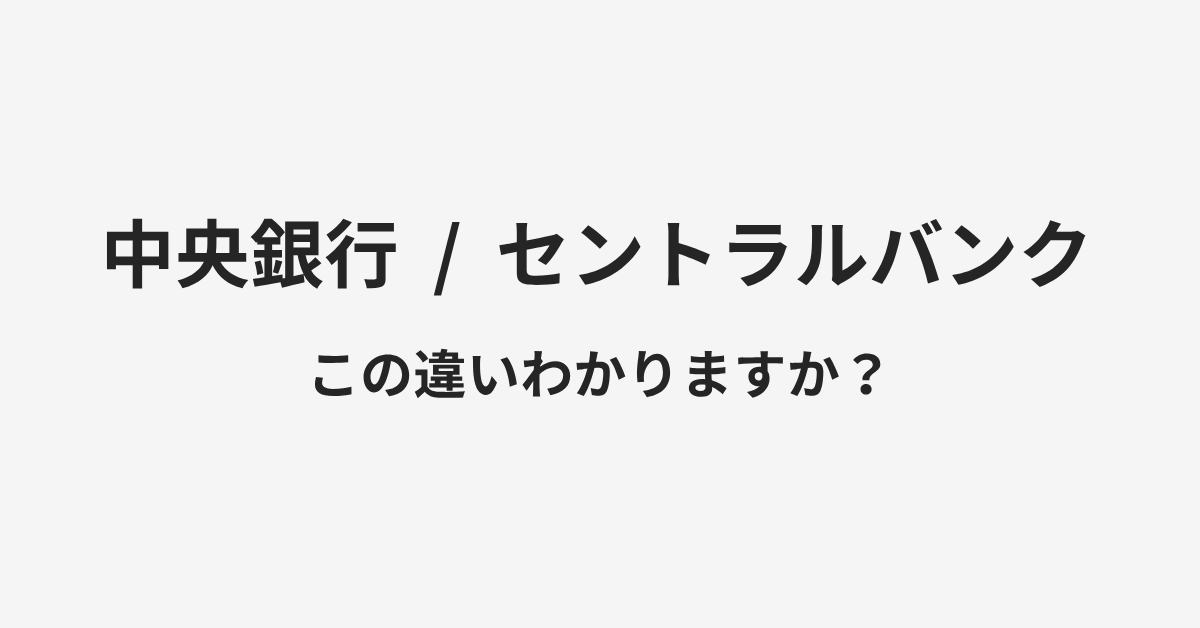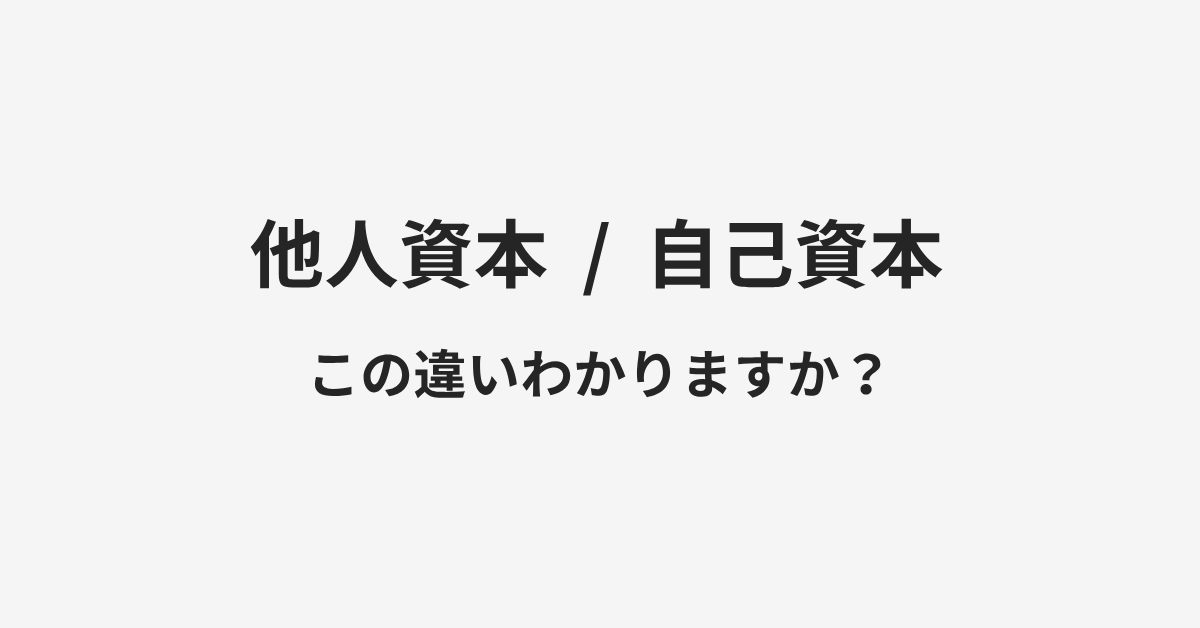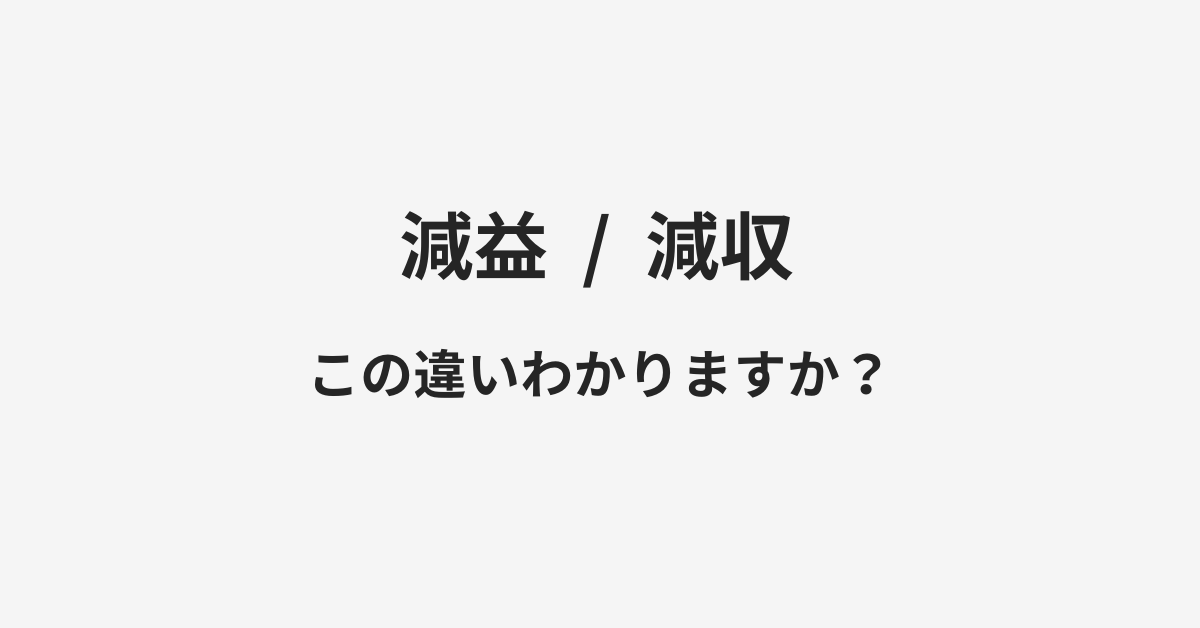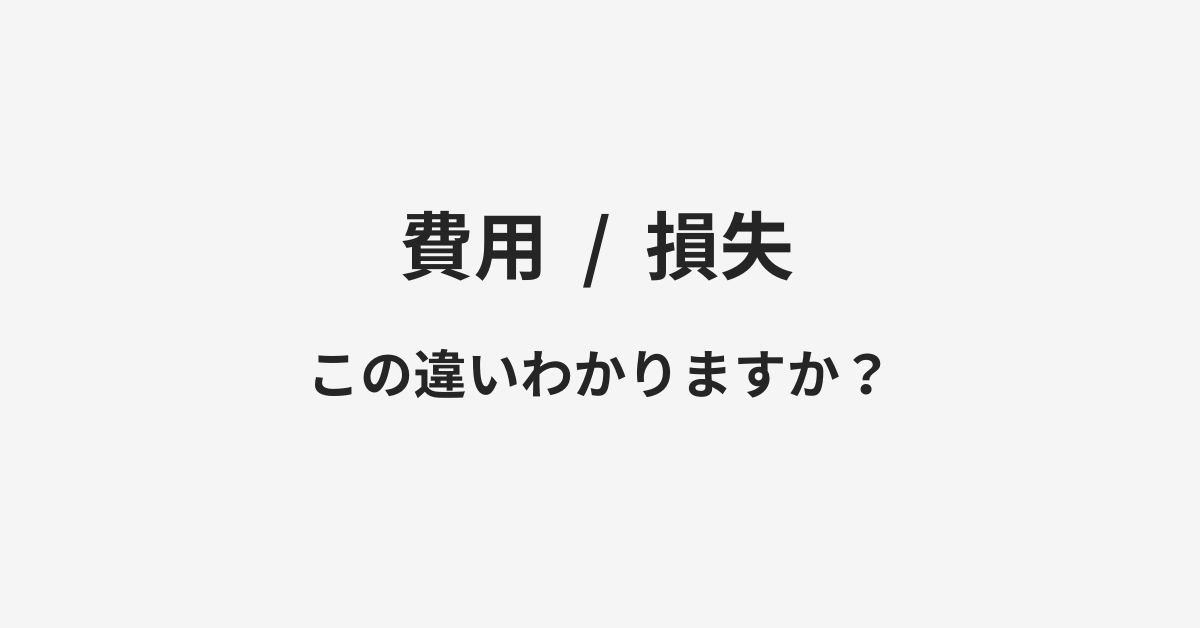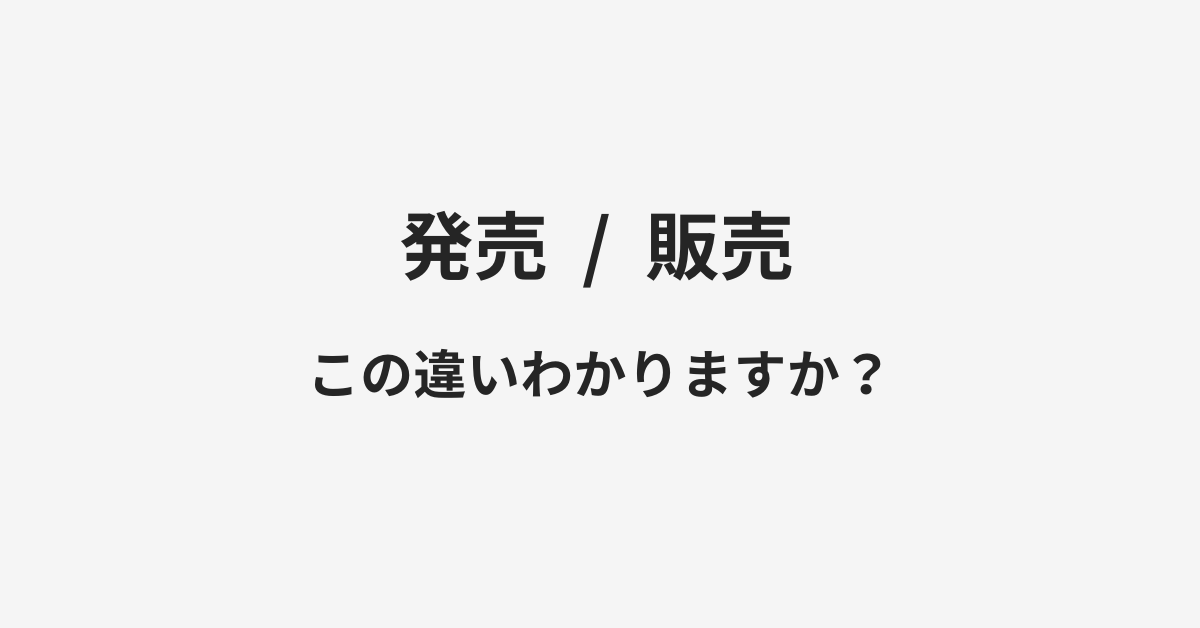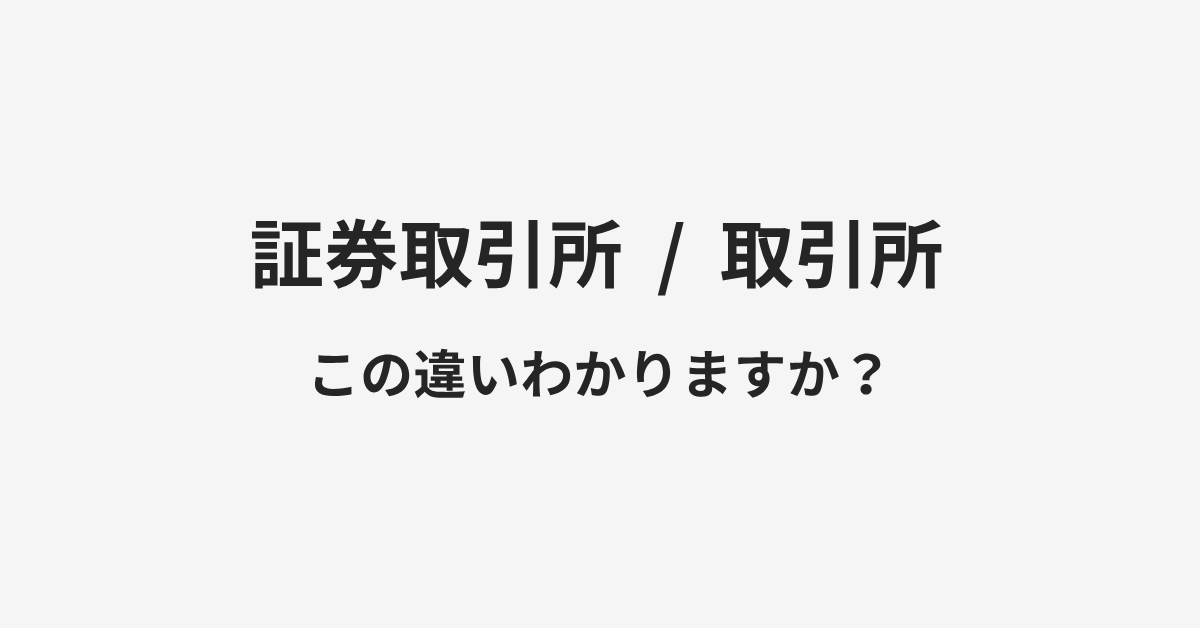【利息】と【受取利息】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
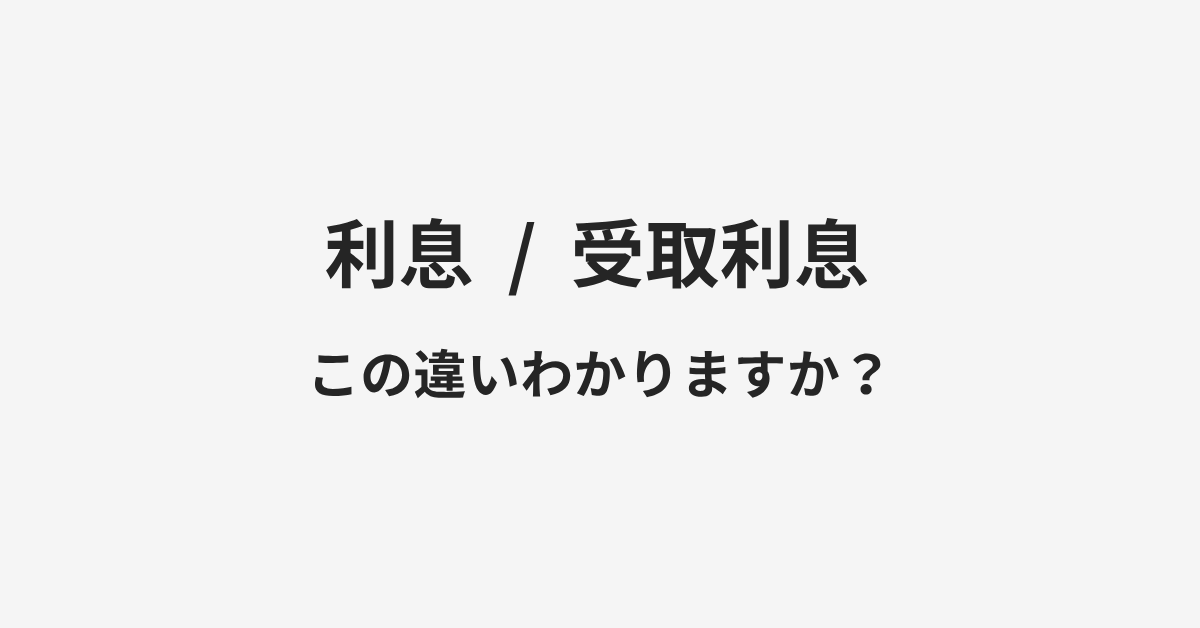
利息と受取利息の分かりやすい違い
利息と受取利息は、お金の貸し借りに関わる重要な金融用語です。利息はお金を貸した人が受け取る、または借りた人が支払うお金の使用料のことです。
利息は支払う側と受け取る側の両方を含む一般的な言葉ですが、受取利息は文字通り受け取る利息だけを指します。
企業の経理では、受取利息は収益として、支払利息は費用として、それぞれ別の勘定科目で管理されます。
利息とは?
利息とは、お金を貸し借りする際に発生する対価のことです。銀行にお金を預けると利息がもらえ、お金を借りると利息を支払います。元本最初に預けたり借りたりした金額に対する割合で計算されます。
利息の計算方法には、単利元本だけに利息がつくと複利利息にも利息がつくがあります。日本の預金は主に単利ですが、住宅ローンなどは複利計算が一般的です。
ビジネスでは、利息は資金調達コストや運用収益として重要な要素です。企業は支払利息を削減し、受取利息を増やすことで、財務体質の改善を図ります。
利息の例文
- ( 1 ) 住宅ローンの利息は、借入残高に応じて毎月計算されます。
- ( 2 ) 定期預金の利息は、満期時に元本と一緒に支払われます。
- ( 3 ) 延滞した場合は、通常の利息に加えて遅延損害金が発生します。
- ( 4 ) クレジットカードのリボ払いには、年率15%程度の利息がかかります。
- ( 5 ) 利息制限法により、貸付金利には上限が設定されています。
- ( 6 ) 複利計算では、利息が利息を生む効果で資産が増えていきます。
利息の会話例
受取利息とは?
受取利息とは、預金、貸付金、債券などから受け取る利息のことです。会計上は営業外収益本業以外の収益として計上され、企業の収益性を高める要素となります。個人の場合、銀行預金の利息が代表例です。
法人では、余剰資金の運用による利息収入や、取引先への貸付金から得る利息などが該当します。税務上は、20.315%の源泉徴収税金の天引きが行われます。
金融機関にとって受取利息は主要な収益源です。預金として集めた資金を企業や個人に貸し出し、その金利差利ざやで収益を得るビジネスモデルの中核を担っています。
受取利息の例文
- ( 1 ) 当社の前期受取利息は、定期預金の運用により500万円となりました。
- ( 2 ) 受取利息は営業外収益として、損益計算書に計上されます。
- ( 3 ) 取引先への貸付金から、年間200万円の受取利息を得ています。
- ( 4 ) 銀行預金の受取利息には、20.315%の源泉徴収税が課されます。
- ( 5 ) 受取利息の増加は、企業の資金運用効率の改善を示しています。
- ( 6 ) 連結決算では、グループ会社間の受取利息は相殺消去されます。
受取利息の会話例
利息と受取利息の違いまとめ
利息は金融取引の基本概念で、受取利息はその中でも受け取る側に焦点を当てた用語です。企業会計では、受取利息と支払利息を明確に区別して管理することが重要です。
低金利時代の現在、受取利息による収入は限定的ですが、企業の資金効率を測る指標の一つとして注目されています。余剰資金の運用方法次第で、受取利息を増やすことも可能です。
個人・法人を問わず、利息の仕組みを理解することは、賢明な資金管理の第一歩といえるでしょう。
利息と受取利息の読み方
- 利息(ひらがな):りそく
- 利息(ローマ字):risoku
- 受取利息(ひらがな):うけとりりそく
- 受取利息(ローマ字):uketoririsoku