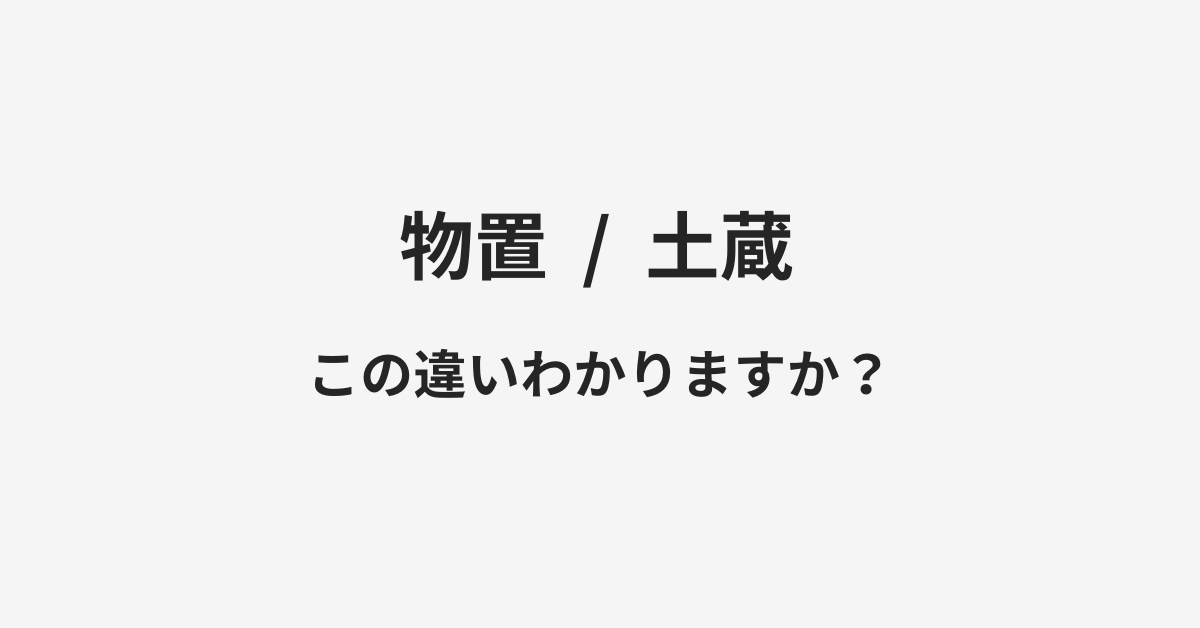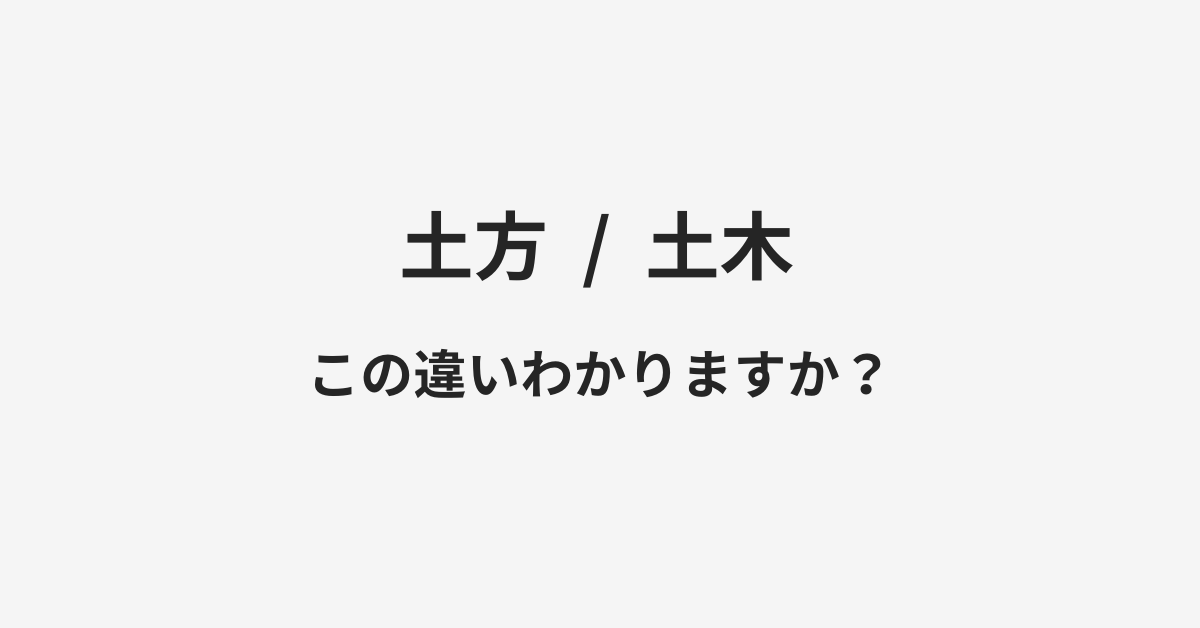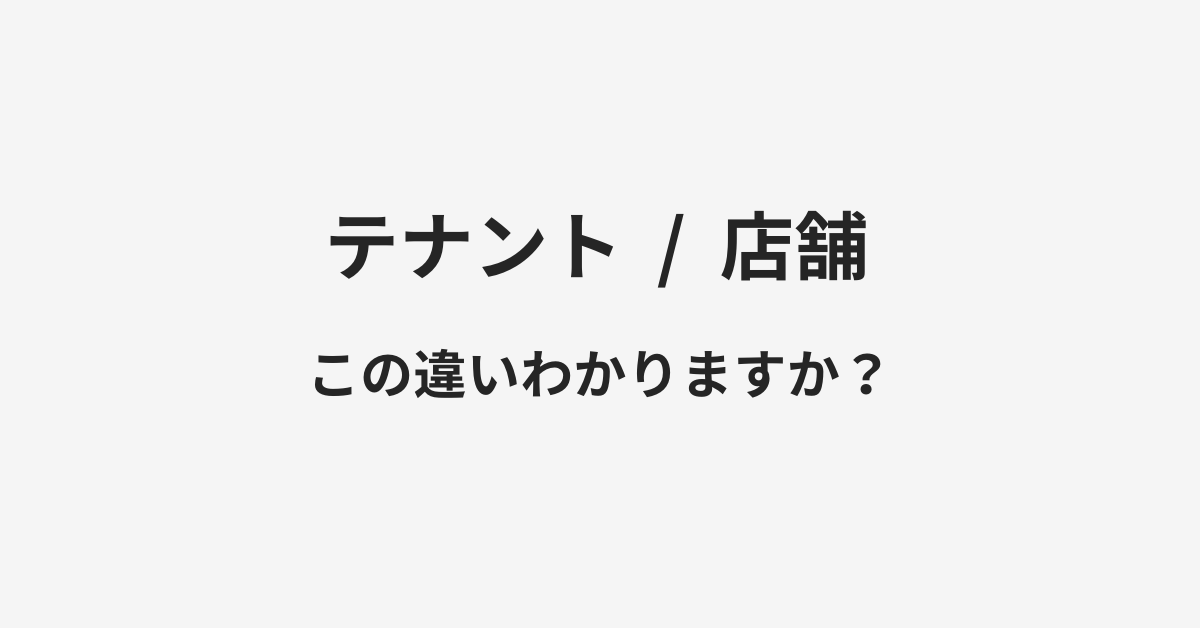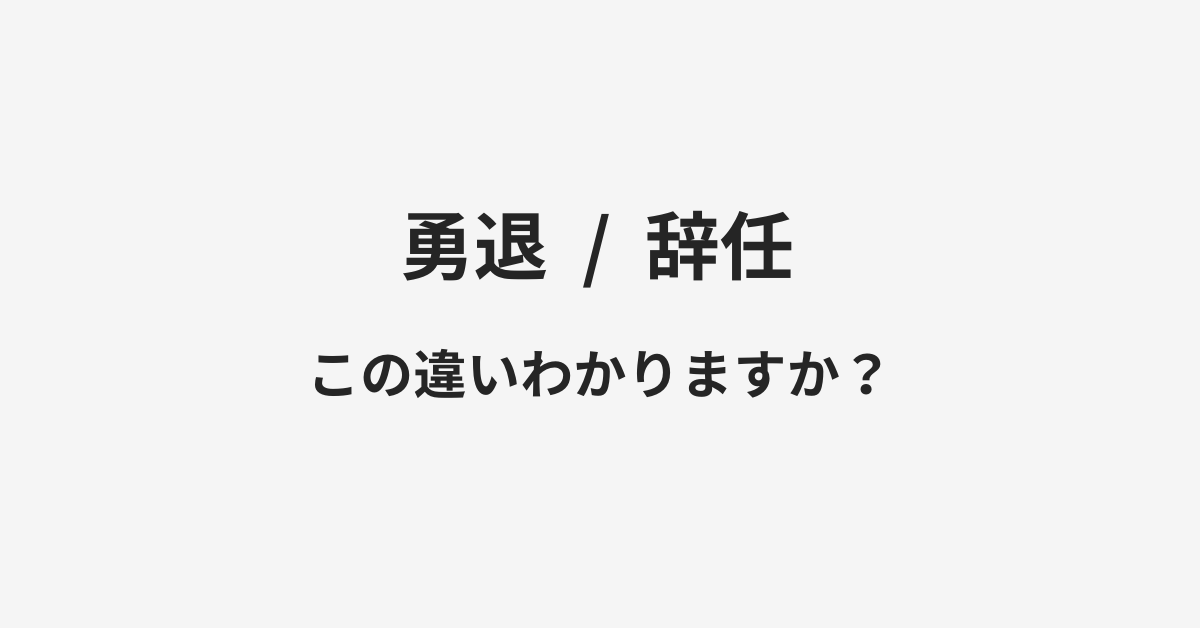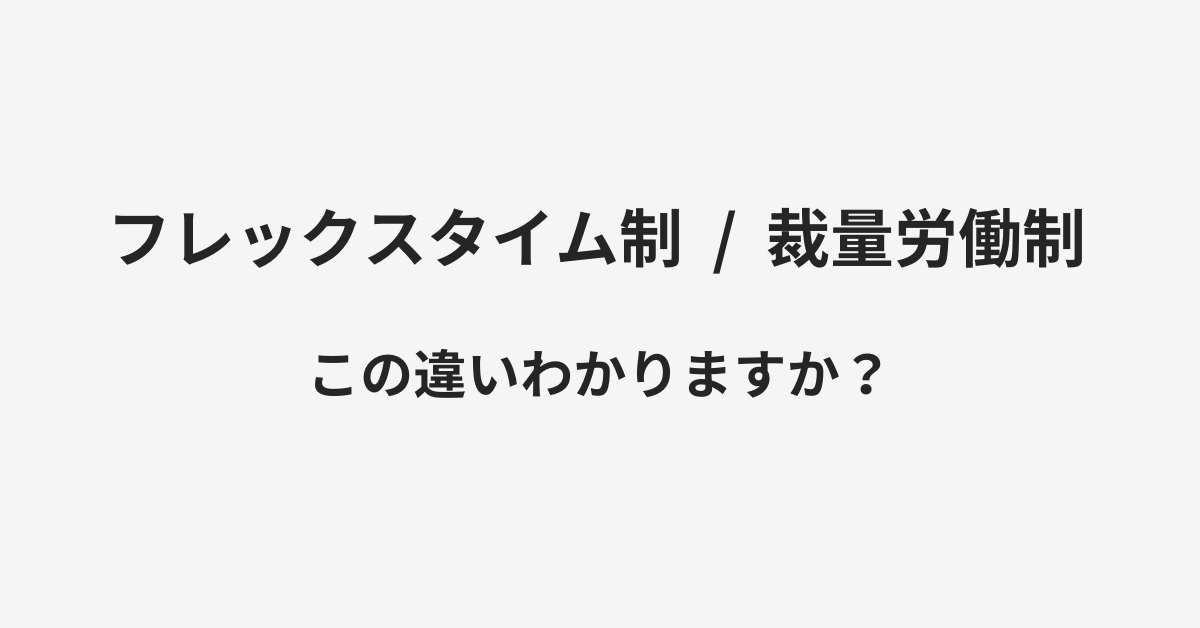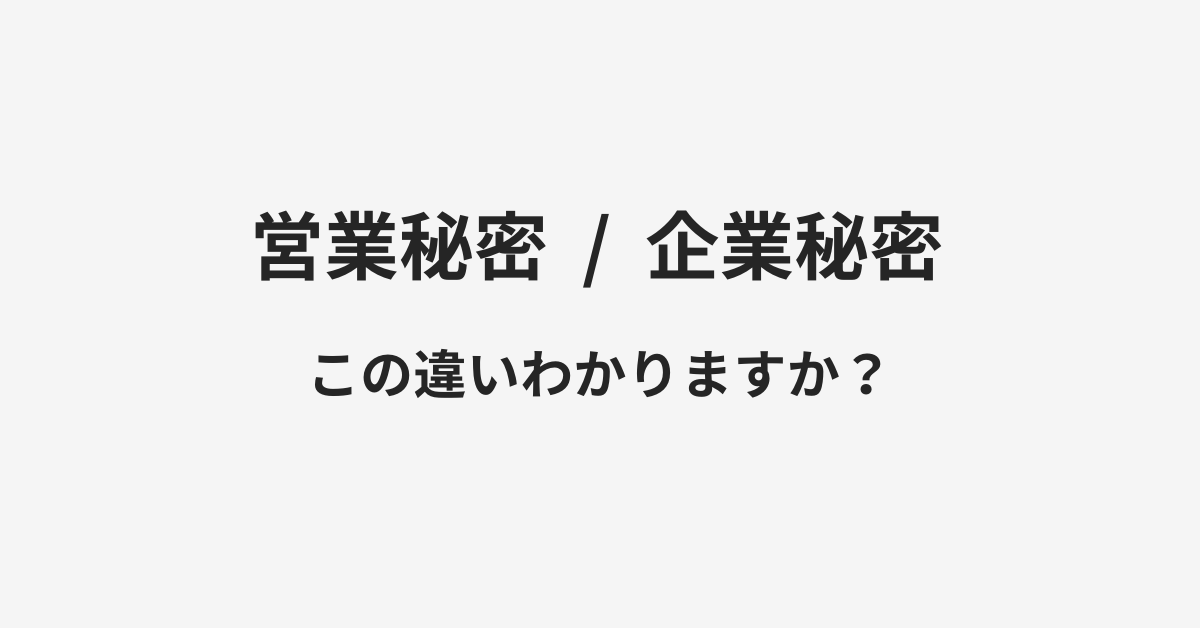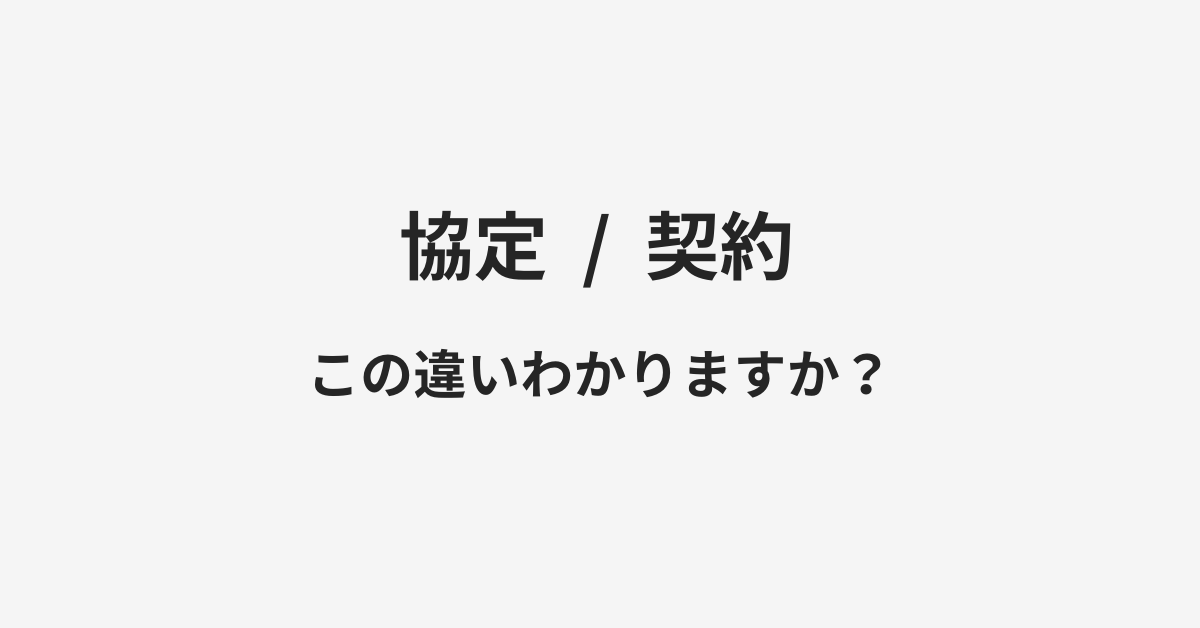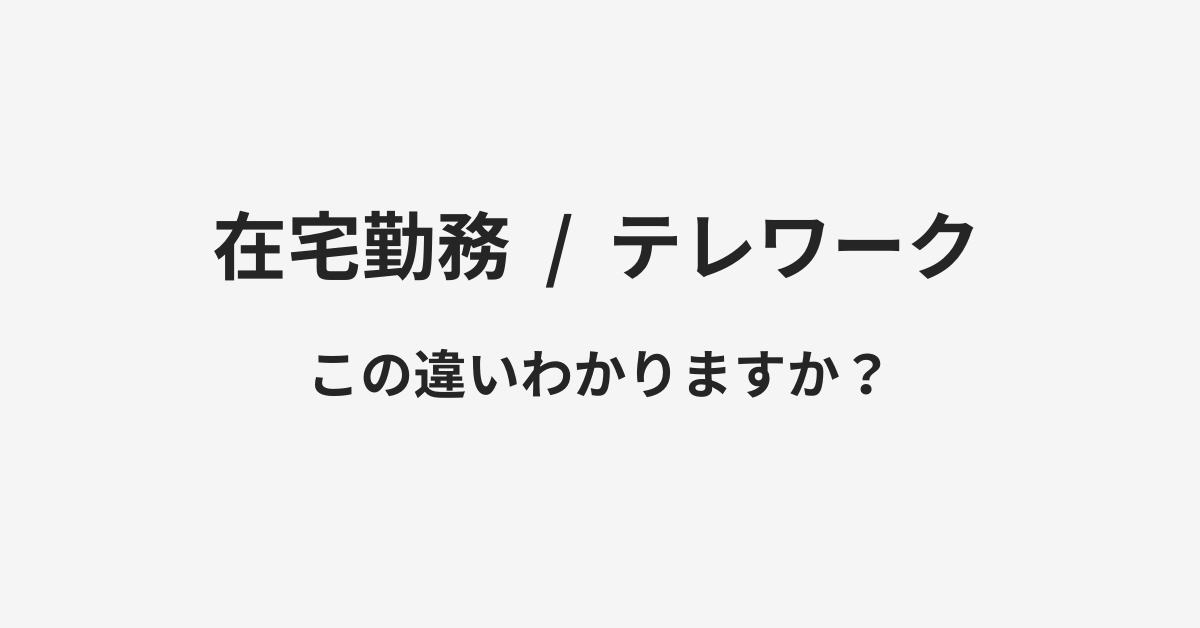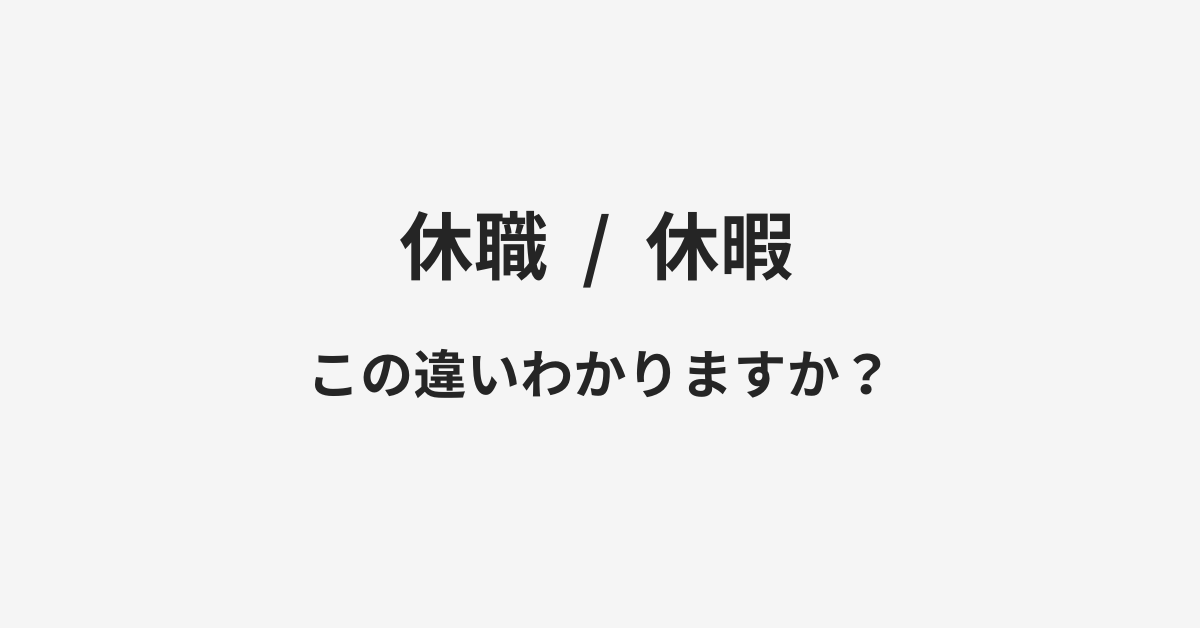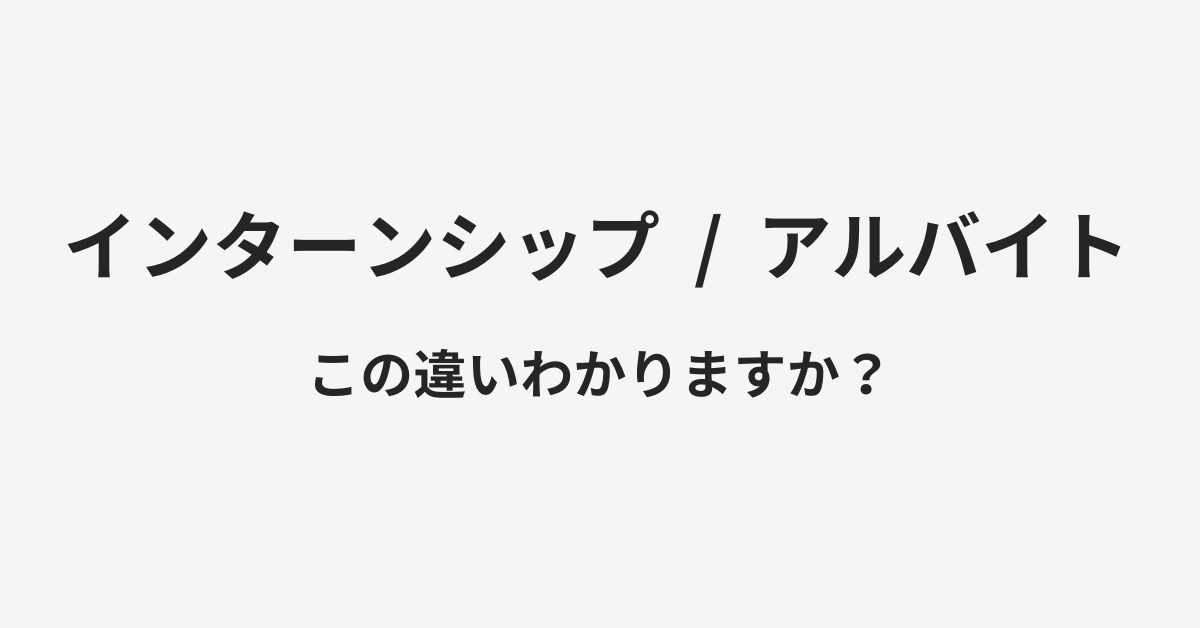【土倉】と【土蔵】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
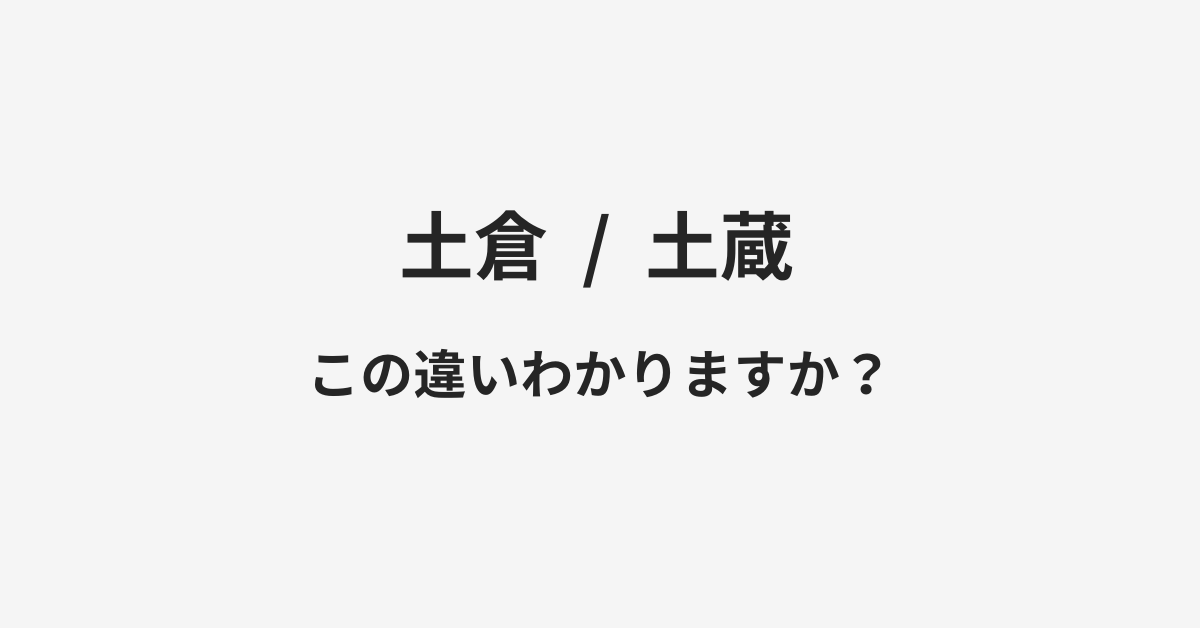
土倉と土蔵の分かりやすい違い
土倉と土蔵は、漢字は似ていますが全く異なる概念です。
土倉は中世日本の金融業者という職業・機能を指し、土蔵は防火構造を持つ倉庫建築を指します。
現代ビジネスでは土倉は歴史用語、土蔵は文化財活用や不動産で使われます。
土倉とは?
土倉(どそう)とは、日本の中世(鎌倉・室町時代)に活動した金融業者で、質屋や高利貸しを営んでいた商人を指します。金銭や米などを貸し付け、担保として土地や物品を預かる金融業を行っていました。現代の銀行や消費者金融の原型とも言える存在で、経済史研究では重要な研究対象です。
土倉は主に京都や奈良などの都市部で活動し、公家や武士、寺社、一般庶民まで幅広い層に融資を行いました。利率は月利3〜5%程度が一般的で、年利換算では36〜60%という高利でした。
担保の管理や債権回収のノウハウを持ち、中世経済の発展に重要な役割を果たしました。現代のビジネス文脈では、金融史の講義、歴史的な商慣習の研究、日本の金融システムの起源を説明する際に使用される専門用語です。
土倉の例文
- ( 1 ) 土倉の金利は現代の基準では違法な高利です。
- ( 2 ) 中世の土倉が日本の金融業の基礎を築きました。
- ( 3 ) 土倉に関する古文書が新たに発見されました。
- ( 4 ) 経済史の講義で土倉の役割を解説します。
- ( 5 ) 土倉の研究から、中世の経済活動が明らかになります。
- ( 6 ) 土倉と現代の金融業を比較研究しています。
土倉の会話例
土蔵とは?
土蔵(どぞう)とは、土壁を厚く塗り重ねて作られた日本の伝統的な倉庫建築です。防火性、防湿性、断熱性に優れ、江戸時代から昭和初期まで、商家の財産や商品の保管に広く使用されました。白漆喰の外壁と重厚な扉が特徴的で、現在も各地に現存しています。
ビジネスでは、歴史的建造物の活用事例として注目されています。レストラン、ギャラリー、ホテル、オフィスなどへの改装(リノベーション)により、地域活性化や観光資源として再生される例が増えています。耐震補強を施せば、現代建築にはない独特の雰囲気を持つ空間として高い付加価値を生みます。
不動産業では土蔵付き物件として、文化的価値の高い物件として扱われます。固定資産税の軽減措置や、文化財指定による補助金制度もあり、適切な活用により収益物件となる可能性があります。
土蔵の例文
- ( 1 ) この土蔵をレストランに改装する計画があります。
- ( 2 ) 土蔵の耐震診断を専門業者に依頼しました。
- ( 3 ) 土蔵を活用した地域活性化プロジェクトを始動します。
- ( 4 ) 歴史的な土蔵群が観光資源になっています。
- ( 5 ) 土蔵の修復には伝統技術が必要です。
- ( 6 ) 土蔵付き物件は付加価値が高く評価されます。
土蔵の会話例
土倉と土蔵の違いまとめ
土倉と土蔵は、日本の経済・建築史における異なる要素です。土倉は中世の金融システムの一端を担った職業、土蔵は優れた保存機能を持つ建築物です。
現代では土倉は歴史研究の対象、土蔵は地域資源として新たな価値を生み出しています。
土倉と土蔵の読み方
- 土倉(ひらがな):どそう
- 土倉(ローマ字):dosou
- 土蔵(ひらがな):どぞう
- 土蔵(ローマ字):dozou