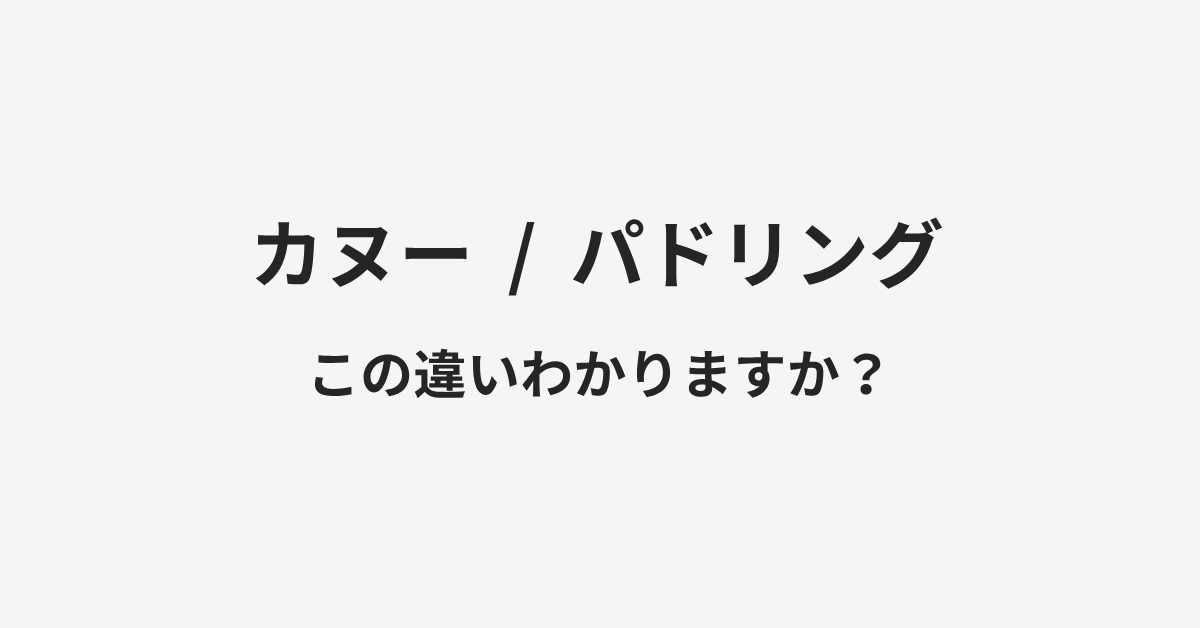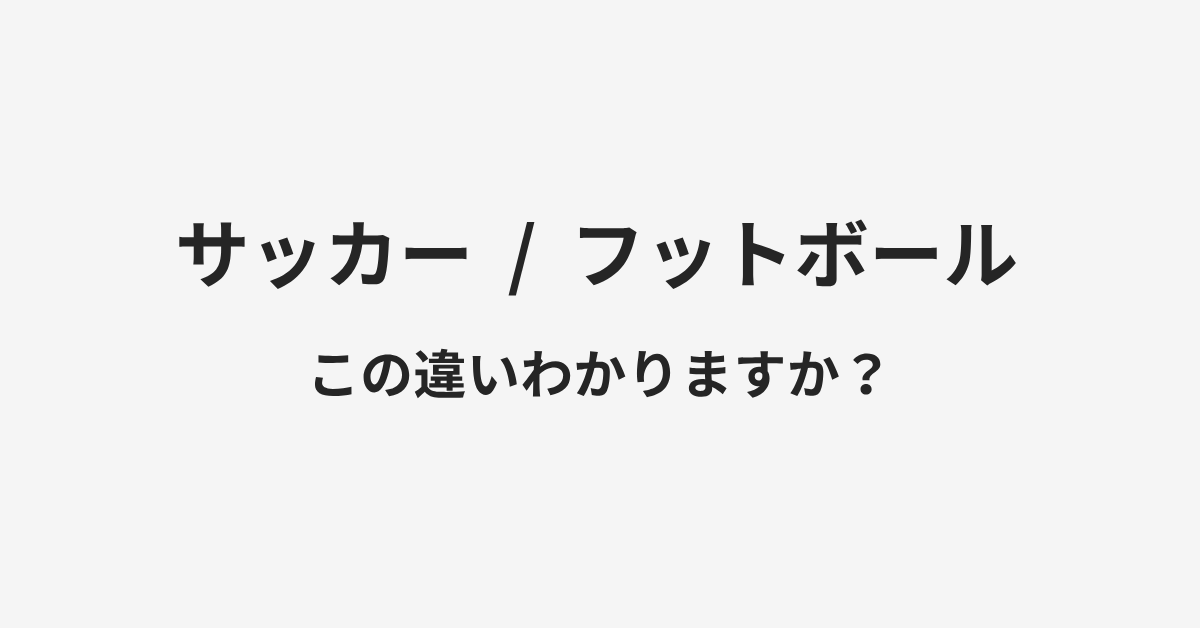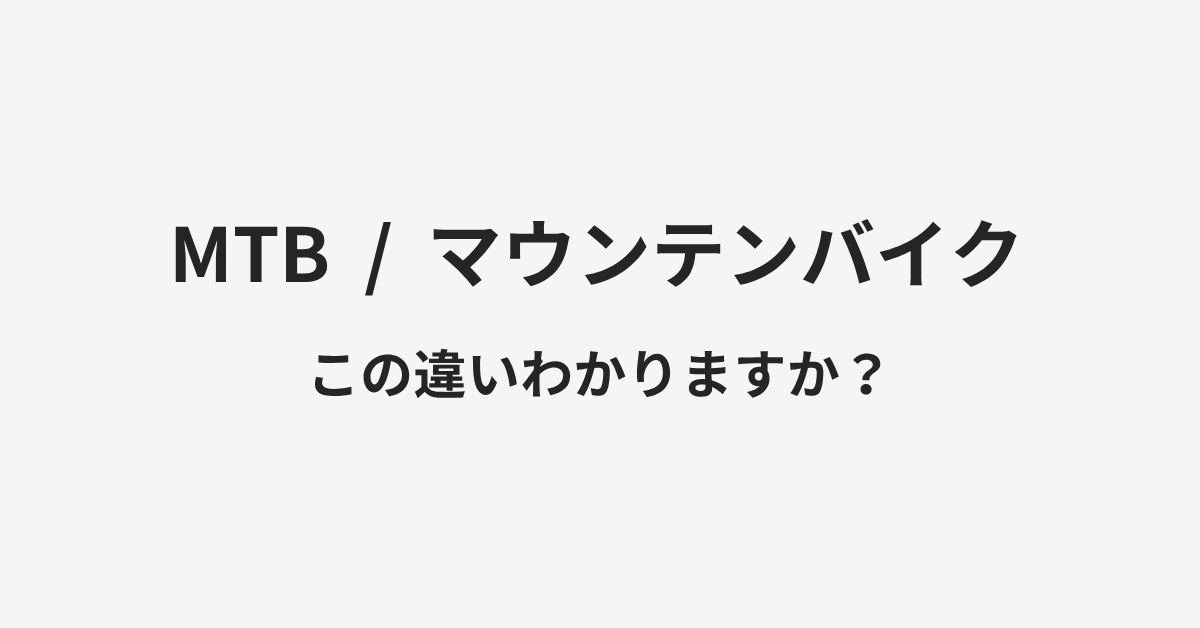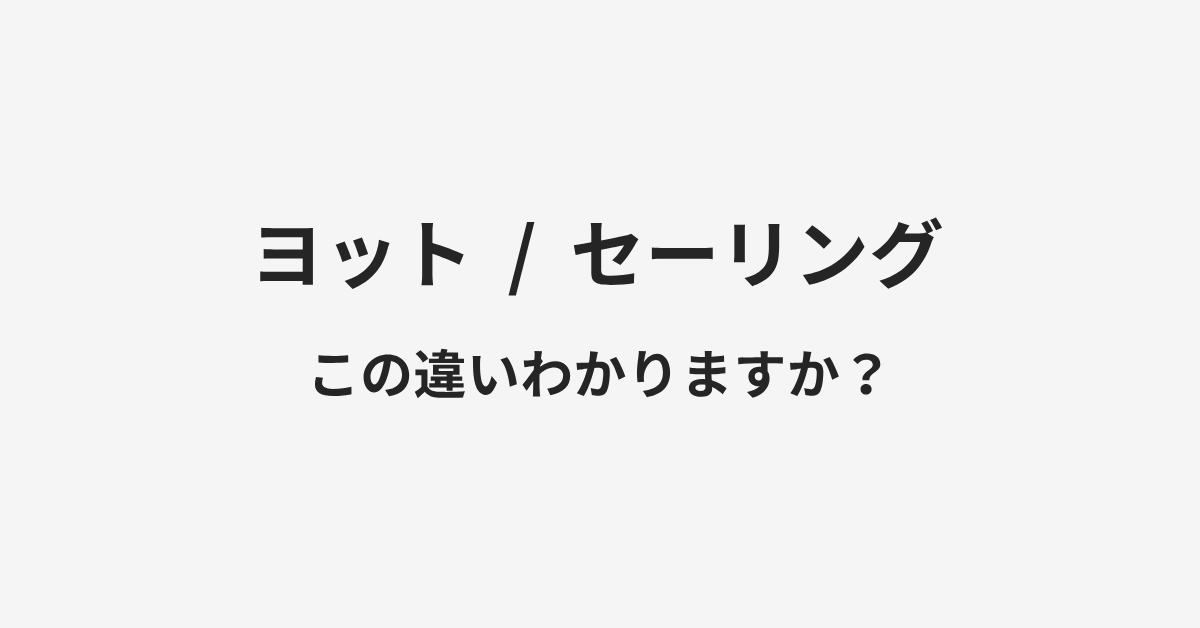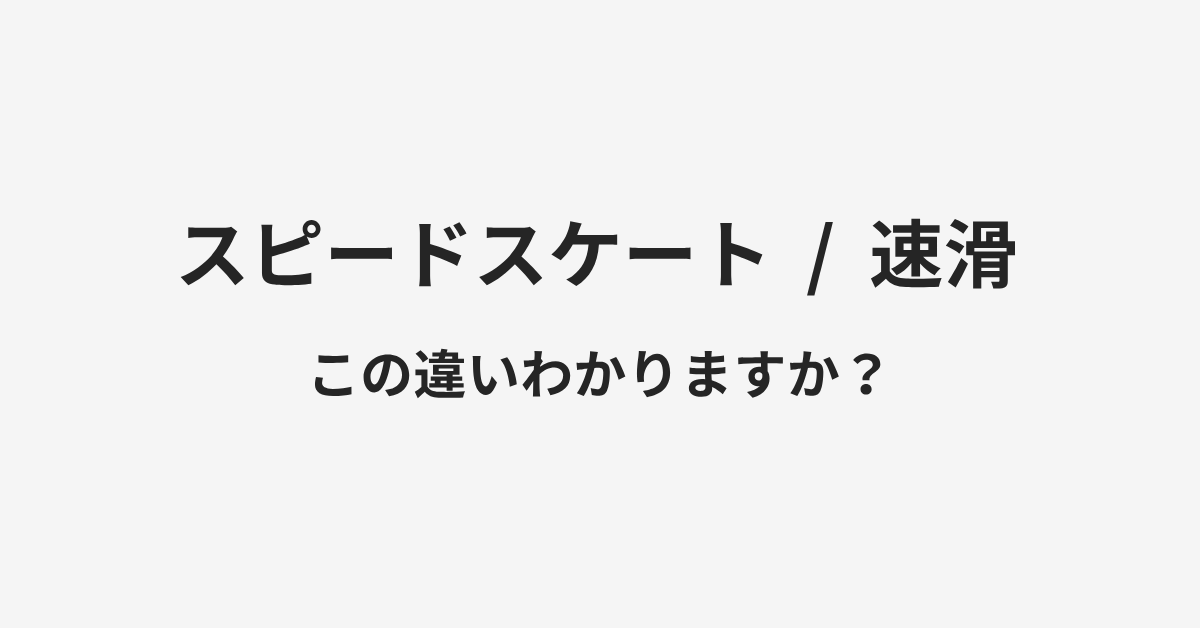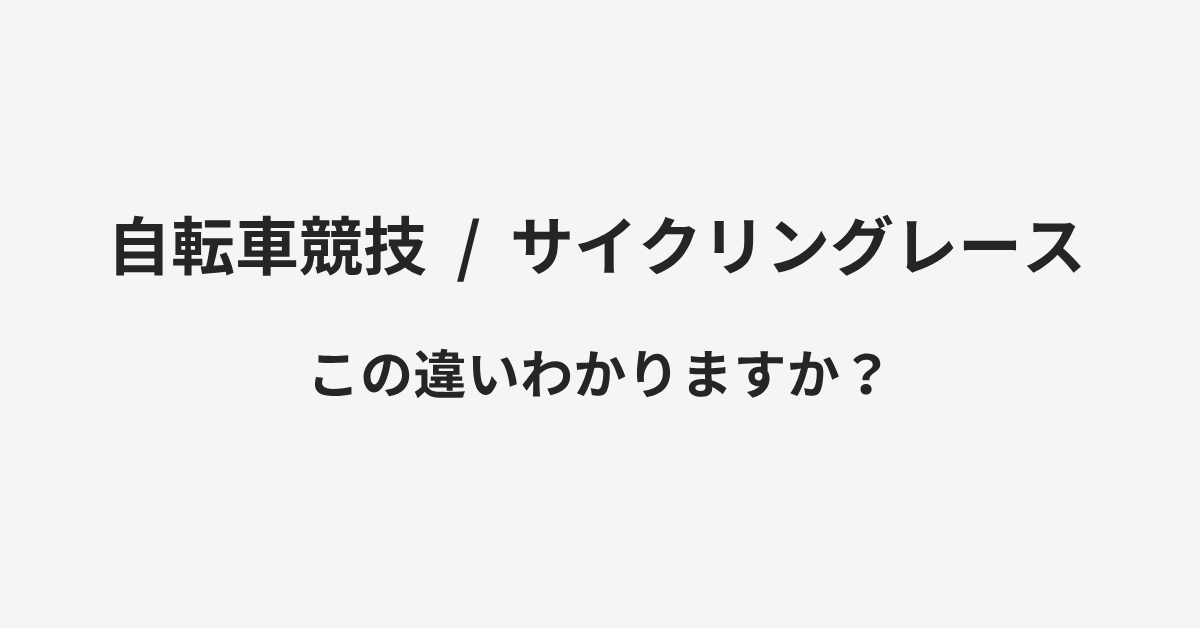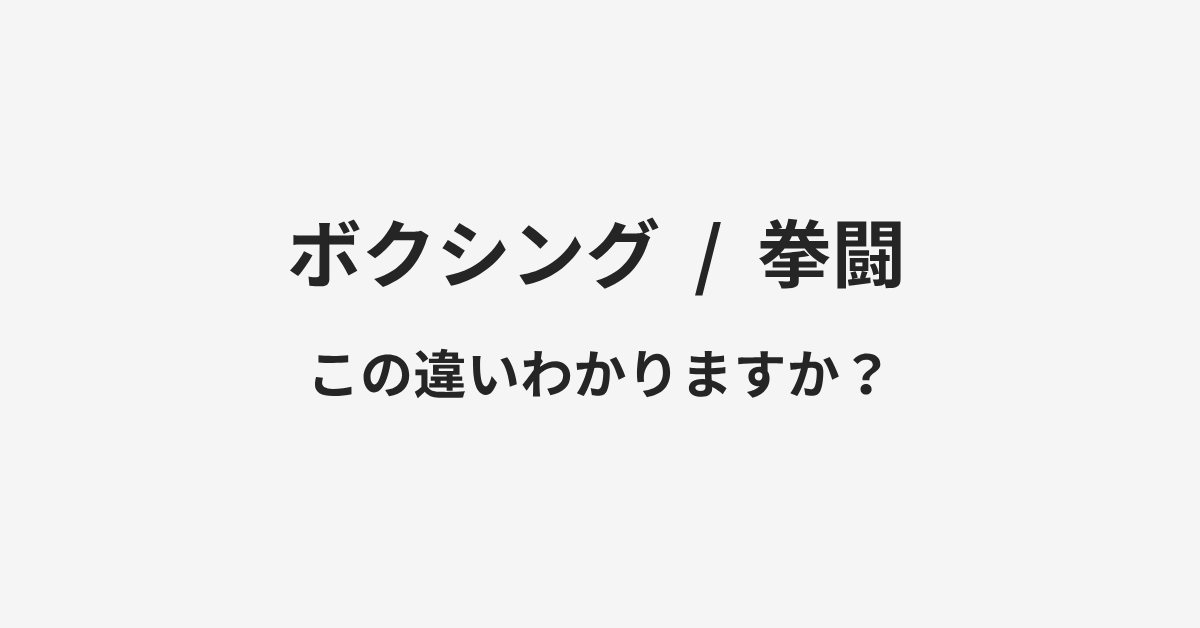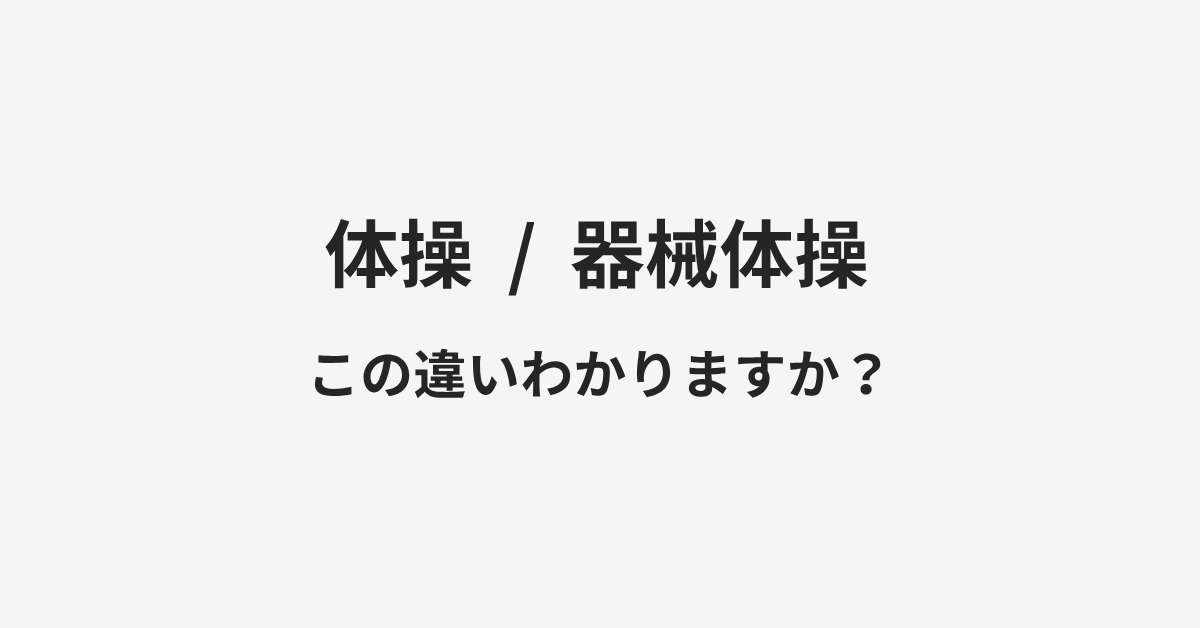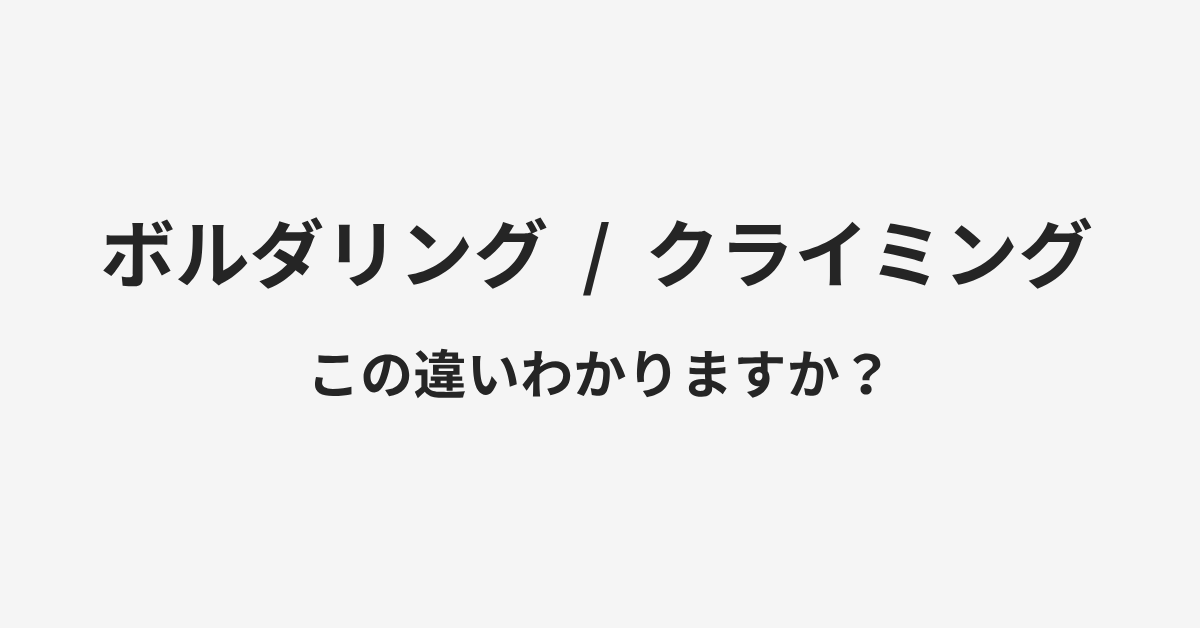【乗馬】と【ホースライディング】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
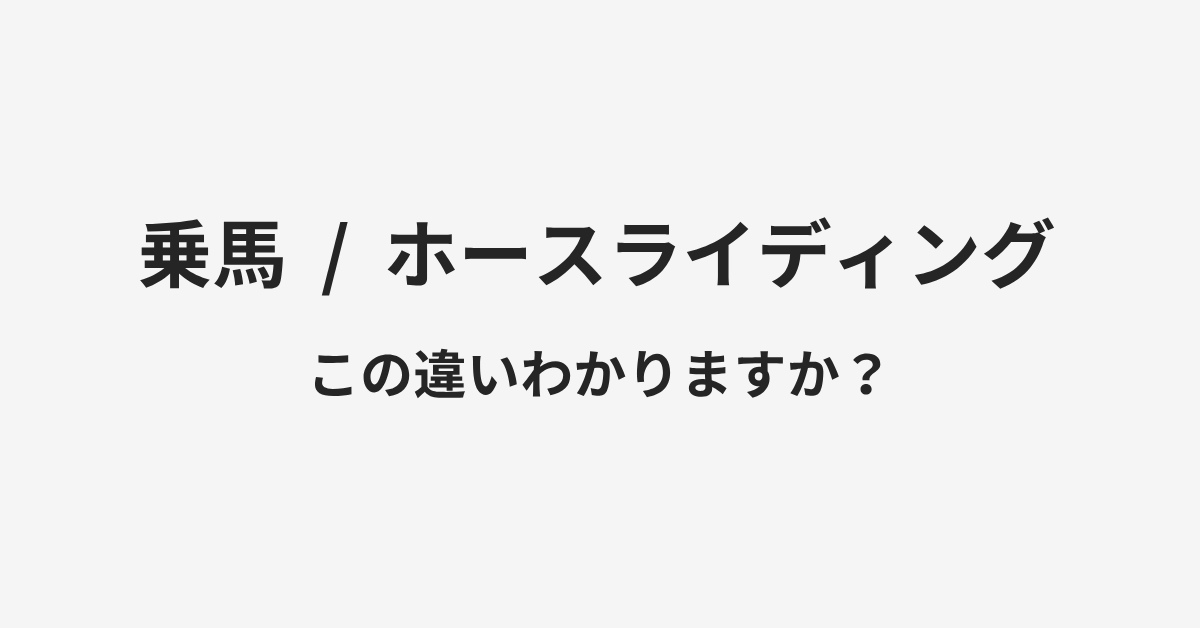
乗馬とホースライディングの分かりやすい違い
乗馬とホースライディングは同じ馬に乗る行為を指しますが、文化的ニュアンスと使用場面が異なります。乗馬は日本で広く使われる表現で、スポーツから趣味、治療まで幅広い意味を持ちます。
ホースライディングは英語由来で、よりスポーツ的、国際的な印象を与えます。
スポーツビジネスでは、日本の伝統的な文脈では乗馬、国際競技や若い世代向けにはホースライディングという使い分けが見られます。
乗馬とは?
乗馬は、馬に乗って移動したり、運動したりする行為全般を指す日本語です。競技スポーツとしての馬術、趣味としての外乗(野外騎乗)、治療目的のホースセラピーなど、幅広い活動を含みます。日本では古くから武士の嗜みとして発展し、現代では健康的なスポーツとして親しまれています。日本の乗馬人口は約7万人で、全国に約300の乗馬クラブがあります。
日本馬術連盟が競技を統括し、馬場馬術、障害飛越、総合馬術の3種目でオリンピックにも参加しています。また、流鏑馬(やぶさめ)のような日本独自の馬術文化も保存されており、伝統と現代スポーツが共存しています。ビジネス面では、乗馬は高額なスポーツとして知られています。
馬の購入・維持費、施設利用料、装具代など、継続的な投資が必要です。しかし、乗馬クラブの会員制ビジネス、体験乗馬、ホースセラピーなど、多様なサービス展開が可能で、特に都市近郊では富裕層向けの高付加価値サービスとして成立しています。
乗馬の例文
- ( 1 ) 全日本乗馬選手権大会が今週末開催されます。
- ( 2 ) 国内トップレベルの乗馬競技を間近で観戦できる貴重な機会です。
- ( 3 ) 乗馬クラブの新規会員を募集しています。
- ( 4 ) 初心者から上級者まで、レベルに応じた乗馬指導を提供します。
- ( 5 ) 企業の福利厚生で乗馬体験を導入しました。
- ( 6 ) ストレス解消と姿勢改善に効果的な乗馬は、社員に好評です。
乗馬の会話例
ホースライディングとは?
ホースライディングは、馬に乗る行為を表す英語Horse Ridingから来た表現で、よりスポーツ的、アクティブな印象を与えます。国際的な馬術競技や、レジャーとしての乗馬体験を指す際に使われることが多く、特に若い世代や都市部では、この表現が好まれる傾向があります。ホースライディングという表現には、伝統的な乗馬よりもカジュアルで親しみやすいイメージがあります。
ホースライディングクラブホースライディング体験など、初心者や外国人にも分かりやすい表現として、マーケティングで活用されています。また、西洋式の馬術をより明確に示したい場合にも使用されます。
グローバル化が進む中、ホースライディングという表現は国際的なコミュニケーションで有利です。海外の馬術団体との交流、国際大会への参加、外国人観光客向けのサービスなどでは、この表現が標準的に使われます。ただし、日本の伝統的な馬術文化を語る際は、乗馬の方が適切な場合もあります。
ホースライディングの例文
- ( 1 ) ホースライディングスクールの生徒が増えています。
- ( 2 ) アクセスの良い立地のホースライディング施設は人気が高いです。
- ( 3 ) ホースライディング用品の新商品を入荷しました。
- ( 4 ) 初心者向けのホースライディングギアも充実しています。
- ( 5 ) 子供向けホースライディングキャンプを開催します。
- ( 6 ) 夏休みのホースライディング体験は、子供たちに大人気です。
ホースライディングの会話例
乗馬とホースライディングの違いまとめ
乗馬とホースライディングは、日本的表現と国際的表現という違いがある同じ活動です。伝統や文化を重視する文脈では乗馬、国際的でスポーティーな印象を与えたい場合はホースライディングが適切です。
どちらも正しい表現で、目的に応じて使い分けることが重要です。
スポーツビジネスでは、ターゲット層の特性を理解し、適切な表現を選択することで、効果的なマーケティングが可能になります。
乗馬とホースライディングの読み方
- 乗馬(ひらがな):じょうば
- 乗馬(ローマ字):jouba
- ホースライディング(ひらがな):ほーすらいでぃんぐ
- ホースライディング(ローマ字):ho-suraidhinngu